検索結果
印刷する検索キーワード
キーワード「山」
札幌のライラック ( 北海道 札幌市 )
大通公園をはじめ個人の庭にも植えられる札幌の市木。花色は、基本的にホワイト、ヴァイオレット、ブルー、ライラック、ピンク、マゼンタ、パープルの7系統がある。ライラックは英名、フランス名はリラ、和名はムラサキハシドイ。名前の響きがいいのでライラックが定着したものと思われる。札幌市には大通公園以外にも見どころの公園*が数多...
大通公園 ( 北海道 札幌市 )
札幌駅から南に約800m、市の中心街に位置する。大通西1丁目から西12丁目までの長さ約1.5km、幅員約60mの公園。1869(明治2)年、札幌にいた開拓判官の島義勇(しまよしたけ)が札幌を2つに分け、北を官庁街、南を住宅・商店街とする計画を立てた。その後1909(明治42)年、長岡安平(ながおかやすへい)*の設計で、逍遥*地としての形態が整...

写真提供:モエレ沼公園
モエレ沼公園 ( 北海道 札幌市 )
ゴミ処理場の跡地を、イサム・ノグチ*の設計で札幌市の総合公園として造成・再生したもの。札幌駅から北東に約10km、面積約190万m2、1982(昭和57)年に工事着工し、イサム・ノグチの死後も工事を続け、23年かけて2005(平成17)年に完成している。 イサム・ノグチは「全体をひとつの彫刻作品とする」というコンセプトのもと...

写真提供:札幌市円山動物園
札幌市円山動物園 ( 北海道 札幌市 )
札幌駅の南西部の円山公園内にあり、地下鉄東西線円山公園駅からバスで約5分、動物園前下車。敷地面積22万4,780m2とスケールの大きさでは北海道で最大である。約150種、750点もの動物を飼育する。 戦後の1950(昭和25)年、札幌市は上野動物園(東京)から移動動物園を招き会場の円山坂下グラウンドで開催、空前の人出で賑わい...
北海道開拓の村 ( 北海道 札幌市 )
札幌駅の東約15kmの、札幌市厚別区の野幌森林公園*内にあり、地下鉄東西線新札幌駅からバスで20分の位置にある。北海道開拓の村の周辺には北海道博物館*もある。 54.2万m2の区域に、1983(昭和58)年4月に開村した野外博物館、旧札幌停車場、旧小樽新聞社、旧浦河支庁庁舎など明治から昭和初期に建てられた道内の歴史的建築...
札幌ラーメン ( 北海道 札幌市 )
札幌ラーメンは第2次世界大戦後、満州からの引揚者人たちが、札幌の繁華街すすきのあたりに屋台を出し工夫されたのが始まりといわれている。中でも味噌ラーメンは札幌が発祥の地である。「味の三平」の大宮守人が考案した味噌のスープと、西山製麺の西山孝之が開発した多加水熟成麺により、1958(昭和33)年に「味噌ラーメン」が誕生したとい...

無意根山 ( 北海道 札幌市 / 北海道 京極町 )
札幌市の西側京極町との境界に位置する標高1,464mの山。アイヌ語の「ムイ・ネ・シリ」(箕・のような・山)が語源である。奥深い森林の上にやわらかく緩やかな楕円形の稜線を描き、椀状に見えるため「箕」の名前になったと思われる。 比較的古い火山による山岳地形で、高山植物が生育し展望にも優れているため、札幌市方面からの格好の日...
北海道神宮 ( 北海道 札幌市 )
札幌駅の南西部の円山公園に隣接しており、地下鉄東西線円山公園駅から徒歩約15分、境内は約18万m2と広く緑に包まれている。1869(明治2)年明治天皇の思し召しにより、北海道開拓の守護神として大国魂神*(おおくにたまのかみ)・大那牟遅神*(おおなむちのかみ)・少彦名神*(すくなひこなのかみ)の三神を祀って北海道の総...

写真提供:トラピスト修道院
トラピスト修道院 ( 北海道 北斗市 )
北斗市当別丸山*の丘陵に映える赤煉瓦のゴシック式建物で、わが国では最初のトラピスト修道院*である。1896(明治29)年、フランス、オランダ、イタリア、カナダから訪れた総勢9人の修道士たちにより創設。正式名称は「厳律シトー会燈台の聖母トラピスト修道院」という。創立修道院長はフランスのブリックベック大修道院から着任したジェラ...
恵庭岳 ( 北海道 千歳市 )
恵庭岳は札幌市の南約30km、支笏湖の北西に位置し、支笏湖岸に高くそびえる標高1,320mの円錐形の活火山。山頂部は無数の裂け目があり噴煙が立ち昇っており、岩塔の幾つかは崩壊が進んでいる。1972(昭和47)年、札幌オリンピックの滑降競技のコースとして使用され、支笏湖へ飛び込むような景観に魅了された。その後、自然保護の観点からロー...
支笏湖 ( 北海道 千歳市 )
千歳市の西端にあるカルデラ*湖で、最深360mと田沢湖に次ぐ日本第2の深さ、面積は78.4km2と日本8位、透明度は17.5mで第4位(環境庁1993「湖沼調査報告書」)である。日本最北の不凍湖で、水中にプランクトンの発生が少なく透明度が高い。 約3万2千年前に始まった火山活動により形成されたカルデラ湖で、当時は丸型の湖だった...

写真提供:千歳市
オコタンペ湖 ( 北海道 千歳市 )
支笏湖の北西、恵庭岳の北西麓に位置し、恵庭岳の火山噴出物によりできた堰止湖。深い森に囲まれ、アクセスが困難なことからオンネトー*、東雲湖*と並んで、北海道の秘湖の一つに数えられる神秘の湖。 周囲約5km、湖面面積はわずか約0.4km2と小さいが、周辺の環境、湖水の色の変化など特色がある。支笏湖より324m高く、エゾ...

写真提供:石狩観光協会
石狩鍋 ( 北海道 石狩市 )
ぶつ切りにした骨付きのサケの身や頭、豆腐、つきこんにゃく、キャベツやたまねぎ等の野菜類を昆布のだし汁で煮込み、白みそで味付けした石狩鍋は寒さが厳しい北国の代表的な冬の料理である。 昭和20年頃、石狩市でサケの地引網漁が注目されると、その漁見たさに多くの観光客が集まった。石狩市を訪れた観光客に「石狩鍋」を振舞ったとこ...
トラピスチヌ修道院 ( 北海道 函館市 )
JR函館駅から東へ約9km、湯の川温泉から3.5km、上湯川町の緑の高台にあり、四方をめぐらす高い塀と赤煉瓦の建物の日本初の女子観想修道院。1898(明治31)年、フランスから派遣された8人の修道女によって創立された。 中では修道女が聖ベネディクトの戒律を守りながら、菓子製造や手工芸品の制作に励み、修道生活を送っている。修道院内に...

写真提供:函館市教育委員会
五稜郭 ( 北海道 函館市 )
五稜郭は、函館山から約6km離れた函館市のほぼ中央にある。1857(安政4)年、蘭学者武田斐三郎*の設計により蝦夷地防備と近代兵器の発達に対処するため、8年の歳月をかけて竣工したわが国最初の洋式城郭で、塁形が五つ星の形をしているところから五稜郭と呼ばれているが、建設当時には亀田役所土塁とも言われていたという。 外堀の幅30m...
函館山山麓周辺の街並み ( 北海道 函館市 )
函館は、横浜・長崎とともに幕末最も早く開港し多くの外国人が生活していた。特に元町付近は海外との交流の場として開けた古い地区。函館山北東斜面の山の手にあり、現在でもハリストス正教会*をはじめ赤煉瓦や木造洋館*など、異国文化の影響を受けた明治の建築物が数多く残存し、風情ある町並みを見せている。 外国人墓地から旧ロシア...
函館山からの夜景 ( 北海道 函館市 )
函館山は函館市街地の最南端にあり、津軽海峡に突出している。海中から噴火した火山であり、標高334m、周囲約9km、別名臥牛(がぎゅう)山とも呼ばれている。函館山は海の中から生まれた山であり、周辺の陸地とトンボロ*という現象で函館山直下の陸地が作り出され陸繋島*となった。山頂からは市街と港を一望でき、両側がくびれた市街地と両...
函館の朝市 ( 北海道 函館市 )
函館駅南側、約3万m2の一角に立ち並ぶ一般消費者、観光客向けの市場。1945(昭和20)年、函館駅前で近隣町村の農家が野菜や果物などを立ち売りしたのが発祥といわれている。店舗数は周辺店舗を合わせて約250店舗。 カニやサケなど海産物や新鮮な海の幸の土産品を中心に、北海道ならではの鮮度の高い食品が一堂に集まる活気あふ...
函館八幡宮 ( 北海道 函館市 )
室町時代に現在の元町、公会堂前あたりに創建*されたが1880(明治13)年に移転、函館市電の谷地頭(やちがしら)停留場から西に約400m、坂と石段の参道を上がった所にある。開運厄除や漁業、航海の守り神として知られている。本殿は聖帝造*と八棟造*を併せた聖帝八棟造であり、大正式八幡造の代表作と言われる。 八幡宮の南には、箱館...
函館山 ( 北海道 函館市 )
函館山は函館市街地の最南端にあり、津軽海峡に突出している。標高334m、周囲約9km、別名臥牛*(がぎゅう)山とも呼ばれている。函館山は大古の火山活動によって生まれた山であり、周辺の陸地とトンボロ*という現象で函館山直下の陸地が作り出され陸繋島*となった。山頂からは市街と港を一望でき、両側がくびれた市街地と両脇の海の形状が...
函館のイカ料理 ( 北海道 函館市 )
海の幸に恵まれた北海道。中でもイカの漁獲量は国内屈指で、特に津軽海峡という豊かな漁場に恵まれた函館は、道内一のイカの産地*。イカを使った料理がふんだんに味わえる。 函館で「イカ」といえば、一般的にはスルメイカを指す。北海道や東北地方では、このスルメイカのことを「マイカ」と呼ぶ。秋に九州西方の東シナ海で生まれた群れ...

写真提供:七飯大沼国際観光コンベンション協会
駒ヶ岳 ( 北海道 森町 / 北海道 鹿部町 / 北海道 七重町 )
北海道森町、鹿部町、七飯町にまたがる駒ヶ岳は、標高1,131mの成層火山*である。噴火により形成された鋭い山頂と美しい裾野の景観で、大沼公園を象徴する道内屈指の名山のひとつに挙げられる。 山頂部にある火口原は剣ヶ峰(けんがみね)、砂原岳(さわらだけ)、隅田盛(すみだもり)に囲まれ、眺める場所によってその山容は姿を変える...

写真提供:七飯大沼国際観光コンベンション協会
大沼 ( 北海道 七飯町 )
大沼公園駅周辺にある大沼・ 小沼・ 蓴菜沼は、駒ヶ岳の噴火によってできた堰止湖、及び陥没湖である。大沼はもっとも北東に位置する公園の中心的な湖で、湖水面積は5.31km2、周囲約24kmの大きさ。 大沼に隣接する小沼は湖水面積3.8km2、周囲約16km。蓴菜沼はその名の通り蓴菜が採れる湖で、湖水面積0.75km2

写真提供:一般社団法人北海道まつまえ観光物産協会
松前のサクラ ( 北海道 松前町 )
松前城*の後方一帯を松前公園と呼び、約21万3,500m2もの広大な敷地内で史跡や多数の社寺が点在している。園内には約250種、合わせて8,000本近い桜があり、4月下旬から5月下旬にかけて次々と花を咲かせる道内有数の桜の名所である。別にこれらの桜の木を1ケ所に展示した桜見本園・桜資料館*があり、松前城から歩いて10分ほどのと...
松前城(福山城) ( 北海道 松前町 )
松前城は函館市の南西約70km、渡島半島の南西端松前町の松前湾に面する台地上に築かれ、海防を重視した縄張り*の城。隣接する寺町などを含む国指定史跡としての面積は約14万8千m2である。 慶長年間(1596~1614年)、松前氏が福山館を築いたのにはじまり、その後1854(嘉永7・安政元)年に外国船打ち払いのための本格的な城郭...
上の湯温泉 ( 北海道 八雲町 )
上の湯温泉は函館市の北西方面に位置する八雲町の温泉地。八雲の中心地から約30km離れた標高約70mの山の中にある、四方を緑に囲まれた落部(おとしべ)川上流にある。昔ここを発見したアイヌの人々は河畔の岩壁に浴槽を設けていたという。 江戸時代後期の1846(弘化4)年には松浦武四郎*が入浴、全国に紹介されたという。また1868(慶応4...
しかべ間歇泉 ( 北海道 鹿部町 )
函館市の北側、太平洋に面した国道278号線の「道の駅しかべ間歇泉公園」にある、1924(大正13)年の温泉開発の際に発見されたという鹿部町の間歇泉。間歇泉とは、規則的または不規則的に熱水や水蒸気を噴き上げる温泉で、火山地域にみられる。ニュージーランド、アイスランドのほか、アメリカのイエローストーン国立公園の間歇泉は世界的に有...

写真提供:江差町
江差追分全国大会 ( 北海道 江差町 )
函館市の西、渡島半島の日本海に面した江差町で行われる民謡「江差追分」の全国大会。全国から選び抜かれた江差追分の唄い手約370人が集い、日本一のノドを競い合うもので、毎年9月中旬の3日間行われる。一般の部以外にも熟年全国大会、少年全国大会も同時期に開催される。 江差追分は、江戸時代に信州中山道で唄われていた馬子唄(まごう...

写真提供:ニセコ町
羊蹄山 ( 北海道 京極町 / 北海道 ニセコ町 / 北海道 俱知安町 / 北海道 真狩村 / 北海道 喜茂別町 )
渡島半島の基部にあたる後志火山群の一つで、円錐形の山容の成層火山*。その秀麗な姿が富士山に似ているところから別名「蝦夷富士」と呼ばれ親しまれており、最高点は1,898mで喜茂別町にある。頂上からは日本海と太平洋を遠望でき、眼下にニセコ連峰などの山々が望める。 後方羊蹄山(しりべしやま)とも呼ばれ、しりべしの語源は、アイヌ...

写真提供:ニセコ町
ニセコアンヌプリ ( 北海道 ニセコ町 / 北海道 倶知安町 / 北海道 蘭越町 / 北海道 共和町 / 北海道 岩内町 )
ニセコ連峰はニセコ比羅夫から日本海側の雷電峠までの東西約25km、南北15kmにわたる11の連なった山々。国道268号線の新見峠を境としてニセコ東山系*とニセコ西山系*に大別される。東山系の山の名はすべてカタカナ名、西山系はすべて漢字名となっている。山の名前が個別に付けられたのは、昭和初期に温泉の開発により入りやすくなり、夏の登...

写真提供:積丹観光協会
積丹半島の海岸 ( 北海道 余市町 / 北海道 古平町 / 北海道 積丹町 / 北海道 神恵内村 / 北海道 泊村 )
積丹半島は小樽市の西、日本海に突き出した半島であり、余市町から岩内町に至る国道229号線(積丹半島ブルーライン)約100kmに及ぶ海岸線で奇岩群が連続する地域である。積丹半島の中でも「神威岬」、「島武意海岸(積丹岬)」、「黄金岬」が主な見どころであり、その他美しい海岸、奇岩が連続している。海岸線はニセコ積丹小樽海岸国定公園...

写真提供:蘭越町
ニセコ湯本温泉 ( 北海道 蘭越町 )
ニセコ連峰チセヌプリの麓にある温泉郷で標高560mの高所にある。絶えず噴煙を上げる長径70m、短径30mの大湯沼が温泉郷に隣接しており周囲を圧している。この大湯沼は水面に珍しい硫黄球が浮遊し、学術上貴重なものとなっている。 ニセコ湯本温泉の湯元は大湯沼。泉質は単純硫黄泉-硫黄泉が主なものとなっている。 宿は2軒で、いずれも...
京極の噴出し ( 北海道 京極町 )
後方羊蹄山(しりべしやま)の北西山麓にある道の駅「名水の郷きょうごく」に隣接してある「ふきだし公園」に、後方羊蹄山から大量に噴き出す湧水がある。「ふきだし公園」は後方羊蹄山腹から湧出する清澄な水を利用してつくられた自然公園。 噴出し湧水は、後方羊蹄山に降った雨や雪が地下に浸透し、数十年かけて湧き出した水。一年中湧...

写真提供:夕張市
夕張岳 ( 北海道 夕張市 / 北海道 南富良野町 )
南富良野町の西端、夕張市との境界に位置し、標高は1,667.8m。夕張山地は日高山地とともに北海道には珍しく非火山性の構造山地*である。 登山口は西側の冷水からと東側の金山からの2か所。原生林を縫って登山道が開かれ、標高1,400mを超えた高山帯には夕張岳固有の植物が生育しており、豊かな自然環境を有することから、国の天然記念物に...

写真提供:安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄
安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄 ( 北海道 美唄市 )
安田侃彫刻美術館 アルテピアッツァ美唄は、札幌から北東へおよそ60km、石狩平野のほぼ中心の美唄市にある野外彫刻公園。JR函館本線美唄駅からバスで19分。「アルテピアッツァ」はイタリア語で「芸術広場」。 かつての炭鉱都市であった美唄市に、1992(平成4)年に芸術交流文化施設としてオープン。閉校した小学校校舎や体育館を改修、姿...
石狩川 ( 北海道 滝川市 / 北海道 石狩市 )
大雪山系の石狩岳に水源をもつ石狩川は層雲峡をつくり、上川盆地・空知平野・石狩平野を流れる。途中、忠別川・雨竜川・空知川・幾春別川・夕張川・千歳川・豊平川などを併せ、石狩市で日本海に注ぐ。日本で3番目に長い約268kmで、流域面積は約14,330km2、全国2位の大河である。 石狩川の語源は、アイヌ語のイシカラ・ペツ「非...

写真提供:中村稜太
雨竜沼湿原 ( 北海道 雨竜町 )
暑寒別連峰に囲まれた、標高850mの高原にあるスケールの大きな高層湿原*。東西約4km南北約2kmにわたる湿原には、大小100を超す池塘(ちとう)が点在し、その池塘には浮島*が浮遊して約150種類の湿原性植物がみられる。 雨竜町市街から道道432号線を西側に26km、車で45分のところに登山口の南暑寒荘がある。その後、徒歩で標高差300m、3....

写真提供:北竜町
北竜町ひまわりの里 ( 北海道 北竜町 )
北竜町は旭川市の西側、国道12号と道道57号で約46kmの距離にある。北竜町ひまわり里は町の中心部から北側に1.6kmにあり、面積23万km2、約200万本のひまわりが8月上旬に咲く。毎年7月下旬から8月下旬に「ひまわりまつり」が開催され、ひまわり迷路や遊覧車の運行、ビールパーティー、花火大会などが行われる。 ひまわり栽培の歴...

写真提供:上野ファーム
上野ファーム ( 北海道 旭川市 )
北国ならではの植物がつくりだす庭を「北海道ガーデン」ととらえ、宿根草を中心に庭づくりをしている。代表的な「マザーズガーデン」「ミラーボーダー」をはじめ、「白樺の小道」「ロングボーダー」「サークルボーダー」「木の声が聞こえる庭」「射的山」など、計算されたコンセプトのもとで、8つのエリアごとに草花が整備されている。 20...

写真提供:旭川市旭山動物園
旭川市旭山動物園 ( 北海道 旭川市 )
旭川駅の東側約11km、桜と紅葉で有名な旭山公園の丘陵に位置し、敷地面積約15.2万km2、飼育動物点数101種/639点(2023年10月現在)の動物園。 1967(昭和42)年に日本最北の動物園として開園し、物珍しさもあり人気となったが施設の老朽化とともに徐々に入園者が減少し閉園の危機もあった。しかし理想の動物園を作る夢を貫き、...

原始ヶ原 ( 北海道 富良野市 )
十勝岳連峰の最南に位置する富良野岳の南側斜面の標高1000~1300m地点に広がる中・高層湿原。総面積は1.15km2にも及ぶ。富良野岳山頂を目指す富良野市側からの入口となる原始ヶ原登山口から登山ルートを歩くとここを通過することになる。まさに手付かずの自然という場所で、その名の通り原始的な風景が広がっており、木道をはじめ...

芦別岳 ( 北海道 富良野市 / 北海道 南富良野市 / 北海道 芦別市 )
夕張山地の中心で標高1,727m、山頂部は富良野市と南富良野町の境界にある。富良野市の西端にそびえ、「北海の槍」や「北海谷川岳」の別称をもつ、尖峰の山頂部と数多くの岩稜や岩壁から成る山である。 山名の芦別はアイヌ語の「アシ・ベツ」で灌木の川を意味し、芦別岳から西に流れる芦別川からきていると言われている。 登山道は富良野市...
大雪山 ( 北海道 東川町 / 北海道 上川町 / 北海道 美瑛町 )
北海道の大屋根といわれる大雪山は独立峰ではなく、旭岳をはじめとしたお鉢平を囲む外輪山とそれらの南部に続くトムラウシ山までの東西約15km、南北約10kmにわたる火山群の総称である。表大雪とも呼ばれ、大雪山国立公園の北部に位置する。 大雪山は約100万~3万年前にかけて複数の火山活動により形成され、中でも約3万4千年前の大規模な...

写真提供:環境省
十勝岳連峰 ( 北海道 美瑛町 / 北海道 上富良野町 / 北海道 富良野市 / 北海道 新得町 )
十勝岳連峰は、富良野盆地の東側に位置する。富良野岳からオプタテシケ山までの約30kmにわたり、火山性の山々が延々と連なる。最高峰の十勝岳を中心に起伏のある稜線が広がり、深く切れ込んだ谷や岸壁が連続している。 富良野側からの主な山は以下の通り。富良野岳(1,912m)、上ホロカメットク山(1,920m)、十勝岳(2,077m)、美瑛岳(2,052m)...

写真提供:環境省
トムラウシ山 ( 北海道 新得町 / 北海道 美瑛町 )
十勝川の源流・トムラウシ川の水源の山で標高2,141m。表大雪と十勝岳連峰の中間に位置し、独立峰ではないものの、他の山々の主峰から遠くひと際高く目立つ存在である。 トムラウシの語源はアイヌ語で「花の多いところ」からという説や、温泉鉱物の湧く沢の「水垢の多いところ」からという説など、諸説ある。 登山道は表大雪や十勝岳連...

写真提供:環境省
沼ノ平 ( 北海道 上川町 / 北海道 東川町 )
沼ノ平は、旭岳北西の標高1400mに位置する高層湿原である。愛山渓温泉登山口から約90分で高層湿原の入口に至る。 湿原には大小多くの池塘*が広がり、タチギボウシやワタスゲなどの花が咲く。湿原からさらに90分ほど登ると、当麻乗越(とうまのっこし)に至る。当麻乗越から見下ろす大小様々な池塘群は「神遊びの庭」と呼ばれる。

写真提供:環境省
沼ノ原 ( 北海道 上川町 / 北海道 新得町 )
北海道中央部にある大雪山系、その中央部に位置する。標高1,420m~1,460mの溶岩台地上に発達した高層湿原*で、南北約1.2km、東西約1kmの広さをもつ。国の天然記念物にも指定されており、「大雪山の奥庭」とも呼ばれる。 旭川紋別自動車道上川層雲峡Icから約50kmでクチャンベツ沼ノ原登山口に到着。登山口から沼ノ原湿原までは、標準的な...
朱鞠内湖 ( 北海道 幌加内町 )
1943(昭和18)年の雨竜第一ダムの完成によって生まれた日本最大級の湛水面積(広さ23.73km2)をもつ人造湖。周囲の山々の地形によって、リアス式海岸のような入り組んだ湖岸となっており、大小の13の島々が浮かぶ様子や、周囲の原生的な森林によって、自然湖を思わせる景観である。内陸に位置し、湖面標高282mと標高が高く、さら...
層雲峡 ( 北海道 上川町 )
大雪湖から上川町中心街に向かって流れる石狩川上流域に形成された延長20数kmに及ぶ大峡谷である。両岸には高さ約200mの溶結凝灰岩による柱状節理がみられる。この大峭壁には、雪渓からの流れが多くの滝となって落ち、周囲の原生林とともに雄々しい景観をみせている。なかでも代表的なのは、流星の滝と銀河の滝。流星の滝は落差90mあり、雄滝...
天塩川 ( 北海道 音威子府村 / 北海道 天塩町 )
北見山地の天塩岳(標高1,558m)を水源とし、北へ向かって流れ、天塩町で日本海に注ぐ川である。本流の長さは256kmあり、北海道内では石狩川に続き2番目に長く、日本国内でも4番目の長さとなる長流河川である。アイヌ語の「テッシ(簗・やな:魚を獲る仕掛け)・オ(多い)・ペッ(川)」が語源であり、岩が簗(やな)のような形で川を横断し...
天人峡 ( 北海道 東川町 )
大雪山国立公園の南東の山麓、忠別川の上流に位置する。約3万年前の巨大噴火による火砕流によって形成された柱状節理で知られる。巨大な一枚岩から流れ落ちる「涙岩」や、柱状節理が7本等間隔で並んだ「七福岩」など、特徴的な岩には名前が付けられている。上流部にある羽衣の滝は、左曲右折七段に分かれて落水する飛瀑であり、北海道一の落...
美瑛の丘の農村風景 ( 北海道 美瑛町 )
大雪山十勝岳連峰のすそ野に位置する、南方の富良野盆地と北側の上川盆地を分ける丘陵地帯の風景。十勝岳の噴火に伴い押し寄せた溶岩や、降り積もった火山灰により形成された傾斜地が小さな河川によって浸食されてできた地形で、美瑛川などの河川がつくる幅の広い谷床には水田が開けているのに対し、大きくうねる幾重にも連なった丘は馬鈴薯...
層雲峡温泉 ( 北海道 上川町 )
上川町の層雲峡地区のほぼ中間地点にあり、十数軒のホテル・旅館・民宿・ぺンション、共同浴場などによる温泉街を形成している。安政年間(1854~60年)の発見といわれ、この地域ではもっとも古くに開けた温泉。近代的な温泉地としての利用は1950年代になってから。温泉街には、ホテルや旅館の他にも、足湯、層雲峡博物館や層雲峡ビジターセ...
白金 青い池 ( 北海道 美瑛町 )
JR富良野線美瑛駅から十勝岳に向かって南東に17kmほどのところにある。さらに3.5kmほど十勝岳の山懐に入れば白金温泉がある。 水面が鮮やかな青い色*をみせている青い池は、1988(昭和63)年に噴火した十勝岳の火山泥流対策のため建設された美瑛川畔の堰堤。水面が青く見える理由は、美瑛川の上流において、十勝岳から流れ出る硫黄沢川や...

写真提供:増毛町
暑寒別岳 ( 北海道 増毛町 / 北海道 雨竜町 )
暑寒別岳は札幌市北部、日本海に面した増毛山地の最高峰で標高1,492m。日本海に直面しているため積雪量も多く、春になっても白く輝く山である。 山頂からは西側の日本海や東側の雨竜沼湿原も望め、天気の良い日には大雪山や積丹なども間近である。 登山ルートは様々な方向から延びているが、一般的なルートは、増毛市街地からの2つのル...

利尻山 ( 北海道 利尻富士町 )
利尻島は直径約19km、周囲約60kmのほぼ円形の島であり、島全体が利尻山で構成されているため、まさに海上に浮かぶ山。隣の礼文島が平坦であるのに対し、円錐形の美しい山からなる島と対照的である。 利尻山は海抜1,721mの火山であるが、活動が早く終わっているため火口跡などは明らかでない。夏期以外は完全に雪と氷の山で、まったく人を...
サロベツ原野 ( 北海道 豊富町 / 北海道 幌延町 )
サロベツ原野は、北海道北部の日本海側に位置する、東西約5~8km、南北約27km、面積67km2を誇り、その一部は日本最大といわれる高層湿原である。多種多様な湿原植物と水生植物の宝庫であり、湿原内の湖沼は渡り鳥の中継地であることから、2005(平成17)年にラムサール条約湿地として登録された。 サロベツ原野の観光拠点は、...

写真提供:浜頓別町
クッチャロ湖 ( 北海道 浜頓別町 )
浜頓別町市街の西方に位置する。かつて陸地に浸入した海の湾口部に、砂州や砂嘴などがつくられ、閉ざされてできた海跡湖。周囲30kmの変形した瓢箪型をしており、大沼(長径5.5km)と小沼(長径3km)が細い水路で繋がっている。平均水深1.5mの汽水湖で、水鳥の重要な中継地。春と秋にはコハクチョウやカモ類が、冬にはオオワシや天然記念物の...
礼文島の高山植物群落 ( 北海道 礼文町 )
礼文島は、北海道の北端、稚内市の西方60kmにある最北の離島。レブンアツモリソウ、レブンウエスユキソウやレブンコザクラなど、この島にしか見ることのできない固有種の他、さまざまな高山植物が生育しており、「花の浮島」とも呼ばれている。南北に細長く標高200~300mほどの丘陵性の起伏の続く島のいたるところには、本州では2000m級の高...

写真提供:(一社)網走市観光協会
網走湖 ( 北海道 網走市 / 北海道 大空町 )
網走市の南西部から女満別町にかけたところに位置する周囲約39kmの汽水湖。かつては海の一部だったものが、海水面の変動や漂砂などによってできた海跡湖である。網走川によってオホーツク海と結ばれ、潮の干満により流入した海水は湖の地形と比重の違いによって湖の底に沈み、上層の淡水層と下層の塩水層とは混じり合うことのない二層構造を...
能取岬 ( 北海道 網走市 )
網走市内の北側に位置する、ゆるやかな弧を描く海岸線がオホーツク海に突きでた岬。砂浜が続くオホーツク沿岸にあって、知床半島、神威岬と並び、およそ40~60mの高さの断崖絶壁がせりだした地形である。アイヌ語の「ノッ・ホロ(岬・の所)」に由来している。断崖の上は比較的平坦で、先端には1917年建築の白と黒に塗りわけられた灯台が立つ...

写真提供:(一社)網走市観光協会
オホーツク海沿岸の流氷 ( 北海道 紋別市 / 北海道 網走市 )
流氷はオホーツク海沿岸の海一面を覆いつくす氷の塊で、紋別、網走、知床でみられる。海水が凍ってできる氷は「海氷(かいひょう)」といい、海氷として動く氷を「流氷」と呼ぶ。海水は真水に比べ凍りにくく、約-1.8℃で結氷する。 11月下旬アムール川河口付近で生まれた流氷*は、サハリン北方の海岸に凍りつき動かなくなり、もっと北の...

写真提供:博物館 網走監獄
博物館網走監獄 ( 北海道 網走市 )
網走湖の東北岸、天都山麓にある1912(明治45・大正元)年に建てられた網走監獄(現網走刑務所)の旧建造物を保存公開する野外歴史博物館。舎房及び中央見張所(重要文化財)、庁舎(重要文化財)、二見ヶ岡刑務所(重要文化財)、教誨堂(重要文化財)、煉瓦造り(登録有形文化財)、網走刑務所裏門(登録有形文化財)、哨舎(登録有形文化...

写真提供:きよさと観光協会
斜里岳 ( 北海道 斜里町 / 北海道 清里町 )
知床半島の付け根の清里町と斜里町の境界にあり、緩やかな円錐形の火山で標高1,547m。頂上からは国後島や阿寒の山々を望む。斜里の語源はアイヌ語の「サルン・ペッ」で葦原にある川の意。 登山道は北側の斜里コースと一般向きの西側の清里コースがある。裾野の広いピラミッド型が印象的。
羅臼岳 ( 北海道 羅臼町 / 北海道 斜里町 )
知床半島の中間部、羅臼町と斜里町の境界線上にある標高1,661mの山。特徴のあるドーム状の形状で、岩場あり雪渓ありと変化に富んでいる。高山植物*も豊富で、約200種にものぼる。 羅臼岳から硫黄山、知床岳への連山が知床半島に連なる。 羅臼の山の名*は「鹿や熊を捕獲、解体した後で臓腑や骨を葬った場所」という意味。 登山ルー...

写真提供:知床斜里町観光協会
知床五湖 ( 北海道 斜里町 )
知床山系の山裾に広がる原生林の中に点在する大小5つの火山性堰止湖。それぞれ一湖、二湖と番号で呼ばれ、一番大きいのが二湖、小さいのが五湖である。流入、流出する川はなく、五湖の水は湖底の岩を伝い、知床半島の断崖(五湖の断崖)にしみ出している。五湖全てを周る大ループと呼ばれる地上遊歩道は1周3kmで、コースタイムは約1時間30分...
サロマ湖 ( 北海道 佐呂間町 / 北海道 湧別町 )
オホーツク海岸の北見市、佐呂間町、湧別町の3つの市町にまたがる周囲約90km 、面積約152km2を誇る北海道内では最も大きな湖である。日本全体では、琵琶湖、霞ヶ浦に次いで第3番目。もとはオホーツク海に接する湾状の地形だったが、湾口に堆積した砂が海と湖を隔てる砂州となり、現在のような湖になった。20km以上の細長い砂州で...

写真提供:斜里町
カムイワッカ湯の滝 ( 北海道 斜里町 )
ウトロ中心街から陸路で25kmほど知床半島の中に入った場所に位置する。硫黄山を源流とするカムイワッカ川の中流域に相当し、活火山である知床硫黄山の中腹から涌き出る温泉が川に流れ込み、川全体が流れる温泉のようになっている。ところどころに滝状に水が落下する箇所があり、それぞれの滝壺は天然の露天風呂である。「カムイワッカ」とは...
知床半島の海岸 ( 北海道 斜里町 / 北海道 羅臼町 )
知床半島は北海道の東北端から北北東に突き出た半島で、長さ約65km、幅は基部で約25km。北側(ウトロ側)はオホーツク海に面し、南側(羅臼側)は根室海峡をはさんで国後島に相対している。知床半島はアイヌ語では「地の涯て」を意味する「シリエトク」と呼ばれている。海岸線は切り立った崖であり、ウトロ側はおよそ20~30mの海岸段丘となっ...
小清水原生花園 ( 北海道 小清水町 )
JR釧網本線の浜小清水駅から北浜駅の間に広がる、オホーツク海と濤沸湖に挟まれた約8km、約2.75km2の細長い砂丘に形成された原生花園。国道244号線を挟んで濤沸湖側の湿原にはアヤメが群生し、海側の砂丘にはハマナス・エゾキスゲ・エゾスカシユリなどが密生する。4月末から9月いっぱいにかけて、200種類にも及ぶ植物を見ることが...
濤沸湖畔の原生花園 ( 北海道 小清水町 )
濤沸湖は、網走市と小清水町にまたがる汽水湖である。オホーツク海に面した遠浅の湾が、潮の満ち引きによって作られた砂嘴によって塞がれた潟湖の一種で、周囲27.3km、総面積9km2。アイヌ語で沼の口を意味する「トープッ(to-put)」を語源とし、かつてはアイヌ語の別名で「チカプントー(鳥がいつもいる沼)」とも呼ばれてたように...

写真提供:滝上町
芝ざくら滝上公園 ( 北海道 滝上町 )
芝ざくら滝上公園は滝上町の小高い丘を中心にした公園。1954(昭和29)年の洞爺丸台風の被害により公園内の桜の木が壊滅状態になった。これを受けて当時の公園管理者が1957(昭和32)年にお寺の境内に咲いていたシバザクラをミカン箱一つ分譲り受け、公園に植えたのが芝ざくら公園の発端である。1959(昭和34)年に、管理者の友人が町長にな...
樽前山 ( 北海道 苫小牧市 )
樽前山は北海道道央地方にある支笏湖の南側、苫小牧市の北西部に位置する三重式活火山。標高は最高点の樽前ドームで1,041m。 江戸時代に大噴火を起こし、苫小牧から千歳市周辺に大量の火山灰と軽石を堆積させた。また、1909(明治42)年の爆発で頂上火口内に溶岩円頂丘*を生成したことで、その姿は一度目にしたら忘れられない独特の姿と...
登別温泉 ( 北海道 登別市 )
登別駅の北8km、標高200mの原生林に囲まれた温泉。多種に及ぶ多彩な泉質と豊富な湯量で、北海道を代表する温泉地のひとつであり海外でも知名度が高い。温泉街の入り口に位置する道南バス登別温泉ターミナルから地獄谷の入口にかけて、旅館、みやげ物店、飲食店が多数並んで賑わいを見せている。また周囲には、大湯沼、四方嶺、倶多楽湖と探勝...
有珠山 ( 北海道 壮瞥町 / 北海道 洞爺湖町 / 北海道 伊達市 )
洞爺湖から内浦湾に至る地域での活火山の王者であり標高は733m。山頂部は成層火山*の上部が陥落して、直径1.8kmのカルデラ*となり、そのなかには3個の溶岩ドーム(大有珠、小有珠、有珠新山)に加え多数の潜在ドーム*を持っている 1663年以降、少なくとも9回の噴火が確認されており、20世紀以降は1910(明治43)年、1944~1945(昭和19...
昭和新山 ( 北海道 壮瞥町 )
洞爺湖の南、有珠山の東麓にあり、標高は395m。茶褐色の岩肌から白煙を噴出し、どこから見てもすぐわかる独特な山容をもっている。 1943(昭和18)年12月28日の夕刻、突然地震があり、地割れとともに麦畑や松林が隆起、数百回の爆発が繰り返された。それから約2年間、噴煙・降灰・泥雨・雷電を伴う数回の爆発によって、畑地は約300mも押し...

写真提供:洞爺湖町 経済部観光振興課
洞爺湖 ( 北海道 洞爺湖町 / 北海道 壮瞥町 )
北海道の南西部に位置する支笏洞爺国立公園のほぼ中心にあり、面積約70km2、約11万年前の巨大噴火によって形成されたカルデラ湖。カルデラ湖では日本で3番目に大きい円形の湖である。湖の中央部には溶岩円頂丘*の中島(大島、観音島、弁天島、饅頭島)が浮かび、いずれもミズナラ、イタヤカエデなどの広葉樹林で覆われており、中...

写真提供:一般社団法人白老観光協会
倶多楽湖 ( 北海道 白老町 )
登別温泉街の東3.5kmにあり、大湯沼を経て湖岸に通じている。俱多楽火山の噴火により形成されたカルデラ湖であるという説が有力という。湖の面積は4.7km2、水深148m、周囲約8kmのほぼ「まる」の形をしており、肢節量(1.01*)はカルデラ湖において全国1位である。 また、透明度(22.0m*)は摩周湖に次いで全国第2位、水質(c...

写真提供:平取町役場 観光商工課
幌尻岳 ( 北海道 新冠町 / 北海道 平取町 )
幌尻岳は、日高山脈の最高峰で、標高2,052mの奥深い健脚向きの山。山頂からは日高山脈の山並みが一望できるほか豊富な動植物が見られることで人気があり、夏にはカール*状大地の一面が高山植物の花畑となる。 登山口は額平川コース(平取町)、新冠コース(新冠町)、チロロ林道コース(日高町)があるが、いずれもアプローチが長く苦労...

写真提供:えりも町役場 産業振興課
襟裳岬 ( 北海道 えりも町 )
造山運動によって形成された南北150kmにわたって2,000m級の山々が鯨の背骨のように連なる日高山脈が、太平洋に落ち込むところが襟裳岬である。この岩礁地帯は襟裳岬展望台*から沖合2kmかけて海へと沈み、海面下でも6km先まで続いている。日高山脈がそのまま太平洋に沈みこんでいることを表している。常に風が強く、ここには高い樹木は見られ...
二十間道路の桜並木 ( 北海道 新ひだか町 )
峰々が連なる日高山脈を背に、太平洋を望む道内では比較的温暖な新ひだか町(日高町の南東に位置する)内を流れる静内川右岸沿いの道道より一本外側の道路の両側に、直接7kmにわたり咲き誇る桜並木である。1872(明治5)年、北海道開拓使長官黒田清隆により北海道産馬の改良を目的として日高管内の静内・新冠・沙流の三郡に及ぶ約7万haの広大な...
アポイ岳高山植物群落 ( 北海道 様似町 )
アポイ岳(810m)は標高が低いにもかかわらず、山腹には約80種の高山植物が生息し、5月初旬から10月頃までの間に入れ替わりに花が咲く。北海道の他の山では通常なら標高1,000m以上でしか見られない高山植物がアポイ岳では約350mの5合目付近から姿を見せ始める。また、このうちの固有な植物は20種近くに及び、これほど固有な植物が集中する地...

写真提供:日高町
日高の競走馬牧場群 ( 北海道 日高町 )
日高地方はサラブレッド(競走馬)の生産地として名高く「優駿*のふるさと」とも呼ばれている。この地方には競走馬の牧場が約1,100戸、約20,000頭の馬がおり、日本の競走馬の8割を占めるというデータもある。北海道のなかでは気候が温暖であり、雪も少ないため昔から馬が育てられてきたということが大きな理由の一つである。 歴史を振り...
日高のコンブ干し ( 北海道 新ひだか町 )
浦河町からえりも町にかけた海岸沿いでは、白い砂利を敷き詰めた「干場」が点在し、漁獲されたコンブが天日干しのために並べられる。天然コンブの好漁場として知られるこのエリアでは、7月上旬から一斉にコンブ漁がスタートし、9月下旬、遅いときで10月中旬まで続く。この季節には前浜から数十メートル先の岩礁地帯が漁場となり、漁師たちは「...

写真提供:ばんえい十勝
ばんえい競馬 ( 北海道 帯広市 )
世界で唯一、帯広競馬場で開催されている「ばんえい競馬」。古くから農耕馬として人々を支えてきた体重約800~1,200kg前後のばん馬が、重量物を積載した鉄製のそりを曳き、2か所の障害(台形上の小山)が設置された直線200mのコースを走る競馬だ。障害を越えることが勝敗を分けるため、コースを一目散に走りきるのではなく、途中で止まり息を...

写真提供:鹿追町役場ジオパーク推進課
然別火山群 ( 北海道 士幌町 / 北海道 上士幌町 / 北海道 鹿追町 )
大雪山国立公園南東部、然別湖を囲む南・北ペトウトル山、東・西ヌプカウシヌプリ、天望山、白雲山などの約30-1万年前に活動を繰り返した火山群。 主峰は然別湖の北西に位置する北ペトウトル山で標高1,421m。南ペトウトル山は然別湖の西にあり標高1,348m。然別湖の南に位置する山は、西から西ヌプカウシヌプリ1,251m、東ヌプカウシヌプリ1...

オンネトー ( 北海道 足寄町 )
阿寒湖温泉の南西部、国道240号線経由で約20km、エゾマツ・トドマツを主体とした亜寒帯性の針広混交林原生林に包まれた神秘的な湖。湖の周囲長は約2.5km、湖沼面積0.23km2、最大水深は約10m。阿寒湖からの道の途中には雌阿寒温泉があり、また赤褐色の水をたたえる錦沼もある。 アイヌ語で「老いた沼・大きい沼」の意の火山堰止湖...
然別湖 ( 北海道 鹿追町 / 北海道 上士幌町 )
大雪山国立公園の南東隅に位置する約3万年前の噴火で川がせき止められて出来た堰止湖。周囲は約13km、標高810mの高所にあり、最深部は約100mの大雪山国立公園唯一の自然湖である。火山の噴火により湖岸の出入は複雑で、北からヤンベツ川が流入し、南西からトウマベツ川が流出する。複雑な湖岸線に9つの湾を形成し、湖北には弁天島がある。 湖...
旧国鉄士幌線アーチ橋梁群 ( 北海道 上士幌町 )
十勝と上川を結ぶ国道273号線沿いに並行して点在するコンクリート造りのアーチ橋梁群。かつての国鉄士幌線で使われたもので、1987(昭和62)年に鉄路が廃止になった後は、東大雪の開拓の歴史を伝える近代産業遺産として残されている。 このうちタウシュベツ川橋梁(通称めがね橋)は、季節によって姿が見え隠れする日本唯一のアーチ橋であ...

写真提供:上士幌町観光協会
ニペソツ山 ( 北海道 新得町 / 北海道 上士幌町 )
東大雪の糠平湖北西に位置する、標高2,013mの石狩連峰最高峰。急峻な山容を持つ独立峰で、溶岩の積み重なった岩場にエゾナキウサギ*が生息する。 2016年の台風被害により杉沢コースに至る林道が消失したため、現在は幌加温泉コースの登山道のみ利用可能となっている。 語源はアイヌ語の「ニペシ・オツ」でシナノ木の多いを意味すると...

写真提供:十勝千年の森
十勝千年の森 ( 北海道 清水町 )
JR帯広駅の西方約30km、十勝平野の西端を南北に連ねる日高山脈の麓にあり、山脈と十勝平野をつなぐ境界に位置している。標高は約275~460m、高低差は185mほどで、全体が緩やかな斜面になっている。敷地面積は約4km2あり、冬は厳しく、寒暖差の激しい場所だが、東向き斜面のため太陽の恵を多く受ける庭造りの適地にある。 十勝...
雌阿寒岳 ( 北海道 釧路市 / 北海道 足寄町 )
釧路市阿寒湖の南西部に位置する、標高1,499mの活火山。阿寒カルデラが陥没した反動でカルデラ壁上に噴出した火山である。頂上付近は多くの小火山や火口が集まり複雑な形状をしている。 山麓付近はエゾマツなどの原生林、7合目以上には高山植物が見られる。 登山道は3か所あるが、西側の雌阿寒温泉とオンネトー湖畔からが一般的である。
雄阿寒岳 ( 北海道 阿寒町 )
釧路市阿寒湖の東に位置する、標高1,370mの円錐形をした山である。阿寒湖南西部の雌阿寒岳に対して、その山容のするどさから雄阿寒岳と呼ばれ、アイヌ語ではピンネシリ(=雄山)という。 阿寒カルデラ*陥没の反動により、カルデラ中心部に噴出した中央火口丘が山頂であり、輝石安山岩・橄欖(かんらん)石*などの溶岩流で構成されてい...
阿寒湖 ( 北海道 釧路市 )
JR根室本線釧路駅から北へ約65km、雄阿寒岳(標高1,370m)、雌阿寒岳(標高1,499m)などの山並みの懐に抱かれ横たわる、やや菱形をした湖。湖岸の出入りは複雑で、北方からイベシベツ川、西方から尻駒別川といった数多くの河川が流入し、東南から阿寒川となって流れ出る。湖にはオンネモシリ(大島)・ポンモシリ(小島)・ヤタイモシリ・チ...
ペンケトー・パンケトー ( 北海道 釧路市 )
阿寒湖温泉街の北東、直線距離で7~8kmに位置する二つの湖。ペンケトーは面積0.3km2、周囲長3.9km、透明度は15.9mで全国5位、下流のパンケトーは面積2.83km2、周囲長12.4km、透明度は11.3mで全国8位の透明度を誇る。 数十万~15万年前の火山活動によってできた長径24km、短径13kmという広大な阿寒湖カルデラのなか...

写真提供:釧路市教育委員会
阿寒湖のマリモ ( 北海道 釧路市 )
緑藻類、淡水産アオミソウ科の一種で、世界の寒冷地の湖に産する。マリモは濃緑色の細い藻が中心から放射状に生えビロード状の球状をなすが、球状にならず糸状体の細い藻のみが、ばらばらに生長した房状のものも多い。球形のマリモの大きさは豆粒大から6~8cmほどが平均的であるが、阿寒湖では30cmを超えるものもみられる。 日本において...

写真提供:阿寒アイヌ工芸協同組合
アイヌ古式舞踊(阿寒湖アイヌシアターイコㇿ) ( 北海道 釧路市 )
北海道一円に居住しているアイヌの人々*1によって伝承されている歌舞。アイヌ独自の信仰に根ざし、信仰と芸能と生活が密接不離に結びついているところに特色がある。 熊送り・梟祭り・菱の実(ベカンベ)祭り・柳葉魚(シシャモ)祭りなどのアイヌの主要な祭りに踊られる儀式舞踊のほか、家庭における各種行事の祝宴、作業歌舞、娯楽舞踊...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会
アトサヌプリ火山群 ( 北海道 弟子屈町 )
アトサヌプリは屈斜路カルデラ*の中央部に形成されたアトサヌプリ火山群*中の標高508mの山で、別名硫黄山とも呼ばれている。現在も活発に火山活動が続いており、独特な景観を生み出している。 この地域は、かつて硫黄の採掘で栄えたものであり、この地に鉄道を敷設させるとともに川湯温泉の発展につなげていったという歴史をもつ。ただ...

写真提供:厚岸町観光商工課
別寒辺牛湿原 ( 北海道 厚岸町 / 北海道 標茶町 )
厚岸湖に流れ込む大別川の上流にある湿地。この湿原が知られるようになったのは比較的新しく、1983(昭和58)年に「厚岸観光十景」を選定したときに、選定された湿原に「別寒辺牛」という名称を冠してからである。さらに1993(平成5)年に「厚岸湖・別寒辺牛湿原」がラムサール条約の登録湿地となったことから急速に注目されるようになった。...

写真提供:弟子屈町役場 観光商工課
摩周湖 ( 北海道 弟子屈町 )
釧網本線摩周駅から摩周湖*1第3展望台まで北へ道道52号線経由で約10km、同じく川湯温泉駅から第1展望台まで南東へ約10km。水の出入の見られぬ勾玉状の湖(長径約7km、短径約3km、面積19.6km2)で、湖心にカムイッシュと呼ばれる小島が浮かぶ。湖面標高は352m、最大深度は212mで、現在の透明度*2は20m前後とされる。周囲は150~350m...

屈斜路湖 ( 北海道 弟子屈町 )
東西約26km、南北約20kmの阿蘇をしのぐ屈斜路*大カルデラ*の北西部にある淡水の大火口原湖で、阿寒摩周国立公園中最大の湖である。摩周火山の堰き止めによって生じたものと考えられるが、周囲には湖岸段丘が発達し、3回に渡って湖面が低下し、湖盆が傾き動いたことが考えられる。 湖面標高121m、湖面積79.4km2、透明度は20m...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会
川湯温泉 ( 北海道 弟子屈町 )
弟子屈町の北部にあり、針葉樹林に囲まれ、アトサヌプリ(硫黄山)の噴煙を仰ぐ温泉。温泉は、摩周湖の伏流水がアトサヌプリで熱せられて自噴しているもの。 この地域は、かつて硫黄の採掘で栄えた。この地に鉄道を敷設させるとともに川湯温泉の発展につなげていったという歴史をもつ。ただし鉄道が開設されたことで硫黄の採掘量が飛躍的...

写真提供:一般社団法人摩周湖観光協会
屈斜路湖畔の温泉 ( 北海道 弟子屈町 )
北海道東部弟子屈町にある屈斜路湖の東岸に仁伏(にぶし)温泉、砂湯、池ノ湯、和琴温泉が並ぶ。湖畔沿いに、ホテル・旅館・民宿などのさまざまな宿泊施設があるが、ここでの楽しみは、湖岸のどこを掘っても温泉が湧出する砂湯*、岩の間から自然に温泉が湧きだしていて湖畔に露天風呂がある池ノ湯温泉*、和琴半島の付け根に露天風呂のある...

春国岱(根室) ( 北海道 根室市 )
風蓮湖と根室湾を区切る長さ8km、幅1.3kmの長大な島。第一浜堤、第二浜堤、第三浜堤の3つの浜堤からなり、面積は6km2。 春国岱には、山と渓谷を除けば、広葉樹林、針葉樹林、草原、湿原、湖沼・川、干潟、塩性湿地といった北海道の自然のエッセンスがほとんどすべてつめこまれているともいわれている。砂丘上に形成されたアカエ...

羅臼湖 ( 北海道 羅臼町 )
ウトロと羅臼を結ぶ知床横断道路のほぼ中央部から、西側の樹林帯の中を約3kmほど進んだところにある面積0.43km2、最大水深2.1mの知床国立公園内では最大の湖。道路沿いの羅臼湖入口からダケカンバやトドマツの混交林内に通る歩道を往復するルートは、標高差約70m、四つの沼や湿原を巡るコースで、往復には3~4時間程度が必要。初...
ウポポイ(民族共生象徴空間) ( 北海道 白老町 )
白老駅から北1kmのポロト湖畔に2020(令和2)年にオープンしたウポポイ(民族共生象徴空間)。以前あったアイヌ文化を扱う野外博物館のポロトコタン*の敷地を拡大してアイヌの文化を紹介し、さらにアイヌ文化の復興・創造等を目指した国立の施設として建設されたもの。 愛称のウポポイとはアイヌ語で「(おおぜいで)歌うこと」を意味し...
鰊御殿 ( 北海道 小樽市 )
小樽駅の北側、直線距離で約5kmの祝津にある高崎岬の高台にあり、日和山(ひよりやま)灯台やおたる水族館に隣接している。ここにある小樽市鰊御殿は、西積丹泊村から1958(昭和33)年この地に移築されたもと網元*の母屋で、間口29m、奥行13m、面積611.9m2の建物。鰊親方田中福松が1898(明治31)年に建築したもので、田中漁場の...
標津湿原(ポー川史跡自然公園) ( 北海道 標津町 )
ポー川*1史跡自然公園は根室中標津空港から北西に約25km、JR釧網本線知床斜里駅から南東に約52km、根室半島と知床半島の中間、オホーツク海を臨むところにある。公園の総面積は約630万m2で、国の天然記念物に指定されている「標津湿原*2」の一部212万m2、国指定の史跡「標津遺跡群*3」のひとつ「伊茶仁カリカリウス遺...

写真提供:株式会社東藻琴芝桜公園管理公社
ひがしもこと芝桜公園 ( 北海道 大空町 )
シバザクラで知られる東藻琴村は、2006(平成18)年に女満別町と合併をして、大空町となった。藻琴山の麓に繰り広がる約10万m2のシバザクラは「ひがしもこと芝桜公園」として整備されている。ここは網走市から車で約45分、女満別空港からは約30分、東藻琴の市街地からは約8kmと至便な地にある。 5月上旬から5月下旬の期間、10...

写真提供:北海道大学植物園
北海道大学植物園 ( 北海道 札幌市 )
札幌市の中央部、北海道庁の西側に隣接した、面積13万3,957m2の植物園。北海道自生植物を中心に約4,000種の植物が育成されており、また世界各地から移植した変わりだねの珍しい植物もある。園内には北方民族植物標本園・高山植物園、温室・冷室とともに北方民族資料室、北海道の動物・考古学の資料の博物館*もある。博物館は北海...

写真提供:江差観光コンベンション協会
姥神大神宮渡御祭 ( 北海道 江差町 )
函館市の西、渡島半島の日本海に面した江差町の町中にある姥神大神宮*の例大祭で、毎年8月9日~11日の3日間に開催されている。ニシン漁で隆盛を極めていた文化・文政年間(1804~1830年)のころ、豊漁を感謝、祈願して行われたのが始まりと言われている。姥神大神宮渡御祭は京都祇園祭に由来したもので、北前船が鰊を京都に運び、京都からは...

写真提供:乙部町役場 産業課
滝瀬海岸(シラフラ) ( 北海道 乙部町 )
乙部町は渡島半島の西部の日本海に面しており、南は江差町、北は八雲町に接している。海岸線沿いに江差町から乙部町に入った直後に長さ約500m・高さ約20mの白壁の断崖がそびえ立つ滝瀬海岸がある。 乙部町役場から南に約1.2km、1国道を右折してくぐり岩への駐車場へ。ここから南側に徒歩で500m海岸線を歩いて到達できる。また、2国道を右...

写真提供:大雪山国立公園管理事務所
大雪高原温泉(池沼群) ( 北海道 上川町 )
大雪山主稜線の高根ヶ原の東斜面のふもとに位置する。ナナカマドやダケカンバ、ミネカエデなどの広葉樹と、エゾマツなどの針葉樹の混交林による森林帯には大小多くの池沼が点在している。標高約1200mの高原温泉を起点にした沼や池をめぐる林間の登山道、大雪高原温泉沼めぐり登山コースが整備されており、1周約7kmの周遊ルートを4時間から5時...
オタトマリ沼 ( 北海道 利尻富士町 )
利尻島の南東に位置する周囲約1.1km、水深約3.5mの島内でもっとも大きな沼である。道路を隔てた海側は、雷泊奇岩で知られる岩礁地帯となっている。沼浦湿原の一部であり、近くには三日月沼がある。沼浦湿原はおよそ7,000年前以前に起きたマグマ水蒸気爆発によってできた火口跡に海面上昇で水がたまり、その後の海退に伴って約4,000年前に誕生...
宗谷丘陵 ( 北海道 稚内市 )
宗谷岬の南部の後背地に広がる標高20~400mまでのなだらかな丘陵地帯。今から約1万年前の氷河期に雨水や川水で削られてできた周氷河地形*である。深い谷はなく、なだらかな波のようにうねる形状をしている。明治の中頃までは丘陵全域にわたりうっそうとした森林が生い茂っていたが、相次ぐ山火事によって、今では一面が宗谷岬牧場による牧草...
盛美園 ( 青森県 平川市 )
弘前市近郊に位置し、津軽尾上駅より西に1kmのところにある。庭園は明治時代に作庭された1.2万m2の池泉廻遊式庭園であるが、一部は枯山水になっている。園内には明治文化の面影を残す盛美館や、御宝殿が立つ。 盛美園は武学流*の真髄を示した名園といわれ、築山庭造伝や造庭秘伝書の形式を忠実に再現したもの。清藤家*24代盛...
種差海岸 ( 青森県 八戸市 )
八戸市の東部、太平洋に面している。蕪島から東の鮫角(さめかど)を南に回って南北約12kmの連続した白い砂浜と岩礁の海岸である。探勝の中心はJR八戸線陸奥白浜駅と種差海岸駅の間、約2kmの海岸が遊歩道で結ばれているエリア。ここの海岸はおだやかな海面を前にして低い段丘が緑の芝におおわれて連続し、一帯は独特の気候に育まれた海浜植物...
蕪島のウミネコ ( 青森県 八戸市 )
蕪島は八戸市の東、種差海岸の西側に隣接している。もとは離島であり吊り橋がかかっていたが、1943(昭和18)年に埋め立てられ、今は周囲約800m、高さ約17mの陸繋島*である。ウミネコ*の繁殖地として有名。毎年2月頃に3万羽から4万羽といわれるウミネコが飛来して巣を営み、4~5月に産卵、7月末に成長したヒナとともに北へ飛び去る。島に...
櫛引八幡宮 ( 青森県 八戸市 )
八戸市の南西、国道104号線沿いにある。古くから南部家*の総鎮守の社、祈願所であった。1664(寛文4)年に八戸藩が盛岡藩から分立した後、盛岡藩の飛び地として残されたのも南部家にとってそれほど重要であったといえる。本殿は1648(慶安元)年南部重直の造営といわれ、三間社流造(さんげんしゃながれづくり)*で屋根は切妻であり、屋根...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
八戸えんぶり ( 青森県 八戸市 )
2月17日の早朝、八戸市と周辺の町村から集まった合計30組を超える「えんぶり組」が長者山新羅神社*に奉納した後、神社の行列にお供をし、美しい烏帽子を冠った太夫*がはやしと歌に合わせ市街で一斉に舞う[一斉摺り(いっせいずり)]。郷土色豊かな田楽として重要無形民俗文化財に指定されている。 東北地方各地では初春の祝いに、田植...

写真提供:八戸市観光課
八戸三社大祭 ( 青森県 八戸市 )
毎年7月31日から8月4日に青森県八戸市で行われる神社神道の祭礼でユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録されている。八戸市内の龗(おがみ)神社*、長者山新羅(ちょうじゃさんしんら)神社*、神明宮(しんめいぐう)*の三社合同例祭である。 7月31日は前夜祭、8月4日は後夜祭で中3日が本祭である。1日目は「お通り(おとお...

法光寺 ( 青森県 南部町 )
南部町の西南、標高615mの名久井(なくい)岳の東麓にある。青い森鉄道、諏訪ノ平駅から南東約6km、15分の位置である。 平安時代に創建された無量山観音寺が草創と伝えるが、建長年間(1249~1256年)に鎌倉幕府の執権北条時頼*が観音寺を廃して当寺を興したと伝わっている。中世には南部氏*と親交をもち、戦国期には東三郎義政の菩提所...
尻屋崎 ( 青森県 東通村 )
下北半島の北東端であり、津軽海峡をはさんで北海道恵山岬と相対している。岬付近の海域は、岩礁が多く、潮の目*にもなっているために、むかしから船の墓場として恐れられてきた。岬の先端には高さ32.8mの尻屋埼灯台*がある。 岬付近の台地は緑の草原に牛馬が群れ、明るく牧歌的な風景である。放牧されている馬は寒立馬*(かんだちめ)...

写真提供:鶴田町企画観光課
鶴の舞橋 ( 青森県 鶴田町 )
JR五能線陸奥鶴田駅の東から県道153号線を利用して約7km、「つがる富士見荘」の駐車場から徒歩で橋のたもとに着く。1994(平成6)年7月8日、日本一長い木製の三連太鼓橋「鶴の舞橋」として架けられたもので、全長300m、幅3m、青森県産のひば材の丸太3,000本、板材3,000枚を使った美しい形の橋である。2016(平成28)年にテレビCM*で知名度が...
大間崎 ( 青森県 大間町 )
下北半島の先端、北緯41度33分に位置する本州最北端の岬で、北海道との距離は17.5km。岬の先端には「本州最北端の地」の碑や「マグロ像」*などのモニュメントがあり写真撮影スポットとなっている。また岬から600m離れた海上にある弁天島と大間埼灯台が岬らしさを感じさせ、絶好の写真背景である。弁天島には赤く小さな弁天神社本殿があり、...
八甲田山 ( 青森県 青森市 / 青森県 十和田市 / 青森県 黒石市 )
青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、那須火山帯*に属し、奥羽山脈北端の堂々とした群峰である。 大別して北・南の2つの山塊に分けられ、北は標高1,585mの主峰大岳を筆頭に1,500m級の火山群10座*からなり、大部分は成層火山である。これらの火山は、いったん陥没してカルデラ*となり、その上に現在の火山群が...
八甲田のブナ林 ( 青森県 青森市 / 青森県 十和田市 / 青森県 平川市 / 青森県 黒石市 )
八甲田山は青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、那須火山帯*に属し、奥羽山脈北端の重鎮である。標高1,585mの最高峰である大岳を中心に、多くの峰が連なる。 植物相の美しさでも名高く、特に山麓の1,000mくらいまでは落葉広葉樹が中心に広がり、その中でも春の新緑、秋の紅葉時の黄色に輝くブナ林は見事である...
八甲田山の樹氷 ( 青森県 青森市 )
八甲田山は青森県の中央、青森市と十和田湖の中間に構える火山群の総称で、奥羽山脈北端の重鎮である。標高1,585mの大岳を最高峰とし、高田大岳、赤倉岳など多くの峰が連なる。 樹氷とはシベリアからの冷たい風が日本海を越えるときに湿気を多く含み、山岳にぶつかり上昇気流に乗るときに急速冷却され、0℃以下の水分のまま雪山の常緑樹に...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
酸ヶ湯温泉 ( 青森県 青森市 )
八甲田大岳の中腹、標高約900mの位置にある古くからの湯治場で、国民保養温泉*の第1号に指定されている。江戸時代 の1684(貞享1)年に開かれたとされている。酸性の強い硫黄泉のため酢ヶ湯と呼ばれていたと考えられる*。高温自然湧出の源泉を求める湯治客と、十和田奥入瀬の途中に立ち寄る観光客でにぎわう。 最近は豪雪地域の代名詞と...
青森のねぶた・ねぷた ( 青森県 青森市 )
東北三大祭り*のひとつで、短い夏を謳歌するように熱気を帯びた祭りである。「ねぶた」や「ねぷた」などと言われ、名称は各地で若干異なるが、青森県内各地域40箇所以上で7~8月に開催されている。禊祓(みそぎはらえ)などその起源*も諸説あるが、古くから大切に受け継がれてきた伝統行事。あかりを灯した巨大な灯籠(=ねぶた)を山車に乗...
城ヶ倉渓流 ( 青森県 青森市 )
城ヶ倉渓流は十和田国立公園、八甲田山系の大岳、櫛ケ峰、駒ケ峰に源を発して、陸奥湾に注ぐ2級河川の上流部。渓流の岩壁は、第三紀中新世中頃(およそ1千万年前)の火山活動でできた柱状節理*の深く狭い渓谷である。流れの水は強酸性で魚は生息しておらず、11月から5月までは数mの雪に埋もれる厳しい環境にある。 以前は酸ヶ湯からの遊...
三内丸山遺跡 ( 青森県 青森市 )
青森駅の南西約7km車で約20分、青森県立美術館や県総合運動公園に隣接した緑豊かな空間の中にある三内丸山(さんないまるやま)遺跡は日本最大級の縄文集落跡である。1992(平成4)年から始まった発掘調査では、約5,900~4,200年前の縄文時代前期~中期(紀元前約3900~2200年)の大規模な集落跡が見つかり、多くの建物跡や盛土、墓、土器や...
写真提供:©ADAGP,Paris&JASPAR,Tokyo,2023,Chagall®X0157
青森県立美術館 ( 青森県 青森市 )
青森駅の南西約7km車で約20分、三内丸山遺跡、県総合運動公園に隣接した緑豊かな空間の中にある。三内丸山遺跡と一帯の文化観光拠点として、また青森県の芸術文化を発信することを目的として2006(平成18)年に開館した。 展示作品はシャガールの大作「アレコ」の舞台背景画(9mx15m)4点(※第3幕はアメリカフィラデルフィア美術館が所蔵...

写真提供:ねぶたの家 ワ・ラッセ
ねぶたの家 ワ・ラッセ ( 青森県 青森市 )
「ねぶたの家 ワ・ラッセ」は2011(平成23)年1月にJR青森駅前の海側にオープンした施設である。ねぶた祭の歴史や魅力を紹介し、ねぶたのすべてを、1年を通じて体感することができる空間である。 入り口から2階に上がると展示施設の「ねぶたミュージアム」が始まる。ねぶたの由来、歴史、制作工程がトンネル内に紹介され歩きながら学べる...
白神山地のブナ原生林 ( 青森県 西目屋村 / 青森県 鰺ヶ沢町 / 青森県 深浦町 / 秋田県 藤里町 / 秋田県 八峰町 )
白神山地は、秋田県北西部と青森県南西部の標高約800~1,250mの山岳地帯、1,300㎢に及ぶ広大な山地の総称で、この地域には人為の影響をほとんど受けていないブナ林が分布している。多種多様な動植物が生息・自生するなど貴重な生態系が保たれており、1,300㎢の山地のうち約170㎢が1993(平成5)年12月に世界遺産(自然遺産)に登録*された。 ...

写真提供:西目屋村役場
暗門の滝 ( 青森県 西目屋村 )
弘前駅から西へ約35km、車で約1時間の位置にあるアクアグリーンビレッジANMON*が滝の散策拠点施設である。ここから遊歩道で片道約1時間。津軽の母なる川「岩木川」の支流である暗門川にかかる3段の滝が暗門の滝である。 3段の滝は上流から第一の滝、第二の滝、第三の滝となり、落差はそれぞれ42m、37m、26mである。世界遺産登録地域の...

写真提供:深浦町役場観光課
十二湖 ( 青森県 深浦町 )
JR五能線十二湖駅の東3~4km、白神山地西部の標高150~250mの起伏の多い台地に約4km2にわたって散在する湖沼群。十二湖と呼ばれてはいるが、実際には大小33の湖沼がある。十二湖の東方にある崩山の大崩展望台から十二の湖が見えるので、十二湖の名前がついたという。 湖沼の成因については地すべり地震によって谷がせき止めら...

写真提供:深浦町役場観光課
日本キャニオン ( 青森県 深浦町 )
JR五能線十二湖駅の東約2.5km、十二湖の入口にあたる一帯に位置する。濁川上流の渓谷にそびえる大断崖で、山崩れで露出した白い凝灰岩が特異な景勝をつくっている。規模こそはるかに及ばないが、アメリカのグランドキャニオンに似ているので、1953(昭和28)年の探検家の岸衛の発言*によって日本キャニオンと命名されたという。 日本キャ...
黄金崎不老ふ死温泉 ( 青森県 深浦町 )
JR五能線ウエスパ椿山駅*の北約2.5km、黄金崎の海岸にある露天風呂で有名な温泉。眼前に日本海がひろがり、海水浴や海釣りを楽しむことができる。一軒宿で、海辺に混浴の露天風呂があり、夕日がみごとである。日帰り利用も可能であるが、時間制限などがあるので、夕日を楽しむのであれば宿泊したい。露天風呂に出られる本館と、宿泊専用の宿...
蔦七沼 ( 青森県 十和田市 )
南八甲田山麓にある蔦温泉の周辺の樹林の中に点在する湖沼群。蔦沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、瓢箪沼の順に連なり、少し離れた赤沼と合わせ蔦七沼と総称される。いずれもブナ林に包まれて緑豊かである。最も大きな蔦沼は周囲約1km、コイ・イワナなどが生息する。赤沼だけは温泉から約3km北西へ離れているが、透明度の高いことで知られる。赤...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
奥入瀬渓流 ( 青森県 十和田市 )
奥入瀬川は十和田湖から流出する唯一の河川で八戸市の北で太平洋に注いでおり、全長は約71kmである。その上流部の、「十和田湖畔子ノ口」(とわだこはんねのくち)から「焼山」(やけやま)までの約14kmの区間が奥入瀬渓流である。この区間は、森の中を千変万化して流れ下る川の水が渓流美をつくりだし、十和田湖とともに東北の代表的な景勝...
蔦温泉 ( 青森県 十和田市 )
八甲田の南東約8km、蔦川の谷と多くの沼に近接した自然美の中にある。発見は約800年前ともいわれ、八甲田の温泉群では酸ヶ湯とともに歴史の古い温泉である。明治の文人大町桂月*が愛したことでも知られ、旅館の近くには墓碑が立ち、ブロンズの胸像もある。 温泉は湯船の足元から湧き出る源泉湧き流しの湯で、男女入れ替え制の「久安の湯...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
八甲田山麓の湿地・湿原 ( 青森県 十和田市 / 青森県 青森市 )
八甲田山の大岳を主峰とする北部八甲田山系の山裾に多くの湿地・湿原*が存在する。このうち山麓を周遊する道路沿いには遊歩道や散策道でトレッキングできるエリアも多い。 八甲田山の北部山麓の八甲田温泉近くには田代平湿原、南麓には谷地湿地と睡蓮沼周辺の湿地、酸ヶ湯温泉近くには地獄沼周辺に湿地があり、八甲田山の中腹、山頂部に...

松見の滝 ( 青森県 十和田市 )
十和田市の西、十和田湖の北部にあり、奥入瀬川の支流である黄瀬川上流の国有林内、標高500mに位置する落差90mの滝である。 国道102号線から徒歩で片道約3時間ほど要し、かなり急勾配な箇所もあるので、ある程度の登山用装備や熊対策などが必要。 松見の滝という名前は滝の両側に自生する松からと言われており、滝は上下二段に分かれてい...
仏ヶ浦 ( 青森県 佐井村 )
斧の形をした下北半島の刃の部分、津軽海峡に面した福浦(ふくうら)と牛滝(うしたき)の間、白い岩の奇岩からなる約2㎞の海岸線である。 名前の由来は、アイヌ語の「ホトケウタ-仏のいる浜」が転訛した結果「仏ヶ浦」と呼ばれるに至ったという説や、「如来の首、十三仏、五百羅漢等の姿が仏像仏具を思わせ、ほとんどが仏の名にちなんで...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
青荷温泉 ( 青森県 黒石市 )
黒石駅から国道102号線で約14km、東方の道の駅虹ノ湖の先を左折して4km、山間の青荷渓流沿いに湧く一軒宿の温泉で、ランプの宿として知られている。国道から左折した後は山道でカーブが続くので注意が必要。駐車場からは徒歩で下り玄関前広場につく。冬期は積雪で一般車は通行止めで、道の駅虹ノ湖から宿の送迎シャトルバスを利用する。 ...
温湯温泉 ( 青森県 黒石市 )
弘南鉄道黒石駅の東南約8km、黒石温泉郷*の玄関口にあたり、浅瀬石川沿いにある。昔は湯治主体の温泉で、浴場の周りには客舎と呼ばれる宿があり、自炊しながら2週間ぐらい滞在する湯治客で溢れ、集落内には商店、魚屋、下駄屋、こけし屋、あけびづる細工の籠屋、製材所、映画館まであった。今は湯治客も客舎も減り、客舎の跡地に車で訪れる...
岩木山 ( 青森県 弘前市 / 青森県 鰺ヶ沢町 )
津軽平野の南西方にそびえる、鳥海火山帯に属する二重式火山。津軽富士と呼ばれる円錐形の独立峰で、標高1,625mの青森県最高峰である。山頂部は中央の岩木山、北の巌鬼山、南の鳥海山の3峰に分かれている。 岩木山の火山活動の大部分は第四紀洪積世*に行われたと言われているが、最後の噴火は1863(文久3)年で新しい火山といえる。まず...

写真提供:弘前市
弘前城 ( 青森県 弘前市 )
弘前城は弘前市の中心部にあり、本丸・北の郭・二の丸・三の丸・四の丸・西の郭の6つの郭*で構成された平山城である。規模は東西約500m、南北約1,000m、総面積約50万㎡に及ぶ。濠は三方・三重に巡らされ、西側は蓮池と、元は岩木川の流路であった西濠に守られている。 弘前藩代々の居城で、1611(慶長16)年に2代藩主津軽信枚(のぶひら...

写真提供:弘前市
弘前城のサクラ ( 青森県 弘前市 )
弘前城は、弘前藩2代藩主・津軽信枚(のぶひら)が1611(慶長16)年に築城したもの。400年を経た今も当時の城の形が残っており、天守、3つの櫓、5つの城門は国の重要文化財に指定されている。日本屈指のサクラの名所としても有名であり、開花時期にはテレビなどでよく取り上げられている。4月下旬には、ソメイヨシノやヤエザクラなど約2,600...
岩木山神社 ( 青森県 弘前市 )
岩木山の東南麓、標高200mの百沢(ひゃくざわ)地区にある。県道3号線に面しており、そこからの参道は正面に岩木山を望んでまっすぐに延び、やがて楼門*、その奥に中門があり、さらに拝殿*・本殿*が立つ。 神社の創建については様々な言い伝えがあるが、奈良時代の780(宝亀11)年*に岩木山頂に祠を祭ったのが始まりといわれ、平安時...

写真提供:金剛山最勝院
金剛山 最勝院 ( 青森県 弘前市 )
弘前城の南東約1㎞の台地の上に位置し、五重塔の美しさで有名な寺院。江戸時代の建立で現存する五重塔は全国で22塔あるが、最勝院五重塔は最北の五重塔。国指定重要文化財の指定説明に特筆される「東北地方第一の美塔」にたがわず、その姿は美しい。高台にあるため、街中からでもひときわ目立つ存在感があり、弘前市のシンボルとして親しまれ...

弘前のりんご畑 ( 青森県 弘前市 )
弘前市はりんごの生産が盛んで、生産量は年間18.2万tと日本一、全国の73.7万t(2022(令和4)年)の約1/4を占めている。春夏秋冬の区分がはっきりし、昼夜の温度差が非常に大きい気象がりんごの栽培に適し、津軽地方の「じょっぱり」と呼ばれる真面目で負けず嫌いの頑固な気質が、りんご生産に生かされていると言われている。 1877(明...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
お山参詣 ( 青森県 弘前市 )
稲が実る旧暦8月1日、五穀豊穣の感謝と祈願をこめ、岩木山の山頂にある岩木山神社奥宮に集団で登山する行事。岩木山は津軽平野の南西方にそびえる、鳥海火山帯に属する二重式火山。津軽富士と呼ばれる円錐形の独立峰で、標高1,625mの青森県最高峰である。津軽平野の各地から美しい姿を望むことができるため、津軽地方の人々にとってかけがえ...
十三湖 ( 青森県 五所川原市 )
津軽半島の中西部、岩木川の河口部にある東西5km、南北7km、周囲31.4kmの潟湖*で、北西部の幅が250mあまりの水路によって日本海と通じている。南から岩木川や山田川など十三の河川が流れ込むので十三湖と言われている。西は七里長浜に続く砂丘帯で、砂州の先端に十三(じゅうさん)*の集落が細長く連なっている。 十三湖の中島へは長さ3...
ストーブ列車 ( 青森県 五所川原市 )
津軽鉄道は、津軽五所川原駅から津軽中里駅間20.7kmを45分で結ぶローカル線であり、1930(昭和5)年に開業。ストーブ列車もこの年の冬から運転を開始している。1944(昭和19)年から3年間は物資欠乏のため中止したが、1947(昭和22)年から再びストーブ列車を運転し、現在に至っている。現在運行されているストーブ列車は4代目の客車で、オハ...
龍飛崎 ( 青森県 外ヶ浜町 )
津軽半島の突端、龍飛崎は北緯41度15分に位置し、津軽海峡をへだてて向かいあう北海道の白神崎とはわずか20kmの距離にある。岬付近は標高100m前後の高台になっており、北西寄りに龍飛埼灯台が立っている。 龍飛崎の周辺には、小説「津軽」の一文を刻んだ「太宰治*文学碑」があり、台地の上の碑の丘には川柳作家「川上三太郎*句碑」、幕...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
横浜町の菜の花畑 ( 青森県 横浜町 )
下北半島の付け根の西側にある横浜町。この町を南北に貫くはまなす街道(国道279号線)や町内の農道周辺が、日本最大級である約100万m2の作付け面積*を誇る菜の花の名所となっている。菜の花の品種はセイヨウアブラナの一種のキザキノナタネといい、美しい景観をもたらすだけでなく、菜種油*としても利用されている。 横浜町...

写真提供:佐井村役場
縫道石山(縫道石) ( 青森県 佐井村 / 青森県 むつ市 )
下北半島北西部のむつ市と佐井村にまたがる、標高626mの名峰のひとつで断崖絶壁の岩山。その特異な姿から江戸時代には地元で「入道石」と呼ばれていたことが、紀行作家、菅江真澄*の「遊覧記」や、古い「佐井村誌」に記録されている。 標高が高くなく、前衛の山に囲まれているため、周辺の平地から確認するのは難しい。 むつ市から国...
宇曽利山湖 ( 青森県 むつ市 )
恐山菩提寺の南に隣接する、火山爆発によってできたカルデラ湖である。水面の標高は210m、周囲は7.1kmで、面積は2.65km2、最大水深は約20m、湖水の透明度は13.0m*でわが国第8位。火口湖特有の強酸性湖で、その形状はほぼ円形で肢節量(1.23)*はカルデラ湖において全国4位である。 平安時代の僧の円仁*が霊場をさがす途中に...
薬研渓流 ( 青森県 むつ市 )
下北半島の北側中央部、薬研温泉を中心とした大畑川上流の約2kmにわたって広がる、滝、渕、岩などの美しい渓谷である。清流を原生林がおおい、遊歩道もあり、新緑、紅葉時にはすがすがしく自然散策や森林浴、バードウォッチングなどが楽しめる。 渓流沿いには緑に包まれた薬研温泉、奥薬研温泉がある。温泉の湧出口の形が漢方薬をすりつぶ...

霊場恐山 ( 青森県 むつ市 )
下北半島の中央部、JR大湊駅からむつ大畑公園線で北西へ約17km、宇曽利山湖畔の北側に位置する。恐山菩提寺の入り口の総門を入ると左側に本堂が見え、さらに山門をくぐると40余基の常夜燈が立ち並び、参道の奥には地蔵殿が立つ。参道の右手には宿坊、左手には古滝ノ湯・花染ノ湯など恐山温泉と呼ばれる質素な造りの浴舎も点在し、現在も入浴...

写真提供:青森県及び公益社団法人青森県観光国際交流機構
田名部まつり ( 青森県 むつ市 )
下北半島、むつ市の中心の田名部にある田名部神社*の例祭で、8月18日~20日に行われる。北前船*によって伝えられた京都祇園祭の流れをくみ、1640年頃(寛永年間)から続いている。 田名部神社の本殿は一間社流造、銅板葺き。拝殿は鉄筋コンクリート、神明造、銅板葺き。祭神は昧耜高彦根命(あじしきたかひこねのみこと)、誉田別命(ほ...
根城 ( 青森県 八戸市 )
根城は、南部師行(なんぶもろゆき)*が1334(建武元)年に築いた平城。南部氏が遠野へ国替えになる1627(寛永4)年までの約300年間、南部氏の居城として北東北地方の中心であった。八戸市中心部の西、国道104号線沿いに塀や土塁などが残り、1941(昭和16)年に城跡が国史跡に指定された。その後、1978(昭和53)年から発掘調査及び整備事業...
高山稲荷神社 ( 青森県 つがる市 )
津軽半島の十三湖南の屏風山中、小高い丘陵の上に鎮座する。入母屋造の現拝殿は1948(昭和23)年に再建され、五穀豊穣、商売繫盛を願う参拝者が訪れる。 津軽半島西側を走るメロンロード*から西側に入ると、1.5km先の大きな鳥居の先に駐車場と参集殿があり、左に折れて96段の石段を上がった所に拝殿がある。拝殿から石段を登り反対側に降...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
北上・みちのく芸能まつり(鬼剣舞) ( 岩手県 北上市 )
毎年8月の第1金曜から3日間にわたって行われる祭り。メイン会場は、東北自動車道北上江釣子ICから約10分、JR北上駅から徒歩約3分のJR東日本北上駅前のまつり広場。 約500mの道路に設けられた8つの会場で、県内外から参加した100余りの団体が鬼剣舞*や鹿踊(ししおどり)*をはじめ、神楽*、田植踊*などの芸能を披露し、町が祭り一色...

夏油温泉 ( 岩手県 北上市 )
JR東北本線・東北新幹線北上駅から西北西へ約22km。夏油川上流、栗駒国定公園の北部に位置し、焼石連山の山ふところ標高700mの高地にある。夏油温泉を含んだ入畑温泉、瀬美温泉、水神温泉の4つの温泉の総称で夏油高原温泉郷と称する。夏油川沿いではいたるところで温泉が湧出しており、真湯・大湯・滝ノ湯・疝気(せんき)ノ湯・女(め)ノ湯...

写真提供:平泉町教育委員会
無量光院跡 ( 岩手県 平泉町 )
JR平泉駅の北800mにある。鎌倉幕府の事跡を記した史書「吾妻鏡」によれば、無量光院は新御堂(しんみどう)と号し、奥州藤原氏三代秀衡が宇治平等院を模して建立したといわれ、現在は土塁・礎石・池跡などが残されている。毛越寺・観自在王院と並ぶ臨池伽藍(りんちがらん)*で、堂内の四壁の扉に観経(かんぎょう)*の大意を図絵し、本尊...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
中尊寺 ( 岩手県 平泉町 )
中尊寺は天台宗の東北大本山で関山と号し、山内の寺塔僧房(17支院)からなる一山寺院をいう。JR東北本線平泉駅から北北西へ約2km、北上川と衣川の合流点の西、こんもりとした小山の中にある。蝦夷と称せられた藤原三代*が100年間にわたって築き上げた仏国土建設の跡である。 寺伝によれば850(嘉祥3)年、慈覚大師*が弘台寿院(こうだ...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
毛越寺 ( 岩手県 平泉町 )
毛越寺は天台宗の別格本山で医王山金剛王院と号し、17院からなる一山寺院をいう。JR東北本線平泉駅の西にある。 寺伝では850(嘉祥3)年、中尊寺と同じく慈覚大師*が嘉祥寺を開き、毛越寺の基としたといわれる。その後、堀河天皇より藤原清衡*が勅命を受け、基衡*、秀衡*の時代に多くの伽藍が造営された。金堂円隆寺をはじめ、嘉祥寺...

写真提供:平泉町教育委員会
観自在王院跡 ( 岩手県 平泉町 )
毛越寺の東隣にあり、JR平泉駅より徒歩8分。観自在王院は安倍宗任(あべのむねとう)*の娘である奥州藤原氏二代基衡の妻が建立した寺院で、16世紀の火災で堂塔を失い、庭園も水田化したが、昭和の遺跡発掘調査の成果に基づいて伽藍遺構と庭園の修復・整備が行われた。調査によれば境域は東西約120m、南北約180m。西域に土塁の一部が残り、大...

写真提供:普代村
黒崎 ( 岩手県 普代村 )
岩手県沿岸北部、北山崎の北方5kmにある岬で、弁天崎まで連なる断崖の北端にあたり、150~200mの高さから黒っぽい絶壁が海に落ち込んでいる。隆起した海岸が荒波に削り取られて、ほぼ垂直に切り立った崖が形作られた隆起海岸である。 赤松の自然林におおわれた岬には先端に白い灯台と北緯40度のシンボル塔が立ち、国民宿舎をはじめ外洋20...

写真提供:八幡平市
八幡平 ( 岩手県 八幡平市 / 岩手県 鹿角市 )
盛岡市から北西に直線で約38km、岩手県と秋田県にまたがる高原で、奥羽山脈北部に位置する。東の茶臼岳(標高1,578m)、南の畚岳(標高1,578m)、西の焼山(標高1,366m)などを含めた地域を八幡平と呼ぶが、狭義にはこの高原のほぼ中央、標高1,614mの頂が八幡平山頂である。 山域は十和田八幡平国立公園に指定され、中でも山頂付近は...

写真提供:八幡平市
岩手山 ( 岩手県 滝沢市 / 岩手県 八幡平市 / 岩手県 雫石町 )
盛岡市の北西約22km、十和田八幡平国立公園の南西部に大きくすそ野を広げる成層火山*。那須火山帯*に属し、第四紀に噴出したものといわれる。少なくとも、国内の活火山の中では最多といわれる7回もの山体崩壊を起こしており、その際の堆積物が山麓を覆っている。山体は東岩手と西岩手の2つの火山群からなるが、西岩手の方が古く、その火口...

写真提供:八幡平市
岩手山焼走り熔岩流 ( 岩手県 八幡平市 )
岩手山の北東山腹、標高1,200m付近で見られる、長さ4km、末端における幅は1.5kmに及ぶ溶岩流である。東北自動車道西根ICから県道233号線を経由して約15分ほど走ると散策路入口に到着する。1719(享保4)年の噴火によって流れ出た溶岩が扇状に広がり、表面の波絞の如き凸凹には樹木がほとんど育たず、わずかに苔などが生えているだけという荒...

写真提供:藤七温泉 彩雲荘
藤七温泉 ( 岩手県 八幡平市 )
東北自動車道松尾八幡平ICより八幡平アスピーテラインまたは樹海ライン経由で約60分。JR盛岡駅より岩手県北バス八幡平頂上行きで1時間50分、松尾鉱山資料館で八幡平蓬莱境行きに乗り換え5分、藤七温泉下車すぐ。 八幡平頂上の南方3.5km、畚(もつこ)岳の麓の標高1,400mの高所にあり、東北最高峰に位置する温泉で、一軒宿である。 温泉...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
北山崎 ( 岩手県 田野畑村 )
岩手県沿岸北部、田野畑村の北東端に位置する。陸中海岸の代表的な景観で、隆起した海岸が荒波に削り取られて、ほぼ垂直に切り立った崖が形作られた隆起海岸である。高さ約200mの大断崖が連なる場所で、日本の海岸風景の中で最も迫力のある美しさを誇り、弁天崎~北山崎~黒崎の間は断崖が連続していることから海のアルプスともよばれている...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
北上川 ( 岩手県 滝沢市 / 岩手県 盛岡市 )
北上川は源を岩手県岩手郡岩手町御堂に発し、岩手県の中央をほぼ北から南に流れ、一関市下流の狭窄部を経て宮城県に入り、登米市津山町付近で北上川と旧北上川に分流する。流域には東に北上山地、西に奥羽山脈の高峰が連なり、これらの山地から流入する数多い支川を合わせて北から南に流下する。幹川流路延長は全国第5位の約249km、流域面積...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
岩洞湖 ( 岩手県 盛岡市 )
東北自動車道盛岡ICから自動車で約1時間、盛岡市藪川にある湖。標高約700mの北上山地に位置し、流域面積*48.6km2、湛水面積*6.23km2と広大な規模を誇る。 岩手山東麓の水田灌漑を主目的とするが、水力発電の目的も兼ねて、1960(昭和35)年に完成した人造湖(ダム湖)である。湖畔にはシラカバやナラなどの広葉樹...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
姫神山 ( 岩手県 盛岡市 )
いわて銀河鉄道(IGR)渋民駅の東8km、登山口まで自動車で約25分、北上川をはさんで岩手山と相対して位置する。岩手山、早池峰山と並び、霊山として知られている。外山早坂高原県立自然公園内にあり、姫神自然観察教育林になっている。 標高は1,123.8m。なだらかな裾野を引く円錐形の山容で、登山が容易で日帰りのハイキング地として人気...

写真提供:盛岡さんさ踊り実行委員会
盛岡さんさ踊り ( 岩手県 盛岡市 )
毎年8月1~4日に盛岡市の中央通、岩手県公会堂前から約500mをパレードする祭典。さんさ踊りの発祥は、名須川町の三ツ石神社にまつわる「三ツ石伝説」に由来するといわれる。その昔、盛岡城下で暴れる鬼に困り果てた里人たちが、三ツ石神社に退治を祈願。三ツ石神社の神は悪鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう、境内の大きな三ツ石に誓いの手...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
日高火防祭 ( 岩手県 奥州市 )
JR東北本線水沢駅から徒歩約10分、岩手県奥州市水沢の市街地で実施される、はやし屋台が巡行して火防を祈願する祭。本祭は4月最終土曜日、前夜祭は本祭の前日に行われる。 少年時代、江戸にいた伊達宗景は、1657(明暦3)年の大火をはじめとした火事の多さ、恐ろしさに驚き、水沢に戻った後、火防の対策に万全の策を講じた。天災を神仏の...

写真提供:住田町観光協会
種山ヶ原 ( 岩手県 住田町 / 岩手県 遠野市 )
北上高地南西部の東西11km、南北20kmに及ぶ緩やかな稜線を持った平原状の山で、岩手県奥州市、気仙郡住田町、遠野市にまたがる。物見山(種山)を頂点とした標高600~870mに位置し、物見山・大森山・立石などを総称して「種山高原」とも呼ばれている。その地形と涼しい気候のため、藩政時代から馬の放牧地として利用され、各所にツツジの群落...

写真提供:小岩井農牧
小岩井農場 ( 岩手県 雫石町 )
JR東北本線・東北新幹線盛岡駅から北西約12km、岩手山南麓に約30km2の敷地面積を有する民営の農場。日本最初の鉄道敷設を始めとした数々の鉄道工事で陣頭指揮し、「日本の鉄道の父」と呼ばれた井上勝*が、鉄道事業により美しい田園風景を損なってきたことへの埋め合わせの意味を込め、国家公共のためになすべき事業として、小野...

写真提供:一般社団法人しずくいし観光協会
国見温泉 ( 岩手県 雫石町 )
東北自動車道盛岡ICから国道46号線経由で約36km、約55分、八幡平国立公園内に位置する。岩手県と秋田県の県境、秋田駒ヶ岳南麓の国見峠の標高約880mの山腹にある素朴な山の湯。 温泉は含重曹土類硫化水素泉で、52~62℃。澄んだエメラルドグリーンの色合いが特徴で、コールタールのような独特のにおいがある。駒ヶ岳や千沼ヶ原などへの登山...

千沼ヶ原 ( 岩手県 雫石町 )
秋田駒ヶ岳と岩手山の間に位置し、乳頭山(烏帽子岳東)の東南方、標高1,400mに広がる高層湿原*。ニッコウキスゲ・ヒナザクラなどの高山植物に彩られ、大小の池塘が点在する大湿原で、周囲はオオシラビソに囲まれている。1954(昭和29)年に初めて人が入り、山上の仙境として話題となった。湿原までのルートが長く、経験を積んだ登山客以外...

写真提供:山田町
山田湾 ( 岩手県 山田町 )
盛岡から車で2時間、岩手県三陸沿岸のほぼ中央に位置する山田湾は、重茂(おもえ)半島と船越半島に囲まれた周囲30km、ほぼ円形に近い湾で、「海の十和田湖」と呼ばれている。 湖水のように波静かな湾内には無人島の大島、小島が浮かぶ。周囲約900m、面積26,960㎡の大島は、1643(寛永20)年にオランダ船のブレスケンス号が食料と水を補...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
栗駒山 ( 岩手県 一関市 / 宮城県 栗原市 / 秋田県 東成瀬村 )
奥羽山脈のほぼ中央に位置し、岩手・宮城・秋田の3県にまたがる1,626mの山で、岩手県側では須川(すかわ)岳、秋田県側では大日(だいにち)岳とも呼んでいる*。那須火山帯*に属する複雑な山容の休火山で、かつては八万地獄、毒気地獄などと呼ばれ、この山に入った者は生きて帰ることがないといわれた。現在でも北斜面中腹にはたくさんの硫...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
金ケ崎町城内諏訪小路 ( 岩手県 金ケ崎町 )
JR東北本線金ケ崎駅から徒歩5分の場所に位置する、旧金ケ崎要害の城と武家町のほぼ全域にあたる地域。江戸時代は大町氏3000石の城下町で、仙台藩伊達領の最北端にあたり、対盛岡藩の拠点として金ケ崎要害と称された。今も表小路・達小路などに武家屋敷のたたずまいが見られ、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。 金ケ崎要害...

写真提供:花巻市
早池峰山 ( 岩手県 花巻市 / 岩手県 宮古市 / 岩手県 遠野市 )
早池峰山は標高1,917mの山で、山頂は花巻市、宮古市、遠野市の3つの市の境界となっている。北上山地の最高峰で、東に剣ヶ峰、西に中岳・鶏頭山・毛無森など標高1,500m前後の山稜が続き、全長は東西16kmにわたっている。 北上山地は、早池峰山を境に北部と南部に分かれ、その成り立ちは異なる。北部北上山地は、古生代石炭紀と中生代ジュラ...

写真提供:宮古市
浄土ヶ浜 ( 岩手県 宮古市 )
浄土ヶ浜*は、宮古市北東の宮古湾の、こぶのように突き出た半島北側に広がる。東北自動車道盛岡南ICから車で90分、第一駐車場から徒歩10~15分、JR宮古駅から浄土ヶ浜行きバスで約20分の浄土ヶ浜バス亭で下車してすぐの場所にある。 白い岩と小石が作る入江となっており、外海から隔てられているため、波の穏やかな浜である。白い岩は流...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
三陸鉄道 ( 岩手県 宮古市 / 岩手県 久慈市 / 岩手県 大船渡市 )
岩手県の三陸海岸を縦貫する鉄道路線(リアス線)および、第三セクター方式の鉄道会社。通称は三鉄(さんてつ)。 1896(明治29)年の三陸地震の際に急峻な地形が支援物資の輸送を阻んだことから三陸沿岸を結ぶ鉄道が構想され、復興策として建設された。1928(昭和3)年11月22日に仙台~石巻間(宮城電気鉄道、現在の仙石線)が開通し、19...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
平庭高原 ( 岩手県 久慈市 / 岩手県 葛巻町 )
JR八戸線、三陸鉄道リアス線の八戸駅から西南西へ約26km、久慈渓流の上流、久慈市と葛巻町の境界にある平庭岳の中腹に広がる高原で、久慈・平庭県立自然公園の一環をなしている。標高800m。 国道281号線の両側4.5km、面積にして369万m2の範囲に約31万本もの白樺が林立しており、日本一の白樺美林といわれる。 レンゲツツジ...

写真提供:久慈市
久慈渓流 ( 岩手県 久慈市 )
久慈市南西部の明神岳に源を発する久慈川の上流に位置する渓流。中でも板状の石灰岩が垂直に切り立ち鏡のように平らになった鏡岩の付近約5kmには、浸食よって形成された石灰岩の絶壁、不老泉、白糸ノ滝などの景勝が続く。 鏡岩を臨む鏡岩園地にある名水の不老泉には、飲用すると持病が治り不老長寿になるという言い伝えがある。また周辺に...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
内間木洞の氷筍 ( 岩手県 久慈市 )
内間木洞は久慈市南端部、内間木川上流の山間にある鍾乳洞で、JR久慈駅、三陸鉄道久慈駅より車で約45分の場所にある。 総延長が6,350m以上にも及ぶ、国内でも有数の鍾乳洞である。特に冬場は、洞内の天井から落ちる水滴が地面で凍りつき、筍(たけのこ)状に成長する氷筍(ひょうじゅん)が群生することで名高い。氷筍は、大きなものでは2...

写真提供:岩泉町役場
早坂高原 ( 岩手県 岩泉町 / 岩手県 盛岡市 )
JR東北本線・東北新幹線の盛岡駅から東北東へ約37km。岩泉町と盛岡市の境、標高916mの早坂峠を中心に広がる大平原で、緩やかに起伏する草原に白樺林や赤松の林が点在する。 北上山地のなだらかな高原に、ブナ、ダケカンバ、シラカンバ、ミズナラ、ドイツトウヒ、アカマツが生育する景勝地。4月下旬~5月中旬はカタクリ、6月上旬~中旬はレ...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
龍泉洞 ( 岩手県 岩泉町 )
岩泉町の北西2km、標高625mの宇霊羅山の東麓に洞口がある。山口県の秋芳洞、高知県の龍河洞とともに日本三大鍾乳洞のひとつに数えられ、国の天然記念物にも指定されている。 約2~3億年前、北上山地一帯が海の底だった頃に有孔虫やサンゴなどの遺骸が海底に沈積し、これが龍泉洞を形成する安家(あつか)石灰岩層のもとになったといわれる...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
安家洞 ( 岩手県 岩泉町 )
安家洞は、三陸鉄道リアス線の岩泉小本駅から北西へ約25kmの距離にあり、安家石灰岩層*のほぼ中央にあたる。総延長は、鍾乳洞では日本最長の23.7km。 約2億数千万年前の海底で有孔虫やサンゴなどの生物の殻が堆積してできた石灰岩層である安家層が、その後の隆起で地上に押し上げられ、雨水に侵食されて形成されたもの。岩泉周辺ではこの...

写真提供:鉛温泉 藤三旅館
鉛温泉 ( 岩手県 花巻市 )
花巻市の大沢温泉の上流4km、豊沢川に臨む静かな山間の温泉。JR花巻駅より岩手県交通バス湯口線、新鉛温泉行きで約30分、鉛温泉下車。東北自動車道花巻南ICより約20分。 宝暦年間(1751~1764年)の発見と伝えられ、南部藩主も来浴したといわれる。加熱、加水、循環させない完全源泉100%の掛け流しであり、白猿の湯、桂の湯、白糸の湯、銀...

写真提供:花巻市
花巻まつり ( 岩手県 花巻市 )
花巻市で毎年9月第2土曜日を中日とした金・土・日曜日に開催される、430年を超える歴史を持つ祭り。 アセチレンガスの灯に包まれた風流山車*、100基を超える勇壮な神輿*、迫力のある鹿踊(ししおどり)や神楽権現舞、優雅な花巻ばやし踊りなど、花巻の情緒豊かな伝統文化が随所で見られる。 花巻城主の北松斎(きたしょうさい)*が...

写真提供:花巻温泉株式会社
花巻温泉 ( 岩手県 花巻市 )
JR東北本線・釜石線の花巻駅から北西約7km、背後に山を負い東南に平野を見晴らす台地にある。1923(大正12)年に盛岡の実業家、金田一国士(きんだいちくにお)*が付近を流れる台川上流の台温泉*から湯を引き、開湯した。現在は桜や松の並木が整備され、花巻温泉株式会社が経営する4軒の大型ホテル(佳松園、ホテル千秋閣、ホテル花巻、ホ...

焼石岳 ( 岩手県 奥州市 / 西和賀町 西和賀町 )
JR東北本線水沢駅から西に約28km。岩手県南西部に位置し、奥州市と和賀郡西和賀町の境にある火山。標高1,547m。奥羽山脈中部に属し、栗駒国定公園の一部である。焼石連峰の主峰で南に横岳、獅子ヶ鼻岳、西に三界山、北に牛形山、東に経塚山などがある。 焼石の名は、山頂付近の焼けたような黒い岩にちなむ、薬師岳に由来するなど諸説ある...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
宮守川橋梁(めがね橋) ( 岩手県 遠野市 )
遠野市内、JR釜石線の宮守駅から徒歩約10分、JR釜石線の宮守駅と柏木平駅の間にある。アーチ状のコンクリート製の橋で、特徴的な形状から通称「めがね橋」と呼ばれている。1915(大正4)年に、釜石線の前身である岩手軽便鉄道が花巻から仙人峠間を走る狭軌鉄道として開通した際に建設された。1943(昭和18)年に改修されて現在の橋となったが...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
遠野ふるさと村 ( 岩手県 遠野市 )
JR釜石線遠野駅から北へ約7kmの場所にある野外博物館。江戸中期から明治中期にかけて造られた茅葺屋根の曲り家(南部曲り家)がそのままの形で移築され、小川が流れ水車がまわり、田畑があり、炭焼き小屋がありと、遠野の昔ながらの集落が再現されている。 南部曲り家は母屋と厩(馬屋)が一体化したL字形の家屋で、旧南部藩領の岩手県部...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
猊鼻渓 ( 岩手県 一関市 )
JR東北線・東北新幹線一関駅から北東へ約13kmの場所に位置し、最寄り駅はJR大船渡線猊鼻渓駅。北上川の支流である砂鉄川が、北上山地の石灰岩層を節理面に沿って浸食してできた渓谷である。両岸には約2kmにわたって高さ30~100mに及ぶ絶壁や奇岩が屹立し、壮夫岩(そうふがん)、馬りょう岩など16カ所の奇岩のみどころが展開する。散策道の最...

写真提供:須川高原温泉
須川温泉 ( 岩手県 一関市 / 秋田県 東成瀬村 )
JR東北線・東北新幹線一ノ関駅から西北西へ約33km、バスで山間部を約90分かけて上っていく*。宮城県、秋田県、岩手県の3県にまがたる栗駒山頂の北方、中央火口丘である剣岳の北麓にある。 岩手県側の標高1,126mに位置する須川高原温泉は、潅木や溶岩に囲まれ野趣に富んだ宿である。高地に位置するため紫外線が強く、気候療養の適地で、19...

写真提供:一般社団法人東北観光推進機構
骨寺村荘園遺跡 ( 岩手県 一関市 )
JR東北線・東北新幹線一ノ関駅から西北西へ約16km、バスで山間部を約40分かけて上っていく。 骨寺村荘園遺跡は、「陸奥国骨寺村絵図」(以下、荘園絵図)と呼ばれる中世荘園絵図の景観が今なお残る貴重な遺跡である。遺跡がある一関市厳美町本寺地区は、かつては骨寺村と呼ばれた荘園で、中尊寺経蔵別当領であった。荘園絵図には、当時の...

写真提供:ひろのイベント事業実行委員会
旧南部領のナニャドヤラ ( 岩手県 洋野町 )
ナニャドヤラは旧南部領一帯、岩手県内では二戸郡、九戸郡、岩手郡などに伝わる盆踊りの唄。平時においても、野山や畑での作業の場で唄われてきた。地域によって「ニャニャトヤラ」あるいは「ナギャトヤラ」とも発音されるが、起源や由来、意味について確かなことはわかっておらず、研究者たちによってさまざまな説が提唱されている。 盆...

写真提供:白石市
鎌先温泉 ( 宮城県 白石市 )
東北新幹線白石蔵王駅から約8kmにある、むかしながらの湯治場の雰囲気を残す山あいの温泉である。歴史は古く1428(正長元)年、白石の農夫がきこりの作業中に渇を覚え、鎌の先で岩角をうかがったところ湯が湧き出したので、これを鎌先温泉と名づけたと伝えられている。昔から「キズに鎌先」と言われ、奥羽の薬湯として知られていた。最近では...
北上川(下流) ( 宮城県 登米市 / 宮城県 石巻市 )
北上川は岩手県北部・岩手町の水源から岩手県を南へ縦貫し、一関市から宮城県登米市を経て、石巻市の追波湾に注ぎ込む東北最大の川。登米市で旧北上川と分流し、旧北上川は石巻湾に注がれる。流域に連なる山地から流れ込む支川が多く、幹線流路延長は約249kmに及び、全国第5位、流域面積は約10.150km2で全国第4位である。 岩手...
登米町の歴史的建造物群 ( 宮城県 登米市 )
登米市(とめし)登米町(とよままち)*は県北部に位置し、北上川がまちの東端を流れる。北上川の舟運で発達しただけに、鉄道からの便は悪く、仙台駅から高速バスを利用して約90分、三陸自動車道登米ICから約4分である。 藩政時代、伊達一門の登米伊達2万1千石の城下町として栄え、明治維新後は北上川の舟運による米などの集散地として繁...
鳴子峡 ( 宮城県 大崎市 )
JR陸羽東線鳴子温泉駅の西2kmほどにある。江合川の支流、大谷川の清流に沿った鳴子峡入口の大谷橋から中山平入口までのおよそ2.5kmにわたる渓谷。大谷川が浸食してつくったV字谷、曲りくねった遊歩道の両側は高さ100mほどの断崖絶壁で、猿の手掛岩・屏風岩・虫喰岩などの奇岩が次々と展開する。特に新緑、10月下旬から11月上旬の紅葉のころは...

写真提供:大崎市教育委員会
旧有備館および庭園 ( 宮城県 大崎市 )
JR陸羽東線有備館駅を出てすぐ、静かな住宅街の中にある。江戸時代の仙台藩家臣である岩出山伊達家が開設した郷学(学問所)である。開校は岩出山伊達家十代邦直が当主の1850(嘉永3)年ころと考えられ、岩出山城本丸の北側にあった隠居所・下屋敷の敷地内に開設された。現存する有備館の「御改所(主屋)」は庭園の池に面して立つ建物で、岩...
鳴子温泉 ( 宮城県 大崎市 )
東北新幹線古川駅で陸羽東線に乗り換え、約45分の鳴子温泉郷の中心である鳴子温泉は、荒雄川の川岸に鳴子温泉駅を中心に半円を描くように広がっている。駅前に温泉街が開け、近代的な旅館や古風な旅館、みやげ物店、こけし工人の店が立ち並んでいる。 鳴子温泉は、837(承和4)年、鳴子火山の爆発によって生まれた。寿永・文治年間(1182...

写真提供:多賀城市教育委員会
多賀城跡附寺跡 ( 宮城県 多賀城市 )
JR東北本線国府多賀城駅の北西約800m、仙台平野を一望できる松島丘陵の先端一帯が多賀城跡である。多賀城は奈良・平安時代に置かれた陸奥国の国府であり、多賀城跡は奈良県の平城京跡、福岡県の太宰府跡と並ぶ日本三大遺跡の一つ。江戸時代初期に多賀城碑*が発見され、この場所が多賀城跡であることが判明した。1922(大正11)年に多賀城廃...
村田の町並み ( 宮城県 村田町 )
JR東北本線大河原駅から約9km。宮城県南部に位置する村田町は、江戸時代、江戸から仙台へむかう奥州街道と、仙台から山形へ抜ける笹谷街道とを結ぶ、羽前街道の脇往還の宿場として賑わいを見せた。 村田商人は、仙台藩内で栽培された紅花や藍を仙南地方で買い集め、上方や江戸に運んでいた。買い集めた紅花は山形の最上紅花に対して、奥州...

写真提供:宮城県柴田郡川崎町
青根温泉 ( 宮城県 川崎町 )
JR白石蔵王駅から車で約50分、遠刈田温泉から車で約10分の花房山の中腹、標高500mにある。1528(大永8・享禄元)年開湯と伝わる長い歴史のある温泉地で、湯神様とも呼ばれる水分(みくまり)神社と、頂には薬師如来を祀る湯神神社がある。旅館は8軒。そのうちの1軒の湯元不忘閣は、歴代の伊達家仙台藩主や文人たちが足を運んだ名湯である。 ...

写真提供:峩々温泉
峩々温泉 ( 宮城県 川崎町 )
青根温泉から西へ約8km、標高850mの蔵王山麓の濁川の谷にある一軒宿。登山者や湯治客が多かったが、近年は秘湯の湯でゆっくりと保養を求める人が増えている。山ザクラ、紅葉、雪景色と四季折々の自然を楽しめる。 嘉永年間(1648~1653年)に自噴する温泉が発見され、古くから胃腸病の名湯として知られる。1875(明治8)年に旅館業の認可...

写真提供:公益財団法人仙台観光国際協会
秋保大滝 ( 宮城県 仙台市 )
国指定の名勝で、「日本の滝百選」に選ばれている秋保大滝。秋保温泉から西へ約14km、山形県立石寺(りっしゃくじ)の奥の院といわれる秋保大滝不動堂*の裏手に滝見台がある。深い木立の中、落差約55m、幅約6mで流れ落ちる滝は水量が多く、滝の白いしぶきと周囲の新緑あるいは紅葉となる時期にはいっそう映える。この滝見台のほかに、秋保大...

写真提供:秋保・里センター
磐司岩 ( 宮城県 仙台市 )
秋保温泉から西へ22km、太白区秋保町馬場岳山国有林内の二口峡谷の最奥にある磐司岩は、名取川沿いの凝灰岩・集塊岩からなる岩壁である。その表面を落ちる多数の滝の浸食で現われた柱状節理が高さ80~150m、長さ3kmにわたって屏風を立てめぐらしたように連立する姿は豪壮そのもの。名取川の南側には、日陰磐司(ひかげばんじ)や日陽磐司(ひ...
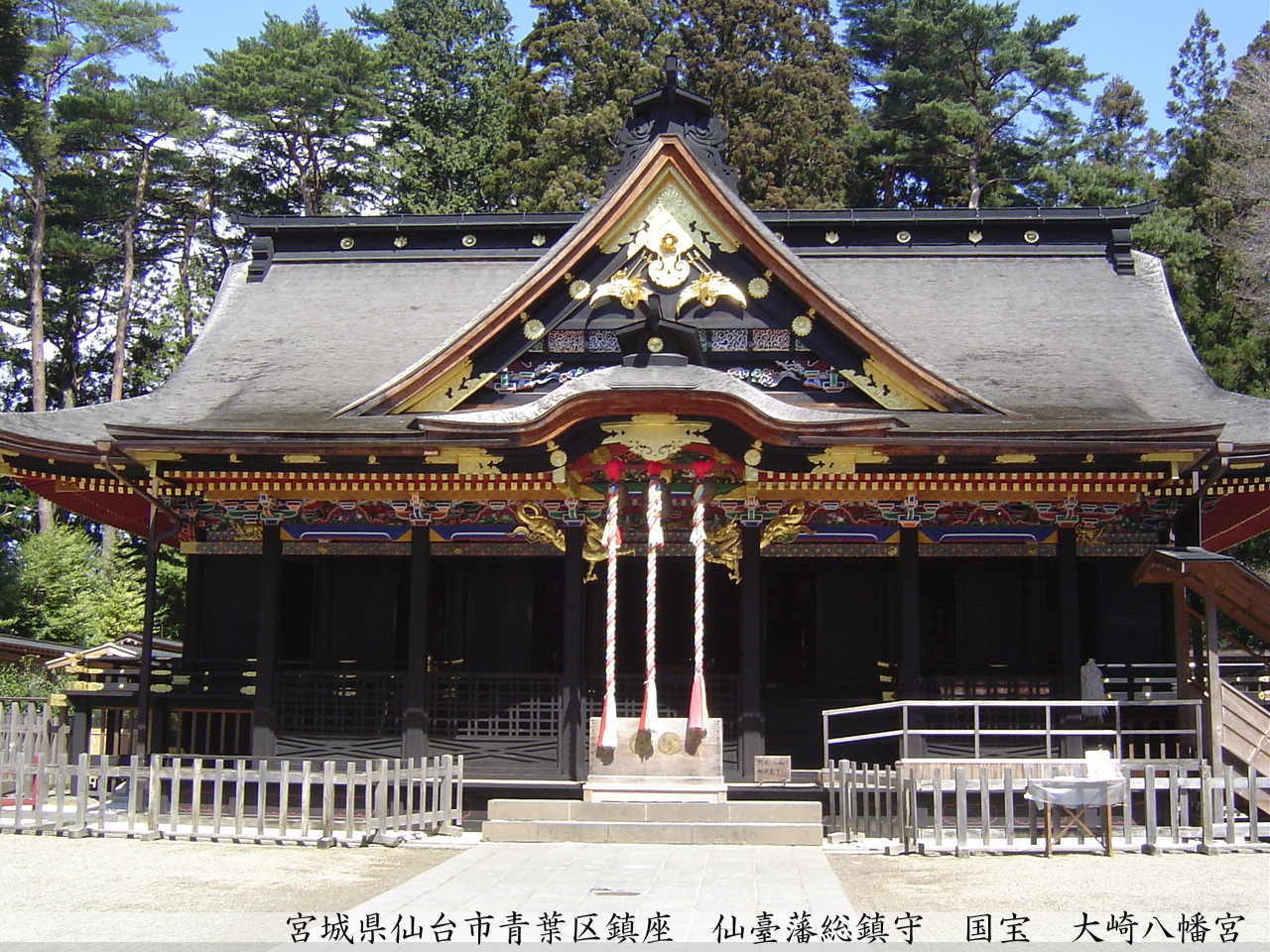
写真提供:大崎八幡宮
大崎八幡宮 ( 宮城県 仙台市 )
仙台城跡の北方、青葉山の緑が望める丘陵地に鎮座する。石鳥居*をくぐって急な石段を一直線に上り、老杉が茂る境内広場に出ると、門のような長床*が構え、その奥に社殿*が立つ。 1604(慶長9)年、伊達政宗によって仙台藩総鎮守として創建。社殿は、1607(慶長12)年に建造された日本最古の桃山様式建築で、1952(昭和27)年に国宝に指...
仙台城跡 ( 宮城県 仙台市 )
仙台城は、仙台藩初代藩主、伊達政宗によって造営された。仙台駅から青葉通りを西へ進み、広瀬川に架かる大橋を渡ったところに大規模なその城跡が残っている。本丸跡の標高は115m、本丸跡の最高所(天守台)は標高143mである。仙台市街を一望に見下ろし、遠く太平洋も望める景勝地の青葉山丘陵に城跡を残す。本丸の南は深さ80mを超える竜の口...

写真提供:輪王寺
輪王寺 ( 宮城県 仙台市 )
仙台駅から西へ約1km、寺屋敷の続く通りの一角にある。輪王寺は1441(嘉吉元)年、伊達家11代当主持宗によって創建された、東北有数の庭園をもつ曹洞宗の寺院。起源は福島県梁川だが、伊達家の居城の移転にともない移転を繰り返し、1602(慶長7)年に現在の地に定まった。1876(明治9)年に、仁王門のみを残し全焼。以降荒廃した輪王寺を、19...

写真提供:瑞鳳殿
瑞鳳殿 ( 宮城県 仙台市 )
仙台駅の西南、広瀬川が大きく屈曲する右岸の経ヶ峯(きょうがみね)にある。廟所に至る石組の美しい石段と、両側に樹齢380余年にもなる杉の巨木がそそり立つ参道が伊達家栄華の一端を伝える。石段登り口に瑞鳳寺*の本堂があり、向かい側に伊達家公子公女廟、通称「お子様御廟」がある。 1636(寛永13)年生涯を閉じた伊達氏17世・仙台藩初...
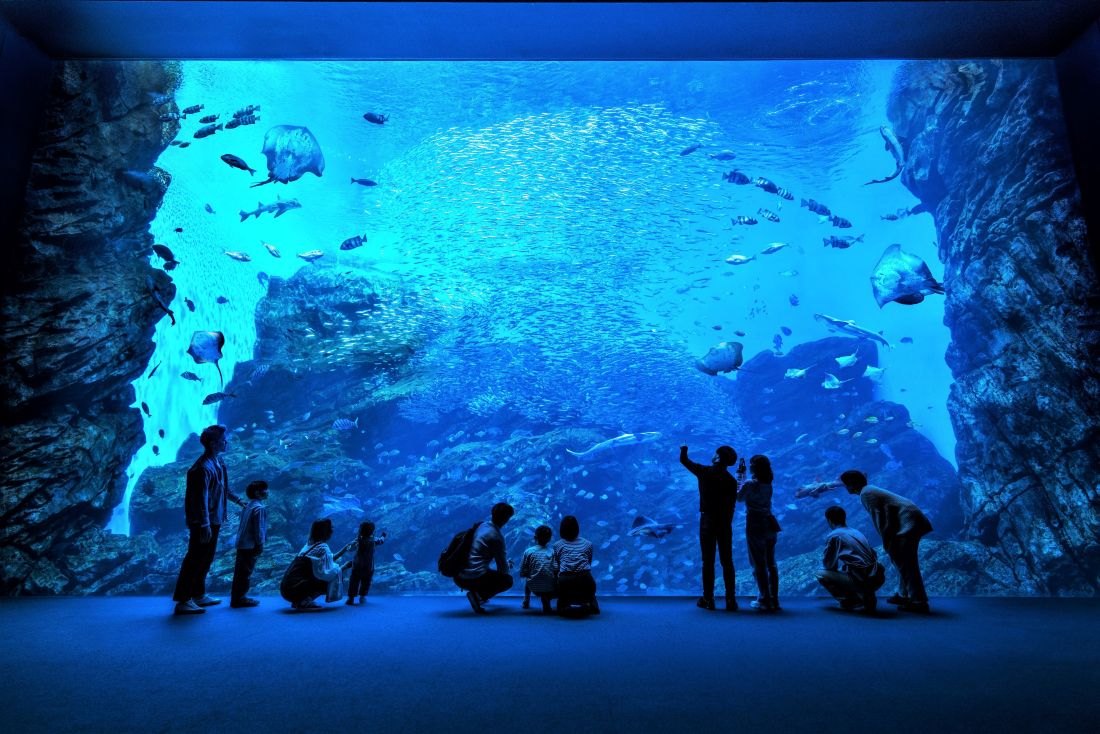
写真提供:仙台うみの杜水族館
仙台うみの杜水族館 ( 宮城県 仙台市 )
2015(平成27)年7月宮城野区に開館。同年5月に閉館したマリンピア松島水族館から生き物や飼育員の多くを引き継ぎ、運営は株式会社横浜八景島が担う。約100基の水槽、総水量約3,000t、延床面積は約9,900m2、300種5万点を展示する東北最大級の水族館。日本の海や世界の海を再現する。 1階が「日本のうみー東北のうみー」。親潮...

金華山黄金山神社 ( 宮城県 石巻市 )
鮎川から毎日曜日に船が運行され、金華山まで20分。それ以外の曜日でも、予約をすれば海上タクシーで、人数によっては定期船とそれほど違わない料金で行くことができる。女川港からも金華山へ毎日曜日・祝日1便運行し、約40分で到着する。 牡鹿半島の南突端に、幅800mの金華山瀬戸をはさんで浮かぶ東西約4km、南北約5kmの角錐状の島。中央...

写真提供:石巻市
日和山公園 ( 宮城県 石巻市 )
日和山*は石巻市内中心部、旧北上川の河口に位置する、石巻港や太平洋まで見渡せる丘陵地。頂上には、780(宝亀11)年創建と 伝わる鹿嶋御児神社がある。また、ここは中世後期には、東西約400m、南北約500mにかけて、奥州総奉行葛西氏の城域だったとも言われている。 1689(元禄2)年には、松尾芭蕉と弟子の河合曾良が訪れ、ここから眺...

松島 ( 宮城県 松島町 / 宮城県 利府町 / 宮城県 塩竈市 / 宮城県 東松島市 / 宮城県 七ヶ浜町 )
湖のように波静かな松島湾に浮かぶ八百八島と呼ばれる大小、約260の島々。その景観を松尾芭蕉が『おくのほそ道』で「扶桑第一の好風にして」と絶賛した、江戸時代に選定された日本三景*の一つである。現在、広い意味で松島と呼ばれる地域は、七ヶ浜町の御殿崎から松島湾をへだてて東松島市波島の南端とを結ぶ線と、鳴瀬川河口右岸から波島東...

写真提供:瑞巌寺
瑞巌寺 ( 宮城県 松島町 )
JR仙石線松島海岸駅より北北東方向に向かって徒歩で10分ほどの、松島海岸から国道45号線を挟んだ北側に位置する。 伊達政宗が創建した菩提寺として知られる古刹。正式名称は「松島青龍山瑞巌円福禅寺」という。 828(天長5)年、平安時代初期に、比叡山延暦寺第3代座主・慈覚大師円仁により開創された天台宗延福寺がその前身と伝わる。...
白石川堤の桜(一目千本桜) ( 宮城県 柴田町 / 宮城県 大河原町 )
JR東北本線船岡駅から徒歩3分、白石川堤に一目千本桜と呼ばれるみごとな桜並木が、大河原町金ケ瀬地区から柴田町船岡地区まで8kmにわたって続く。 白石川堤の桜は、堤防竣工のしらせを聞いた東京で成功した髙山開治郎が、大正末期から昭和初期に東京から植木職人を同伴し、町の職人とともに白石川の堤防に桜の苗木1,200本を寄贈し、自ら植...

芝草平 ( 宮城県 七ヶ宿町 )
南蔵王縦走コースの中間に位置する。標高1620m、面積約100万m2の蔵王連峰唯一の湿原である。登山口は、蔵王エコーラインの刈田岳駐車場から往復で約7時間(休憩・昼食含む)の日帰りのできるコースからの登山が多い。もう一つのコースは、白石スキー場駐車場から、不忘山と水引入道の二つのルートから屏風岳を経て、芝草平に達す...

リアス・アーク美術館 ( 宮城県 気仙沼市 )
JR気仙沼駅の南、車で20分ほどの場所にある。1994(平成6)年に開館したリアス・アーク美術館は、主に東北・北海道の現代美術を紹介すると同時に、地域の歴史・民俗資料を常設展示し、博物館としての一面を併せもつ。気仙沼市と南三陸町で構成する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が管理運営している。 展示は2フロアに分かれており、1階...

写真提供:一般社団法人気仙沼市観光協会
徳仙丈山のツツジ ( 宮城県 気仙沼市 )
徳仙丈山は岩手県境に近い、気仙沼市にある標高711mの山。5月中旬になると、全山がヤマツツジとレンゲツツジにおおわれ、文字通りツツジの山となる。約50万m2に50万本ほどのツツジがあるともいわれ、日本最大級のツツジの名所である。北側と南側の駐車場、どちらから登っても40分ほどで山頂に立てる。 山頂からは真っ赤なツツ...

写真提供:志波彦神社・鹽竈神社
志波彦神社・鹽竈神社 ( 宮城県 塩竈市 )
JR仙石線本塩釜駅から西へ東参道を通り徒歩15分、またはJR東北本線塩釜駅から表参道経由で徒歩25分の場所にある。 鹽竈神社は奥州一ノ宮として名高く、杉木立におおわれる一森(いちもり)山の頂、松島の島々や遠く金華山を眺望できる地に鎮座する。表参道からは石鳥居をくぐり、一直線で急勾配の202段の石段を登り切ってたどり着く。その...

写真提供:塩竈市
浦戸諸島のノリひび(海苔網)・カキ棚の風景 ( 宮城県 塩竈市 )
浦戸諸島は、松島湾の南に桂島、野々島、寒風沢(さぶさわ)島、朴(ほう)島の4島*の有人島と多数の無人島で構成される。これらの島々が湾の入り口に横たわるので、松島湾はいつも波が静かである。 浦戸諸島周辺は、時期になるとノリとカキ養殖の風景が見られる。ノリ養殖が行われるのは9月~1月ころで、松島湾、石巻湾、仙台湾で養殖さ...

写真提供:仙台東照宮
仙台東照宮 ( 宮城県 仙台市 )
仙台市青葉区、JR仙山線東照宮駅の北約200mのところにある。1654(承応3)年、仙台藩2代藩主伊達忠宗が建立した徳川家康を祀る神社。伊達藩の威信をかけて造られたこの仙台東照宮は、忠宗が数々の寺社を建造している中で、晩年を代表する大事業となった。 日光東照宮の建築様式である権現造ではなく、本殿と拝殿が別棟になっていることが...
大徳寺(横山不動尊) ( 宮城県 登米市 )
JR気仙沼線陸前横山駅の西方約500mにある。寺伝では、保元年間(1156~1159)年、南三陸町の水戸辺浜に百済から流れついた仏像を安置したのが始まりといわれ、3mほどもあるカツラ材の寄木造りの不動明王の胎内に5cmほどの純金の本尊、不動明王を安置する。本像の制作時期は平安時代まで遡ることができ、1997(平成9)年、国の重要文化財にな...
材木岩 ( 宮城県 白石市 )
小原温泉から白石川を約5km遡った、七ヶ宿ダムの東にある。 材木岩は、高さ約65m、長さ約100mに及ぶ、石英安山岩の柱状節理で、1934(昭和9)年に国の天然記念物に指定された。柱状の岩が連なる絶景が広がり、秋には材木岩をとりまく紅葉が美しい。材木岩に沿って流れる白石川の河辺には、「水と石との語らいの公園(材木岩公園)」が整備...
田沢湖 ( 秋田県 仙北市 )
秋田県の中央部岩手県寄り、東に奥羽山脈、西に出羽山地が連なる山間にある。JR秋田新幹線・田沢湖線田沢湖駅から田沢湖畔の白浜まで北へ約6km。周囲約20kmの湖岸線は、六角形に近い円形をしており、ゆるやかな山稜に囲まれ、水面標高は250mである。最水深423.4mは日本一の深さを誇る。成因としては那須火山帯中に生じた火山陥没によって生じ...

法体の滝 ( 秋田県 由利本荘市 )
JR羽越本線羽後本荘駅から南東に約48km、由利高原鉄道矢島駅から約25km、鳥海山の東麓、子吉川の起点から2kmほどの渓流沿いに流れ落ちる末広がりの瀑布。約10万年前の鳥海山の噴火で東に向かって流れ出た法体溶岩流によって形成された末端崖と側方崖が下玉田川や赤沢川などによって侵食され、末端中央部には上玉田川により溶岩原を横断するよ...

男鹿西海岸 ( 秋田県 男鹿市 )
秋田県の中央部、日本海に突き出している男鹿半島は、かつては、本土から切り離されていた島であったが、北側の米代川と南側の雄物川などが運んだ土砂により成長した砂州、砂丘がつながり、八郎潟を抱える形で陸繋島となり半島となった。 半島は海岸段丘が発達しており、さらに西部には標高715mの本山(ほんざん)火山群、東部には標高355...
川原毛地獄 ( 秋田県 湯沢市 )
JR奥羽本線湯沢駅から南へ約30km、泥湯温泉の西2km、灰白色の荒々しい岩肌を見せ、硫化水素ガスを噴出させている標高約800mの硫黄山で、川原毛地獄*1と呼ばれている。辺りには鼻をつく強い硫黄臭が漂う。807(大同2)年に修験場*2として僧月窓によって開かれたという。この地は、川原毛硫黄山と呼ばれた鉱山でもあり、1623(元和9)年に採掘...

写真提供:横手市役所増田地域局 まちづくり推進部 増田地域課
真人公園のサクラ ( 秋田県 横手市 )
JR奥羽本線十文字駅から東に約5km、増田の内蔵地区からは約3km。標高391mの真人山(まとやま)*1を東側に背負って広がる公園。1917(大正6)年に大正天皇即位の記念事業として造園された。公園の総面積は5万4,600m2で前面に池と中島を配し、ソメイヨシノ・ヤマザクラ、ウメ、アヤメ、ツツジが植栽されている。とくにソメイヨシノ...
後生掛の泥火山と大湯沼 ( 秋田県 鹿角市 )
後生掛温泉の宿泊施設の脇の駐車場から沢筋に沿って自然観察研究路が整備されている。研究路は湯が沸き立つ2つの噴出孔オナメ・モトメ*1からスタートして、紺屋地獄、マッドポット泥熱泉)が点在する沢、大泥火山、大湯沼など様々な火山活動の様子を約2km、徒歩40分で観察することができる。 紺屋地獄の泥湯の泥は硫黄や硫化鉄が沈殿した...
大湯環状列石 ( 秋田県 鹿角市 )
JR花輪線十和田南駅から北東へ約4.5km、大湯温泉*1からは西南3kmの台地上にある。県道をはさんで東に野中堂環状列石、西に万座環状列石の2つの環状列石を有する縄文時代後期(約4000年前)の大規模な遺跡である。遺跡近くにはガイダンス施設、大湯ストーンサークル館*2もある。野中堂環状列石は最大径44m、万座環状列石の最大径は52mあり、と...
旧小坂鉱山事務所 ( 秋田県 小坂町 )
JR花輪線十和田南駅から北へ約9km、明治から大正期にかけて日本でも有数の鉱産額を誇った鉱山の町、小坂町のシンボルとして建つ。 小坂の鉱山は、1861(万延2・文久元)年小坂村の農民により銀山として発見された。その後、南部藩が経営に乗り出したが、明治維新後に官営化され、1884(明治17)年に藤田組に払い下げられ、銅を主力に金・...

写真提供:秋田県
竿燈まつり ( 秋田県 秋田市 )
8月3日から6日までの4日間、秋田市の中心部、竿燈大通りなどで繰り広げられる祭り。この祭りの主役となる竿燈*1の最大である「大若」は、12mの竹竿に46個の提燈*2を米俵を重ねたように九段にわけて吊するすため重量が50kgに及ぶ。これを印半纏、白足袋姿の若者の差し手が囃子に合わせ額、肩、腰へと倒れないようバランスをとりながら移動させ...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟
大曲の花火 ( 秋田県 大仙市 )
JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から南西に2kmほどの雄物川河畔「大曲の花火」公園で毎年8月最終土曜日に全国から約30社の花火業者が参加し、花火師たちが腕を競い合い、厳正な審査が行われる競技大会。17時10分から始まる「昼花火の部」と18時50分から始まる「夜花火の部」と合わせて約1万8千発の花火が打ち上げられる。 「大曲の花火」は...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟
横手のかまくら ( 秋田県 横手市 )
ドイツの建築家ブルーノ・タウト*1が「雪中の静かな祝祭」*2と称した、横手の「かまくら」は毎年2月15日、16日に催され、16日、17日の「梵天(ぼんでん)」*3や市内各所に雪像が展示される「雪の芸術」と合わせ、「横手の雪まつり」として開催される。 かまくらは、高さ3mあまりの雪室で、内部正面に祭壇を穿ち、御幣をたてて水神様を祭って...
男鹿のナマハゲ ( 秋田県 男鹿市 )
大晦日の夜、ナマハゲとなった地区の青年たちが藁蓑をまとい包丁を手にウォーウォーと叫んで民家を回る男鹿半島の民俗行事である。 「ナマハゲ」に扮する未婚の青年が男鹿一帯のそれぞれの集落の神社に集まったのち数人ずつ集落に下りて一軒一軒回って歩く。「なまけものはいねガァ」、「親の言うこときかね子はいねガァ」などと子供たち...

写真提供:鹿角市
大日堂舞楽 ( 秋田県 鹿角市 )
例年1月2日にJR花輪線八幡平駅近くの鹿角市八幡平の小豆沢地区にある大日霊貴神社(おおひるめむちじんじゃ:通称大日堂)1*の拝殿中央に設けられた10尺(約3m)四方の特設舞台で、古くからこの地方に伝承される舞楽が、鹿角市八幡平の大里、谷内、小豆沢、長嶺4つの集落の能衆と呼ばれる氏子によって交替で多彩な舞楽を奉納する。 舞楽奉納*2...

玉川温泉 ( 秋田県 仙北市 )
JR花輪線鹿角花輪駅から南へ約35km、焼山(標高1,366m)の西麓、八幡平(1613m)と田沢湖を結ぶ道の途中、標高800mほどの所にある。温泉の周辺は、焼山の火山活動が活発で、いたるところから噴気があがっており、江戸時代からすでに硫黄が掘り出されていた。その際に温泉の湧出については、毒水*1源として確認されていた。1882(明治15)年に...

乳頭温泉郷 ( 秋田県 仙北市 )
JR秋田新幹線・田沢湖線田沢湖駅から乳頭温泉郷の入口にあたる「鶴の湯温泉入口」まで北東へ約15km。標高1,478mの乳頭山*1の西麓、標高600mから900mほどの先達(せんだつ)川上流の渓谷沿いに7つの一軒宿の温泉が点在している。下流から妙乃湯*2・大釜温泉*3・蟹場(がにば)温泉*4、さらに、黒湯温泉*5・孫六温泉*6があり、先達川に流れ込む...

写真提供:鹿角市
後生掛温泉 ( 秋田県 鹿角市 )
八幡平の西、焼山(標高1,336m)東麓の谷間に佇む、標高約1,000mの一軒宿の温泉で、蒸ノ湯の西方2.5km下ったアスピーテライン沿いにある。後生掛*1温泉は火山活動が盛んな温泉地獄や泥火山を沢の奥に抱え、周辺は硫黄の臭いと噴煙が充満している。 開湯は江戸中期とされ、古くから湯治場として「馬で来て足駄で帰る後生掛」と謳われていた...
泥湯温泉 ( 秋田県 湯沢市 )
JR奥羽本線湯沢駅から南へ約30km。高松岳(標高1,348m)の北東麓、標高630mの山あい、高松川沿いにある。温泉施設*1は2軒。温泉の発見については、不詳だが、1814(文化11)年に訪れた紀行家菅江真澄は「泥湯山(高松岳、山伏岳、小安岳)の麓になりぬ。湯のもとに、天狗岩とていといと高き岩嶺に松生ひ、紅葉したるなど、いとおもしろし。此...
蒸ノ湯温泉 ( 秋田県 鹿角市 )
JR花輪線八幡平駅から南へ約28km、八幡平の北西麓、標高1,100mの地にある。江戸時代*1からの湯治宿として知られ、オンドル式の湯治*2宿舎が数多く立っていたが、1973(昭和48)年の地すべりによって宿舎が流され、現在は少し離れた場所に木造2階建ての旅館部(客室26室)で営業を行っている。浴場は宿泊棟にある総ヒバ造りの男女別内湯と男女...

写真提供:発祥の地 鹿角きりたんぽ協議会事務局
秋田県北部地方のきりたんぽ鍋 ( 秋田県 鹿角市 / 秋田県 大館市 )
新米を炊いて突きつぶし、秋田杉の串に握り付け、炭火で焼目をつけたものが「たんぽ」。これを切って用いるところから「きりたんぽ」という。この「きりたんぽ」を鶏肉・ネギ・セリ・ゴボウ・キノコ類・蒟蒻などとともに薄く味つけして煮込む鍋物料理である。「たんぽ」の名は、蒲の立ち穂を鹿角地方の方言では「たんぽ」といい、その形状が...

稲庭うどん ( 秋田県 湯沢市 )
稲庭うどんは奥羽本線湯沢駅から南東へ約15kmの皆瀬川沿いの稲庭町(湯沢市)で生まれた手延べの平たい乾麺である。なめらかな舌ざわりと、つるつるとしたのどごしが特徴の麺。 稲庭うどんの始まりについては諸説あるが、1814(文化11)年にこの地を訪れた紀行家菅江真澄の「雪の出羽路」では「稲庭郷中町驛」の項で「名産御用乾饂飩とし...
康楽館 ( 秋田県 小坂町 )
JR花輪線十和田南駅から北へ約9kmにあり、旧小坂鉱山事務所の南にある。1910(明治43)年に鉱山労働者の慰安施設*1として建築され、歌舞伎、新劇、映画など芝居小屋、劇場として利用されていた。外観は木造ゴシック風の白い洋館で、正面はイギリス下見板張の外壁、棟飾や妻飾,破風板を縁取る装飾あるいは客席部の洋風の格縁天井などは洋風の...
能代ねぶながし(能代役七夕) ( 秋田県 能代市 )
例年8月上旬に行われる能代市の夏まつりで別名「役七夕(やくたなばた)」と言われ、市街地と米代川河畔で行われる。 祭り当日は、シャチを載せた城郭型の灯籠(山車)複数基がそれぞれ担当する各町内を80人ほどの若者たちによって曳き回される(自丁廻丁)。そのあと、子供たちが持った田楽灯籠を先頭に、笛と太鼓に続き、灯籠(山車)がそ...

安の滝 ( 秋田県 北秋田市 )
森吉山(標高1454m)の東南、標高900mの高原にある落差90mの2段構造の滝。安の滝は米代川に合流する阿仁川の支流、打当川にある8kmほど続く中ノ又渓谷の最深部にある。安の滝遊歩道入口へは、秋田内陸縦貫線阿仁マタギ駅から県道、林道を打当川に沿って約11km。林道にある安の滝入口の駐車場からの遊歩道*1は約2km。 なお、林道は途中狭隘...

写真提供:秋田県
角館武家屋敷のシダレザクラ ( 秋田県 仙北市 )
角館の現在の町割りは、蘆名義勝*1により元和年間(1615~1624年)にこの地に開かれ、1656(明暦2)年、秋田(久保田)藩から佐竹(北家)義隣(よしちか)*2が所預(ところあずかり・所司代)として任ぜられ入部した。以降約200年間、明治の廃藩置県まで支配し武家屋敷*3の内町や町人の外町などの整備が進められた。シダレザクラは、佐竹北家...

写真提供:一般社団法人 田沢湖・角館観光協会
角館祭りのやま行事 ( 秋田県 仙北市 )
角館祭りのやま行事は、角館総鎮守神明社と勝楽山成就院薬師堂の例祭に合わせ、毎年9月7日~9日の3日間催される。18丁内から武者人形や歌舞伎人形を乗せた18台の「やま(山車)」が、7日の夕方には神明社へ参拝し、8日には江戸期にこの地を治めた佐竹北家当主の上覧を仰ぎ、8日、9日には薬師堂を参拝するため市街地で曳き回される。「やま」の...
天然秋田杉の古里「仁別国民の森」 ( 秋田県 秋田市 )
JR秋田新幹線・奥羽本線秋田駅から北東へ23km、秋田市の東端にそびえる太平山の西麓一帯に「仁別国民の森(仁別自然休養林)」は広がる。「仁別国民の森」は秋田藩の藩有林*1として保護されていた歴史があり、現在は国有林で2795万m2の広大な面積を有し、標高700~800mまでは、秋田スギを主体とする針葉樹とブナ等の広葉樹の混交...

雄物川 ( 秋田県 横手市 / 秋田県 大仙市 )
雄物川は、秋田・山形県境の奥羽山脈の大仙山(標高920m)を源として、西側に出羽丘陵を見ながら上流域の山間部を抜け横手盆地の西縁を北流しながら皆瀬川、横手川などの支流を合わせ、大曲付近で玉川が合流し屈曲を繰り返す中流域を経て、秋田空港近くで北西に流れを変える。そこで下流域となる秋田平野に出て秋田市新屋では旧雄物川を分派...
十和田ホテル本館 ( 秋田県 小坂町 )
十和田湖の西畔、湖を見渡す高台に建つホテル。本館と新館の2棟が並ぶが、本館は1938(昭和13)年に竣工し、翌年6月に県営ホテルとして開業した。本来は1940(昭和15)年に開催予定であった「東京オリンピック」を前に、政府の要請で全国に建てられた訪日外国人観光客向けの宿*1としての、ホテルのひとつだった。しかし、オリンピックが中止...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟
毛馬内の盆踊 ( 秋田県 鹿角市 )
秋田県鹿角市毛馬内地区に伝承されている盆踊。毎年8月21日から23日の3日間、地区の「こもせ通り」の真ん中に数ヵ所かがり火を並べ、盆踊の会場としている。 由来は定かではないが、すでに文化・文政年間(1804~1830年)に書かれた、紀行家菅江真澄の「鄙廼一曲(ひなのひとふし)」に盆踊唄「大(だい)の阪(坂)ぶし」の記事があること...

写真提供:一般社団法人秋田県観光連盟
土崎港曳山まつり ( 秋田県 秋田市 )
JR男鹿駅から西へ200mほどのところにある土崎神明社*1の祭礼で、神輿の渡御に合わせて、町内を曳山が巡行する。例年7月20日、21日の両日に行われる。祭礼は町を挙げて行われ、旧47町内が9つの組に分かれて当番を務め、祭礼の3か月ほど前から様々な神事や曳山の蔵出し、製作、飾り付けなどの準備が進められる。曳山*2の台数は年により異なるが...
花輪ばやし(花輪祭の屋台行事) ( 秋田県 鹿角市 )
花輪祭の屋台行事(通称:花輪ばやし)はJR花輪線鹿角花輪駅から東約3kmにあるこの地方で古くから産土神として信仰を集めていた幸稲荷神社(さきわいいなりじんじゃ)*1の例大祭の祭礼囃子として伝承されてきた。祭、囃子*2の起源については、定かではないが、明確な記録*3としては、1765(明和2)年の尾去沢銅山の「御銅山御定目帳」のなか...
旧料亭金勇 ( 秋田県 能代市 )
JR五能線能代駅から西へ900mのところにある。1937(昭和12)年に秋田スギなどの良材をふんだんに使って施工された大規模和風建築物。1階には庇、2階のガラス窓に手摺りがつけられ、正面及び側面の両端は入母屋造の屋根となっている。室内は、110畳ほどの2階大広間をはじめとして各部屋とも手が込んだ造作がなされており、秋田スギほか、マツ...

森吉山 ( 秋田県 北秋田市 )
秋田県の中央部の東、米代川に合流する阿仁川の上流にそびえる形の整った成層型楯状火山*1といわれ、那須火山帯*2に属している。森吉山はカルデラ*3内の中央火口丘である最高峰向岳(標高1,454m)を中心に、一ノ腰(標高1,264m)、前岳(標高1,308m)、カンバ森(標高1,187m)、ヒバクラ岳(標高1,326m)小池ヶ原(標高1,280m)の外輪山から...
増田町の内蔵と町並み ( 秋田県 横手市 )
JR奥羽本線十文字駅から南東に約3km、増田町の中心街の中町、七日町商店街通り(中七日通り)には、「内蔵」と呼ばれる土蔵を擁する明治から昭和期の商家などが建ち並び、重要伝統的建造物群保存地区(約10.6万m2)に選定されている。増田町は雄物川の支流、成瀬・皆瀬両河川の合流点にある市場町*1として江戸時代から発展してき...
小安峡大噴湯 ( 秋田県 湯沢市 )
JR奥羽本線湯沢駅から南東へ約30km、栗駒山(標高1,626m)西麓を流れる皆瀬川の上流に、約8kmの険しいV字谷の小安峡がある。その谷底の川岸には、轟音とともに98℃の熱湯を噴き出す大噴湯があり、高低差60mほどを降りると、その先に渓流沿いの遊歩道が続く。この遊歩道は上流、下流2個所の駐車場から降りることができ、徒歩片道30分ほど。岩壁...
風の松原 ( 秋田県 能代市 )
能代市街の西側、米代川河口をはさむ能代海岸に広がるクロマツ700万本の防砂林。東西幅1km、南北総延長14km、 面積約760万m2の規模を誇り、現在は砂防の役割のみならず、市民のレクリエーションの場ともなっている。かつては「能代海岸防砂林」とされていたが、1987(昭和62)年に愛称を公募し、「風の松原」と命名された。 風...

写真提供:大潟村役場
大潟村の「桜と菜の花ロード」と農業景観 ( 秋田県 大潟村 )
わが国第2の大きさの湖であった八郎潟*1の約5分の4が干拓されて172km2にも及ぶ大水田地帯に変貌した。残り5分の1は船越水道の防潮水門により日本海と遮断された淡水の調整池となっており、干拓地に用水を提供している。 「桜と菜の花ロード」は干拓地の中央部を東西に走る県道で、総延長11kmにわたり、菜の花が帯のように植えられ、さら...
強首温泉 樅峰苑 ( 秋田県 大仙市 )
JR奥羽本線峰吉川駅の西へ約4km、雄物川を渡った強首*1集落のなかに建つ。宿の建物は、江戸時代からの豪農であった小山田家*2が1917(大正6)年に建築した本邸で、1966(昭和41)年から旅館を営んでいる。屋根の千鳥破風、軒唐破風付き入母屋とムクリ破風の玄関など豪壮な正面構えとなっており、また、1914(大正3)年の秋田仙北地震*3後の建...
秋田駒ヶ岳 ( 秋田県 仙北市 / 岩手県 雫石町 )
秋田駒と呼ばれる、田沢湖の北東にある火山である。頂上部は楕円形の大きな火口があり火口内にある火口丘を女岳(めだけ)と呼び、外輪山に男岳(おだけ)と標高1,637mの最高峰男女(おなめ:女目とも)岳がそびえている。那須火山帯*1に属し、近年では1970(昭和45)年9月に女岳でマグマ噴火があり、約4カ月で噴火は停止したものの、その後...
十和田湖 ( 青森県 十和田市 / 秋田県 小坂町 )
青森・秋田の県境にまたがる二重カルデラ*1湖。東西約10km、南北約10km、面積は約61km2で、南側から中山・御倉(おぐら)の両半島が突き出し、全体としてはクルミを割ったような形をしている。水面標高は400m、最大水深は327mで、秋田県の田沢湖、北海道の支笏湖に次いで第3位である。貧栄養湖*2で、透明度*3は約12m、水色はフォ...
赤神神社五社堂 ( 秋田県 男鹿市 )
JR男鹿線男鹿駅から男鹿半島の西海岸を西へ約13km、本山(標高715m)の中腹、標高約180mの高台に五社堂は建つ。参道*1は船川港門前にある赤神神社遥拝殿の横にあり、長楽寺の脇を通り、999段とされる石段が参道となっている。 五社堂は、向かって右から三の宮堂、客人権現堂、赤神権現堂、八王子堂、十禅師堂*2の5棟が並列しており、い...
払田柵跡 ( 秋田県 大仙市 )
JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から東へ約6km、横手盆地の北部、仙北地方の平野部にある真山・長森の2つの小丘陵*1を取り込むように展開する遺跡。遺跡周辺は「あきたこまち」で知られる稲作地帯で水田が広がる。 払田柵跡の発見は、明治30年代に行われた耕地整理の際、土中から角材が並んで発見されたことが端緒である。規則的・連続的に...

写真提供:一般社団法人大仙市観光物産協会
旧池田氏庭園 ( 秋田県 大仙市 )
JR秋田新幹線・奥羽本線大曲駅から南東へ約4kmのところにある庭園。この庭園は旧池田家*1の邸宅に属していたもので、横手盆地北部、仙北地方の平野部のほぼ中央部に位置している。邸宅の敷地面積は約4.2万m2に及ぶ。周囲は「あきたこまち」の米作地帯で耕地整理が良くなされた水田が広がり、東に奥羽山脈、南西に鳥海山を遠望する...
蔵王山 ( 山形県 上山市 / 宮城県 川崎町 )
奥羽山脈の南部に位置し、山形・宮城両県にまたがる南北約30kmの火山群の総称である。蔵王山という固有の山はなく、最高峰の熊野岳*をはじめとする多くの峰の連なりであり、蔵王連峰ともいう。那須火山帯に属し、旧火山群の南蔵王と新火山群の中央・北蔵王*に分けることができる。古来、刈田嶺(かつたみね)と呼ばれていたが、天武天皇の...
写真提供:朝日町役場
朝日連峰 ( 山形県 朝日町 )
朝日連峰は、山形・新潟の県境に大朝日岳(1,871m)を主峰として、南北60km、東西30kmにわたって標高1,500m以上の山並み*が連なり、地質的には花崗岩と中古生層から成る褶曲山塊だ。周氷河地形や雪食地形*が見られ、大朝日岳の主稜線の東西で地形が大きく異なる非対称山稜を形成している。多雪地帯で植生は森林帯と高山帯の中間となる亜高...

鳥海山 ( 山形県 遊佐町 / 秋田県 )
秋田と山形との県境にそびえる鳥海山は標高2,236mで、東北地方では福島県の燧ヶ岳(標高2,356m)についで2番目に高い山。鳥海山の山域は、地形的には、東部の出羽丘陵山地、中部から西部の独立峰をなす鳥海火山で形成されており、西は日本海に直接落ち込み、南西部は庄内平野が広がる。鳥海火山は成層火山で日本有数の規模を誇り、おおまかに...

写真提供:戸沢村観光物産協会
最上川 ( 山形県 長井市 / 山形県 戸沢村 )
最上川は、山形と福島との県境、西吾妻を発し、山形県内の置賜*・村山・最上・庄内の各地方を貫き、約400の支流を集め、酒田市で日本海に注ぐ。最上川の全長は229kmで全国7位、流域面積7,040km2、流域人口約100万人を誇る。 現在は河川改修により流れは穏やかになっているが、かつては球磨川・富士川とともに日本三大急流の一...
写真提供:一般社団法人 山形市観光協会
蔵王の樹氷 ( 山形県 山形市 / 山形県 上山市 )
蔵王の冬のシンボル。シベリアから吹いてくる季節風が、日本海の水分を含み朝日連峰を越える時急激に冷却されて水滴となり、これと雪雲のなかの雪片がアオモリトドマツに繰り返し付着して凍りつき樹氷となる。風上に向かって成長し、さらにその上に雪が積もって人の形に似てくることから、スノーモンスターの愛称もある。 樹氷ができる時...
善寳寺 ( 山形県 鶴岡市 )
JR羽越本線鶴岡駅の北西約10km、湯野浜温泉から約4km。鶴岡市の西部にあり、市街地と日本海を隔てるように立つ高館山の北東麓に、庄内平野と向かい合うようにある。天慶・天暦年間(938~957)の創建と伝えられ、その開基に関する伝承は、平安末期の説話集「今昔物語集」*にも載っている。境内にある貝喰の池には龍神伝説*があり、そのため...
本山慈恩寺 ( 山形県 寒河江市 )
JR左沢線羽前高松駅から北へ約2kmにある。746(天平18)年に聖武天皇の勅命により、東大寺の毘盧遮那仏(大仏)の開眼を行った導師婆羅門僧正が開山したとも伝えられる古寺で、聖武・鳥羽・後白河3帝の勅願所であった。宗派としては当初、興福寺系の法相宗であったが、その後、天台、真言、時宗の影響もうけ、同時に葉山権現など修験道との関...
山居倉庫 ( 山形県 酒田市 )
JR羽越本線酒田駅から南へ約2km、市街の南部、新井田川の河口近くにある庄内米の貯蔵庫。酒田は古くから庄内のみならず、奥羽地方の米の集散地*であった。現在の倉庫は酒田米穀取引所*の設立に尽力した旧庄内藩の藩主酒井家が、取引所の付属施設として1893(明治26)年に建設したものである。米の収容能力は、最大時の昭和初期には15棟で約...
銀山温泉 ( 山形県 尾花沢市 )
JR奥羽本線大石田駅から東へ約17km、尾花沢盆地の平野部の農村地帯を抜け銀山川を登りつめ少し緩やかに下ると、大正末期から昭和初期に建てられた3層・4層の木造旅館をまじえ14軒の湯宿が川を挟んで建ち並ぶ、こじんまりとした温泉街にたどり着く。 銀山温泉の名は1456(康正2)年儀賀市郎左衛門がこの地で延沢銀山を発見し江戸初期には銀...

蔵王温泉 ( 山形県 山形市 )
蔵王連峰の西麓、標高約880mに位置し、背後に広がる蔵王スキー場の基地としても賑わう温泉で、奥羽三高湯*の一つである。街の中央、高湯通りを中心に数十軒の旅館が軒を連ね、硫黄の臭気が鼻をつく。伝承では、西暦110年、東征中の日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の家臣吉備多賀由(キビノタガユ)が戦いで傷ついた折、この湯を見つけ、完...

飯豊山(飯豊連峰) ( 山形県 小国町 / 福島県 / 新潟県 阿賀町 )
山形、福島、新潟の3県にまたがる飯豊連峰の総称。標高2,128mの大日岳を最高峰に、飯豊本山とも呼ばれる飯豊山(標高2,105m)など、2,000m級の山々*が約20kmにわたって連なる。花崗岩と中古生層から成る褶曲山地で、氷河地形、周氷河地形及び雪食地形*が見られ、稜線の東西で地形が大きく異なる非対称山稜を形成している。植生も雪田群落な...
写真提供:本間家旧本邸
本間家旧本邸 ( 山形県 酒田市 )
JR羽越本線酒田駅の西南約1km、山居倉庫から北東に500mほどのところにある。酒田の豪商、本間家*3代光丘が1768(明和5)年に幕府の巡見使一行の宿として建築し、庄内藩主酒井家に献上した武家屋敷。その後、本間家が拝領し、代々、本邸として使用した。一つ屋根の下に武家屋敷と商家造り*が一体となった全国的にも珍しい建物である。 敷...
山形市郷土館(旧済生館本館) ( 山形県 山形市 )
JR奥羽本線山形駅からすぐ北に広がる霞城公園*内に建つ。現在、山形市郷土館として使用されている旧済生館本館は、1878(明治11)年に創建された。1階は八角形、2階は十六角形をした3層4階建ての擬洋風建築物*である。初代山形県令の三島通庸*は政府の威信を高め、近代化を推し進めるために、街の中心部に県庁、郡役所、師範学校など多く...
写真提供:山形県花笠協議会
山形花笠まつり ( 山形県 山形市 )
毎年8月5日~7日の三日間にわたり、山形市内で繰り広げられる祭り。祭りの見どころは夕方からはじまる花笠パレードである。市の中心街である十日町角から市役所前までの約1.2kmを「花笠音頭」に合わせて、3日間延べ約1万数千人の踊り手が集団ごとに、山車に先導されて踊る。踊り手は、特産の紅花をあしらった花笠を手に、団体ごとに揃いの浴...
写真提供:新庄市
新庄まつり ( 山形県 新庄市 )
毎年8月24日~26日の3日間、新庄市内で開催される。1756(宝暦6)年、新庄藩主5代戸沢正諶(まさのぶ)が、前年の大凶作に疲弊した領民たちを鼓舞し、五穀豊穣を祈るために、氏神である城内天満宮の新祭を始めたのが起源とされる。このため、当初は藩主が在城する隔年で行われていたと伝えられている。 24日は、戸沢家*の始祖などを祀る...

黒川能 ( 山形県 鶴岡市 )
鶴岡市の中心街から南へ約10kmの黒川集落にある春日神社*の神事能で、氏子(農民)によって継承されてきた。起源は諸説あり、9世紀後半に清和天皇が黒川を訪れた際に伝えられたとするものや、15世紀初めに後小松天皇の第三王子小川の宮が黒川に入り、その従者が伝えたとするものがあるが、いずれも口伝の域をでない。史料記録などはないもの...

写真提供:酒田市教育委員会
黒森歌舞伎 ( 山形県 酒田市 )
JR羽越本線酒田駅から南に10kmほどの酒田市黒森に伝わる農村歌舞伎。起源は不詳だが、江戸時代中期の享保年間(1716~1736年)ころからはじめられ、黒森日枝神社*の祭礼(旧暦の小正月)に合わせ、境内の常設の舞台で、毎年2月15日と17日に奉納上演される。演じるのはすべて「妻堂連中」*という地元住民。伝承演目は、現在、高田馬場十八番...
写真提供:一般社団法人 天童市観光物産協会
天童桜まつり ( 山形県 天童市 )
天童桜まつりは、毎年4月上旬から5月上旬にかけて開かれる祭りで、会期中は「人間将棋」「子ども将棋大会」「天童百面指し」「しだれ桜まつり」*「天童花駒踊りフェスティバル」などが市内各所で開催される。 メインイベントは、1956(昭和31)年から催されている「人間将棋」(4月第3土、日曜日)だ。当初は「将棋野試合」と呼ばれ、天...
写真提供:酒田市
酒田まつり(酒田山王祭) ( 山形県 酒田市 )
1609(慶長14)年に創始したとされる上・下日枝神社の例大祭「山王祭」*は、1976(昭和51)年の酒田大火からの復興と防災の願いを込め、1979(昭和54)年以降は「酒田まつり」として毎年5月19日~21日に開催している。 19日の宵祭りでは、2008(平成20)年から復活した高さ22.36mの立て山鉾に日没とともに明かりを灯し、中心街を巡行する...

米沢上杉まつり ( 山形県 米沢市 )
米沢上杉家*の家祖である上杉謙信を祀る上杉神社と、上杉鷹山、上杉景勝、直江兼続などを祀る松岬神社の春の例大祭に合わせ、米沢市を挙げての春の祭り。毎年4月29日~5月3日に開催される。第2次世界大戦前は「県社のまつり」あるいは「城下のまつり」といわれ、神輿渡御や武者行列などを行っていた。戦後、復興が進むなか、両神社の例大祭...
鶴岡市立加茂水族館(クラゲドリーム館) ( 山形県 鶴岡市 )
JR羽越本線鶴岡駅から西へ13km、湯野浜温泉の南約4km、日本海に面した海岸に立つ。前身となる水族館は昭和初期よりあったが、1964(昭和39)年から移転・新築し開館。経営的には厳しい時期もあったが、クラゲに特化した水族館を目指すこととし、2005(平成17)年にはクラゲの展示種類数が世界一の水族館となり、2012(平成24)年には世界記録...
本間美術館 ( 山形県 酒田市 )
JR羽越本線酒田駅の北西約500mにある。美術館は、2万m2の敷地内に、本館の京風建築の清遠閣と池泉回遊式庭園の鶴舞園、および美術展覧会場の新館からなる。清遠閣と鶴舞園は、酒田の豪商、大地主として知られた本間家*の4代光道が藩主酒井侯の領内巡検宿泊施設として別荘を造ったのがはじまり。 清遠閣は、茶室「六明廬」を備...
写真提供:公益財団法人 土門拳記念館
土門拳記念館 ( 山形県 酒田市 )
酒田市の中心街から南へ2km、飯森山公園内にある。酒田市出身の昭和を代表する写真家土門拳*の全作品7万点を収蔵している。代表作の『古寺巡礼』をはじめ『室生寺』『文楽』『ヒロシマ』『風貌』などが展示されている。谷口吉生の設計による記念館は、公園の緑を背景に遠く鳥海山を望み、人口池に突き出した短形状のシンプルなものだが、周...
肘折温泉 ( 山形県 大蔵村 )
JR山形新幹線の終着駅である新庄駅から南西へ約28km、カルデラ地形*の底を流れる銅山川のほとりに肘折温泉がある。そこから約1km離れた西の黄金(こがね)温泉、南の石抱(いしだき)温泉*と合わせ、肘折温泉郷と総称している。 肘折温泉の開湯には諸説があり、もっとも古い説では807(大同2)年ともいわれるが、1390(明徳元)年に月山...
滑川温泉 ( 山形県 米沢市 )
国道13号線の山形県と福島県の県境近くから県道、林道で約10km。東大巓(標高1,927m)の東北麓、標高850mほどのところにあり、前川の渓谷右岸にすっぽりとはまるように建つ一軒宿の温泉。開湯は1763(宝暦13)年。温泉に至る道は旧米沢街道の一部で、途中、旧道の小径に石畳も残されている。 静養、湯治向きの温泉で、家形山(いえがたや...
姥湯温泉 ( 山形県 米沢市 )
国道13号線の山形県と福島県の県境近くから県道、市道*で約14km。滑川温泉からは山道を4kmほどの一軒宿の温泉。吾妻山系の稜線に近い標高1,230mの深い渓谷の中にある。 温泉の周囲は切り立った黄褐色の断崖絶壁で、渓谷はガレ場を呈しており、その中を渓流が駆け下っている。断崖の上や渓谷の下流は、コメツガ・ブナ・ダケカンバなどの原...
写真提供:新庄市
神室山 ( 山形県 新庄市 / 山形県 金山町 / 秋田県 湯沢市 )
山形・秋田の県境にあり、栗駒国定公園の一角を占める。神室山(1,365m)を主峰に、黒森(1,057m)、水晶森(1,097m)、前神室山(1,342m)、天狗森(1,302m)、最高峰の小又山(1,367m)、火打岳(1,237m)などの山々が連なる。壮年期の隆起山塊で、多雪地帯で気候が厳しいことから、稜線は非対称に削ぎ落とされ、急峻な山容をみせる...
写真提供:寒河江市
葉山(村山) ( 山形県 村山市 / 山形県 寒河江市 )
村山市西端に位置し、北は大蔵村、南は寒河江市との境にあたる。麓の村山平野側からみると、連なる稜線と山容は馬蹄型になっており、火山であった面影を残す。山麓から山頂近くまでブナの原生林が見られ、県の天然記念物に指定されているトガクシショウマをはじめ、ドウダン、チングルマ、ハクサンシャクナゲ等の高山植物の群生地もある。山...
熊野大社 ( 山形県 南陽市 )
赤湯駅から北へ約5km、町並みを見下ろす丘の上にある。創建*の由緒は不明だが、8世紀にはすでに山岳信仰などの下地があった東北地方に熊野信仰*が浸透しつつあることを背景に、806(大同元)年に平城天皇の勅命により紀伊の熊野三山の神々が勧請され再建されたという。そののち、慈覚大師の天台系などの仏教宗派の影響を受けた古社である。...
上杉家廟所 ( 山形県 米沢市 )
JR米坂線西米沢駅から約1km、JR山形新幹線米沢駅からは約4kmの米沢市街の西部にある。上杉家*の初代謙信から12代斉定(なりさだ)までの歴代藩主の廟所。杉木立に囲まれた約2万m2の敷地に謙信の廟が中央に建ち、右側に奇数代の藩主、左側に偶数代の藩主の霊屋形式の廟が並んでいる。霊屋の前には家臣が寄進した燈籠群が整然と立...
写真提供:山形県
ベニバナ ( 山形県 山形市 / 山形県 天童市 / 山形県 寒河江市 / 山形県 上山市 )
キク科でアザミによく似た花をもち、古くから染料や口紅の原料として使用されていた。原産地は未詳だが、中近東だとされている。日本にはすでに3世紀には伝来していたといわれ、万葉集*にも「久礼奈為」、「呉藍」などとして詠み込まれており、10世紀後半に編纂された「和名類聚抄」には「紅藍」*の記載がある。 山形での栽培が始まった...
写真提供:南陽市観光協会
烏帽子山公園のサクラ ( 山形県 南陽市 )
JR山形新幹線赤湯温泉駅から東へ約1.4km、赤湯温泉の裏手にあり、烏帽子山八幡宮*の社域が公園になっている。桜の名所で、米沢(置賜)盆地をはじめ吾妻、飯豊、朝日連峰の好展望地である。 この公園は1875(明治11)年に温泉客向けにサクラなどの花木を植えたのが始まりである。その後、町が2度の大火に遭うなどして公園の拡張事業は困...
写真提供:村山市
山形板そば ( 山形県 村山市 )
そば自体は、日本においても他の雑穀として混ぜ粥状にしたり、餅状にしたそばがきにしたりして、古代から食されてきた。現在の細長い麺の形になったのは、江戸初期の頃に「そば切り」が考案されたからだといわれている。その後、各地でその風土や文化に合わせ、そばの打ち方、つなぎ、出汁、付け合わせ、食べ方、そして、それに応じた器など...

芋煮会 ( 山形県 全県 )
芋煮会は、河原で天高く晴れわたった秋の空のもと、サトイモ*、牛肉、コンニャク、ネギなどをしょうゆベースの出汁で煮て食べる行事。日本海岸側の庄内地方では牛肉のかわりに豚肉を使用し、うまみを出すために酒粕をいれ味噌仕立てで煮るなど、山形県内においても材料や出汁の違いは見られる。 起源は諸説あるが、 もっとも代表的なもの...
写真提供:公益財団法人 致道博物館
致道博物館 ( 山形県 鶴岡市 )
JR羽越本線鶴岡駅から南西に約2km、鶴岡公園の西にある。致道博物館は1950(昭和25)年、旧庄内藩主*酒井家が土地建物および伝来の文化財などを寄付し、開設された。現在は、庄内藩第11代藩主酒井忠発の隠居所であった御隠殿(ごいんでん)を中心に、明治前期に建設された旧西田川郡役所、旧鶴岡警察署庁舎、田麦俣の多層民家旧渋谷家住宅が...
山五十川の玉スギ ( 山形県 鶴岡市 )
JR羽越本線五十川駅から五十川沿いに6kmほど山間に入り、支流の温俣川がつくる沢の斜面にある熊野神社の境内に立つ。樹高36.8m、根元幹囲が22.2m、目通幹囲11.4mの杉の巨木で半球状の樹冠を有し、姿が良いことから、この名がついたという。樹齢は1,500年くらいといわれているが、樹勢は旺盛で太い根幹は斜面をしっかりつかみ、一部は地表に露...
写真提供:最上町教育委員会
旧有路家住宅(封人の家) ( 山形県 最上町 )
JR陸羽東線堺田駅の北東400m、国道47号に面している。雪の多い東北地方によくみられる広間型*と呼ばれる造りの約81坪の民家。築300年以上といわれ、松尾芭蕉*が「おくのほそ道」*の旅で宿泊したとされる唯一の現存する家である。 芭蕉は雨に降り込まれ、この家に1689(元禄2)年5月15日から17日(新暦では7月1日から3日)まで滞在した...
旧致道館 ( 山形県 鶴岡市 )
JR羽越本線鶴岡駅から南へ約2km、鶴岡公園の東南、鶴岡市役所前に位置する。致道館は庄内藩*酒井家第9代藩主酒井忠徳が藩制の緩みから武士の風紀の退廃を案じ、学問により正すことを目指し、1805(文化2)年に創設した庄内藩の藩校。致道館の名称は、論語の「君子學以致其道(君子学ンデ以テソノ道ヲ致ス)」による。当初は鶴ケ岡城の城外に...
写真提供:鶴岡市役所
松ヶ岡開墾場 ( 山形県 鶴岡市 )
JR羽越本線鶴岡駅から南東約8kmにある。譜代大名・酒井氏を藩主とする庄内藩は、江戸時代末期、江戸市中取締まり役を担い治安を守っていた。1867(慶應3)年、幕命により江戸の薩摩藩焼き討ちを決行したことをきっかけに、翌年、鳥羽・伏見の戦いが起こり、戊辰戦争が始まる。庄内藩は会津藩らとともに新政府軍と戦ったが、会津藩が破れ、最...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会
燧ヶ岳 ( 福島県 檜枝岐村 )
尾瀬沼の北にそびえる山で、尾瀬ヶ原・尾瀬沼の原型をつくり出した火山である。花崗岩を基盤として北は成層火山、南は小さい火口湖を抱く鐘状火山の様相を示しており、山頂は三角点のある爼嵓(まないたぐら)、最高峰(標高2,356m)の柴安嵓(しばやすぐら)、ミノブチ岳、赤ナグレ岳、御池岳の5峰からなっている。 登山道はブナ・オオシ...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会
会津駒ケ岳 ( 福島県 檜枝岐村 )
檜枝岐村の北西にある会津駒ケ岳*は標高2,133m。隆起平原が浸食されて生成された山なので、麓から尾根に向かい急坂が続くが、山頂部や尾根筋は平たん部も多く残されている。雪解け後には山頂付近に駒ノ大池が現れ、中門岳に伸びる稜線には池塘が点在し、7月上~中旬にかけハクサンコザクラなどの高山植物が咲く。頂上付近には北方的なオオシ...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会
三条ノ滝 ( 福島県 檜枝岐村 )
平滑ノ滝の約1km下流にある。檜枝岐側の御池からは上田代、兎田代分岐を経て展望台まで7kmあまり。尾瀬ケ原を流れるヨッピ川、沼尻川などを集めた只見川の上流にある。豊富な水を、高さ100m、幅30mで一気に落とし込む豪壮な滝である。水量が減少する時期には三筋に分かれて落下するのでこの名がある。滝は登山道から少し下ったところにある展...
桧原湖 ( 福島県 北塩原村 )
猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで最大の湖が、周囲約37.5kmの桧原湖で、水面標高は819m、最大深度は約31m。湖岸線は複雑に入り組み、南北約18km、東西約1kmの細長い形をしている。1888(明治21)年の噴火*によって磐梯山の...

小野川湖 ( 福島県 北塩原村 )
猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで3番目の大きさの湖が小野川湖である。東側に桧原湖、西側に秋元湖があり、水面標高794m、周囲約9.8km、最大深度約22m、北東から南西に約4kmと細長い形をしている。 小野川湖は、1888(明...
秋元湖 ( 福島県 北塩原村 )
猪苗代湖の北、会津若松の市街の北東に聳える磐梯山の北麓には、磐梯高原あるいは裏磐梯と呼ばれる高原地帯におよそ300の湖沼群が点在する。そのなかで秋元湖は周囲約19.8kmと2番目の大きさの湖。水面標高736m、最大深度約34mで東西に細長い形をしている。秋元湖は、1888(明治21)年の噴火*で小磐梯という磐梯山の北側の山が山体崩壊し、吾...

写真提供:福島市商工観光部観光交流推進室
吾妻連峰 ( 福島県 北塩原村 / 山形県 米沢市 )
福島市の西部から山形県境に広がる山塊で、最高峰2,035mの西吾妻山(にしあづまやま)をもつ西吾妻と、東大巓などの中吾妻、いまだに噴煙をあげる一切経山(いつさいきようざん)を含む東吾妻に大別され、火山群としても東吾妻火山、中吾妻火山、西吾妻火山の3つにくくることができ、東西20km、南北12kmの200km2を超える広大な面...

雄国沼湿原 ( 福島県 北塩原村 )
磐梯山の西にそびえる猫魔ガ岳(標高1,404m)・厩岳山(同1,261m)・古城ガ峰(同1,288m)・雄国山(同1,271m)など、猫魔火山の外輪山に囲まれて雄国沼*があり、沼の西岸から南岸にかけては、周囲の山からの流水、湧水によって、排水の悪い緩傾斜に谷湿原が発達している。これが雄国沼湿原である。とくに南岸は水辺から500~600mの幅で広が...
五色沼 ( 福島県 北塩原村 )
桧原湖南端のバス停磐梯高原駅から秋元湖寄りの裏磐梯ビジターセンター*(バス停五色沼入口)までの3.6kmの探勝路周辺に散在する大小30余りの沼を総称して五色沼湖沼群という。探勝路からは10数個の湖沼が観察できる。 この湖沼群は1888(明治21)年の噴火*で磐梯山北側の山、小磐梯の山体崩壊により、岩屑雪崩が生じ、長瀬川とその支流...

写真提供:一般社団法人 福島市観光コンベンション協会
花見山公園 ( 福島県 福島市 )
JR東北本線・東北新幹線福島駅から東南へ直線距離で約3.4km、標高180mほどの山を花木で埋め尽くした個人所有の公園。 この公園は、1935(昭和10)年ごろから山の所有者である阿部家が開墾し、出荷用の花卉(かき)生産のためにウメやサクラなどの花木を植えたことに始まる。その後も家族で営々と花木を植え育て続け、山全体が花の山となっ...

写真提供:高湯温泉観光協会
高湯温泉 ( 福島県 福島市 )
JR東北本線・東北新幹線福島駅から西へ約16km、吾妻山の北東山腹、標高750mにあり、磐梯吾妻スカイライン北入口にあたる。9つの源泉を引き湯した6軒ほどの旅館が、道路沿いに緑に埋もれるように点在する。 開湯は江戸時代初期慶長年間(1596~1615年)*といわれ、古くから湯治場として知られてきた。現在も自然湧出している源泉をアカマ...
慧日寺跡 ( 福島県 磐梯町 )
JR磐越西線磐梯町駅北約1.5km、磐梯山へ連なる山並みの山裾にある。平安時代初期に徳一*が開いた慧日寺は、江戸後期の『新編会津風土記』によると、「徳一當寺ニスミセシヨリ以來相續テ寺門益繁榮シ子院モ三千八百坊ニ及ヒ數里ノ間ハ堂塔軒ヲ比シ」たという。徳一は南都仏教の法相宗の出身だが、同寺は山岳信仰と密接な関係があり、磐梯山を...

写真提供:白河市役所
白河関跡 ( 福島県 白河市 )
白河関跡は、JR東北本線白河駅から南へ約12kmの山間に位置している。栃木県境からは約3km北の地点に、南北約300m、東西250mほどの小高い丘があり、丘の上にはこんもりとした木立の中に白河神社が鎮座し、周囲には中世に城館として使われた際のものと考えられる空堀や土塁がみられる。 古代の白河は、陸奥国の南端に位置し、南側は下野国・...

写真提供:白河市役所
小峰城 ( 福島県 白河市 )
JR東北本線白河駅の北側約500mに位置する。小峰ヶ岡と呼ばれる標高約370m、東西約450m、南北約80mの丘陵を利用した悌郭式平山城(ていかくしきひらやまじろ)である。丘陵の西端に本丸を設け、本丸の東側と南側に二之丸や三之丸などの曲輪を階段状に配置する。曲輪の周囲には石垣や堀が設けられ、全体としては五角形のような形状をした城郭...

写真提供:白河市役所
南湖公園 ( 福島県 白河市 )
南湖公園は、JR東北本線白河駅の南2.5kmにある。南湖は、天明の飢饉ののち、白河藩主松平定信*が1801(享和元)年に完成させた周囲約2kmの湖で、湖畔にサクラ・カエデ・マツなどを植え、「士民共楽」という理念のもと身分を問わず親しめる場所とした。文化年間(1804~1818年)には、「関の湖」、「共楽亭」、「千代松原」など南湖十七景*...
二本松城跡(福島県立霞ヶ城公園) ( 福島県 二本松市 )
JR東北本線二本松駅の北約2km、安達太良山系の裾野に位置する白旗ケ峰(標高345m)の頂上から麓にかけて城跡が残っている。霞ヶ城とも呼ばれる。南・西・北は丘陵に囲まれ、東に向け少し開けた地形となっている。 1414(応永21)年に奥州管領畠山国氏の孫満泰が、この地を本拠地としたのが始まりとされ、1586(天正14)年まで畠山氏の居城...

写真提供:南会津町
田代山湿原 ( 福島県 南会津町 )
田代山は福島県南部、栃木県境にある標高1,926mの山で、台地状の頂上部に湿原が広がる。田代山は数百万年前に生成された火砕流台地*といわれている。台地面は南西から北東に向け長い楕円形をしており、その直径は長い方が約800m、短い方が約350mである。 湿原の標高は約1,920~1,970mであり、北東方向に緩く傾いた傾斜湿原となっている。...

写真提供:南会津町
田島衹園祭 ( 福島県 南会津町 )
会津鉄道会津田島駅から北へ約500mにある田出宇賀(たでうが)*、熊野両神社の例大祭で、毎年7月22日、23日、24日の3日間開催される。 田島衹園祭の淵源については、この地方が文治年間(1185~1190年)頃から下野に本拠地を置く長沼氏の支配下に入り、その長沼氏の守護神が牛頭天王(衹園信仰)だったため居城の鴫山城の守護神として祀...
前沢の町並み ( 福島県 南会津町 )
会津鉄道会津高原尾瀬口駅から国道352号線を西に向かって約22kmのところにある。前沢集落は、現在の金山町横田(JR只見線会津横田駅付近)に本拠地があった山内氏勝が1590(天正18)年に伊達政宗勢との戦い敗れ越後に去ったのに伴い、その家臣であった小勝入道沢西が文禄年間(1592~1595年)にこの地に移り住んだのが始まりという。このため...

写真提供:尾瀬檜枝岐温泉観光協会
檜枝岐歌舞伎 ( 福島県 檜枝岐村 )
檜枝岐での歌舞伎興行は、1743(寛保3)年に購入された浄瑠璃本が残されており、1810(文化7)年の絵図に舞台が描き込まれ、1846(弘化3)年に歌舞伎衣装の借用の記録があるため、江戸後期から盛んになったとされる。現在も、地元民が伝統を継承するため「千葉之家花駒座」*の名で伝承、上演活動を行っている。 檜枝岐の舞台での歌舞伎...

写真提供:南会津町
木賊温泉 ( 福島県 南会津町 )
会津鉄道会津高原尾瀬口駅から桧枝岐方面に向かい約30km、西根川の渓谷に数軒の宿泊施設*と共同浴場がある。標高は900mほどあり、湯治のほか渓流釣り、登山基地として利用されている。 共同浴場の露天「岩風呂」*は、道路面から急坂の小道を西根川の渓流に下った河原にへばりつくようにある。湯船は2つあり、大きな岩盤をくり抜いて造っ...

写真提供:南会津町
駒止湿原 ( 福島県 昭和村 / 福島県 南会津町 )
会津鉄道会津田島駅から国道289号線で西へ約10kmの針生地区から町道に入り、さらに北西に7kmほど進むと、福島県大沼郡と南会津郡の郡境が接する分水嶺地域に広がっている。標高1,135mの駒止峠の北側一帯の沢には寒地性の低層・中間・高層の3段階の湿原群*が発達し、学術的に貴重なものとされている。国の天然記念物指定保護区域で面積はおよ...
磐梯山 ( 福島県 猪苗代町 / 福島県 磐梯町 / 福島県 北塩原村 )
福島県の中央部、猪苗代湖の北に位置する磐梯山*は、主峰の大磐梯(標高1,816m)、櫛ガ峰(標高1,636m)、赤埴山(標高1,430m)の3つの山体から成る成層火山。山頂部では櫛ヶ峰、赤埴山そして大磐梯に囲まれた標高約1,400mのところに、長径500mほどの低地沼ノ平を抱える。 磐梯山の火山活動の歴史は、約70万年前から開始されたと思われ、...

写真提供:二本松市観光連盟
安達太良連峰 ( 福島県 二本松市 / 福島県 猪苗代町 )
二本松市街の西約15kmに位置する安達太良連峰は、吾妻山と土湯峠で分かれて南へ9kmにわたって延びる火山連峰である。乳首山と呼ばれる標高1,700mの安達太良山*を主峰に、南端の和尚山(標高1,601m)、主峰から北に向かって鉄山(標高1,709m)、箕輪山(標高1,728m)、鬼面山(標高1,482m)など200~500mの円錐形をした火山が連なり、主峰の...

写真提供:国指定重要文化財 天鏡閣
天鏡閣 ( 福島県 猪苗代町 )
猪苗代湖の北西岸、長浜を見下ろす丘陵に立つ故有栖川宮威仁親王の旧別邸で、八角塔屋(展望室)付ルネッサンス様式風の和洋折衷の2階建洋館。1908(明治41)年の建築。建物の規模は建築面積492m2 、延床面積927m2 、総高17.9mである。皇太子であった嘉仁親王(のちの大正天皇)が「天鏡閣」と命名*した。 各部屋...
只見川 ( 福島県 只見町 / 福島県 檜枝岐村 / 福島県 三島町 / 福島県 柳津町 / 福島県 会津坂下町 )
福島・群馬県境の尾瀬沼、尾瀬ヶ原に源を発し、山間部を一旦北に流れ、福島県西部では北東に向かい、途中伊南川、野尻川などを合わせ、喜多方市で猪苗代湖から来る日橋川と合流して阿賀川となる全長137kmの川。阿賀川は新潟県に入ると阿賀野川と名を変え日本海に注ぐ。 只見川の上・中流部は深い山間部で上流部の只見町までの 50kmは会津...

写真提供:相馬野馬追執行委員会
相馬野馬追 ( 福島県 相馬市 / 福島県 南相馬市 )
「相馬流れ山、習いたかござれ。五月中申(なかのさる)、アノサお野馬追」と民謡「相馬流れ山」にうたわれる相馬地方最大の相馬野馬追は、現在は7月の最終土、日、月曜日に行われる。 起源は平将門*が野馬を狩って妙見宮に献じていたという故事によるといわれ、将門の末裔と伝えられる相馬氏が、1323(元亨3)年に、すでに源頼朝から所領と...

写真提供:相馬市ホームページ
相馬民謡全国大会 ( 福島県 相馬市 )
毎年秋に、相馬民謡振興会、相馬市の主催のもと開催されている。 相馬地方の民謡は、藩主相馬氏の影響を受けた勇壮なものと、民謡本来の農民の生活に根ざしたものに分けられる。野馬追の騎馬武者が唄う『相馬流れ山』が前者の代表なら、後者には明るい『相馬盆唄』、哀調を帯びた『新相馬節』がある。関東・東北両方の影響を受け、それを...

須賀川松明あかし ( 福島県 須賀川市 )
JR東北本線須賀川駅から南へ約1.2kmの中心街松明通りと隣接する翠ケ丘公園*を中心に、毎年11月第2土曜日に開催される火祭り。 由来について現在は、この地を文安年間(1444~1449年)から統治していた須賀川二階堂氏(行光の系統)の居城須賀川城が、1589(天正17)年、伊達政宗に攻め落とされた際の故事による。江戸後期の『白河風土記...

猪苗代湖 ( 福島県 郡山市 / 福島県 猪苗代町 / 福島県 会津若松市 )
福島県のほぼ中央部にあり、日本第4位の面積(103.3km2)をもつ淡水湖*で「天鏡湖」とも呼ばれる。磐梯山の麓のおだやかな湖面には、小さな岬や湾入はあるが大きな屈曲はなく、形は卵形に近い。湖に長瀬川が流入する北東部から北岸一帯がやや開けるほかは、山が湖岸に迫っている。北西部から流れ出る日橋川(にっぱしがわ)の水...

うねめまつり ( 福島県 郡山市 )
毎年8月第1木・金・土の3日間開催される。初日は、市内片平町のうねめ神社で開催される「采女供養祭」や市内西部プラザでは「ちびっこうねめまつり」が実施される。2日目・3日目は郡山駅前で「ミスうねめパレード」や学校や市民団体による「パフォーマンスステージ」、「商店街イベント」などが開催され、多くの市民が訪れる。祭のメインイ...

写真提供:(一社)喜多方観光物産協会
喜多方蔵のまち並み ( 福島県 喜多方市 )
喜多方市は会津盆地の北部に位置し、豊かな地下水に恵まれ良質な米の産地で、近世以降、酒・味噌・醤油などの醸造業が盛んであった。さらに、漆器などの産地でもあり、定期市が開かれ物産の集散地として栄えた。このため市の中心部を南北に流れる田付川両岸の中心街から山間に至るまで粗(あら)壁・白壁・黒漆喰(しつくい)・煉瓦造などの...

写真提供:喜多方市山都総合支所
山都そば ( 福島県 喜多方市 )
JR磐越西線山都駅から北西へ約10km、喜多方市山都町の山懐に入った宮古地区*は古くから良質なソバの産地として知られていた。この良質なソバを活用し、1984(昭和59)年から当時の山都町商工会の主導により「むらおこし」としてブランド化に取り組んだのが「山都そば」である。* 「山都そば」の特色は、製粉の歩溜まりを約70%とし甘皮...

写真提供:(一社)喜多方観光物産協会
喜多方ラーメン ( 福島県 喜多方市 )
喜多方には良質な水*があり、優良な米作りの地域であることから、古くから酒・味噌・醤油などの醸造業が栄えてきた。喜多方ラーメンは、その良質な水によって麺が作られ、茹でられ、伝統の醤油・味噌などによってラーメンスープの味のベースが作られている。麺の特徴はコシが強い「熟成多加水麺」*の平打ち麺を多くの店が使用している。ス...

写真提供:一般財団法人会津若松観光ビューロー
若松城(鶴ヶ城) ( 福島県 会津若松市 )
会津若松駅の南2km、市街地の南にある。芦名直盛*が1384(至徳元)年に築城し、1593(文禄2)年蒲生氏郷*が東日本で初めて水堀や天守閣を備えた本格的な近代城郭を築き「鶴ヶ城」と命名した。東西約2km、南北約1.5kmの外郭と7層の天守閣*をもち、鶴ケ城の名にふさわしい広壮かつ優美な城郭であったという。 藩政時代は会津松平氏*二十...

写真提供:一般財団法人会津若松観光ビューロー
御薬園(会津松平氏庭園) ( 福島県 会津若松市 )
鶴ケ城の北東1.3kmにある。中世に会津地方を支配していた芦名氏がこの地を霊地として別荘としたが、その後の戦乱で放置された。 会津に入部した会津松平家*初代藩主の保科正之が改めて庭園の整備を行ったといわれている。さらに2代藩主保科正経が貧民救済のため、1670(寛文10)年に園内に薬草園を設け、3代藩主松平正容が引き継ぎ、庭園...

写真提供:會津藩校日新館
日新館 ( 福島県 会津若松市 )
JR磐越西線広田駅から東北に約1.4km、江戸期の会津藩の藩校であった日新館を1987(昭和62)年に復元したもので、会津若松市街を見下す高塚山にある。かつての藩校*があった場所は鶴ヶ城の西出丸(馬場郭)濠端の米代(よねだい)であるが、現在、その場所には日新館天文台跡を残すのみである。日新館は白虎隊の出身校としても知られる。 ...

大内宿 ( 福島県 下郷町 )
会津鉄道湯野上温泉駅から北西3.5km、山間にある会津西街道*の旧宿場。会津西街道は会津藩の廻米*を江戸に送るルートであり、会津盆地との間に標高900mの大内峠があるため、大内宿は荷駄の中継・宿泊地として重用された。1884(明治17)年に大川沿いの国道121号線が開通するまで繁栄した。 現在でも、水路が両端を走る街道沿いに約30戸...
白水阿弥陀堂 ( 福島県 いわき市 )
JR常磐線内郷駅の西へ約2km、経塚山に三方を囲まれ、南に白水川を望んで建つ。阿弥陀堂の前と左右には大きな池が囲い、浄土庭園が広がる。浄土庭園の中島には北岸の阿弥陀堂に渡るため、南北二本の橋が架けられている。 藤原清衡の養娘徳姫(のちに徳尼)が、夫で「海道平氏」と称した岩城則道を弔うため1160(永暦元)年に建てたものと伝...

写真提供:環境水族館アクアマリンふくしま
環境水族館アクアマリンふくしま(ふくしま海洋科学館) ( 福島県 いわき市 )
JR常磐線泉駅から東へ約5kmの所にある。2000(平成12)年に開館し、2011(平成23)年には東日本大震災での被災もあったが、復旧、再オープンした。建物はガラスで覆われ、光や風を取り込む構造になっているのが特徴的で、小名浜港の人工的な風景と対比しつつ海の雄大さと自然を感じさせるような設計になっている。 水族館としてのテーマは...

写真提供:南会津町
南会津のそば畑 ( 福島県 南会津町 / 福島県 下郷町 )
南会津地方は、昼夜の寒暖の差が大きく水はけの良い土壌など、ソバ栽培の適地が多く、福島県のなかでも、猪苗代、喜多方に並んでソバの栽培が盛んである。なかでも下郷町の猿楽台地と南会津町の会津高原たかつえのソバ畑は、会津の山々に四方を囲まれながら大規模な栽培地が広がる。 下郷町南西部、会津鉄道養鱒公園駅から南東へ約3kmにあ...

写真提供:湯川村教育委員会
勝常寺 ( 福島県 湯川村 )
JR磐越西線会津若松駅から国道121号線経由で北西に約10km、田園風景が広がる湯川村のこんもりとした木立の中に勝常寺はある。 寺伝によれば、810(弘仁元)年に慧日寺の開祖でもある徳一*が開創したといわれている。中世には一時衰退したが、仁和寺の僧玄海が再興し、会津を支配していた芦名氏の庇護をうけ、七堂伽藍が備わり100ヶ寺ほど...
恵隆寺(立木千手観音) ( 福島県 会津坂下町 )
恵隆寺は、JR只見線塔寺駅から東へ1.5km、会津坂下駅からは北西に約3kmの微高地に建つ。「立木千手観音」は恵隆寺の本尊で、観音堂*に納めれている。恵隆寺の起源は、欽明天皇のころ(540年ごろ)、2.5kmほど西北にある高寺山遺跡の場所に梁国の僧青岩によって開かれ一時は隆盛を誇ったが、慧日寺(磐梯町)との戦いに敗れ荒廃し、1190(建...

写真提供:金山町観光物産協会
沼沢湖 ( 福島県 金山町 )
JR只見線早戸駅から只見川を渡り、つづら折りを登って約5kmのところにある。湖面標高474m、周囲7.5km、最大水深96mの透明度の高いカルデラ(火口)湖である。沼沢火山は11万年前から活動が始まったといわれているが、このカルデラ湖が生成されたのは約5600万年前の噴火活動によるものとされている。 周囲の外輪山は林野庁の自然観察教育林...

願成寺(会津大仏) ( 福島県 喜多方市 )
JR磐越西線喜多方駅の北6kmほどのところにある。願成寺の始まりは法然の高弟で浄土宗多念義派の祖隆寛が法難に遭い、奥州に配流となったが、途中相模国で遷化したため、1227(嘉禄3)年に意を受けた法弟の實成が遺骨を配所があった加納松原(現在地の南方)に葬り、一宇を建立したことによる。このため、同寺では隆寛を開山、實成を創立とし...

筑波山神社 ( 茨城県 つくば市 )
筑波山の中腹、老杉に包まれた境内に大きな鈴が印象的な拝殿をはじめ境内社が並ぶ。本殿は男体山と女体山の山頂付近にある祠で古代の山岳信仰を今も伝えており、2峰寄り添う姿は男女陰陽・夫婦和合の神にふさわしい。 延喜式内名神大社に数えられた格式ある社だが、平安時代に僧徳一*によって知足院中禅寺が開かれ、筑波の神は筑波両大権...
写真提供:ミュージアムパーク茨城県自然博物館
ミュージアムパーク茨城県自然博物館 ( 茨城県 坂東市 )
1994(平成6)年に「茨城の風土に根ざした自然に関する総合的な社会教育機関」として「過去に学び、現在を識り、未来を測る」ことを基本理念に、茨城県最大の自然環境保全地域である菅生沼*の西岸に開設された。16.4万m2という広い敷地ではあるが、隣接する菅生沼との一体的な景観を意図して博物館の建物・施設は設計されている...

写真提供:大子町観光協会
袋田の滝 ( 茨城県 大子町 )
福島県から茨城県へと流れる久慈川*の支流滝川にかかる滝。滝は4段から成り、高さ120m、幅73m。成因は、1,500万年前に形成された火山角礫岩層の硬い岩石に対し、滝の上下が浸食されやすい凝灰質の砂岩や頁岩だったため、硬質の火山岩が残り、節理と断層面が浸食され段差が生まれたと、考えられている。滝の途中に四本の大きな節理があり、4...
古河公方公園(古河総合公園) ( 茨城県 古河市 )
JR東北本線古河駅より南へ約2km、渡良瀬川の東岸にある。 1972(昭和47)年に「古河公方館跡*を中心に残されている美しい自然を保存し市民のレクリエーションの場所」とするという構想案がまとまり、1975(昭和50)年、古河総合公園として、一部開園。その後、桃林*、大賀ハスの移植、御所沼の復元*や管理棟・カフェテラスなどの整備を...
写真提供:古河市役所
古河堤灯竿もみまつり ( 茨城県 古河市 )
毎年12月の第一土曜日、JR宇都宮線古河駅前に高さ約10mの矢来を組んだ会場を設け、市内の自治会などのグループがそれぞれ20m近い竹竿の先に提灯をつけ集まり、激しく揉み合い相手の提灯の火を消し合う祭り。 この祭りの起源は、江戸時代は古河藩領であった野木神社(現在は栃木県野木町)*の神官が、神鉾を奉じ11月27日から神領である八...

楽法寺(雨引観音) ( 茨城県 桜川市 )
坂東三十三ケ所第24番札所。加波山の尾根続きになる雨引山の中腹斜面に真壁城の薬医門を移築した黒門をはじめ、仁王門*、本堂、鐘楼堂、多宝塔、本坊、客殿など多数の堂宇が甍を並べ、仁王門の脇には城郭を思わせる大石垣がそびえる荘厳な寺である。 587(用明天皇2)年中国の帰化僧法輪独守の創建と伝え、その後、勅願寺として朝廷や真...
真壁の町並み ( 茨城県 桜川市 )
つくば市の北にあり、町並みの東側に足尾山と加波山(かばさん)、南側には筑波山が見られる。真壁*は、律令期(7世紀後半~10世紀)から国府(現・石岡市)と東山道をつなぐ要衝の地にあり、中世には真壁氏の支配のもと城下町が形成され、近世には、笠間藩の陣屋を中心に木綿などの物産の集散地として栄えた。このため、真壁の町並みの特徴...
写真提供:鹿島神宮
鹿島神宮祭頭祭 ( 茨城県 鹿嶋市 )
祭頭祭は毎年、3月9日に執り行われる*。起源は、奈良時代あるいは平安時代ともいわれているが、近世までは、その囃し言葉*から窺えるように「五穀豊穣」を主に祈る祭りであったり、神仏習合の影響を受け、釈迦入滅の「常楽会」(涅槃会)ともされ、幕末までは鹿島神宮と神宮寺*が習合して執り行っていた。昭和初期には、軍国化の時流の中...

弘道館 ( 茨城県 水戸市 )
1841(天保12)年、徳川斉昭*が当時、内憂外患だった時勢に対応するために水戸城三の丸に創設*した藩校。ここで尊王攘夷運動に活躍した人材が育成された。『弘道館記』に示されたごとく神儒合一・文武不岐・学問事業の一致を目的に水戸学*の振興・尊王攘夷論が展開された。儒学・武道のほかにも医・薬・天文・地理などの実学も重んじられ...

写真提供:茨城県土木部都市整備課
偕楽園 ( 茨城県 水戸市 )
水戸駅の西方に広がる都市公園で、梅の公園としても知られ、金沢の兼六園、岡山の後楽園とともに日本三名園の一つに数えられる。本園と拡張部と合わせ、面積58万m2におよぶ広大な公園*である。本園は1842(天保13)年、徳川斉昭*が造園し、藩主1人が楽しむものではなく、領民と偕(とも)に楽しむという意味から「偕楽園」と名付...

霞ヶ浦 ( 茨城県 行方市 / 茨城県 土浦市 / 茨城県 他 )
茨城県南部の淡水湖で、琵琶湖に次いで日本第2の面積をもつ。桜川・恋瀬川(こいせがわ)の下流部が沈降したところへ、海水が流れ込んで入江となり、そののち鬼怒川によって運ばれた沖積物が出口をせき止めたためにできた湖だ。香澄ケ浦(かすみがうら)とも書き、北浦に対して西浦とも呼ばれ、広い意味では北浦を含めて霞ケ浦という。北西部...

あんこう鍋 ( 茨城県 北茨城市 / 茨城県 日立市 / 茨城県 ひたちなか市 / 茨城県 大洗町 / 茨城県 水戸市/他 )
深海魚でグロテスクな姿をしたアンコウ*は日本の近海の各地で獲れ、現在、水揚げが圧倒的に多いのは山口県の下関港で、茨城県の平潟、大津、久慈、那珂湊などの各港を合わせても及ばない。しかし、栄養たっぷりの黒潮で育ち、冬に南下する冷たい親潮で脂がのった肝が肥大化する常磐沖のアンコウは、絶品だとされる。 日本においてはアン...
写真提供:一般社団法人水戸観光コンベンション協会
磯節全国大会 ( 茨城県 水戸市 )
「磯で名所は大洗様よ・松が見えますほのぼのと」の名文句と尻あがりの口調で知られる磯節は、その起因は明らかでないが、大洗や那珂湊の漁師たちが舟端をたたきながら、荒海と岩礁と波涛が作りだす景色のおもしろさを唄ったとも伝えられる。明治になって芸者置屋の主人矢吹万作や俳諧宗匠の渡辺竹楽坊が大洗の祝町の芸妓に三味線にのせ唄わせ...
那珂川 ( 茨城県 水戸市 / 茨城県 ひたちなか市 / 茨城県 大洗町 / 茨城県 他 )
那須火山の那須岳(標高1,917m)に源を発し、栃木・茨城両県を流れ、ひたちなか市と大洗町の間で太平洋に注ぐ。余笹川、箒川、桜川や河口近くで最後に合流する涸沼川なども含め、196の支流を有する。全長は150km、流域面積は3,270km2。 支流を含め那珂川は、古代から鉄道開通する近代まで舟運が盛んだった。そのため、古くから...
かみね公園・平和通りのサクラ ( 茨城県 日立市 )
平和通りは日立駅中央口から国道6号まで約1km、幅員36mの日立市のメインストリート。1951(昭和26)年から沿道にサクラが植えられはじめ、現在では約120本のサクラが満開時には道路を覆うように咲き誇る。日立さくらまつりの中心会場となり、ユネスコ無形文化遺産である日立風流物(山車)なども披露される。 かねみ公園は日立駅の北方約2...
日立風流物 ( 茨城県 日立市 )
高さ15m、重さ5tにも及ぶ巨大な山車。正面は唐破風造、5層からなる城を模し、その背面は大きな山に見立てた裏山と呼ばれる造りである。屋形は中央から割れるように開いて舞台となり、『源平盛衰記』『忠臣蔵』といった人形芝居が催される。それが終わると山車は半回転し、裏山の舞台では『花咲爺』『自雷也』といった伝説・神話などが演じら...
牛久大仏 ( 茨城県 牛久市 )
JR常磐線牛久駅から東へ約9km、圏央道阿見東インターチェンジの近くにある。牛久大仏(阿弥陀如来像)は、浅草にある浄土真宗東本願寺派本山東本願寺の関連施設の一部として1992(平成5)年に建立、開園された。 牛久大仏は高さ120m(像高100m、台座20m)あり、青銅(ブロンズ)製仏像の高さとしては世界一ということから、ギネス世界記録...

茨城県天心記念五浦美術館 ( 茨城県 北茨城市 )
日本の芸術・文化に対する評価が国内外で定まらなかった明治期に日本の伝統美術の維持・発展に尽力していた岡倉天心*は日本美術の向上・開発を目指した美術団体、日本美術院を東京に興した。しかし、運営上の行き詰まりから、天心の新しい拠点となった五浦の地に日本画部門を移転することにした。日本美術院に参画していた横山大観、下村観...
写真提供:日立市
日立駅 ( 茨城県 日立市 )
日立駅は、1897(明治30)年に開業(当時は助川駅)した。当初は日立鉱山の積み出し駅として、その後は日立製作所に関連する貨物取扱などで重要な役割を果たしてきた。現在は貨物駅も含め縮小されているが、1日の乗降客が1万人を超えるJR常磐線の主要駅のひとつである。 駅は市街地を背に太平洋を前面にして、30mほどの高さの海岸段丘の...
写真提供:宇都宮美術館
宇都宮美術館 ( 栃木県 宇都宮市 )
「宇都宮美術館」及びその周辺の公園施設「うつのみや文化の森」は、宇都宮市制100周年を記念して1997(平成9)年3月にオープン。この施設は、宇都宮市中心部より北に約5kmに位置し、里山の姿を残す緑豊かな自然環境の中で、憩いの場、芸術文化活動の拠点施設としての活用を目的としている。
唐沢山城跡・唐沢山神社 ( 栃木県 佐野市 )
佐野駅の北約4kmの唐沢山、247mの山頂に築かれた関東七名城の一つに数えられる広大な山城である。城郭は、山頂から東西に伸びる尾根や山腹を巧みに利用して、堀や土塁が設けられている。 城は940(天慶3)年、大ムカデ退治の伝説で知られる藤原秀郷により築かれた。戦国時代、勢力を伸ばした佐野氏が唐沢山城を修築して居城とした。1600(...

写真提供:(一社)佐野市観光協会
万葉自然公園かたくりの里 ( 栃木県 佐野市 )
三毳山(みかもやま)は、万葉集にも詠まれた佐野市の東部に位置する美しい山。北斜面の中腹1.5ヘクタールに150万株のカタクリが群生している。カタクリの見頃は、3月中旬から3月下旬頃。 また、春のイチリンソウ、チゴユリ、夏のヤマユリ、キツネノカミソリ、秋のキバナアキギリ、ヤマトリカブトなど、数多くの野草や樹木が花を咲かせる。
写真提供:足利市教育委員会事務局
足利学校跡 ( 栃木県 足利市 )
JR足利駅の北西500mにある。創建については、平安初期の小野篁説や、鎌倉時代初期の足利義兼説がある。歴史が明らかになるのは室町中期以降で、1439(永享11)年に関東管領上杉憲実が鎌倉の禅宗五山のうち円覚寺の僧快元を初代庠主(しょうしゅ)*として学校を整備し、学則を定め学生を養成した。憲実以後もその子憲忠などが学校の基礎を固...
鑁阿寺 ( 栃木県 足利市 )
鑁阿寺は足利學校跡の北側に隣接する。本尊が大日如来であるところから、市民の間では「大日様」とも呼ばれて親しまれている。 1196(建久7)年、足利義兼が鑁阿と号し、その邸内に持仏堂を建てたのが始まりとされる。それ以後、足利家累代の氏寺として栄え、鎌倉時代には堀の外縁部に12の支院を配し、一山十二坊へと発展した。江戸時代に...

太平山神社 ( 栃木県 栃木市 )
栃木駅の西方約4km、太平山(343m)の山頂の東側には太平山神社が鎮座する。祭神は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)。創建は827(天長4)年に円仁が当山に参拝した際とも、神護景雲年間(767~770年)ともいわれるが、明らかではない。 境内には、太平山神社(太平権現)、連祥院般若寺などがあり、平安時代以来神仏習合の霊場であった。約1,00...
栃木市の町並み ( 栃木県 栃木市 )
まちの北から南へ渡良瀬川の支流巴波川が流れ、西に太平山がそびえている。江戸時代には巴波川の河川交通により、卸問屋が集まる町として発達し、また例幣使街道の宿場町としても栄えた。 1871(明治4)年には栃木県庁が置かれ、栃木県の県庁所在地として急速に繁栄したが、1884(明治17)年に宇都宮に県庁が移り、県名だけが残った。 ...
満願寺 ( 栃木県 栃木市 )
栃木市内の北西、出流山(いずるさん)の中腹、老杉におおわれた静寂境にある坂東三十三ケ所霊場第17番札所。765(天平神護元)年、勝道上人が開いたといわれ、820(弘仁11)年、弘法大師の巡錫の折、本尊の千手観音像を刻んで安置したと伝えられる。勝道上人が日光を開いたことから徳川氏の尊信が厚く、日光の修験僧は必ず一度はここで修行...
写真提供:国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所
渡良瀬遊水地(谷中湖) ( 栃木県 栃木市・小山市・野木町 / 茨城県 古河市 / 群馬県 邑楽郡板倉町 / 埼玉県 加須市 )
栃木、群馬、埼玉、茨城4県の県境にまたがる日本で最大の遊水地であり、渡良瀬川、巴波川、思川に沿って広がり、その洪水流を受け入れることで遊水地周辺の河川水位を下げるとともに、下流へ流す流量を減らし、利根川の氾濫を防止するという治水上の重要な役割を果たしている。 当地は、関東平野で一番の低地で、水がたまりやすい地形であ...
写真提供:那珂川町馬頭広重美術館
那珂川町馬頭広重美術館 ( 栃木県 那珂川町 )
歌川広重の肉筆画や歌川派の浮世絵版画、小林清親を中心とした明治の版画、川村清雄の油絵等、「青木コレクション」*を中心に展示している。 来客は、浮世絵目的の他に、美術館の建物見学に訪れる人も多い。建物の設計は隈研吾。彼の出世作とも位置づけられている建物である。地元産の八溝杉の格子で覆われ、平屋建で切妻の大屋根が流れ...
写真提供:那須烏山市
山あげ祭 ( 栃木県 那須烏山市 )
1560(永禄3)年時の烏山城主那須資胤が、当地方の疫病防除、五穀豊穣、天下泰平を祈願し牛頭天王を烏山に勧請した。その祭礼の奉納余興として、当初は相撲や神楽獅子舞等が行われていた。やがて、江戸で常磐津所作が流行したのをきっかけに常磐津所作を奉納余興として行うようになり、今日のような絢爛豪華な野外歌舞伎舞踊となった。この「...
写真提供:那須塩原市
板室温泉 ( 栃木県 那須塩原市 )
黒磯駅から北西に約20km、那須岳の山裾の、那珂川の支流湯川に沿う山間の温泉街である。約900年前に発見され、「下野の薬湯」として知られてきた。現在もむかしの静寂さと素朴さをとどめたたたずまいである。 付近は春の新緑、秋の紅葉で知られている。

三斗小屋温泉 ( 栃木県 那須塩原市 )
朝日岳の西に派生した稜線を下ったところ、標高約1,460mの高所にある歴史の古い温泉。山奥のため自家発電で夜9時ごろまで電気がつくが、それ以後はランプをともす素朴さである。旅館の東側高みに温泉神社がある。 登山者の利用が多く、朝日岳や大峠・三本槍岳方面への基地となっている。 温泉へは、車でいくことはできず、峠の茶屋県営...

写真提供:特定非営利活動法人塩原温泉観光協会
塩原温泉郷 ( 栃木県 那須塩原市 )
塩原温泉郷のエリアは、面積の80%以上が森林地帯。太平洋側と日本海側、また関東地方と東北地方の気候の交差点で、昆虫や両生類、木々や草花などの種類が豊富。北には標高1849mの日留賀岳(ひるがたけ)、南には標高1789mの釈迦ヶ岳(しゃかがたけ)などがあり、山からは無数の沢が流れ、東西に流れる箒川(ほうきがわ)に注ぐ。長い年月を...

那須湯本温泉 鹿の湯 ( 栃木県 那須町 )
県道17号線が貫通する那須湯本温泉と湯川で分かつ向かいが元湯で、なだらかな斜面を登り詰めたところに鹿の湯がある。 元湯はむかしながらのひなびた雰囲気の湯治場で、小規模の旅館や民宿が石畳の元湯通りに建ち並ぶ。民宿では自炊もできる。 鹿の湯の発見は古く、1390年前といわれている。738(天平10)年、正倉院の文書のなかに那須...

那須岳(茶臼岳) ( 栃木県 那須町 / 栃木県 那須町 / 福島県 西郷村 )
広大な関東平野の北端に関東と東北とを分けるように連なるのが、那須火山帯に属しその名の起こりとなった那須火山群である。那須岳は、その火山群の主峰茶臼岳をさす場合と、茶臼岳とその左右に連なる三本槍岳・朝日岳・南月山・黒尾谷山など、いわゆる那須五岳をさす場合とがある。 那須火山群は新生代第三紀から第四紀にかけてできたも...

那須岳南東麓の温泉群(大丸温泉、弁天温泉、北温泉) ( 栃木県 那須町 )
那須岳南東麓の標高1,000m前後の高原にわく温泉群。那須七湯、八湯とも呼ばれるほど温泉が豊富な地域であるが、この中でも大丸温泉、弁天温泉、北温泉は湯量が豊富であることで知られている。
写真提供:(一社)日光市観光協会
霧降ノ滝 ( 栃木県 日光市 )
華厳ノ滝、裏見ノ滝とともに「日光三名瀑」の一つで、駐車場からは徒歩10分程度で観瀑台へ行くことができる。観瀑台からは遠く正面に霧降ノ滝を望むことができる。 霧降ノ滝は霧降川の岩壁にかかる二段の滝で、上段が25m、下段が26m、高さは75m 、幅20m。下段の滝が霧が降るように落下するのでその名が付けられた。

日光二荒山神社 ( 栃木県 日光市 )
恒例山の西麓にあり、東照宮造営以前は二荒山(日光山)信仰によって山内の中心を成していた。主神大己貴命(おおなむちのみこと)は秀峰二荒山(男体山)の神、妃神の田心姫命(たごりひめのみこと)は女峰山の神、御子神の味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)は太郎山の神である。別宮の滝尾神社・本宮神社とともに、もとは日光三...
日光二荒山神社中宮祠 ( 栃木県 日光市 )
中禅寺湖の北岸、男体山を背後にする。湖畔に銅鳥居が立ち、中門・拝殿・本殿など、総朱塗、銅板葺の華麗な社殿が湖に面して立ち並んでいる。 784(延暦3)年、勝道上人が二荒山(男体山)の冬季遥拝所として、この地に二荒山権現を祭ったことに始まると伝え、以後、山岳崇拝の道場として栄えた古社である。江戸時代までは神仏習合の信仰...
大猷院霊廟 ( 栃木県 日光市 )
東照宮の西方約500m、大黒山にある徳川3代将軍家光公の霊廟である。家光公は1651(慶安4)年4月、48歳で没し、その遺命によって同年5月、遺骸をここに葬った。霊廟建築は1652(承応元)年2月に工を起こし、翌年4月に完成。建築総指揮は幕府の作事方大棟梁であった平内大隅守応勝。 境内は東照宮に準じた伽藍配置であるが、東照宮の絢爛豪...

日光山輪王寺 ( 栃木県 日光市 )
長坂を登りつめると、日光開山勝道上人像の前へ出る。太い眉、大きな鼻、右手に錫杖を持つ上人像の後ろに、山内最大の建物である三仏堂がどっしりと静まっている。このあたりが輪王寺の中心部で、三仏堂を本堂に、勝道上人像をとり囲むように一山15院の甍が連なる。神仏習合の地であるため、このほか四本竜寺・開山堂・大猷院廟・慈眼堂など...

滝尾神社 ( 栃木県 日光市 )
輪王寺行者堂から滝尾神社へ向かっていくと、「大小便禁制の碑」*がある。ここから滝尾神社の神域に入り、筋違橋から白糸の滝が見える。さらに老杉の木立を縫って続き、苔むした石段の上に、石鳥居、楼門、拝殿、唐門、本殿などの華麗な社殿が立ち並ぶ。 東照宮遷座以前は、二荒山神社、本宮神社とともに三社権現の一つとして庶民の信仰...

常行堂・法華堂(二つ堂) ( 栃木県 日光市 )
二荒山神社の近く、大猷院廟への参道沿いに北面して立つ2棟の建物。848(嘉祥元)年、慈覚大師が創建したと伝える天台宗の修行道場である。 もとは東照宮三神庫のあたりにあったが、東照宮造営のため移転した。向かって左が常行堂、右が法華堂で、ともに宝形造、総朱塗、2棟は歩廊でつながり、常行堂が和様、法華堂は唐様の建築であるが、...

慈眼堂 ( 栃木県 日光市 )
常行堂・法華堂をつなぐ歩廊を抜け、坂道を200mほど登りつめた山の上にある。慈眼大師の号を贈られた天海大僧正の墓所で、廟塔・拝殿のほか、阿弥陀堂・経蔵・鐘楼などが立ち、参道の賑わいとはうって変わって、ものさびしい雰囲気に包まれている。 慈眼堂拝殿は八棟造、総朱塗の豪壮な建築、その背後に廟塔がある。石柵で囲まれた高さ約3...

写真提供:(一社)日光市観光協会
華厳ノ滝 ( 栃木県 日光市 )
高さ97m。中禅寺湖から流れ出る大尻川が大岩壁から一気に落下し、「日本三名瀑」の一つに数えられる豪壮な瀑布を形成している。 華厳ノ滝は日光山開山の祖 勝道上人の発見と伝えられており、鏡のような中禅寺湖を仏の大円鏡智にたとえ、仏の教えが滝のように響きわたるように、経典の名から名付けられたという。下流の阿含滝・般若滝・方...
写真提供:(一社)日光市観光協会
中禅寺湖 ( 栃木県 日光市 )
男体山の南麓にあり、日光国立公園の湖沼の中で最も大きく、日本の代表的な高山湖に数えられている。 面積11.9km2、水色は深緑色から藍色まで季節によって変化する。新緑・紅葉のころはひときわ神秘的である。 湖水は東西に細長く、北岸の汀線はほぼ直線に近いが、南岸は出入りに富む沈降型汀線となり、八丁出島をはじめ岬...
写真提供:(一社)日光市観光協会
男体山 ( 栃木県 日光市 )
中禅寺湖の北岸に円錐形の雄大な山容を見せてそびえ立つ、日光火山群中の雄峰。高さ2,486m。中禅寺湖の水面上からの高さは約1,200mほどで、裾野は長く、大きく、日光市街近くにまで達する。頂上北側に直径約800mの爆裂火口跡があり、山頂からは放射状に薙(なぎ)と呼ばれる涸れ谷が発達しているほか、北側には固まった溶岩が尾根状になり戦...
写真提供:(一社)日光市観光協会
竜頭ノ滝 ( 栃木県 日光市 )
菖蒲ヶ浜の湖畔から戦場ヶ原へ向かう道の中間点にある。国道120号はこの滝下から大きくカーブしており、バスを降りればすぐ滝壷前へ出る。 華厳ノ滝のように直下型の瀑布ではなく、戦場ヶ原を流れてきた湯川が男体山の軽石流溶岩の上を210m、幅10mで奔流する渓流瀑である。下流部の観瀑台では、急流状に激しい水音をたてて白いしぶきを上...
写真提供:(一社)日光市観光協会
戦場ヶ原・小田代原 ( 栃木県 日光市 )
戦場ヶ原は中禅寺湖の北、男体山の西に広がる平均標高1,400mの湿原状の東京ドーム85個分、4km2の規模を誇る高原で、日光国立公園に位置する。また、湯ノ湖、湯川、戦場ヶ原、小田代原のうちの約2.6km2が「奥日光の湿原」としてラムサール条約の登録湿地に登録されている。 大昔の男体山噴火の折り、その噴出物が竜...
奥日光湯元温泉 ( 栃木県 日光市 )
戦場ヶ原の北西、湯ノ湖北岸にある奥日光のうちでも最奥の温泉で、西に白根山、北西に温泉ガ岳、東に三岳の山々を巡らしている。 温泉の発見は1200年もむかし勝道上人によると伝え、湯治温泉として長い間親しまれてきた。今でも一角に残る石畳や、しっとり落ち着いた雰囲気の中に歴史が感じられる。 旅館は近代化しながらも風格を備え...
写真提供:(一社)日光市観光協会
湯ノ湖 ( 栃木県 日光市 )
湯元温泉の目前に広がる、三方を山に囲まれた静寂な湖であり、三岳の溶岩流により湯川がせき止められて形成された標高1,478mにある堰止湖である。水の色はフォーレル9号から10号(1948(昭和23)年)、全般に水深は浅く、温泉が湧き出ている北岸の一部を除いて冬季は結氷する。 周囲3km、湖岸には1時間ほどで一周できる散策道が整備されて...
写真提供:(一社)日光市観光協会
龍王峡 ( 栃木県 日光市 )
今から2200万年程前に海底火山によって噴出された火山岩が、鬼怒川の流れによって浸食されて現在のような景観になったといわれる。 まず初めに安山岩が流出し、その後流紋岩の活動を経て、火山爆発による火山灰が堆積して緑色凝灰岩ができたとされる。さらには、その上に流紋岩が流出したと言われる。その後もマグマの活動により、岩脈が...
写真提供:(一社)日光市観光協会
鬼怒沼湿原 ( 栃木県 日光市 )
鬼怒沼山・物見山の鞍部南側、鬼怒川の源流あたりに広がる標高2,030mの高層湿原「鬼怒沼」には、大小48個の池塘が散在している。 6月中旬頃にはミズバショウが咲き始め、7月から8月にかけては、ヒメシャクナゲ、イワカガミ、タテヤマリンドウ、キンコウカなど数々の花が見られる。8月下旬には草紅葉がはじまり、9月中旬にもなると湿原全体...
写真提供:(一社)日光市観光協会
霧降高原のニッコウキスゲ ( 栃木県 日光市 )
赤薙山の南側に広がる標高1,200m前後の斜面一帯が霧降高原である。キスゲ平は赤薙山の中腹、標高1,300~1,600mにかけて広がる。 キスゲ平では、100種類を超す花々が春から秋まで楽しめるが、その中でも6月中旬から7月にかけて咲くニッコウキスゲの群生は見事。霧降高原一帯に数々の滝や沢があり、ヤマツツジやニッコウキスゲなどの群生地...
写真提供:栃木県
女峰山 ( 栃木県 日光市 )
霧降高原から赤薙山、女峰山と回る登山が多く、両山は一つの火山体を成している。 女峰山は2,010mの赤薙山よりも2,483mと高いうえに、尖った頂きと雄大な裾野を引く成層火山である。女体山ともいわれ男体山・太郎山とともに古くから崇拝され、信仰登山が盛んであった。展望がすばらしく、峰修行の遺跡も多い。

写真提供:(一社)日光市観光協会
日光杉並木街道 ( 栃木県 日光市 )
日光街道・例幣使街道・会津西街道の両側に延37kmにわたって続く杉並木で、松平正綱が日光東照宮鎮座の後に、紀州熊野から杉苗を取り寄せ、当初約5万本植樹して寄進した。正綱は家臣を植栽のために日光に派遣し、苗木は日光神領の農民に育てさせたと言われる。正綱はその後も、日光神領の拡大とともに、3里(約11.8km)、7里(約27.5km)と、...
写真提供:栃木県
雲竜渓谷の氷瀑 ( 栃木県 日光市 )
稲荷川の上流、女峰・赤薙山の谷間にあり、渓谷をはさんで多くの滝がかかる。 厳冬期には谷一面巨大な氷柱が出現する。高さは100mにもおよび、横にもさまざまな形に変化して、氷の殿堂などと呼ばれている。年により気温が変化し氷瀑の大きさも変化するが、2月第一週がふだんでも最大に成長する。 上級登山者には氷壁登攀地として有名で...
写真提供:日光市
奥鬼怒温泉郷 ( 栃木県 日光市 )
奥鬼怒温泉郷は、日光市川俣にある温泉の総称であり、鬼怒川の源流部付近にある温泉地である。加仁湯、八丁の湯、日光澤温泉、手白澤温泉の4つからなる。鬼怒沼、根名草山、尾瀬への登山客の利用も多い。 なお、女夫渕から先はマイカー通行が禁止されており、宿泊する宿の送迎バス、または徒歩で向かうことになる。

日光山中禅寺立木観音 ( 栃木県 日光市 )
坂東札所三十三観音第十八番札所。日光開山の祖、勝道上人が784年に建立した。 中禅寺はもと二荒山神社中宮祠の別所(別当寺)で、その境内にあったが、1902(明治35)年の山津波による倒壊後、日光修験の修行地の一つであった歌が浜の現在地に再建された。本堂には、高さ4.8mの木造千手観音立像(立木観音)、脇侍として源頼朝が戦勝祈願...
写真提供:宇都宮二荒山神社
宇都宮二荒山神社 ( 栃木県 宇都宮市 )
二荒山神社は「下野国一の宮」であり、宇都宮はこの神社の門前町として発展した。神社の別称であった「宇都宮」が、市名の由来である。いまも神社は宇都宮一の繁華街にあり、市の中心部に建つ。大鳥居を通り抜け、石段をのぼり神門をくぐると、境内には拝殿・本殿・神楽殿などが立ち並ぶ。これらの社殿は1868(慶応4・明治元)年の戊辰戦争に...
高勝寺 ( 栃木県 栃木市 )
JR両毛線岩舟駅の北方、約200mの岩船山*山頂にある。770(宝亀元)年、弘誓坊明を願という地蔵信仰に厚い僧が、夢のお告げにより、生身の地蔵菩薩を求めて岩船山に登ったところ、夢の通りに地蔵を拝したとして、堂宇を建てたのが始まりという。入口の山門は弁柄塗装の楼門で、1742(寛保2)年の再建、棟高12.95mは県内一の大きさ。山上には...

写真提供:足利織姫神社奉賛会
足利織姫神社 ( 栃木県 足利市 )
足利織姫神社は織姫山の中腹にある。参拝するには229段の石段を直登する。足の不自由な方は車 で大きく裏手に回って山頂まで行ける。山名は古くは「機神山(は たがみやま)」・「魚住山(うおずみやま)」などと呼ばれていた。 1879(明治12)年、足利織物業の繁栄を祈って、市内の八雲神社境内から 遷宮された。織物の神八千々姫命と天...
栗田美術館 ( 栃木県 足利市 )
故栗田英男(1996(平成8)年没)が、伊万里・鍋島に限定して収集した2,000点あまりにのぼる作品を収蔵する、世界最大級の陶磁器美術館である。約8万m2の敷地内には、陳列館だけでも、本館、歴史館、資料館、陶磁会館など数々の展示館が立ち並ぶ。代表作品として、国の重要文化財の鍋島色絵岩牡丹植木鉢文大皿がある。常時、600点...
惣宗寺(佐野厄除大師) ( 栃木県 佐野市 )
開基は藤原秀郷と伝えられ、佐野城跡のある春日岡にあったが、1600(慶長5)年、佐野城築にあたり現在の地に移転した。 境内は広く、本堂、鐘楼など古い堂宇が建つ。境内の北西部に東照宮が祀られ、本殿・拝殿・唐門・透塀が県の文化財に指定されている。江戸時代後期の建築様式が随所にうかがえ、なかでも欄間、妻飾りの装飾彫刻は見事で...
写真提供:(一社)栃木市観光協会
とちぎ秋まつり ( 栃木県 栃木市 )
栃木に山車が誕生したのは、1874(明治7)年、県庁内で行われた神武祭典のとき。倭町3丁目が東京日本橋の町内から購入した静御前の山車と、泉町が宇都宮から買い求めた諫鼓鶏(かんこどり)の山車を参加させたのが始まり。1893(明治26)年に、新調した三国志の人形山車が3台、ほかに神武天皇の人形山車が加わり、6台となった。1906(明治39...
写真提供:那須塩原市
明治時代の別荘建築 ( 栃木県 那須塩原市、矢板市 )
那須野が原の開拓は、印南・矢板らの「那須疏水の開削」と結社農場、青木、松方、大山ら政府高官や旧藩主などによる大農場によって進められた。 旧青木家那須別邸:明治時代の外交官青木周蔵が、1881(明治14)年の青木開墾(青木農場)開設後、1888(明治21)年に建築した。その後、1909(明治42)年に大改築をして、現在の姿になる。白...
殺生石(賽の河原) ( 栃木県 那須町 )
温泉神社に隣接する殺生石園地には亜硫酸ガスや硫化水素など有毒ガスが噴出し、硫黄の香りが立ち込め草木もない荒涼とした風景が広がる、賽の河原と呼ばれる場所がある。 その園地の奥には能や謡曲の題材になり、芭蕉が「おくのほそ道」でも訪れ、九尾狐伝説にまつわる史跡の「殺生石」がある。 九尾狐伝説とは、中国・インド・日本を...

写真提供:片品村観光協会
アヤメ平 ( 群馬県 片品村 )
鳩待峠の東約4km、標高1,900m近い高地に開けた高層湿原*。アヤメ平の名があるがアヤメはなく、葉がアヤメに似ているキンコウカが8月に黄色の花を咲かせる。大小無数の池塘が点在し、かつては地上の楽園と歌われたが、ハイカーに荒らされてしまった。近年、木道以外は立入禁止とし、東京電力*を中心に回復作業を進めてきて、もとの姿を取り...

丸沼・菅沼 ( 群馬県 片品村 / 栃木県 日光市 )
沼田市からの国道120号線、金精峠トンネル手前約1kmの間に2つ並ぶ湖沼。金精峠側が菅沼で下流に丸沼がある。2つの湖沼は日光白根山の溶岩による堰止湖。 1931(昭和6)年、丸沼と下流の大尻沼との間に東京電力のダムが造られ、丸沼は水位が28m上昇したので、南北1.2km、東西500m、面積0.45km2と広くなった。満水時の標高1,428m...

至仏山 ( 群馬県 片品村 )
尾瀬の南西にそびえる山で、標高2,228m、燧ケ岳とともに尾瀬を代表するシンボリックで雄大な山。至仏山の名前は渋沢沿いにしか登る道がなく、その「しぶっさわ」から来たのではないかともいわれている。 尾瀬ヶ原から見ると南北の稜線がなだらかな線を描き、ほぼ左右対称の女性的なピラミッド型である。しかし西側は対照的に、岩壁の厳し...

日光白根山 ( 群馬県 片品村 / 栃木県 日光市 )
金精峠の南西、栃木・群馬両県境にそびえる活火山で標高2,578m、那須火山帯に属する。第3紀に噴出した流紋岩の上に、小規模の火山活動をくり返して、橄欖(かんらん)石や輝石安山岩から成るドーム状の奥白根山ができたといわれる。また奥白根の溶岩が北西に流れて丸沼・菅沼、東に流れて五色沼などの堰止湖を造りだした。 この山の名前は...

写真提供:観光ぐんま写真館
尾瀬ヶ原 ( 群馬県 片品村 / 新潟県 魚沼市 / 福島県 檜枝岐村 )
尾瀬沼の西約4km、至仏山・燧ケ岳・景鶴山・アヤメ平など2,000m級の山々に囲まれた盆地状をなす標高1,400m内外の高地に、東西約6km、南北約2kmにわたって広がる本州最大の湿原で、尾瀬を象徴する存在である。牛首と沼尻川を境に、下田代・中田代・上田代に分かれている。尾瀬ヶ原ははじめ燧岳溶岩流が只見川をせき止めてつくった古尾瀬湖とい...

武尊山 ( 群馬県 川場村 / 群馬県 みなかみ町 / 群馬県 片品村 )
群馬県北部にそびえるコニーデ型火山*。みなかみ町と片品村、川場村の境界に位置し、標高2,158mの沖武尊が主峰である。 山の名は日本武尊(やまとたけるのみこと)*の故事にちなんでついたといわれ、沖武尊山頂と前武尊に日本武尊の銅像が立っている。北アルプスの穂高岳と「ほたか」の発音がおなじため、上州武尊(じょうしゅうほたか...

写真提供:一般社団法人 草津温泉観光協会
草津温泉 ( 群馬県 草津町 )
白根火山の東麓、標高1,200m付近の小盆地とその周辺に温泉街・ホテル街が形成されている。古くから湯治温泉として全国的に有名で、西の有馬温泉に対し、東国一の名湯といわれてきた。恋の病を除いてはどんな病気でも治るといわれている。現在では、志賀・草津高原ルート(国道292号線)の開通、スキー場やゴルフ場、コンサートホールなどの整...

白根山(草津白根山・本白根山) ( 群馬県 草津町 )
上信越国境部にそびえ、本白根山(2,171m)と北側にある逢ノ峰(2,110m)、草津白根山(2,160m)からなる成層活火山である。文献に初めて現われる1783(天明3)年から現在まで、しばしば噴火活動を繰り返し、爆発のたびに草津の湯温が激変、また火山弾が火口付近に降り注いだこともあった。 草津白根山山頂部は一木一草もないむき出しの岩...

西の河原(露天風呂) ( 群馬県 草津町 )
草津温泉街の西はずれ、広い河原の多くの場所から温泉が湧き出ている所で、温泉水が川をなして流れ、滝や池(瑠璃の池、琥珀の池など)となり、天然の露天風呂を作り出している。古くは、鬼の泉水と呼ばれ、「湧き出る湯口はわれも恐ろしや、鬼の茶釜の湯土産噺」と怖がられた事もある。 流れや湯の池は泉質によって白濁、または緑色をお...

写真提供:(C)林喜代種
草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル ( 群馬県 草津町 )
1980(昭和55)年、ヴァイオリニスト豊田耕児氏を音楽監督、音楽評論家遠山一行氏を実行委員長として始められた音楽祭。群馬交響楽団のレベルアップを目的に企画されたという。毎年テーマを決めて開催されている。音楽家を目指す人たちの学びの場、人材育成の場として夏期2週間、テーマに合わせて世界的な芸術家を招き講習会を行う。 また...

荒船山 ( 群馬県 下仁田町 / 長野県 佐久市 )
下仁田町の南西端、長野県境に接し頂上周辺が平らな形状の山。山頂は南側にある経塚山で1,423m。 かつて溶岩が平らな地面に流れて固まり、その後の隆起と侵食によって一番固い溶岩台地が残ったため長い平らな稜線をもつ不思議な形をした山ができたという。 下仁田ジオパークの見どころのひとつにもなっており登山道中では、溶岩噴出前...

写真提供:一般社団法人 四万温泉協会
四万温泉 ( 群馬県 中之条町 )
中之条町北東部、四万川上流の三方を山に囲まれた渓流沿いの標高700mの高地にある。四万温泉の名前は、四万の湯が『四万(よんまん)の病を癒す霊泉』であるとする伝説*がある。また古文書によると1600年代初期の江戸時代には温泉宿があり、 湯治客は江戸からも来遊があったと記されている。 源泉は全42ヶ所で、3ヶ所が堀さく源泉、39ヶ...

尻焼温泉 ( 群馬県 中之条町 )
長野原草津口から白砂川沿いに上流に向かい約16km、長笹川渓流沿いの山峡にある尻焼温泉の「川の湯」は、川そのものが大きな露天風呂となっている。痔の治療に特効があるといわれ、かつては、河原に穴を掘って臀部だけ湯につかる入浴療法や、温まった石の上に腰かける治療が行われていたため、「尻焼」と名付けられたという。現在は川をせき...

野反湖 ( 群馬県 中之条町 )
群馬、新潟、長野の県境に位置し、周囲10km、標高1,513mにある山上の人造湖で、湖水は越後の魚野川、信濃川へそそいでいる。発電用に作られた人造湖。 外周には弁天山・八間山・高沢山などの山々がゆったりとそびえ、なだらかな草原状の裾野が乳緑色の湖面に落ち、明るく開けた高原地帯となっている。 6月にはレンゲツツジ、7月にはノ...

芳ケ平 ( 群馬県 中之条町 )
2015(平成27)年5月にラムサール条約*に登録された、中之条町と草津町にまたがる「芳ヶ平湿地群」の中でも中心となる湿原。草津白根山中腹の標高約1,800mに広がり、白根山の荒涼とした景観とは対照的に、高山植物が豊富に生育する緑豊かな湿地帯である。 江戸時代、草津から善光寺に抜ける街道の裏道を通り、わざわざ芳ヶ平、渋峠を経由...

チャツボミゴケ公園 ( 群馬県 中之条町 )
中之条町の最奥部、入山地区の西端に位置している。穴地獄と呼ばれている泉から湧き出る暖かめの鉱泉が強酸性のため、こうした環境を好んで生育するチャツボミゴケ*が群生したものである。 入山地区はかって群馬鉄山と呼ばれ、国内第2位の生産量の鉱山として栄えた歴史がある。この地から鉄鉱石が索道と吾妻線経由で高崎へと運ばれていた...

湯の丸高原レンゲツツジ群落 ( 群馬県 嬬恋村 / 長野県 東御市 )
湯ノ丸山の地蔵峠付近標高1,600~2,100m前後とその山麓の高原に、6月下旬約60万株のレンゲツツジが開花する。レンゲツツジは群馬県の県花である。 この群落は明治時代に始まった牛の放牧により、湯の丸地域が草原化してできたといわれる。牛はレンゲツツジを食べないため、草原一面がレンゲツツジの花畑になったという。1956(昭和31)年...

写真提供:観光ぐんま写真館
万座温泉 ( 群馬県 嬬恋村 )
草津白根山と万座山との谷間にある標高1,800mの温泉。ツガ・ダケカンバの原生林に囲まれ、静かな高原保養地といった趣で、温泉街の雰囲気はない。志賀・草津・長野・軽井沢とは国道・有料道路で結ばれている。 土器をはじめとする出土品から、弥生時代にはこの地に人の住居があったと推測されている。温泉としての記録は古く*、1560年代...

鎌原観音堂 ( 群馬県 嬬恋村 )
1783(天明3)年の浅間山大噴火の時に、鎌原村(現在の嬬恋村の一部地域)を埋め尽くした浅間山噴火土石なだれから残った唯一の建物。大噴火の土石なだれは、時速100km以上のスピードで火口から12km離れた鎌原村を襲い、村は5~6mの深さに埋もれた。 災害前の観音堂は村から石段で50段上がった場所にあった。その階段を駆け上がって助かっ...

嬬恋村のキャベツ畑 ( 群馬県 嬬恋村 )
嬬恋村の広域農道「つまごいパノラマライン」の沿道に展開する約3,000haのキャベツ畑。標高700~1,400mの高冷地で栽培されており、夏の昼夜間の温度差が大きいため美味しいキャベツができる。キャベツの作付面積を夏の嬬恋村のキャベツ農家戸数で割ると、農家1軒でおよそ5haとなる。これは東京ドーム1個分の面積にあたる。 7~10月が出荷...

谷川岳 ( 群馬県 みなかみ町 / 新潟県 湯沢町 )
群馬・新潟の県境にある谷川岳は標高1,977m、オキノ耳とトマノ耳*の2つのピークを持つ。 太平洋側と日本海側を分ける脊梁山脈にあたり、北西の季節風が吹きつける豪雪地域である。そのため、新潟県側は穏やかだが、群馬県側は雪崩による浸食作用のため荒々しい山相をなし、東側斜面にはマチガ沢・一ノ倉沢・幽ノ沢などの急峻な谷が湯桧曽...

宝川温泉 ( 群馬県 みなかみ町 )
藤原湖北端から、利根川の支流宝川を1kmさかのぼった所にある。湯は宿の庭の中を流れていく宝川の渓畔に湧き、毎分1,800リットルの湧出量を誇る。川の両岸の露天風呂は4つあり、1つは婦人専用、総面積470畳の広さ。旅館は山峡の一軒宿。 大正時代に湯治場として宿泊施設が作られ、1945(昭和20)年以降、周辺のダム開発で道路と電気が通っ...

奥利根湖(矢木沢ダム) ( 群馬県 みなかみ町 )
みなかみ町の利根川最上流部に位置するダムと湖。1967(昭和42)年完成の矢木沢ダムによりできたのが人造湖の奥利根湖で、洞元・藤原と続く奥利根三湖の一番上流にあり、三湖中最大の湖。 主ダム部はアーチ式コンクリートで、堤高131m、堤頂長352m。洪水吐き部は重力式コンクリート、透水層止水対策部はロックフィル式と、3タイプで構成さ...

照葉峡 ( 群馬県 みなかみ町 )
利根川の上流部、湯ノ小屋沢川に大小11の滝がおよそ5kmにわたって点在する。滝の名前は俳人 水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)*が命名したもので、「山彦(やまひこ)の滝」、「翡翠(ひすい)の滝」、「木精(こだま)の滝」など。奥利根ゆけむり街道(県道63号線)の湯の小屋温泉から上流部にかけての道路沿いであるが、駐車場や散策道...

黒瀧山不動寺 ( 群馬県 南牧村 )
標高870mの黒瀧山に立つ山岳信仰の霊場。上州南牧谷の奥深い黒瀧山の岸壁から滝しぶきの舞う所にあり、山門から不動堂、本堂、黒瀧泉、そして開山堂とつづく。江戸時代前期の1675(延宝3)年、徳川綱吉が帰依した潮音禅師によって中興開山された。 行基作と伝わる不動明王を安置し、厄除けの不動の霊場として千余年の歴史を重ねる静寂幽玄...

碓氷峠鉄道施設 ( 群馬県 安中市 )
横川駅から鉄道文化むら、旧丸山変電所、峠の湯、めがね橋(碓氷第3橋梁)を経て熊ノ平まで、6kmの信越本線アプト式鉄道*時代の廃線跡「アプトの道」周辺の鉄道施設群。線路や枕木を取り除き、歩きやすい道として整備されており、第1号から第10号までのトンネル、めがね橋を含め3つの橋梁がある。 旧丸山変電所は碓氷線電化のため、1912...

写真提供:つつじが岡公園
つつじが岡公園のつつじ ( 群馬県 館林市 )
館林駅の東方約4kmにある。「館林のつつじ」とはここのつつじのことで、俗に花山と呼ばれる城沼南岸一帯の丘陵地である。12.93haの敷地は、ヤマツツジをはじめ、キリシマツツジ・クルメツツジなど100余品種、約1万株のつつじが咲き誇る。 この公園のつつじは1605(慶長10)年、初代館林藩主の榊原康政*が側室「お辻」の霊を弔うためつつじを...

茂林寺 ( 群馬県 館林市 )
茂林寺前駅の南東約300m、杉の茂った平地にある。1426(応永33)年開山の末寺18カ寺を有する大寺で、むかし話で登場する「分福茶釜」*があるので有名。山門を入ると、ユーモラスな22の大きな陶製の狸が両側にずらりと並んで迎えてくれる。本堂内の宝物室には分福茶釜を初め狸のコレクションや寺宝が展示されている。 茂林寺沼とその周辺は...

写真提供:高崎市教育委員会
上野三碑(金井沢碑・山上碑・多胡碑) ( 群馬県 高崎市 )
群馬県下にある金井沢碑・山上碑・多胡碑という平安時代より古い3つの碑をいう。それぞれの碑には覆堂が立っているが、一定時間の照明でのぞき窓から見ることができ、またテープによる解説を聞くことができる。 <金井沢碑> 根小屋駅の南西、小高い丘の中腹に立つ。高さ1.1m、幅0.7m。碑面には726(神亀3)年、群馬県下賛郷の豪族三家の...

高崎白衣大観音 ( 群馬県 高崎市 )
1936(昭和11)年、高崎市の実業家井上保三郎氏*によって、高崎歩兵第一五連隊戦没者慰霊供養、観光高崎の建設を目的に、白衣大観音像が建立され開眼法要された。 高さおよそ42m、9階に分かれた内部には20体の仏像が安置され、上部まで階段で胎内巡りができる。上部からは三国山脈、秩父・八ガ岳、赤城の山々が眺望できる。参道にはみや...

写真提供:少林山達磨寺
少林山達磨寺 ( 群馬県 高崎市 )
市の西、鼻高丘陵の北斜面にある。その昔、行基菩薩作とされる観音菩薩をお祀りする御堂があった。江戸時代に碓氷川の氾濫の折流れ着いた光り輝く香木で、一了居士が達磨大師坐像を彫刻し安置したのが達磨寺となる由縁である。 1697(元禄10)年に水戸光圀公の帰依された心越禅師を開山と仰ぎ、前橋城の裏鬼門を護る寺として、第5代前橋城...

榛名湖 ( 群馬県 高崎市 )
榛名火山のカルデラに生じた火口原湖である。大きさは東西1km、南北1.3kmで、勾玉形をしている。伊香保の沼ともいわれ、湖面に榛名富士を映して静まる美しさは歌(湖畔の宿*)にも歌われてきた。湖の周りはいくつかのピークを持つ榛名山に囲まれており変化に富む。湖岸には一周道路がつけられ、湖畔には桜・ツツジ・キスゲなどが春から夏に...

榛名山 ( 群馬県 高崎市 / 群馬県 東吾妻町 / 群馬県 渋川市 )
妙義山・赤城山とともに上毛三山の一つ。那須火山帯に属する複式火山である。火口原は東西4km、南北2km。ほぼ中央に中央火口丘の榛名富士と火口原湖の榛名湖があり、これを取り巻いて相馬山(そうまさん)・烏帽子岳・鬢櫛山(びんぐしやま)・掃部ヶ岳(かもんがたけ)・天目山などの外輪山が並ぶ。最西端にある掃部ヶ岳が最高峰1,449mであ...

榛名神社 ( 群馬県 高崎市 )
榛名湖南西約2kmの榛名山中腹にある。延喜式内社で創立は用明天皇(585~587年)のころと伝わる古社。修験者の霊地として古くから榛名山信仰の参詣者を集め栄え、中世以降は神仏習合し満行宮とも称して、上野寛永寺の管理下に繁栄を極めた。 境内は約15万m2、老杉・奇岩・渓流に囲まれて山気に満ち、社殿は屹立する巨岩の間に...

榛名梅林 ( 群馬県 高崎市 )
生産量、栽培面積は東日本一。明治の中期頃から栽培が始まり、桑園や水田からの転作作物として昭和50年代に入ってから急速に増え、東日本一の梅の産地となった。400haの広大な土地に、約12万本の梅が植えられている。中でも上里見にある榛名梅林には7万本の梅がある。3月の第3日曜日、榛名梅林に囲まれた町総合文化会館エコールでは、「はる...

写真提供:高崎市教育委員会
保渡田古墳群 ( 群馬県 高崎市 )
高崎市保渡田・井出にまたがる田園地帯の中に点在する3つの大きな丘が保渡田古墳群で、八幡塚古墳、二子山古墳、薬師塚古墳の総称。3つの古墳は、約1,500年前の豪族が葬られた墓で、いずれも墳丘長約100mの前方後円墳。広大な二重の堀を巡らし、多量の埴輪を立て並べていたという。 八幡塚古墳・井出二子山古墳を中心とする地域は「上毛野...

写真提供:渋川伊香保温泉観光協会
伊香保温泉 ( 群馬県 渋川市 )
榛名山の北東中腹、標高約700mの高所にあり、古くから上州の名湯として知られる。温泉街は山間の急斜面に造られ、階段式の道路やヒナ段状に立ち並ぶ旅館や店舗、たちこめる湯の香りなどが独特の湯の町情緒をかもしだしている。春の新緑・ツツジ、夏の避暑、秋の紅葉など、どの季節も楽しめ、近くの榛名山・榛名湖、榛名神社、水沢観音など様...

赤城山 ( 群馬県 前橋市 / 群馬県 渋川市 / 群馬県 沼田市 / 群馬県 桐生市 )
関東平野の北西端にそびえ、榛名山・妙義山とともに上毛三山の一つとして知られる二重式火山。赤城山という単独の山はなく、最高峰1,828mの黒檜山をはじめとする外輪山と中央火口丘の地蔵岳を合わせた総称。赤城山は成属火山*で、1251(建長3)年の第4次爆発を後に火山活動を中止した。外輪山と地蔵岳の間には、大沼と小沼が静かに水をたた...

写真提供:公益財団法人 前橋観光コンベンション協会
赤城南面千本桜 ( 群馬県 前橋市 )
三夜沢赤城神社の南東、標高430m~540mにある桜並木。近年一段と立派になり、県内有数の桜の名所となった。 樹齢60年近いソメイヨシノが市道に沿って約1,000本、延長約1.3kmにわたって咲く。満開時には桜のトンネルとなる。 桜まつり期間中(4月上中旬)は、郷土芸能・地元のグルメや特産品などのふれあい物産市や、ステージパフォーマ...

大沼・小沼 ( 群馬県 前橋市 )
赤城山の山頂部、黒檜山、地蔵岳、駒ケ岳などの外輪山に囲まれた標高1,350m付近には、カルデラ湖の大沼と高層湿原*の覚満淵、その南東1,470mに長七郎山の火口湖*の小沼が並んで位置する。大沼と小沼間は1km程度であり、トレッキングや自転車で回ることができる。 大沼は周囲4km、南岸から東岸には旅館街や土産屋がならび、赤城山の観光...

写真提供:ぐんまフラワーパーク
ぐんまフラワーパーク ( 群馬県 前橋市 )
赤城山の南麓、標高300~350mにある花と緑の公園。18.4haの敷地内に1年を通して手入れされた花々を見ることができる。 園内には様々な施設があり、特にゲートの正面にある「フラトピア大花壇」では季節ごとに花を植え替えている。その他バラ園、サザンカ園、ショウブ園、ツツジ園などの園地があり、またイングリッシュガーデン、熱帯植物...

三夜沢赤城神社 ( 群馬県 前橋市 )
県内外に散在する赤城神社約300社の総本社のひとつといわれる神社である。杉木立ちの中に、上野国二の宮*と称されるこの社がある。社伝によると、古代、豊城入彦の命の子孫である上毛野君という氏族の創祀といわれ、戦国時代には、上杉・北条・武田の3氏を始め各武将の崇敬を集め栄えた。 本殿・中門などは県の重要文化財。神社の北裏2km...

金山城跡 ( 群馬県 太田市 )
太田駅の北2.5kmにあり、1469(文明元)年に新田一族の岩松家純(いわまついえずみ)*が築城した山城である。国指定史跡。石垣を多用し、山上に軍用貯水池の日ノ池・月ノ池をもつなど難攻不落といわれ、上杉謙信、武田勝頼などの10数回に及ぶ攻撃にも落城しなかった。関東では代表的な山城の一つとされる。岩松氏を下剋上で退けた、横瀬氏改...

大光院 ( 群馬県 太田市 )
太田駅の北西約1.8kmにあり、「子育て呑龍さま」と広く呼び親しまれている。1611(慶長16)年、徳川家康が先祖とした新田義重の旧跡を訪ねて寺を建て、呑龍上人(どんりゅうしょうにん)*を招いたと伝えられる。呑龍上人は、当時農民の間で行われていた赤子の間引を悲しみ、農民を説得し子育てにつとめたので子育呑龍と慕われるようになった。...

桜山公園の冬桜 ( 群馬県 藤岡市 )
藤岡市南東部の鬼石の西方、標高591mの桜山*山頂にある47haの自然公園。山頂付近の急斜面をうめる約5,000本の冬桜*は、1908(明治41)年3月に植栽されたもので、国の名勝・天然記念物に指定されている。雪化粧した武甲山などの山容を望んでのお花見は11月上旬~12月中旬。 山頂の碑文によると、1906(明治39)年、国有林野を村有の公園...

写真提供:富岡市
妙義山 ( 群馬県 富岡市 / 群馬県 安中市 / 群馬県 下仁田町 )
群馬県の南西部にあり、赤城山・榛名山とともに上毛三山の一つに数えられている。那須火山帯浅間火山群の一つ。山全体が浸食を受けやすい輝石安山岩と凝灰角礫岩でできているので、石門群や大砲岩などの奇岩が多い。 山は3峰に分かれ、安中市側から白雲山・金洞山・金鶏山と三角形を描くようにそびえる。白雲山は妙義神社の背後にあり、山...

妙義神社 ( 群馬県 富岡市 )
妙義山の主峰、白雲山(1,104m)の中腹にある。今からおよそ1500年前、宣化天皇の時代に創建されたと伝わる古社。春には参道や神社境内にある樹齢200年余りのしだれ桜が見事である。樹木がうっそうと茂る奥深い境内には、色鮮やかなお堂が立ち並ぶ。 黒漆塗り、権現造り*の本殿をはじめ各社殿とも江戸時代の建築様式の壮麗なもの。また関...

小幡の町並み ( 群馬県 甘楽町 )
城下町小幡は、室町時代に小幡氏の拠城であった国峰城が築かれ、江戸時代に織田氏、松平二万石の陣屋町として栄えたところで、武家屋敷の町並みを今に残している。織田信長の次男信雄(のぶかつ)*が小幡に城下町を築く際に作られた庭園は楽山園として残されており、現在では当時の姿に復元された。 小幡地区を南北に流れる雄川堰は、古...

写真提供:久喜市
久喜提燈祭り「天王様」 ( 埼玉県 久喜市 )
久喜提燈祭り「天王様」は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼である。1783(天明3)年の浅間山の大噴火で、桑をはじめ夏作物が全滅したことによる、生活苦、社会不安などを取り除くため、祭礼用の山車を曳き廻して豊作を祈願したのが始まりと伝えられ、230余年の歴史と伝統を誇る祭りである。 祭りは毎年7月12日と18日に行われ、町内か...

熊谷うちわ祭 ( 埼玉県 熊谷市 )
「熊谷うちわ祭」は、八坂神社の祭礼で、京都八坂神社の「祇園祭」の流れを受け、江戸中期(1750年頃)より始まったとされる。 7月20日から22日の3日間であるが、それぞれ違った催しになる。鉦と太鼓の音も勇ましい熊谷囃子を奏でながら豪華な 12 台の山車と屋台が中心市街地を巡行し、20日には神輿の渡御がある。22日の夜には、全町12台...

写真提供:妻沼聖天山歓喜院
妻沼聖天山歓喜院 ( 埼玉県 熊谷市 )
熊谷市の真北、妻沼集落の北西にある。『源平盛衰記』や歌舞伎の『実盛』物語で知られる斎藤実盛が、 1179(治承3)年に聖天堂を創建したのに始まり、次いで実盛の次男実長(阿請房良応)が別に歓喜院を開山したという。明治初年、一山すべて歓喜院所属となったが、中心は聖天堂である。 聖天堂の本尊大聖歓喜天は弘法大師が唐より仏法の...

さきたま古墳公園 ( 埼玉県 行田市 )
市の南東部、県名発祥の地に所在する古墳群。二子山*・鉄砲山・稲荷山古墳など8基の前方後円墳と1基の円墳、日本最大級の円墳である丸墓山古墳*、方墳の戸場口山古墳などの総称。もとは近辺に多数の小円墳があったことが確認されており、関東地方でも有数の古墳群といえる。これらは武蔵国造の一族の墳墓と考えられている。 稲荷山古墳...

写真提供:喜多院
喜多院 ( 埼玉県 川越市 )
川越大師として親しまれている天台宗の関東総本山で、市街北東部にある。830(天長7)年、慈覚大師の草創になり、1588(天正16)年、天海僧正が来住して寺運が開けた。しかし 1638(寛永15)年の川越大火では山門を残し、すべて灰と化した。 喜多院には江戸城内の建物の遺構である客殿・書院・庫裏などが残るが、これらは大火のあと徳川家...

川越まつり ( 埼玉県 川越市 )
川越まつりは、川越の総鎮守氷川神社の祭礼行事に由来する。1648(慶安元)年当時の藩主松平信綱が神輿と獅子頭、太鼓など祭礼用具を奉納したのをきっかけに祭りが始められたという。1698(元禄11)年、現在の元町2丁目からはじめて踊屋台が出て以来、年々盛大になり、天保年間(1830~1844年)には当時の十カ町すべての山車に上に人形をのせ...

鉢形城跡 ( 埼玉県 寄居町 )
鉢形城は、荒川の断崖と深沢川の渓谷に囲まれた自然の要害の地に建てられた。戦国時代を代表する平山城であり、関東屈指の名城であった。築城には諸説あるが、1476(文明8)年に長尾景春が築いたとする説が有力。北条氏邦のときに現在の規模まで拡大された。しかし豊臣秀吉の天下統一が進み、1590(天正18)年、前田利家、上杉景勝らの大軍の...

両神山 ( 埼玉県 小鹿野町 )
標高1,724m。深田久弥選定の日本百名山の一つ。平らな山稜をつなぐ秩父の山々のなかで、ギザギザの特色ある岩稜を刻むこの山は遠くからでも一目でわかる。 古く日本武尊(やまとたけるのみこと)*が足跡をしるし、役行者も登山したと伝わり、修験の山としても信仰されおり、以前は白装束、手甲脚絆で登る信者も多かった。伊弉諾・伊弉再...

写真提供:宝登山神社
宝登山神社 ( 埼玉県 長瀞町 )
今から1900年ほど前、日本武尊(やまとたけるのみこと)*が東征の帰途、山容の美しさに惹かれ山頂を目指すと山火事に遭遇し、神犬(山の神の使い)の助けを得て、無事に宝登山山頂に神霊を祀った事が、宝登山神社創建の始めと伝えられる。ご神徳は火防盗賊除、諸難除として高く、多くの参拝者で賑わう。 現在の社殿は1874(明治7)年に建...

写真提供:三峯神社
三峯神社 ( 埼玉県 秩父市 )
関東の山岳信仰の霊場として知られる。三峰の名称は、景行天皇が訪れた際、妙法ケ岳、白岩山、雲取山の美しく連なることから名づけられたという。 境内は広く、古木に囲まれて色鮮やかな1661(寛文元)年建立の本殿と、1800(寛政12)年建立の拝殿が並ぶ。拝殿前に続く石段の両脇に、樹齢約800年のご神木がそびえる。 創祀は日本武尊(...

写真提供:秩父神社
秩父神社 ( 埼玉県 秩父市 )
秩父市の中心に鎮座する。三峯神社・宝登山神社とともに秩父三社に数えられるこの社は、崇神天皇のころの創始といわれる古社で、明治維新前は秩父妙見宮と称されていた。広い境内に権現造*の本殿・幣殿・拝殿が鎮まり、左甚五郎作と伝えられる龍虎の彫刻をはじめ、社殿には華麗な彫刻が施されている。 日本三大曳山祭のひとつに数えられ...

写真提供:秩父観光協会
秩父夜祭 ( 埼玉県 秩父市 )
京都祇園祭、飛騨祇園祭(岐阜県)と並ぶ日本三大曳山祭の一つで、毎年12月3日を中心に行われている。国の重要有形民俗文化財に指定される高さ平均約6.5m2、重さ15tもある重厚な6台の山車(屋台4基、笠鉾2基)が秩父神社中心に曳き廻され、とりわけ本番の3日は秩父盆地の街並みをこだまする屋台ばやしの太鼓の音が祭りを一層盛り...

和銅採掘遺跡 ( 埼玉県 秩父市 )
「続日本書紀」によると、708(慶雲5)年に「武蔵国秩父郡、和銅を献る」とあり、自然銅(にぎあかがね)を朝廷に献上したとある。貨幣を鋳造した朝廷では宣命を発し、年号を和銅と改めた。和同開珎は長い間わが国最初の貨幣とされていたが、1999(平成11)年の富本銭(ふほんせん)の出土によりその座を譲ることになった。 しかし、富本...

写真提供:高麗神社
高麗神社 ( 埼玉県 日高市 )
JR川越線・八高線の高麗川駅から徒歩約20分。西武線高麗駅からは徒歩約40分。 高麗神社は、奈良時代に創建され、高句麗からの渡来人高麗王若光を主祭神としている。若光は高句麗からの使節として渡来した。朝廷から「王姓(こきしのかばね)」を賜っていることから高句麗の王族出身者と考えられている。716(霊亀2)年に高麗郡が置かれ、...
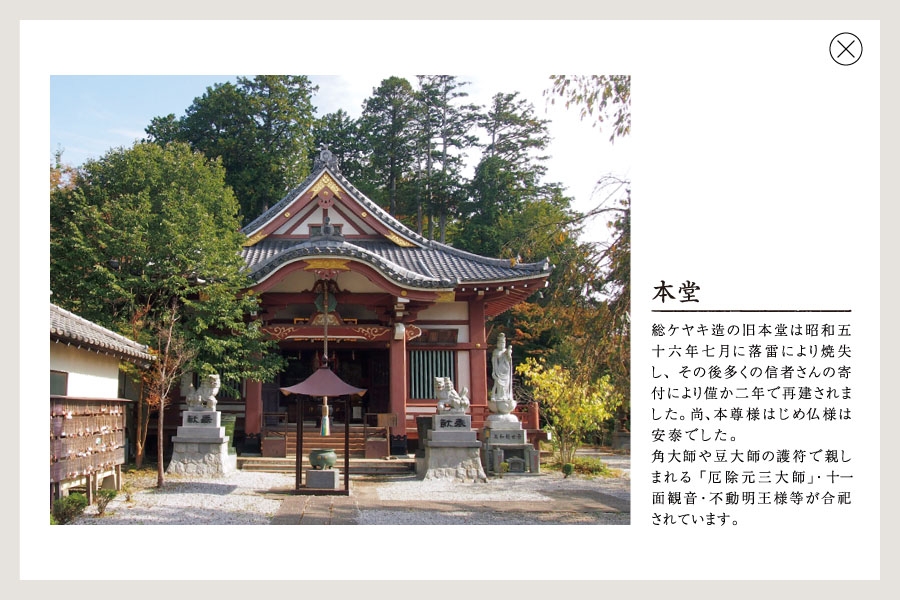
写真提供:子ノ権現天龍寺
子ノ権現天龍寺 ( 埼玉県 飯能市 )
子ノ権現といわれるのは、子の年子の月子の日子の刻に生まれ、911(延喜11)年にこの地に天龍寺を開山した「子ノ聖」を高弟の恵聖上人が祀って天龍寺の境内に権現社の社殿を建立したことに始まる。天龍寺を子ノ権現社の管理をする別当寺とした。 天龍寺の本尊は十一面観世音菩薩で、12年ごとの子の年には子ノ聖の尊像が開帳される。

写真提供:慈光寺
慈光寺 ( 埼玉県 ときがわ町 )
県内最古の寺で坂東三十三ケ所第9番札所。673(天武天皇2)年飛鳥時代に鑑真の弟子釈道忠によって開かれ、鎌倉時代は畠山重忠や源頼朝が篤く帰依したという。 都幾山麓から参道を登る途中の道端に8基の大型青石塔婆がある。さらに登ると古い伽藍が見えてくる。覆堂に入った開山塔、鐘楼などであるが、蔵王堂と釈迦堂は 1985(昭和 60)年...

写真提供:吉見町役場
吉見百穴 ( 埼玉県 吉見町 )
東松山市との境界付近は凝灰岩質砂岩の丘陵で、白い岩肌にたくさんある横穴が、まるで蜂ノ巣のような奇観を呈する。江戸時代には十数個が開口し、不思議な存在であった。 吉見百穴には横穴住居説をめぐる激しい論争の歴史がある。オーストリア公使シーボルトの視察以来有名になり、1887(明治 20)年には当時の東京帝国大学生坪井正五郎ら...

写真提供:日本スリーデーマーチ実行委員会
日本スリーデーマーチ ( 埼玉県 東松山市 )
⽇本スリーデーマーチは、例年3⽇間で延べ8万⼈を超える参加者があり、その数は世界第2位、日本最大のウォーキングイベントである。1978(昭和53)年から第2回までは群⾺県新町で⾏なわれたが、3回⽬以降現在まで、ずっと東松⼭市で⾏なわれている。 開催地が東松⼭市に移ってからは、10kmや5kmの短いコースをつくったり、⼩中学校の⼦供...

写真提供:印西市
吉高の大桜 ( 千葉県 印西市 )
吉高の大桜は、印西市吉高地区にある樹齢300年を超える孤高の一本桜(ヤマザクラ)である。樹高10.6m、根回り周囲6.85m、枝張最大幅25.8mで、開花の時期(4月上旬~中旬)にはピンク色の小山のような景観を見せる。 根元周囲は、所有者である須藤家の祭祀場(氏神)として周辺よりも1m程度小高く塚状に盛土されている。 通常、ソメイヨ...

誕生寺 ( 千葉県 鴨川市 )
日蓮聖人*の生まれた地であることを記念して建立された寺で、日蓮宗の大本山である。1276(建治2)年、日蓮の弟子日家上人が上総興津(かずさおきつ)城主佐久間兵庫守重偵(さくまひょうごのかみしげさだ)の助けを受け建立した。ところが、1498(明応7)年の地震の際に津波で流失し、鯛の浦(妙の浦)を望む地に再建されたが、1703(元禄1...

清澄寺 ( 千葉県 鴨川市 )
清澄寺は、清澄山(きよすみやま)の頂上近くに位置する。天津・小湊周辺には日蓮聖人*にゆかりの寺が多いが、その中でももっともゆかりの深い寺である。 771(宝亀2)年、不思議法師と呼ばれる僧がこの山を開いたといわれる。836(承和3)年、天台宗比叡山延暦寺の中興の祖・慈覚大師円仁師がこの地を訪れ修行したことから、天台宗の寺...

鋸山・日本寺 ( 千葉県 鋸南町 )
鋸山は、富津市と鋸南町の境にそびえ、清澄山地の西端にあたる。文字どおり鋸の歯のような険しい稜線で、昔から東京湾に入る船の目じるしとされていた。頂上から山裾は一気に海へ落ち込んでおり、かつて房州石を切り出した石切場跡が絶壁となって随所に残っている。頂上には、360度の展望が得られる「十州一覧台」(じゅっしゅういちらんだい...

佐原の町並み ( 千葉県 香取市 )
古い家並みを残す佐原は、江戸時代から利根川水運の中継地として発展し、商人の町として栄えた。町中を流れる小野川沿いや香取街道沿いには、江戸時代から昭和期に至るまでの町屋や土蔵、レンガ造りなど情緒漂う建物が多く残っており、国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に選定されている。それらの建物の多くは、現在も活用されてい...

写真提供:香取市
佐原の大祭(八坂神社、諏訪神社) ( 千葉県 香取市 )
「お江戸見たけりゃ佐原へござれ 佐原本町 江戸優り」と唄われた佐原では、商業都市としての財力を背景に、独自の文化を築いた。毎年夏と秋に行われる「佐原の大祭」もその1つである。 佐原にある24地区は、それぞれ山車を有しており、最上部の「大天井」と呼ばれる部分には、日本神話も含む歴史上の人物の人形や鯉・鷹といった動物の藁...

市原ぞうの国 ( 千葉県 市原市 )
市原ぞうの国は、千葉県のほぼ中央に位置する。1989(平成元)年に開園し、敷地面積は3.5haに及ぶ。開園当初は「山小川ファーム動物クラブ」だったが、1996(平成8)年に現在の名称となった。 国内最多飼育数(13頭)を誇るぞうをはじめ、カピバラ、カバなど約100種類の動物が暮らしている。アトラクションも豊富で、サッカーやダンスなど...

写真提供:成田山新勝寺
成田山新勝寺 ( 千葉県 成田市 )
成田山新勝寺は、全国に8ケ所の別院のほか、60以上の分院・末寺・末教会・成田山教会を有する真言宗智山派の大本山である。境内、公園をあわせた面積は22万m2に及び、国指定重要文化財である仁王門、三重塔、光明堂、釈迦堂、額堂をはじめ、多くの堂宇や美術館、図書館などを有する。 大本堂の裏の丘陵地には、16万5,000m...

写真提供:加曽利貝塚博物館
加曽利貝塚 ( 千葉県 千葉市 )
加曽利貝塚は、直径140mの環状である縄文時代中・後期の北貝塚と、直径190mで馬蹄形をした縄文時代後・晩期の南貝塚が8字形に連結した、日本最大級の貝塚である。貝塚やその周辺からは多数の住居跡が発見されており、この地域の中核的な「ムラ」の跡が拡がっている。2017(平成29)年に、縄文時代の遺跡としてはわが国で4箇所目となる国指定特...

写真提供:日本中央競馬会 中山競馬場
中山競馬場の有馬記念 ( 千葉県 船橋市 )
中山競馬場は、日本中央競馬会(JRA)が管理・施行する競馬場である。敷地総面積は約68万m2で、芝コース、ダートコース、障害コースが設定されていて、リフレッシュ工事を実施しリニューアルしたスタンドや馬を間近にみることができるグランプリロード、大型ビジョンが設置されたメディアホール等を有する他、隣接するけやき公苑...

写真提供:一般社団法人 大多喜町観光協会
麻綿原高原のアジサイ ( 千葉県 大多喜町 )
麻綿原高原は、大多喜町の南西部、鴨川市と君津市との境付近にある高原である。勝浦付近の海岸から蜿々と続く九十九里浜を一望でき、また房総の山々を望むことができる。 アジサイの咲く高原として知られる。「天拝園(てんぱいえん)」と名付けられた妙法生寺(みょうほうしょうじ)境内を中心に、2万株ものアジサイが高原の斜面を埋めて...

犬吠埼 ( 千葉県 銚子市 )
犬吠埼は、銚子半島の最東端、太平洋に突き出た岬である。三方を海に囲まれた高さ約20mの海食台地で、複雑な地質構造を示す古生層・中生層からなっている。植物は、コウボウムギ、ハマエンドウ等の砂浜植物のほか、ハチジョウススキ、トベラ等の風衝面群落がみられる。動物は、ウミウ、ウミネコ、オオハム、アビ、カモメ等が生息している。 ...

笠森寺(笠森観音) ( 千葉県 長南町 )
町の北西端に位置する笠森寺は、坂東三十三観音霊場の第31番札所であり、「笠森観音」の名で親しまれている。開創は784(延暦3)年、最澄によると伝えられており、観音堂*は後一条天皇の勅願によって1028(長元元)年に建立されたといわれる。 山頂の巨岩の上に建てられた観音堂は、日本でただひとつの『四方懸造り』として、国の重要文...

写真提供:株式会社マザー牧場
マザー牧場 ( 千葉県 富津市 )
マザー牧場は、東京湾や富士山を望む鹿野山の南西、標高約300mの山頂に位置する観光牧場である。開業は1962(昭和37)年で、250haという広大な敷地内に、牛、馬、羊、アルパカ、ミニブタ、アヒルなど様々な動物が暮らしている。また、場内各所には花畑が広がり、350万本の菜の花、30万本のサルビア、10万株のスイセン、2万5,000株のペチュニ...

写真提供:NEXCO東日本
東京湾アクアライン(一般国道409号) ( 千葉県 木更津市 / 神奈川県 川崎市 )
東京湾アクアラインは、川崎側から約10kmのシールドトンネル、木更津側から約5kmの橋梁、トンネルと橋梁の接続部に設置された人工島(海ほたるパーキングエリア)、および換気用の人工島(風の塔)で構成される、1997年(平成9年)12月18日に開通した自動車専用の有料道路。 東京湾アクアラインは、民間企業と地方自治体、日本道路公団が...

銚子の醤油づくり関連施設群 ( 千葉県 銚子市 )
銚子の醤油づくりは、江戸時代に本格的に始まった。1616(元和2)年に、三代目田中玄蕃(たなかげんば)*が醤油造りを開始した。一方、紀州(和歌山県)出身の初代濱口儀兵衛(はまぐちぎへえ)は、1645(正保2)年に湯浅で行われていた醤油造りの技法を銚子に持ち込み、醤油造りを始めた。 黒潮(暖流)と親潮(寒流)が沖合でぶつかる...

写真提供:大山千枚田保存会
大山千枚田 ( 千葉県 鴨川市 )
大山千枚田は、鴨川市の西部、面積約3.2haの急傾斜地に階段のように連なる、大小375枚の田んぼの総称である。東京から一番近い棚田として知られており、耕地整理が遅れたことで美しい姿が残されている。 大山千枚田は日本で唯一、雨水のみで耕作を行っている天水田である。そのため、動植物も貴重なものが多く生息しており、生物多様性の...

写真提供:(一社)成田市観光協会
成田祇園祭 ( 千葉県 成田市 )
成田祇園祭は、成田山新勝寺のご本尊不動明王の本地仏である奥之院に奉安された「大日如来」に五穀豊穣・万民豊楽・所願成就を祈願する「成田山祇園会」と、成田山周辺の町内が一体となり行われる夏祭りで、約300年の歴史がある。毎年7月初旬に開催される。見事な彫刻や装飾で彩られた10台の山車・屋台と御輿1台が繰り出し、3日間にわたって...

写真提供:大島町役場
三原山 ( 東京都 大島町 )
東京・竹芝客船ターミナルから高速船で1時間45分、夜発の大型船で8時間の大島のほぼ中央に位置し、大島の象徴ともいえる活火山である。現在の大島を形づくる大島火山は、海底火山として誕生し、今から約100万年前に現在の姿になったと考えられている。成層火山*の複式火山で山頂付近は直径3~4kmに及ぶカルデラ*と火口原、それに火口を囲む...

大島のツバキ ( 東京都 大島町 )
東京・竹芝客船ターミナルから東海汽船の高速船に乗れば、最短1時間45分で着ける大島で、「大島町の木」および「大島町の花」に制定されており、伊豆大島を象徴する植物がツバキ。強くしなやかな幹枝と常緑の厚い葉を持つツバキは風、塩や炎に強いため、防風林にも適しており、島特有の強い季節風から守るため家や畑の周囲に数多く植えられた...

写真提供:利島村
利島のツバキ ( 東京都 利島村 )
東京・竹芝客船ターミナルから東海汽船の高速船で約2時間20分の利島は、伊豆諸島の大島と新島の間に位置する。面積は4.04km2、周囲約8kmで、標高508mの宮塚山を中心としたゆるやかな円錐形の島である。約300名の村民が暮らすこの小さな島は、島全体の約8割がツバキに覆われている。面積が小さく資源が限られた利島は水資源が乏し...

写真提供:新島村
羽伏浦海岸 ( 東京都 新島村 )
東京・竹芝客船ターミナルから高速船の直行便で2時間30分の新島港から車で5分、新島の東岸に南北にのびる羽伏浦海岸は、全長約7kmの白砂の海岸である。海岸には、高さ数10mの海食崖が連なり、その前には白い砂浜と青い海が広がる。新島は火山活動によって誕生した流紋岩からなる火山島で、この白砂は黒雲母流紋岩(コーガ石・抗火石*)など...

写真提供:三宅島観光協会
三宅島溶岩地形 ( 東京都 三宅村 )
東京・竹芝客船ターミナルから夜発の大型船に乗り最短で6時間30分の三宅島では、11世紀以降に少なくとも15回の噴火が記録されている。ここ100年間には4回の噴火活動が起きており、ダイナミックな火山地形を形成している。例えば、1940(昭和15)年の噴火では、三宅島中央に位置する雄山の北東山麓の標高200m付近からマグマが噴出して海まで...
御蔵島の黒崎高尾山断崖 ( 東京都 御蔵島村 )
御蔵島は東京から南へ約200km、三宅島の南18kmに位置し、東京・竹芝客船ターミナルから夜発の大型船で最短で7時間25分の場所にある。面積27.5km2、周囲約16km、島の中央部に標高851メートルの御山(おやま)を擁する、お椀を逆さにしたような円形の島。周囲を切り立った断崖に囲まれた御蔵島の中でも島の南西部にある黒崎高尾に形...

御蔵島周辺に生息するイルカ ( 東京都 御蔵島村 )
御蔵島は東京から南へ約200km、三宅島の南18kmに位置し、東京・竹芝客船ターミナルから夜発の大型船で7時間25分の場所にある。面積27.5km2、周囲約16km、島の中央部に標高851メートルの御山(おやま)を擁するお椀を逆さにしたような円形の島である。この島の沿岸海域には百数十頭のミナミハンドウイルカ*が通年にわたり生息し...

写真提供:一般社団法人 八丈島観光協会
西山(八丈富士) ( 東京都 八丈町 )
八丈島は東京の南287kmに位置し、北西部の標高854.3mの西山(八丈富士)と、南東部の標高701mの東山(三原山)の2つの火山が接合して形成されたひょうたん型の島である。八丈島へは、羽田空港から航空機で1時間程度、東京・竹芝客船ターミナルから夜発の大型船で10時間20分でアクセスできる。西山は1万年前に誕生した伊豆諸島最高峰となる円...
小笠原の見送り ( 東京都 小笠原村 )
小笠原諸島は、東京から南約1,000kmの太平洋上に散在する多くの島々の総称で、小笠原群島(聟島、父島、母島列島)、火山列島(硫黄列島)、三つの孤立島(西之島、南鳥島、沖ノ鳥島)から成る。誕生以来、一度も大陸と陸続きになったことがない海洋島であるため、多くの固有種・希少種が生息・生育し、特異な島しょ生態系を形成している。小...
青ヶ島二重式カルデラ火山 ( 東京都 青ヶ島村 )
青ヶ島(あおがしま)は、伊豆諸島に属する火山島*1で、都心から約360km、八丈島からは南に約70kmの位置にあり、有人島では伊豆諸島最南端の島。青ヶ島村の人口は約160人で、日本で最も人口が少ない市町村である。周囲を黒潮の海食によってできた高さ250mもの断崖で囲まれた、外輪山と内輪山のある世界でも珍しい二重(複)式カルデラ構造*...
雲取山 ( 東京都 奥多摩町 )
東京都・山梨県・埼玉県の境をなす標高2017mの山。東京都の最高峰として知られ、奥多摩と奥秩父を結ぶ位置にあり、都心近郊ながら高山を味わえる山として人気がある。山頂付近は針葉樹と草原におおわれ、平地では見られない花々が咲く。 秩父側の三峰山と奥多摩側の石(いし)尾根、そして奥秩父主脈の飛竜(ひりゆう)山方面へと3つの尾...

写真提供:帝釈天題経寺
柴又帝釈天(帝釈天題経寺) ( 東京都 葛飾区 )
京成電鉄柴又駅の東にある。同寺は1629(寛永6)年に下総国中山法華経寺第19世日忠を開山とし、その弟子日栄を開基として開創した。日蓮自刻と伝える帝釈天板*1本尊を祀るところから、一般に柴又帝釈天と呼ばれるようになった。この帝釈天と庚申信仰が結びついたのは、一時所在不明となっていた帝釈天板本尊が、1779(安永8)年の本堂改修の...

写真提供:江戸川区花火大会実行委員会
江戸川区花火大会 ( 東京都 江戸川区 )
江戸川区花火大会は、江戸川区と市川市にまたがる江戸川河川敷において、毎年8月第一土曜日に行われる。1976(昭和51)年に初回の「江戸川区花火大会」が開催された当時は、オイルショック後の不景気が続いていた。そこで、地域を元気づけるため、広い江戸川の河川敷で花火大会を開くという構想が生まれ、地元住民が一丸となって実現した。そ...
富岡八幡宮 ( 東京都 江東区 )
東京メトロ・都営地下鉄門前仲町駅から永代通り沿いに南東へ約300m、左に入ると参道となり、富岡八幡宮の朱塗りの大鳥居が建つ。西北隣には深川公園、深川不動堂*1などがある。境内には重層準型八幡造の本殿などの社殿や七渡神社、住吉社、恵比須社など10指に余る末社がある。菅原道真の末裔とされる僧長盛が1627(寛永4)年に創建*2したと...
清澄庭園 ( 東京都 江東区 )
都営地下鉄・東京メトロ清澄白河駅のA3出口から徒歩約3分、清澄通り沿いに広がる。 元禄年間(1688~1704)のころの江戸の豪商紀伊国屋文左衛門(きのくにやぶんざえもん)*の屋敷があった場所と伝えられ、明治になって三菱の創始者岩崎弥太郎の別邸となった。弥太郎は社員の慰安や貴賓を招待する場所として庭園造成を計画、1880(明治13...

写真提供:富岡八幡宮
深川八幡祭り ( 東京都 江東区 )
富岡八幡宮の例祭で8月15日の前後に行われる。期間中には種々の神祭事*が行われるが、見せ場は神輿*渡御である。3年に1度の本祭りでは、八幡宮の祭神が遷座した鳳輦が渡御し、その翌日に御礼として本社一の宮神輿(現在は担ぎ手の関係で二の宮神輿)と町内の神輿渡御が行われる。その翌年は本社二の宮神輿渡御、本祭りの前年に当たる翌々年...

東京都現代美術館 ( 東京都 江東区 )
1995年(平成7)年に開館した現代美術専門の公立美術館である。東京メトロ清澄白河駅から徒歩9分、江東区三好四丁目の木場公園に隣接している。 収蔵している作品は主に1945(昭和20)年から現代に至る日本、及び一部の国外の作品、約6,000点であり、これらは東京都美術館 (台東区上野公園)から引き継がれた現代美術コレクションに加え...
泉岳寺 ( 東京都 港区 )
都営地下鉄泉岳寺*1駅から西へ約200m、JR高輪ゲートウェイ駅から西へ約450mのところにある。江戸時代には曹洞宗江戸三カ寺*2の一つに数えられた名刹。もともとは、1612(慶長17)年徳川家康が今川義元の菩提を弔うため、桜田門外に創建し、今川義元の孫、門庵宗関(もんあんそうかん)を迎え開山とした。1641(寛永18)年の大火で焼失して...

写真提供:増上寺
増上寺 ( 東京都 港区 )
都営地下鉄御成門駅、大門駅から約350m、JR浜松町駅から650mほどの、芝公園の中央部に位置する増上寺*1は、上野の寛永寺に次ぐ江戸の大寺である。1393(明徳4)年浄土宗8祖聖聡(しょうそう)上人の創建*2で、当初は麹町貝塚(現・千代田区紀尾井町)にあったが、1590(天正18)年徳川家康の江戸入府の際に徳川家の菩提寺となり、1598(慶...

写真提供:国立科学博物館
国立科学博物館附属自然教育園 ( 東京都 港区 )
国立科学博物館に付属する自然緑地で、JR目黒駅から徒歩9分の目黒通り沿いに位置する。 東京23区内で自然林が残っている20万m2の緑地で、明治神宮外苑や上野恩賜公園、代々木公園のような50万m2を越える規模ではないが、日比谷公園(16万m2)や浜離宮公園(25万m2)とほぼ同規模である。...

写真提供:©TOKYO TOWER
東京タワー ( 東京都 港区 )
都営地下鉄赤羽橋駅・ 御成門駅・ 大門駅、東京メトロ神谷町駅それぞれから徒歩5~10分以内にある。JR浜松町駅からは15分。芝公園の西端にそびえる総合電波塔*で、1958(昭和33)年12月23日に完成した。自立鉄塔としてはパリのエッフェル塔より3m高い、333mの世界有数の鉄塔である。 都心での建設にあたっては、地盤が固く広大な場所探し...

写真提供:迎賓館ウェブサイト
迎賓館赤坂離宮 ( 東京都 港区 )
JR・東京メトロ四ツ谷駅の南、徒歩7分。迎賓館赤坂離宮は、1909年(明治42)年、ご成婚を控えた皇太子嘉仁(よしひと)親王(後の大正天皇)の住まいである「東宮御所」として建設された。設計は片山東熊(とうくま)*が担当し、当時の一流の建築家や美術工芸家が総力をあげ、10年もの歳月をかけて完成した日本初の本格的なネオ・バロック様...

写真提供:根津美術館
根津美術館 ( 東京都 港区 )
東京メトロ表参道駅から徒歩8分にある私立美術館。実業家、初代根津嘉一郎(1860~1940)*が蒐集した日本・東洋の古美術品を公開している。 開館は1941(昭和16)年。根津嘉一郎の遺志を引き継いだ二代嘉一郎が嘉一郎の邸宅内に開設した。この場所にはもと河内国丹南藩藩主の高木家下屋敷などがあり、現在は美術館本館のほか、4つの茶室...

写真提供:松岡美術館
松岡美術館 ( 東京都 港区 )
港区白金台にある私立の美術館で、東京メトロ白金台駅から徒歩7分に位置する。松岡地所の創業者である松岡清次郎(1894~1989年)が蒐集した美術品を展示する美術館として1975(昭和50)年に新橋に開館し、2000(平成12)年に現在の白金台に移転した。 松岡清次郎は貿易商・不動産業を営むかたわら日本画や陶磁器等の蒐集を始め、1970年代...

写真提供:東京都庭園美術館
東京都庭園美術館 ( 東京都 港区 )
1933(昭和8)年に建てられた旧朝香宮(あさかのみや)邸を美術館とした施設で、JR山手線の目黒駅から徒歩7分、国立科学博物館附属自然教育園の南に隣接している。約3,500m2の敷地には西洋庭園、日本庭園、芝庭があり、建物自体がアール・デコ様式の作品と言える旧朝香宮邸(本館)2,100m2と、美術展示やイベントの...
表参道ケヤキ並木 ( 東京都 渋谷区 )
JR原宿駅前、神宮橋から青山通りまでのびる原宿のメインストリートには約1.1kmのケヤキ並木となっており、ファッションビルや喫茶店・レストラン、有名なブティック、古美術店などが軒を並べる。 原宿駅は現在の位置より500mほど代々木寄りの林の中で開業した。米・麦・野菜を運ぶ貨物駅で、1両連結の旅客列車が貨物列車の合間に運転され...

殿ヶ谷戸庭園(随冝園) ( 東京都 国分寺市 )
JR国分寺駅から徒歩2分に立地する歴史ある庭園である。大正初期に三菱合資会社の江口定條(後の満鉄副総裁)の別荘*として整備され、当時は随宜園(ずいぎえん)と名付けられていた。1929(昭和4)年に三菱財閥の岩崎彦彌太(ひこやた)*が買収して岩崎家の殿ヶ谷戸別邸となり、1934(昭和9)年に本館建物や回遊式の庭園が完成した。 三...
明治神宮 ( 東京都 渋谷区 )
渋谷区のほぼ中央、JR山手線の西側にひろがる広大な緑の神域につつまれた都内有数の社。毎年の初詣ランキングでは、つねにトップクラスにあり、人気が高い。彦根藩主井伊家の下屋敷があったこの地は、1874(明治7)年に宮内省に買い上げられて南豊島御料地ととなり、井伊家の屋敷を改造縮小して南豊島御用邸あるいは代々木御用邸とされた。明...

原宿 ( 東京都 渋谷区 )
原宿といえば「カワイイ」文化の発祥地であるとともに、「ストリートファッション」の聖地であり、アニメ・キャラクターの「コスプレ」文化を楽しめる町。また、インスタ映えする原宿グルメを扱う店には行列が絶えず、世界からも注目を集めるトレンド発信地となっている。 しかし、「野原の宿」を意味する地名が示すように、江戸時代初期...

代官山 ( 東京都 渋谷区 )
代官山は、渋谷台地の南西端にあり、目黒川から段丘状に土地がせり上がった場所に位置する。ちょうど台地の尾根部分が旧山手通りにあたり、その尾根の崖線に沿うように西郷山公園をはじめ、緑豊かな住宅地が広がっている。渋谷駅から東急東横線で1駅目の代官山駅周辺から住宅地にかけて、洗練されたレストランや気軽に立ち寄れるカフェやデリ...

渋谷 ( 東京都 渋谷区 )
JR山手線と埼京線、京王井の頭線、東急線2線と東京メトロ3線が乗り入れるターミナル駅を中心とする渋谷は、新宿・池袋と並ぶ都内有数の繁華街。武蔵野台地を侵食する渋谷川と宇田川の合流点にあるため、谷底の街となっており、谷の低地に渋谷駅が位置する。そのため、宮益坂や道玄坂など坂道が多い。もともと渋谷駅構内はわかりにくかったが...

写真提供:山種美術館
山種美術館 ( 東京都 渋谷区 )
山種美術館は山種証券(現SMBC日興證券)の創業者である山崎種二が1966(昭和41)年に開設した美術館である。当初は日本橋兜町にあったが2009(平成21)年にJR恵比寿駅から徒歩10分の「ワイマッツ広尾」ビル内に移転した。同ビルの2フロアを占めている。 日本画を専門とした美術館としては全国初であり、特に近代から現代までの日本画を多...

写真提供:江戸東京たてもの園
江戸東京たてもの園(東京都江戸東京博物館分館) ( 東京都 小金井市 )
JR武蔵小金井駅北口、西武新宿線花小金井駅南口のいずれからもバスで5分の「小金井公園西口」で下車し、徒歩5分。小金井公園*の中にある。 1993(平成5)年、東京都が江戸東京博物館の開館に合わせ、博物館の分館として開設した施設で、敷地面積は約7万m2。現地保存が不可能な文化的価値の高い歴史的建造物を移築して復元・...

明治神宮外苑いちょう並木 ( 東京都 新宿区 )
東京メトロ・都営地下鉄青山一丁目駅そばの青山通りから聖徳記念絵画館へまっすぐにのびるイチョウ並木の道は、都内でも風情のある並木路の一つといわれる。1923(大正12)年に整備された並木で、イチョウは樹齢100年を超える。これらのイチョウは、1908(明治41)年に新宿御苑の在来木から採集した種子を豊島御料地(現在の明治神宮内)の苗...

新宿 ( 東京都 新宿区 )
新宿駅の1日の鉄道乗降客数は約350万で、その数は世界最多でギネス記録にもなっている。JR東日本、私鉄、地下鉄合わせて14路線が乗り入れる一大ターミナル駅で、近くには「新宿」の名の付く駅が9駅もある。 1603(慶長8)年に江戸幕府を開いた徳川家康が、江戸を起点とした主要幹線道路の五街道を整備。そのひとつの甲州街道では、日本橋...
末廣亭で上演される演芸 ( 東京都 新宿区 )
JR新宿駅東口から東へ約500mほどのところにある寄席*。末廣亭は落語*を中心とはしているが、漫才・奇術・音曲などのいわゆる色物*にも力を入れており、10日ごと(上席・中席・下席)に内容を変え、昼の部、夜の部の2部制で公演し、落語協会と落語芸術協会*の落語家・芸人が交互に出演する。現在の末廣亭の建物は1946(昭和21)年に建て...
国立競技場の全国高校サッカー選手権大会 ( 東京都 新宿区 )
国立競技場は新宿区と渋谷区に跨った敷地にあり、明治神宮外苑に隣接している。JR千駄ケ谷駅・信濃町駅、都営地下鉄国立競技場駅、東京メトロ外苑前駅から徒歩圏内にある。 現在の国立競技場の前身の前身である「明治神宮外苑競技場」(神宮競技場)は、日本で初めての本格的陸上競技場として、青山練兵場跡地に1924(大正13)年に建設さ...
武蔵御嶽神社 ( 東京都 青梅市 )
JR御嶽駅から御岳山ケーブルカー滝本駅まで南西へ2.8km、ケーブルカーで御嶽山駅まで登り、さらに参道を約2.2km(徒歩30分ほど)進んだ御岳山(標高929m)の山上に建つ。門前の鳥居前広場から社殿までは約330段の石段になっている(石段のない女坂もある)。滝本から門前までの参道は、通行許可車両しか通行できない。神社周辺の山々では古...
千鳥ヶ淵・牛ヶ淵のサクラ ( 東京都 千代田区 )
東京メトロ・都営地下鉄九段下駅から近い千鳥ヶ淵・牛ヶ淵には約230本のサクラがあり、3月下旬から4月上旬にかけて咲く。 北の丸公園の西側、旧江戸城内堀の千鳥ヶ淵沿いの緑が美しい細長い公園に、サクラの並木を縫って、約700mの遊歩道がつけられている。堀水に影を落としている石垣は、ヒカリゴケ*の生育地として知られている。濠端に...
神田明神(神田神社) ( 東京都 千代田区 )
JR御茶ノ水駅の北東、聖橋を渡り、本郷通りを挟んで湯島聖堂のはす向かいに位置する。正式名称は神田神社だが、江戸時代から現代にいたるまで、神田明神と呼ばれ、親しまれている。江戸開府以前の同社については定かではないが、社伝では730(天平2)年の創建*1と伝えられる古社で、当初は豊島郡芝崎村(現在の千代田区大手町1丁目・将門塚...

写真提供:宮内庁
江戸城跡 ( 東京都 千代田区 )
室町時代に太田道潅が秩父平氏の流れを汲む江戸氏の館跡に城を築いたのが、江戸城のはじめと伝えられている。当時は海辺に近い、けわしい崖の上に立ち、周囲に堀をめぐらせた堅固な城郭であったとされている。道潅の死後、上杉氏、北条氏を経て、1590(天正18)年に徳川家康が入城し、1606(慶長11)年から30年間、徳川家康・秀忠・家光の三...

神田古書店街 ( 東京都 千代田区 )
JR御茶ノ水駅から明大通りを下りきった駿河台下交差点から右、靖国通りやすずらん通り一帯には古書店が軒を連ねる。直接、古書街に入りたい方は、東京メトロ神保町駅で下車すればよい。江戸時代、神田の駿河台一帯には旗本が住んでいた。江戸末期になると、一橋通りを中心に東大の前身となる大学東校や南校ができ、明治になると、商法学校、...
国会議事堂 ( 東京都 千代田区 )
東京メトロ「国会議事堂前」駅から徒歩5分。東京メトロ永田町駅や溜池山王駅からも徒歩10分圏内。皇居の南西にそびえる白亜の重厚な建物で、日本の議会政治の殿堂である。国会議事堂は1890(明治23)年、第1回帝国議会のために、内幸町に仮議事堂として建設された。焼失と再建をくり返しながらも、46年間、木造の仮議事堂を使用した後、1936...

神田祭 ( 東京都 千代田区 )
神田祭は神田神社の例祭で、例大祭などの神事は、毎年5月中旬に行われ、神輿渡御などがある神幸祭(本祭)は山王祭と交互に隔年で催される。本祭は、1日目の境内での「鳳輦*神輿遷座祭」からはじまり、2日目に氏子町会神輿神霊入神事、3日目(日曜日に設定される)に鳳輦・神輿の氏子町内巡行、その翌々日に前斎神事(宵宮)、最終日に例大...

写真提供:日枝神社
山王祭 ( 東京都 千代田区 )
東京メトロ赤坂駅または溜池山王駅近くにある日枝神社*の例祭。なかでも神幸祭は、同社が徳川家の産土神であったことから、3代将軍家光公以来、歴代の将軍が上覧拝礼する「天下祭」として盛大を極めた。神幸祭では、鳳輦(ほうれん)*が渡御する神幸行列が江戸城内にも練り込み、将軍が親拝した。 祭の起源については、不詳ではあるが、...

写真提供:東京国立近代美術館
東京国立近代美術館 ( 東京都 千代田区 )
独立行政法人国立美術館が運営する美術館で、東京メトロ竹橋駅から徒歩3分の北の丸公園内にある*。日本の国立美術館は、1952(昭和27)年に中央区京橋に開館しているが、その後の収蔵品の増加を受けて、1963(昭和38)年に京都分館(京都国立近代美術館)が開館し、1969(昭和44)年に東京国立近代美術館が現在地に移転開館した。建物は建築...

出光美術館 ( 東京都 千代田区 )
出光興産創業者の出光佐三(1885-1981)が蒐集した美術品を公開するために、1966(昭和41)年に開館した美術館*1である。 コレクションは、東洋の古美術、特に日本の書画と中国・日本の陶磁器を系統的に蒐集したものであり、国宝2件、重要文化財57件を含む約1万件の美術品を所蔵している。著名な作品としては、日本四大絵巻の一つである...

写真提供:皇居三の丸尚蔵館
皇居三の丸尚蔵館 ( 東京都 千代田区 )
皇居三の丸尚蔵館は、皇室から寄贈された美術品を収蔵し、保存と研究、公開を目的とした施設。その名の通り、かつての江戸城の三の丸、現在の皇居東御苑内に位置しており、東京駅から徒歩15分、または地下鉄大手町駅から徒歩10分で到着する。 同館の発足のきっかけとなったのは、1989(平成元)年に上皇陛下と香淳皇后*により、昭和天皇...
上野恩賜公園のサクラ ( 東京都 台東区 )
JR上野駅と鴬谷(うぐいすだに)駅の西側に広がる高台の一帯が上野恩賜公園である。上野恩賜公園は、1873(明治6)年の太政官布達によって、芝、浅草、深川、飛鳥山と共に、日本で初めて公園に指定された。ここは、江戸時代、東叡山寛永寺の境内地で、明治維新の際、彰義隊と官軍の戦いで兵火にかかり、そのほとんどを焼失した。明治維新後官...
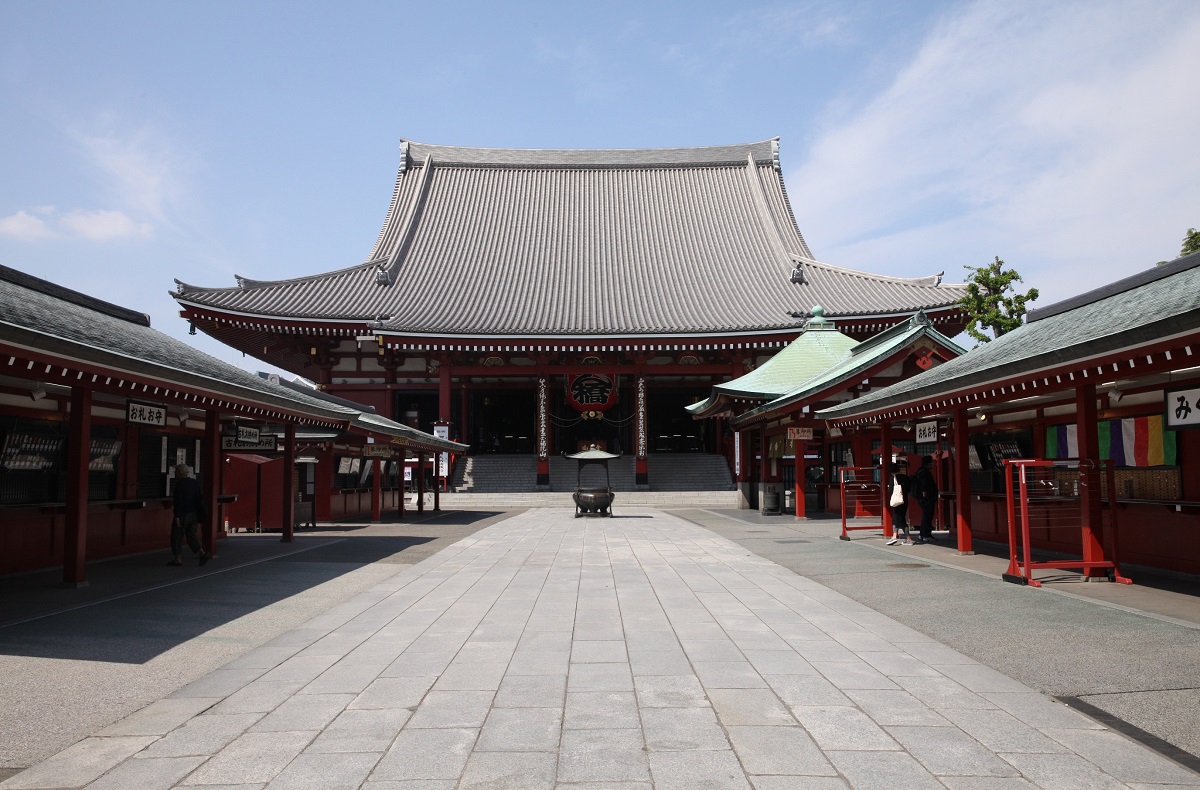
写真提供:浅草寺
浅草寺 ( 東京都 台東区 )
隅田川の西岸、東武線・東京メトロ・都営地下鉄の浅草駅近くにあり、浅草の観音様で知られる都内最古の寺。同寺の縁起によると628(推古天皇36)年に聖観世音菩薩像*1を祀った小堂を建てたのが始まりと伝られ、その後小堂は荒廃したが、645(大化元)年に勝海上人がこの堂を再建したことから、同寺の開基は勝海としている。 鎌倉時代には...
寛永寺 ( 東京都 台東区 )
上野恩賜公園(通称・上野公園)の北端、東京芸術大学の裏にある。天台宗の関東総本山で、江戸時代は118万8,000m2の広大な寺域と、5代将軍綱吉の建立による根本中堂を中心に、子院36坊をもつ大寺であった。 1625(寛永2)年に天海*1が徳川幕府の安泰と万民の平安を祈願するため、江戸城の鬼門(東北)にあたる上野の台地に創...

写真提供:上野東照宮
上野東照宮 ( 東京都 台東区 )
JR上野駅から300mほど、不忍池と上野動物園にはさまれた小高いところにある。藤堂高虎*1から拝領した忍ヶ岡(上野)にあった屋敷地に、天海*僧正が東叡山寛永寺を開山した。境内に建立された多くの伽藍のひとつとして、1627(寛永4)年に創建されたのが、東照社である。1646(正保3)年に後光明天皇から宮号を賜わり、以後上野東照宮と称す...
秋葉原 ( 東京都 台東区 )
JR3線と東京メトロ日比谷線が乗り入れ、つくばエクスプレスの発着駅でもある秋葉原駅。JRの電気街北口と電気街南口を出るとすぐ、中央通りを中心に秋葉原電気街は広がっている。 江戸時代は下級武士の居住地域で、「火事と喧嘩は江戸の華」といわれたように、火災に悩まされた。意外にも地名はそんな火災に由来している。1869(明治2)年...
旧東京音楽学校奏楽堂 ( 東京都 台東区 )
JR上野駅・京成上野駅から近い上野公園内にある音楽ホール兼音楽資料館。1890(明治23)年に東京音楽学校(現在の東京藝術大学音楽学部)の校舎として建てられ、2階には日本初の西洋式音楽ホール「奏楽堂」を備える。 国の重要文化財に指定された学校建築であり、現在は「生きた文化財」として建物が公開されているほか、演奏会や音楽資料...

写真提供:浅草神社
三社祭 ( 東京都 台東区 )
山王祭、神田祭や深川八幡祭などと並ぶ江戸の大祭で、浅草神社*1の例祭である。毎年5月の第3土曜日を中心として、3日間行われる。金曜日の初日は、お囃子屋台や鳶頭木遣り、芸子連の手古舞・組踊などが練り歩く、祭の名物「大行列」があり、古式豊かな神事「びんざさら舞」*2も奉納される。2日目の土曜日は、神事として「例大祭式典」が行...
酉の市(浅草鷲神社) ( 東京都 台東区 )
毎年、11月の酉の日に各地の鷲(おおとり)、あるいは大鳥神社で行われる祭礼。鷲神社あるいは大鳥神社は日本武尊を祀り、武家には武運長久の神として、庶民には開運、商売繁盛の神として信仰されてきた。大阪府堺市の大鳥神社が本社とされるが、関東各地の鷲神社、大鳥神社との関係は定かではない。また、酉の市には由来についても諸説*が...

写真提供:上野動物園
上野動物園 ( 東京都 台東区 )
JR及び京成電鉄上野駅から徒歩5分、上野公園の西端にあって、総面積約14万m2の敷地をもつ大規模な動物園である。日本の動物園の中でもっとも歴史が古く、1882(明治15)年に博物館の付属動物園として開園。1924(大正13)年に上野公園とともに東京市に下賜された。江戸時代から動物を人々に観覧させることは盛んであった。上野動...

写真提供:東京国立博物館
東京国立博物館 ( 東京都 台東区 )
JR上野駅から徒歩10分、上野恩賜公園の寛永寺輪王寺宮本坊跡にある。日本及び東洋諸地域における美術・工芸・考古遺物を収蔵、展示している。 広い敷地には本館(日本の美術・博物展示)、東洋館(アジアの美術・博物展示)、平成館(考古遺跡展示と特別展の開催)、法隆寺宝物館(法隆寺が献納した宝物の展示)、表慶館(特別展の開催)...
東京都美術館 ( 東京都 台東区 )
JR上野駅から徒歩7分の上野恩賜公園内に立地する日本で最も歴史のある公立美術館*1である。その前身は明治末に「日本には美術館が欠けている」という美術界の意見をもとに東京府(現・東京都)が計画した東京府美術館にある。この美術館は北九州の石炭商「佐藤慶太郎*2」の支援を受けて1926(大正15)年に開館した。日本の芸術家の登竜門と...

写真提供:鈴本演芸場
鈴本演芸場で上演される演芸 ( 東京都 台東区 )
東京メトロ上野広小路駅A3出口から徒歩1分にある寄席*1。地上5階建てビルの3・4階が吹き抜けの演芸場になっており、席はすべて椅子席で285席ある。出し物(番組)の中心は落語*2で落語協会*3所属の落語家が高座に上がる。これに漫才・奇術・音曲などの色物*4が出し物に加わり、10日ごと(上席・中席・下席)に内容を変え、昼の部、夜の部...
浅草演芸ホールで上演される演芸 ( 東京都 台東区 )
東武伊勢崎線・東京メトロ浅草駅から西へ約550mのところにある寄席*1。周辺は明治期から浅草公園六区(通称浅草六区)とよばれる興行街であり歓楽街で、下町の雰囲気も色濃い。「浅草演芸ホール」は5階建てのビルの1階と2階を利用し、落語*2を中心にマジック、物まね、漫才などの色物*3を交え公演を行っている。落語協会と落語芸術協会*...

写真提供:©(公財)東京都公園協会
旧岩崎邸庭園 ( 東京都 台東区 )
東京メトロ湯島駅1番出口から徒歩3分。入り口から東大病院へ通じる無縁坂に沿って、長いレンガ塀がつづく。旧岩崎邸は1896(明治29)年に岩崎彌太郎の長男で三菱第3代社長の久彌の本邸として建てられた。往時は越後高田藩榊原家の中屋敷であった約4万9,500m2の敷地に、20棟もの建物が並んでいたが、現在残っているのは洋館、撞球...
東京藝術大学大学美術館 ( 東京都 台東区 )
東京藝術大学の美術館である。JR上野駅、及び東京メトロ根津駅から徒歩10分、上野恩賜公園内の東京藝術大学・上野キャンパス内にある。 収蔵品は、1887(明治20)年に創立された東京美術学校が芸術教育や研究のために収集してきた古美術品に加えて、歴代教員の作品や学生らの制作品などが加わり、約3万件に及ぶ。そのうち、国宝・重要文化...

写真提供:池上本門寺
池上本門寺 ( 東京都 大田区 )
東急池上線池上駅から総門まで北へ600m。池上台地上に広大な寺域を構え、総門から石段*1を上ると、大堂*2・五重塔*3・鐘楼・経蔵・多宝塔*4・本殿・本院など10指に余る堂塔が建っている。かつては関東随一の七堂伽藍を誇っていたが、1945(昭和20)年4月の空襲でその多くを焼失したため、総門・五重塔・経蔵・多宝塔などのほかはすべて戦...

写真提供:築地本願寺
築地本願寺 ( 東京都 中央区 )
東京メトロ築地駅を出てすぐ、新大橋通りと晴海通りの交差点近くで、新大橋通りに面する。1617(元和3)年に本願寺12世准如(じゅんにょ)*1が浅草横山町に浅草御堂を創建したのが始まりと伝わる。1657(明暦3)年の明暦の大火後、現在地に移った。宗派は京都の西本願寺を本山とする浄土真宗。『江戸名所図会』には、当時の伽藍や境内が描か...
銀座通り ( 東京都 中央区 )
JR有楽町駅から徒歩5分。東京メトロの銀座線、丸の内線、日比谷線、有楽町線の4線が銀座通り周辺に集結する。銀座は1丁目から8丁目まであるが、メインストリートの中央通りが一般に銀座通りとも呼ばれ、松屋・三越などのデパートのほか、海外の一流ブランドショップや何代も続く老舗などの名店が軒を連ねる、日本有数の繁華街である。一歩裏...
日本銀行本店本館 ( 東京都 中央区 )
JR東京駅から徒歩8分、東京メトロ三越前駅から徒歩5分にある日本銀行本店本館は、日本の建築史における重要な建物で、1974(昭和49)年に国の重要文化財に指定された。 日本銀行は、1882(明治15)年に隅田川に架かる永代橋のたもとで開業し、開業当初は旧北海道開拓使物産売捌所の建物を借用した。この建物はイギリス人ジョサイア・コン...

写真提供:松竹㈱・㈱歌舞伎座
歌舞伎座 ( 東京都 中央区 )
東京メトロ・都営地下鉄の東銀座駅3番出口は、歌舞伎座の地下2階にある土産物と歌舞伎グッズを扱う売店や飲食店が並ぶ「木挽町広場」に直結している。400年以上の歴史を持つ日本の伝統芸能を体感できる劇場。歌舞伎は、江戸の初期、京都において出雲の阿国(おくに)が、当時の流行を取り入れ、男装して奇抜に踊る「かぶき踊り」を演じて人気...
深大寺 ( 東京都 調布市 )
京王線調布駅から北へ約1.9kmのところにある。江戸時代初期に書かれた寺伝の開創縁起*1によれば、733(天平5)年の開基と伝えられ、都内では浅草寺に次ぐ古い歴史をもつ古刹である。中世には関東一の密教道場となり、また江戸幕府の保護によって壮大な堂宇を構えて栄えたが、2度の火災にあった。茅葺の山門*2を入ると、本堂*3・元三(がん...
正福寺地蔵堂 ( 東京都 東村山市 )
西武新宿線東村山駅の北西約700mにある臨済宗の古刹。寺伝では1278(弘安元)年、北条時宗が病平癒を謝して仏殿を建てたとされるが、北条一族の入宋僧無象静照 (むぞうじょうしょう)(1234~1306年)が師の南宋径山寺石渓心月を勧請して開山し、草創したものと考えられている。臨済宗建長寺派。 山門を入り、本堂手前にある地蔵堂*1に...
高幡不動尊(高幡山明王院金剛寺) ( 東京都 日野市 )
京王線高幡不動駅の南口に出て200mほどで高幡不動尊の仁王門前に立つことができる。同寺の創建*1について、古文書では大宝年間(701~704年)以前とも伝えられるが、平安時代初期に慈覚大師円仁が、清和天皇の勅願により東関鎮護の霊場と定め、この地の山中に不動明王を安置し、不動堂を建立したことに始まるとされる。 丘陵が迫る境内に...

写真提供:府中観光協会
馬場大門ケヤキ並木 ( 東京都 府中市 )
京王線府中駅からすぐ西側、大國魂神社大鳥居から桜通りまでの約600mに、約120本のケヤキ等の高木が並ぶ。このうち、約4割の45本が約50年以上の樹齢で幹周り2m以上の巨木である。残り6割はここ50年の間に植栽された比較的歴史の浅い個体であり、幹回りは1~2m程度である。このほかにエノキ、イヌシデなど9本が生育する。ケヤキ並木としては日...
大國魂神社 ( 東京都 府中市 )
京王線府中駅から南へ約150本のケヤキ並木を通って大鳥居まで300m、またはJR武蔵野線・南武線府中本町駅の改札を出て東に100mほどのところにある。同社の縁起*1では創建は、111(景行天皇41)年と伝えているものの定かではない。ただ、同社については、律令制度が整いつつある7世紀末から8世紀前半に隣接地に武蔵国の国府*2が置かれたため...

武蔵府中のくらやみ祭 ( 東京都 府中市 )
「武蔵府中のくらやみ祭」は大國魂神社の例大祭で、4月30日から5月6日まで、往古*1から時代によって育まれてきた多種多彩な神祭事がとり行われる。 4月30日には神職のお清めのため「品川海上禊祓式(潮汲み・お浜降り)=潮盛り神事」が品川の海上にて行われる。 5月1日には安全と晴天祈願の祭事「祈晴祭」が催され、5月2日は神輿奉持...
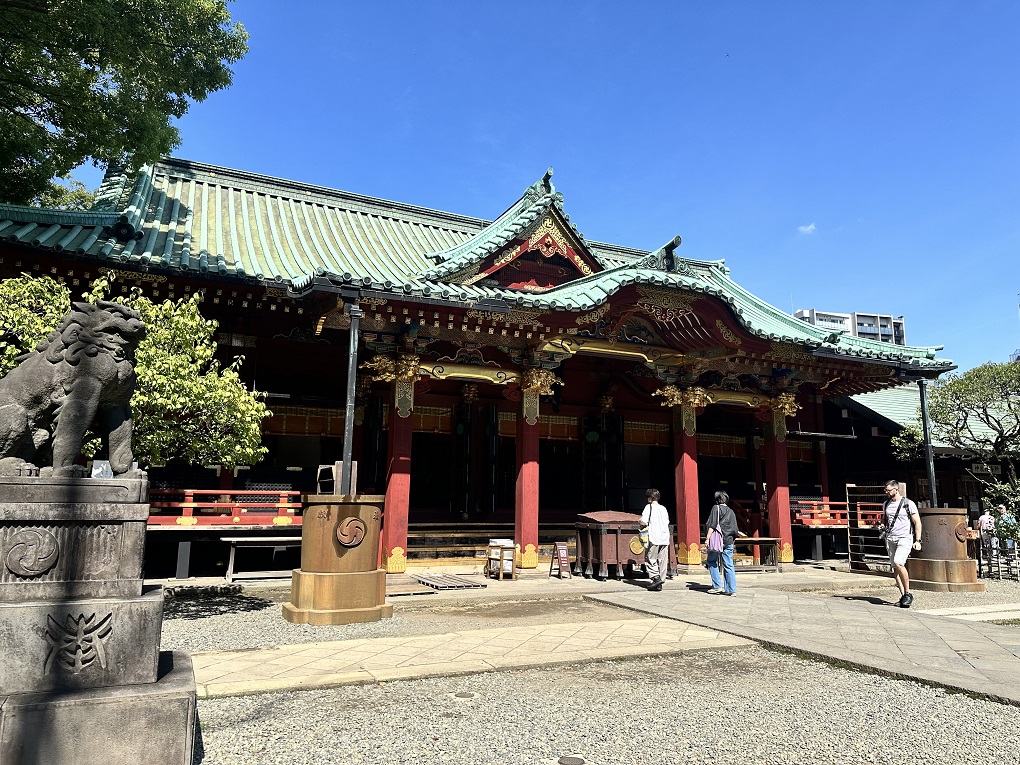
写真提供:根津神社
根津神社 ( 東京都 文京区 )
東京メトロ根津駅の北西にある古社。同社の草創*1については不詳であるが、「御府内備考続篇」の由緒書によれば、中世には「駒込惣鎮守にて千駄木村に鎮座有之」とされる。ただ、「太田道灌の再興有之候とも云。万治年中(1658~1661年)頃迄別当も無之」と管理するものもいない状況だったとされる。その後、地元民が力を合わせ社祠などを整...
護国寺 ( 東京都 文京区 )
東京メトロ護国寺駅のすぐ近く、不忍通りが首都高速5号と交差するあたりにある。1681(天和元)年に江戸幕府5代将軍徳川綱吉が、生母桂昌院の発願によって創建、幕府所属の高田薬園の地に堂宇を建立し、翌1682(天和2)年に完成した。桂昌院念持仏の天然琥珀如意輪観世音菩薩像を本尊とし、歴代将軍の崇敬を得た。1703(元禄16)年には寺領12...
六義園 ( 東京都 文京区 )
JRと東京メトロ駒込駅の南側にあり徒歩7分で到達する。園内は8万7,809m2の回遊式築山泉水庭園である。 六義園は1695(元禄8)年に柳澤吉保*が、徳川5代将軍綱吉から拝領した土地を自ら設計、7年あまりの歳月をかけて築造した名園である。六義園の名は、庭園の風致を詩歌の六義*になぞらえて吉保自身が命名したという。吉保...

写真提供:©(公財)東京都公園協会
小石川後楽園 ( 東京都 文京区 )
東京ドームの西に隣接している。もとは水戸藩上屋敷内の庭園で、面積は約7万847m2。東門へはJR水道橋から徒歩5分、西門へはJR飯田橋から徒歩8分で到達する。 1629(寛永6)年、水戸初代藩主徳川頼房が名匠徳大寺左兵衛に命じて作庭に着手、2代光圀のときに完成した回遊式築山泉水庭園である。園内に神田上水を導いて池水を作...
湯島聖堂 ( 東京都 文京区 )
JR御茶ノ水駅の東、神田川に架かる聖橋の北の橋詰にある。道路をはさんだ西側には東京医科歯科大学のキャンパスと病院が広がる。1690年(元禄3)年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉が儒学振興のため、上野忍岡の林羅山*の私邸にあった私塾と廟殿をこの地に移し、孔子*廟を拡大・整頓し、大成殿と改称したのがはじまり。この時から大成殿と附属の...
小石川植物園 ( 東京都 文京区 )
都営地下鉄白山駅から徒歩10分、文京区のほぼ中央、白山台地の上にある。正式名称は東京大学大学院理学系研究科附属植物園で、植物学の教育・研究を目的とする東京大学の施設である。徳川幕府5代将軍綱吉が館林藩主だったころに白山御殿と呼ばれる下屋敷が置かれていた場所で、その後、1684(貞享1)年に幕府が当地に設けた小石川御薬園に源...

写真提供:永青文庫
永青文庫 ( 東京都 文京区 )
文京区目白台にある私立美術館。都電荒川線早稲田駅より徒歩10分、東京メトロ江戸川橋駅・早稲田駅から徒歩15分にある。旧熊本藩主・細川家に伝わる美術工芸品約6,000点と、歴史資料88,000点を所蔵し、これらを管理保存・研究・一般公開している。「永青」の由来は、細川家の菩提寺である永源庵(建仁寺塔頭、現在は正伝永源院)の「永」と、...
宝生能楽堂で上演される能・狂言 ( 東京都 文京区 )
JR水道橋駅から徒歩3分、都営地下鉄水道橋駅より徒歩1分の宝生能楽堂は、宝生流の活動中心舞台である。宝生流は、能楽諸役のうち、主演などをつとめるシテ方の流儀をいう。シテ方宝生流は、大和猿楽四座*のうち、外山(とび)座を源流とする。外山座は、日本芸能発祥の地といわれる現在の奈良県桜井市外山を拠点として、多武峰(とうのみね...

写真提供:カトリック東京大司教区
東京カテドラル聖マリア大聖堂 ( 東京都 文京区 )
JR目白駅から都営バスで椿山荘下車すぐ、目白通りに面してそびえたつ。国内のカトリック教会の中で最多の信徒数をもつ東京教区の中心地として、多くの人が訪れる。1945(昭和20)年の東京大空襲で聖堂は焼失したあと、1964(昭和39)年に、丹下健三が設計して建てられたローマカトリックの教会で、高さは約40m。聖堂の隣に建つジョセフィーヌ...

写真提供:株式会社東京ドーム
東京ドームシティ アトラクションズ ( 東京都 文京区 )
全天候型の多目的スタジアム・東京ドームをはじめ、東京ドームホテル、後楽園ホール、ミュージアム、商業・飲食施設などで構成する「東京ドームシティ*」に立地し、水道橋駅などからほど近くJR山手線の内側では数少ない都心型の遊園地である。 1955(昭和30)年に「後楽園ゆうえんち」としてオープンし、限られたスペースを有効活用しな...
巣鴨地蔵通り商店街 ( 東京都 豊島区 )
JR巣鴨駅の北西にあるとげぬき地蔵*の門前通り。江戸時代の中山道にあり、日本橋からの最初の休憩地として栄えた。いまでは、高齢者に人気があることから、別名、「おばあちゃんの原宿」として知られる。地蔵参りで発展し、780mの商店街に200店舗を超す商店がひしめくように続いている。眞性寺*と高岩寺のふたつの地蔵尊と庚申塚*をお参り...
池袋 ( 東京都 豊島区 )
銀座や新宿、渋谷と並ぶ、東京の繁華街のひとつ。池袋の特徴や発展史を知る上で欠かせないポイントが4つある。 ひとつは、鉄道の影響だ。今でこそ、JR、東武鉄道、西武鉄道、東京メトロなど4社8路線が乗り入れる巨大ターミナル駅だが、鉄道黎明期には、駅の候補地にもあがらなかった。1885(明治18)年に、山手線の前身となる私鉄日本鉄...

写真提供:学校法人学習院
学習院大学 ( 東京都 豊島区 )
JR目白駅を出てすぐ右手に広がる緑の森の中に学習院大学は位置する。 幕末、京都御所近くに設けられた公家の教育機関を起源とし、1849(嘉永2)年に孝明天皇より「学習院」の勅額を賜り、学習院の名称が定まった。明治に入って京都の学習院は廃止され、1877(明治10)年に東京の神田錦町に華族学校が開設し、改めて学習院と命名された。そ...

写真提供:立教大学
立教大学(池袋) ( 東京都 豊島区 )
JR・東京メトロ・西武池袋線池袋駅の西口から徒歩約7分の地に池袋本校はある。アメリカ聖公会主教ウィリアムズが、1874(明治7)年に東京築地に設立した私塾「立教学校」に始まる。1883(明治16)年、校名を立教大学校に変更した。1907(明治40)年、専門学校令により立教大学として文科、商科から出発したキリスト教系大学である。中興の祖...
飛鳥山公園のサクラ ( 東京都 北区 )
JRと東京メトロの王子駅のすぐ西側にある高台一帯が公園になっている。標高25m近い高台へは、高齢者、身障者、ベビーカー利用者に、あすかパークレール、愛称「アスカルゴ」*が運行されている。江戸時代から桜の名所として知られ、広重の絵などにもよく描かれた。8代将軍徳川吉宗は財政の建て直しを図った「享保の改革」で、質素倹約を断行...

写真提供:©(公財)東京都公園協会
旧古河庭園 ( 東京都 北区 )
JR上中里駅の南、本郷通りに沿っている。鉱山経営で財をなした古河財閥の3代目当主、古河虎之助*の旧邸宅で、面積は約3万780m2。 現在の洋館と洋風庭園の設計者は、英国人ジョサイア・コンドル*で、1917(大正6)年に完成した。日本庭園は庭師七代目植治こと小川治兵衛の作で、心字池*を中心とした池泉回遊式庭園。大戦後...
国技館で開催される大相撲 ( 東京都 墨田区 )
JR・都営地下鉄両国駅から徒歩数分の場所にある両国国技館は、大相撲興行が行われる施設である。正式名称は国技館。初代国技館は、1909(明治42)年に両国回向院の境内の一角に辰野金吾らの設計により誕生したが、関東大震災や第二次世界大戦の大空襲などにより焼け落ちてしまう。1954(昭和29)年に完成した2代目の蔵前国技館は、建物の老...

写真提供:国営昭和記念公園
国営昭和記念公園 ( 東京都 立川市 / 東京都 昭島市 )
東京都心部から西へ約35kmの距離にあり、北に狭山丘陵、南に多摩丘陵をひかえた武蔵野台地の一角に位置する。公園の有料区には5つのゲートがあり、そのうち西立川ゲートはJR西立川駅公園口より約徒歩2分。
昭和天皇御在位50年記念事業の一環として、1983(昭和58)年に昭和記念公園として開業した。現在も整備中の都市公園で、約180万m
浅草 ( 東京都 台東区 )
東京メトロ、東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)の浅草駅からすぐの場所に東京最古の寺、浅草寺がある。都営地下鉄とつくばエクスプレス浅草駅からも、それほどの距離ではない。浅草の歴史は浅草寺から始まる。628(推古天皇36)年、地元の漁師が宮戸川(隅田川下流)で聖観音を引き上げたことが縁起とされ、これが今に伝わる浅草寺の本...

写真提供:日本空港ビルデング株式会社
羽田空港(東京国際空港) ( 東京都 大田区 )
羽田空港は、正式には東京国際空港という。空港までは首都圏の各地からバスの便があるが、鉄道では品川駅からの京急線とJR浜松町駅からの東京モノレールで行くことができる。 わが国で民間航空が盛んになってきた大正時代に、日本初の民間の飛行機学校のあった関係から、1930(昭和5)年、多摩川河口の鈴木新田*と隣接する埋立地の羽田...

写真提供:伊勢原市観光協会
大山 ( 神奈川県 伊勢原市 )
丹沢山地南東端にあるピラミッド状の山で、高さは1,252m、相模平野や武蔵野台地からその姿を望むことができる。別名「雨降山」と呼ばれ、雨乞いに霊験があるとされる。古くから有名な山岳信仰の山で、今も先達を先頭に白い行衣の信者たちが「さんげ さんげ 六根清浄」と唱えながら山頂をめざす光景が見られる。 山頂に阿夫利神社本社、中腹...

写真提供:大山阿夫利神社
大山阿夫利神社 ( 神奈川県 伊勢原市 )
大山阿夫利神社は、約2,200年前の崇神天皇のころの創建と伝えられている。祭神は大山祗大神(おおやまつみのおおかみ)、高龗神(たかおかみのかみ)、大雷神(おおいかずちのかみ)で、延喜式内社に位置づけられている。755(天平勝宝7)年、東大寺別当良弁が堂塔・僧坊を建て、神仏混淆の時代が始まった。 源頼朝・足利氏・北条氏などの...

よこはま動物園ズーラシア ( 神奈川県 横浜市 )
1999(平成11)年に開園した横浜市で一番新しい動物園。面積は45.3haで、国内の動物園としては最大級の広さを誇る。園内は世界の気候帯ごとに、「アジアの熱帯林」「亜寒帯の森」「オセアニアの草原」「中央アジアの高地」「日本の山里」「アマゾンの密林」「アフリカの熱帯雨林」「アフリカのサバンナ」の8つのゾーンで構成され、展示場には...

写真提供:(一社)横浜金沢観光協会
称名寺 ( 神奈川県 横浜市 )
北条実時(さねとき)*が金沢の別邸内に、称名念仏を行うための持仏堂を建てたのが寺の起こりと伝える。1267(文永4)年、下野薬師寺の審海(しんかい)を請じて開山とし、律院に改められた。寺は金沢北条氏の庇護のもと隆盛を極め、1323(元享3)年に描かれた『称名寺絵図並結界記』には、堂宇の建ち並ぶ姿が見られる。その後、鎌倉幕府が...

写真提供:野毛山動物園
野毛山動物園 ( 神奈川県 横浜市 )
1951(昭和26)年に開業した横浜市で最も古い動物園。 関東大震災から3年後の1926(大正15)年、被災地復興事業の一環として、原善三郎や茂木惣兵衛といった豪商の邸宅跡地などを利用し、回遊式日本庭園、洋風庭園、和洋折衷庭園の3つの様式を持つ「野毛山公園」が開園した。 1949(昭和24)年、野毛山公園は神奈川県と横浜市が主催す...

写真提供:日本郵船株式会社
山下公園 ( 神奈川県 横浜市 )
横浜港に面して大桟橋入口から山下埠頭まで長さ約700mにわたって広がる、面積約7万4,000m2の臨海公園。関東大震災復興事業の一環として、被災地の瓦礫や焼土を埋め立てて長方形に整地したもので、1930(昭和5)年に開園した。臨海公園としては日本初ともいわれる。 公園の東側には氷川丸が係留されている。氷川丸は日本郵船が...

写真提供:公益財団法人 横浜市緑の協会
横浜山手西洋館 ( 神奈川県 横浜市 )
1858(安政5)年に締結された日米修好通商条約をはじめとする安政の五カ国条約を機に、1859(安政6)年に横浜は開港場となり、1860(万延元)年には外国人居留地が開放された。当初の居留地は現在の山下町のエリアに設けられたが(「関内居留地」や「山下居留地」とよぶ)、埋立による低湿地帯であったために山手丘陵地の開放が求められ、現...

写真提供:公益財団法人 三溪園保勝会
三溪園 ( 神奈川県 横浜市 )
明治時代末から大正時代にかけて製糸・生糸貿易で財をなした横浜の実業家 原三溪(本名 富太郎)氏の本邸であった日本庭園で、園内は1906(明治39)年から一般公開されている外苑と、原家が私庭として使用していた内苑とからなる。三之谷と呼ばれる谷あいに、自然の起伏を生かして造られ、その敷地面積は約17万m2。京都や鎌倉など...

円覚寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )
北鎌倉駅のすぐ東に接する臨済宗円覚寺派の大本山。鎌倉五山の第二位に列せられている。1282(弘安5)年8代執権北条時宗が元寇の戦いの双方の戦死者を弔うために宋の高僧無学祖元*を招いて開山とし、この地に禅院を開いたのが始まりで、寺名は寺の起工の際、地中から円覚経を収めた石櫃(せきひつ)が出現したことによるという。その後、数...

円覚寺舎利殿 ( 神奈川県 鎌倉市 )
円覚寺塔頭の正続院*の内にある。方3間、単層、入母屋造、裳階付き、柿葺。わが国に現存する唐様(禅宗様)建築*の最古のものといわれ、扇垂木・粽柱・花頭窓など、いたるところによくその特徴を伝えている。以前は創建当初の建築とみられていたが、現在では室町時代に太平寺*の仏殿を移したものと考えられている。内陣に源実朝が中国宋か...

写真提供:明月院
明月院 ( 神奈川県 鎌倉市 )
北鎌倉駅南東700mの明月谷の奥。数千株のアジサイの花が参道に並び咲くことからアジサイ寺とも呼ばれている。寺は、北条時頼が建てた最明寺跡に再興された禅興寺の塔頭で(禅興寺が明治初期に廃寺となり塔頭でなくなる)、室町時代初期、関東管領上杉憲方*によって開創された。 境内には1973(昭和48)年に再建された本堂、北条時頼廟、...

写真提供:建長寺
建長寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )
臨済宗建長寺派の大本山で、鎌倉五山*の第一位に列する名刹。 1253(建長5)年5代執権北条時頼が宋の蘭渓道隆*を開山として創建した寺で、わが国最初の臨済禅専門道場となった。かつては七堂伽藍、塔頭49院を備えていたが、たびたびの火災で堂宇のことごとくを焼失、江戸時代になって将軍家の寄進を受けて、ようやく寺運は復興した。 ...

鶴岡八幡宮 ( 神奈川県 鎌倉市 )
鎌倉駅の北東、若宮大路の突きあたりにある。1063(康平6)年源頼義が奥州の前九年の役平定の後、京都の石清水八幡宮を由比郷鶴岡に現在の由比若宮を勧請し、その後1180(治承4)年鎌倉に本拠を置いた源頼朝は、大臣山のふもとに由比若宮を遷し、1191(建久2)年には大臣山の中腹に新たに御社殿を造営して源氏の守護神とした。これが現在の鶴...

瑞泉寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )
二階堂の東端、紅葉ガ谷にある。1327(嘉暦2)年、鎌倉幕府の重臣二階堂道薀が夢窓国師*を開山として一宇を創建、瑞泉院と称したのが始まりで、のちに初代鎌倉公方足利基氏が中興して瑞泉寺と号し、以来、鎌倉公方足利氏4代の菩提所として、おおいに栄えた。境内に大正時代以降に再建された総門・山門・本堂・地蔵堂・開山堂・鐘楼・客殿な...

写真提供:長谷寺
長谷寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )
由比ガ浜通りの西の突きあたりにある。参道を抜けて拝観口を通ると、回遊式庭園があり四季の花木が楽しめる。階段を登った観音山の山腹に観音堂・阿弥陀堂・観音ミュージアム・鐘楼などが並ぶ。 736(天平8)年、藤原房前が徳道上人を開山として創建した寺と伝え、本尊に長谷観音の名で有名な十一面観音立像を祭っている。ミュージアムに...

高徳院(鎌倉大仏殿) ( 神奈川県 鎌倉市 )
「美男におはす」(与謝野晶子の歌の一部)鎌倉の大仏として、あまりにも有名。 正式には大異山高徳院という寺の本尊である。寺の創建については明らかではなく、江戸中期の1712(正徳2)年、増上寺の祐天上人が中興して浄土宗とし、もと材木座光明寺の奥院であった。広々とした境内の奥、三方に回廊をめぐらした中央に露坐の大仏が鎮座し、...

杉本寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )
鶴岡八幡宮から金沢八景へと通じる金沢街道沿いの山腹にある。杉本観音とも呼ばれ、坂東三十三観音の第1番札所である。寺は、734(天平6)年、行基の開創と伝える鎌倉最古の仏地。1191(建久2)年源頼朝が参詣して寺領を寄進、再興した。その後も頼朝・政子・実朝らがたびたび参詣している。 茅葺の仁王門をくぐり、100段を超える急な石段...

海蔵寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )
鎌倉駅の北西1.2km、扇ガ谷と呼ばれる静かな住宅街の奥にある。1394(応永元)年、上杉氏定が鎌倉公方足利氏満の命を奉じて建立した。 盛時は塔頭10院を擁したと伝わるが、今は、小ぢんまりとした境内に、1776(安永5)年浄智寺から移した仏殿のほか、本堂・鐘楼・山門・庫裏を数えるのみである。本堂は、関東大震災後、1925(大正14)年...

銭洗弁財天(宇賀福神社) ( 神奈川県 鎌倉市 )
源氏山の西方、佐助ガ谷にある。三方を岩に囲まれた狭い境内に、社殿・社務所・茶店・奉納鳥居が並び、社殿脇の洞窟、奥宮に鎌倉五名水*の一つの銭洗水が湧き出ている。この清水で銭を洗うと倍になるという信仰で、広く人々に親しまれている。 社伝によれば、この霊水の発見は、1185(文治元)年、源頼朝の夢枕に現れた隠れ里の主、宇賀...

光明寺 ( 神奈川県 鎌倉市 )
材木座の海岸近くにある浄土宗の大本山。境内は広く、壮大な山門をくぐると、17間四面の大殿をはじめ、開山堂・大聖閣・書院・方丈・鐘楼などが軒をつらね、大寺の格式を誇っている。 寺の起源は、4代執権北条経時が佐助ガ谷に一宇を建て、蓮華寺と称したのが始まりとされており、1243(寛元元)年現在地に移して、寺号を改めた。その後も...

写真提供:江ノ島電鉄
江ノ島電鉄 ( 神奈川県 鎌倉市 / 神奈川県 藤沢市 )
鎌倉駅~藤沢間を結ぶ私鉄。鎌倉の歴史と文化、湘南の海と江の島*を見渡す開放的なロケーションを有する鉄道は1902(明治35)年に日本で6番目の鉄道として藤沢~片瀬(現江ノ島)間で開業し、110年以上の歴史を持つ。

写真提供:小田原城総合管理事務所
小田原城 ( 神奈川県 小田原市 )
小田原城は、小田原駅の西南、相模湾に向かって延びた箱根外輪山麓の台地上にある。 1416(応永23)年、土肥氏に代わった大森氏の治世を経て、1500年頃に小田原北条氏の初代 早雲が小田原城へと進出した後、五代約100年に渡り関東一円を支配した。1590(天正18)年の豊臣秀吉の小田原攻めにより北条氏が五代で滅んだ後は、家康の家臣の大...

写真提供:小田原城総合管理事務所
石垣山城 ( 神奈川県 小田原市 )
一夜城は伝説の話。実際は1590(天正18)年、豊臣秀吉が水陸15~16万の大軍を率いて小田原北条氏を包囲し、その本営としてこの地に、関東初の総石垣の城を築いた。建設には約4万人が動員され、82日間を費やした。石積みは近江の穴太衆(あのうしゅう)による野面積(のづらつみ)で、長期戦に備えた本格的な城構えであった。公園面積は約5.8h...

写真提供:平間寺(川崎大師)
平間寺(川崎大師) ( 神奈川県 川崎市 )
平間寺は、正式には「金剛山金乗院平間寺」と称する真言宗智山派の大本山である。大治年間(1125~1130年)、平間兼乗という武士が、夢のお告げにより海中から弘法大師の木像を引き揚げた。ささやかな草庵をむすび、供養を怠らなかった兼乗が、高野山の尊賢上人と力を合わせ、一寺を建立したのが始まりと伝えられている。 川崎大師駅前か...

写真提供:©2019川崎市立日本民家園
川崎市立日本民家園 ( 神奈川県 川崎市 )
川崎市立日本民家園は、急速に消滅しつつある古民家を永く将来に残すことを目的として、生田緑地の丘陵に、1967(昭和42)年に開園した古民家の野外博物館である。東日本の代表的な民家をはじめ、水車小屋、船頭小屋、高倉、歌舞伎舞台など25件の建物が配置されている。これら25件の建物全てが国・県・市の文化財指定を受けている。園路には...

写真提供:©Fujiko-Pro
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム ( 神奈川県 川崎市 )
「川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム」は、藤子・F・不二雄氏が富山県高岡市から上京後、トキワ荘時代を経て、晩年までを過ごした川崎市にある美術館である。2011(平成23)年9月に開館し、藤子・F・不二雄氏の作品世界やメッセージを、原画などの展示を通じて発信している。 同ミュージアムは、「まんが」「遊びゴコロ」「SF-すこしふ...

箱根火山後期中央火口 ( 神奈川県 箱根町 )
富士火山帯に属する箱根火山は、伊豆半島の基部に噴出したカルデラ火山(外輪山、前期中央火口丘、後期中央火口丘)である。このうち、後期中央火口丘部分(最後の噴火により構成された火山群)については、最高峰である1,438mの神山を中心に、二子山、駒ヶ岳、冠ヶ岳、早雲山、台ヶ岳などが囲む。 歴史的にみると、箱根火山が活動を始め...

写真提供:彫刻の森美術館
彫刻の森美術館 ( 神奈川県 箱根町 )
箱根二ノ平の明るく開けた丘陵に、1969(昭和44)年開設された野外美術館。7万m2の敷地には樹木に縁どられた広々とした芝生にロダン、ブールデル、ヘンリー・ムーアなどの巨匠の彫刻約120点が展示され、小道を歩きながら鑑賞できる。野外展示場の周りにはピカソ館などの室内展示場があり、多くの作品を展示している。また、こども...

写真提供:箱根ジオパーク推進協議会
仙石原高原(仙石原湿原・すすき草原) ( 神奈川県 箱根町 )
仙石原高原は、金時山・丸岳などの外輪山と台ヶ岳などの後期同中央火口丘との間、標高約700mに広がる高原である。箱根内カルデラの平坦な地形が広がる場所で、現在は一面の草原となり、ゴルフ場やテニスコートが造られ、温泉や寮、別荘が点在する。9~10月の初秋の頃には黄金色のススキの原となり、秋の箱根の代表的景観をつくる。 面積約...

写真提供:公益社団法人神奈川県観光協会
芦ノ湖 ( 神奈川県 箱根町 )
芦ノ湖は、箱根外輪山内に北東から南西に横たわるカルデラ湖で、湖面の標高724m、周囲約19km、最大深度43.5mほどのひょうたん形となっている。中央部のやや北のところで東西の幅がもっとも狭くなり、わずか300mとなる。水温は年間4度以上で冬期も結氷することがない。湖水の水は北岸から流れ出る早川によって相模湾へ注ぎ、同時に北西岸に掘...

写真提供:箱根神社
箱根神社 ( 神奈川県 箱根町 )
奈良時代の757(天平宝字元)年箱根山に入峰修行中の万巻上人が、箱根大神の御神託により芦ノ湖畔の現在地に鎮斎された古大社。 鎌倉期、源頼朝は深く当社を信仰し、二所詣の風儀を生み、以来、執権・北条氏や戦国武将の徳川家康等、武家による崇敬の篤い社として、また修験の霊場として栄えた。 近世、箱根道の整備と共に庶民信仰の聖...

大涌谷 ( 神奈川県 箱根町 )
大涌谷はおよそ3,000年前、箱根火山活動の最末期に神山北山腹の爆裂によってできた谷である。神山を形成した岩しょうが冷え固まるにつれて、揮発性物質がガスとなって蓄積され爆発したもので、この爆発は冠ガ丘を造り、押し出された土砂は芦ノ湖を造った。標高は約1,000m。 大涌谷はかつて「大地獄」と呼ばれていたが、1873(明治6)年8月...

写真提供:箱根登山鉄道株式会社
箱根強羅公園 ( 神奈川県 箱根町 )
強羅公園は、1914(大正3)年に早雲山の中腹に開園された、面積約2万4,500m2の公園である。噴水を中心に斜面を利用して造られたフランス式整形庭園で、園内には桜、ツツジが多い。公園内には、白雲洞茶苑、ローズガーデン、熱帯植物館、ブーゲンビレア館、箱根クラフトハウスなどの施設がある。 白雲洞茶苑は、明治・大正・昭...

箱根旧街道杉並木 ( 神奈川県 箱根町 )
屏風山の西麓、芦ノ湖湖岸近くに延びる箱根旧街道に残る杉並木。現在は約500m、元箱根から恩賜箱根公園まで続く。高さは30m程度、中には幹回り4mを超える大木が約400本残されている。 徳川家康が江戸幕府を開いた翌年の1604(慶長9)年に諸国の街道の両側に松や杉を植えたのが始まりで、1618(元和4)年幕府の命を受け、川越藩主・松平正...

箱根登山電車 ( 神奈川県 箱根町 )
箱根登山電車は日本の普通鉄道での最急勾配80‰(1,000mの区間で80m上下する勾配)、箱根の山を箱根湯本(標高96m)から強羅(541m)までの8.9kmを登る山岳鉄道で箱根登山鉄道株式会社が運行している。 箱根登山鉄道株式会社は、小田原市にある小田急グループの鉄道会社。東海道本線の経路から外れる小田原と箱根を結ぶことを目的として建...

写真提供:ポーラ美術館
ポーラ美術館 ( 神奈川県 箱根町 )
「箱根と自然と美術の共生」のコンセプトのもと、ポーラ創業家二代目・鈴木常司が1950年代後半から40数年にわたり収集したコレクションを有する美術館として、2002(平成14)年9月に開館した。コレクションは約1万点にのぼり、19世紀フランスの印象派を中心とした西洋絵画や日本の洋画、日本画、版画、彫刻、東洋陶磁、日本の近現代陶芸、ガ...

清浄光寺(遊行寺) ( 神奈川県 藤沢市 )
藤沢駅の北東約1kmにある。1276(建治2)年一遍上人によって開宗された時宗の総本山。時宗は遊行念仏宗ともいわれ、歴代の宗主が信仰の歓喜を踊念仏に表わし、全国を遊行教化したので、同寺の住職を代々遊行上人と呼び、寺名も一般に遊行寺というようになった。 当寺の開基は1325(正中2)年、遊行4代の呑海によるもので、以来、足利・徳...

写真提供:江島神社
江島神社 ( 神奈川県 藤沢市 )
江の島の裸弁天で知られる。江の島弁天は安芸の宮島、近江の竹生島とともに三弁天の一つに数えられて信仰を集め、特に、江戸時代は江戸町民や東海道の旅人など庶民の参詣で賑わった。 創起は552(欽明天皇13)年、今の御岩屋に海の守護神である3女神を祭ったと伝えられるが、1182(寿永元)年、源頼朝が文覚上人に命じて社殿を建立し、弁...

小田原文学館 ( 神奈川県 小田原市 )
文学館の建物は、明治時代から昭和戦前期にかけての陸軍軍人、官僚、政治家であった田中光顕の元別邸で、1937(昭和12)年築のスパニッシュ様式の本館、1924(大正13)年築の和風建築の別館ともに国登録有形文化財である。 本館1階は尾崎一雄、川崎長太郎など小田原出身の文学者、2階は谷崎潤一郎、三好達治など小田原に居住した文学者の...

写真提供:松永記念館
松永記念館 ( 神奈川県 小田原市 )
本館展示室は、「電力王」と言われた松永安左エ門(耳庵 じあん)が収集した古美術品を一般公開するために、「財団法人松永記念館」を設立し、建設したもの。財団の解散後は、市に寄付し、市が管理している。本館2階は松永の意向が反映された茶室が保存されている。広間の太い床柱は平等院山門に使用されたものといわれ、横浜の三溪園で知ら...

写真提供:神奈川県立生命の星・地球博物館
神奈川県立生命の星・地球博物館 ( 神奈川県 小田原市 )
神奈川県立生命の星・地球博物館は、地球の歴史と生命の多様性をテーマとする自然史系博物館である。竣工は1994(平成6)年、延べ床面積は19,020m2で、実物標本は巨大な恐竜や隕石から豆粒ほどの昆虫まで約1万点にのぼる。 1階の常設展示室では、地球誕生のなぞについて隕石やクレーター形成などをもとに解説を行う「地球を考...

写真提供:岡田美術館
岡田美術館 ( 神奈川県 箱根町 )
岡田美術館は、明治時代に建設された欧米人向けのホテル「開化亭」の跡地に2013(平成25)年、開館した私設美術館である。 延床面積は約7,700m2の全5階建て、1階は中国・韓国の陶磁器、2階は日本の陶磁器やガラス、3階は屏風を中心とした日本絵画、4階は絵画・書跡・漆芸、5階は仏教美術の展示とテーマ別に分類されている。展...

写真提供:古我邸
古我邸 ( 神奈川県 鎌倉市 )
幕末の横浜開港後、横浜の居留地に住む外国人たちは鎌倉をリゾート地として見出し、頻繁に訪れるようになった。その後、JR横須賀線の開通を契機に、洋風の別荘が相次いで建てられた。 古我邸は、三菱合資会社の専務理事だった荘清次郎の別荘として15年を費やして建てられた。関東大震災後の対策会議もここで開かれた。 1937(昭和12)...

つがわ狐の嫁入り行列 ( 新潟県 阿賀町 )
1990(平成2)年に始まった祭りである。狐火で有名な津川に伝わる、江戸時代の嫁入りを再現した結婚の儀式。その年結婚予定のカップルが、白無垢姿の花嫁で狐の真似をしながら、住吉神社から夜の街道を練り歩き、108匹(人)のお供を連れて、披露宴会場となる麒麟山公園まで行列*する。まちでは灯りを消し松明や提灯で幻想的な雰囲気を演出...
写真提供:五頭温泉郷旅館協同組合
五頭温泉郷(出湯温泉、今板温泉、村杉温泉) ( 新潟県 阿賀野市 )
五頭・菱ヶ岳西麓にあり、旧笹神村の出湯・今板・村杉の三温泉を称して五頭温泉郷という。ゆっくりと保養する人のほかに、周辺の瓢湖、五頭山、ゴルフ場などの基地として利用されている。 北にある出湯温泉*は、弘法大師が錫杖で地面を突いたところ湧出したと伝えられる。五頭山華報寺の門前町と発達した温泉で、華報寺が名実ともにこの...
写真提供:国土交通省北陸地方整備局
信濃川(大河津分水) ( 新潟県 燕市 )
3年に1度の頻度で水害が発生していた越後平野。潟や沼が点在する低湿地帯であるため、水はけが悪く浸水が長期化したほか、腰まで水に浸かりながら稲刈りをする泥沼の深田が各地に広がっていた。その惨状は良寛も嘆くほどであった。 1896(明治29)年7月22日に発生した「横田切れ」では越後平野のほぼ全域が約1か月にわたって浸水し、食料...

渡邉邸 ( 新潟県 関川村 )
JR米坂線越後下関駅の東、旧米沢街道沿いにある。渡邉家初代は村上藩士で郡奉行を務めたが、1667(寛文7)年に隠居して現在地に転居した。二代目は廻船業や酒造業で財を成し、新田開発をするなど大地主に発展していった。三代目は、1726(享保11)年以降、財政難に苦しんでいた米沢藩への融資を幕末まで続け、その額は10万両を超えた。その功...

加茂湖 ( 新潟県 佐渡市 )
両津湾が、北から南から発達してきた砂嘴によって仕切られ、加茂湖が誕生し、両津市街地で海と隔てられた海跡湖である。むかしは越ノ湖と風雅な名で呼ばれた淡水湖であったが、1904(明治37)年に水害予防と船溜まりのため湖口を開削、そのため、海水が流れこんで、鹹湖(かんこ)*となった。 面積4.85km2は県内最大であり、...

写真提供:新潟県観光文化スポーツ部文化課世界遺産登録推進室
佐渡金銀山 ( 新潟県 佐渡市 )
国史跡の佐渡金銀山遺跡は、「佐渡島(さど)の金山」の名称で、2022(令和4)年2月に世界遺産候補としてユネスコに推薦された。 佐渡島の金生産の最古の記録は、平安時代後期(12世紀)に編纂された『今昔物語集』で、佐渡島で金を採取したという説話が収録されている。15世紀半ばには佐渡へ流された世阿弥が『金島書』の中で、佐渡島を...

写真提供:新潟県佐渡市
トキの森公園 ( 新潟県 佐渡市 )
トキ*の森公園には、「トキふれあいプラザ」と「トキ資料展示館」とがある。前者では、飼育ケージ内を生息環境に近い状態にして、トキの採餌、飛翔のほか、抱卵や子育てなどトキの生態を間近で観察できる。後者では、展示テーマを「保護から共生そして未来へ」と題し、近年リニューアルした展示物や従来展示していた「キン」のはく製などを...

妙宣寺(阿仏房妙宣寺) ( 新潟県 佐渡市 )
佐渡に配流された順徳上皇*の供をしてきた北面の武士遠藤為盛(えんどうためもり)は、上皇崩御ののち、出家して阿仏房日得(にっとく)となった。その後、流されて塚原に謫居中の日蓮に、妻千日尼と共に帰依し、いろいろと尽した。その子盛綱が父母の志を継いで、その住居を寺としたのが始まり。 寺地はアカマツの林の中にあり、江戸末...

佐渡の能・狂言 ( 新潟県 佐渡市 )
佐渡では、宝生流の能楽が盛んである。かつて観世三郎元清(世阿弥)*が流されて来た影響もあるが、慶長年間(1596~1615年)に金山奉行となった大久保長安が、猿楽師の出身で、能を奨励したことによるといわれる。今でも、島内の古い宮には能舞台が見られ、1924(大正13)年に訪れた大町桂月も「鴬や十戸の村に能舞台」と詠んだほどである...
写真提供:一般社団法人糸魚川市観光協会
小滝川ヒスイ峡 ( 新潟県 糸魚川市 )
大糸線小滝駅の西方、姫川の支流・小滝川の、明星山*の大岩壁が落ち込んだ河原が国の天然記念物「小滝川硬玉産地」である。硬玉とはヒスイのことで、一帯は小滝川ヒスイ峡とよばれる。日本随一のヒスイ産地と知られ、150mほどの河床には白色・緑色・紫色の硬玉が散在する。 1938(昭和13)年、日本で初めてヒスイの原石がここで発見され...
写真提供:一般社団法人糸魚川市観光協会
雪倉岳 ( 新潟県 糸魚川市 / 富山県 朝日町 )
新潟県と富山県との境界にある飛騨山脈後立山連峰にある標高2,611mの山。大きく根を張り、おおらかな山体を横たえる。山名は、積雪期に雪の間にところどころ岩が見え、その岩を地元猟師らは「倉」と呼んでいたことから、雪*と倉の山という意味で「雪倉岳」と呼ばれるようになったという。
写真提供:一般社団法人糸魚川市観光協会
焼山 ( 新潟県 糸魚川市 / 新潟県 妙高市 )
糸魚川市と旧妙高村にまたがる、釣鐘状のトロイデ型、標高2,400m。約3000年前に活動が始まった若い火山で、新潟県唯一で活火山で、長い間、登山禁止であったが、2018(平成30)年11月15日付けで、立入り規制は解除された。山の大部分は火山体でなくフォッサマグナ由来の第三紀層である。山頂部は森林限界の高山帯で、日本におけるライチョウ...

信濃川(河口付近) ( 新潟県 小千谷市 / 新潟県 十日町市 / 新潟県 燕市 / 新潟県 新潟市 / 新潟県 他 )
山梨・埼玉・長野の三県にまたがる甲武信ガ岳(2,475m)に源流を発し、千曲川として善光寺平に入ると最大の支流である犀川をあわせ、飯山盆地を経て、信越国境を越えて初めて、信濃川に名を改める。信越国境から小千谷までの「中流域」は、幾段もの河岸段丘を形成し、小千谷からは自らの土砂で生成した越後平野を貫流、新潟市で日本海に注ぐ...
写真提供:柿崎観光協会
米山 ( 新潟県 上越市 )
標高993mの海岸線にある独立峰で、遠くからも目立つ山容は実に堂々としている。山頂には避難小屋や一等三角点があり、円錐型秀麗な山容を見せる。 712(和銅5)年泰澄大師によって開山と伝えられ、山頂には日本三薬師に数えられる米山薬師が祀られており、柿崎側の麓には別当寺密蔵院護摩堂がある。山毛欅に囲まれた登山道の随所にお地蔵...

林泉寺 ( 新潟県 上越市 )
春日山城跡の北麓にある。1497(明応6)年に越後の守護代長尾能景*が、父重景の17回忌にあたり同家の菩提所として建立した名刹。現在の寺は春日山城主となった堀秀治が再興したもので、江戸時代になってからは、歴代高田藩主の保護を受けた。上杉謙信は能景の孫にあたり、幼少からこの寺で6代天室光育に学び、さらに7代益翁宗謙について禅の...

旧笹川家住宅 ( 新潟県 新潟市 )
笹川家は、安土桃山時代の信濃国水内郡笹川村から、この味方の地に移住し、1970(昭和45)年にこの地を離れるまで、14代300年以上にわたって続いた名家である。1649(慶安2)年から明治維新までは、9代にわたり味方組8か村、約8千石を束ねる大庄屋をつづけた。年貢の取りまとめ、藩から与えられた警察権・裁判権を行使していた。その一方で、...
写真提供:新潟市役所 観光政策課
新潟まつり ( 新潟県 新潟市 )
新潟まつりは、住吉まつり、開港記念祭、川開き、商工祭の4つの行事*を総合して1955(昭和30)年から実施されている新潟の代表的な祭りである。2020(令和2)年は8月21日~23日の3日間開催。 約1万5,000人の踊り手が市街地の通りを埋め尽くす「大民謡流し」や古式ゆかしい住吉行列。港の安全と発展を願う水上おこし渡御、市民みこし、そ...

佐潟 ( 新潟県 新潟市 )
佐潟は、新潟砂丘列間の低地に位置し、上流側の小さな上潟(うわかた)と、下流側の下潟(したかた)の、大小2つの潟から成り立つ淡水湖。潟の面積は43万6千m2、水深は平均1mと浅く、湖底は船底形をしている。外部からの流入河川はなく、周辺地域からの湧水と雨水で涵養されている。 この地域は、国定公園第3種特別地域として...

北方文化博物館 ( 新潟県 新潟市 )
阿賀野川西岸の小さな集落沢海に、江戸中期、農より身を起こし、代を重ね越後随一の大地主になったのが伊藤家である。明治に入り、農地の集約を計り、全盛期には、所有の田畑1,372町歩(約14ha)、山林1,000町歩(約10ha)を超え、差配人78名、米蔵58か所、小作人2,800名を数え、作徳米約3万俵といわれ、昭和期には県下一の地主となった。 ...

市島邸 ( 新潟県 新発田市 )
月岡駅の北西にある。阿賀野市水原の市島家*旧邸が戊辰戦争の兵火により焼失したあと、1876(明治9)年に建てられたもの。 現在、2万6,000m2の敷地に、茶室の水月庵、約150mの渡り廊下、93畳の広さがある南山亭など明治初期の建築作風を残した2,000m2の建物と、広い回遊式庭園の静月園、背後に竹林・梅林がある。...

阿賀野川 ( 新潟県 阿賀町 / 福島県 西会津町 / 新潟県 他 )
阿賀野川は、福島・栃木両県の県境にある荒海山(標高1,581m)に源があり、新潟市北区松浜地先において980mの川幅で日本海へ流れ出る。長さ210kmは日本で10番目であるが、年間の総流出量は142億tで信濃川に次いで多い。阿賀野川という名は新潟県内に限られ、福島県では阿賀川(大川)と呼ばれる。豊富な水を利用して多くの水力発電所が建設...
写真提供:村上市山北支所
笹川流れ ( 新潟県 村上市 )
県北部、浜新保から寒川(かんがわ)まで11kmにわたり独特の奇岩景観を見せている海岸線をいう。笹川流れの名称は、岩の間を盛り上がるように流れる潮流を、中心地笹川集落の名にちなんで付けられた。 隆起花崗岩が日本海の荒波で浸食されたもので、青々と松が茂る奇岩礁と、白砂の浜が交互に続き、前方に粟島が横たわる。頼三樹三郎*は...

村上の鮭料理 ( 新潟県 村上市 )
川煮、がじ煮(雅味煮)、しょう油ハラコ(腹子)、子皮煮、酒びたし、氷頭(ひず)なます、飯(いい)ずし、すっぽん煮、ナワタ汁、塩引き……。いずれも、新潟県の村上ではぐくまれ、今も口にすることのできるサケ料理である。サケの本場の北海道にも見られないこれだけのサケ文化が生まれたのには次のような背景がある。 村上市を流れる...
写真提供:一般社団法人村上市観光協会
村上大祭 ( 新潟県 村上市 )
江戸時代初期、1633(寛永10)年に藩主堀直竒(なおのり)が西奈弥(せなみ)羽黒神社社殿を城から見下ろすのは畏れ多いとして、臥牛山中腹から現地に遷座した際、その祝いとして町民が大八車に太鼓を積んで乗り回したのが始まりと言われる。祭りは3基の神輿に御神霊を奉って、荒馬14騎、稚児行列を先頭に町内を巡行する「お旅神事」だが、圧...

越後山古志 牛の角突き ( 新潟県 長岡市 )
奉納神事であり、山古志の人たちの娯楽であった「牛の角突き」の歴史は古く千年まえからと言われ、江戸時代から明治大正と盛んになる。昭和戦後一時途絶えていたが復活。1976(昭和51)年、越後闘牛会、山古志観光開発公社が発足し、闘牛場が整備された。5月から11月の毎月1~2回(日曜日)山古志闘牛場で行われる。
写真提供:一般財団法人長岡花火財団
長岡まつり大花火大会 ( 新潟県 長岡市 )
長岡の花火大会の歴史は、1879(明治12)年、千手町八幡様の祭で350発の花火の打ち上げに始まると言われる。1926(大正15)年に正三尺玉が打ち上げられ、昭和初期には全国に知られるようになる。しかし、太平洋戦争を鑑みて花火大会は中止された。1945(昭和20)年8月1日、B29大型戦略爆撃機が長岡の旧市街地をほとんど焼き尽くし、1,480余名...

写真提供:田上町役場 産業振興課 商工観光係
護摩堂山あじさい園 ( 新潟県 田上町 )
護摩堂山の山頂付近に広がる「あじさい園」には、約3万株のアジサイが植えられていて、初夏になると西洋アジサイやガクアジサイなどの品種もあり多彩で、青、赤、紫、白の色とりどりの花が、訪れる人々を楽しませる。見ごろは、例年6月下旬から7月上旬で、開花期に合わせて「あじさいまつり」が行われる。

苗場山 ( 新潟県 湯沢町 / 新潟県 津南町 / 長野県 栄村 )
標高2,145m。新潟・長野の県境に、南にゆるやかに傾く広大な山頂をもつ火山で、なだらかな山頂には高層湿原が発達し、オオシラビソノの樹林の間には、径数mから20mほどの池塘が何百も点在している。まさに天上の楽園の言葉にふさわしい。山名が表わすように、むかし池塘は苗田と考えられ、神が稲を植えた所と伝えられている。北面の中腹には...

写真提供:南魚沼市産業振興部商工観光課
巻機山 ( 新潟県 南魚沼市 )
標高1,967m。割引岳・巻機本山・牛ヶ岳を含め巻機山と総称され、新潟と群馬の県境に優雅な山容を見せる。山名は当地方の産物である機織りと関係があり、頂上一帯は御機屋と呼ばれ、機織りの伝説がある。山麓には機織りの女神の巻機権現が祀られている。五合目までは「井戸の壁」といわれる樹林帯の急登であるが、五合からのブナ林、六合目の...

写真提供:南魚沼市産業振興部商工観光課
八海山 ( 新潟県 南魚沼市 )
標高1,778m。JR上越線の六日町駅と浦佐駅の途中の車窓から、岩塊を積み上げたように鋸の目状のゴツゴツした山容を見せる。八海山は薬師岳・大日岳・入道岳(最高峰)の総称。岩場が多く、山頂付近は八ツ峰とも呼ばれる。古くから信仰を集めてきた山で、山麓三地区にはそれぞれ八海山神社里宮がある。六合目女人堂は、女人禁制の時代、女性は...

奥只見湖 ( 新潟県 魚沼市 / 福島県 桧枝岐村 )
奥只見ダム*によって只見川本流をせき止め、銀の採掘で知られる銀山平*のほとんどを沈めてできた人造湖。新潟県と福島県の県境にあたり、越後の荒沢連峰や会津駒ガ岳をはじめとする会津の山並みにはさまれて、紺碧の湖水が南北、東西に細長くのびる。静かな湖面に残雪や新緑、紅葉を映し、秘境の趣を感じさせる。ことに紅葉時はみごと。 ...
写真提供:貞観園保存会
貞観園 ( 新潟県 柏崎市 )
当地方の大庄屋村山家の五代当主が貞観堂を建てた頃より庭園*を本格的に造り始める。代々手を加え、九代・十代の江戸末期から明治の始めに基礎が出来上がった。八代・九代当主は京都まで出掛けて学び、幕府の庭師の指導も受け、庭園を造った。越後の豪雪地帯に都の文化を取り込んだ苔の庭園である。1937(昭和12)年に名勝としての指定を受...

写真提供:柏崎市教育委員会博物館
綾子舞 ( 新潟県 柏崎市 )
綾子舞は柏崎市の中心から南へ16km離れた黒姫山の麓、旧鵜川村(現柏崎市)女谷の下野と高原田(たかんだ)で伝承されている古雅な民俗芸能である。 綾子舞は女性による小歌踊(こうたおどり)と男性による囃子舞(はやしまい)・狂言の3種類から成り立っている。 綾子舞の由来にはいくつかの説があり、小歌踊は今から約500年前、越後...
写真提供:一般社団法人糸魚川市観光協会
火打山 ( 新潟県 糸魚川市 / 新潟県 妙高市 )
妙高山の北西に連なり、標高2,462mは妙高火山群では最高峰で、長い稜線を引く不整三角形のやさしい感じの山容を見せる。しかし、高田平野以外、山容を山麓から望むところがないので、あまり知られていない山である。 一般的な笹ヶ峰から山頂へのルートは変化があり、楽しい。ブナ林、岩塊が露出する十二曲がり、オオシラビソの樹林帯を過...

写真提供:彌彦神社
彌彦神社 ( 新潟県 弥彦村 )
弥彦山の東麓に鎮座している越後一ノ宮である。神武天皇の命を受けて野積浜に上陸し、人々に製塩や漁労・農業技術を教えたと言われる、「産業の神様」である天照大神の曽孫天香山命が祭神である。 弥彦山頂には、天香山命と妃神熟穂屋姫命(ひめがみうましほやひめのみこと)を祀った御神廟(奥宮)がある。彌彦神社は古くから「おやひこ...

西福寺 ( 新潟県 魚沼市 )
室町時代後期1534(天文3)年に開山芳室祖春大和尚によって開かれた。 本堂は唐様で、江戸時代の建立。江戸末期1857(安政4)年に当山の23世によって建てられた開山堂は本堂の左手にあり、雪を防ぐため覆い屋根がかけられているが、ケヤキづくり・茅葺きの堂々とした大屋根である。内部の三間四方の天井と欄間には、道元禅師が宗で猛虎に...
写真提供:五泉市教育委員会
小山田ヒガンザクラ樹林 ( 新潟県 五泉市 )
江戸時代から知られている桜の名所で、その美しさに良寛の弟橘由之をはじめ、多くの文人が花見に来訪した記録が残る。サクラ並木は、寛永年間(1850年)ころ、旧川東村(現、五泉市)の斎藤源左衛門が衰えの見えた桜を補植、整備したと伝えられ、当時、サクラ並木は1,000本を数えたと言われる。このころ訪れた頼三樹三郎*は「花の吉野にまさ...
写真提供:アース・セレブレーション実行委員会
アース・セレブレーション ( 新潟県 佐渡市 )
佐渡市小木を拠点に活動する太鼓芸能集団「鼓童」は1981(昭和56)年に設立。1988(昭和63)年から国際芸術祭「アース・セレブレーション(地球の祝祭)」を佐渡で開始する。毎年、8月下旬の金曜日から日曜日の3日間開催。期間中、国内外のアーティストが佐渡に集い、佐渡島内外から大勢の人が訪れ楽しむ。 鼓童は佐渡南西部に位置する...
写真提供:一般社団法人佐渡観光交流機構
佐渡おけさ ( 新潟県 佐渡市 )
佐渡おけさの由来については諸説あるが、その前身は九州のハンヤ節といわれ、それが江戸時代、北前船の西廻り航路によって、関西から北陸・越後を経て佐渡に入り、今日の哀調を帯びたおけさになった。 「おけさ」は、新潟県内では、佐渡のほかにも、出雲崎、寺泊、小千谷、蒲原、魚沼地方にも伝わる。鉱山の作業歌であったおけさが、佐渡...

根本寺 ( 新潟県 佐渡市 )
国仲平野の中部、緑の森の中にある。1271(文永8)年佐渡に流された日蓮が配所した塚原*の三昧堂(さんまいどう)跡に建てられた寺で、日蓮宗十大聖跡の一つ。 参道は一周できるようになっていて、左手が行きで、戒壇塚、再建された三昧堂、二王門、二天門をくぐり鐘堂・経蔵・宝蔵・千仏堂がつづき、正面に祖師堂。右手に本堂がある。こ...

蓮華峰寺 ( 新潟県 佐渡市 )
蓮華峰寺の中心は金堂*であり、その西方に守り神である小比叡神社*があるという、寺院と神社が一体の区域の中に建てられており、神仏習合の面影を残している。 806(延暦25・大同元)年頃、空海が開いたと伝えられ、嵯峨天皇の勅願寺となったという由緒ある古寺。ここが京都の鬼門にあたるところから、比叡山にならって皇城鎮護のために...

写真提供:糸魚川市教育委員会文化振興課 フォッサマグナミュージアム
フォッサマグナパーク ( 新潟県 糸魚川市 )
フォッサマグナパークは、日本列島がアジア大陸から離れる時にできた「フォッサマグナ」*の西端にあたる「糸魚川―静岡構造線」を見ることができる公園。 屋外施設(無人)のため見学できる期間は、4月下旬から11月下旬までと限られる。
写真提供:Photo by Nakamura Osamu
大地の芸術祭 ( 新潟県 十日町市 / 新潟県 津南町 )
「大地の芸術祭」は、越後妻有地域の里山で開催される国際芸術祭である。2000(平成12)年に開始し、2018(平成30)年で第7回目を迎えた。基本理念は「人間は自然に内包される」。 越後妻有とは、十日町市と津南町にまたがる760km2、人口約5万人の地域である。十日町、川西、津南、中里、松代、松之山の各エリアに分かれ、それ...

写真提供:鈴木牧之記念館
鈴木牧之記念館 ( 新潟県 南魚沼市 )
越後の冬の風物や雪の中で暮らす様子をまとめた雪の本『北越雪譜(ほくえつせっぷ)』を世に出した鈴木牧之*(1770~1842年)の記念館。 牧之は、縮の仲買と質屋をする家業に生まれ、19歳ではじめて江戸に行ったことがきっかけで雪国の暮らしを伝えようと出版に生涯をかける。 雪の本の執筆活動には紆余曲折あったが、40年という歳月...

雲洞庵 ( 新潟県 南魚沼市 )
717(霊亀3・養老元)年に藤原房前(ふささき)公により、母の菩薩を弔うため律宗に属する尼寺を建立、雲洞寺と称した。1429(正長2・永享元)年、関東菅領上杉憲実公により曹洞宗寺院、金城山雲洞護国禅庵として開創され、日本一の庵寺、越後一の寺といわれた。 金城山を背にし、境内はスギの巨木に囲まれた幽すいさの漂う中に、本堂*・...

写真提供:八海神社
八海神社 ( 新潟県 南魚沼市 )
当時の国司であった中臣鎌足が八海山に不思議な雲がかかっている様を見て、従者数十人を引き連れて登山し、御祭神を奉祭したと伝えられる。 水分神・農耕神を崇める思想から始まり、山麓にて自然石を祀り、御神木を神の依り処として御山そのものを遥拝する形から信仰が始まった。1794(寛政6)年、木曽御嶽山を開いた普寛行者が来越し、屏...

普光寺(浦佐毘沙門堂) ( 新潟県 南魚沼市 )
JR浦佐駅を出て、浦佐のまちなかを通る旧三国街道から、堂々たる山門が目につく。山門は日光の陽明門をかたどり、江戸時代、1820(文政3)年から12年の歳月と10万余の信者の奉仕によって建立された。天井には、江戸時代に谷文晁が描いた双竜がある。2階天井には、天女の舞姿絵が見られる。 寺伝によると、807(大同2)年、坂上田村麻呂が...

写真提供:朝日町観光協会
朝日岳 ( 富山県 朝日町 )
飛騨山脈(北アルプス)の後立山連峰の北部に位置する標高2,418mの山。古成層の変成岩で構成されている。富山県朝日町の東南端にそびえ、新潟県との県境に位置する。南陵には雪倉山、白馬岳が控え、北稜は長栂山、黒岩山、犬ヶ岳と続き、やがて親知らずに至る。 朝日岳を含む白馬連山高山植物帯は、富山県の下新川郡朝日町と黒部市、長野...
洞杉 ( 富山県 魚津市 )
魚津市南東部の毛勝三山を源として富山湾に注ぐ片貝川の上流部・南又谷の500~700m付近を中心に樹齢500年以上と推定される天然スギ(タテヤマスギ・アシウスギ)が群生している。これらの群生するスギの古木は、幹に空洞ができることから地元では洞杉と呼ばれている。洞杉の多くは、何本にも枝分かれしながら巨大な石や露出した岩の上に乗る...
富山湾の埋没林 ( 富山県 魚津市 )
埋没林とは、「何らかの原因で林が地中に埋まり、現在まで保存されたもので、河川の堆積物に覆われたものや、地上で水成及び風成堆積物、火山の噴出物などに埋もれたもの」をいう。 魚津の埋没林は、河川の堆積物に覆われたのちに海水面下に没したもので、1930(昭和5)年、魚津港修築の際多くの古代の樹根が発掘された。この埋没林は約20...
富山湾の蜃気楼 ( 富山県 魚津市 )
蜃気楼とは、大気中の温度差によって光が屈折し、遠方の風景などが、伸びたり、反転した像が現れたりする現象のこと。魚津市の海岸は古くから蜃気楼の展望地として知られており、対岸の建物や航行中の船舶が伸びた姿などが見られる。蜃気楼には2種類あり、春の蜃気楼として有名な「上位蜃気楼」と冬の蜃気楼として知られる「下位蜃気楼」があ...
大岩山日石寺 ( 富山県 上市町 )
大岩山日石寺は富山地方鉄道上市駅から車で15分ほど南方(山側)に向かったところに位置する真言密宗大本山。寺院の縁起では、725(神亀2)年、遊行でこの地を訪れた行基*1が、凝灰岩の一枚岩に磨崖仏*2を彫ったことを開基とするといわれている。もとは高野山真言宗であった。室町時代には、21の末社・七堂伽藍・60の寺が建ち並び、千を超...
剱の大王杉 ( 富山県 上市町 )
剱の大王杉は剱岳の麓、上市町の早月尾根・松尾平(標高1,010m付近)の麓にある立山杉の巨木で、幹周りは約12m。早月尾根にある松尾平の麓、白萩川を見下ろす標高900~950mあたりに杉の巨木が何本も立ち並ぶエリアがあり、その最も奥に立つ。 一部の登山者の間では知られていたが、2004(平成16)年北日本新聞に取り上げられたことで知ら...
剱岳 ( 富山県 上市町 / 富山県 立山町 )
飛騨山脈(北アルプス)北部の立山連峰にある標高2,999mの山で、富山県の上市町と立山町にまたがる。山名の文字は2003(平成15)年に現在の「剱岳」に登録された。山頂から東側に、長次郎谷、三ノ窓、小窓、大窓とU字谷が並ぶ。山頂のわずかに西より、背骨のような早月尾根が登山拠点となる上市町馬場島との2,200m以上の高低差を急角度で結ん...

黒部峡谷 ( 富山県 黒部市 )
黒部峡谷は、北アルプスの中央部、雲の平の南方にある標高2,924mの鷲羽岳と2,721mの祖父岳付近を源として、富山湾に流れ込む黒部川が後立山連峰と立山連峰の間に刻み込んだ峻険な峡谷。黒部川の源流は雲の平の南側にあり、わずかな湧き水が雲の平を回り込む間に大量の水を加えて黒部川となっていく。黒部川は延長86kmと長さでは中級だが、滝...
黒部峡谷トロッコ電車 ( 富山県 黒部市 )
黒部峡谷鉄道株式会社が運営する黒部峡谷トロッコ電車は、黒部市の宇奈月駅から欅平駅までの黒部川沿いを走る黒部峡谷鉄道の列車。全長約20kmを片道約1時間20分で結んでいる。「トロッコ電車」はその愛称である。 黒部峡谷は水力発電による電源開発に適した地形であり、1919(大正8)年に東洋アルミナム株式会社が設立され、本格的な電源...

写真提供:YKKセンターパーク丸屋根展示館
YKKセンターパーク ( 富山県 黒部市 )
世界約70の国と地域で事業を展開しているYKKグループ*1は、黒部事業所の一部をYKKセンターパークとして一般に開放している。その園内には3つの展示館がある。丸屋根展示館1号館ではファスナーや窓の仕組みと歴史、創業者・吉田忠雄*2の企業理念について触れられる。YKKの技術を紹介している丸屋根展示館2号館では、海外へ初めて進出した際...

写真提供:小池岳彦
黒部五郎岳 ( 富山県 高山市 )
北アルプスの奥深く、立山連峰の南端に位置し、頂上は富山県と岐阜県の境となる(標高2,840m)。黒部源流の山々の中でも雄々しく、雄大な山である。頂上から大きなカールが形成されている。山頂には岩が積み重なっており、五郎というのは人名ではなく、岩のごろごろした場所を「ゴーロ」というところからきており、「黒部」にある「岩のごろ...
勝興寺 ( 富山県 高岡市 )
雲龍山勝興寺は、JR氷見線の伏木駅の西に立地する浄土真宗本願寺派の寺院である。1471(文明3)年、本願寺8世蓮如上人*が越中布教のため、現在の南砺市福光土山に開いた土山御坊が始まりと言われている。土山御坊は、蓮如の子孫が代々住職を務めるなど、本願寺と血縁関係のある寺院として強い勢力をもった。寺号の由来は1517(永正14)年、...
瑞龍寺 ( 富山県 高岡市 )
瑞龍寺は、あいの風とやま鉄道高岡駅の南、徒歩約10分。曹洞宗の寺院で、加賀2代藩主前田利長の跡を継いだ弟で3代藩主の利常が兄の菩提を弔うために建立したものである。隠居した利長は、当初富山城を隠居所としたが、火災により高岡に移り、この地で亡くなった。その後、利常は加賀藩御大工山上善右衛門嘉広に命じて七堂伽藍の大寺院を建立...
高岡御車山祭(高岡御車山祭の御車山行事) ( 富山県 高岡市 )
高岡の御車山行事は、1609(慶長14)年に前田利長が高岡に城を築いて町を開いたとき町民に御所車を与え、関野神社の春祭(御車山祭)に山車として神輿の巡行に伴って奉曳したのがはじまりといわれている。利長が与えた御所車は、父利家より譲り受けたものだが、伝承では、1588(天正16)年に豊臣秀吉が後陽成天皇を京都聚楽第に行幸を仰いだ...
雄山神社(峰本社・祈願殿・前立社壇) ( 富山県 立山町 )
雄山神社は、701(大宝元)年の立山開山*1にはじまる立山信仰*2を今に伝える神社で、祭神は、伊邪那岐神(いざなぎ)・立山大権現雄山神(本地・阿弥陀如来)、天手力雄神・刀尾天神剱岳神(本地・不動明王)である。立山の主峰である雄山に峰本社(奥社)をもち、麓の芦峅寺(あしくらじ)の祈願殿、さらに下った岩峅寺(いわくらじ)にあ...
黒部ダム(黒部湖) ( 富山県 立山町 )
黒部ダムは、富山県東部を流れる黒部川の標高1,454mの地点に、関西電力が建設した水力発電専用のダムである。堤高186mは日本一の高さで、アーチ式ダムとしては世界でもトップクラス。通称「くろよん」と呼ばれている*1。 1956(昭和31)年に着工、7年の歳月をかけて1963年(昭和38年)6月5日に完成した。工費は513億円、1,000万人もの人...
五色ヶ原 ( 富山県 立山町 )
立山の南側の標高2,400~2,500mに広がる高原で、北アルプスでは弥陀ヶ原に次ぐ広さをもつ。立山から薬師岳に続く縦走路の途中にある。立山火山(弥陀ヶ原火山)の噴火により流れ出した溶岩によって形成されたといわれている。北西側は立山カルデラ*と呼ばれる巨大な崩壊地があり、カルデラ壁には鷲岳、鳶山といった山がある。 高山植物で...
称名滝 ( 富山県 立山町 )
室堂平周辺の水を集めて流れる称名川が弥陀ヶ原にはいると、ほぼ垂直にその北端を削りとり、150m以上の深さに切れ込んだ峡谷の中を流れる。称名滝は、この立山の大噴火による溶結凝灰岩の台地を浸食してできたV字峡谷「称名廊下」の末端から、標高差350mの高さを落下する瀑布である。称名滝は、上から70m、58m、96m、126mの4段からなり、それ...
立山 ( 富山県 立山町 )
飛騨山脈(北アルプス)の北部に位置する。立山という独立峰はなく、狭義には雄山神社峰本社のある「立山山頂」または「雄山(おやま、標高3,003m)」と「大汝山(おおなんじやま、標高3,015 m)」と「富士ノ折立(ふじのおりたて、標高2,999 m)」の3つのピークを総称して立山と呼んでいる。古くは立山連峰全体を指していたと思われ、今でも...
立山地獄谷の温泉 ( 富山県 立山町 )
立山地獄谷は、立山・室堂平の北方約1km、標高2,300mに位置する高所の噴気地帯として知られている。弥陀ヶ原火山の約4万年前以降の火山活動によってみくりが池などと共に形成された。以前は谷の内側に山小屋があったが、火山性ガスの危険のために閉鎖された。現在は周囲にある「みくりが池温泉」、「らいちょう温泉雷鳥荘」、「雷鳥沢温泉(2...

立山のライチョウ ( 富山県 立山町 )
ライチョウは立山の自然環境を象徴する動物である。 日本のライチョウは、世界中のライチョウ(学名:Lagopus muta)の中で一番南に生息する亜種であり、氷河期に大陸から来た生き残りともいわれる。 本州中部の北アルプス、南アルプスなど標高2,200m以上の高山帯に生息。現在生息数は、生息環境の変化などにより2000羽を下回っている...
美女平の立山杉 ( 富山県 立山町 )
美女平は立山・黒部アルペンルートの玄関口で、麓の立山駅と立山ケーブルカーで結ばれ、標高977mに位置する。ここから標高1460mの上ノ小平上部にかけての美女平溶岩台地は、タテヤマスギとブナの巨木が集団で生育する森林となっている。このうちタテヤマスギは杉の変種のアシウスギの一種で、枝が垂れ、雪に耐える性質が特徴である。 富...
弥陀ヶ原 ( 富山県 立山町 )
立山の西側山腹の標高1,500mから2,400mに広がる立山の火山活動で形成された火砕流台地。河川による浸食等で成立し、現在では東西4km、南北2kmの東西に長細い形状の起伏に富んだ高層湿地*1である。広義では、美女平・下ノ子平・弘法平・追分平・天狗平・室堂平などを含めることもあるが、一般には室堂平などとは区別して、丸山台から追分平を...

雪の大谷 ( 富山県 立山町 )
雪の大谷とは、立山有料道路を除雪した際に現れる巨大な雪壁である。 立山黒部アルペンルートの室堂は標高2,450mの豪雪地帯で、室堂ターミナル付近にある「大谷」は吹き溜まりとなっているので特に積雪が多い。春先、この「大谷」を通る道路をGPSで確認しながら慎重に雪を削り取りながら掘り進めていく。除雪された道路の両側には深さ最...
大日岳 ( 富山県 立山町 / 富山県 上市町 )
弥陀ヶ原の北側に連なりを見せる山塊で標高は2,501m。大日岳・中大日岳(2,500m)・奥大日岳(2,606m)をもって大日三山とする記述を多くの登山書で見かけるが、富山県山名録では早乙女岳(2,093m)・大日岳・奥大日岳を大日連山としている。大日という名から分かるように、信仰の対象になっていた山で、大日如来体現の聖地であった。 189...

写真提供:一般社団法人 砺波市観光協会
庄川峡 ( 富山県 砺波市 )
庄川峡は、一級河川の庄川沿い、小牧ダム上流のダム湖から庄川水記念公園、庄川温泉郷までの地域を指す。 庄川は、岐阜県の鳥帽子岳を源とし、世界遺産の合掌造り集落で知られる五箇山の山懐を縫い、富山県南西部の砺波平野を通って富山湾に注ぐ北陸有数の大きな河川で、古くから、日本最大規模の散居村の穀倉地帯を支えてきた。また、昭...

写真提供:一般社団法人 砺波市観光協会
砺波平野のチューリップ畑 ( 富山県 砺波市 )
富山県はチューリップの球根出荷量日本一である。なかでも砺波市は最大の出荷量を誇り、県全体の4割強を占めるチューリップの里である。花の時期には、至る所で鮮やかなチューリップの絨毯を目にすることができる。 砺波市のある砺波平野は、県下で初めてチューリップ栽培が始められた場所である。大正時代、東砺波郡庄下村(現在の砺波市...

写真提供:一般社団法人 砺波市観光協会
砺波平野の散居村(散村) ( 富山県 砺波市 / 富山県 南砺市 )
富山県の西部に位置し、庄川と小矢部川によって作られた約220km2の扇状地・砺波平野では、50~100mほどの間隔で屋敷林に囲まれた7,000戸を超える農家が点在しており、このような集落形態を散村と呼んでいる。富山県内では「散居村(さんきょそん)」と呼んで親しまれてきた。 その成り立ちは、それぞれの農家が家の周りを開拓...
おわら風の盆 ( 富山県 富山市 )
おわら風の盆*1は、9月1日~3日に八尾町(現富山市八尾地区)で行われる祭りである。ここは、浄土真宗本願寺派の寺院・聞名寺の門前町として生まれ、江戸時代の町づくりにより発展した町である。「おわら風の盆」では、福島、下新町、天満町、今町、西町、東町、鏡町、上新町、諏訪町、西新町、東新町の町内11の地区で、それぞれ個性ある「...
雲ノ平 ( 富山県 富山市 )
富山市南部、飛騨山脈(北アルプス)の最奥部、黒部源流域に位置する標高約2,600mに広がる溶岩台地。面積は25万m2。黒部川の源流部にあたり、南、西、北を黒部川が取り囲んでいる。北アルプスの中でも最も奥深いところに位置し、どの登山口からでも当日中にたどり着くことが困難であり、「日本最後の秘境」、別名を奥の平とも呼ば...

神通峡 ( 富山県 富山市 )
飛騨山地を水源として北流する神通川が、飛騨山地から富山平野に抜ける間の峡谷である。かつては、豊かな水量と岩を嚙むような峡谷美を誇っていたが、ダムの建築により、今は満々と水をたたえた人造湖に変貌をとげ、季節の花や紅葉が水面に映え、静かな湖畔のたたずまいをみせている。 第一ダムの下流にある庵谷峠に登ると神通峡の展望を...
水晶岳(黒岳) ( 富山県 富山市 )
水晶岳は飛騨山脈(北アルプス)北部、富山市の南東部に位置する標高2,986mの山である。山頂は切り立った岩の双耳峰で針峰状の側壁に囲まれた急峻なカール地形をなしており、このあたりでの最高峰である。 水晶岳の名称は、水晶がとれたことによる。別名黒岳で、これは山肌が黒々としていることによる。日本百名山において深田久弥は「北...
富山城 ( 富山県 富山市 )
富山駅の南約1km、市街地のほぼ中央に富山城址公園がある。富山城は1543(天文12)年に畠山氏の守護代・神保長職が築城したことに始まり、江戸時代には前田氏の居城として整備され、富山藩政の中心であった。現在の城址公園は、主に本丸と西之丸の部分であり、当時はこの約6倍の広さがあった。公園として残された部分以外は、市街地となって...
富岩運河(富岩運河環水公園) ( 富山県 富山市 )
「富岩運河」は、富山市と当時の東岩瀬町をつなぐ運河である。富山城の外堀でもあった神通川は、富山市中心部で大きく蛇行しており、たびたび洪水を引き起こしていた。富山県はその流れを直線化する工事に1901~1903(明治34~36)年に着手。その工事で生まれた広大な廃川地対策として、東岩瀬港から富山駅北まで約5kmの運河を作り、運河を掘...
松川のサクラ ( 富山県 富山市 )
富山市の中心部を流れる松川は、富山城の外堀・神通川の名残りである。松川の川辺には、上流の磯部の布瀬橋から、いたち川合流点下流の宮下橋まで、右岸側と左岸側合わせて3.9km(右岸・左岸どちらかに桜のある川の距離としては約2.5km)にわたり、ソメイヨシノが530本植えられている。 富山藩10代藩主前田利保は、隠居所として建てた千歳...
薬師岳 ( 富山県 富山市 )
飛騨山脈(北アルプス)北部の立山連峰南部に位置し、標高は2,926m。立山(たてやま)や剱(つるぎ)岳の峻険(しゅんけん)な山容に比べ、雄大だが穏やかな山容を示しており、重量感のあるどっしりとした山容は北アルプス随一だといわれる。薬師岳は山麓有峰の住民の信仰の山で、頂上には薬師堂が祀られている。立山などと同様に、薬師岳も...
常願寺川 ( 富山県 富山市 / 富山県 立山町 )
常願寺川は富山県と岐阜県の県境にある北ノ俣岳(標高2,661m)から流れる真川と、立山カルデラを源とする湯川があわさり常願寺川となり、さらに千寿ヶ原で称名川と合流して富山県の中央部を北流し、富山湾に注いでいる。流路延長約56km、河床勾配は山地部で約1/30、扇状地部で約1/100の、日本有数の急流河川である*1。古くは「新川(にいか...

写真提供:富山県 立山カルデラ砂防博物館
立山カルデラの山体崩壊 ( 富山県 富山市 / 富山県 立山町 )
立山カルデラは立山連峰の南西、室堂平から弥陀ヶ原の南に位置する東西6.5km、南北4.5kmの楕円形の大規模なくぼ地である。この地形は4万年前頃まで活動した弥陀ヶ原火山などが地震や大雨などにより侵食されてできた「侵食カルデラ」と考えられており、日本有数の巨大崩壊地形である。 周辺には跡津川断層をはじめいくつもの活断層が分布し...
ホタルイカ漁 ( 富山県 滑川市 )
ホタルイカは、世界中で日本近海にのみ生息する小型の発光イカで、「ホタルイカ」の名前は1905(明治38)年、ホタルの生態調査を行っていた東京帝国大学の渡瀬庄三郎博士が名付けたとされており、学術名の「Watasenia scintillans(Berry, 1911)」は渡瀬博士に由来する。富山県の漁村では、古くは「マツイカ」「コイカ」などと呼ばれており...

写真提供:井波別院瑞泉寺
井波別院瑞泉寺 ( 富山県 南砺市 )
井波別院瑞泉寺は、富山県南砺市(旧井波町)にある1390(明徳元)年、本願寺第5代の綽如(しゃくにょ)によって開かれた浄土真宗の真宗大谷派寺院である。明から送られてきた難解な国書を綽如が解読したことから、後小松天皇より才と功績を認め、一寺寄進を申し出られたと伝わる。その後は北陸の浄土真宗信仰の中心としての役割も果たすとと...

五箇山の合掌造り集落 ( 富山県 南砺市 )
五箇山は、富山県の西南端部、庄川の上流および支流利賀川に沿う地域で、上梨谷・下梨谷・赤尾谷・小谷・利賀谷の5つの谷間(やま)の総称といわれる。1,500m級の山々に囲まれた豪雪地で、合掌造りの家屋で知られ、岐阜県の白川郷荻町とともに相倉集落、菅沼集落がユネスコ世界遺産に登録されている。 合掌造りは豪雪地帯である五箇山・...
城端曳山祭(城端神明宮祭の曳山行事) ( 富山県 南砺市 )
城端曳山祭は城端神明宮の春の例祭として、5月4日に宵祭、5月5日に本祭が執り行われる。その起源は、1717(享保2)年に神輿がつくられ獅子舞や傘鉾の行列が始まり、1719年には曳山が創始され1724年には神輿の渡御にお供したと伝わる。城端曳山祭の舞台である城端は、砺波平野の南端に位置しており、浄土真宗大谷派の城端別院善徳寺の寺内町と...

写真提供:一般社団法人 氷見市観光協会
氷見の寒ブリ料理 ( 富山県 氷見市 )
富山湾のブリ漁は、越中式定置網であり、大型のもので水深50~70mのところに4~6kmの網を起こす。12月、海が荒れ激しく鳴り響く雷を「ブリ起こし」という。これが富山湾のブリの季節の到来を表す。富山湾で獲れるブリは越中ブリとして昔から人気があり、高級品でもあった。塩ブリとなって飛騨高山、さらには野麦峠を越え、信州の松本や諏訪地...

シロエビ料理 ( 富山県 富山市 / 富山県 射水市 )
シロエビは富山湾独特の海底谷「藍瓶(あいがめ)」に群泳する体長は約6センチほどのエビ。水揚げ直後、透明感のある淡いピンク色をした姿から「富山湾の宝石」とも呼ばれる。ブリやホタルイカと並んで「富山県のさかな」*のひとつであり、富山湾の海の幸を象徴する食材になっている。標準和名は「シラエビ」だが、地方名あるいは商品名とし...
妙成寺 ( 石川県 羽咋市 )
北陸における日蓮宗の本山で、能登一の大伽藍を誇る名刹である。羽咋市北部の丘の上にあり、シンボルの五重塔*が聳える。1294(永仁2)年、日蓮の孫弟子日像が開祖*し、建立したと伝えられている。現在の建物は加賀前田家初代から五代にわたって造営されたもので、天災・火災にあわず、10棟*が国の重要文化財に指定されている。 前田家...
氣多大社 ( 石川県 羽咋市 )
能登一ノ宮として知られ、かつては国幣大社に列せられていた。羽咋駅の北方約4km、海を望む高台にあり社叢を背に神門・拝殿・本殿・摂社などが並ぶ。創建年代は明らかでないが、古くは崇神天皇が社頭を造営したといわれ、大己貴命(オオナムチノミコト)を祀っており、奈良時代にはこの地で祭祀が始まったとされている。大伴家持が参詣した際...
片野鴨池の坂網猟 ( 石川県 加賀市 )
加賀市街の北西部にある「片野鴨池」は、日本海にほど近い約10万㎡の自然の池で、水田と山林が混在する丘陵に囲まれている。シベリアから飛来する渡り鳥の越冬地として知られ、とくにカモ類のうち、全国的に個体数の少ないトモエガモにおいては、日本に越冬する中の約半数が鴨池に飛来する。この池のカモを捕える古式猟法が「坂網猟」である...

写真提供:(一社)山中温泉観光協会
山中温泉 ( 石川県 加賀市 )
山中温泉は、大聖寺川の渓流に臨み、東からは東山が、西からは水無山・薬師山が迫り、四方がほとんど山に囲まれた文字どおり山中の湯の町である。温泉の歴史は古く、医王寺に伝わる「山中温泉縁起絵巻」には、1300年前の天平年間(729~749年)に僧行基*によって温泉が発見され、 一時荒廃するも、長谷部信連(はせべのぶつら)*によって...

写真提供:山代温泉観光協会
山代温泉 ( 石川県 加賀市 )
山代温泉は、加賀平野の南のはずれ、薬師山をはさんで山中温泉と背中あわせの地にある。725(神亀2)年に行基が開湯したという伝承があり、その後、10世紀後半(985~988年)に花山法皇が明覚上人を従えて北陸巡歴*のおり、この温泉に入浴、その効が優れているとして温泉寺を中興、七堂伽藍を建立したとされている。 また、1565(永禄8)...
加賀東谷の町並み ( 石川県 加賀市 )
加賀市南部の山間部は、近世には大聖寺藩の奥山方に属し、藩の御用炭を生産しており、近代から昭和前期にかけても大半の集落が炭焼きを主産業としていた。昭和30年代以降、ダム建設や災害、離村などにより失われた集落があるなかで、大日山を源とする動橋(いぶりはし)川と杉ノ水川の上流域に点在する荒谷(あらたに)、今立(いまだち)、...
橋立町の船板住宅群 ( 石川県 加賀市 )
石川県南西部に位置し、JR北陸本線加賀温泉駅から北西へ約5km。橋立は、かつて北前船の船主や船頭、船乗りなどが多く住んでいたまちで、日本でも1、2を競う富豪村と呼ばれていた。北前船とは、大坂と蝦夷地(北海道)を結び、瀬戸内海と日本海の各港に寄港して積荷を売買する商売をしてまわった買積船で、近世後半から明治期にかけて盛んに活...

尾山神社 ( 石川県 金沢市 )
尾山神社は、金沢市の中心市街地香林坊の北にあり、主祭神は加賀藩祖前田利家公とお松の方。 1599(慶長4)年、卯辰八幡宮として創建されたものが、1873(明治6)年に現在地へ遷座し、尾山神社となった。神門は重要文化財に指定されている。
金沢城 ( 石川県 金沢市 )
浅野川と犀川にはさまれた小立野台地の北西端に位置する。面積は堀を含めて約30万㎡、最高所は本丸跡の海抜約60mで、南東へ延びる小立野台地とは百間堀によって分かれている。城内の建物は1881(明治14)年の大火で大部分を焼失し、今ではわずかに石川門などが往時の威容をとどめている。 〔歴史〕佐久間盛政が4年間居城とした尾山城に158...
卯辰山山麓寺院群 ( 石川県 金沢市 )
金沢駅の東方、卯辰山の西麓から山腹にかけて約50の寺院が散在している。1599(慶長4)年に前田利家を祀る宇多須神社、1601(慶長6)年には豊臣秀吉を祀る豊国神社(卯辰山王社)を建立し、歴代藩主が崇敬した。一方、前田家の祈願所である観音院が広大な境内を占めており、卯辰山は加賀藩の宗教空間として特別な意味を持つエリアでもあった...
兼六園 ( 石川県 金沢市 )
金沢市内中央部、金沢城跡の南東に隣接する、江戸時代を代表する大名庭園。築山や茶屋が点在し、曲水が巡る美しい林泉回遊式庭園で、日本三名園*のひとつに数えられている。1676(延宝4)年より5代藩主綱紀(つなのり)の時代に最初の庭(蓮池庭)が造られ、1822(文政5)年に12代藩主斉広(なりなが)が竹沢御殿を建てるに際し、御殿に付属...
石川県立能楽堂 ( 石川県 金沢市 )
「石川県立能楽堂」は、百万石の城下町金沢に伝わる加賀宝生流の能楽をはじめ、邦楽など伝統芸能の継承と振興を目的として建設された。兼六園の南東にあり、舞台および白洲(しらす)を旧金沢能楽堂より移したもので、約400名の収容力と近代的設備をもつ。能楽文化の拠点として、1972(昭和47)年に、全国で初めて、独立した公立能楽堂として...

写真提供:金沢市
前田家墓所 ( 石川県 金沢市 )
金沢市街の南、野田山丘陵の傾斜地にある、加賀藩前田家歴代の藩主・正室および一族の墓地。加賀藩藩祖の前田利家(としいえ)の遺言でこの地に墓が造られて以降、歴代藩主や正室、子女など、約80基が一堂に会す。6万㎡を超える広い墓所に並ぶ墓のほとんどは、土を盛った古墳式で、石の墓標が立てられている。なお、墓所の中で6代吉徳の左に...

写真提供:金沢市
にし茶屋街 ( 石川県 金沢市 )
ひがし茶屋街、主計町茶屋街と並ぶ金沢三茶屋街のひとつ。茶屋街のエリアはそれほど広くないものの、約100mのメインストリートには出格子の茶屋建築が連なり、江戸時代の面影を色濃く残している。現役の茶屋も多く、芸妓も活躍している。茶屋の跡地に建つ金沢市西茶屋資料館は見どころのひとつ。隣接する西検番事務所は芸妓衆の稽古場と事務...

写真提供:七尾市産業部交流推進課
青柏祭 ( 石川県 七尾市 )
5月3~5日に行われる大地主(おおとこぬし)神社の例祭。祭りの起源については、981年(天元4)年に能登国国守の源順が能登国の祭りと定めたことに始まり、1473(文明5)年の国祭りで、京都の祇園祭の山鉾にならって曳山を奉納したのが山車の始まりという説があるが、明確ではない。悪事を行って白狼に退治された3匹の大猿の慰霊のために3台...

写真提供:七尾市産業部交流推進課
石崎奉燈祭 ( 石川県 七尾市 )
漁業が盛んで、能登国守護畠山氏から能登・越中一円の漁業権を免許されていたという伝承をもつ石崎町(いしざきまち)にある八幡神社の例祭。もともと祇園祭の流れを汲む納涼祭として行われていたが、何度も火事に見舞われて山車が焼け、明治時代の中頃に宇出津からキリコ(奉燈)を譲り受け、大漁や五穀豊穣の祈願とともに火を鎮める神事と...
和倉温泉 ( 石川県 七尾市 )
北陸随一の規模を誇る”海の温泉”として、高温で豊富な湯量が魅力の温泉である。七尾湾に突き出た弁天崎の先端にあり、湾前に能登島や机島を望む。温泉の湧出は1200年前と伝わり、その後の地殻変動で湧き口が海中に移動したとされ、傷ついた足を癒すシラサギを見つけた漁師夫婦によって湯脈が発見されたという伝説がある。海中に湧き口があっ...
見附島 ( 石川県 珠洲市 )
能登半島の珠洲市の南部、鵜飼川河口一帯は、松林越しに内浦の海を望む穏やかな海岸である。その中央部に周囲約300m、高さ28mの大きな岩がそびえ立つ。市内にある式内社三社の一つである加志波良比古(かしはらひこ)神社の神(加志波良比古)が、当地に着いた際に初めて見つけた島、また弘法大師が佐渡から能登へ渡った際に最初に目についた...

写真提供:石川県観光連盟
奥能登の黒瓦の集落群 ( 石川県 珠洲市 / 石川県 輪島市 / 石川県 能登町 / 石川県 穴水町 )
「能登には、黒瓦の屋根と下見板張りの伝統的な住居が多く、統一感のある景観と独特の風情を生み出している。黒瓦は、「能登瓦」とも呼ばれ、材料に能登の水田の土を使い、山の薪を燃料にして、七尾市や珠洲市などの農村地帯で生産されてきた。黒あるいは銀黒の美しい釉薬で覆われた能登瓦は、耐寒性に優れるといわれている。輪島市の黒島(...
那谷寺 ( 石川県 小松市 )
粟津温泉から山代温泉へ向かう県道が加賀市に抜ける1kmほど手前に立つ。717(養老元)年に泰澄大師によって創建されたと伝わり、自然智の道場とされる。その後、寛和年間(985~987年)に花山法皇がこの寺に御幸した折り、観音三十三身の姿を見て西国三十三ケ所を巡る必要はないとして、第1番札所の紀伊那智山と第33番札所の美濃谷汲山の山号...

こまつの杜 ( 石川県 小松市 )
建設・鉱山機械メーカーのコマツ(登記社名:株式会社 小松製作所)が、会社創立90周年の記念事業の一環として、会社発祥の地である小松工場跡地に整備した施設で、2011(平成23)年5月13日に誕生した。 コマツグループ社員のグローバルな人材育成の機能を担う「コマツウェイ総合研修センタ」、「テクノトレーニングセンタ」等の社員研修...
九十九湾 ( 石川県 能登町 )
深い入り江が大小九十九もあるとされることから名付けられた、典型的なリアス海岸*の小湾である。江戸時代中期に著わされた「能登名跡誌」には、「風景日本の三景にもひとしき處也。誠に風景仙境共云つべし」とあり、古くから景勝地とされていた。東西1km、南北1.5kmの小さな湾だが、入り組んだ延長13kmにもおよぶ海岸線には赤松が生い茂り...

あばれ祭 ( 石川県 能登町 )
7月の第1金・土曜日に、能登各地のキリコ祭りの中で最初に開催される。宇出津の八坂神社の夏祭りで「いやさか祭り」ともいう。祭りの起源は、江戸時代初期に疫病が大流行した際に、京都の祇園社(八坂神社)から牛頭天王を勧請して神事を行ったところ、神の化身とされる大きな青蜂が現れ、刺された人々が快癒したことに感謝し、お礼としてキ...
白山 ( 石川県 白山市 )
富士山や立山と並ぶ三名山の一つ。火山としては比較的小規模だが、白山火山帯の主峰として、山域は石川・富山・岐阜・福井の4県にまたがっている。万年雪を頂いた優美な姿は古くから信仰の対象として仰がれ、「越のしらね」、「しらやま」などと古歌*に詠まれてきた。最高峰は御前峰*(2,702m)で、北西の大汝(おおなんじ)峰*(2,684m)...
手取峡谷 ( 石川県 白山市 )
鶴来地域から山間部に入ると、手取川は狭い河岸段丘の下に深い谷をなし、中流域の黄門橋~対山橋間の約8kmにわたって高さ20~30mの絶壁が続く峡谷美をつくっている。清冽な流れは淵となり、瀬となり、幾条もの滝が白い飛沫を上げて岩壁を滑り落ち風情を添える。おもな景観に、黄門(こうもん)橋・御仏供杉(おぼけすぎ)・不老橋・綿ヶ滝、...
白山比咩神社 ( 石川県 白山市 )
「白き神々の座」と言われる白山をご神体とする延喜式内の名社。加賀一ノ宮で、古くから下白山あるいは白山本宮と呼ばれ、地元では「白山(しらやま)さん」として広く親しまれている。白山頂上の御前峰に奥宮を祀り、全国約3,000社以上に及ぶ白山神社の総本宮として、白山信仰*の中心となっている。祭神は白山比咩大神・伊弉諾尊・伊弉冉尊の...

写真提供:白山手取川ジオパーク推進協議会
岩間の噴泉塔群 ( 石川県 白山市 )
白山国立公園の地獄谷に源を発する中ノ川の上流域に点在しており、一帯は国の特別天然記念物に指定されている。噴出する温泉に含まれる石灰質分が沈殿してできる石灰華が釣鐘型の塔状になったもので、高さ4mに達するものもある。先端の噴気孔から100度近くの熱湯が勢いよく噴き出し、2~3mの高さに湯煙を上げるものもある。噴泉塔の形成につ...
總持寺祖院 ( 石川県 輪島市 )
輪島市門前町の中央、八ガ川の南にあり、山内の広さが約2万坪とされる風光幽玄な寺院。正式名称を諸嶽山總持寺といい、越前の永平寺とともに曹洞出世之道場として栄えた曹洞宗の大本山である。1321(元亨元)年、瑩山紹瑾(けいざんじようきん)*によって開かれ、2世峨山韶碩(がざんしょうせき)が定めた五院輪住制*により発展。前田氏の...
白米千枚田 ( 石川県 輪島市 )
輪島市白米町の国道沿いに広がる。山裾が落ち込む海に面した3.8haの斜面に1,004枚の小さな田が段々に並び、畦が美しい模様をつくっている。平野の少ない輪島は急傾斜地が多く、昔から地滑りに悩まされてきた。それでも、この土地は用水源が確保されれば地味が良く、適当な日当たりがあって良質の米が採れたため、幾つにも斜面を分けて田んぼ...

輪島の朝市 ( 石川県 輪島市 )
日本三大朝市*の一つとされる。輪島の市の起源については明確ではないが、平安時代には市が立ち、室町時代には定期的に開催されるようになったといわれている。現在のように市が毎日立つようになったのは明治時代からで、午前8時を過ぎると、通称「朝市通り」と呼ばれる河井町本町通り商店街の道路両側に、約350mにわたって約160の露店が並ぶ...

名舟大祭(御陣乗太鼓) ( 石川県 輪島市 )
舳倉島の奥津比咩神社の大祭で、7月31日~8月1日に行われる。奥津比咩神社は名舟の産土神といわれ、名舟大祭はまず、急陵な崖に張りつくように鎮座する奥津比咩神社の遥拝所である白山神社に各地区のキリコが参集。その後、海上の鳥居まで白山神社から下った神輿を乗せた舟を漕ぎ出し、奥津比咩の神を迎える神事から始まる。護岸堤に仮設した...
七尾城跡 ( 石川県 七尾市 )
七尾市街地の南東約4kmにある、戦国時代に能登国の守護・畠山氏が築いた山城である。標高約300mの本丸を中心に、石動山系の尾根上に築かれた城域は南北約2.5km、東西約0.8km、面積は約200haにおよび、一帯は「城山」と呼ばれている。山が急で谷が深いという自然の地形を巧みにいかし、七尾の地名の由来となった7つの尾根筋を中心に屋敷地であ...
雨の宮古墳群 ( 石川県 中能登町 )
眉丈山(標高188m)の山頂を中心に、4世紀の中頃から5世紀の初めにかけて造られた古墳群で、現在、36基が発見されており、大部分が円墳である。雷ヶ峰の通称で呼ばれる山頂に築かれた1号墳は墳丘長が64mで、前方後方墳としては県内最大規模とされる。この1号墳の北東に向き合うように築かれた2号墳は、墳丘長が約65mの前方後円墳。いずれの古...

永平寺 ( 福井県 永平寺町 )
全国に1万5,000の末寺、檀信徒800万人をもつ曹洞宗の大本山で、開祖道元(どうげん)*が坐禅修行の場として志比谷最奥部のこの地を選んで以来、約770年にわたって法燈を伝えてきた古刹である。 1244(寛元2)年、京都深草に開庵していた道元が、志比庄地頭波多野義重の請に応じて越前に下り、開山したと伝える。当初は傘松峰大仏寺(さん...

紙祖神岡太神社・大瀧神社 ( 福井県 越前市 )
紙祖神岡太神社・大瀧神社は権現山の頂にある上宮(奥の院)とその麓に建つ下宮からなる。上宮は簡素ながら大瀧神社*と岡太神社、八照宮の三殿が並び建ち、下宮は両社の里宮となっている。 歴史の上では岡太神社が古く、今より1500年ほど前、この里に紙漉きの業を伝えた女神・川上御前を紙祖として祀り、「延喜式神名帳」(926(延長4年...

越前和紙の里 ( 福井県 越前市 )
越前和紙の歴史は古く、およそ1500年前の継体(けいたい)天皇の時代に、岡太(おかもと)川のほとりで女神から製造技術を教えられたという伝説*が残っている。 奈良時代に宮中御用の教書紙となり、中世以後、「越前奉書紙」と呼ばれて広く世に知られるようになった。戦国時代は「紙座」により、江戸時代には福井藩によって保護された。...

瀧谷寺 ( 福井県 坂井市 )
真言宗智山派の寺。えちぜん鉄道三国芦原線三国駅の北500mの丘陵上にあり、昼でもほの暗い杉木立ややぶツバキに囲れたゆるやかな笏谷石(しゃくだにいし)の石畳の参道を登りきると、山門(鐘楼)に至る。山門をくぐると、正面右手から観音堂、本堂、庫裏が並ぶ。観音堂正面には、前庭園石庭がある。国指定名勝の庭園*は本堂より書院ににわ...

東尋坊 ( 福井県 坂井市 )
国の天然記念物・名勝に指定されている東尋坊。巨大な柱状の岩(柱状節理*)が約1kmにわたり広がる豪快な景観が特徴。 長い年月をかけて日本海の波や風に浸食された荒々しい風景に悠久の大自然を感じることができる。
写真提供:三国祭保存振興会
三国祭 ( 福井県 坂井市 )
山車に5~6mの人形をのせ、そのできばえを競い合うというもので、各町内からの6台の山車が町中を練り歩く。湊町三国の栄華と町民の気概が受け継がれている祭りである。三國神社で5月15日の宮開式から21日の後日祭まで執り行われる神事で、祭りは、5月19日から21日まで開催され、中日の20日が山車巡行日となる。 三国祭りを特徴づける山車...
写真提供:一般社団法人若狭美浜観光協会
水晶浜 ( 福井県 美浜町 )
JR小浜線美浜駅の北東、敦賀半島の西側中央に位置する。ビーチから常神半島が一望できる。白砂の粒がたいへんきめ細かく、水晶のように輝く砂浜ということで、この名前がついた。透明度も高く、日本の水浴場88選の一つでもある。 両サイドは、山が海に落ち込み、その先端は岩礁となり、浜は弧を描く。浜の西側(海に向かい右手)は鳴き砂...

平泉寺白山神社(白山平泉寺) ( 福井県 勝山市 )
勝山の東南約4kmの山腹、白山神社の境内の一帯はかつて中世に隆盛を誇った天台宗平泉寺のあったところである。寺跡周辺は源平時代に城として利用されたこともあり、「白山平泉寺城跡」として史跡に指定されている。 白山神社は養老年間(717~724年)、泰澄*の草創と伝えられ、平泉寺はその別当寺として修験僧多数を擁して繁栄し、室町前...
写真提供:勝山市
勝山左義長まつり ( 福井県 勝山市 )
地元では「さぎっちょ」と呼ぶ。左義長*は古く平安朝の頃から正月に行われた行事のひとつで、全国で行われる小正月(1月15日)火祭りである。 勝山左義長は、1691(元禄4)年、小笠原公入封以来300年余の歴史を誇り、2月の最終土日、各町内に数基の櫓を立て、赤い長襦袢を着用し太鼓をたたきながら、三味線、笛、鉦の囃子に乗って「蝶よ...

明通寺 ( 福井県 小浜市 )
北川の支流、松永川を8kmさかのぼった上流にある。橋を渡って参道を行くと山門があり、一直線に行ったところに本堂*、三重塔*が、杉木立に囲まれた境内に美しい姿を見せている。 この寺は、蝦夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷征代による多くの犠牲者を弔い平和を願い、806(大同元)年に建立したと伝えられる。中世以前の沿革は判然としてい...
写真提供:公益社団法人福井県観光連盟
蘇洞門 ( 福井県 小浜市 )
大断崖として有名な蘇洞門は、日本海に突き出した内外海(うちとみ)半島の先端、久須夜ガ岳(くすやがたけ)の北の山裾が外海に洗われてできた豪壮な景勝地である。荒波は花崗岩を柱状節理に沿って浸食し、松ヶ崎の小山付近から白石黒石(しろいしくろいし)まで約6kmの間を奇岩、洞門、洞窟、断崖などに造りあげたのである。 遊覧船*は...

若狭彦神社・若狭姫神社 ( 福井県 小浜市 )
JR東小浜駅からまっすぐ南、若狭姫神社(若狭国鎮守二宮、下社、下宮)が、さらに遠敷川沿い1.5kmほど上流に行ったところに若狭彦神社(若狭国鎮守一宮、上社、上宮)が鎮座する。創建は彦神社が715(霊亀元)年、姫神社が721(養老5)年と伝え、若狭最古の神社である。 祭神は彦神社が天津彦火火出見尊(あまつひこほほでみのみこと、山...
写真提供:大野市
越前大野城 ( 福井県 大野市 )
市街の西部、標高249mの亀山山頂に建つ2層3階の天守は、大野のシンボルとなっている。 1575(天正3)年、織田信長より大野郡の3分の2を与えられた金森長近*によって、1576(天正4)年から約4年の歳月をかけて築城された平山城で、以後明治まで19代の領主の居城となった。本丸には2層3階の大天守、2層2階の小天守、山の麓には二の丸、三の...
写真提供:大野市
荒島岳 ( 福井県 大野市 )
隣の石川県出身の深田久弥*が『日本百名山』に選んだ福井県唯一の山であり、四季を通じて全国からの登山者が訪れる。 1,523m。山の歴史は古く、泰澄大師の開山と伝えられ、風土記には「蕨生(わらびょう)山」、延喜式には「阿羅志摩我多気」と書かれていて、古くから信仰の山として崇められ、山頂には祠が祀られている。 白山火山帯...

越前陶芸村 ( 福井県 越前町 )
越前焼*の歴史は、約850年前の平安時代にさかのぼる。室町時代後期に、日本海沿岸を流通圏に収め、生産は最盛期を迎えた。しかし、明治末から大正時代にかけて窯元の廃業が相次ぎ、絶滅に瀕した。 再び注目されるようになったのは戦後で、越前焼は「日本六古窯*」の一つになり、越前焼産地の拠点として、1971(昭和46)年に越前陶芸村が...
写真提供:敦賀市
敦賀まつり ( 福井県 敦賀市 )
毎年、9月初めに行われる敦賀まつりは、氣比神宮例祭に合わせて開催される。氣比神社例祭は氣比の長祭といわれ、9月2日に始まり4日までが祭りの山であるが、5日から10日に後日祭があり、15日の月次祭で終了する。祭りのハイライトは山車(やま)6基が勢ぞろいする4日目の山車巡行である。 山車の起源は定かではないが、室町末期には成立し...

西福寺 ( 福井県 敦賀市 )
敦賀市内の西部、大原山(おおはらさん)西麓にある。浄土宗鎮西派。1368(応安元)年、後光厳天皇の勅願所として、良如上人*が開山した。浄土宗の中本山で、時の朝廷や室町幕府、戦国大名や領主の崇敬も篤く、禁制には松平家と関係深く、北国浄土宗の中心寺院として、「越の秀嶺」の別称の格式をもっていた。 樹木に囲まれた広い境内に...

一乗谷朝倉氏遺跡 ( 福井県 福井市 )
福井市街の南東約10kmの一乗谷は戦国大名の雄朝倉氏*が5代103年間にわたって本拠地とし、独特の文化をはぐくんだところ。 1573(天正元)年8月、織田信長軍に与する平泉寺衆徒の放火により、栄華をきわめた城下町は灰燼に帰した。その後越前支配の中心は北ノ庄に移り、一乗谷は農地として維持された。それがかえってよく、昭和初期に往時...

福井県年縞博物館 ( 福井県 若狭町 )
特徴的な縞模様の地層「年縞(ねんこう)」をテーマにした世界初の博物館。三方五湖の一つ、水月湖の湖底には世界最長となる7万年分もの連続した年縞が形成されている。水月湖では直接流れ込む大きな河川がない、水深が深く生物が湖底に生息できないなど、年縞が形成されるための奇跡的な条件がそろっている。水月湖の年縞は考古学などにおけ...

羽賀寺 ( 福井県 小浜市 )
小高い山と北川に囲まれて広がるのが、中世荘園の一つであった国富荘である。羽賀寺はこの国富荘の裾に閑静にたたずんでいる。鳳凰が飛来し、羽をこの地に落としたことから鳳聚山羽賀寺と名付けられた。 716(霊亀2)年、奈良朝の女帝元正天皇が僧行基に命じて、羽賀寺を創建したと伝えられ、元正天皇の勅願所となった。947(天慶10・天暦...
ほうとう ( 山梨県 甲府市 / 山梨県 甲州市 / 山梨県 笛吹市 / 山梨県 富士河口湖町 / 山梨県 身延町 )
独特の麺を味噌仕立ての汁で煮込む山梨県の郷土料理のひとつ。「ほうとう」に使う麺は、うどんとは異なり、塩を加えずに麺を打ち、ねかさずにそのまま切って味噌仕立ての汁で煮込む。このため、麺の煮崩れがおこりやすく、汁にとろみがつくのが特徴。具にはジャガイモ・ナス・ネギなどのたくさんの野菜を入れることが多く、とくに冬に旬とな...

恵林寺 ( 山梨県 甲州市 )
JR中央本線塩山駅の北西4kmにある。1330(元徳2)年に甲斐牧ノ庄(現・山梨市牧丘町等)の地頭職二階堂出羽守貞藤が自分の邸宅を禅院として夢窓国師*を招き開創した古刹であり、本堂裏には夢想国師作庭の庭園*が現存している。1564(永禄7)年に武田信玄*が快川国師*を招いて寺領を寄進し菩提寺とした。 信玄が病死してから3年を経た1...

写真提供:甲州市観光協会
大菩薩嶺 ( 山梨県 甲州市 / 山梨県 丹波山村 )
JR中央本線塩山駅から北東10kmほど先に、なだらかなカヤトの原の尾根が目立つ山がある。これが大菩薩嶺*(標高2057m)であり、連なる峰々と合わせ大菩薩連嶺とも呼ばれている。山頂からカヤトの原の尾根を南に下ると、介山荘がある大菩薩峠(標高1897m)となる。大菩薩峠から南に突き出た山陵は南大菩薩嶺と呼ばれ、小金沢山・牛奥雁ケ腹摺...

写真提供:天目山栖雲寺
栖雲寺 ( 山梨県 甲州市 )
JR中央本線甲斐大和駅から東北へ約6km、景徳院*を経て日川渓谷*沿いにさかのぼった山中にある。1348(貞和4)年、「元」の天目山(中国・浙江省杭州市)で修行した業海本浄*によって創始されたため、山号は天目山。兵庫県の高源寺*を西天目というのに対し東天目とも呼ばれている。武田氏の菩提寺として庇護され、武田信満*の墓もある。...

大善寺 ( 山梨県 甲州市 )
JR中央本線勝沼ぶどう郷駅から南へ3kmほど、国道20号沿いのブドウ畑と日川を見渡せる山腹にある。創建については、諸説*あり不詳だが、代表的なものとしては、江戸後期編纂の「甲斐国志」によると「寺記曰、元正天皇養老二年(718年)八月、行基菩薩草創 号柏尾山 聖武天皇勅賜鎮護国家大善寺定額並御祈願所宣旨」とあり、また、「天文十...
甲府盆地のブドウ畑 ( 山梨県 甲州市 )
甲府盆地は内陸性気候で、降水量が少なく、日照時間も長く、昼夜、季節の寒暖差が大きいという気象条件と、扇状地などの傾斜地が多く、標高差があるという地形的な条件から果実栽培に適している。このため古くから甲斐八珍果*といわれる、ブドウ・桃・ナシなど多種多様な果実が作られていた。なかでもブドウ栽培が日本一の生産高を誇るほど...

藤切り祭 ( 山梨県 甲州市 )
甲州市勝沼町柏尾にある大善寺で毎年5月2日から5月5日に行われる祭りである。修験道の開祖といわれる役小角(役行者)が大蛇を退治しこの地を災厄から救ったといわれる故事に習い、そのご利益をさずかろうと始まったという。総代を務める地元の人々と、大善寺と近隣の真言宗寺院の僧侶たちが参加して執り行われる。 5月2日の「藤取り」か...

雲峰寺 ( 山梨県 甲州市 )
JR中央本線塩山駅から北東へ約8km、大菩薩嶺の山ふところにある。「甲斐国志」によると、「寺記曰天正十七(745)年行基菩薩草創*本尊十一面観音行基手自彫刻焉」と伝えられ、また、甲斐源氏の府城の鬼門にあったところから、武田氏などからの崇敬を受けたという。当初、真言宗であったが、その後臨済宗に改宗している。 天文年間(1532...
放光寺 ( 山梨県 甲州市 )
JR中央本線塩山駅から北西に4.5km、恵林寺の北1kmほどにある。1184(元暦元)年、甲斐源氏の創始といわれる新羅三郎義光の孫安田義定*が平家追討のなか、戦勝を祝い、賀賢上人を開山とする天台宗の寺院として建立し、安田氏一門の菩提寺とした。その後真言宗に改宗、現在は真言宗智山派。義定は大日如来*、愛染明王*、不動明王*など多く...

写真提供:北杜市観光課
茅ヶ岳 ( 山梨県 北杜市 / 山梨県 甲斐市 )
JR中央本線を松本方面に向かい甲府の市街を抜けると、右手奥に茅ヶ岳*(標高1704m)が裾野の広い山容を見せる。甲府盆地から望むと複数のピークが連なり、八ヶ岳と間違えられることも多く、「ニセ八ツ」ともいわれている。1971(昭和46)年に「日本百名山」の著者である作家・登山家の深田久弥が急死した山としても知られる。登山口*には深...

昇仙峡 ( 山梨県 甲府市 )
JR中央本線甲府駅から北へ約10km、天神森からさかのぼって仙娥滝までの約4kmをいう。秩父山地の国師岳(標高2592m)・金峰山(標高2599m)に発する荒川*が花崗岩を浸食して造形した渓谷。清冽な渓流と灰白色の巨石、巨岩、そして緑の松が織りなす動と静の景観が連続する。渓谷入口の天神森から滝下までの約3kmは遊歩道*(一方通行の車道と...

写真提供:武田神社
武田神社(武田氏躑躅ヶ崎館跡) ( 山梨県 甲府市 )
JR中央本線甲府駅より北へ約2km、住宅街を抜けたところにある。1915(大正4)年、大正天皇即位に際し、武田信玄に対し従三位(じゅさんみ)が追贈されたことを契機に、武田神社創建の気運が沸き上がり、1917(大正6)年に武田信玄を祭神として、武田氏三代(信虎・信玄・勝頼)*の居館があった躑躅ヶ崎館跡*の一郭に武田神社が創建され、19...

写真提供:PIXTA
甲斐善光寺 ( 山梨県 甲府市 )
JR中央本線甲府駅から愛宕トンネルを通り、東へ約2.7km、JR身延線善光寺駅の北へ約900mほどのところにある。武田信玄*は、数次にわたる川中島の戦いのなか、1555(弘治元)年に信州善光寺が戦火に巻き込まれたため、本尊の秘仏 善光寺式阿弥陀三尊像をはじめ諸仏寺宝類を、一旦、信濃国禰津村(現・東御市)に持ち出し、1558(永禄元)年に...

信玄公祭り ( 山梨県 甲府市 )
川中島合戦への出陣の様子を再現した勇壮な祭り。例年、武田信玄命日(4月12日)の前の金~日曜に開催される。多くの行事、イベントが市の中心街で行われるが、メインイベントは土曜日の夕方から行われる「甲州軍団出陣」である。県内各地から千数百名を超える軍勢が甲府駅近くの舞鶴城公園に集結し、武田二十四将*とともに出陣式を行ったあ...

写真提供:山梨県立美術館
山梨県立美術館 ( 山梨県 甲府市 )
JR中央本線甲府駅の南西約4km、国道52号沿いの芸術の森公園内にある。1978(昭和53)年の開館以来、「ミレーの美術館」として広く親しまれている。 最初の収蔵品であるジャン=フランソワ・ミレーの《種をまく人》をはじめ、ミレーやバルビゾン派の作家、ヨーロッパの主要な風景画家、ならびに山梨ゆかりの作家や日本の近現代作家の作品収...

写真提供:金櫻神社
金櫻神社 ( 山梨県 甲府市 )
甲府市街から北へ16kmほど、昇仙峡の仙娥滝滝上から北東へ2kmほどの山中にある。当社の始まりは、現在地より北20kmほどのところに聳える金峰山(標高2599m)の山頂にある山宮(五丈岩)*の里宮として、7世紀頃に蔵王権現を勧請し建立されたといわれている。金峰山の登山口は9ヵ所あり、金桜神社といわれる里宮*も数ヵ所あったとされ、当社...

本栖湖 ( 山梨県 富士河口湖町 / 山梨県 身延町 )
富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 もっとも西にある本栖湖は、標高900m、面積は470万㎡と3番目の大きさで、最大水深が121.6mともっとも深く、湖水の透明度も高い。 北西南の三方を山に囲まれ、東は青木ヶ原樹海と大室山を前に富士山が望むことができ、静岡県の富士...

写真提供:富士河口湖町観光連盟
精進湖 ( 山梨県 富士河口湖町 )
富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 精進湖は面積51万㎡、周囲6.8kmと五湖中もっとも小さな湖で、平均水深も7mともっとも浅い。 東・北・西の三方を山に囲まれ、南側は青木ガ原溶岩流が張り出し、南岸の一部には黒い溶岩流が剥き出しになっており、大室山を裾野に抱え...

写真提供:(一社)山中湖観光協会
山中湖 ( 山梨県 山中湖村 )
富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 そのなかで山中湖は湖面標高が980mでもっとも高く、面積も657万㎡ともっとも大きい。湖岸線は比較的単純で、その形から三日月湖・臥牛湖などの別名をもっている。 山中湖の名の通り、北は大平山、東は高指山・三国山、南は籠坂峠な...

写真提供:山梨市観光協会
西沢渓谷 ( 山梨県 山梨市 )
秩父山地、国師ヶ岳(標高2592m)付近に源を発する渓谷で、甲武信ヶ岳(2475m)付近から流れ出る東沢とともに笛吹川の源流になっている。東沢との合流地点近くから上流約4kmのところまで、よく整備された1周10kmの遊歩道*がつけられている。七ツ釜五段の滝*をはじめとして、渓流が巨大な花崗岩*の岩床の上を滑り、連続して滝と淵が現れる...

写真提供:ほったらかし温泉
ほったらかし温泉 ( 山梨県 山梨市 )
JR中央本線山梨市駅から北へ約5kmの丘の上にある温泉で、日帰りの温泉施設が1軒ある。 市街地からブドウ畑の丘を登ると、笛吹川フルーツ公園*があり、この公園の第一駐車場の中を通り抜けて進む。登り詰めると大きな駐車場があり、その奥に素朴な木造と鉄骨の建物が並び、休憩所、お土産屋、軽食スタンドと、「あっちの湯」「こっちの湯...

身延山久遠寺 ( 山梨県 身延町 )
JR身延線身延駅より、北西に5kmほどの山間に入った、身延山*(1153m)の山ふところにある。久遠寺は日蓮宗*の総本山で、この地は日蓮門下の祖山とされ、「身延山」の名で篤い崇敬を寄せられており、全国から多くの信者や観光客が詣でる霊山である。 総門*から続く門前町の突き当たりにある三門をくぐると、大木の杉木立を両側に菩提梯...
下部温泉 ( 山梨県 身延町 )
JR身延線下部温泉駅周辺と下部川沿いに宿泊施設があり、温泉街は駅からは1kmほど上流にある。 下部温泉の発見は、景行天皇の代の甲斐国造塩海足尼だとする説もあるが、江戸後期の「甲斐国志」では、熊野神社の「祠記ニ據ルニ承和三丙辰年(837年)熊野ノ神此ニ現出シ温泉湧出」したとし、その後「天正年中(1573年~1593年)穴山梅雪之ヲ再...
七面山敬慎院 ( 山梨県 身延町 )
身延山の西方約6kmにそびえる七面山*(標高1982m)の山頂近く、標高1720mのところにある。もともとは山岳信仰の対象となっていたが、日蓮*の身延山入山とともに、法華経の霊山ともなり、末法の世に法華経を奉ずる者を守護するという七面大明神*を祭るようになった。ただ、日蓮自身の登拝はなく、高弟の日朗*によって1297(永仁5)年に開...

赤沢宿 ( 山梨県 早川町 )
身延山の西、七面山*(1982m)の麓を流れる春木川の谷を見下ろす急な斜面にへばりつくようにあるのが、赤沢宿である。 古くから七面山は山岳信仰の対象で修験場であったが、日蓮*が身延山に久遠寺を開創して以降、七面山が身延山の守護神七面大明神*の鎮座する山としても崇敬されはじめ、身延山と七面山を信者が行き交うようになった。...

奈良田温泉 ( 山梨県 早川町 )
JR身延線下部温泉駅から早川に沿って遡ること約38km、西山温泉の北約3kmのところにある。広河原とともに白根三山登山の根拠地であり、白鳳渓谷の入口にあたる。 奈良田集落は奈良田湖*に臨み、周囲は2000から3000m級の山々に囲まれる山の里で、アクセスは一般車では早川沿いの県道(愛称:南アルプス街道)*となる。奈良田集落は奈良時...

写真提供:笛吹市
甲府盆地の桃畑 ( 山梨県 笛吹市 )
中央自動車道を西に向かうと、勝沼インターチェンジからは山間部を抜け甲府盆地の南端を走るが、釈迦堂パーキングエリア辺りから車窓はブドウ畑から桃畑へ徐々に変わっていく。4月上旬から中旬にかけて、甲府盆地の東部の南側の丘陵地帯は、桃の花に覆われ、濃いピンクの絨毯を敷き詰めたようになる。 山梨県は古くから甲斐八珍果*と呼ば...

写真提供:南アルプス市観光施設課
白根三山 ( 山梨県 南アルプス市 / 山梨県 早川町 )
南アルプス*は、甲斐駒・鳳凰山系、白根山系、赤石山系の3つの大山系によって構成される。このなかでも、最も標高が高い白根山系が白根三山と呼ばれる。日本において富士山に次ぎ標高が高い北岳(3193m)、同じく第3位の間(あい)ノ岳(3190m)、そして農鳥岳(3026m)からなる。 北岳は東側斜面の北岳バットレスと呼ばれる山頂から落ち...

写真提供:韮崎市観光協会
鳳凰三山 ( 山梨県 韮崎市 / 山梨県 北杜市 / 山梨県 南アルプス市 )
南アルプス*は、甲斐駒・鳳凰山系*、白根山系、赤石山系の3つの大山系によって構成される。甲斐駒ヶ岳から南東へ延びる尾根上に鳳凰山系の地蔵ヶ岳(標高2764m)、観音岳(標高2840m)、薬師岳(標高2780m)があり、鳳凰三山と呼ぶ。いずれも花崗岩で構成され、山頂付近は風化が激しいが、白砂や灰白色の岩とハイマツの取り合わせが映える...

白鳳渓谷 ( 山梨県 南アルプス市 )
南アルプスの麓、早川の上流野呂川の一部をいい、北岳などへの登山口となる広河原付近から荒川と合流して早川となる付近までの渓谷を指す。白根山系と鳳凰山系の間にあるため、この名が付けられた。南アルプス林道は甲府盆地側の芦安から夜叉神トンネルを抜け広河原に至り、広河原から白鳳渓谷沿いを下る南アルプス公園線は早川町の奈良田に...
富士川(山梨・静岡県境周辺) ( 山梨県 富士川町 / 山梨県 身延町 / 山梨県 南部町 / 静岡県 富士宮市 / 静岡県 富士市 )
富士川はその源を山梨県と長野県の県境にある鋸岳(標高2,685m)に発し、北上したのち南東に流れを変え、八ヶ岳裾野の峡谷を左手に七里岩を見ながら甲府盆地に向かって流れ下る。さらに扇状地を形作りながら周辺の山々から流れ落ちる大武川、小武川、御勅使川、塩川など左右から支流を合わせ、甲府盆地西部を南流する。盆地の南端部で、流域...
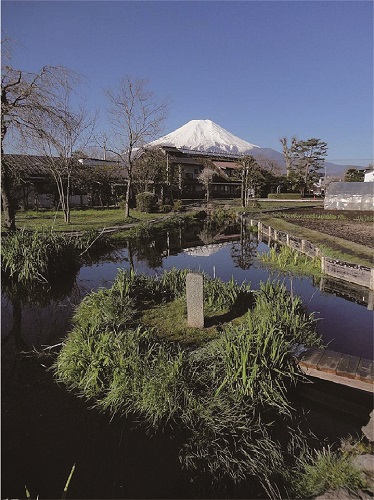
写真提供:忍野村役場
忍野八海 ( 山梨県 忍野村 )
はるか昔の忍野八海の周辺には、富士山の伏流水を溶岩がせき止めて形成された忍野湖があったとみられている。この忍野湖の水位が下がり、湧水口が池として残ったのが忍野八海*で、富士山東麓忍野村(忍草)に点在する、湧池*、出口池*、お釜池、濁池、鏡池、菖蒲池、底抜池*、銚子池の8つの池のことを指す。 富士山に降った雨や雪が溶...
河口湖 ( 山梨県 富士河口湖町 )
富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 そのなかで五湖観光の中心になっているのが河口湖である。面積は548万m2、湖岸線は19km。面積は山中湖に次いで二番目だが、湖岸線は複雑でもっとも長い。標高は833mで五湖の中ではもっとも低いが、気候は高原のような清涼...

写真提供:富士河口湖町観光連盟
西湖 ( 山梨県 富士河口湖町 )
富士五湖*は富士山の北麓、山梨県側に東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖の順で並んでいる。 西湖は、その真ん中、河口湖と精進湖の間にあり、面積は210万m2で4番目の大きさ、最大水深が71.7mで本栖湖に次ぎ深い。このため、水の色は藍色で透明度が高く、その湖面の色合いは本栖湖と同様に神秘的な印象を与える。 ...

写真提供:富士本栖湖リゾート
富士本栖湖リゾートの芝桜 ( 山梨県 富士河口湖町 )
富士本栖湖リゾートは、富士急行線河口湖駅から西へ約23km、本栖湖の南、竜神池を囲むように広がる敷地面積約4万m2の植物庭園。同リゾートでは毎年4月中旬から5月下旬まで「富士芝桜まつり」が開催され、植付面積約1万5千m2、株数約50万株、7種*の芝桜が園内一面を埋め尽くす。残雪の富士山やそれを映す竜神池ととも...

写真提供:久保田一竹美術館
久保田一竹美術館 ( 山梨県 富士河口湖町 )
富士急行線河口湖駅から、北へ河口湖の湖岸に沿って約5km、河口湖もみじ回廊の奥にある。久保田一竹*1は、室町時代に隆盛し、江戸時代初期には衰退していた染色技術「辻が花」*2を1962(昭和37)年に復活させ、独自の工夫を加え、独創的な「一竹辻が花」を生んだ。久保田一竹美術館は1994(平成6)年に開館し、この技法で染めた着物などの作...
青木ヶ原の樹海 ( 山梨県 富士河口湖町 / 山梨県 鳴沢村 )
富士山西北麓一帯、西湖・精進湖・本栖湖から大室山に広がる3000万m2の広大な原生林帯。864(貞観6)年の富士山の大噴火*の際、大量に流れ出た青木ヶ原溶岩流は西北麓一帯を焼け野原にしたが、溶岩が冷えたあと、その上に新しく木々が芽吹き森が再生された。このため、土壌の厚さは10数cmしかないが、ツガ、ヒノキなどの常緑針葉...

写真提供:北口本宮冨士浅間神社
北口本宮冨士浅間神社 ( 山梨県 富士吉田市 )
富士急行線富士山駅の南約2km、国道138号に面している。一般には略して冨士浅間神社と呼ばれている。110(景行天皇40)年にその起源をもつ*と伝えられる。江戸期に入ると、富士講*など富士山信仰の登拝による富士北口登山道の基点として、また、遥拝の場所として多くの信者を集めていた。 参道の両側には燈篭が並び、赤い大鳥居*をくぐ...
吉田の火祭り ( 山梨県 富士吉田市 )
富士山の鎮火祭として例年8月26日、27日に行われる。 26日の午後、北口本宮冨士浅間神社境内で本殿祭、諏訪神社*祭が催行されたのち、御影といわれる赤漆塗の富士山型神輿(御山神輿)と明神神輿の二基が市中にくり出し、御旅所に奉安される。やがて、市内各所に設けられた直径約1m、高さ3mの大きな松明に火がともされる。同時に山小屋で...
富士急ハイランド ( 山梨県 富士吉田市 )
富士吉田と河口湖の間、中央自動車道の河口湖インターチェンジ出口に隣接しており、富士急行富士急ハイランド駅では入園口と直結している。富士山の裾野の剣丸尾溶岩流におおわれた台地上に、1969(昭和44)年に開業した面積約50万m2の大レジャーランド。絶叫マシンをはじめとする40種類ほどのアトラクション*やトーマスランドの...

富士山 ( 山梨県 富士吉田市 / 静岡県 御殿場市 )
静岡県と山梨県にまたがり、日本でもっとも高い成層(円錐)火山である。富士火山帯の主峰でフォッサマグナ*1上に位置し、ユーラシアプレート、北米プレート、フィリピン海プレートの三重の会合点にあり、プレートの押し合いでできた割れ目からマグマが噴き上げ形成したといわれている。山域は東西約35km、南北約38kmに及び、山頂には直径約8...

写真提供:北杜市観光課
瑞牆山 ( 山梨県 北杜市 )
甲府盆地の北、奥秩父の山並みの一角を占める。花崗岩の岩峰の群立する独特な山容を示し、ゆるやかな山体の多い奥秩父では特異な存在感を見せるのが標高2,230mの瑞牆山*だ。とくに西麓の黒森集落やみずがき山自然公園からはその雄姿がよく眺められる。 登山コースは、JR中央本線韮崎駅から25kmほど北にある瑞牆山荘から入り、富士見平で...

写真提供:清泉寮
清泉寮ソフトクリーム ( 山梨県 北杜市 )
JR小海線清里駅から北西へ約2km、標高約1400mの高原にある清泉寮*は、240万m2の広大な敷地に清里聖アンデレ教会、宿泊施設、レストラン、売店、清泉寮ジャージー牧場、ポール・ラッシュ記念館、山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター、清泉寮やまねミュージアムなどの施設が点在する。そのレストラン、売店*では清泉寮ジャージー...

写真提供:北杜市オオムラサキセンター
長坂のオオムラサキ ( 山梨県 北杜市 )
オオムラサキ*1は、羽を広げると10~12cmとなる大型の蝶で、東アジアに生息し、日本では九州中部から北海道南西部まで広く分布している。タテハチョウ科に属し、オスは前翅と後ろの翅の根元近くから中央部にかけて鱗粉の構造から青紫に輝く(メスは輝きがない)。1957(昭和32)年に日本昆虫学会で、当時、日本全国に広く分布しており、その高...
三代校舎ふれあいの里 ( 山梨県 北杜市 )
JR中央本線長坂駅から北西へ約10km、JR小海線清里駅から南へ10kmのところにある。この地は東側に奥秩父の山々が控え、北西に八ヶ岳、南西に甲斐駒ヶ岳、鳳凰三山などの南アルプスを望む標高790mの高原で、伸びやかな農村風景が広がっている。その一画に近代西洋風木造建築の明治校舎をはじめ、大正校舎、昭和校舎の3校舎が校庭跡を前に並列し...

写真提供:PIXTA
山高神代桜 ( 山梨県 北杜市 )
JR中央本線日野春駅から西へ釜無川を渡り、約5kmの大武川の南岸にある實相寺*1の境内にある。大きな樹幹に、長い枝を伸ばしている「神代桜*2」はエドヒガン(シロヒガン)*3ザクラの古種で樹齢約2000年と推定される。最盛期*4は幕末から大正期といわれ、現在はその頃に比べると小さくなったものの、高さ約10m、周囲12mほどで東に枝を伸ばして...

写真提供:サントリーホールディングス株式会社
サントリー白州蒸溜所 ( 山梨県 北杜市 )
JR小淵沢駅の南西約8km、南アルプス・甲斐駒ケ岳のふもとの広大な森の中に1973(昭和48)年に開設されたモルトウイスキー蒸溜所。南アルプスの山々が生み出す良質な天然水*を活用した、自然との調和をめざす「森林公園工場」と掲げている。 約82万m2におよぶ敷地内には白州蒸溜所と天然水南アルプス白州工場がある。またウイ...

写真提供:山中湖花の都公園
山中湖花の都公園 ( 山梨県 山中湖村 )
富士急行富士山駅から南東へ約10km、山中湖北岸からは約1.5kmの標高約1000mの高原にある。北東から南西に向け、約30万m2の農園や花畑が広がり、その先には、裾野まで見渡せる富士山が大きく望める。 公園は、無料の花畑・農園エリアと有料の「清流の里」エリアに分かれている。 花畑・農園エリアでは、4月下旬から5月上旬には...

甲府盆地のワイナリー群(勝沼を中心として) ( 山梨県 甲州市 / 山梨県 笛吹市 / 山梨県 山梨市 )
山梨県のブドウ栽培の歴史*は古く、8世紀あるいは12世紀ともいわれるが、ワイン醸造は明治時代からはじまり、日本のワイン発祥の地*である。山梨県内には甲府盆地を中心に、現在、明治初期創業の老舗から最近の創業の醸造所まで新旧約80のワイナリーがある。ワイナリーは、小さな家族経営のものから大規模なものまで、同じ県内でも、盆地気...

写真提供:平山郁夫シルクロード美術館
平山郁夫シルクロード美術館 ( 山梨県 北杜市 )
JR小海線甲斐小泉駅前にあり、周囲は雑木林のなかに住宅、別荘などが点在し、八ヶ岳や富士山を遠望する標高1000mほどの高原にある。 日本画家平山郁夫*が1988(昭和63)年に鎌倉にシルクロード研究所を創設し、1999(平成11)年にこの地に「八ヶ岳シルクロードミュージアム」を開設した。2004(平成16)年には「平山郁夫シルクロード美術...
写真提供:一般社団法人 戸隠観光協会
戸隠そば(信州そば) ( 長野県 長野市 )
「信濃では月と仏とおらがそば」と一茶の句にもあるように、そばは信州の代表的な名産である。 そばは白い清楚な花を夏と秋に咲かせる。いわゆる夏そばと秋そばで一年に二回収穫される。白い花が咲いたのち黒い皮におおわれた種実ができる。この種実をひいて、胚乳部を出し、これを粉にしたのがそば粉で、つなぎに小麦粉を入れて作る。 ...

恵那山 ( 長野県 阿智村 / 岐阜県 中津川市 )
長野県阿智村と岐阜県中津川市にまたがる、中央アルプス最南端の標高2,191mの山。 恵那山の名前は天照大神の胞衣(えな)を山頂に納めたからという。古くからの信仰の山で頂上には恵那神社奥宮本社が祀られている。また、恵那山の姿が船を伏せた形に見えるので舟覆山(ふなふせやま)とも呼ばれていた。 山頂にもトウヒやコメツガなど...
写真提供:公益財団法人 碌山美術館
碌山美術館 ( 長野県 安曇野市 )
安曇野に生まれた彫刻家荻原守衛(おぎはらもりえ 号:碌山(ろくざん))の作品を展示した美術館で、1958(昭和33)年に開館したもの。赤レンガ造の小さな教会風の建物で、代表作『女』『北條虎吉像』など14点の彫刻や彼の蔵書・資料が並べられている。 第一展示棟、第二展示棟には彼の影響をうけた芸術家や友人の高村光太郎、戸張孤雁...

中房温泉 ( 長野県 安曇野市 )
北アルプス燕岳の山麓で標高1,462m、中房川上流の渓間にある一軒宿の温泉。中房温泉招仙閣と中房温泉ロッヂの2つの建物があり、湯治客と登山客の両者に向けての施設を備えている。旅館には浴室が14ケ所、露天風呂・蒸し風呂・湯滝などがある。中房川下流では、木の葉脈を転写した珪華が見られる。 現在、中房温泉で湧出する源泉は多数あり...

甲斐駒ヶ岳 ( 長野県 伊那市 / 山梨県 北杜市 / 山梨県 南アルプス市 )
南アルプスの北端に位置し長野県と山梨県の県境にある。一般的には日本の数ある駒ヶ岳*の中で甲斐駒と呼ばれ、JR中央本線から巨大なピラミッド型の雄姿が見られる。標高2,967mと駒ヶ岳の中では最高峰である。 岩登りで知られる鋸岳や坊主山・摩利支天・駒津峰などを四方に従えたこの山は堂々たる姿をしている。特に摩利支天は山梨県側か...

仙丈ヶ岳 ( 長野県 伊那市 / 山梨県 南アルプス市 )
長野県と山梨県の県境にあり、北沢峠の南西に甲斐駒ヶ岳と対峙し3,033mとそびえ立つ。隣の花崗岩のピラミッドの甲斐駒ヶ岳とは対照的に女性的な山で、南アルプスでも特にスケ-ルが大きく南アルプスの女王といわれている。仙丈の名前は高さが千丈もあるからではないかと言われている。 山頂近くには薮沢(やぶさわ)・大仙丈沢カール・小...

高遠城 ( 長野県 伊那市 )
長野県伊那市の内東部、中央・南アルプスを遠望する高台の上にある。1547(天文16)年、武田信玄*の命によって家臣の秋山信友・山本勘助*らが築城したという。1582(天正10)年に高遠城主であった仁科盛信(武田信玄の五男)は、敵方の総大将であった信長の嫡男、信忠からの降参の要請に応じず城に籠り、数千の兵で数万の軍勢を相手に一戦...
写真提供:(一社)伊那市観光協会
高遠のサクラ ( 長野県 伊那市 )
高遠は伊那市の東部。四方を山に囲まれたわずかな平地に民家が密集している。高遠城は明治維新までは内藤氏3万3,000石の城下町で、南信地方の中心であった。 高遠城は築城技術に武田流兵法を取り入れた堅固な城であったが、明治維新時に藩校進徳館を残して本丸御殿や門、橋など城内の建物はすべて取り壊され、民間に払い下げとなり、1875...

塩見岳 ( 長野県 伊那市 / 静岡県 静岡市 )
南アルプスのほぼ中央、長野県伊那市と静岡県静岡市の県境にあり標高は3,052m、漆黒の山体にずんぐりした頂をのせている。東側には大井川源流の谷が深く切れ込み、北は絶壁、西には天狗岩と呼ぶジャンダルムがあり、近づくとかなりきびしい表情である。 塩見の名前は、山頂から太平洋が見えるからという説もある。しかし塩見岳の山麓に塩...
写真提供:(C)阿部 宣彦
鳥甲山 ( 長野県 栄村 )
長野県北端の栄村の山深い秘境の秋山郷、この地の西に位置する標高2,037mの岩山。南北に尾根を伸ばし東側は切れ落ちた絶壁であり、登山にはワイヤーロープや梯子が連続するので注意が必要。 第2の谷川岳と呼ばれる男性的な山で、鷲が翼を広げたような山姿が特徴。

白砂山 ( 長野県 栄村 / 群馬県 中之条町 / 新潟県 湯沢町 )
白砂山は、長野県・新潟県・群馬県の3県の境にそびえる奥深い山で、標高2,140m。かつては秘境の名峰として知られていたが、野反湖周辺が開発され、登山道*が整備されてからは登りやすくなった。距離が長く、アップダウンを繰り返すため体力に自信のある人向け。山頂までは片道4時間を要する。

奈良井宿 ( 長野県 塩尻市 )
中山道六十九次のうち、江戸から数えて34番目の宿場で、江戸時代には奈良井千軒といわれたほど賑やかな宿場町であった。現在もJR奈良井駅の南西、旧街道沿いに庇(ひさし)の深い2階建、猿頭*、黒い千本格子の民家がつづいている。創業230年という旅籠越後屋など、町並みは往時の街道・宿場情緒を偲ばせる。西に難所といわれた鳥居峠をひか...

漆工町 木曽平沢 ( 長野県 塩尻市 )
漆工町「木曾平沢」は、木曽谷の入口に位置する贄川と奈良井の中間にある集落で、輪島や会津若松とともに日本有数な漆器産地の一つ。 木曽の豊かな大森林で育った、木曽ヒノキ、サワラなどの良材や、海抜およそ900mに位置し、夏は涼しく冬は寒く、年間湿度が高いという気候が漆を塗る環境に適し、中山道の街道文化とともに産業として発展...

蓼科山 ( 長野県 茅野市 / 長野県 立科町 )
八ケ岳連峰の北八ヶ岳の北端に位置し、標高は2,531m。地形的には北八ヶ岳の中の1つとしてとらえられているが、北横岳からの縦走の対象となりにくいこと、独立峰的な山容で評価が高いことなどから単独の山として取り上げている。 円錐形の山、コニーデ型*の上にトロイデ型*火山が噴出したもので、中腹の深い森林帯に対し、露岩の多い山頂...

写真提供:光前寺
光前寺 ( 長野県 駒ヶ根市 )
駒ケ根高原にある天台宗寺院。860(貞観2)年本聖上人の創建と伝えられ、武田、羽柴家などの信仰が厚く、信濃国有数の大寺であった。 境内には本堂・三重塔・三門などが杉林の中に建っており、樹齢数百年の巨木も多い。蘭渓道隆式池泉庭園や築山式枯山水、築山式池泉庭園と三つの庭園があり、ヒカリゴケも自生している。また三重塔近くに...

白糸の滝 ( 長野県 軽井沢町 )
軽井沢の北部、湯川の源流にかかる。高さ3m、幅70m、黒い岩壁から数百条と思われるほどの水流が、白糸のように落下している滝。この滝の水源は浅間山の伏流水のため、滝の上には川がなく黒い岩肌から水が噴き出している。 軽井沢三笠から峰の茶屋までの有料道路「白糸ハイランドウェイ」*の途中にあり、駐車場から5分程度で到達できる。...

重要文化財・旧三笠ホテル ( 長野県 軽井沢町 )
洋式の2階建の建築物で、1905(明治38)年に日本郵船・明治製菓役員の実業家山本直良(やまもとなおよし)が建造、明治期の純西洋式木造ホテルとして、わが国で2番目に古いとされている。 かつては政財界人が集い「軽井沢の鹿鳴館(ろくめいかん)」として賑わい、太平洋戦争中は外務省出張所となった。戦後はアメリカ軍に接収されたが、195...
写真提供:セゾン現代美術館
セゾン現代美術館 ( 長野県 軽井沢町 )
軽井沢千ヶ滝温泉の北西部の緑に囲まれた別荘地区の一角にある。敷地面積27,732m2の広い庭の中に、延べ床面積2,078m2、鉄筋2階建の美術館。東京(高輪)にあった高輪美術館が1981(昭和56)年に新築移転したもの。 全国でも数少ない現代美術が主体で、マン・レイのオブジェや、パウル・クレー、マックス・エルンス...

軽井沢教会群 ( 長野県 軽井沢町 )
英国聖公会の宣教師として派遣されたアレキサンダー・クロフト・ショーが軽井沢に訪れ、夏を過ごしたのがリゾート軽井沢の始まり。その後外国人の避暑地として人気が高まり、多くの外国人が訪れるようになった。そのため様々な教会が作られ、2018(平成30)年度の軽井沢のパンフレットでは20ほどの教会が紹介されている。そのうち軽井沢の主...

軽井沢保養地 ( 長野県 軽井沢町 )
碓氷峠(うすいとうげ)を越えると、冷気が一瞬のうちに身を包む。夏でも平均最高気温*が26℃程度という軽井沢は浅間山南東斜面のゆるやかな裾野、標高900~1,000mの部分を占め、国際的に名高い高原避暑地である。 英国聖公会の宣教師として派遣されたアレキサンダー・クロフト・ショーが、その高原や気候風土などが避暑地として好適であ...

八ヶ岳 ( 長野県 原村 / 長野県 富士見町 / 長野県 茅野市 / 長野県 南牧村 / 山梨県 北杜市 )
八ケ岳連峰*の中で、夏沢峠を境に北八ケ岳と南八ケ岳に分かれる。南八ケ岳は標高2,899mの主峰赤岳をはじめ横岳、硫黄岳、権現岳、編笠山と荒々しい男性的な岩山が連なる。北八ケ岳は白樺、カラマツの森林や草原が広がり、女性的なやさしさと豊かさを秘めている。 成因は約300万年前、本州を南北に縦断する大地溝帯(フォッサマグナ)のほ...

金峰山 ( 長野県 川上村 / 山梨県 甲府市 )
奥秩父主脈の西端、長野県と山梨県の県境に位置し、標高2,599mと標高でこそ北奥仙丈岳(2,601m)におよばないものの、奥秩父の主峰ともいうべき堂々たる山である。山頂には五丈岩(ごじょういわ)*がどっかと腰をすえている。 奈良県吉野の金峰山から始まるとされる金峰山信仰。この山も古くから修験道の盛んな山で、古文書類にも「金峰」...

乗鞍岳 ( 長野県 松本市 / 岐阜県 高山市 )
長野県松本市と岐阜県高山市の県境、北アルプスの南端にあるコニーデ型の山。馬の鞍に似て複数の峰とその峰間のなだらかな尾根の姿から、その名がついたといわれている。 乗鞍スカイライン(岐阜側)*や乗鞍エコーライン(長野側)*で2,702mの畳平までバスが入り、容易に頂上をきわめられる。剣ケ峰を盟主として3,000m級の恵比須岳・大...

五龍岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 黒部市 )
長野県大町市と富山県黒部市の県境にあり、鹿島槍ケ岳の北に岩峰を連ねてそびえる男性的な姿の岩山。標高は2,814m。遠見尾根をのばしているため山麓からは望みにくいが、唐松岳からの五龍岳は堂々として立派である。 越中からは餓鬼岳、信州からは割菱ノ頭などと呼ばれていた。五龍の名は戦国時代の武田氏の菱型の紋章「御菱」からという...
写真提供:佐久穂町
白駒の池 ( 長野県 佐久穂町 / 長野県 小海町 )
北八ケ岳の中心、麦草峠の南東1.5kmにある八ケ岳火山湖沼の中で最大の池。標高は2,155m、面積114ha、水深8.6m。その名は白馬とともに池へ消えた乙女の伝説*に由来する。 国道299号線沿いの駐車場から歩いて約15分程度で白駒の池まで行け、急俊な高山を登らなくても、気軽に季節の移り変わりを見ることができる。 また、北八ヶ岳の登...

渋温泉 ( 長野県 山ノ内町 )
湯田中温泉、安代温泉などの湯田中渋温泉郷のひとつ。その中の渋温泉は温泉寺の開山虎関師錬(こかんしれん)が浴場としたという。2層、3層の凝った木造の旅館が棟を接するように立ち並び、老舗も多い。 温泉は弱食塩泉や単純温泉など。51~98度と温度が高い源泉をそのまま利用した源泉かけ流し。共同浴場の外湯が9ケ所あり、宿泊客は湯巡...

岩菅山 ( 長野県 山ノ内町 )
志賀高原の北方の最奥、岩菅火山群の主峰で標高2,295m。スキーコースの多い志賀高原の中では手つかずの自然が残る山として貴重である。原生林におおわれた雄大な山体で広大な展望が開ける。なお、山頂の北東稜線には志賀高原の最高峰の裏岩菅山(2,341m)がある。 山頂には岩菅神社があり、信仰登山のむかしを偲ばせる。登山口はリフトや...

志賀高原 ( 長野県 山ノ内町 )
長野県北東部、群馬との県境にある横手山(2,307m)を頂点に西は異様な姿を見せる笠ケ岳*、北は岩菅山(いわすげやま)、西に折れて焼額山(やけびたいやま)・竜王山・五輪山と連なる山並みに囲まれた標高1,300~2,300mの高原。 高原内は志賀山(2,035m)*を中心に坊寺山・東館山・西館山の山々がそびえ湿原や湖沼が点在する。 成因...

甲武信ヶ岳 ( 長野県 川上村 / 山梨県 山梨市 / 埼玉県 秩父市 )
奥秩父主脈のほぼ中央に位置する標高2,475mの山で、甲州(山梨)、武州(埼玉)、信州(長野)の境にあるのでこの名が付けられている。また、山容が拳に似ているため拳岳の字もあてられる。 この山を中心に尾根は3つに分かれ、また、千曲川、荒川、笛吹川が源流を発する重要な山でもある。山頂近くまで原生林が覆うが、山頂からの展望は開...

国師ヶ岳 ( 長野県 川上村 / 山梨県 山梨市 )
甲武信ヶ岳と金峰山の間にあるピーク。高さは2,592mと高いが、頂上直下まで森林帯に覆われている。国師の名は甲州の名刹恵林寺(えりんじ)を創立した夢窓国師の修行伝説からだといわれる。 一般的な縦走路からは外れるが、この山頂の南西方には奥秩父の最高峰北奥千丈岳*(2,601m)がある。 西方の大弛峠(おおだるみとうげ)*には...
写真提供:一般社団法人こもろ観光局
小諸城址(懐古園) ( 長野県 小諸市 )
小諸駅の西方にあり城は千曲川の地形を利用して築城されている。1487(長享元)年大井光忠が現在の城跡の北方に鍋蓋城(なべぶたじょう)を築いたのがはじめである。のち信濃攻略の基地として、1532~1555年武田信玄*が山本勘助*に命じて城を築き、酔月城と称した。完成のとき、勘助は「遠近の深山隠れの秘事の縄幾千代を経む城の松風」と詠...
写真提供:(一社)こもろ観光局
千曲川(小諸周辺) ( 長野県 小諸市 / 長野県 東御市 / 長野県 上田市 / 長野県 坂城町 / 長野県 千曲市 )
千曲川は山梨・埼玉・長野の三県にまたがる甲武信岳(こぶしだけ)に源を発し、全長214kmにわたる。八ケ岳・蓼科山・浅間山などの山々を縫って流れ、越後に入って日本一の長流 信濃川となる。 千曲川は長野県を象徴する川の一つ。佐久鯉を育むのも、戸倉上山田の温泉街を流れるのも、また川中島の戦いの舞台となったのも、この千曲川である。
高峰温泉 ( 長野県 小諸市 )
高峰山の西側、標高2,000mの山あいの高原にある静かな一軒宿の温泉。1956(昭和31)年から山麓で温泉旅館を開いていたが、1978(昭和53)年火災で全焼。これを機に標高2,000mの移転を考え、1983(昭和58)年現在の地で開業したもの。 温泉は36度、含硫黄・カルシウム・ナトリウム・硫酸塩・炭酸水素塩泉で神経痛・高血圧によい。浴場は...

写真提供:一般社団法人 小谷村観光連盟
雨飾山 ( 長野県 小谷村 / 新潟県 糸魚川市 )
長野・新潟の県境にあり、妙高火山群につづく頚城(くびき)山塊に属している。雨飾山は「猫の耳」と呼ばれる双耳峰が特徴である。 2,000m弱の高くはない山だが、好天の日には日本海が望まれ、布団菱(ふとんびし)とよばれる大岩壁が美しい姿を見せる。また山頂には石仏があり、羅漢上人(らかんしょうにん)*が石を刻みそれをコツコツ...
写真提供:一般社団法人 小谷村観光連盟
栂池高原 ( 長野県 小谷村 )
白馬連峰の北東部にある乗鞍岳(2,437m)の山腹一帯、標高1,000~2,000mの広い地域をいう。スキー場のある山麓部の親ノ原一帯は、白馬三山を背景に湿原が広がり、明るい高原風景が展開する。上部はブナ・ツガ・シラビソの深い原生林の中に神の田圃*、栂池自然園などの高層湿原が点在している。 栂池自然園まではゴンドラリフトとロープウ...
写真提供:小布施文化観光協会
小布施の町並み ( 長野県 小布施町 )
小布施町は長野県の北部に位置し、西部に千曲川、南部に松川、北部に篠井川と三方を川に囲まれている、半径2km以内にすべての集落が入る長野県で1番小さな町。北信五岳・北アルプスを望むことができ、果樹栽培が盛んで特にリンゴと栗が代表的産物。葛飾北斎がこの地に4回も訪れているゆかりの地でもある。1982(昭和57)年から始まった町並み...
写真提供:北斎館
北斎館 ( 長野県 小布施町 )
小布施町は須坂市に隣接し、千曲川右岸の松川扇状地に位置し、半径2km以内にすべての集落が入る長野県で1番小さな町。北信五岳・北アルプスを望むことができ、果樹栽培が盛んで特にリンゴと栗が代表的産物。葛飾北斎ゆかりの地で、切妻風白壁の江戸時代の町並みも復元されている。 北斎館は市街地のほぼ中央、小布施駅南東約800mにあり、1...
写真提供:安曇野ちひろ美術館
安曇野ちひろ美術館 ( 長野県 松川村 )
安曇野ちひろ美術館は安曇野市の北、松川村のほぼ中央にあり、周囲を広大な安曇野ちひろ公園(松川村営)に囲まれている。ちひろ美術館・東京の開館20周年を記念して開館した。館内には5つの展示室があり、絵本画家・いわさきちひろや世界の絵本画家の作品、絵本に関する歴史資料を展示している。 美術館のある松川村は、戦後、ちひろの両...

常念岳 ( 長野県 松本市 / 長野県 安曇野市 )
梓川の渓流を間にして穂高連峰・槍ケ岳と相対する常念山脈の主峰。標高は2,857m。花崗岩よりなる山頂は、ピラミッド型をしており、南北に長くバランスのとれた稜線をのばしている。山頂に立てば、穂高連峰・槍ケ岳の山並みをはじめJR大糸線沿いの町々まで360度の展望が開ける。 蝶が岳から大天井岳への縦走コースのほか東側安曇野の一の沢...

焼岳 ( 長野県 松本市 / 岐阜県 高山市 )
上高地大正池の西にそびえるトロイデ型活火山*。標高2,455m。北アルプスの活火山で、たえず水蒸気を上げ、山頂付近は山肌をあらわにし、木も草も生えていない。南峰と北峰からなり、最高峰は南峰である。 1915(大正4)年の噴火では、梓川をせき止め、大正池を出現させ、1962(昭和37)年の噴火では焼岳小屋を倒壊させた。以来、山頂1km...

乗鞍高原 ( 長野県 松本市 )
乗鞍高原へは、松本から梓川沿いに島々、稲核(いねこき)、奈川渡(ながわと)経由で到達する。 乗鞍岳の東麓、標高1,200~1,700mに位置する広大な高原。番所と鈴蘭が高原の中心で、高天ヶ原火山の溶岩原である。かつては鈴蘭高原と呼ばれていたところで、白樺やカラマツの林の中に、ペンションや乗鞍高原国民休暇村などの宿泊施設や別荘...

白骨温泉 ( 長野県 松本市 )
梓川の支流湯川沿いに湧く。緑濃い山々に囲まれてむかしながらの木造旅館が並び、露天風呂が点在して、湯けむりが立ちのぼっている。江戸時代から知られた名湯だが、中里介山(なかざとかいざん)の小説『大菩薩峠』*の一場面を飾って一躍有名になり、バス停近くには『大菩薩峠』文学碑も立つ。 付近にはスキー場があり、特別天然記念物...

穂高岳 ( 長野県 松本市 / 岐阜県 高山市 )
北アルプスの南部に連なり、東に梓川、西に蒲田川の清流が流れる。上高地から梓川の上流へ向かうと、つねに穂高連峰が左側にそびえている。わが国第3位の高峰、奥穂高岳(3,190m)を中心に北の涸沢岳3,103m・北穂高岳3,106m、吊尾根*で結ばれる南東の前穂高岳3,090m、南西の西穂高岳2,909mからなり、総称して単に穂高岳と呼ばれている。 ...

牛伏寺 ( 長野県 松本市 )
松本市の南東、鉢伏山(はちぶせやま)の中腹、標高1,000ⅿにある真言宗の名刹である。参道を登ると山門・庫裏・如意輪堂、さらに階段を登って楼門造の仁王門、観音堂・太子殿などが配置されている。厄除祈願の殿堂として広く知られ、1月の「厄除縁日大祭」では多くの参詣客が訪れる。 756(天平勝宝7)年に唐から信州善光寺に大般若経600...

アルプス公園のサクラ ( 長野県 松本市 )
アルプス公園は松本市街地の北西部の丘陵にあり、標高750~800m前後に位置し広大な敷地71.1haを持つ、1974(昭和49)年に開園した総合公園である。城山公園の北の尾根続きに位置している。 西に北アルプス連峰や安曇野が一望でき、東には美ヶ原と松本市街を望むことができる。 展望台のある「山と自然博物館」、小さな動物園「小鳥と小動物の...

梓川(上高地) ( 長野県 松本市 )
長野県中西部を流れる川。槍ヶ岳に源を発し、途中穂高岳の横尾谷や徳沢と合流し、上高地を経て松本盆地で奈良井川と合流して犀川(いがわ)となる。長さ77km。 梓川の上流域は景勝地も多く、流量の豊かな清流と山岳景観が美しい。この中でも標高約1,500mの細長い盆地が上高地である。 上高地は日本のアルピニズムの発祥の地とされると...

牛伏川フランス式階段工 ( 長野県 松本市 )
松本市の南東、鉢伏山(はちぶせやま)の中腹標高1,000mにある牛伏川フランス式階段工は、1918(大正7)年に完成した治山治水の土木施設。 新潟県下の信濃川で多くの災害が相次ぎ、明治時代には信濃川改修問題が起こった。この問題の主たる要因となる土砂の供給源が長野県の水源地帯、中でも牛伏川にあるとされていた。そのため1885(明治...

美ヶ原高原 ( 長野県 松本市 / 長野県 上田市 / 長野県 長和町 )
松本市、上田市、長和町にまたがり標高2,000m前後に位置する、広さ5km2の広大な高原台地である。信州のほぼ中央にあって中部山岳のほとんどの山を眺める360度の展望台として知られている。高原の最高峰は標高2,034mの王ケ頭で、東側は平坦な台地状でいくつかのピーク*がある。王ケ頭の真下には三城牧場がある。放牧場としては明...

寝覚の床 ( 長野県 上松町 )
木曽川の中流部の上松町の中央部、JR上松駅の南に位置する寝覚の床。木曽川の激流が花崗岩の岩盤を長期にわたって水食した奇景である。約1.5kmの間、柱状・方状節理や甌穴(おうけつ)が見られ、様々な形をした岩がつづく。寝覚の床へは、無料駐車場から臨川寺経由で散策コースがつづいている。江戸時代の参勤交代では臨川寺を小憩所として、...

安楽寺 ( 長野県 上田市 )
別所温泉の北西の山腹にある。温泉街から登りにはなるが歩いて10分程度のところにあり、静寂な中に建っている。 1288(弘安11・正応元)年執権北条貞時の援助を得て樵谷惟仙(しょうこくいせん)*が開山したという。鎌倉の建長寺などと並んで日本では最も古い臨済宗寺院の一つ。鎌倉時代中期すでに相当の規模をもった禅寺であり、学問・...

戦没画学生慰霊美術館 無言館 ( 長野県 上田市 )
上田駅の南西部、上田電鉄別所線「塩田町駅」南の標高570mの静かな丘にある。窪島誠一郎*により、信濃デッサン館の分館として1997(平成9)年に開館した美術館。 「戦没画学生慰霊美術館 無言館」という名が示すように、第二次世界大戦中、志半ばで戦場に散った画学生たちの残した絵画や作品、イーゼルなどの愛用品を収蔵、展示している...
写真提供:上田市
信州上田の松茸料理 ( 長野県 上田市 )
長野県の松茸収穫量*は日本一、中でも上田市は県内でも有数の松茸の産地である。市内の山にはアカマツが多く、かつて燃料として積極的に松葉利用が行われた結果、松茸が生育しやすい環境が広がっていった。収穫時期ともなると直売所では松茸の販売が盛んで、多くの人々が旬の味覚を求めてやってくる。山間には、松茸小屋*がオープンし、松...

黒姫山 ( 長野県 信濃町 )
北信五岳*の1つ。信濃町の西部にそびえる姿から「信濃富士」とも呼ばれ、標高2,053mの二重式のコニーデ型火山。頂上は外輪山にあり、火口原を隔てて中央火口丘の小黒姫山と向かい合う。旧火口付近には小さい湖沼があり、中央に小さな火口丘がある。黒姫山の語源は中野市の高梨城主の娘「黒姫」にまつわる伝説*からと言われている。中腹には...

野尻湖 ( 長野県 信濃町 )
黒姫駅の北東、斑尾山(まだらおやま)の溶岩による堰止湖で、信州では諏訪湖に次いで大きい湖。西部に黒姫山、東部に斑尾山、北西部に妙高山がそびえる。湖岸には、砂間ガ崎、琵琶ガ崎、竜宮崎など48の岬があるといわれるほど湖岸線の出入りに富み、芙蓉の葉に似ているため、芙蓉湖の別名もある。 野尻湖畔では、ナウマン象をはじめ古代...

霧ヶ峰高原 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 長門町 )
諏訪市の北東部、大門峠から鷲ヶ峰(わしがみね)の間に、ゆるやかな起伏をもつ高原が3,000haにわたってつづいている。最高峰の車山は標高1,925mの火山でいくつかの断層が発達し、車山湿原、踊場湿原(池のくるみ)、八島ヶ原湿原と3つの湿原を生んだ。上昇気流が盛んで、この気流を利用してグライダーの基地ともなっている。 茅野市本町か...

霧ヶ峰のニッコウキスゲ ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 長門町 )
諏訪市の北東部、大門峠から鷲ヶ峰(わしがみね)の間に、ゆるやかな起伏をもつ高原が3,000haにわたってつづいている。最高峰の車山は標高1925mの火山でいくつかの断層が発達し、車山湿原、踊場湿原(池のくるみ)、八島ヶ原湿原と3つの湿原を生んだ。 この草原に7月になるとニッコウキスゲが咲き誇る。ニッコウキスゲ(日光黄菅)は草丈40...

写真提供:©(一社)諏訪観光協会
諏訪湖 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 岡谷市 )
八ヶ岳や中央アルプスなどの美しい山々に囲まれて信州のほぼ中央に位置し、周囲約16kmの信州一大きな湖。諏訪盆地の地溝帯にできた断層湖で、岡谷市、下諏訪町、諏訪市にまたがる。 流出部は天竜川だけで釜口水門によって水量が調整されている。観光の中心は上諏訪温泉付近の東岸で湖畔公園・カリン並木があり、サイクリングロードを整備...
写真提供:諏訪市
諏訪湖の御神渡 ( 長野県 岡谷市 / 長野県 諏訪市 / 長野県 下諏訪町 )
岡谷市、諏訪市、諏訪郡下諏訪町にまたがる諏訪湖独特の冬の自然現象で、氷点下10度前後の日が続くと湖が全面結氷し、さらなる冷え込みにより氷が裂け、昼と夜の温度差によってその裂け目が徐々にせり上がることで大音響とともに山脈のような筋になる現象。 最近は、気温の上昇とともに出現することが少なくなってきているが、1月から2月...

御柱祭 ( 長野県 諏訪市 / 長野県 茅野市 / 長野県 下諏訪町 / 長野県 富士見町 / 長野県 原村 )
6年に1度(数え年で7年に1度)、寅と申の年に諏訪大社4社の社殿の四隅に立つ御柱の建て替えを行う祭事で、規模の大きさ、勇壮さで日本の大祭の一つに数えられている。祭りのいわれは清浄な神地の境界を示すものとも、式年造営の省略した形とも様々な説がある。 御柱祭の幕明けは4月初旬上社の山出しに始まる。山から伐採された長さ五丈五...

赤石岳 ( 長野県 大鹿村 / 静岡県 静岡市 )
赤石山脈すなわち南アルプスの南部にあり、赤石山脈の盟主で巨体をすえる。浸食が著しく、険しい尾根を四方に張り重量感があり、その存在感から赤石山脈の名にふさわしい。山名はこの地域の岩石に含まれるラジオラリヤ板岩*が赤紫色からである。山頂は広く、カール状の地形が散見される。 昔の信仰登山のなごりをとどめる石や鉄製の剣が...

荒川三山 ( 長野県 大鹿村 / 静岡県 静岡市 )
塩見岳と赤石岳の間、前岳・中岳・東岳を荒川岳、荒川三山と総称している。南アルプス南部の主要山岳の縦走路の大半は南北方向であるが、この荒川三山は東西方向にならんでいる。前岳(3,068m)・中岳(3,084m)は巨大な一つの山塊だが、標高3,141mの東岳は南アルプスの中でも北岳、間の岳につぐ3番目の高峰。 最高峰の東岳は独立して重厚...

姨捨の棚田 ( 長野県 千曲市 )
姨捨の棚田は千曲市、戸倉上山田温泉街の西にあり、篠ノ井線姨捨駅の東斜面に広がる棚田である。40ha、約1,500枚の棚田がある。国の「重要文化的景観」や「日本棚田百選」にも選定されている。また、田植えの頃にしか見られない姨捨(田毎の月)は国の名勝に指定されている。
写真提供:(C)信州千曲観光局
あんず・科野の里 ( 長野県 千曲市 )
千曲市の東部の「森」と「倉科(くらしな)」の両地区にある観光名所「あんずの里」。4月上旬から中旬にかけて、標高 380~450mの緩やかな山間の斜面に一面に咲くアンズの花は、満開になると更に美しさを増す。 「アンズ」の生産量は長野県が全国トップクラスで、県内の生産量の中でも千曲市が一番多いことから「日本一のあんずの里」とも...

光岳 ( 長野県 飯田市 / 静岡県 川根本町 / 静岡市 静岡市 )
南アルプス最南端の山、標高2,592mで南西に露出する巨岩が日光を受けて光るのでこの名がある。長野県と静岡県の県境に位置し、長野県の飯田市遠山郷奥の易老渡が主な登山口。 北部のイザルガ岳にかけて平坦地が連なり、お花畑のセンジガ原がある。周囲に群生するハイマツはわが国の南限である。

空木岳 ( 長野県 大桑村 / 長野県 駒ヶ根市 )
中央アルプスの木曽駒ヶ岳、宝剣岳の南方にあり、標高2,864mの山。高さでは木曽駒ヶ岳に劣るが、スケールの大きい風貌は中央アルプスでも第一級で、山頂もどっしりとして広く、展望はすばらしい。 東側には空木平が広がり、中央部にお花畑がある。山の名は山麓にあるウツギの木からだという説と、カールに残る雪形がウツギの花に似ている...

南駒ヶ岳 ( 長野県 大桑村 / 長野県 飯島町 / 長野県 駒ヶ根市 )
中央アルプスの主要山脈の南に位置し、空木岳に寄り添うように立ち、2つのピークを持つどっしりした山容で、2,841mの山。中央アルプスの縦走では木曽駒ヶ岳から空木岳までが一般的で、南駒ヶ岳まで足をのばす人は少ない。樹林帯の多い周辺の山々の中でも、頂上付近や尾根筋は白い花崗岩とハイマツによって明るく開放的な山で、岩場の山として...
写真提供:大鹿村教育委員会
大鹿歌舞伎 ( 長野県 大鹿村 )
赤石山脈と伊那山地にはさまれた中央構造線谷沿い、山深い所に位置する大鹿村。ここで行われる大鹿歌舞伎は重要無形民俗文化財に指定されている。大鹿村の大鹿歌舞伎は江戸歌舞伎に影響されて始まった村芝居で、300年以上の歴史を持ち、1767(明和4)年以来演じられている。 歌舞伎は江戸初期に発生し、日本全国に広がった。大鹿村でも、...

鹿島槍ヶ岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 富山市 / 富山県 黒部市 )
長野県大町市と富山県立山町・黒部市の県境にあり、標高2,889m、後立山連峰*の中央に位置している。北峰と南峰のピークが吊尾根で結ばれた双耳峰の優美な山容で、後立山連峰の盟主ともいわれている。かつてはこの山周辺一帯の山域を後立山と呼んだというが、山麓の鹿島集落から取って鹿島槍ヶ岳の名になったといわれる。 鹿島槍ヶ岳への...

烏帽子岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 富山市 )
長野県大町市街の西方19km、大町市と富山県富山市との県境に位置する。北アルプス後立山連峰*の南につづく尾根の一峰で、標高2,628m。槍ケ岳への裏銀座コース*の起点である。 頂上部は烏帽子*状のとがった岩峰が立ち、その形から山の名が付けられたといわれる。烏帽子岳という名の山は日本全国でも数多く50座以上、烏帽子山を含めると9...

爺ケ岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 立山町 )
長野県大町市と富山県立山町の県境にあり、鹿島槍ヶ岳の南に3つのピークを持つ山。春、種まき爺さんの雪形*が現れるところから爺ケ岳と呼ばれ、大町付近からその姿が望める。安曇野の人々はこの雪形が現れると種まきを行ったといわれる。 山頂部は北峰、三角点2,670mの中央峰と南峰が立ち、稜線はハイマツでおおわれている。 登山は大...

槍ヶ岳 ( 長野県 松本市 / 長野県 大町市 / 岐阜県 高山市 / 長野県 安曇野市 )
北アルプスの中央部、穂高連峰の北方にそびえ標高3,180m。高さでは奥穂高岳に及ばないが、天に向かって尖峰を突き上げ、キリリとひきしまった山容は、日本アルプスの王者と仰がれている。尾根も雄大で、北は険しい北鎌尾根がつづき、東は大天井岳、南は穂高連峰、西は三俣蓮華岳へと延びている。 山体の標高2,500m以上の部分は、洪積世氷...
写真提供:大町市観光協会
高瀬渓谷 ( 長野県 大町市 )
大町市の西部の山間部、高瀬川に沿って連なる大町ダム・七倉ダム・高瀬ダムの連続する3つのダムと、葛温泉周辺の渓谷である。 最大の高瀬ダムは七倉ダムと共に発電を目的として1979(昭和54)年に竣工。高さ176m、総貯水量7,620万m3の規模。七倉から高瀬ダムまでの東電管理道路は一般車通行止めとなっており、シーズン中はタク...

仁科三湖 ( 長野県 大町市 )
仁科三湖は木崎湖、中綱湖、青木湖からなり、糸魚川静岡構造線(フォツサマグナ)*の溝上にできた断層でできた湖群と考えられている。 湖畔には、古道塩の道「千国街道」が通り、北西部には街道沿いに三十三観音像がある。また周辺にはスキー場、キャンプ場などがある。
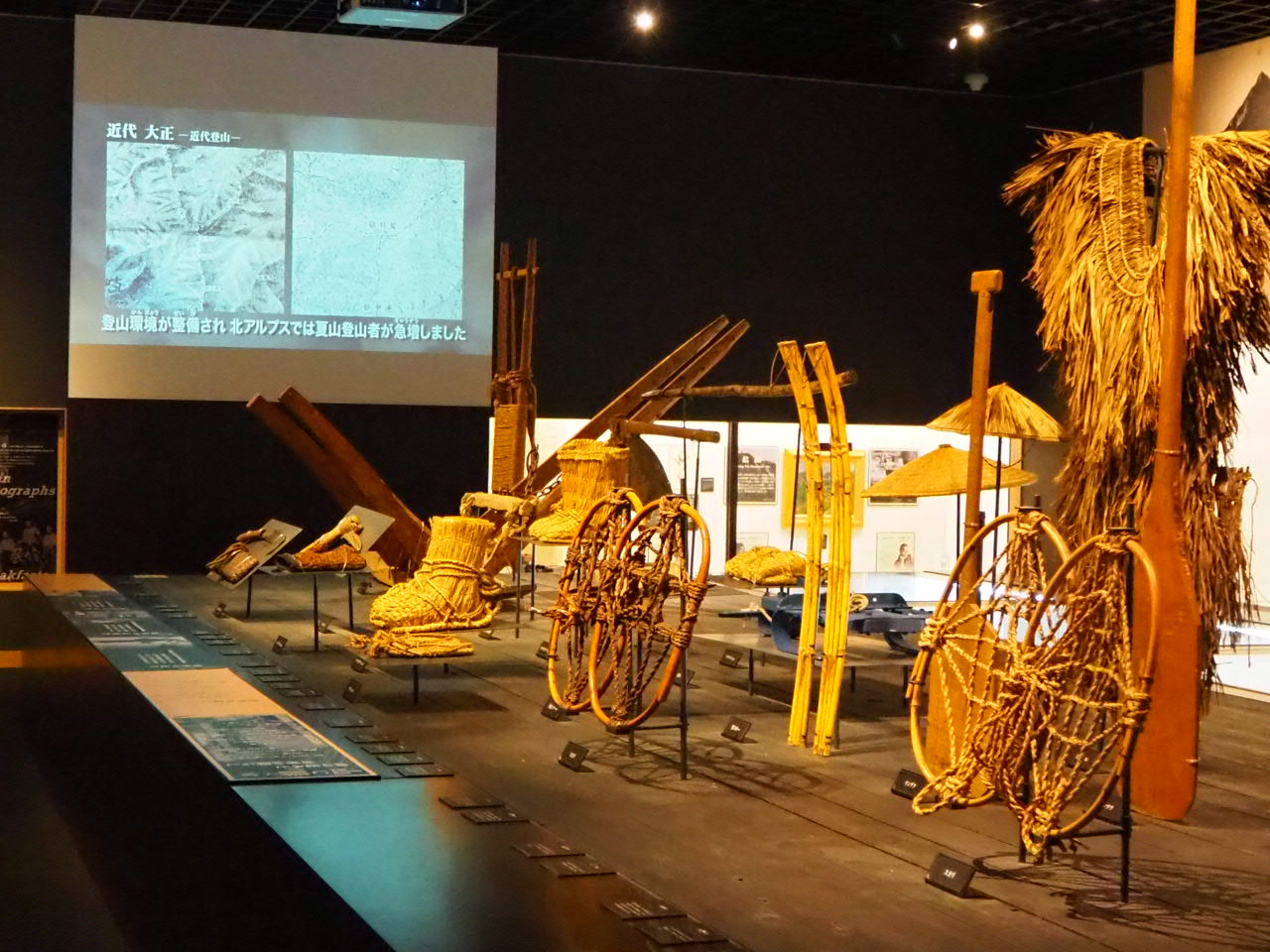
市立大町山岳博物館 ( 長野県 大町市 )
立山黒部アルペンルートの信州側玄関口である長野県大町市。大町市内東山に位置する市立大町山岳博物館は、昭和26年に誕生し、「北アルプスの自然と人」をメインテーマに、後立山連峰を中心とした山岳の自然や歴史について紹介する、日本初の山岳をテーマとした博物館です。 ここでは3階にある展望ラウンジからの北アルプスの展望を...

戸隠山 ( 長野県 長野市 )
「天岩戸神話」*を秘めた戸隠山は、凝灰質の集塊岩からなり、戸隠高原北西部に屏風のようにそそり立つ連峰のうちの一つである。 この地域の北信五岳*のうち戸隠連峰だけが岩稜の山であり、連峰は西岳と、八方睨から五地蔵山までの表山、それに高妻山・乙妻山の裏山の3つの山塊からなる。一般には戸隠山といえば表山を指す。表山は平安時代...

写真提供:(C)善光寺
善光寺 ( 長野県 長野市 )
長野市中心部、”善光寺”信号または二天門跡から約460mの石畳の参道が、仁王門*・山門*を経て本堂*へとつづく。境内は5万9,000m2と広く、参道に大勧進・大本願をはじめ39の宿坊が並ぶ大寺院である。「牛にひかれて善光寺参り」*で知られるように、一生に一度お参りすれば極楽往生が約束されると、全国から多くの老若男女を集める...

戸隠神社 ( 長野県 長野市 )
戸隠神社は霊山・戸隠山のふもとにある奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五社の総称で、創建以来二千年余りに及ぶ歴史を刻む神社といわれている。天の岩戸伝説*の神話に縁深い神々、天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)・天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)などを祀る。 神社の創建は諸説あって明らかでな...

高妻山 ( 長野県 長野市 )
長野市の北部地域の北信五岳*のうち戸隠連峰だけが岩稜の山である。戸隠連峰は長野市善光寺の北西部、飯縄山の西に位置し、北から乙妻山・高妻山の山域、戸隠山を中心とした山域、西岳の山域からなる。 高妻山は戸隠連峰の最高峰2,353mで、戸隠山の岩峰と好対照のピラミッド型の山である。戸隠山の表山に対し裏山ともいわれている。 ...

写真提供:真田宝物館 画像提供
松代城跡 ( 長野県 長野市 )
旧松代駅の西方にある。松代城は元々海津城と呼ばれていた城で、武田信玄*が山本勘助*に命じて築城したと伝えられている。甲州流築城術の特徴を強く持ち、武田氏築城の代表的な城のひとつとされている。1561(永禄8)年川中島合戦*では武田軍の本陣とされた。 松代城と改名されたのは、江戸時代になってからのこと。その後明治維新まで...

浅間山 ( 長野県 軽井沢町 / 長野県 御代田町 / 長野県 小諸市 / 群馬県 嬬恋村 / 群馬県 長野原町 )
長野・群馬県境にある日本を代表する活火山で、標高2,568m。白い噴煙を上げる浅間山の雄姿は古来から名高い。成層火山でいくつかの噴火跡の山塊が集中し、その総称を浅間山という。全体はなだらかな女性的な山相で、南・北に広大な裾野が延びて草木や樹木が茂り、標高2,300m以上は裸地となっている。また中腹から山麓にかけてはわが国でも有...

四阿山 ( 長野県 上田市 / 長野県 須坂市 / 群馬県 嬬恋村 )
群馬県嬬恋村と長野県上田市、須坂市の東との境にある臼状火山で四阿火山の主峰、標高2,354m。北面に中央火口丘をともなうカルデラがあり、根子岳も外輪山をなす。南西の広大な裾野に菅平高原が広がる。草地の根子岳に比べて、頂上付近までモミやツガなどの樹林が多く、ツツジの群落も見られる。 四阿山の名は公園や庭園などに眺望、休憩...

海野宿 ( 長野県 東御市 )
東御市西部、田中駅の北西約1.5km。JR信越本線と千曲川にはさまれた河岸段丘にある町並み。徳川幕府によって開かれた脇往還「北国街道」*の宿場町で、現在でも東西約650mにわたり街道時代の町並みと遺構が残る。道路中央に設けられた堀割や、独特の格子戸や防火用の火返しを付けた民家が、当時とほぼ同じ姿で道路両側に軒を連ねる。
写真提供:南木曽町役場
田立の滝 ( 長野県 南木曽町 )
南木曽町の北西端、JR田立駅の北にある。駅からは山道で約6km、20分程度で粒栗平の駐車場に着き、ここからは登山道で約3.5km、1時間余で主瀑の天河(てんが)滝(高さ40m、幅13m)に着く。 田立の滝は、うるう滝、らせん滝、洗心(せんしん)滝、霧ヶ滝、天河滝、不動滝、そうめん滝など、大滝川の峡谷にかかる大小十余りの瀑布を総称したも...
写真提供:南木曽町役場
田立の花馬祭り ( 長野県 南木曽町 )
10月第1日曜日の五宮(いつみや)神社*の例祭。神馬3頭が田立駅前広場から五宮神社まで約800mを練り歩く。先頭馬には神が宿るヒモロギ(神を迎えるための依り代)を、中馬には豊作を表す菊を、後馬には南宮社社紋の日月の幟を立て、その周囲に五色の色紙によって稲穂をかたどった竹ひごを365本ほど差し回して、厄除けと豊作を祈願する。

写真提供:(一社)南木曽町観光協会
妻籠宿 ( 長野県 南木曽町 )
岐阜県側から木曽路に入ると1番目の宿。伊那谷への追分でもあり、賑やかな宿場町であった。明治末の中央本線開通後、荒れて寒村となっていたが、1968(昭和43)年から集落保存を実施して脚光を浴びるようになった。現在、周辺の自然景観も含めて、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 出し梁に千本格子、卯建*のある古風な...

白馬三山 ( 長野県 白馬村 / 富山県 朝日町 / 富山県 黒部市 / 新潟県 糸魚川市 )
北アルプス北東部、主峰白馬岳(しろうまだけ)(2,932m)とその南に杓子岳(しゃくしだけ)(2,812m)、白馬鑓ケ岳(はくばやりがたけ)(2,903m)の3つのピークが並び、白馬三山と呼ばれている。白馬岳(しろうま岳)の名前の由来は、春になると雪解けで岩が露出し、黒い「代掻き馬」の雪形が現れることから「代掻き馬」→「代馬」→「しろう...

白馬連山高山植物帯 ( 長野県 白馬村 / 富山県 朝日町 / 富山県 黒部市 / 新潟県 糸魚川市 )
北アルプス北東部、主峰白馬岳(しろうまだけ)(2932m)とその南に杓子岳(しゃくしだけ)(2812m)、白馬鑓ケ岳(はくばやりがたけ)(2903m)の3つのピークが並び、白馬三山と呼ばれている。白馬の名は山頂北部の三国境の南東面に黒く馬の雪形が現れ、これをめやすに苗代を作るところから、苗代馬(なわしろうま)、代馬(しろうま)といわ...

唐松岳 ( 長野県 白馬村 / 富山県 黒部市 )
唐松岳は標高2,696mで、北アルプスの連峰の中ではあまり目立つ山ではなが、山頂はやさしいピラミッド型のピークであり、後立山のなかでは女性的な山容をしている。 唐松岳の北には不帰(かえらず)のキレット*をはさんで白馬三山と対峙している。また南には五竜岳、鹿島槍ヶ岳と稜線が続いている。 唐松岳の中腹にはパウダースノー...
写真提供:(C)信州千曲観光局
千曲川(千曲市~飯山市周辺) ( 長野県 飯山市 / 長野県 千曲市 / 長野県 小布施町 / 長野県 他 )
千曲川は山梨・埼玉・長野の三県にまたがる甲武信ヶ岳(こぶしがたけ)に源を発し、全長214kmにわたる。八ヶ岳・蓼科山・浅間山などの山々を縫って流れ、越後に入って日本一の長流、信濃川となる。 千曲川は長野県を象徴する川の一つ。佐久鯉を育むのも、戸倉上山田の温泉街を流れるのも、また川中島の戦いの舞台となったのも、この千曲川...

聖岳 ( 長野県 飯田市 / 静岡県 静岡市 )
長野県と静岡県の県境にあり、日本アルプス中で最も南にある3,000m峰である。登山口は長野県側では飯田市の遠山郷奥の易老渡先、便ヶ島からと、静岡県大井川上流の椹島からとがあるが、いずれも山深く3泊は見ておきたい。 宗教的な山名だが、語源はヘズル、肘を曲げたようなうねうねした川のヒジリ沢からか、登山道がまがりくねって登るこ...

遠山郷・上村下栗の里 ( 長野県 飯田市 )
遠山郷上村は飯田市の中心部から東に車で約1時間のところにある、秋葉街道*と共に栄えた土地。「下栗の里」はさらに7kmの曲がりくねった道を上がったところにある、標高800~1,100mの斜面に張り付いたような集落である。最大斜度30度以上の急傾斜地で、今も雑穀を作り続けている集落で、別名『日本のチロル』とも呼ばれている。 下栗の歴...

天竜川(上流部) ( 長野県 飯田市 / 長野県 天龍村 / 長野県 他 )
JR天竜峡駅の東、故射橋(こやきょう)を中心とした100mを天竜峡と呼び、天竜川*舟下りの名所である。 天竜ライン下りが、天竜峡温泉港(姑射橋下)から唐笠港(唐笠駅そば)までの12km、天竜ライン遊舟有限会社によって運行されており、また、天竜峡から上流に当たる弁天港から時又港までの6km、天竜舟下りを運航している。(現在運休中...

鷲羽岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 富山市 )
長野県大町市と富山県富山市の県境にあり、黒部川源流付近、三俣蓮華岳の北東にピラミッド型の雄姿を見せている。標高2,924m。 1697(元禄10)年に鷲ノ羽ヶ岳という記述が残っている。ただしこれは隣の三俣蓮華岳だったらしく、山の取り違えで現在の山名になったという。鷲が翼を広げた姿に似ているのでこの名がついたという説もある。

三俣蓮華岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 富山市 / 岐阜県 高山市 )
北アルプスの中央部にあり、長野・富山・岐阜3県の境になっている。標高は2,841m。北東部は烏帽子岳方面から後立山連峰*へ、西は黒部五郎岳方面から立山連峰へ、南は槍ケ岳へと稜線がのび、縦走路の重要な分岐点である。 山の名前は、信州・美濃・越中の三国の境であり(三俣)、大きく広がった姿が蓮の花のよう(蓮華)ということからと...
写真提供:大町市観光協会
野口五郎岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 富山市 )
長野県大町市と富山県富山市との県境にあり、北アルプスのほぼ中央に位置する。標高2,924mで本格的な登山を楽しむことができる山である。北方の白馬三山から続く尾根上にある。この稜線は南の三俣蓮華岳方面まで続き、そこで槍ヶ岳方面と薬師岳方面の稜線に分かれている。 高瀬ダムから烏帽子岳、野口五郎岳経由で槍ヶ岳までの登山ルート...
鋸岳 ( 長野県 伊那市 / 山梨県 北杜市 )
長野県伊那市と山梨県北杜市の県境にあり、甲斐駒ヶ岳の北西に連なる鋸岳。標高は最高峰第一高点が2,685mであるが、小ギャップ・鹿窓・大ギャップ、第二高点、などなど鋸十峰が続き、名前のごとく鋸状のピークが形成されている。 甲斐駒ヶ岳の支脈としての認識が強いこと、また登山の難易度や崩壊の危険性が高いことから、この鋸歯状の山...

御嶽山 ( 長野県 木曽町 / 長野県 王滝村 )
乗鞍火山帯の南端、長野・岐阜の県境にそびえる独立峰の活火山である。北アルプスに含まれてはいるが、独立峰として我が国最大級の山頂の広がり、裾野を持っている。最高峰の剣ヶ峰を中心に、継子(ままこ)岳・摩利支天(まりしてん)・継母(ままはは)岳が並び、一ノ池、二ノ池、火口原である賽の河原、さらに北へ三・四・五ノ池の噴火口...
写真提供:(一社)木島平村観光振興局
カヤの平のブナ林 ( 長野県 木島平村 )
上信越高原国立公園の中心志賀高原の北、高標山(たかびょうやま)東麓、標高約1,400~1,700mの広大で秘境的な高原にブナの原生林が広がる。山ノ内町の奥志賀から野沢温泉村に至る60km以上の奥志賀林道(北信州もみじわかばライン)が続いており、その途中にあるカヤノ平には、樹齢200年を超す大木のブナがうっそうと茂る。 カヤの平には...

野沢温泉 ( 長野県 野沢温泉村 )
奥信濃の名湯として知られる温泉。奈良時代、高僧の行基が発見したと伝えられており、江戸時代に飯山藩主が入湯して以来繁栄し、現在では湯治やスキーのできる温泉として親しまれている。毛無山(けなしやま)(1,650m)の山ふところに抱かれた標高600mの地にある。 あちこちから湯けむりを上げる共同浴場を中心に、民宿の看板をあげた民...

野沢温泉の道祖神祭り ( 長野県 野沢温泉村 )
野沢温泉村で古来行われてきた行事の道祖神*祭り。全国的には「どんど焼き」などの呼称で正月飾りや締め飾りなどを焼く行事として広く行われているが、ここ野沢温泉村の道祖神祭りは壮大な規模で行われる火祭り。 1月15日の夜に行われる祭りであるが、その準備は前年の9月から始まる。9月中旬には燃え草を集める作業、10月にはブナの木5...

針ノ木岳 ( 長野県 大町市 / 富山県 立山町 )
後立山連峰*の南端にあり標高2,821m、重量感のある整ったピラミッド型の山容である。山頂の東にはかつて信州と越中を結んだ針ノ木道*が通る針ノ木峠があり、北面は大雪渓で東に蓮華岳がそびえている。 黒部湖を隔てて立山連峰や五色ケ原と対峙する。 登山ルートは扇沢から針ノ木雪渓を登り、針ノ木峠経由の東側ルートと、黒部湖から...

烏帽子岳 ( 長野県 上田市 / 長野県 東御市 )
上田市、東御市の北東側にくっきりと見える、標高2,066mの双頭の山。浅間山から続く連峰の西側の最後部。緩やかな稜線の両端に二つの峰がとがっているので烏帽子*とよばれている。数万年前は湯ノ丸山とともに烏帽子火山群を成していた。そのためか、頂上北側は火口壁の名残でするどく切り立っている。 山頂からは北アルプスのパノラマ、...

黒斑山 ( 長野県 小諸市 / 群馬県 嬬恋村 )
標高2,404mで浅間山第一外輪山の最高峰。山頂へは車坂峠から約2時間ほど。浅間山噴火警戒レベル2*以上の時は、この黒斑山に登頂することで浅間山に登頂したものとされる。しかし、近づいてみると浅間山の外輪山で、湯の平を間に挟み、まったくの別山の様相を見せる。 浅間山の絶好の展望台であり、西側の高峰山から湯の丸山方面の展望も...

前山寺 ( 長野県 上田市 )
上田市街の南西約8km、独鈷山麓にある。空海が開き、鎌倉時代に讃岐国善通寺からの長秀上人が発展させたと伝えられる。この地を治めていた塩田北条氏*の祈祷所でもあった。 境内には大イチョウを前景に、室町初期の三重塔が立っており国の重要文化財となっている。また、藤をはじめ数々の花の名所としても知られている。

北八ケ岳 ( 長野県 佐久穂町 / 長野県 茅野市 / 長野県 小海町 / 群馬県 南牧村 )
八ヶ岳の硫黄岳の北にある夏沢峠から大河原峠までを北八ヶ岳とし、又は北八ヶ岳に蓼科山を加えて北八ヶ岳と呼ぶ場合もある。前者の範囲では南から根石岳、高峰の天狗岳をはじめ、中山・丸山・茶臼山(ちゃうすやま)・縞枯山(しまがれやま)・横岳*・大岳などであり、2,500m前後の山を連ねている。 南の八ケ岳が荒々しい男性的な岩山で...

屋根岩 ( 長野県 川上村 )
川上村の南部に位置し、小川山(2,418m)の東側の標高1,906mの岩峰。小川山と尾根で続き「日本のヨセミテ」とも言われ、ロッククライミングの人気あるスポットのひとつ。周辺には金峰山(別掲)や国師ヶ岳(別掲)などの奥秩父の名峰がある。 山麓には金峰山の登山口があり、金峰山荘やキャンプ場までは自動車が入ることができる。
大王わさび農場 ( 長野県 安曇野市 )
安曇野市には名水百選に選定されている「安曇野わさび田湧水群」があり、北アルプスからの雪解け水が伏流水となって豊富に湧き出しており、日量70万tもの湧水量で、真夏でも水温が15度を超えることはない。 こうした清らかで豊富な水は、ワサビ*栽培に用いられ、さらにワサビ田からの流出水を利用してニジマス養殖が行われている。 ...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
華厳寺 ( 岐阜県 揖斐川町 )
岐阜市の中心街から北西20kmほどの山中にある。西国三十三所*第33番、結願の霊場で、「谷汲(たにぐみ)山」と呼ばれ親しまれている。798(延暦17)年に創建された古刹。 寺伝によると、奥州(福島県)会津の大口大領が京都から故郷に観音像を持ち帰る途中、観音像が自ら歩き出し谷汲の地で動かなくなったことから、この地を結縁の地として...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
横蔵寺 ( 岐阜県 揖斐川町 )
華厳寺の西方、西台山麓にある。最澄は、1本の霊木から2体の薬師如来を自ら刻み、1体を比叡山延暦寺(滋賀県大津市坂本)に祀り、もう1体の安置場所を求めて諸国を巡った。平安時代801(延暦20)年にその薬師如来*を本尊として横蔵寺を創建したと伝えられる。鎌倉時代には38坊、300余の末寺となり栄えた。室町時代には兵火や災害によって衰...
写真提供:揖斐川町
谷汲踊 ( 岐阜県 揖斐川町 )
長さ4mの竹製で鳳凰の羽根を形取った「シナイ」を背負い、胸先に直径70cmの大太鼓を抱えた12人が1組となって踊る。揖斐川上流の各地に伝わる「太鼓踊り」の一つである。 シナイは4m程の竹を細く割り裂いて広げ、扇状に束ねて作り、竹の1本1本に金銀五色の紙を飾り、華やかな模様になっている。鉦鼓(しょうこ)、ホラ貝、横笛、拍子木、唄・...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
根尾谷淡墨ザクラ ( 岐阜県 本巣市 )
樽見鉄道樽見駅から徒歩約15分の淡墨公園にある。地元では、継体(けいたい)天皇お手植え*と伝わり、樹齢1500余年といわれるエドヒガンザクラで、高さ17.3m、幹囲9.4m、枝張り東西22.4m、南北24.2m。幹からは東・北・西南にそれぞれ大枝が出ており、幹基部には各所に大きなこぶがある。 淡いピンクのつぼみが、満開になれば白に、そして...

写真提供:日本自動車道株式会社(伊吹山ドライブウェイ)
伊吹山 ( 岐阜県 関ケ原町 / 滋賀県 米原市 )
標高は1,377m、岐阜・滋賀の県境にそびえる山で、伊吹山地の南端を占める。古事記や日本書記に記され、日本武尊(やまとたけるのみこと)*の伝説がある。平安時代から修験者が集まる山岳修行の山でもあった。深田久弥選定の日本百名山の一つ。 全山石灰岩*からなり、大部分が小潅木を交えた草原、さらに伊吹百草の名があるほどの薬草の...

写真提供:(一社)美濃市観光協会
美濃町の町並み ( 岐阜県 美濃市 )
岐阜市から長良川を20kmほど上流の県南部中央に位置し、美濃紙*の本場として知られる。市域中央で長良川と支流板取川が合流し、その合流点の南に中心市街が開ける。古くは上有知(こうずち)と呼ばれた地で、江戸時代初期に高山の町並みを作り上げた金森氏*が築き、小倉山城*の城下町として発達した。往時は長良川の水運を利用した、紙や...
飛騨古川の瀬戸川と白壁土蔵街 ( 岐阜県 飛騨市 )
飛騨市古川町は、高山市の北西(JR高山線で3駅北)に位置し、町中心地で宮川と荒城川(あらきがわ)が合流している。 天正年間(1573~1592年)に飛騨を平定した金森氏により、増島城の城下町として、碁盤目に区割りされ整えられた。その際、新田開発の用水として整備された瀬戸川は、武家屋敷と商人町を分けることにもなり、武家屋敷があ...

写真提供:(一社)飛騨市観光協会
古川祭 ( 岐阜県 飛騨市 )
毎年4月19・20日に催される気多若宮(けたわかみや)神社の例祭で江戸時代から続く。 祭の由来は、年に一度、この地の氏神(うじがみ)様が高い所にある山の神社から古川町内へ降臨され、氏子(うじこ)である町人がそれを迎える行祭事である。最初は神事のみだったが、「神輿(氏神様)行列」が加わり、更に、まつりの始まりを知らせる目...

写真提供:八百津町
久田見まつり ( 岐阜県 八百津町 )
岐阜県の中南部に位置する八百津町久田見地区の神明(しんめい)神社と白髭(しらひげ)神社の祭礼として、4月第3日曜日に行われる。1590(天正18)年、稲葉右近方通がこの地を領地とするようになって、振獅子・神馬廻とともに、山車を曳く祭礼が始められたと伝わる。 彫刻を漆や金箔で飾った高さ4~5mの6両の山車が行列を組んで進む。両...

写真提供:HIROSHI SUGIYAMA
白川郷合掌造り集落 ( 岐阜県 白川村 )
白川郷の中心である荻町(おぎまち)地区は、山あいを縫うように流れる庄川によって形成された三日月形の河岸段丘の平地にある。急勾配の茅葺き屋根の家屋や小屋が約1kmにわたり点在し、家屋周辺には水田や畑、水路が広がっている。 江戸時代末期(1830~1867年)の建築と伝わる「和田家(わだけ)」や、5階建ての庫裡(くり)がある「明...

どぶろく祭 ( 岐阜県 白川村 )
稲刈りを終えて紅葉に彩られた頃、10月14日から19日にかけて、五穀豊穰・家内安全を願い、山の神様にどぶろくが奉納される祭礼。和銅(わどう)年間(708~715年)に始まったと伝わり、長い年月の間に変遷しながら受け継がれてきた。 神社では、もろみを漉さない濁り酒である「どぶろく」の製造免許を取得している。どぶろくは、真冬の1月...

写真提供:白川村
白水滝 ( 岐阜県 白川村 )
白山国立公園内で白山平瀬登山口の近くにあり、庄川の支流大白川に注ぐ滝。大白川の水は硫黄分を含み、時には白く濁って流れる。落ちる瀑布が乳白色に見えることから「白水滝」と呼ばれる。原生林に囲まれた絶壁から水が落差約70m、幅8mで流れ落ち、水煙あげて爆音をとどろかせている。 その成り立ちは、約2200年前、西側に聳える白山の噴...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
馬籠宿 ( 岐阜県 中津川市 )
江戸日本橋と京都三条大橋を結んだ中山道(なかせんどう)六十九次の43番目の宿場町。その中で木曽川に沿い、険しい峠を越え深い谷を抜け、山あいをめぐる区間を中山道・木曽路十一宿と称し、北は長野県塩尻市の贄川(にえかわ)宿から、妻籠(つまご)宿を経ていちばん南が馬籠宿である。 馬籠峠からつづく斜面にのったところで、ひと筋...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
苗木城跡 ( 岐阜県 中津川市 )
中津川市のほぼ中央、中津川ICから約10分に位置し、恵那峡の東端で木曽川の北岸、通称城山と呼ばれる標高432mの高森山に築かれた山城。 戦国時代大永年間(1521~1528年)に苗木の領主遠山氏によって築城された。その後、戦国の動乱の中で遠山氏は苗木城を追われたが、1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いに先立ち遠山友政が城を取り戻した。...

写真提供:大垣市
大垣祭の軕行事 ( 岐阜県 大垣市 )
JR東海道本線、樽見鉄道樽見線、養老鉄道養老線の大垣駅から徒歩10分にある大垣八幡神社の例祭で、5月15日直前の土曜日と日曜日に行われる山車(だし)行事である。 江戸時代1648(慶安元)年、八幡神社が大垣藩主戸田氏鉄(とだうじかね)により再建整備された折、大垣10か町が10両の軕(出しもの)を造り、曳き出したのが始まりとされる...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
永保寺 ( 岐阜県 多治見市 )
JR中央本線・太多線多治見駅の北東、土岐川に面した虎渓山(こけいざん)*北麓の緑に囲まれた古刹。鎌倉時代1313(正和2)年、夢窓疎石(むそうそせき)*が元翁本元(げんおうほうげん)*を伴い諸国行脚の途中、中国江西省の廬山(ろざん)の渓谷・虎渓*に似ていると、この地の自然風景を愛でて庵を建てた。翌年に本元を開基として寺を開...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟(南宮大社寄贈)
南宮大社 ( 岐阜県 垂井町 )
JR東海道本線垂井駅から南へ約1.5km。南宮山の北東麓にあり、美濃国一の宮として、古くから広く崇敬されてきた。 社伝によれば、神武(じんむ)天皇が「東征」した折、八咫烏(やたがらす)を輔(たす)けて力を顕した金山彦大神(かなやまひこのおおかみ)が祭神として祀られ、後に崇神(すじん)天皇(紀元前97年~30年)の代に現在地に...

笠ヶ岳 ( 岐阜県 高山市 )
新穂高温泉の北西にそびえる独立峰。標高は2,898mで、県境を接しない山としては岐阜県内の最高峰である。どこから見ても笠を伏せたような姿をしている。古くから信仰の対象とされた山で、江戸時代に円空(えんくう)上人(1632~1695年)が開山し、文政年間(1818~1829年)には播隆(ばんりゅう)上人が、山頂に阿弥陀(あみだ)仏を奉納し...

写真提供:飛騨大鍾乳洞観光
飛騨大鍾乳洞 ( 岐阜県 高山市 )
国道158号線で高山市街から奥飛騨温泉郷へのおよそ中間のところにあり、標高約900mに位置する。洞内の温度は、年間を通じて8度から12度である。 鍾乳洞のある飛騨地方は、2億5千万年前には海だった。海中でサンゴやフズリナ(紡錘虫)などの死骸が固まって、石灰石ができた。 その後、石灰岩のできた場所が地殻変動により隆起した。隆起...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
高山陣屋 ( 岐阜県 高山市 )
高山駅から700m程にある。江戸時代1692(元禄5)年に飛騨が幕府直轄領となり、その出先機関として高山城主だった金森氏の下屋敷を陣屋としたもの。明治維新まで25代の代官・郡代が江戸から派遣され、飛騨の行政・財政・警察などの政務を行った。御役所・郡代役宅・御蔵等を併せて「高山陣屋」と称する。 陣屋設置以来、江戸時代1725(享保...

写真提供:安国寺
安国寺 ( 岐阜県 高山市 )
飛騨国府駅の北東3kmにある。足利尊氏・直義兄弟が、南北朝内乱における戦没者や後醍醐天皇の冥福を祈るため、国ごとに安国寺と利生塔を設置した。飛騨では南北朝時代の1347(貞和3)年に、この地に以前よりあった少林寺の寺号を安国寺と改め創建された。開山は瑞巌(ずいがん)和尚である。 創建当時の本堂は永禄年間(1558~1570年)に...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
飛騨国分寺 ( 岐阜県 高山市 )
JR高山駅の北東300mに位置する。飛騨国の国府が高山に移った奈良時代(710~794年)に、聖武天皇の勅願により全国に建立された国分寺のひとつで、746(天平18)年に創建された古刹である。本堂に、本尊の薬師如来坐像、旧国分尼寺の本尊であった聖観世音菩薩像*を安置する。 室町時代(1333~1573年)中期に再建された本堂は、正面5間、側...
高山三町の町並み ( 岐阜県 高山市 )
市の中心部を流れる宮川(みやがわ)の東、南北に連なる三本の通りを総称して「三町(さんまち)」という。三町は、さらに安川通りを境に上町と下町に分かれていて、南側が上一之町(かみいちのまち)から上三之町(かみさんのまち)、北側が下一之町(しもいちのまち)から下三之町(しもさんのまち)である。江戸時代末期から明治時代*に...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
高山の朝市 ( 岐阜県 高山市 )
米市や塩市は、金森氏による統治(1586~1692年)の頃や、天領になった江戸時代1692(元禄5)年以降も開かれていた。 養蚕(ようさん)用に桑の葉を売る桑市が、1820(文政3)年頃には高山別院前で行われ、その後も弥生橋詰、中橋と場所を変えながら開かれた。1894(明治27)年頃からは、養蚕業の不振もあり「桑市」から、農家の奥さん達に...

写真提供:飛鳥
高山祭 ( 岐阜県 高山市 )
春の「山王祭(さんのうまつり)」と秋の「八幡祭(はちまんまつり)」、二つの祭りをさす総称。 高山祭が始まったのは、金森長近が飛騨を平定し統治していた1586(天正14)年から1692(元禄5)年の間といわれる。以後、江戸幕府直轄地(天領)になり、1718(享保3)年頃に祭用の山車(だし)である「屋台(やたい)」が登場。更に、形や...

写真提供:飛騨民俗村 飛騨の里
飛騨民俗村 飛騨の里 ( 岐阜県 高山市 )
高山市街の南西、松倉山麓にあり、有料施設の飛騨の里と、山岳資料館*がある無料施設の民俗村を合わせた施設である。飛騨地方各地に点在していた古い民家を移築・復元し、農山村の生産・生活用具などと共に紹介した野外集落博物館。 飛騨民俗村(旧民俗館)は、御母衣(みぼろ)ダム建設により水没してしまう若山家住宅を移築・公開した1...

写真提供:(一社)奥飛騨温泉郷観光協会
奥飛騨温泉郷 ( 岐阜県 高山市 )
日本列島の中央部で3000m級の飛騨山脈(北アルプス)の麓に、こんこんと湧き出る湯量豊富な温泉が点在する。乗鞍岳(のりくらだけ)から流れ出す高原(たかはら)川に、上流から平湯(ひらゆ)温泉・福地(ふくじ)温泉・新(しん)平湯温泉が、穂高(ほたか)連峰から流れ出す蒲田(がまだ)川に沿って、新穂高(しんほたか)温泉・栃尾(と...
飛騨の朴葉みそ料理 ( 岐阜県 高山市 )
乾燥させた朴(ほお)の葉の上に味噌をのせ、ネギ、シイタケ、漬物など好みの具と一緒に、ゆっくり焼きながら食べる飛騨地方の郷土料理。朴葉の風味が味噌などにしみこんだ素朴な味わいである。ご飯のおかずに合うほか、酒の肴にも良い。 元々は寒さの厳しい飛騨で、囲炉裏(いろり)の炭火に金網をのせ、朴葉を敷き、凍った漬物や土に埋...

写真提供:岩村町観光協会
岩村城 ( 岐阜県 恵那市 )
恵那市の南、標高717mの城山頂上に築かれた山城で、麓の岩村藩藩主邸跡からの高低差が180mもある。 1185(文治元)年に源頼朝の家臣、加藤景廉(かとうかげかど)により建てられたと伝わる。以後、景廉を祖とする美濃の遠山氏が代々居城とした。美濃・信濃・三河国境に位置していたので、戦国時代は武田信玄・勝頼と織田信長との攻防によ...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
恵那市岩村町本通りの町並み ( 岐阜県 恵那市 )
岩村町は恵那市の南部に位置し、岩村城の城下町として発展してきた。周囲が山々で囲まれて標高は500~600mと比較的高い。全長約1.3kmにおよぶ本通りが、緑や川の周辺環境と一体となった歴史の町並みとして、1998(平成10)年に「重要伝統的建造物群保存地区」として選定された。 岩村城方面から、江戸時代の切妻造・平入り二階建ての町家...

いとしろ大杉 ( 岐阜県 郡上市 )
東海北陸自動車道の白鳥ICから約60分。郡上市白鳥(しろとり)町石徹白地区の白山中居(はくさんちゅうきょ)神社の北、福井県・石川県との県境近くの白山登山道登り口にあり、推定樹齢1800年以上、高さ25m、幹周14mを誇る巨木である。大人12人が手をつないでやっと囲めることから、別名を「12抱えの大杉」とも呼ばれている。大杉は標高1,00...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
郡上八幡城 ( 岐阜県 郡上市 )
郡上市八幡町の市街の北、標高354mの八幡山上にある。南に吉田川、西に小駄良(こだら)川を擁した要害の地。城は1559(永禄2)年遠藤盛数(えんどうもりかず)*によって砦として築かれ、1588(天正16)年に二ノ丸・三ノ丸などを備えた平山城に改修された。城主はその後、稲葉・井上・金森・青山の各氏と代わり、明治維新に至った。 古色...
郡上八幡 水とおどりの城下町 ( 岐阜県 郡上市 )
郡上市は岐阜県のほぼ中部で長良川上流に位置する。その中心市街地の八幡町は、古くから飛騨・美濃・越前を結ぶ交通の要衝であり、郡上八幡城の城下町である。三方を山に囲まれた盆地で、町の中央には吉田川と小駄良(こだら)川が流れる。雨は周辺の山々や南東部の石灰岩層の割れ目から地下浸透し、伏流水として湧き水や井戸の水源となる。...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
郡上おどり ( 岐阜県 郡上市 )
「郡上の八幡出てゆくときは、雨も降らぬに袖しぼる」(踊り曲「かわさき」の一節)哀調を帯びた盆踊り歌が街を流れる。郡上八幡の夏は踊りで始まり、踊りで終わるといえる。7月中旬の発祥祭(はっしょうさい)から9月上旬の踊り納めまで、日替わりで広場や神社境内、町内の道路を会場にして約30夜にわたって踊り続けられる。なかでも盂蘭盆会...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
美山鍾乳洞 ( 岐阜県 郡上市 )
郡上市郡上八幡地区から東に山をへだてた美山にある。立体迷路型の珍しいタテ穴式鍾乳洞で、深さ約80m・東西160m・南北130mの範囲に上下6段のホールやトンネルがある。全長2km以上のうち、一般観光洞は約800m。この付近一帯は美山洞穴群と呼ばれ、約2億5千万年前のペルム紀の海底で出来た石灰岩が多くあり、その中に数十の鍾乳洞が分布している...

写真提供:大滝鍾乳洞
大滝鍾乳洞 ( 岐阜県 郡上市 )
郡上市南東部は、古生代の石灰岩層に生じた断層が地下水によって溶解、拡大され生成された鍾乳洞が点在している。 大滝鍾乳洞は、郡上八幡から山ひとつへだてた安久田(あくた)にあり、東西270m、南北40m、高度差100m、総全長約2km(公開通路700m)の鍾乳洞である。 鍾乳洞は、空気中の二酸化炭素を溶かしこんだ雨水が、石灰岩の主成...
長滝白山神社 ( 岐阜県 郡上市 )
東海北陸自動車道の白鳥ICから約10分、長良川鉄道越美南線白山長滝駅から徒歩約1分の郡上市白鳥町長滝にある。 奈良時代717(養老元)年、越前の高僧泰澄(たいちょう)*の創建と伝わり、のち神仏習合によって白山中宮長滝寺と称された。平安時代832(天長9)年、白山に登拝する美濃禅定道(ぜんじょうどう)*の美濃馬場(みのばんば)...

写真提供:岐阜市
岐阜城 ( 岐阜県 岐阜市 )
清流長良川をのぞむ金華山頂(標高329m)にあり、急峻な崖にまもられた山城。鎌倉時代に二階堂行政(にかいどうゆきまさ)*が砦を築いたのが始まりとされる。 古くは稲葉山城とよばれ、1539(天文8)年頃斎藤道三*によって近世的城郭に改修された。1567(永禄10)年*織田信長が攻略して岐阜城と改め完成させ、天下布武の足掛りとした...
写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
ぎふ長良川の鵜飼 ( 岐阜県 岐阜市 )
長良川が夕闇に閉ざされるころ、かがり火を赤々と水面に映して、鵜舟が川を下ってくる。鵜舟は長さ約16mの大型のもので、鵜匠一人、中乗りと艫(とも)乗りの船頭二人が乗り込む。鵜匠は舳先で手縄を付けた10~12羽の鵜を巧みに操り、鵜を引き上げて呑んだ魚を吐かせる。中乗りは捕獲した魚や器具を扱い、艫乗りは船尾で棹をとる。舳先ではか...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
関の刃物 ( 岐阜県 関市 )
岐阜県の中央部(中濃地方)に位置し、岐阜市に隣接する関市では、13世紀前半の鎌倉時代に、現在の九州地方もしくは鳥取県から関に移り住んできて刀を打ち始めた鍛冶(かじ)の「元重(もとしげ)*」を元祖として、刀作りが始まったと伝わる。京都と鎌倉を結ぶ東西交通の要所として栄えていたこの地は、刀作りに必要な良質の土と松炭、長良...

写真提供:(一社)関ケ原観光協会
関ケ原古戦場 ( 岐阜県 関ケ原町 )
現在、古戦場一帯はのどかな田園風景が広がり、山上や林の陰・田の中に石碑が立ち、武将の陣旗がはためき、合戦を偲ばせる。関ケ原の戦い*は、天下分け目の合戦とも言われるほど、歴史上でも重要な戦いである。 JR関ケ原駅の北約900mに古戦場を一望できる「丸山」(岡山烽火場、黒田長政・竹中重門陣跡)があり、山頂から南を見ると細長...
千本松原 ( 岐阜県 海津市 )
木曽川・長良川・揖斐川の3河川は、濃尾平野を貫流した後、下流の河口部ではほとんど同一地点に集まって海に注いでいる。これらの3つの川を総称して「木曽三川(きそさんせん)」という。 古くから木曽三川は、下流部で合流・分流を繰り返し、大雨が降ると川から水があふれ出し大きな水害を起こしていた。これを防ぐため、木曽・長良川と...

写真提供:飛騨小坂観光協会
濁河温泉 ( 岐阜県 下呂市 )
標高3,067mの御嶽山(おんたけさん)西腹6合目(標高1,800m)に位置し、濁河川上流の「湯の谷」渓谷を臨み、野鳥がさえずる原生林に囲まれた温泉地。標高1,800mと日本でも有数の高地に沸いている温泉で、湯温50度以上で源泉かけ流し、泉質は炭酸水素塩泉(ナトリウム・マグネシウム・カルシウム一硫酸塩)。 かつては徒歩で1日がかりで登...

写真提供:(一社)岐阜県観光連盟
美濃焼 ( 岐阜県 多治見市 / 岐阜県 土岐市 / 岐阜県 瑞浪市 / 岐阜県 可児市 )
美濃の南東部(主に多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市)で焼かれたやきものを「美濃焼」という。この地域は窯業に適した地形と、原料の陶土や燃料の薪に恵まれていた。日本六古窯(ろっこよう)*の愛知県瀬戸市とは隣接した地域で、地中の粘土層は同質である。 奈良時代には、「須恵器(すえき)」という釉薬(うわぐすり)を施さない灰...

写真提供:島田市
牧之原の茶畑 ( 静岡県 島田市 / 静岡県 牧之原市 / 静岡県 菊川市 )
牧之原は静岡県の中南部、標高100~200mの広大な台地で、延々と茶畑がつづく日本一の茶どころである。島田市金谷地区を軸としてヤツデの葉のような地形が遠州灘に向かって広がり、最南の御前崎までは28kmほどある。年間平均気温14.3℃、雨量も比較的多いという気象条件は茶の栽培に適し、現在、台地全体での茶畑は5千万m2にも及び...

写真提供:富士宮市観光課
白糸の滝 ( 静岡県 富士宮市 )
JR身延線富士宮駅の北約11km、芝川の上流で、国道139号沿いにある。高さ20m、幅150mの湾曲した絶壁の全面に大小数百の滝が幾筋もの絹糸をたらしたように落ちる優美な滝で、古くからの景勝の地*1であった。水を通さない古富士火山層の上に、水をよく通す新富士火山層の段層があり、その間を富士山の雪どけ水が通り、この地で噴き出したもの。 ...
狩宿の下馬ザクラ ( 静岡県 富士宮市 )
JR身延線富士宮駅の北9km、国道139号から西に入った、井出館*1の門前にある。富士山の南面の裾野に自生する樹齢800年余りの赤芽白花山桜(アカメシロハナヤマザクラ)*2で、シロハナヤマザクラの変種の巨木。若葉は赤色、花は初め淡紅色、後に白色となる。 源頼朝が富士巻狩*3のとき馬を繋いだと伝えられ、頼朝下馬桜、駒止桜、駒繋桜等の...
富士山本宮浅間大社 ( 静岡県 富士宮市 )
JR身延線富士宮駅の北西500m、市街中心にある。古くから駿河一ノ宮として名高く、全国の浅間神社の総本宮である。富士の山霊を鎮めるために祀られたもので、社記によれば806(大同元)年に社殿*1が造営されたといわれている。富士山表口登山道の入口にあって、富士山信仰の隆盛とともに勢力を誇った。富士山山頂に奥宮*2が祀られている。 ...

大石寺 ( 静岡県 富士宮市 )
JR身延線富士宮駅の北約7km、国道139号から西に入ったところにある。富士五山*1の一つで、日蓮正宗の総本山である。日蓮の直弟子である日興*2が身延山を離れ、1290(正応3)年に創建した寺。富士門流の大石寺は、1900(明治33)年日蓮宗富士派として独立し、その後、改名して日蓮正宗となった。 古くからの信徒組織は法華講と呼ばれている...

写真提供:公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
浜名湖 ( 静岡県 浜松市 / 静岡県 湖西市 )
静岡県南西端に位置し、湖面面積約65km2、周囲114kmで全国10番目の大きさの湖である。古くから「遠淡海(とおつおうみ)」と呼ばれる景勝地*1として知られていた。陸地内部の浸食谷が沈降し海水が浸入したのち、湾口を天竜川の漂砂による砂州でふさがれて湖となった海跡湖である。遠州灘とつなぐ現在の今切の水道は、1498(明応7...
奥山方広寺 ( 静岡県 浜松市 )
天竜浜名湖鉄道気賀駅より北へ約8km、臨済宗方広寺*1派の大本山。1371(応安4)年、当地を支配していた奥山六郎次郎朝藤が後醍醐天皇の皇子無文(むもん)禅師を招き、土地、建物を寄進し創建*2した。このため、同寺の開基は奥山六郎次郎朝藤とし、開山を無文禅師としている。本尊は木造釈迦如来及両脇侍坐像*3。同寺の鎮守である半僧坊大権...

秋葉山本宮秋葉神社 ( 静岡県 浜松市 )
浜松市の中心街から北へ約30km、南アルプスの南端、標高866mの秋葉山山頂に鎮座し、秋葉山を御神体として火之迦具土大神(ひのかぐづちのおおかみ 別称:火産霊神)を祀る。社伝によれば、秋葉の火の神の社として709(和銅2)年の創建*1と伝えられる。中世両部神道*2の影響を受け、秋葉大権現と称し、火防の神の総本宮として名高い。とくに...
龍潭寺 ( 静岡県 浜松市 )
天竜浜名湖鉄道金指駅から北西へ約2.5kmにある井伊家*1のゆかりの古刹。臨済宗妙心寺派。 寺伝には行基の開山と伝えられており、古くから地蔵寺と称し信仰の場となっていた。中世には井伊家の祖、井伊共保(1010~1093年)の法名にちなみ自浄院と号し井伊家の菩提寺になったという。また、江戸中期の「遠江国風土記伝」では、宗良親王*2の...

写真提供:公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
浜松凧あげ ( 静岡県 浜松市 )
例年5月3~5日の3日間、浜松まつりの中心行事として中田島凧揚げ会場で行われる。大凧揚げの起源*1は定かではないが、遠州地方は季節風の「遠州の空っ風」や遠州灘からの風もあり古くから凧あげが盛んで、各家の長男が誕生すると、最初の端午の節句に縁戚者から祝い凧が贈られ、村の若衆によって揚げられる風習があったという。明治中期に至...

写真提供:はままつフラワーパーク
はままつフラワーパーク ( 静岡県 浜松市 )
浜松市制60周年を記念して1970(昭和45)年に開園された植物公園。JR東海道本線・東海道新幹線浜松駅から北西に約13km、浜名湖東岸、庄内半島の付け根にあり、舘山寺温泉にも近い。浜名湖畔の自然の地形や樹木を生かした造園で、面積は31.9万m2に及ぶ。 園内には「桜とチューリップの庭園」をはじめ、噴水池を囲む幾何学模様の...

写真提供:MOA美術館
MOA美術館 ( 静岡県 熱海市 )
JR東海道本線・東海道新幹線熱海駅の北約2kmの丘陵地に建つ。1957(昭和32)年に開館した熱海美術館を前身としている。 1982(昭和57)年、創立者岡田茂吉*1の生誕100年を記念して、日本美術を中心とした美術品の展示、能や茶の湯などの推進、日本文化の情報発信などを目的とし、地上3階、地下1階、延べ床面積1万7,000m2の近代...
熱海温泉 ( 静岡県 熱海市 )
丘陵の中腹にあるJR東海道本線・東海道新幹線熱海駅から、相模湾に向いた傾斜地や海岸沿いの平坦地に、旅館やホテル、土産物店や飲食店などが所狭しと建ち並ぶ。熱海駅から海岸沿いの左手には、熱海温泉に隣接して「走り湯」で知られる伊豆山温泉*1もある。 ...

伊豆山神社 ( 静岡県 熱海市 )
JR東海道本線・東海道新幹線熱海駅の東北約1.5㎞、小高い山の中腹にあり、境内は歌枕にもなった伊豆の御山「こごい(古々比)の森」*¹の一部で約13万2千㎡の広さがある。本殿は、「伊豆山神社前」バス停近く逢初橋の北側から石段の参道を登った鬱蒼とした巨木のなか標高170mのところに建ち、前面には相模湾が広がる。本殿は度重なる火災など...

写真提供:熱海市
熱海梅園 ( 静岡県 熱海市 )
JR東海道本線・東海道新幹線熱海駅から西へ約2km、丹那トンネル熱海口近くのゆるやかな山間に位置し、広さは44,000m2。1886(明治19)年、横浜の豪商茂木惣兵衛の出資により造られた歴史ある梅園で、現在は熱海市が管理している。 初川の渓流をはさんで、樹齢100年を越える古木を含め、60品種・469本の梅が咲き誇り、そのなか...

南伊豆の海岸(石廊崎~波勝崎) ( 静岡県 南伊豆町 )
伊豆急行線伊豆急下田駅から国道136号線、県道16号を経て南西へ18kmほどのところに石廊崎がある。その石廊崎から波勝崎までの海岸線は、多数の岩脈の上に海底火山から噴出した溶岩や火山灰などの火山性堆積物が地層を形成し、さらには陸上側の火山が載る形となっているため、複雑多様な地質・地形となっている。それを太平洋の波浪が浸食した...
天城山 ( 静岡県 東伊豆町 / 静岡県 伊豆市 / 静岡県 伊東市 / 静岡県 河津町 )
伊豆半島の中央部に位置する富士火山帯の連山で、伊豆半島を北の口伊豆(北伊豆)と南の奥伊豆(南伊豆)に分ける。噴出した溶岩流や火山灰が堆積してできたいわゆる成層火山で、火口は東南側が欠けた直径6.5kmの爆発カルデラをなし、外輪山は最高峰の万三郎岳(1,406m)、その東の万二郎岳(1,300m)、箒木山(1,024m)、南の三筋山(822m)...

稲取温泉 ( 静岡県 東伊豆町 )
伊豆急行線伊豆稲取駅の南、相模湾にせり出す稲取岬に1956(昭和31)年に湧出した温泉。伊東と下田のほぼ中間にあたり、伊豆最大の漁港である稲取港*1を中心に、古くから伊豆東海岸の交通・経済の要地として栄えた。 1961(昭和36)年に伊豆急行線が開通し、首都圏などからの交通の便が改善されると、一挙に温泉地としても知られるように...
智満寺 ( 静岡県 島田市 )
JR東海道本線島田駅の北約10km、標高478mの千葉山中腹にあり、奈良時代末の創建*1といわれる古刹。宗派は天台宗。 鬱蒼とした杉木立に埋もれて、天正年間(1573~1593年)に徳川家康が再建造営した仁王門・中門・本堂・薬師堂などが点在している。なかでも1589(天正17)年に建立された本堂は、間口・奥行き5間、木割(原木から切り出した...

写真提供:大井川鐵道
大井川鐵道のSL列車 ( 静岡県 島田市 )
大井川鐵道*1は、JR東海道本線と接続する金谷駅から井川線への接続駅となる千頭駅までの本線39.5kmと、千頭駅から井川駅までの井川線*2(南アルプスあぷとライン)25.5kmの2路線を運行している。 SLは、始発の金谷駅から一つ先の新金谷駅と本線の終点千頭駅間で、年間を通して多くの日に運行されている。同社が運行しているSLは、C11形が2...
蓬莱橋 ( 静岡県 島田市 )
JR東海道本線島田駅から南東に約1.5km、大井川にかかる蓬莱橋は、全長897.4m、通行幅2.4mの木造歩道橋。 江戸幕府最後の将軍徳川慶喜が1869年(明治2)年に静岡へ移住した際、付き従ってきた旧幕臣たちが大井川右岸の牧之原に茶畑を開拓するために入植した。この橋は、その旧幕臣たちが島田の市街との往来を確保するために、1879(明治12...
可睡斎 ( 静岡県 袋井市 )
JR東海道本線袋井駅の北約4kmにある曹洞宗の巨刹。輪蔵や山門が建つ本堂前広場を本堂、禅堂、書院などがコの字状に囲み、その東側に萬松閣、瑞龍閣などが並ぶ。広い境内には古松・老杉が茂る。ただ、江戸期から明治初期にかけ、たびたび火災などに遭い、現在の堂宇は明治以降に再建されたものである。 同寺は、1401(応永8)年に道元禅師7...

写真提供:法多山尊永寺
法多山尊永寺 ( 静岡県 袋井市 )
JR東海道本線袋井駅から東南に約5km。寺号の尊永寺というより山号の「法多山」*1の名で古くから知られている。本尊は厄除観音として広く信仰されている。境内は広く、1640(寛永17)年建立の仁王門*2をくぐると右側に杉並木がつづく長い参道があり、その参道を抜けた先にある約250段の階段を上がった場所に1983(昭和58)年落慶の本堂が建ち、...
油山寺 ( 静岡県 袋井市 )
JR東海道本線袋井駅から北へ約6km入った山あいにある。山門を入ると正面の石段の上に書院、方丈があり、参道を左にとると三重塔*1・薬師堂*2がある山腹に至る。山腹に向かう途中は切通しや渓流、「るりの滝」があり、苔むした石段と鬱蒼とした杉の林がつづく。油山寺の名は、かつて「るりの滝」で油が湧出し「油の滝」とも称され、同山が「あ...

寸又峡 ( 静岡県 川根本町 )
大井川の支流、寸又川の中流域に位置します。標高は約550m。寸又峡は寸又川が曲流しながら下方浸食作用を進め穿入蛇行(せんにゅうだこう)*1した峡谷。上流域では、深く刻まれ谷の両岸の絶壁から大小無数の滝が落ち込み、清流が奔流している。 電源開発も古くから行われ、寸又川に沿いダムが点在する。渓谷の奥には寸又峡温泉*2があり、...
日本平 ( 静岡県 静岡市 )
静岡市の中南部、駿河湾に面する丘陵が標高 307mの有度山、その山頂付近が日本平公園となっている。公園は、富士山や清水港、三保松原の眺望で知られる。公園内の山頂付近にレストランやお土産ショップと展望施設の「日本平夢テラス」*1が建ち、山頂直下の平原ゾーンには大芝生広場、富士見の散策ガーデン、茶畑*2などが広がり、平原ゾーンの...
大井川 ( 静岡県 静岡市 / 静岡県 島田市 / 静岡県 藤枝市 / 静岡県 大井川町 / 静岡県 吉田町 )
静岡・山梨・長野3県の県境にある南アルプス間ノ岳(3,189m)に源を発し、静岡県中部を縦断し駿河湾に注ぐ全長約168kmの川。 上流では切り立った深い峡谷を利用して、畑薙・井川など多くのダムが造られ電源開発がなされてきた。山岳景観に優れるとともに、接阻峡*1や寸又峡などの渓谷の景勝地も多い。 中流の川根地方は、大井川が「鵜山...

写真提供:公益財団法人するが企画観光局
三保松原 ( 静岡県 静岡市 )
JR東海道本線清水駅から南へ約6kmの駒越を基点に、東北方向へ約5kmに及ぶ砂嘴*1が駿河湾に突出している。この砂嘴の内側には清水港を抱え、駿河湾に面した外側に白砂と松の緑が連なる浜があり、これが三保松原である。 松原の東北端の鎌ガ崎付近は海越しの富士山の眺望がよく、『万葉集』以来の歌枕*2として親しまれ、江戸時代には浮世絵*...

写真提供:静岡県観光協会
久能山東照宮 ( 静岡県 静岡市 )
JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅から南東へ約7.5km、有度山の南に位置する久能山の山頂(標高216m)に鎮座する。東照宮へは、久能山山麓からは16折、1,159段の急な石段*1を登るか、あるいは日本平からのロープウェイを利用する。社殿をはじめ楼門・鼓楼・神楽殿・神庫・玉垣・渡廊などの建築物は、山頂付近の傾斜を利用して巧みに配置され...

静岡浅間神社 ( 静岡県 静岡市 )
JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅の北西に約2km、静岡の名のもとになった賎機山(しずはたやま 標高171m)を背にして鎮座する。約4.5万m2の境内に、神部(かんべ)神社・浅間(あさま)神社・大歳御祖(おおとしみおや)神社の3本社*1と、麓山(はやま)神社・八千戈(やちほこ)神社・少彦名(すくなひこな)神社・玉鉾(たま...

駿府城跡(駿府城公園) ( 静岡県 静岡市 )
JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅の北700mにある平城の城跡で、明治以降は石垣と堀を残すのみだったが、1989(平成元)年に静岡市市制100周年を記念して巽櫓*1が復元され、現在は駿府城公園として市民に親しまれている。 駿府城は今川氏*2・武田氏のあと駿府を治めた徳川家康*3が1585~1590(天正13~18)年に築いた城で、三河・駿河・遠...

写真提供:丁子屋
丸子のとろろ汁 ( 静岡県 静岡市 )
丸子の宿はJR東海道本線・東海道新幹線静岡駅の西南7km、国道1号に沿った地域で東海道五十三次の宿駅があったところ。鞠子とも書いた。とろろ汁の丸子として古くから*1知られ、『東海道中膝栗毛』*2の中では弥次さん、喜多さんが立ち寄り、歌川広重は『東海道五十三次』の画題として取り上げ、芭蕉の句*3にも詠み込まれている。 これらの...

写真提供:臨済寺
臨済寺 ( 静岡県 静岡市 )
JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅から北へ約3km、静岡浅間神社からは約1kmの賎機山(しずはたやま)東麓にある。臨済宗妙心寺派。山門につづく境内は築地塀・石段・踏み石が直線的に整然と配され、禅寺にふさわしい厳粛な雰囲気が漂う。1536(天文5)年に今川義元*1が兄氏輝の菩提寺として、妙心寺の住持などを歴任した大休宗休に請い、開闢...
堂ヶ島海岸 ( 静岡県 西伊豆町 )
伊豆西海岸のほぼ中央、堂ヶ島の瀬浜から安城岬(あじょうみさき)にかけての2kmほどの海岸線。海上に白色の安山岩質凝灰岩からなる大小の波食群島を浮かべ、島には松が茂り、松島に似た風景を造っている。これらは海底に堆積した火山物質が、いったん隆起したのち沈降して多島海となったもので、島の表面に風波の浸食によって斜交層理と呼ば...
柿田川の湧水 ( 静岡県 清水町 )
JR東海道本線・東海道新幹線三島駅から南西に約2.5kmの場所に柿田川の湧水群がある。周囲は柿田川公園*1として整備されている。狩野川の支流柿田川は全長1.2kmで、富士山周辺に降った雨や雪が11000~8000年前の富士山噴火により流出した三島溶岩流の中を通り、この地で湧出した水源によって形成されている清流である。地質鉱物が学術上貴重で...

写真提供:富士サファリパーク
富士サファリパーク ( 静岡県 裾野市 )
JR御殿場線御殿場駅から西へ約14km、富士山の南東麓、十里木高原の雄大な自然を生かした敷地面積74万m2にも及ぶ動物公園である。 一周4.5kmのサファリゾーンには、クマ・ライオン・トラ・チーター・ゾウ・一般草食動物・山岳草食動物の7つのゾーンが設けられており、マイカーまたはジャングルバス、ナビゲーションカーなどの車...

写真提供:焼津市
藤守の田遊び ( 静岡県 焼津市 )
JR東海道本線藤枝駅から南東に約7kmのところにある、大井八幡宮で例年3月17日に行われる民俗芸能。大井八幡宮*1は、延暦年間(782~806年)の創祀当初は川除と平安豊饒の祈願所だったといわれ、985(寛和元)年には山王権現の大井川宮として社殿も建立された。その後、大井川の川筋の変化もあり、1205(元久2)年に社殿が再建され、同時に大...

千本松原 ( 静岡県 沼津市 )
狩野川河口の西、千本浜公園から駿河湾に面し、緩やかな弧を描くように田子の浦港近くまで延長約15km、幅100~200mほど続くマツ林。クロマツを中心とした造林地で、本数は10数万本に及ぶともいわれている。千本浜公園へは東海道本線沼津駅から南約1.6km。また、同線片浜駅や東田子の浦駅からもマツ林や浜に近い。 ...

写真提供:小國神社
小國神社 ( 静岡県 森町 )
天竜浜名湖鉄道遠江一宮駅から北へ4km、森町の西南部、宮川を遡った比較的開けた谷あいにある。『延喜式』にその名はあり、遠江国一宮である。創祀*1は不詳だが、1680(延宝8)年の社記によれば、555(欽明天皇16)年に、現在の本殿より6kmほど北にある本宮峯(本宮山)*2に神霊を奉斎し、後に勅命により現在地に社殿が造営されたとしている...

三嶋大社 ( 静岡県 三島市 )
JR東海道本線・新幹線三島駅の南東約1km、木立に囲まれた広い神域をもつ。延喜式にもその名があるものの詳しい縁起は不詳*1であるが、古くから伊豆一宮として広く崇敬を集めた。源頼朝も源氏再興を祈願したといい、頼朝腰掛け石がある。鎌倉期以後、「三嶋大明神」として崇敬された。 本殿・幣殿・拝殿は、1854(嘉永7)年の東海地震で被...

写真提供:三島市
三島のウナギ ( 静岡県 三島市 )
三島は、富士山の伏流水、湧水や狩野川支流など豊富な良水に恵まれ、古くからウナギの棲息が確認されてきた。三嶋大社の境内の神池に大量のウナギが棲んでいたともいわれる。 江戸期の俳人上島鬼貫の『鬼貫句選』では、「眞砂はその白玉にうるほひ、御池は水の面青み立て、底おぼつかなくすごし。雜『 ちはやぶる苔のはへたる神鱣(ウナギ...
駒門風穴 ( 静岡県 御殿場市 )
JR御殿場線富士岡駅の西南約1kmにある。富士山東南麓にある、約1万年前に富士山頂の火口から噴出した三島溶岩流の中に形づくられた溶岩洞穴*1の一つ。富士山周辺で発見されている溶岩洞窟としては、もっとも古く規模が大きい。 内部は横穴で途中から2道に分かれ、本穴は243m、枝穴は105mで入口部分の天井高は20mほど、洞穴内でも3m以上の...

掛川城 ( 静岡県 掛川市 )
JR東海道本線・東海道新幹線掛川駅の北700mにある。もともとの城は、15世紀の終わりごろに今川家の重臣朝比奈泰熈によって、現在の掛川*1城跡から北東500mほどにある掛川古城に築かれたが、16世紀の初め頃*2、現在地に移り、築城した。 1569(永禄12)年に武田信玄に追われた今川氏真が朝比奈氏を頼り掛川城に立てこもったものの、包囲...

写真提供:掛川市
掛川大祭 ( 静岡県 掛川市 )
3年に1度*1、干支の丑、辰、未、戌にあたる年の10月上旬に4日間にわたり行われる。掛川市内にある7神社(龍尾神社、神明宮、利神社、池辺神社、白山神社、津島神社、貴船神社)の氏子41町が参加する合同祭礼大祭で、約40の山車と龍尾神社の神輿渡御の露払いを務める瓦町の獅子舞「かんからまち」*2、仁藤町の「大獅子」*3、掛川宿当時を偲ぶ...

写真提供:掛川市
三熊野神社大祭 ( 静岡県 掛川市 )
JR東海道本線・東海道新幹線掛川駅から南へ約10km、江戸時代は横須賀藩の城下町だった横須賀に三熊野神社*1がある。三熊野神社の創建は701(大宝元)年といわれ、神事祭礼は熊野信仰にしたがって行われてきた。 江戸時代に入り、踊りを中心とした祭礼も始まったといわれるが、現在の形式の原型が生まれたのは享保年間(1716~1735年)頃だ...

写真提供:加茂荘花鳥園
加茂荘花鳥園 ( 静岡県 掛川市 )
掛川市街の西郊、天竜浜名湖鉄道原田駅から東へ1.5kmにある。江戸時代からの古い庄屋屋敷*1が里山を背に白い土塀に囲まれて立ち、この屋敷の前庭の約1万m2の敷地には、ハナショウブ他、ハスやサイレンなどが栽培されている。 同屋敷では、花菖蒲は古くから厄除けとして作られていたと伝えられ、明治初期には門前に拡張して花菖...

松崎町のなまこ壁と鏝絵 ( 静岡県 松崎町 )
伊豆西海岸の南部に位置し、駿河湾に面している松崎町*1は、古くから松崎港を中心に栄えていたといわれる。明治期に入ると、繭が早い時期からとれる温暖な土地柄であることから養蚕業が盛んになり、富裕層も増え、瓦葺きの堅牢な建物が求められるようになった。 冬の松崎は駿河湾からの西風が強く防火が欠かせなかったため、壁面に四角い...

写真提供:河津町
河津ザクラ ( 静岡県 河津町 )
伊豆急行河津駅から南西に約250m、河津川沿いの約3kmの両岸に850本ほどの河津ザクラの並木が続く。河津町全体では約8,000本の河津ザクラが植えられている。 河津ザクラは早咲きサクラで、花は直径約3cm、淡紅色で、葉が展開する前に咲く。果実は径1cmほどの黒紫色の球形。河津ザクラは早咲きオオシマザクラ系とヒカンザクラ系の自然交配種...
爪木崎のスイセン ( 静岡県 下田市 )
伊豆急行下田駅から東南へ約6km、須崎半島の東南端に爪木崎がある。須崎半島は長い歴史の中で隆起と海食を繰り返し、4段の隆起海岸段丘となっている。爪木崎付近では、1段目は浜に続く段丘が池の段と呼ばれ、2段目は白い灯台のある台地、3段目が須崎半島自体、4段目は下田市街の東にある寝姿山へと続く。 その爪木崎の先端、2段目の燈台下...

下田公園のアジサイ ( 静岡県 下田市 )
下田公園は伊豆急下田駅から南へ約1km、小田原北条氏が築城した下田城址*1にある。下田港に臨む小高い丘が自然公園となっており、マツ・サクラ・アジサイ・ツバキ・ツツジの中を散策路が通じている。 とくに6月には園内の斜面に300万輪のアジサイが咲き、「クロジクセイヨウアジサイ」「ウズアジサイ」など100種以上を見ることができる。...

写真提供:了仙寺
了仙寺 ( 静岡県 下田市 )
伊豆急行線伊豆急下田駅から南へ約800mのところにある。開国を求め来航したアメリカのペリー提督との交渉により、1854(嘉永7)年3月に日米和親条約が横浜で締結された。 その後、下田の了仙寺で細則につき折衝がつづき、1854年6月、日米和親条約付録協定として下田条約13カ条が結ばれた。同寺はその後も同条約に基づいて玉泉寺とともに米...
伊豆下田河内温泉 ( 静岡県 下田市 )
伊豆急行線蓮台寺駅から稲生沢川を渡って250mほど、金谷山の麓にある一軒宿の温泉。稲生沢川とすぐ下流で合流する蓮台寺川沿いにある蓮台寺温泉にもほど近い。 一軒宿の「金谷旅館」は1867(慶応3)年の開業*1で、本館は1929(昭和4)年建築の数寄屋造り。天城山の木材を使用した柱など素朴で昔ながらの宿屋建築。大浴場は1915(大正4)年...
修禅寺 ( 静岡県 伊豆市 )
伊豆箱根鉄道修善寺駅から西へ約2.7km、虎渓橋前の石段を上った奥に境内がある。平安時代初期の807(大同2)年に、弘法大師が修行した霊跡と伝わり、江戸中期に編纂された日本の高僧の伝記集「本朝高僧伝」では、弘法大師の弟子、杲隣*1が開山したとの記述もある。 鎌倉期の1275(建治元)年には、鎌倉から中国の高僧蘭渓道隆*2が入山し臨...
修善寺温泉 ( 静岡県 伊豆市 )
伊豆箱根鉄道の終点、修善寺駅から西へ約2km、左右から山が迫った桂川の両岸に、大小の旅館がぎっしりと軒を連ねて温泉街を形成している。 修善寺温泉は、約50万年前まで噴火をしていた達磨火山の麓の谷あいを流れる桂川が、達磨火山の下にあった海底火山噴出物の地層に達するまで浸食し、この地層から湧出したものである。このため、温泉...

浄蓮の滝 ( 静岡県 伊豆市 )
伊豆急行線河津駅から国道414号線経由で北西に約21km、湯ケ島温泉*1からは南へ2.3km。狩野川の最上流、伊豆東部火山群に属する鉢窪山と丸山が約1万7000年前の噴火でスコリア丘*2として生成され、その際の溶岩流で形成された茅野台地の溶岩末端崖にできたのが浄蓮の滝である。このため、滝脇の溶岩末端崖には溶岩が冷える際に形成された柱状節...

写真提供:伊豆の国市
韮山反射炉 ( 静岡県 伊豆の国市 )
伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅から東へ約1.5kmにある。反射炉*1は韮山の代官・江川太郎左衛門英龍*2が、国防上の必要から幕府に建議進言して、1855(安政2)年に築いた金属溶解炉。当初、建設地は下田港近くに予定されていたが、1854(安政元)年、ペリー艦隊の下田入港により当地で混乱が起き、韮山代官所に近い現在地で着工することになった。蘭...

願成就院 ( 静岡県 伊豆の国市 )
伊豆箱根鉄道韮山駅から南に約1.5km、国道136号線沿いにある。1189(文治5)年、源頼朝の奥州進攻にあたり戦勝祈願のため北条時政*1が建立したと、鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』にも記載*2がある古刹。鎌倉時代初期の運慶*3作の阿弥陀如来坐像をはじめ、不動明王、毘沙門天などの仏像群*4が開創とともに奉納されたことが『吾妻鏡』に記されてお...

城ヶ崎海岸 ( 静岡県 伊東市 )
伊豆半島の東海岸、半島の付け根にあたる熱海から国道135号線で南へ約35km、北は富戸(ふと)集落の払(はらい)から南は八幡野集落まで、全長約9kmの海岸をいう。約4000年前に大室山が噴火した際、東南及び南に流出した溶岩流によって溶岩台地が生成され、相模灘に向けて舌状に突き出した小半島が形成された。その先端部の溶岩崖は、波の浸...

大室山 ( 静岡県 伊東市 )
JR伊東線伊東駅の南約8kmにある標高580mの火山。天城火山群の北に位置する伊豆東部火山群の中でも最大のスコリア丘*1である。一木もない草山で、頂上には、約4000年前の噴火でできた直径約300m、深さ70mの火口があり、1周約1kmの遊歩道が整備されている。 遊歩道からの展望は広く、南に大島をはじめとする伊豆七島、北に富士山、さらに箱...

写真提供:由比港漁協
桜えびの料理 ( 静岡県 静岡市 )
由比港は、東海道本線、国道1号線、東名高速道路などの大動脈が、北側から迫る山と南側の駿河湾に挟まれた狭隘な海岸線に集まるところに、ひっそりとある。駿河湾でしかとれない桜えび*1の存在は、江戸時代*2から知られていたものの、桜えび漁*3が広まったのは、1894(明治27)年に2艘一組でアジの網引き漁をしていた際に、偶然、網が深く入...

摩訶耶寺 ( 静岡県 浜松市 )
天竜浜名湖鉄道三ケ日駅の北約2kmにある。摩訶耶寺の前身*1は、古くは山岳信仰に結びついた真言密教の道場として、愛知県との県境近くの富幕山に開創された新達寺といわれ、平安時代に、現在地近くの千頭ヶ峯の観音岩と呼ばれる場所に移り、寺号を真萱寺と称していた。 平安時代末期に一条天皇の勅願により現在地へと移り、摩訶耶寺の号を...

写真提供:写真集「井の国 棚田と伝承の里」鈴木一記著より
久留女木の棚田 ( 静岡県 浜松市 )
浜松市の中心街から北へ約30km、三遠南信自動車道浜松いなさ北インターチェンジから北東へ約6km、観音山の南西斜面(標高210~290m)に広がる。総面積約7.7万m2、800枚ほどの棚田は、石積みや土坡(どは)で固められた法面によって、小さく曲線的な田から大きく直線的な田まで様々な形状に区切られている。 久留女木*1の棚田の...

写真提供:竜ヶ岩洞
竜ヶ岩洞 ( 静岡県 浜松市 )
天竜浜名湖鉄道金指(かなさし)駅から北西約5kmにある鍾乳洞。標高359mの竜ヶ石山の南麓にあり、総全長約1km、そのうち、一般公開しているのは約400m。 2億5千万年前の地層と言われる秩父古生層の石灰岩地帯にあり、1912(大正元)年から1975(昭和50)年までは中断もあるが石灰岩の採石場として操業していた。1978(昭和53)年から学術...
浜名湖ガーデンパーク ( 静岡県 浜松市 )
JR東海道本線・東海道新幹線浜松駅から西に約14km、浜名湖の東岸、庄内半島の先端にある。湖畔の美しい自然の中、開放感あふれる都市公園。入場無料。 2004年に浜名湖花博の会場となった所で、56万m2の広大な園内には、緑地広場などがある「西側エリア」、水遊び広場や屋外ステージ、展望塔、体験学習館、中央芝生広場などがあ...

安倍の大滝 ( 静岡県 静岡市 )
JR東海道本線・東海道新幹線静岡駅から北へ約45kmの梅ケ島温泉*1から3つの吊橋を渡り、沢づたいの山道を約1.2kmたどると目前に現われる。高さは約90m、幅は4mほど。安倍川の源流を構成している沢の上流にあたる。
大谷崩 ( 静岡県 静岡市 )
静岡市の最北、山梨県境にあるのが標高1,999.7mの大谷嶺(おおやれい)。この山の南斜面には山体崩壊で形成された大谷崩れ(おおやくずれ)があり、日本三大崩れ*1のひとつといわれる。 山体崩壊のあった北側尾根上には線状凹地*2が発達し、緩やかな稜線を作っている。この山体崩壊は宝永地震*3(1707年)によってできたと記録されており...

島田大祭(帯まつり) ( 静岡県 島田市 )
JR東海道本線島田駅から北へ500mほどのところにある大井神社の例祭。3年に1度(干支で寅・巳・申・亥の年)、10月中旬に3日間にわたり開催される。大井神社は大井川鎮護や安産の神として、島田宿で古くから崇敬されている。 1695(元禄8)年から下島にあった元の社地(現在の御仮屋町)*1へ神輿渡御が行われることになり、現在の形式の神...
妙興寺 ( 愛知県 一宮市 )
名鉄名古屋本線妙興寺駅から徒歩5分程度。1365(貞治4)年に創建された臨済宗の巨刹。正式には、長島山(ちょうとうさん)妙興報恩禅寺と称す。 南北朝時代には、尾張の北朝の拠点として隆盛をきわめる。1356(延文元)年に後光厳天皇より勅願寺の綸旨を賜り、1364(貞治3)年には足利二代将軍義詮(よしあきら)により、鎌倉五山の諸山と...

写真提供:稲沢市
祖父江のイチョウ ( 愛知県 稲沢市 )
名鉄尾西線山崎駅から5分。稲沢市の西部に位置する祖父江のまちは、10月下旬からイチョウが黄色に色づき始める。11月下旬には、全町が黄金色になり、「そぶえイチョウ黄葉まつり」が開催される。10,000本を超えるイチョウの樹が点在しており、なかには樹齢100年を超える古木やイチョウの原木がみられる。 祖父江では冬季の冷たい伊吹おろ...

写真提供:一般社団法人岡崎市観光協会
瀧山寺 ( 愛知県 岡崎市 )
名鉄名古屋本線東岡崎駅からバスで25分。686(朱鳥元)年天武天皇の勅願により建立されたと伝わる古刹。源頼朝の帰依厚く、建久年間(1190~1199年)に寺領四百石が寄進された。保安年間(1120~1124年)に比叡山の僧・仏泉上人永救が再興。徳川家ほか数々の中央権力に密接な檀家からの信仰と擁護により栄える。 バス停のかたわらの朱もあ...

写真提供:大樹寺
大樹寺 ( 愛知県 岡崎市 )
名鉄東岡崎駅からバスで15分。「大樹」とは唐名で「将軍」を意味する。 1475(文明7)年松平4代親忠が念仏堂を設けたのが始まりで、松平家・徳川家代々の菩提寺である。1535(天文4)年岡崎城主松平清康(徳川家康の祖父)により七堂伽藍・多宝塔が造営される。1603(慶長8)年、徳川家康*は征夷大将軍に任ぜられると、将軍先祖の菩提寺...

三谷祭 ( 愛知県 蒲郡市 )
1954(昭和29)年の蒲郡市になる合併前の三谷町の六つの地区が結束して、それぞれが特色を出す三谷の町あげての祭礼である。10月第3または第4の土・日曜日に開催される。 1696(元禄9)年、三谷村の庄屋佐左衛門の夢枕に立った八劔神社の八劔(やつるぎ)大明神が、若宮神社に渡りたいと告げたのを契機に始まったと伝わる。 明治から昭...

写真提供:一般社団法人 犬山市観光協会
犬山城 ( 愛知県 犬山市 )
木曽川の南岸に天守が立つ。小高い山を利用した山城と平城の中間型の平山城である。1537(天文6)年に織田信康により築城された。現存する日本最古の天守は初期望楼型で、国宝五城の一つに指定されている。3重4階、地下2階、本瓦葺の屋根に唐破風と入母屋破風を備え、標準的な規模だが軽快で洒脱な趣がある。最上階には廻り縁(展望台)があ...

写真提供:日本モンキーセンター
日本モンキーセンター ( 愛知県 犬山市 )
名鉄犬山線・広見線・小牧線犬山駅からバスで5分。 日本モンキーセンターは、1956(昭和31)年に、サルに関する総合的な研究及び野生ニホンザルの保護を目的に、名古屋鉄道が出資して設立された。世界各国の霊長類50種以上約700頭が、地域別種別に展示・飼育されている。 ワオキツネザルがいる「Waoランド」や、ボリビアリスザルのいる...

写真提供:博物館 明治村
博物館 明治村 ( 愛知県 犬山市 )
名鉄犬山駅東口から「明治村行き」バスで約20分。犬山市街の南東郊、入鹿池(いるかいけ)の西岸に沿って広がっている。取り壊されていく明治の建築物の保存を計るため、また明治時代の文化を理解してもらうため、名古屋鉄道が用地を寄付するとともに財政面でも全面的に協力して、1965(昭和40)年に開館した。現在、公益財団法人明治村が管...

写真提供:野外民族博物館リトルワールド
野外民族博物館リトルワールド ( 愛知県 犬山市 / 岐阜県 可児市 )
名鉄犬山線犬山駅から日本モンキーセンター経由の直通バスあり。犬山市の南東、岐阜県との境界上の愛岐丘陵にあり、面積123万m2の広さをもつ。 野外民族博物館リトルワールドは、さまざまな民族の生活文化を衣・食・住を通して紹介し、来館者の異文化理解や国際理解を深め世界の諸文化を考える場として1983(昭和58)年に開館...

写真提供:一般社団法人犬山祭保存会
犬山祭 ( 愛知県 犬山市 )
名鉄犬山遊園駅または犬山駅(西口)から徒歩15分、犬山城の麓にある針綱神社の祭礼である。 1635(寛永12)年から始まった祭礼で、4月第1土・日曜日に行われる。城下に大火があり、その翌年に復興祈願のために始められたとされる。 最初は、茶摘みの練り物と馬の塔を出していたが、名古屋東照宮祭の影響も受けながら形を変え、1641(寛永...
鳳来寺山 ( 愛知県 新城市 )
JR飯田線本長篠駅から豊鉄バス(田口行き)で約10分。鳳来寺バス停で下車。門谷の町並みを北に進むと、標高695mの急峻な鳳来寺山が眼前にせまる。鳳来寺山は愛知県の県鳥で「ブッポウソウ」*の鳴き声で知られるコノハズクの生息地としても知られ、旧鳳来町の象徴ともいうべき山である。 表参道には、樹齢1400年と推定されるネズの樹や鳳...
津島神社 ( 愛知県 津島市 )
名鉄尾西線と津島線の起終点の津島駅からまっすぐ西、約1.2km、徒歩17分のところにある。東側鳥居の横に大イチョウがあり、その前に日本の和菓子のルーツといわれる「あかだ屋清七*」の店舗がある。 540(欽明天皇元)年の鎮座といわれ、古くは津島牛頭(ごず)天王*社と称し「津島の天王さん」として親しまれた。「お伊勢さんに詣って...

尾張津島天王祭(津島祭) ( 愛知県 津島市 / 愛知県 愛西市 )
天王まつりが行われる津島神社は、名鉄尾西線と津島線の起終点の津島駅からまっすぐ西、約1.2km、徒歩17分のところにある。かつては津島祇園会とされていた津島神社の7月第4土・日曜日に繰り広げられる夏季大祭である。 宵祭と朝祭とがある。宵祭前夜に、児打廻(ちごうちまわし)*の祈願が行われる。宵祭は午後の6時から10時頃まで行わ...

伊良湖岬 ( 愛知県 田原市 )
伊良湖岬は、渥美半島先端の岬で、愛知県の最南端でもある。地殻変動により隆起した古生層岩石が、伊良湖水道の潮流に浸食されて形成されたもので、岬周辺は海岸段丘になっている。 この地は古くは7世紀、万葉集に麻績王(おみのおおきみ)の歌*が歌われ、江戸時代には松尾芭蕉*らによって歌われた景勝地である。1898(明治31)年にこの...

写真提供:南知多町
(豊浜)鯛まつり ( 愛知県 南知多町 )
鯛まつりは、知多半島の南端に近い南知多町豊浜で、毎年*、7月中・下旬の土・日曜日に行われる。木と竹で長さ12~15m、高さ約5mの鯛の骨格をつくり、それに白木綿を巻いてつくった大小の鯛5匹が若者たちにかつがれ、まち中や海を練りまわる祭りである。 祭りの由来は、中須村(現南知多町大字豊浜中洲)の森佐兵衛が舟形の山車を作ったこ...

写真提供:半田市
亀崎潮干祭の山車行事 ( 愛知県 半田市 )
3月下旬から5月初めにかけて、知多半島は祭り一色*になる。半田市においても、乙川(おっかわ)祭を皮切りに、4月中旬に、8地区で山車祭りが挙行され、最後が亀崎である。半田では1979年に、この10地区*の山車31輌が勢ぞろいする「はんだ山車まつり*」を開催した。そののち、いまでも5年に1度開催している。 10地区の中でも、ユネスコ...
豊川稲荷(妙嚴寺) ( 愛知県 豊川市 )
JR飯田線豊川駅・名鉄豊川線豊川稲荷駅から徒歩5分。 商売繁盛・家内安全・福徳開運のお稲荷さんとして親しまれ、全国から年間数百万の参拝者が訪れる。 1441(嘉吉元)年、永平寺6代目の法孫東海義易により、曹洞宗の寺として創建。のちに今川義元により伽藍が整備された。本尊は寒嚴禅師*伝来の千手観音を祀り、山門の守護として寒嚴禅...

写真提供:豊田市足助観光協会
香嵐渓 ( 愛知県 豊田市 )
足助川と巴川の合流点付近、巴川が浸食してできた渓谷で、巴橋から香嵐橋までの約1kmをいう。名鉄名古屋本線東岡崎駅からバス*でアクセス可能。 1634(寛永11)年の頃、標高254mの飯森山にある香積寺の11世住職・三栄本秀和尚が、巴川沿いの参道から香積寺境内までの約400~500mの間に、カエデ、スギを植えたのが始まりとされる。その後...

写真提供:名古屋市東山動植物園
名古屋市東山動植物園 ( 愛知県 名古屋市 )
地下鉄東山線東山公園駅から正門まで徒歩3分。隣の星ヶ丘駅からは植物園に近い星ヶ丘門まで徒歩7分。 1937(昭和12)年に開園した東山動植物園は本園・北園・植物園の3つのエリアで構成され、約60万m2の広さを誇る。動物園、植物園、遊園地、東山スカイタワーなどの諸施設の他、スカイビュートレインや、植物園では園内バ...

写真提供:徳川美術館
徳川美術館 ( 愛知県 名古屋市 )
JR中央本線大曽根駅南口から徒歩10分。または地下鉄東山線栄駅で名城線に乗り換え大曽根駅下車徒歩15分。美しい庭園の徳川園*に隣接する。開館は1935(昭和10)年で、徳川家康の遺品である「駿府御分物(すんぷおわけもの)」を中核に、初代義直をはじめとする尾張徳川家歴代当主やその家族の遺愛品、いわゆる「大名道具」を収蔵、展示してい...

写真提供:名古屋城総合事務所
名古屋城 ( 愛知県 名古屋市 )
地下鉄名城線名古屋城駅下車徒歩5分。「尾張名古屋は城でもつ」といわれたように、金鯱*で有名な名古屋城はむかしも今も名古屋の象徴である。 1521(大永元)年今川氏豊が、現在の二之丸の地に那古野城を築いたのが最初で、1538(天文7)年頃、織田信秀が氏豊を追ってこの城に入り、その子織田信長もここで生まれたという。その後信秀は古...
大須観音(寶生院) ( 愛知県 名古屋市 )
地下鉄舞鶴線大須観音駅で降り、50mほど南へ行くと左側に、あざやかな朱塗りの堂々たる建物が見える。これが俗に「大須の観音さん」と親しまれ、東京の「浅草の観音さま」にあたる寺である。大須観音は正式には、北野山真福寺寶生院という。 建久年間(1190~1199年)に創建された中島観音堂が始まりで、その後、1333(元弘3)年頃、開山能信...

写真提供:熱田神宮
熱田神宮 ( 愛知県 名古屋市 )
名鉄神宮前駅の改札口を出ると、道路をはさんでほぼ正面に緑豊かな熱田の杜が見える。年間およそ700万人を数える参拝者でにぎわう。祭神は熱田大神で、三種の神器の一つである草薙神剣を御神体とする天照大神。相殿に天照大神以下草薙神剣とゆかりの深い4柱が祀られている。古来、伊勢の神宮につぐ崇敬を受けている。神明造りの本宮や別宮を...

写真提供:御園座
歌舞伎が上演される御園座 ( 愛知県 名古屋市 )
名古屋市営地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅から徒歩2分。1896(明治29)年に名古屋の財界有志によって、名古屋劇場株式会社が創立され、東京明治座を手本とする劇場が翌年に開場した。名古屋きっての歴史と格式を持つ劇場で、歌舞伎の顔見世興行をはじめ大衆演劇や歌謡ショーなどが上演されている。名古屋大空襲で全焼し、再建されたが、1961...

写真提供:名古屋まつり協進会
名古屋まつり ( 愛知県 名古屋市 )
1955(昭和30)年に始まった秋を彩る名古屋市最大の祭りである。祭りのメインは、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑に三姫が付き添い、鎧武者や足軽隊などを従えて行進する郷土英傑行列である。その他、からくりの演技や華やかな水引幕、夜空に点灯された数多くの提灯など見どころが多い山車揃*の他、神楽揃、華やかなフラワーカーなど...
久屋大通公園 ( 愛知県 名古屋市 )
名古屋市の戦災復興計画で実現した2本の100m道路のうち、1本が東西に走る若宮大通、もう1本が南北に走る久屋大通である。久屋大通は、「清州越し」で整備された1辺が約100mの碁盤割がそのまま利用された。 久屋大通は、若宮大通から北方、外堀町通まで名古屋市街の中心を南北にのびる延長1.7km、平均幅員112m、片側4車線、日本では数少な...

写真提供:知立市
八橋かきつばた園 ( 愛知県 知立市 )
名鉄三河八橋駅南西、徒歩8分。無量壽寺境内などにある。以前この地を流れる逢妻川流域の低湿地一帯にカキツバタが咲き、古くから多くの歌人に親しまれ、詠まれてきた名所である。また幾筋にも分かれた川の流れに八つの橋が架けられていたところから八橋*と呼ばれたと伝わる。この地で詠まれたのが有名な在原業平の歌*である。 1805(文...

写真提供:小牧市教育委員会
小牧山城跡 ( 愛知県 小牧市 )
小牧駅の西1.7kmにある小高い山の全体が史跡に指定されてい る。織田信長が斎藤道三なきあと、美濃攻略の拠点として、1563(永禄6)年に本格的な石垣と先進的な城下町をともなう城を築き、約4年間居を構えた。1584(天正12)年の小牧・長久手の戦い*では織田信雄・徳川家康連合軍の本陣が置かれた。 山中には空堀や土塁・大手道が残り、...
知立神社 ( 愛知県 知立市 )
名鉄知立駅の北西、国道1号線沿いにある。駅より徒歩12分。池鯉鮒(ちりふ)大明神と呼ばれ、蝮(まむし)除け・雨乞い・安産の神として知られる。 社伝によると、12代景行天皇の時代に創建されたという古社。「延喜式」神名帳には碧海(あおみ)郡六座の一つと記され、三河二宮にあたる。旧県社。 境内には、本殿・幣殿・祭文殿・拝殿...

写真提供:INAX ライブミュージアム
INAX ライブミュージアム ( 愛知県 常滑市 )
LIXILがINAX ブランド発祥の地常滑市で運営する、ものづくりの心を伝えるミュージアムである。2006(平成18)年には、「窯のある広場・資料館(2019(令和元)年リニューアル)」*、「世界のタイル博物館」*、「陶楽工房」の既存施設に、「土・どろんこ館」。「ものづくり工房(2021(令和3)年、やきもの工房へ名称変更)」が加わり、グラ...

写真提供:豊田市美術館
豊田市美術館 ( 愛知県 豊田市 )
名鉄豊田市駅から南に400m進み、国道153号線を西上した拳母(ころも)台地上の童子山と称される独立丘陵に拳母城跡があり、その本丸部分に1995(平成7)年に開館したのが豊田市美術館である。美術館正面わきにある復元された二重櫓がその面影を伝える。 美術館は、一人ひとりの鑑賞者が作品と対話し、それぞれの作品との関係を結ぶ場とな...

写真提供:松平観光協会
松平氏遺跡 ( 愛知県 豊田市 )
名鉄三河線豊田市駅からバス。1994(平成6)年、高月院*・松平氏館跡*・松平城跡*・大給(おぎゅう)城跡*の4か所が一括されて、「松平氏遺跡」として、国指定史跡となった。松平氏は江戸幕府の創始者である徳川家康の祖で、この地が発祥の地、松平郷である。伝承によると時宗の遊行僧徳阿弥が東国からこの地に入り、在原信重の娘婿にな...

写真提供:瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
瀬戸やきもの風景 ( 愛知県 瀬戸市 )
名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅下車。「せともの(瀬戸物)」というように、瀬戸の焼き物は昔からよく知られている。その歴史は1000年余に及ぶといわれ、日本六古窯のひとつとして日本遺産に認定された。 瀬戸物がほかの地域の焼き物と違いを見せるのは、古瀬戸と呼ばれる施釉(せゆう)陶器の出現による。中世(鎌倉・室町時代)を通して釉薬をほ...

木曽川・中流 ( 愛知県 犬山市 / 岐阜県 各務原市 / 岐阜県 坂祝町 / 岐阜県 美濃加茂市 )
木曽川は、長野県南西部にある標高2,446mの鉢盛山に源を発し、長野・岐阜・愛知・三重の四県を貫いて伊勢湾に注ぐ。全長229kmの全国7位の長流である。 上流部の長野県から流れ出た木曽川は、岐阜県に入ってからも、両岸に山が迫る峡谷美を展開するが、美濃加茂市で飛騨川と合流すると、川幅はぐんと広くなり、水量も豊富でとうとうと流れ...
赤目四十八滝 ( 三重県 名張市 )
近鉄「赤目口駅」からバス10分「赤目滝」下車。日本に数多く存在する四十八滝の一つで、三重県名張市赤目町を流れる滝川の渓谷に存在する一連の滝の総称である。奈良時代には修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ)の修行の場となったとも言われ、古来より山岳信仰の聖地であった。今でも地元では「滝参り」という呼び方が残っている...

写真提供:南伊勢町
五ヶ所湾 ( 三重県 南伊勢町 )
宇治山田駅から五ヶ所行きバスで50分。志摩半島の一部で典型的なリアス海岸の湾、南方向は熊野灘に開いている。名前の由来は、湾内に5ヶ所の天然の良港があったことからと言われている。入り江が多く、その形状が楓の葉のように見えることから、かつては「楓江湾(ふうこうわん)」とも呼ばれていた。 五ヶ所湾沿岸部を含む南伊勢町は平地...

写真提供:専修寺
専修寺 ( 三重県 津市 )
JR紀勢本線一身田駅から徒歩約5分。県都・津市の北郊に位置する専修寺(せんじゅじ)は、宗祖親鸞聖人により開山された真宗高田派の本山である。通称、高田本山と呼ばれており、寺院一帯は一身田寺内町(いっしんでん じないちょう)となっている。真宗高田派に属する寺院は、全国に600余寺あり、栃木県真岡市にある本寺専修寺(ほんじせんじ...

写真提供:大杉谷登山センター
大杉谷 ( 三重県 大台町 )
JR紀勢本線「三瀬谷駅」から町営バスで63分、終点「大杉」下車。大杉谷は、三重県多気郡大台町の宮川上流、吉野熊野国立公園内にある渓谷であり、国の天然記念物(天然保護区域)に指定されている。 2016(平成28)年3月にはユネスコの生物圏保護区「大台ヶ原・大峯山」が拡張され、大杉谷もその一部となった。同時にユネスコエコパークの登...

写真提供:松阪市
松坂城跡 ( 三重県 松阪市 )
JR・近鉄松阪駅から徒歩で約15分。松坂城を作ったのは、蒲生氏郷(がもううじさと)*である。織田信長、豊臣秀吉に仕え、文武に秀でた才能豊かな武将であった。1584(天正12)年に松ヶ島城主となった氏郷は、城の南約4kmにある小高い丘、四五百森(よいほのもり)に新たな城を築くことになる。1588(天正16)年に入城した氏郷は、秀吉の作っ...
英虞湾 ( 三重県 志摩市 )
英虞湾へのアクセス*は近鉄志摩線の発着駅が賢島となっているが、周辺観光地への二次交通の拠点は鵜方駅(志摩市内の各方面に向かう三重交通バスの路線バスの停留所が鵜方駅前にある)。志摩半島南部に位置する一番大きな入海。わが国有数のリアス海岸美を誇り、2016(平成28)年の第42回先進国首脳会議(伊勢志摩サミット)の会場となった賢...

写真提供:多度大社
多度大社 ( 三重県 桑名市 )
養老鉄道「多度駅」から徒歩約20分。太古より神体山と仰がれてきた多度山の麓に鎮座する。 社殿の創建は、5世紀後半の雄略天皇の御代と伝えられる。落葉川に架かる橋を渡ると、左に本宮、右に別宮があり、本宮に天津彦根命(あまつひこねのみこと)、別宮にその御子神の天目一箇命(あめのまひとつのみこと)を祀る。天津彦根命は、伊勢神...
六華苑 ( 三重県 桑名市 )
桑名駅より徒歩20分。山林王として知られた三重県桑名の実業家・二代諸戸清六の邸宅として1913(大正2)年に完成した。鹿鳴館や旧古河庭園(東京)の洋館も設計したイギリス人建築家ジョサイア・コンドルの設計による4層の塔屋をもつ木造2階建て天然スレート葺きの洋館、さらに和館や蔵、池泉回遊式庭園などから構成されている。 桑名市が...

写真提供:桑名市観光協会
伊勢大神楽 ( 三重県 桑名市 )
江戸時代より、伊勢神宮に参拝できない人のため全国各地を巡って大神楽を奉納したり、代理参拝の神札を配る桑名市太夫村を本拠地とする伝統芸能である。1年を掛け全国を巡業しているが、12月24日の「増田神社総舞(そうまい)」では本拠である増田神社での奉納のため旅から全社中が帰還する。総舞では八つの舞(獅子舞)と八つの曲(放下芸)...

写真提供:桑名宗社(春日神社)
桑名石取祭 ( 三重県 桑名市 )
全部で43台の祭車(さいしゃ)に鉦や太鼓をつけ、それらを一斉に打ち鳴らす音が人を圧倒する勢いがあることから「日本一やかましい祭り」「天下の奇祭」として知られている。桑名市の春日神社(桑名宗社)を中心に行われる夏の祭で、毎年8月第1日曜日の本楽では春日神社への巡行を行うため、旧東海道などを練り歩くその姿は荒々しく、勇敢さ...

写真提供:熊野市観光協会
七里御浜 ( 三重県 熊野市 / 三重県 紀宝町 )
JR熊野市駅から徒歩5分。七里御浜は、熊野市から紀宝町に至る約22km続く日本で一番長い砂礫海岸であり、熊野吉野国立公園に指定されている。この七里御浜は熊野三山を目指す熊野古道伊勢路の一部にもなっている。 「世界遺産(浜街道)」「日本の渚百選」「21世紀に残したい日本の自然百選」「日本の白砂青松百選」「日本の名松百選」など...

写真提供:鬼ヶ城センター
鬼ヶ城 ( 三重県 熊野市 )
JR熊野市駅から「大又大久保行」バスで約5分。国の名勝および天然記念物「熊野の鬼ケ城 附 獅子巖」(くまののおにがじょう つけたり ししいわ)の一部である。熊野灘の波の浸食によって生じた大小無数の海食洞が、地震による隆起と風化によって並び、熊野灘に面して約1.2km続いている。志摩半島から続くリアス海岸の最南端で、これより南は約...
花窟神社 ( 三重県 熊野市 )
JR熊野市駅から新宮駅行きバスで約4分。花窟神社(花の窟神社)は、伊弉冊尊(いざなみのみこと)と軻遇突智尊(かぐつちのみこと)を祀る神社である。『日本書紀』巻一*に登場する、伊弉冊尊(いざなみのみこと)を葬った紀伊国熊野の有馬村とはこの花の窟だといわれる。今日に至るまで社殿はなく、熊野灘に面した高さ約45mの巨岩である磐...

写真提供:(一財)熊野市ふるさと振興公社
丸山千枚田 ( 三重県 熊野市 )
JR熊野市駅からバス(熊野古道瀞流荘線 瀞流荘方面)で40分、「千枚田・通り峠入口」にて下車、徒歩30分。丸山千枚田は1,340枚の規模を誇り、日本の棚田百選にも選ばれた日本有数の棚田である。その規模や雄大かつ美しい景観は日本一とも言われている。 400年以上前、1601(慶長6)年には2,240枚の田畑があったという記録が残されている...
関宿 ( 三重県 亀山市 )
JR関西本線関駅より徒歩約5分。三重県亀山市にある関宿(せきじゅく)は、東海道53次、江戸から数えて47番目の宿場町である。宿場町の距離は約1.8km。道路の両脇には江戸時代から明治時代にかけて建てられた町家が今でも奇跡的に200軒ほどが残っている。鈴鹿山脈の東麓に位置し、古代には三関*のひとつである鈴鹿関が置かれていた。 関宿...

写真提供:海津市観光・シティプロモーション課
木曽三川の下流部 ( 岐阜県 海津市 / 三重県 桑名市 / 三重県 木曽岬町 / 愛知県 愛西市 / 岐阜県 羽島市 )
木曽三川とは、濃尾平野を流れるわが国有数の大河川・木曽川、長良川、揖斐川の3つの川の総称である。流域の人々はこれらを一筋の川と同様に考え“木曽三川”と呼んで親しんできた。ただ、網状に流れる3つの川は洪水のたびに形を変え、治水の難しさは、輪中や水屋に代表されるこの地域特有の水防共同体を生んだ。輪中とは、洪水に悩まされた地...

伊勢神宮 ( 三重県 伊勢市 )
伊勢神宮は正式には「神宮」と称し、三重県伊勢市とその周辺に鎮座する125のお社の総称である。その中心は、皇室の祖先である天照大御神をおまつりする皇大神宮(内宮)と、天照大御神の食事をつかさどり、衣食住はじめ産業の守り神である豊受大御神をおまつりする豊受大神宮(外宮)である。二つの正宮には宮域内および宮域外に14の別宮、43...
皇大神宮(内宮) ( 三重県 伊勢市 )
内宮(皇大神宮)は、皇室の祖と仰がれ、国民の大御祖神(おおみおやがみ)として崇敬を集める天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀っており、垂仁天皇26年に鎮座した。三種の神器の一つ八咫鏡は、御霊代として宮廷内に祭られていたが、崇神天皇のとき、宮廷内に祭るのは恐れ多いとされ豊鍬入媛命(とよすきいりひめのみこと)を御杖代(...
倭姫宮(内宮別宮) ( 三重県 伊勢市 )
10宮ある内宮別宮の一つであり、内宮と外宮のほぼ中間、倉田山の一角に祀られている。1923(大正12)年11月5日に創立された伊勢神宮の中で最も新しいお宮である。境内は40,000m2の広大な森に包まれており、瑞垣に囲まれた神明造の本殿がある。祭神は倭姫命(やまとひめのみこと)*である。 倭姫命は、諸国をめぐりながら天照...

式年遷宮 ( 三重県 伊勢市 )
神宮の祭典は大きく分けて恒例祭と臨時祭、そして遷宮祭の3つに区別される。恒例祭は毎年定められた日に執行されるもので、特に三節祭(さんせつさい)と呼ばれる神嘗祭と6・12月の月次祭、さらに祈年祭・新嘗祭が重要である。臨時祭は皇室・国家の重大事にあたり、祈願や奉告のため恒例祭に準じて臨時の奉幣を行う祭儀をいう。遷宮以外の祭...
金剛證寺 ( 三重県 伊勢市 )
朝熊山のほぼ山頂にあり、弘法大師空海ゆかりの古刹で、伊勢神宮の鬼門を守る寺として有名である。寺伝では6世紀後半、欽明時代、暁台上人によって創建されたという。825(天長2)年空海が登山し、堂塔を興して真言密教の根本道場としたが、1392(明徳3)年に東岳文昱(とうがくぶんりゅう)が真言宗から臨済宗へと改宗し、臨済宗南禅寺派の...

写真提供:㈱伊勢福
おはらい町・おかげ横丁 ( 三重県 伊勢市 )
近鉄・JR「伊勢市駅」または近鉄「宇治山田駅」から内宮前行バスで約20分。内宮前のいわゆる門前町である。宇治橋から五十鈴川に沿って続く南北約800mの美しく整備された石畳がおはらい町通りである。切妻造、妻入りの風情ある歴史的な建物が並び、通りの両脇に土産物店や味処などが軒を連ねている。かつては日本全国の庶民のあこがれの地で...

写真提供:PIXTA
宇治山田駅 ( 三重県 伊勢市 )
近畿日本鉄道の山田線の駅。伊勢神宮への最寄り駅として1931(昭和6)年に建設され、国の登録有形文化財に指定されている。その前年に開催された「御遷宮奉祝神都博覧会」の会場跡地に開設された。建設当時の面影を、今でも残しており、繊細な装飾とあいまって優美な形態の駅*である。第1回「中部の駅百選」にも選ばれている。

写真提供:神宮徴古館農業館蔵
神宮の博物館 ( 三重県 伊勢市 )
伊勢神宮の内宮と外宮の中間に位置する伊勢市倉田山の丘陵は文教地区となっており、神宮関係の文化施設が集まっている。その代表的な施設が神宮徴古館、神宮農業館、式年遷宮記念神宮美術館であり、その他に神宮文庫*、そして最も新しい内宮別宮である倭姫宮がある。 神宮徴古館は1909(明治42)年に創設された日本で最初の私立博物館で...

写真提供:伊賀上野城
伊賀上野城 ( 三重県 伊賀市 )
JR伊賀上野駅または近鉄伊賀上野駅から伊賀鉄道上野市駅下車、徒歩8分。上野市駅の北側、市街を見下ろす高台にある。日本100名城の一つに選ばれている。1585(天正13)年、筒井(つつい)氏が、天正伊賀の乱で焼かれた平楽寺跡(へいらくじあと)に築城した。1608(慶長13)年、藤堂高虎(とうどうたかとら)*が大改修したが、1612(慶長17...

写真提供:上野文化美術保存会
上野天神祭 ( 三重県 伊賀市 )
伊賀市上野東町の「菅原神社」で行なわれる秋祭りで約400年の歴史をもつ。神輿行列に続き、4町にて構成される百数十人の鬼行列*と9町が持つだんじり(楼車)9基が繰り出し、伊賀上野の城下町を巡行する。祭りの日程は、10月25日までの直近の日曜日に「神幸祭」、前日と前々日を含め3日間開催される。 上野天神祭は国の重要無形民俗文化財...

写真提供:伊賀流忍者博物館
伊賀流忍者博物館 ( 三重県 伊賀市 )
伊賀鉄道「上野市駅」から徒歩で約7分。1964(昭和39)年、上野市(現伊賀市)高山にあった民家を移築し、忍術研究家である奥瀬平七郎が忍者屋敷として開設したのが始まりである。1998(平成10)年には、施設を増築し、現在の名称である伊賀流忍者博物館に名称を変更した。2008(平成20)年には博物館法に基づく登録博物館として三重県が認定...
二見興玉神社 ( 三重県 伊勢市 )
JR二見浦駅より徒歩約15分。海辺より賓日館などがある旅館街、松並木を抜けた先が立石崎である。主祭神は猿田彦大神、相殿が宇迦乃御魂大神。眼前の夫婦岩の沖合700mには、二見浦*に入られた天照大神を猿田彦大神が出迎えたとさえる「興玉霊石」が鎮まっている。「興玉神石」を拝するための神聖な鳥居として夫婦岩に注連縄を張り遙拝所とし...
斎宮跡 ( 三重県 明和町 )
近鉄山田線「斎宮駅」から徒歩約5分。三重県多気郡明和町にある遺跡。斎宮とは、天皇に代わり伊勢神宮に奉仕するために派遣された皇族の女性斎王*が住む御殿と運営のために置かれた斎宮寮という役所があった場所。斎王は天皇の代替わり毎に交替し、飛鳥時代から南北朝時代まで660年間続いたとされる。斎宮跡は都と伊勢神宮を結ぶ古代伊勢道...

写真提供:椿大神社
椿大神社 ( 三重県 鈴鹿市 )
近鉄四日市駅またはJR四日市駅よりバスで約1時間。伊勢平野を見下ろす鈴鹿山系ノ中央に位置する入道ガ岳の山裾にある。2,000社に及ぶ猿田彦大神(さるたひこのおおみかみ)*を祀る神社の総本宮と言われ、式内社、伊勢国一ノ宮、現在は神社本庁の別表神社となっている。三重県内では伊勢神宮、二見興玉神社に次いで3番目に参拝者数の多い神社...

写真提供:伊勢河崎商人館
伊勢河崎のまちなみ ( 三重県 伊勢市 )
JR・近鉄「伊勢市駅」、近鉄「宇治山田駅」から徒歩約15分。伊勢の河崎は、伊勢市の中心を流れる勢田川の両側に広がる町で、水運を生かした問屋街として知られ、特に江戸時代からは伊勢神宮の参宮客への物資を供給する「伊勢の台所」として栄えた。当時は蔵や町家が川の両岸に建ち並び、直接船から物資を蔵に入れることができるようになって...

写真提供:熊野古道センター
三重県立熊野古道センター ( 三重県 尾鷲市 )
JR尾鷲駅からバスで約20分。2004(平成16)年7月、三つの霊場とそれらを結ぶ参詣道*が「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録された。道(巡礼の道*)の世界遺産は世界でも珍しく、この地では、自然崇拝に根ざした神道、中国から伝来し日本で独自の展開を見せた仏教、その両者が結びついた修験道など信仰の多様な形態が育まれてき...

苗村神社 ( 滋賀県 竜王町 )
名神高速道路竜王インターチェンジから東へ4.4kmほど、雪野山と鏡山の間に広がる平野部の綾戸集落の北、大きな鎮守の森にある。近郷33カ村の総社として崇められ、現在でも竜王地方の氏神として信仰が篤い。 茅葺の楼門(国重要文化財)を挟み東西両社からなる。西本殿(国宝)は、鎌倉時代1308(徳治3)年造営の三間社流造*(さんげんし...

御上神社 ( 滋賀県 野洲市 )
延喜式内社で社格は旧官幣中社である。ご祭神は天之御影命であり、紀元前285(孝霊天皇6)年6月18日に三上山に天降ったといわれ、718(養老2)年3月15日に藤原不比等(ふじわらのふひと)が勅命によって現在地に社殿を造営したと伝えられている。金工鍛冶の神として崇敬され、また武神としても源頼朝をはじめ、武家の尊崇を集めた。 神社...
三上山(近江富士) ( 滋賀県 野洲市 )
野洲市の南部にそびえる標高432mの小山で、近江富士*と呼ばれるごとく、円錐形の山容が美しく、湖東平野に君臨している。対岸の大津市側からは、琵琶湖越しに優しい姿を見せる。 山麓にある御上神社のご祭神天之御影命(あめのみかげのみこと)が降臨した山といわれ、山頂には奥宮が祀られ、古代からの原始的な信仰の場である。俵藤太(...
大笹原神社 ( 滋賀県 野洲市 )
JR東海道本線野洲駅から東に向かい、国道8号線に出合ったら、北上し、大篠原交差点を右折するとすぐにある。鏡山の北西麓に鎮座する。薬師如来の化身といわれ、神社南西方の岩蔵寺*の薬師は、大笹原神社とは一体の神社である。 廃仏毀釈が出る前までは、「天王さん」として親しまれ、除疫神としてまつられた。明治になり、境内社の篠原神...

長岡のゲンジボタル ( 滋賀県 米原市 )
JR近江長岡駅前、天野川(あまのがわ)にかかる長岡橋一帯に発生する。6月の全盛期には無数のゲンジボタル*が飛び交い、夏の訪れを告げる。例年その時期に合わせ、地元住民の手づくりイベント「天の川ほたるまつり」を開催し、子ども達手づくりの行灯により道標や観賞の案内所などが設置され、多くの観賞者で賑わう。 長岡地域一帯は「長...

福田寺 ( 滋賀県 米原市 )
JR北陸本線田村駅から徒歩約10分の長沢地区にあり、大きな甍(いらか)が目立つ。長沢御坊(ながさわごぼう)の名で親しまれている。 寺伝によると、飛鳥時代の684(白鳳12)年に地元豪族の息長(おきなが)氏の菩提寺として建立された。後に近江で最初に浄土真宗寺院となり、戦国時代は一向一揆の拠点の一つとして、浅井長政と共に織田信...

青岸寺庭園 ( 滋賀県 米原市 )
JR東海道線米原駅から東へ国道8号を渡って10分程歩くと、太尾山(ふとおやま)西麓に青岸寺がある。もとは米泉寺(べいせんじ)といい、室町時代初期に、近江守護の佐々木京極道誉による開基と伝えられている。その後、兵火により焼失した。 江戸時代前期に彦根藩主三代の井伊直澄の命を受けて入山した彦根大雲寺の要津(ようしん)禅師よ...
彦根城 ( 滋賀県 彦根市 )
JR彦根駅西方の金亀山(こんきざん)の丘上に、琵琶湖畔を望み、白壁の三重三階の天守をのぞかせ聳え立つ。 井伊直政の遣志を継いで、子直継(のちに直勝と改名)が約20年をかけて築城、1622(元和8)年頃に完成した。近江に残る豊臣色一掃の目的を兼ねて、資材は大津・小谷(おだに)・長浜・安土・佐和山などの城の石垣や用材を使用し造...

彦根の街並み ( 滋賀県 彦根市 )
彦根市は、江戸時代は井伊家35万石の城下町で、彦根城を中心に往時を偲ばせる古い町並みが各所に残っている。 彦根城の城下町は、1600(慶長5)年に関ヶ原の戦いで勝利した徳川方の井伊家(直政・直継)によって造られた。1604(慶長9)年から着工された彦根城の築城に伴い、 元和期(1615年から1624年)に3重の堀を巡らす城下町の骨格が...

玄宮楽々園 ( 滋賀県 彦根市 )
彦根城の北東、黒門の外にあり、内堀と中堀の間に位置している。彦根藩主の井伊家の下屋敷として、4代藩主井伊直興(いいなおおき)が1677(延宝5)年に造営し、槻御殿(けやきごてん)と呼ばれていた。現在は、建物部分を楽々園、庭園部分を玄宮園と呼び、国指定の名勝である。 楽々園は、1813(文化10)年の11代藩主井伊直中の隠居に際...

鎌掛谷の石楠花 ( 滋賀県 日野町 )
名神高速道路八日市インターチェンジから東南へ約30分、鈴鹿国定公園特別地域内で鎌掛谷または石楠谷と呼ばれるアカマツの多い谷の山肌に、ホンシャクナゲの群落がある。標高300~400m地点に、面積およそ4万m2、約2万本が密生している。高さ2m前後が多いが、5m近いものもある。 4月中旬から下旬にかけて咲き競い、つぼみのとき...

日野祭 ( 滋賀県 日野町 )
霊峰綿向山の山頂にある大嵩神社の里宮で、日野町村井に鎮座する日野谷の馬見岡綿向神社(うまみおかわたむきじんじゃ)の春の例祭。850年以上の歴史があり、湖東地方で大きな規模の祭である。 毎年5月2日、3日にわたって行われ、2日は宵祭で、夕暮れより各町内の山倉や辻まで曳山が引き出され、提灯に明かりを灯し夜遅くまで祭ばやしが奏...

石馬寺 ( 滋賀県 東近江市 )
繖山(きぬがさやま)東側の明神山の山裾にある。 594(推古2)年に聖徳太子がこの山麓に馬をつなぎ、山上に霊地を探して下山すると馬が石と化して池に沈んでいた*というところから石馬寺の寺号がつけられたと伝える。織田信長の兵火を受けて一時衰微したが、松島瑞巌寺(ずいがんじ)の雲居(うんご)国師の手で再興された。 楓が覆...
永源寺 ( 滋賀県 東近江市 )
湖東の山間で愛知(えち)川の北岸に、1361(康安元)年に佐々木六角氏頼(ささきろつかくうじより)が寂室元光(じゃくしつげんこう)*を迎えて開山した。後にたびたび兵火により荒廃したが、寛永年間(1624~44)に後水尾天皇の勅により、彦根藩の援助を受けて復興した。 石段の参道を登ると、右手に愛知川、左手の石崖には十六羅漢の...

東近江市五個荘金堂の町並み ( 滋賀県 東近江市 )
東は愛知川、西は繖山、南は箕作山に区切られ、ほぼ平坦な水田地帯が広がり、古墳群や古代条里制遺構を残す古い歴史の町である。近世に活躍した近江商人のひとつ五個荘商人の発祥地「てんびんの里」として知られ、今も当時の蔵屋敷が残っている。近江商人たちの本宅と伝統的な農家住宅が一体となった町並みで、1998(平成10)年には国の重要...

阿賀神社 ( 滋賀県 東近江市 )
箕作山(みつくりやま)の南に岩肌を見せてそびえ立つ赤神山(あかがみやま)(標高350m)の中腹にあり、地元では太郎坊宮(たろうぼうぐう)の名で知られる。 社伝によれば、7世紀前期に赤神山に霊威を感じた聖徳太子が神祀りをしたことに始まり、799(延暦18)年には最澄が50余の社殿を山中に建立したという。源義経が参詣したという伝...
余呉湖 ( 滋賀県 長浜市 )
JR北陸本線余呉駅の南にあり、東・南・西の三方を山に囲まれた湖。面積約1.8km2・周囲約6.4km、最大水深13m・平均水深7.4m。南方にそびえる賤ヶ岳(約421m)により、琵琶湖とは隔てられている。海抜132.8mで、琵琶湖より約50m高い。 もともとは、柳ヶ瀬断層の働きによってできた天然の陥没湖で、周囲の山々の渓流や伏流水が流...
宝厳寺 ( 滋賀県 長浜市 )
琵琶湖に浮かぶ竹生島(ちくぶしま)(周囲2km、面積0.4km2 )にある。 寺伝によれば724(神亀元)年、聖武天皇の勅願で僧行基が堂塔を開基させたのが始まりで、弁才天像(大弁才天)を本尊として本堂に安置。753(天平勝宝5)年、近江国浅井郡大領が観音堂に千手千眼観世音菩薩像を安置したとある。豊臣秀吉との関係も強く、...

都久夫須麻神社 ( 滋賀県 長浜市 )
琵琶湖に浮かぶ竹生島(ちくぶしま)(周囲2km、面積0.4km2)にある。 社伝によると、459(第21代雄略天皇3)年に浅井比売命(あざいひめのみこと)(弁財天)を祀った祠(ほこら)を建てたのが始まりと伝えられる。724(神亀元)年、市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)(大弁才天)を祀った「宝厳寺(ほうごんじ)」が創...

長浜曳山祭 ( 滋賀県 長浜市 )
宮前町にある長濱八幡宮(ながはまはちまんぐう)*の春の例祭の中で、毎年4月に行われる。 1573(天正1)年に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が長浜城主になり、その後、初の男子出生を喜び、長浜町民に金子(砂金)をふるまった。それを元手に町民たちが12基の曳山(山車)を作り、八幡宮の祭礼に曳き回したのがこの祭の始まりといわれている...

慶雲館 ( 滋賀県 長浜市 )
JR長浜駅から徒歩5分、旧長浜駅舎前(長浜鉄道スクエア)の南にある。 1887(明治20)年、長浜の豪商・浅見又蔵*氏が、明治天皇行幸に合わせ、私財を投じて建設した迎賓館。「慶雲館」という名称は、時の内閣総理大臣・伊藤博文が命名したと伝わる。約6000m2の敷地内に、高さ約5m、推定重量20tの大灯篭や、高さ5mの芭蕉の句...

黒壁スクエア ( 滋賀県 長浜市 )
北国街道(北陸と京阪神を結ぶ道)と、長浜城から東に延びる大手門通り(美濃の谷汲山華厳寺へと通じる街道)との交差点は、江戸時代に高札が立った「札の辻」と呼ばれ、古くから長浜の中心地である。 この辻に1900(明治33)年、第百三十国立銀行長浜支店(6年後に明治銀行となる)が建てられ、壁が黒塗りだったことから「黒壁銀行」の愛...
比叡山延暦寺 ( 滋賀県 大津市 / 京都府 京都市 )
大津市と京都市に属する境界に位置する。両市から様々な交通手段を利用して、延暦寺まで容易に達することができる。比叡山には、延暦寺という名称の個別の寺院はない。延暦寺には133の堂宇が存在するが、その位置によって大きく、東塔、西塔、横川(よかわ)の3つの地域に分けられ、3地域を総合して延暦寺と呼ぶ。寺域も区切るのがむずかしい...
三井寺(園城寺) ( 滋賀県 大津市 )
京阪電鉄三井寺駅から徒歩7分、三井寺とも園城寺とも呼ばれる天台寺門宗の総本山である。 園城寺という呼び名は、672年の壬申の乱で敗れた大友皇子(おおとものみこ)*の子、大友与多(おおとものよた)王が、父の霊を弔うために、「田園城邑」を寄進して寺を創建し、この文字にちなみ、天武天皇から「園城」という勅額が贈られたことが...
日吉大社 ( 滋賀県 大津市 )
比叡山の東麓、八王子山(牛尾山)の山裾に鎮まる当大社は、紀元前91(崇神天皇7)年に創祀された全国3800余りの分霊社(日吉、日枝、山王神社)の総本宮である。古くは山王七社*といわれたように、国宝の東本宮*・西本宮*など建築美を誇る多くの社殿が、大宮川の渓流が流れる森に立つ。境内には約3000本のモミジがあり、とりわけ秋は、壮...
浮御堂(満月寺) ( 滋賀県 大津市 )
大津市北部、堅田にある。湖中にのびた橋の先に宝形造の仏堂が立っている、これが浮御堂である。臨済宗大徳寺派の寺院で、寺名を海門山満月寺という。 源信(恵心僧都)*が長徳年間(995~999)、湖上安全と衆生済度のため一堂を建て、1000体の阿弥陀仏を安置して千本仏堂と名付けたのに始まると伝わる。その後長らく荒廃していたが、江...

写真提供:西教寺
西教寺 ( 滋賀県 大津市 )
京阪石山坂本線坂本比叡山口駅の北西約1.5km、比叡山の東麓に広大な寺地を占める天台真盛(しんせい)宗の総本山。 聖徳太子が恩師である高麗僧の恵慈*、恵聡のために創建したと伝えられている。良源(慈恵大師)*が天台の念仏道場とし、源信(恵心僧都)*も入寺し、次第に栄えるようになった。1486(文明18)年、真盛(しんせい)*が...
石山寺 ( 滋賀県 大津市 )
京阪電鉄石山寺駅から約1km、瀬田唐橋から南へ約2km、伽藍山(がらんやま)を背に瀬田川に臨む佳景の地に立つ。天平時代からの豊かな歴史に支えられ、古来石山詣と称して人々に親しまれた。文学にも再々登場し、加えて貴重な文化財も多く保存する。西国三十三所第13番霊場で、今も多くの人が訪れる湖南屈指の名刹。境内には石山寺硅灰石が露...
近江神宮 ( 滋賀県 大津市 )
京阪電鉄石山坂本線近江神宮前から徒歩7分。天智天皇6年(667年)、同天皇が都を飛鳥から近江大津宮へ遷された由緒に因み、天智天皇を祭神に、1940(昭和15)年、皇紀2600年を記念して大津市街の北方、宇佐山(うさやま)の山腹に創建された。官幣大社に列せられる。 朱塗の楼門をくぐると、樹林に包まれた白木造の外拝殿が現れ、背後に回...
坂本門前町の街並み ( 滋賀県 大津市 )
比叡山の東麓にある延暦寺や日吉大社の門前町。比叡山の歴史とともに栄枯を重ね、平安時代から、山側の上坂本が門前町、湖畔の下坂本が荷揚げ港として発展し、中世には近江国最大の都市として繁栄。坂本港から運ばれる物資の集積地、京への中継地として人口1万数千人を数える商業都市になった。 比叡山焼討ち後は次第に浜大津にその地位...
大津祭 ( 滋賀県 大津市 )
湖国三大祭*の一つで、天孫(てんそん)神社*の例祭。スポーツの日前日に行われる本祭で、13基の曳山(ひきやま)が市内を練り歩く曳山巡行が祭りのハイライト。豪華なゴブラン織りや精巧な金具に飾られた曳山がコンチキチンの囃子にのってゆるゆると動き、からくり人形の所作が演じられる。 慶長年間(1596~1615)に鍛治屋町に住む塩...

山王祭(日吉大社 ) ( 滋賀県 大津市 )
山王さんといわれる日吉大社の例祭で、湖国三大祭*の1つ。791 (延歴10)年、桓武天皇により日吉社に2基の神輿が寄進されて以来、1200年以上の歴史を有する祭りで、西本宮 大己貴神(おおなむちのかみ)・東本宮 大山咋神(おおやまくいのかみ)の鎮座の由来をたどりながら、天下泰平・五穀豊穣を祈る。祭礼中、山王七社の7基の神輿(1基150...
滋賀院門跡 ( 滋賀県 大津市 )
京阪電鉄坂本比叡山口から国道47号線を西に向かい、生源寺の前を左に折れると、老舗のそば屋鶴喜がある。隣には鶴屋益光、少し先に廣栄堂寿延の和菓子の店があり、ともに延暦寺や日吉大社など各寺院の御用達になっている。この道を進むと、すぐに右手に滋賀院の門がある。現在は延暦寺の本坊があるが、江戸時代末まで天台座主(ざす)の法親...

河内の風穴 ( 滋賀県 多賀町 )
近江鉄道多賀大社前駅から北東へ、芹川渓谷を7km遡った霊仙山(りようぜんさん)南西麓のカルスト地帯にあり、約55万年前にできた鍾乳洞である。総延長は10,000m以上で、入口は高さ1mと小さいが、洞内は3層構造で小洞が複雑につながっていて、推定面積は1500m2といわれる。 1922(大正11)年に観光用の松明がつけられ、現在は...

多賀大社 ( 滋賀県 多賀町 )
近江鉄道多賀大社前駅の前に大鳥居が立ち、神社まで徒歩10分の参道には土産物店が並ぶ。お多賀さんの愛称で知られ、かつて「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」と里謡にも謡われ、伊勢神宮の祭神である天照大神(あまてらすおおみかみ)の両親、伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)を...

琵琶湖 ( 滋賀県 高島市 / 滋賀県 長浜市 )
日本最大の面積(約670km2)をもつ淡水湖。滋賀県の約6分の1を占め、湖岸線は235kmにも及ぶ。古くは近淡海(ちかつあふみ)、鳰の海(におのうみ)などと呼ばれていたが、近世にその形がちょうど楽器の琵琶に似ていることから、琵琶湖と名付けられたといわれる。 断層による陥没で生じた湖である。湖西は山地が湖水間近までそ...

マキノ高原のメタセコイア並木 ( 滋賀県 高島市 )
JR湖西線マキノ駅からマキノ高原線バスで約6分。農業公園マキノピックランドを縦貫する県道小荒路牧野沢線に、約2.4kmにわたりメタセコイア*が約500本植えられている。遠景の野坂山地の山々と調和し、マキノ高原へのアプローチとして、25mの高さの並木が四季折々に美しい景観を見せている。 この並木は、1981(昭和56)年に学童農園「マ...

写真提供:西明寺
西明寺 ( 滋賀県 甲良町 )
琵琶湖の東、鈴鹿山脈の麓に位置する天台宗寺院で、湖東三山の一つ。 2015年にアメリカのニュース専門局CNNのWeb特集において『日本の最も美しい場所31選』(現在は36選)に選ばれた関西有数の観光名所。名神高速道路湖東三山スマートI.Cから約5分である。 平安時代の初期にあたる834(承和元)年に仁明(にんみょう)天皇の勅願により...
油日神社 ( 滋賀県 甲賀市 )
JR草津線油日駅から東へ歩き、ご神体となる油日岳(694m)の北西麓に鎮座する。 山頂に奥宮があり、水の神である岳大明神「罔象女命(みつはのめのかみ)」が祀られている。当社はその里宮にあたり、油の火の神を祀っている。 開創年代は明らかではないが、『日本三代実録』*に「元慶元年(877年)……近江国正六位上油日神社に従五位下...
大池寺 ( 滋賀県 甲賀市 )
近江鉄道水口駅北西、丘陵地に囲まれた閑静な地にある。長い刈込み垣に挾まれた参道を行くと、山門と白壁の塀が目を引く。天平年間(729~749)、行基菩薩が開創という古寺で、1321(元享元)年東福寺の僧無才智翁禅師によって禅宗に改宗された。1577(天正5)年、戦火にあい境内全域が焼失したが、1667(寛文7)年、瑞鳳寺(仙台市)の丈巌...
櫟野寺 ( 滋賀県 甲賀市 )
JR草津線油日駅の北東、油日神社の北にあり、「いちいの観音さん」の名で親しまれている。792(延暦11)年、最澄が比叡山根本中堂の用材を求めてこの地を訪れたとき、櫟(いちい)の木に十一面観音を彫刻し、これを本尊にして開いたのが始まりという。これ以後、この地方の中心的天台寺院として栄え、今なお藤原時代(894~1185)の仏像を多数...
MIHOMUSEUM ( 滋賀県 甲賀市 )
甲賀市の西部、信楽と大津市との境界に近い山中にある。美術館までは信楽高原鐵道信楽駅と大津市のJR石山駅からバスが出ている。 創立者小山美秀子の「美術を通して、世の中を美しく、平和に、楽しいものに」との想いからはじまったコレクションは、多彩な日本美術ととも世界の古代美術など約3,000件を所蔵。設計はパリ・ルーヴル美術館ガ...

常楽寺 ( 滋賀県 湖南市 )
JR草津線石部駅の南方約4km、阿星山の北麓にある。湖南三山の一つ。広い境内にどっしりとした本堂*と三重塔*がおちついた雰囲気で立つ。 和銅年間(708~715)に元明天皇の勅命により、良弁*が開基した「阿星寺五千坊」の中心寺院として建立され、紫香楽宮(742~745)の鬼門鎮護として栄えた。平安~鎌倉時代には、皇室の帰依を受けて...
善水寺 ( 滋賀県 湖南市 )
JR草津線甲西駅と三雲駅のちょうど真ん中から北東方向に位置する岩根山(標高405m)の中腹にあり、湖南三山の一つ。曲がりくねった山道を登りつめたところに、堂々とした本堂*が立つ。 和銅年間(708~715)に国家鎮護の法相宗道場として創建されたといわれ、和銅寺と号した。そののち最澄が比叡山を開創し、堂舎建立のため用材を甲賀の...
長寿寺 ( 滋賀県 湖南市 )
JR草津線石部駅から車で10分、常楽寺の南東1.5km、阿星山北東麓にある。常楽寺の西寺に対して東寺と呼ばれる古刹。山門から本堂まではモミジの並木道がつづき、参道の右手に鎌倉時代の石造多宝塔があり、さらに進むと樹林を背にして本堂*が立つ。むかしは大伽藍があったと伝えられる境内も、今は森閑としている。 天平年間(729~749)に...

長命寺 ( 滋賀県 近江八幡市 )
琵琶湖に臨む長命寺山(標高333m)の8合目(250m)に建てられ、西国三十三所観音霊場*の第31番札所で、健康長寿を祈願する多くの参拝者で賑わう。 寺伝によれば、3世紀後半から4世紀初頭の第12代景行(けいこう)天皇の時代に、大臣の武内宿禰(たけのうちのすくね)が、この山で柳の巨木に「寿命長遠所願成就(じゅみょうちょうおんしょ...

日牟禮八幡宮 ( 滋賀県 近江八幡市 )
JR近江八幡駅の北西で、標高272mの八幡山(はちまんやま)の南麓にあり、「八幡さま」として広く親しまれ、近江商人からの信仰も篤く、近江八幡の地名の由来にもなっている。 社伝によれば、131年に第13代成務天皇が即位の折に創建され、991(正暦2)年には八幡山に社を建て、九州の宇佐八幡宮を勧請して上の八幡宮を祀った。1005(寛弘2...

観音正寺 ( 滋賀県 近江八幡市 )
琵琶湖の東、標高433mの繖山(きぬがさやま)の山腹にあり、西国三十三所観音霊場*の第32番札所で、万事吉祥の縁結びの祈願道場として多くの参拝者で賑わう。 寺の縁起によれば、近江を遍歴していた聖徳太子が、琵琶湖から現れた人魚に苦しみから救ってほしいと懇願され、太子自ら千手観音像を刻み、飛鳥時代605(推古天皇13)年、山頂に...

安土城 ( 滋賀県 近江八幡市 )
JR東海道線安土駅の北東約1.5kmの安土山(標高199m)に織田信長が築いた平山城。 1575(天正3)年に、「長篠・設楽原の戦い」で信長・徳川家康連合軍の鉄砲隊が武田勝頼軍を潰滅した後、信長が天下統一に向けて、翌1576年に築城を命じ、1579(天正7)年に完成した。現在は、その後の干拓により四方とも陸地だが、当時は琵琶湖の内湖(伊庭...

近江八幡左義長まつり ( 滋賀県 近江八幡市 )
日牟禮八幡宮で行なわれる火祭。近江八幡に春の訪れを告げるお祭りで、例年3月14・15日に近い土・日曜日に催される。 元々は安土城下で行われていたもので、城主であった織田信長自らも踊り出たと伝えられる。信長亡き後、領主となった豊臣秀次が八幡山城の城下町を開き、安土から八幡城下に移り住んだ町衆によって再開された。 左義長...
近江八幡の町並み ( 滋賀県 近江八幡市 )
近江八幡市は琵琶湖に面し、湖東地域のほぼ中央にある。 1585(天正13)年、豊臣秀次(ひでつぐ)が叔父の豊臣秀吉の命により八幡山(はちまんやま)に城を築き、その南麓に安土城下の人々を移し住まわせて城下町とし、琵琶湖の水を導く八幡堀を開削し、楽市楽座を開いた。八幡山城廃城後は、幕府直轄地(天領)となったが、江戸時代を通...
百済寺 ( 滋賀県 東近江市 )
琵琶湖の東、鈴鹿山脈の麓に位置し、名神高速道路湖東三山スマートI.Cから約10分である。西明寺(さいみょうじ)・金剛輪寺(こんごうりんじ)と並んで湖東三山の一つに数えられ、最も南にある。 寺伝では、606(推古天皇14)年に聖徳太子の勅願により創建されたという古刹。仏教が朝鮮半島の百済(くだら)国経由で伝来したことから山号...
宇治川 ( 滋賀県 大津市 / 京都府 宇治市 / 大阪府 大阪市 )
宇治川は、上流部の滋賀県が瀬田川で、京都府に入って宇治川となり、大阪府に入るころから淀川となる。古来、本河川は近江~山城~大和~難波を結ぶ要路であったことから、その川の美しさを知られていた。 瀬田川は上流部ではあるが、琵琶湖から流れ出る唯一の川であるため、たっぷりとした水量で流れ、大津市内で瀬田唐橋*、瀬田川洗堰...
金剛輪寺 ( 滋賀県 愛荘町 )
名神高速道路湖東三山スマートI.Cより約1分。西明寺(さいみょうじ)・百済寺(ひゃくさいじ)と並ぶ湖東三山の一つ。 寺伝では、741(天平13)年、聖武天皇の命で行基が建立、848~851年(嘉祥年間)に円仁(慈覚大師)が天台の道場として中興した。織田信長の兵火の被害は少なく、湖東三山の中では寺宝がもっとも多く残っている。総門の...
田村神社 ( 滋賀県 甲賀市 )
鉄道はJR草津線油日駅が最寄り駅になるが、土山中学校を目指して北東へ8kmほど歩くことになるため、貴生川駅南口のバスターミナルより市内バスを利用するのが良い。国道1号線のすぐ北、野洲川の支流田村川沿いにある閑静な森の中に鎮座する古社。 開創年代は明らかではないが、812(弘仁3)年の建立と言われる。鈴鹿の鬼退治をした坂上田...

勝部の火祭り ( 滋賀県 守山市 )
鎌倉時代、土御門天皇を呪う大蛇を退治し焼き払ったところ、天皇の病気が治ったとの言い伝えを起源とする。胴体は勝部で、頭は浮気(ふけ)で退治されたことから、勝部神社*と浮気町(守山市)の住吉神社で、それぞれ胴体と頭に見立てた松明を燃やし、1年の無病息災を祈る。 勝部神社の火祭りは800年余りもの長い間続けられている。1月第...
佐川美術館 ( 滋賀県 守山市 )
JR東海道本線守山駅からバスで約30分。対岸のJR湖西線堅田駅はバスで約15分。 佐川急便株式会社が創業40周年記念事業の一環として、1998(平成10)年に開館した。3棟の建物は水に浮かぶように佇み、周辺の自然環境とも調和して、それ自体がアートとなっている。 日本画家の平山郁夫*、彫刻家の佐藤忠良*、陶芸家の樂直入*の作品を展...

銅鐸博物館(野洲市歴史民俗博物館) ( 滋賀県 野洲市 )
JR東海道本線野洲駅から北東方向、弥生の森歴史公園に隣接する。 博物館の約500m北西の大岩山の中腹から、1881(明治14)年に14個の銅鐸(うち2個は現在所在不明)が、さらに1962(昭和37)年には10個の銅鐸が出土した。これらの中には、高さ134.7cm・重さ45.47kgと日本最大のものも含まれていた。その大半は近畿式銅鐸*であるが、東海...

保津川 ( 京都府 亀岡市 / 京都府 京都市西京区 / 京都府 京都市右京区 )
丹波高地に発する大堰川(おおいがわ)の中流部にあたり、亀岡盆地南東端から京都盆地西端の嵐山までの約16kmをいい、古生層の山地を曲流しながら峡谷をなして流れるので保津峡ともいう。嵐山渡月橋から下流は桂川と呼ばれている。 保津川下り(乗船時間約2時間)では、様々な景観が楽しめる。乗船場はJR嵯峨野線亀岡駅から徒歩8分の位置...

鴨川 ( 京都府 京都市 )
京都市の代表的な川であり、市街地東部を北から南に流れる。北区雲ヶ畑(くもがはた)・桟敷ヶ岳を源とし南下、上京区出町付近で高野川と合流後、伏見区下鳥羽で桂川と合流し淀川に入る。全長約27km。814(弘仁5)年「日本紀略」に記されたのが最も古い記録とされ、以後歴史や文学にしばしば登場する。現在、高野川合流点(出町柳)以北を賀...

写真提供:パーソナル企画
天橋立 ( 京都府 宮津市 )
京都丹後鉄道天橋立駅から徒歩5分。宮島(広島県)・松島(宮城県)と並ぶ日本三景*の一つ・天橋立は、宮津湾北西岸の江尻から南の文珠までの間、宮津湾と阿蘇海(あそかい)を真一文字にたち切り、南西につき出した全長3.6km、幅20~170mの砂州(さす)*である。砂州上には大小約6,700本の松が続き、遠目には海面上に松並木が浮かび上がっ...

写真提供:京都北山杉の里総合センター
北山杉 ( 京都府 京都市北区 )
北山杉は京都市の北西部、北区中川を中心とする地域で産する杉である。一帯は北山杉の里と呼ばれ、中川・杉阪・真弓・小野・大森という5地域に分かれる。中川は京都駅からJRバスで約1時間。市街地を抜けたバスは国道162号(周山街道)を北上し、紅葉で有名な高雄を過ぎ、ほどなくして中川に着く。川岸まで山裾を延ばす山々に、青葉の帽子を被...

写真提供:京都市都市緑化協会
円山公園のサクラ ( 京都府 京都市東山区 )
円山公園は西に八坂神社、南に高台寺、北に知恩院の古社寺に囲まれ、さらに東は東山連峰に続くところにある。京阪本線「祇園四条駅」から徒歩10分で到達する。明治時代の神仏分離により、安養寺、八坂神社などの境内の一部を没収して、1886(明治19)年に円山公園が開設されたもの。京都市ではもっとも古い公園で小川治兵衛(植治)*の手に...

写真提供:清水寺
清水寺 ( 京都府 京都市東山区 )
京都駅の東北に位置し、比較的運行本数の多いバス路線にある五条坂ないしは清水道のバス停で下車(京都駅からバスで約15分)。バス停から清水寺までは坂道を徒歩約10分。道筋*には、土産物店、茶店などが立ち並び楽しい。往時より数は減ったとはいえ、清水焼*の店も目に付く。 清水寺は清水山(音羽山)の中腹にあり、13万m2...

鹿苑寺(金閣寺) ( 京都府 京都市北区 )
正式名称は鹿苑寺だが一般に金閣寺の名で知られる。京都駅から北へバスで約50分。衣笠山の東、背後に大文字山があり、自然を巧みに取り入れた境内の西に、寺の通称の由来ともなった金閣がさん然と鏡湖池(きょうこち)に姿を映している。金閣が再建とはいえ、そのみごとに一体化した建築美と庭園美が室町時代北山文化*の面影を伝えている。...

写真提供:平等院
平等院 ( 京都府 宇治市 )
JR奈良線宇治駅から徒歩10分。宇治川の左岸に位置する。朝日山を望む境内には鳳凰堂の名で知られる阿弥陀堂のほかに、鐘楼*・観音堂*・ミュージアム鳳翔館*などが立つ。1053(天喜元)年、藤原頼通*が建立した「鳳凰堂」の中央部にある「中堂」内には、平安期の名仏師・定朝*作の阿弥陀如来坐像*が安置される。堂内壁面には雲に乗って音楽...

写真提供:パーソナル企画
東寺(教王護国寺) ( 京都府 京都市南区 )
京都駅の西南にあり、境内の東は大宮通、南は九条通に面して築地塀に囲まれている。最寄り駅は近鉄東寺駅で、九条通を西へ徒歩10分。京都駅八条口からも徒歩15分とアクセスがよく、バスの便もよい。 平安京が開かれたときに、羅城門の左右(東西)に置かれた官寺(国立寺院)の一つで、境内は創建当初の伽藍配置のままといわれ、西寺が廃...

写真提供:東本願寺
東本願寺 ( 京都府 京都市下京区 )
京都駅から北へ徒歩約6分、七条通まで上がると、北西側一帯に広大な伽藍が目に入る。正式名称を「真宗本廟」という真宗大谷派の本山である。西本願寺の東に位置し、一般に東本願寺とよばれ、地元では「お東さん」と親しまれる。親鸞聖人の死後、その末娘の覚信尼が1272(文永9)年に東山の大谷に廟堂を建てたことが本願寺の起源。1602(慶長7...

写真提供:パーソナル企画
西本願寺 ( 京都府 京都市下京区 )
通称を西本願寺、正式名称を龍谷山本願寺という、浄土真宗本願寺派*の本山である。親しみを込めて「お西さん」とも呼ばれる。堀川通と七条通の交差点の北西側に位置する寺地は広大で、東西約330m、南北約290mにおよぶ。桃山文化を代表する建造物や庭園を今に伝え、世界遺産にも登録されている。 1272(文永9)年、親鸞聖人の末娘の覚信...

三十三間堂(蓮華王院) ( 京都府 京都市東山区 )
京都駅から市バスで約10分、博物館三十三間堂前下車すぐ。東山地区の入口にあり、七条通を挟んで京都国立博物館と向かい合っている。本堂内陣の柱間が33あるので「三十三間堂」と呼ばれるが、正式名称は「蓮華王院」。本堂内に千体観音がずらりと立ち並ぶ光景は圧巻である。 1164(長寛2)年、後白河法皇の院御所の法住寺殿の一角に、法皇...

写真提供:PIXTA
南禅寺 ( 京都府 京都市左京区 )
東山地区の北部にあり、南禅寺橋から東にのびる松並木の道が南禅寺の参道で、やがて中門に至る。東山山麓に位置する南禅寺は、京都五山*の最高位の寺格にあたる「五山之上」に列せられた大寺で、臨済宗南禅寺派の大本山である。この地には亀山天皇が1264(文永元)年に造営した離宮があったが、のちに天皇は大明国師に帰依して法皇となり、1...

写真提供:東福寺
東福寺 ( 京都府 京都市東山区 )
東山区の最南部、伏見区に接するところにあり、京都駅からJR奈良線で東福寺駅下車。京阪本線東福寺駅もJR駅と並んでいる。駅から東福寺北大門まで徒歩約10分である。約16万5,000m2の寺域が広がる、臨済宗東福寺派の大本山。京都五山*の4位であり、三門・浴室・本堂・東司・禅堂・方丈などの堂宇が禅宗の伽藍様式どおりに並んでい...

鞍馬寺 ( 京都府 京都市左京区 )
京都市街の北方、深い緑におおわれた標高584mの鞍馬山南東斜面にあり、牛若丸の修行の場として、また、大天狗僧正坊の住む地として知られる寺である。叡山電車の終点鞍馬駅で下車すると、大きな天狗の面が出迎える。駅から鞍馬寺仁王門*まで徒歩5分。門から左手に進むと「鞍馬の火祭」*で名高い由岐(ゆき)神社*、九十九(つづら)折り...

慈照寺(銀閣寺) ( 京都府 京都市左京区 )
年間通して多くの観光客でにぎわう「哲学の道」の北端、銀閣寺橋を東に入ったところにある臨済宗相国寺派の寺。正しくは慈照寺といい、観音殿(銀閣)*のあることから一般に銀閣寺といわれる。北山文化を象徴する金閣寺に対し、室町時代後期の東山文化*を象徴する代表的寺院である。銀閣というものの銀箔貼りではなく、当初、上層の内外壁...

平安神宮 ( 京都府 京都市左京区 )
岡崎公園*を南北に貫く神宮道は、平安神宮の参道にあたる。冷泉通から正門の神門*(応天門)をくぐると、広い前庭の向うに大極殿*の優美な姿が望まれる。平安神宮は、1895(明治28)年、平安遷都1100年を記念して創建され、桓武天皇を祀り、市民の総社としたものである。1940(昭和15)年10月には、孝明天皇の神霊も合祀している。 社...

写真提供:一般社団法人西芳会
西芳寺(苔寺) ( 京都府 京都市西京区 )
阪急嵐山線上桂駅から徒歩20分、京都駅から京都バス苔寺・すず虫寺行きに乗れば終点下車、徒歩3分、西芳寺川の畔に西芳寺は立つ。庭一面絨毯を敷きつめたような苔の美しさから一般に苔寺として名高い。創建については諸説ある。1400(応永7)年に記された『西芳寺縁起』では、創立は聖徳太子の別荘にさかのぼる。『夢窓国師年譜』では、天平...

写真提供:龍安寺
龍安寺 ( 京都府 京都市右京区 )
京福電鉄北野線龍安寺駅徒歩7分にある。1450(宝徳2)年、細川勝元が徳大寺家の別荘であったこの地を譲り受け、妙心寺の義天玄承に帰依して禅刹を建立した。当時威容を誇ったが、応仁の乱やその後の火災で焼失し、現在の姿になった。龍安寺駅から北上し総門をくぐり、道路を横断してなお進むと山門が立つ。山門を抜けると左手に鏡容池*が広...

圓通寺 ( 京都府 京都市左京区 )
叡山電鉄京都精華大前駅から徒歩25分、地下鉄北山駅からは徒歩30分。閑寂な地に佇む臨済宗妙心寺派の寺院。境内には本堂・客殿・庫裏などが建ち、比叡山を借景にした庭園*で知られる。ここは後水尾上皇*が造営した幡枝(はたえだ)離宮だったところで、1672(寛文12)年上皇の離宮、修学院の完成とともに近衛家に下賜された。1678(延宝6)...

写真提供:酬恩庵(一休寺)
酬恩庵(一休寺) ( 京都府 京田辺市 )
JR京田辺駅から東へ約1.3km。元の名は妙勝寺で、鎌倉時代、臨済宗の高僧大應国師が中国の虚堂和尚に禅を学び、帰朝後の1267(文永4)年、禅の道場をここに建てたのが始まりである。その後、元弘の戦火にかかり復興もならず荒廃していたものを、一休禅師*が、1456(康正2)年、宗祖の遺風を慕って堂宇を再興し、師恩にむくいる意味で「酬恩庵...

写真提供:天龍寺
天龍寺 ( 京都府 京都市右京区 )
世界文化遺産。嵐電嵐山本線嵐山駅を下車すると正面すぐ北側に参道入口が見える。京都五山*の第1位という格式を誇った臨済宗天龍寺派の大本山である。度重なる火災で伽藍の大半は明治以降の再建だが、亀山を背景に法堂・大方丈・多宝殿が、また総門から法堂に至る参道の両脇に塔頭が整然と並ぶ。法堂の天井いっぱいに描かれた雲龍図*は、加...

写真提供:醍醐寺
醍醐寺 ( 京都府 京都市伏見区 )
世界文化遺産。地下鉄東西線醍醐駅から東へ徒歩約10分で醍醐寺の総門に至る。山科盆地の南東に位置する醍醐山とその麓付近を醍醐と呼び、伽藍は山上の上(かみ)醍醐と山麓の下(しも)醍醐に分かれる。真言宗醍醐寺派の総本山。本尊は薬師如来。山上山下に80余棟の堂塔伽藍が甍を連ね、江戸時代以来の修験道当山派本拠地としての森厳な雰囲...
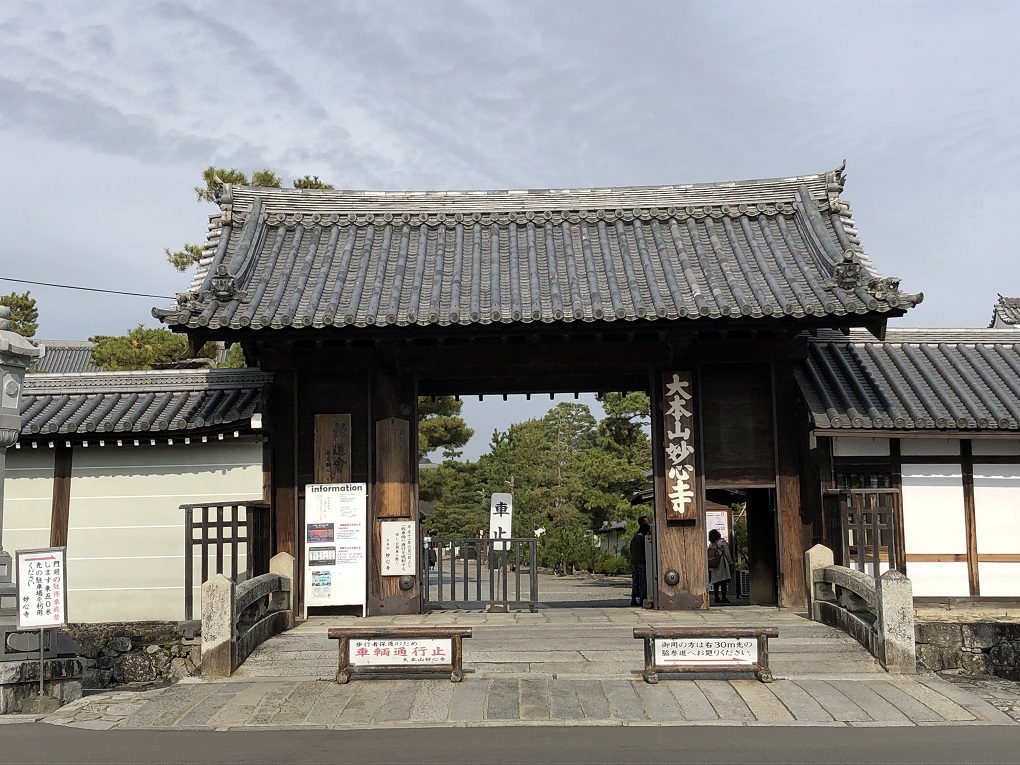
妙心寺 ( 京都府 京都市右京区 )
JR山陰線(嵯峨野線)花園駅から南総門まで徒歩5分、嵐電北野線妙心寺駅から北総門まで徒歩4分。臨済宗妙心寺派の大本山である。妙心寺派は臨済宗最大の宗派で、国内外に約3,400の関係寺院を擁する。境内は広く、南北約600m、東西約500m、総面積は約33万m2。その中心に堂々たる七堂伽藍を構え、周囲に46もの塔頭寺院が立ち並んで...

八坂神社 ( 京都府 京都市東山区 )
京阪本線祇園四条駅から徒歩約5分。四条通の東の突き当たり、祇園の花街と円山(まるやま)公園にはさまれた東山の中心にあり、「祇園さん」の名で親しまれている。祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)・櫛稲田姫命・八柱御子神。社伝では656(斉明天皇2)年、高句麗系渡来人伊利之の創祀、または876(貞観18)年の南都の僧・円如の創祀という...

写真提供:高台寺
高台寺 ( 京都府 京都市東山区 )
豊臣秀吉の正室、北政所ねねこと、高台院が秀吉の菩提を祈るために曹洞宗の弓箴を開基に迎え、1606(慶長11)年に建立した禅宗寺院(曹洞宗)。造営に際し、取りまとめ役の寺院への口添えをするなど徳川家康が積極的に援助したと伝わる。高台院の意向により伏見城の遺構や秀吉と高台院の所縁のものが堂宇には使用され、壮麗な寺院であった。...

写真提供:黄檗山萬福寺
萬福寺 ( 京都府 宇治市 )
JR奈良線・京阪宇治線黄檗駅から徒歩5分。宇治の北方にある。中国明の僧、隠元隆琦(いんげんりゅうき)*が開創した黄檗(おうばく)宗*の大本山。1654(承応3)年63歳で福建省から来朝した隠元が、1661(寛文元)年に中国の黄檗山萬福寺にならって建立。隠元のあと13代まで明僧の住持が続き、14世竜統が日本人で初めて住持となった萬福寺...

写真提供:知恩院
知恩院 ( 京都府 京都市東山区 )
正式名称は、華頂山知恩教院大谷寺という、浄土宗の総本山。東山三十六峰の一つ・華頂山の麓に広がる大寺院である。法然上人が草庵を結び人々に念仏の教えを説き、1212(建暦2)年に生涯を閉じた地に建つ。日本最大級の木造門である三門*をくぐり、石組の階段を登り切ると、法然上人の御影を祀る堂々たる大建築の御影堂*がどっしりと構えて...

写真提供:智積院
智積院 ( 京都府 京都市東山区 )
京阪七条駅から徒歩10分、七条通の東の突き当たり、東山の阿弥陀ヶ峰の麓にある。真言宗智山派の総本山の大寺院。智山派は大本山として成田山新勝寺・川崎大師平間寺・高尾山薬王院、別格本山として高幡山金剛寺・大須観音宝生院があり、末寺は全国に3,000余を擁する。 智積院はもと紀州根来寺(ねごろじ)の塔頭だった。真言教学を学ぶ学...

伏見稲荷大社 ( 京都府 京都市伏見区 )
京都駅からJR奈良線で5分、稲荷駅を降りると目の前には壮観な大鳥居。全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮である伏見稲荷大社は、古くから五穀豊穣・商売繁昌の神として崇敬を集め、参拝者は絶えることがない。大鳥居をくぐると、稲荷山*を背にして楼門・外拝殿・本殿*・権殿*など、朱塗りの壮麗な社殿が並び、また境内には多くの摂末社が...

青蓮院門跡 ( 京都府 京都市東山区 )
地下鉄東西線東山駅から徒歩5分。駅を出て三条通を東へ行き、神宮道の交差点を南に進むと、大きなクスノキが見えてくる。皇室とのゆかりが深い雅な名刹・青蓮院門跡の目印である。寺は、天台宗総本山比叡山延暦寺の三門跡の一つとして古くから知られ、現在は天台宗の京都五箇室門跡の一つに数えられている。最澄が比叡山延暦寺を創建した際に...
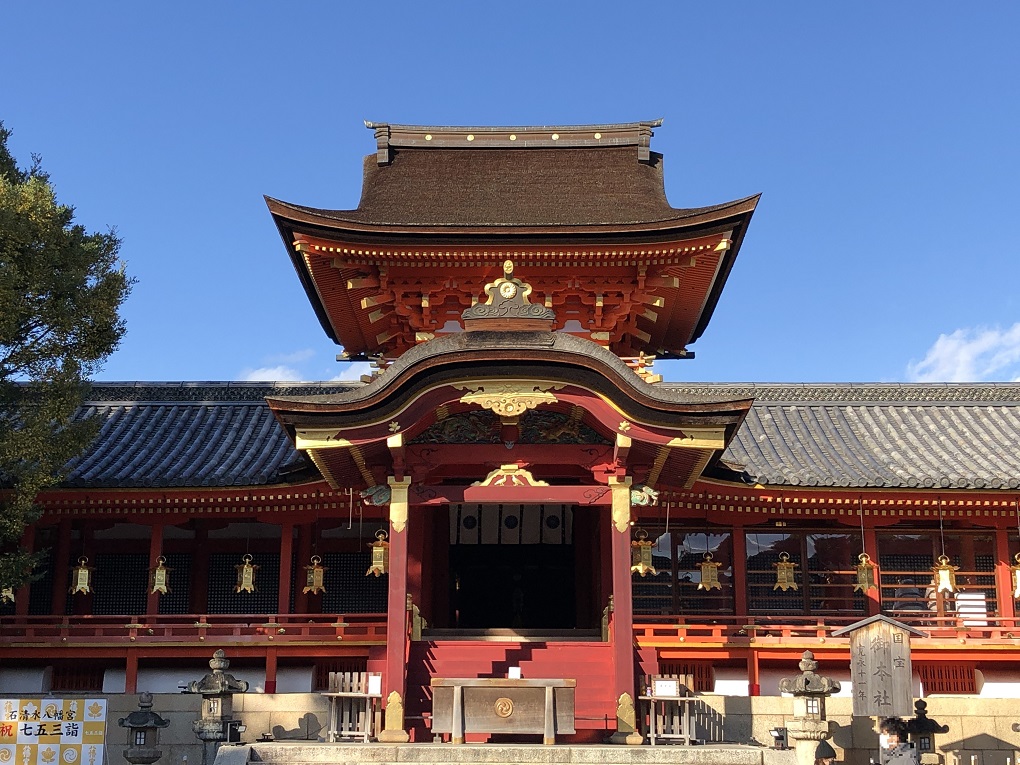
石清水八幡宮 ( 京都府 八幡市 )
京阪電車石清水八幡宮駅から表参道を歩いて登って約30分。同駅前から参道ケーブルカーを利用すれば八幡宮山上駅下車、徒歩5分。木津川・宇治川・桂川の合流点の南、対岸には天王山がそびえる要害の地、男山山頂に立つ。祭神は応神天皇・比咩(ひめ)大神・神功皇后。859(貞観元)年、奈良大安寺の行教律師の奏請で大分の宇佐八幡宮から勧請...

詩仙堂丈山寺 ( 京都府 京都市左京区 )
叡山電鉄叡山本線一乗寺駅から徒歩15分。江戸時代初期の文人・石川丈山*が1641(寛永18)年に造営し、31年間隠棲した山荘跡。現在は詩仙堂丈山寺という曹洞宗の寺院となっている。詩仙堂は、正しくは凹凸窠(おうとつか)という。斜面のでこぼこの地に建てられた住居という意味で、丈山は凹凸窠と名づけた。詩仙堂とよばれるのは、堂内の中...

建仁寺 ( 京都府 京都市東山区 )
祇園の繁華街の南。花街宮川町にも隣接する、臨済宗建仁寺派の大本山。1202(建仁2)年、源頼家の帰依を受けた栄西*が、中国(宋)の百丈山(ひゃくじょうざん)にならって建立した寺で、寺名は創建時の年号からつけられた。当初は、天台・密教・禅の三宗兼学の道場だったが、第十一世蘭渓道隆のときから、臨済宗の寺院となり、足利義満が京...

写真提供:旧嵯峨御所 大本山大覚寺
旧嵯峨御所 大本山大覚寺 ( 京都府 京都市右京区 )
JR山陰本線(嵯峨野線)嵯峨嵐山駅から徒歩15分。大沢池を東に望む北嵯峨の景勝地に立つ。真言宗大覚寺派の本山で、代々天皇もしくは皇統の方が門跡(住職)を務めた門跡寺院。般若心経写経の根本道場・いけばな嵯峨御流の総司所*でもある。 嵯峨天皇の離宮であった嵯峨院を、876(貞観18)年に天皇の皇女で淳和天皇皇后の正子内親王が、...

泉涌寺 ( 京都府 京都市東山区 )
JR東福寺駅、京阪電鉄東福寺駅から徒歩20分。月輪山(つきのわやま)の麓にあり、皇室の菩提寺として御寺(みてら)とも呼ばれ、尊崇されている。草創の時期や事情は明らかでないが、空海が、天長年間(824~834)にここに草庵を立てて法輪寺としたのが寺の起こりともいわれる。1218(建保6)年に俊芿(しゅんじょう)律師(月輪〈がちりん〉...

永観堂(禅林寺) ( 京都府 京都市左京区 )
地下鉄東西線蹴上駅下車、徒歩15分。市バス南禅寺・永観堂道下車、徒歩3分。正式には禅林寺というが永観堂の名で親しまれている。広い境内には、山を負うように諸堂が並び、方丈(釈迦堂)・勅使門(唐門)・鐘楼・御廟・中門・多宝塔・阿弥陀堂(本堂)*など多くの建物は、臥龍廊*とよばれる回廊で結ばれている。 寺は、平安時代初期の...

写真提供:パーソナル企画
光悦寺 ( 京都府 京都市北区 )
市バス鷹峯源光庵前で下車し、三差路を約150m西へ入った南側に光悦寺がある。1615(元和元)年、本阿弥光悦*は徳川家康から拝領した鷹ケ峯の地に、一族縁者や工芸職人、豪商とともに移り住み、光悦を中心とする、いわば芸術村を営んだ。光悦の死後、幕府に返還されたが、すこしでもその足跡を残すためにと寺院を建てた。それが光悦寺である...

写真提供:三千院
三千院 ( 京都府 京都市左京区 )
京都バス大原下車、徒歩10分。鯖街道(若狭街道。国道367号線)の東、大原の里の一角にある。左右に呂川(りょせん)・律川(りつせん)の清流が流れ、周囲には堂々とした石垣を巡らしている。三千院は、最澄が比叡山に根本中堂を創建した際、東塔の南谷に一宇を建てたのが起こりである。860(貞観2)年、承雲が堂塔を整備し、比叡山麓の東坂...

曼殊院 ( 京都府 京都市左京区 )
市バス一乗寺清水町から徒歩20分。延暦年間(728~806)、最澄が比叡山上に建てた小堂を草創とする。のちに比叡山の西塔北谷に移され、東尾坊と称した。947(天暦元)年、北野神社(現北野天満宮)が造営されると、当時の住持、是算国師は菅原氏の出であったので勅命により別当職に補せられ、以後歴代、明治の初めまで、これを兼務した。 ...

仁和寺 ( 京都府 京都市右京区 )
世界文化遺産。嵐電北野線御室(おむろ)仁和寺駅から徒歩3分で仁和寺二王門に着く。宇多天皇陵のある大内山陵を背景に、南に双ヶ岡を控えた景勝地を占め、深い緑に包まれる真言宗御室派の総本山である。886(仁和2)年に光孝天皇の勅願で着工、宇多天皇即位後の888(仁和4)年に完成、年号から仁和寺と号する。のちに宇多天皇が落髪後入寺し...

写真提供:賀茂別雷神社(上賀茂神社)
賀茂別雷神社(上賀茂神社) ( 京都府 京都市北区 )
世界文化遺産。地下鉄烏丸線北山駅から徒歩15分、市バスは上賀茂神社前からすぐ、または上賀茂御薗(みその)橋から徒歩5分。賀茂川に架かる御薗橋の東に鎮座し、下鴨神社とともに賀茂社と呼ばれ、京都でもっとも古い神社の一つ。御祭神は賀茂別雷大神(わけいかづちのおおかみ)。雷神を祀るところから、厄除けの信仰を集めている。山城国の...

北野天満宮 ( 京都府 京都市上京区 )
嵐電北野白梅町駅から一の鳥居まで徒歩7分、市バス北野天満宮からは徒歩2分。平安時代前期の学者であり、政治家であった菅原道真を祀る。道真は35歳で文章博士に任じられた後、右大臣にまで昇ったものの、左大臣藤原時平の讒言により、大宰権帥に左遷され、903(延喜3)年に大宰府で死去。その後、時平や皇太子の病死、天変地異の続発、さら...

写真提供:あだし野念仏寺
あだし野念仏寺 ( 京都府 京都市右京区 )
JR山陰本線(嵯峨野線)嵯峨嵐山駅から徒歩約30分。小倉山の麓のこのあたりはかつて化野*(あだしの)と呼ばれ、東の鳥辺野、北の蓮台野と並ぶ平安京の葬送の地であった。寺伝によれば、約1,200年前に弘法大師が、この地に葬られた多数の死者を弔うために五智山如来寺を創建し、のち法然上人が念仏道場に改め、念仏寺と称するようになったと...

高山寺 ( 京都府 京都市右京区 )
京都市の北西郊、愛宕山の東麓に位置する高雄(高尾)・槇尾・栂尾(とがのお)は「三尾(さんび)」と総称され、古来、紅葉の名勝として知られてきた。高山寺はその三尾の最も北、栂尾にある世界遺産の古刹である。京都駅からだとJRバスで約1時間、栂ノ尾下車、徒歩5分。 774(宝亀5)年、光仁天皇の勅願で開創。1206(建永元)年、明恵...

広隆寺 ( 京都府 京都市右京区 )
嵐電嵐山本線太秦(うずまさ)広隆寺駅の目の前に、「太秦廣隆寺」と深く彫った石碑と大きな楼門がそびえる。国宝指定第1号の弥勒菩薩半跏思惟像をはじめとする京都でも有数の多くの古仏を伝える寺。京都の人には「太秦のお太子さん」として親しまれている。 603(推古天皇11)年、秦氏*の長、秦河勝(はたのかわかつ)が聖徳太子から与...

写真提供:神護寺
神護寺 ( 京都府 京都市右京区 )
京都駅からJRバスで約1時間、高雄下車、徒歩20分。三尾*の一つ、高雄山の山腹にある真言宗の古刹である。紅葉の名所としても名高い。 東寺や高野山金剛峰寺とともに真言密教の寺院として古い歴史をもつ。781(天応9)年、和気清麻呂*が、河内国に神願寺を、同時期に当地に高雄山寺を建立。清麻呂没後、息子の弘世・真綱・仲世らが最澄・...

写真提供:賀茂御祖神社(下鴨神社)
賀茂御祖神社(下鴨神社) ( 京都府 京都市左京区 )
世界文化遺産。京阪鴨東線と叡山電鉄の出町柳駅から高野川を渡って北へ徒歩10分。上賀茂神社が祀る賀茂別雷命(かもわけいかづちのみこと)の母神である玉依媛命(たまよりひめのみこと)と祖父神の賀茂建角身命(たけつぬみのみこと)を祭神とし、社伝では神武天皇の御代に比叡山西麓の御現山(みあれやま)に降臨し、崇神天皇の代に神社の...

本法寺 ( 京都府 京都市上京区 )
地下鉄烏丸線鞍馬口下車、徒歩約15分。表千家・裏千家の家元邸に向かい合う閑静な地にある。1436(永享8)年、日親上人*が東洞院綾小路の地に創建(開創時期や場所は諸説あり)。その後、法難や火災などで移転、再建を重ね、1587(天正15)年、豊臣秀吉の命により現在地へ移転した。その際、伽藍の整備に尽力したのが、芸術家・文化人として...

法金剛院 ( 京都府 京都市右京区 )
JR山陰本線(嵯峨野線)花園駅下車、徒歩約3分。平安時代に貴族の別荘や寺院が営まれた双ヶ丘の山麓にある。830(天長7)年頃、右大臣清原夏野がこの地に山荘を築いた。清原の死後、山荘を寺に改め、双丘寺と号したのが始まり。庭園に珍花奇花を植え、嵯峨・淳和・仁明天皇の行幸を仰いだ。なかでも仁明天皇は寺の背後の内山に登られ、その景...

写真提供:宮内庁京都事務所
桂離宮 ( 京都府 京都市西京区 )
桂川西岸にあり、阪急京都線桂駅の北東徒歩20分。八条宮智仁(としひと)親王*によって始められた八条宮家の別荘で、1615(元和元)年ごろ工事に着手し、約35年の歳月を費やし、その子智忠(としただ)親王の代にさらに増築、整備された。のちに後水尾上皇の御幸に際して改装を加えたのが現在の姿である。かつては桂山荘、桂別業などと呼ば...

写真提供:宮内庁京都事務所
京都御所 ( 京都府 京都市上京区 )
京都御苑*の西北部にあり、地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩5分。東西約250m、南北約445m、面積約11万m2。周囲に5筋の白線をつけた築地塀と清流の溝を巡らし、南に建礼(けんれい)門、北に朔平(さくへい)門、東に建春門、西に宜秋(ぎしゅう)門、清所門、皇后門を置く。御所の正殿である紫宸(ししん)殿は建礼門の正面に南面す...

写真提供:元離宮二条城事務所
元離宮二条城(二条城) ( 京都府 京都市中京区 )
地下鉄東西線二条城前駅から徒歩すぐ。堀川通を正面にして東西約600m、南北約400mの周囲に堀を巡らし、総面積は27万5,000m2。世界文化遺産。 1603(慶長8)年、徳川家康が御所の守護と将軍上洛の際の宿所として築城した。当初の規模は現在の二の丸エリアに相当する小さなもので、城郭というより居所であった。徳川家康と豊臣秀...

写真提供:パーソナル企画
祇園 ( 京都府 京都市東山区 )
江戸時代以来の、京都指折りの繁華街。京都五花街*の祇園甲部と祇園東があり、舞妓や芸妓の姿を見うける華やかな町である。祇園の範囲は、東西は京阪本線祇園四条駅からすぐ東の大和大路通から八坂神社西門前を走る東大路通まで、南北は四条通をはさみ、北は白川南通・新橋通から南は団栗(どんぐり)通まで。 鎌倉初期に祇園社(感神院...

写真提供:一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会
美山かやぶきの里 ( 京都府 南丹市 )
美山(南丹市美山町)の観光拠点である「京都丹波国定公園ビジターセンター」へは京都市中心部から国道162号などで約50km、美山かやぶきの里はさらに府道38号で約6kmの距離にある。美山は京都府のほぼ中央、由良川の最上流部にあって、標高800~900m級の連山の間に開けている。山間を縫って由良川、棚野川(たなのがわ)が流れ、河川一帯は鮎...

写真提供:パーソナル企画
上賀茂の街並み ( 京都府 京都市北区 )
上賀茂神社の東、「ならの小川」が神域を出て名を変えた明神川に沿って、土塀を連ねた社家*の屋敷が立ち並び、閑雅なたたずまいを見せている。上賀茂神社に仕える神官の屋敷町として室町時代から発展してきたもので、現在一帯は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。主屋は敷地に奥まって立ち、切妻造・平家建・妻入の特色ある...

嵯峨鳥居本の街並み ( 京都府 京都市右京区 )
阪急嵐山駅から京都バスで「鳥居本」下車、徒歩約3分に愛宕神社の一の鳥居がある。このあたりは嵯峨鳥居本といい、嵯峨野の最も奥に位置する。もとは農林漁業を主体とする集落であったが、江戸時代中期以降、愛宕神社の門前町としても発展した。集落内を通る「愛宕街道」沿いには往時を偲ばせる古い街並みが残っており、「八体地蔵」が立つ三...

写真提供:和束町
和束町の茶畑 ( 京都府 和束町 )
JR関西本線(大和路線)加茂駅から奈良交通バスで約15分。和束町は京都府南部、奈良県との府県境近くに位置する。南山城地域の最高峰である鷲峰山(じゅうぶさん)が北にそびえ、町の中央を木津川の支流・和束川が流れる。その流域の丘陵地に茶畑*が広がっている。宇治茶生産800年の歴史*があり、現在も京都府最大の茶産地として宇治茶の約...

修学院離宮 ( 京都府 京都市左京区 )
市バス修学院離宮道から徒歩15分、または叡山電鉄鞍馬線修学院駅から徒歩20分。雲母(きらら)坂に近い比叡山西麓に1655(明暦元)年のころから1659(万治2)年にかけ、後水尾(ごみずのお)上皇*により造営された。約54万m2に及ぶ広大な敷地を占める離宮は上・中・下の3つのエリアからなり、その間は細い松並木道で結ばれている...

写真提供:宮内庁京都事務所
京都仙洞御所 ( 京都府 京都市上京区 )
京都御苑*の東寄り、寺町御門と清和院御門の間にある。地下鉄烏丸線丸太町駅から徒歩15分、京都市バス府立医大病院前からは徒歩10分。仙洞とは上皇の住むところをいうが、ここは1630(寛永7)年徳川幕府が後水尾上皇のために小堀遠州を奉行として二条城の行幸御殿を移して造営したもので、もとは桜町殿と称した。御殿はその後火災と再建を繰...

写真提供:植彌加藤造園/ 撮影:相模友士郎
無鄰菴 ( 京都府 京都市左京区 )
地下鉄東西線「蹴上」駅下車、北西に徒歩約7分。蹴上駅を出て、右手に琵琶湖疏水のインクライン跡を見ながら進み、南禅寺前の交差点を左に行くと無鄰菴の入口がある。明治の元勲・山縣有朋(やまがたありとも)*の別荘として、1894(明治27)年~1896(明治29)年に造営され、現在は京都市の所有になっている。木造の母屋(おもや)と茶室、...

祇園祭 ( 京都府 京都市東山区 / 京都府 京都市中京区 )
「コンコンチキチン、コンチキチン」のお囃子で知られる祇園祭は、7月1日から約1カ月にわたって行われる八坂神社の祭礼。京都の夏の風物詩であり、日本を代表する祭りの一つである。863(貞観5)年に疫病が大流行した。当時、非業の死を遂げた人が怨霊(御霊)となって疫病や災害をもたらすと考える御霊信仰が盛んで、その退散を願って神泉苑*...

写真提供:上賀茂神社
葵祭 ( 京都府 京都市左京区 / 京都府 京都市北区 )
毎年5月15日に行われる上賀茂・下鴨両神社の例祭。正式名を賀茂祭というが、祭りの際、内裏宸殿の御簾や牛車、衣冠などに二葉葵を飾ることから葵祭と呼ばれる。祭りは路頭の儀・社頭の儀からなる。路頭の儀は、平安時代の風俗そのままの優雅な装束を着けた約500人と馬36頭、牛4頭、牛車2車、風流傘10基からなり、行列が延々約1kmにも及び、さ...

写真提供:PIXTA
時代祭 ( 京都府 京都市左京区 / 京都府 京都市中京区 / 京都府 京都市上京区 )
毎年10月22日に行われる平安神宮の大祭。平安京遷都1100年を記念して、1895(明治28)年に始められた。当日の朝、平安神宮での祭典の後、2基の御鳳輦(ごほうれん・御祭神〈桓武天皇と孝明天皇〉の乗る神輿)が京都御所へ向かう(神幸列)。建礼門前行在所において行在所祭を執り行った後、12時に出発するのが祭りのハイライト・時代祭風俗行...

写真提供:鞍馬寺
竹伐り会式(鞍馬寺) ( 京都府 京都市左京区 )
6月20日に竹伐り会式の行われる鞍馬寺は、京都市街の北郊。叡山電車鞍馬線鞍馬駅を降りて徒歩5分の仁王門から会式のある本殿金堂まで徒歩約25分、または仁王門を入ってからケーブルカーと徒歩で約10分。 寺伝によると寛平年間(889~898年)に鞍馬山中興の祖、峯延(ぶえん)上人が護摩修行中に襲ってきた大蛇を毘沙門天に祈って退治した...

鞍馬の火祭 ( 京都府 京都市左京区 )
京都三大奇祭*の一つとして有名な、由岐(ゆき)神社の例祭。由岐神社は940(天慶3)年、京都御所に祀られていた由岐大明神を、都の北方にあたる鞍馬に遷したのが始まり。その御遷宮の際の様子を今に伝えるのが、鞍馬の火祭だ。10月22日、午前9時から本殿にて例祭、奉遷の儀などが執り行われた後、午後6時、「神事にまいらっしゃーれ」の合...

花脊松上げ ( 京都府 京都市左京区 )
洛北の山村に古くから伝わる勇壮な火の祭典。花脊八桝地区の上桂川畔にあるトロギバ(灯籠木場)と呼ばれる広場で行われる。京阪電鉄出町柳駅より京都バス32号系統・広河原行きで約90分の「花脊交流の森前」下車、「花背リゾート 山村都市交流の森」の前にトロギバがある。 花脊松上げ(京都市登録無形民俗文化財)は毎年8月15日に行われ...

写真提供:宮津市
宮津燈籠流し花火大会 ( 京都府 宮津市 )
京都府宮津市の宮津湾で毎年8月16日夜に行われる火の祭典。宮津湾に面する主会場の島崎公園へは、京都丹後鉄道宮津駅から北西へ徒歩約10分。宮津湾に約1万個の紅白の燈籠が流されるとともに、約3,000発の花火が打ち上げられ、夏の夜空を彩る。 宮津の燈籠流しは約400年前に始まったといわれる。お盆の13日に迎えた先祖の霊を、16日に浄土...

写真提供:PIXTA
京都五山送り火 ( 京都府 京都市 )
8月16日の夜に行われる盂蘭盆会(うらぼんえ)*の行事であり、盛夏の終りを告げる風物詩になっている。起源については諸説あり明らかではないが、盆に迎えていた精霊を再び浄土に送り帰すために始められたという。もともと家々では、遠く去った霊が振り返ったときに家がすぐわかるようにと門火を焚いていたが、やがて山の上で点火されるよう...

写真提供:車折神社
三船祭 ( 京都府 京都市右京区 )
三船祭は例年5月の第3日曜日に嵐山・渡月橋の上流「大堰川(おおいがわ)」で行われる祭りで、車折神社(くるまざきじんじゃ)の例祭の延長神事として行われている。嵐山へは市バス・京都バス、JR嵯峨野線、嵐電嵐山本線、阪急嵐山線と、さまざまな方法でアクセスできる。 898(昌泰元)年に宇多上皇(第59代・宇多天皇)が嵐山・大堰川で...

写真提供:今宮神社
やすらい祭 ( 京都府 京都市北区 )
4月第2日曜、春の精にあおられ飛散するといわれる疫神を鎮めるため、今宮神社周辺で行われる祭。今宮神社は地下鉄烏丸線北大路駅の西約1.6kmにあり、徒歩20分、または同駅より京都市バスで船岡山下車、徒歩7分で到達する。 平安時代後期、桜の花が散り始める旧暦の3月頃に疫病が流行し、疫病退散(無病息災)を祈願したのが始まりといわれ...

写真提供:引接寺
引接寺 千本ゑんま堂大念佛狂言 ( 京都府 京都市上京区 )
市バス千本鞍馬口または乾隆校前から徒歩2分のところにある引接寺(いんじょうじ)は、閻魔法王を祀ることから「千本ゑんま堂」と親しまれる。引接寺は、平安初期、神通力をもった小野篁(おののたかむら)*が、葬送地・蓮台野(れんだいの)の入口に自ら閻魔王の姿を刻み安置したのが始まり。その後、1017(寛仁元)年、藤原道長の後援を得...

写真提供:吉田神社
吉田神社の節分行事 ( 京都府 京都市左京区 )
神楽岡とも呼ばれる標高105mの吉田山。その西麓にある吉田神社へは、京阪本線出町柳駅から南東へ徒歩20分、市バスを利用するなら京大正門前が最寄りである。バス停から東一条通を京都大学の時計台などを見ながら徒歩5分で吉田神社一の鳥居に着く。吉田神社は、859(貞観元)年に後に中納言となる藤原山蔭が、奈良春日の神を勧請(かんじょう...

八瀬赦免地踊 ( 京都府 京都市左京区 )
八瀬は、京都の市街地からみて北東部に位置する山間の里。比叡山の麓にあり、日本海から京の都へ魚などが運ばれた「鯖街道」が通る、自然豊かなエリアである。京都駅から京都バスで約1時間、「ふるさと前」で下車し徒歩5分のところに八瀬天満宮社がある。八瀬天満宮社の摂社・秋元神社では、毎年10月第2日曜日に「八瀬赦免地踊」が奉納される...

写真提供:一般社団法人 亀岡市観光協会
亀岡祭 ( 京都府 亀岡市 )
亀岡市にある鍬山(くわやま)神社の鍬山宮・八幡宮の例祭。11基の山鉾が旧丹波亀山城の城下町である市街地を巡行し、「丹波の祇園祭」ともいわれる。亀岡市は京都駅からJR山陰本線(嵯峨野線)で約30分の亀岡駅下車。旧城下町は駅の南1kmほどに広がっており、鍬山神社は駅の南2.5kmにある。 亀岡最大の秋祭りであり、10月1日の吉符入(き...

写真提供:松尾大社
松尾祭 ( 京都府 京都市西京区 )
四条通の西端、阪急嵐山線松尾大社駅のすぐ西にある松尾大社の祭礼。山から神を迎え、もてなしてその霊威を高め、人々を災厄から守ってくれるよう祈りが込められている。「松尾の国祭」とよばれ、貞観年間(859~877年)に始まるともいわれ、神幸祭(おいで)と還幸祭(おかえり)からなる。神輿渡御の祭礼は、古くは3月中卯日(なかのうのひ...

写真提供:京都市動物園
京都市動物園 ( 京都府 京都市左京区 )
京都市左京区の岡崎公園*内にあり、地下鉄東西線蹴上駅から北西へ徒歩約7分。41,383m2の敷地内に「アフリカの草原」「ゴリラのおうち」「京都の森」などのエリアがあり、ニシゴリラやアジアゾウ、キリン、絶滅危惧種のツシマヤマネコなど約110種500点の動物を飼育、展示している。 開園は1903(明治36)年4月。東京の上野動物...

写真提供:パーソナル企画
京都府立植物園 ( 京都府 京都市左京区 )
京都市街北部、賀茂川の東畔に位置し、地下鉄烏丸線北山駅前からすぐの北山通に北山門がある。日本の代表的な植物園で、総面積約24万m2に及ぶ園内に、約1万2,000種の植物が植えられている。 1924(大正13)年に国内初の公立総合植物園「大典記念京都植物園」として開園。戦後連合軍に接収され荒廃したが、1961(昭和36)年に府...

写真提供:京都国立博物館
京都国立博物館 ( 京都府 京都市東山区 )
貴重な文化財の殿堂として約130年の歴史を誇る京都国立博物館。京都駅から市バス博物館三十三間堂前下車すぐ、または京阪電車七条駅下車徒歩7分のところにある。京都駅からは徒歩20分ほどなので、バスに乗らず、散策がてら七条通を歩いていくのもいい。 始まりは、1889(明治22)年。都であった京都と奈良には社寺に伝えられた宝物が集中...

写真提供:パーソナル企画
京都国立近代美術館 ( 京都府 京都市左京区 )
地下鉄東西線東山駅から徒歩約10分、市バス岡崎公園 美術館・平安神宮前すぐ。岡崎公園*内にあり、平安神宮の大鳥居を挟んで京都市京セラ美術館と向かい合う。敷地面積5,000m2、延床面積9,983m2。1963(昭和38)年、東京国立近代美術館の京都分館として京都市勧業館別館を改装し開館、1967(昭和42)年に京都国立近代...

写真提供:泉屋博古館
泉屋博古館 ( 京都府 京都市左京区 )
地下鉄東西線蹴上駅より徒歩約20分、紅葉の美しさで知られる禅林寺(永観堂)の北、閑静な鹿ケ谷通にある。1960(昭和35)年、住友家旧蔵の美術品を保存、公開するため財団法人を設立。1970(昭和45)年には1号館(青銅器館)が建設され、中国古代青銅器の一般公開を開始。1980(昭和55)年に登録博物館として認可され、翌年から本格的な公開...

写真提供:東映太秦映画村
東映太秦映画村 ( 京都府 京都市右京区 )
嵐電嵐山本線太秦広隆寺駅から正面入口まで徒歩約5分、広隆寺の北隣にある。JR太秦駅から撮影所口までも徒歩約5分。東映京都撮影所*の一角を1975(昭和50)年に公開した、映画をテーマとした観光施設と映画のオープンセットを兼ね備えた施設である。2011(平成23)年に大々的にリニューアルして拡大、2年後にも新施設を追加し広げ、現在は敷...

写真提供:松竹
南座 ( 京都府 京都市東山区 )
鴨川に架かる四条大橋の東詰に立つ、現存する日本最古の歴史を持つ劇場。京阪本線祇園四条駅下車すぐ、阪急京都河原町駅下車徒歩3分と、交通至便な地にある。江戸時代初期、出雲の阿国(いずものおくに)*が「かぶき踊り」を披露するなど、四条河原では踊りや芝居が盛んに行われており、付近に常設の芝居小屋を設けたのが始まりである。7軒...

写真提供:公益社団法人京都観世会
京都観世会館 ( 京都府 京都市左京区 )
京都観世会館*は、地下鉄東西線東山駅から徒歩約5分、美術館などの文化・芸術施設が集中する岡崎エリアにある能楽堂。京都における観世流シテ方の本拠地として広く知られ、京都観世会月例会を中心に年間を通じて様々な能楽公演を行っている。現在の会館は1958(昭和33)年に建てられたもので、2023(令和5)年に65周年を迎えた歴史ある能楽...
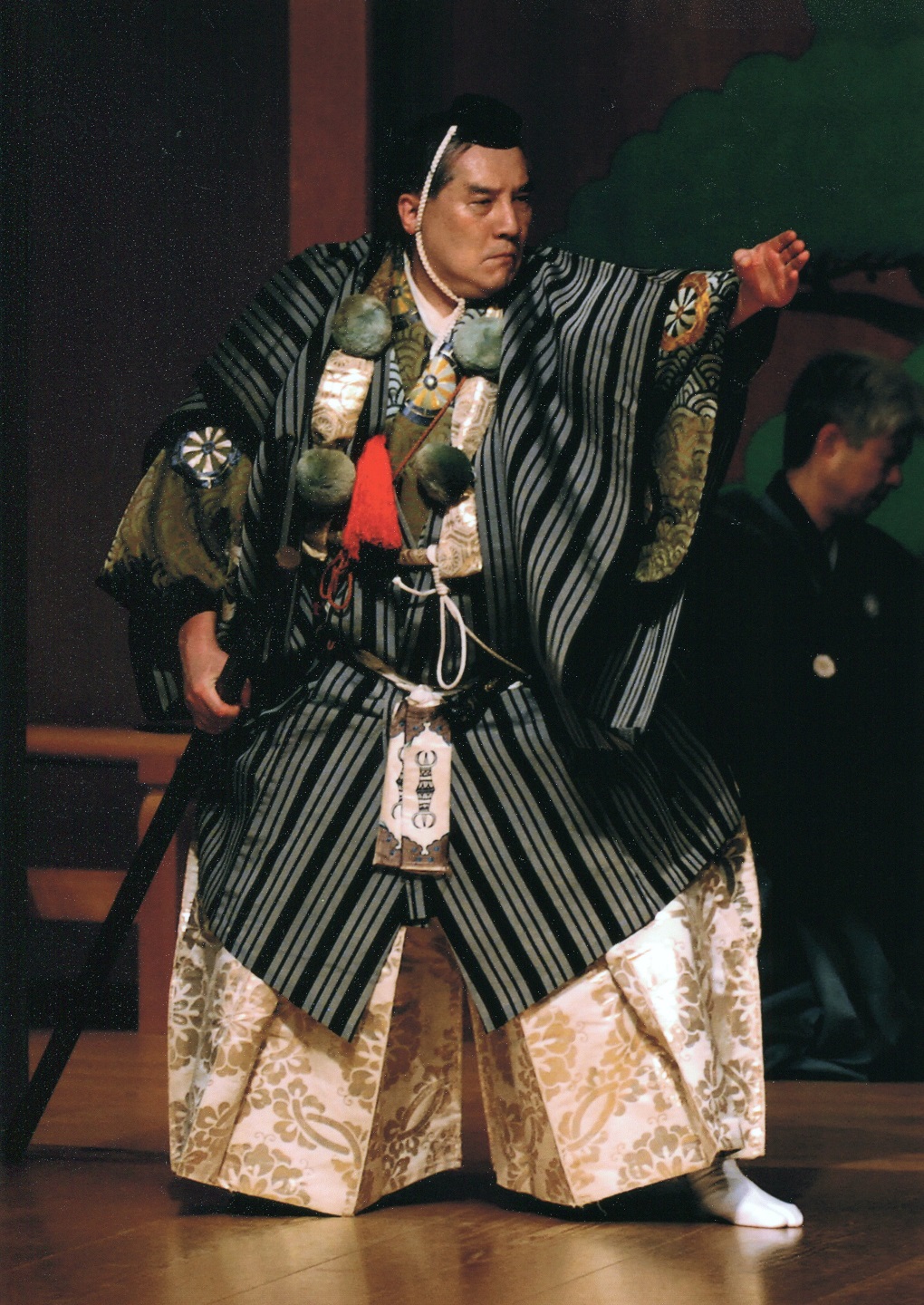
写真提供:金剛能楽堂
金剛能楽堂 ( 京都府 京都市上京区 )
地下鉄烏丸線今出川駅下車、 烏丸通を南へ徒歩5分のところにある。かつては四条室町にあったが、2003(平成15)年この地に移転した。その際、約130年にわたり使用されてきた能舞台をそのまま移築。最新の設備を備えた能楽堂の中に、19世紀に造られた能舞台が収まるという、新旧が入り交じる独特の空間となっている。座席数は、定席1階378席、...

写真提供:パーソナル企画
哲学の道 ( 京都府 京都市左京区 )
左京区の東山山麓を流れる琵琶湖疏水分線に沿う散歩道。若王子神社前の疏水にかかる若王子橋を南の起点とし、北の浄土寺橋まで約2kmにわたって続いている。若王子橋は地下鉄東西線蹴上駅から徒歩20分。浄土寺橋は京都市バス銀閣寺道バス停からすぐ。 琵琶湖疏水分線は本線(第1疏水)と同時に1890(明治23)年に竣工した。付近を流れる白...

写真提供:京丹後市観光公社
琴引浜 ( 京都府 京丹後市 )
京都丹後鉄道宮豊線網野駅から丹後海陸交通バスで約20分、琴引浜下車、徒歩10分。松林を背にして全長1.8kmにわたる白い砂浜が広がる。砂の上を歩くと「キュッキュッ」と音がする鳴砂(なきすな)の浜として知られる。この音を琴の音色になぞらえて「琴引浜」の名が付けられており、国の天然記念物・名勝*に指定されている。琴引浜の中央より...

松尾大社 ( 京都府 京都市西京区 )
阪急嵐山線松尾大社駅を出るとすぐ目の前に松尾大社の大鳥居がある。標高223mの松尾山の山裾にある古社で、約40万m2の広大な境内に、赤鳥居・楼門・拝殿・本殿*等が整然と並ぶ。祭神は、山と水を司る大山咋神(おおやまぐいのかみ)*と、水の神の市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)*。山水に生活を左右された古代の人々が水...

相国寺 ( 京都府 京都市上京区 )
地下鉄今出川駅から徒歩約10分、同志社大学の北側に広大な寺域を構える、臨済宗相国寺派の大本山。正式名称は萬年山相國承天禅寺。室町に花の御所を造営した足利義満が、その隣接地に約10年の歳月を費やして1392(明徳3)年に完成した。 「相国」とは唐名で大臣を意味し、当時、左大臣だった義満にちなんだもの。義満は禅の師春屋妙葩(しゅ...

宇治上神社 ( 京都府 宇治市 )
京阪宇治駅から宇治川沿いに歩いて約10分。菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)*、応神天皇、仁徳天皇を祀る古社で、世界文化遺産に登録されている。もとは隣接する宇治神社と一体の神社であった。大吉山の山裾に位置する静かな境内は、菟道稚郎子と仁徳天皇の伝説を語るにふさわしいところである。平安時代後期に建立された本殿は現存日本最...

くろ谷 金戒光明寺 ( 京都府 京都市左京区 )
市バス岡崎道から徒歩10分、または東天王町から徒歩15分、黒谷町の小高い岡の上にあり、「くろ谷さん」と親しまれる浄土宗の大本山。山内には、山門*・阿弥陀堂・御影堂(大殿)*・大方丈・三重塔(文殊塔)*などのほか、18カ寺の塔頭寺院が立ち並ぶ。1175(承安5)年、法然上人が比叡山の黒谷を下り、この地に草庵を結び、浄土宗最初の念...

善峯寺 ( 京都府 京都市西京区 )
西国三十三所観音霊場の第20番札所。徳川5代将軍綱吉の生母・桂昌院*ゆかりの寺としても知られる。京都西山の釈迦岳の中腹にあり、JR京都線向日町駅から車で約20分。縁起によれば、1029(長元2)年、恵心僧都源信の高弟・源算が創建。1034(長元7)年には後一条天皇より鎮護国家の勅願所と定められ、「良峯寺」の寺号を賜った。1042(長久3...

霊鑑寺 ( 京都府 京都市左京区 )
市バス「真如堂前」「錦林車庫前」下車、徒歩約7分。「哲学の道」のほぼ中央を東に入ったところにある。1654(承応3)年、御水尾天皇の皇女・多利宮を開基として創建。1890(明治23)年まで皇女が代々住持を務めた格式の高い尼門跡寺院である。「谷の御所」、「鹿ヶ谷比丘尼御所」とも呼ばれた。もとは、後陽成天皇の典侍・持明院基子の屋敷...

写真提供:PIXTA
愛宕神社 ( 京都府 京都市右京区 )
京都市の北西、山城と丹波の国境にある愛宕山(標高924m)の山頂に鎮座。二の鳥居が立つ山麓の清滝から約4kmの表参道を登ってたどり着く。全国に約900社ある愛宕神社の総本宮で、京都の人には「あたごさん」と親しまれる。祭神の伊邪那美命の子・迦倶槌命(カグツチノミコト)は火の神であることから、古来、火伏せ・防火の神*として信仰さ...

写真提供:城南宮
城南宮 ( 京都府 京都市伏見区 )
近鉄・地下鉄竹田駅から徒歩15分、竹田駅から市バスで行けば城南宮東口下車すぐ。名神高速京都南ICの南のこんもりとした城南の森にある。社伝によれば平安遷都に際し、都と国土の守護を願い、都の南に創建されたと伝わる。国常立尊(くにのとこたちのみこと)を八千矛神(やちほこのかみ)と息長帯日売尊(おきながたらしひめのみこと)に合...

豊国神社 ( 京都府 京都市東山区 )
市バス博物館三十三間堂前から徒歩5分。豊臣秀吉を祀る神社である。秀吉は1598(慶長3)年に亡くなり、東山・阿弥陀ヶ峯の頂に葬られた。その翌年、山の中腹に豊国神社が創建された。社殿は壮麗を極めたが、1615(慶長20)年の大坂夏の陣で豊臣氏が滅ぶと、徳川家康の命で廃絶。明治時代になって天皇の命で再興が決まり、1880(明治13)年、...

光明寺 ( 京都府 長岡京市 )
JR長岡京駅よりバス約15分、阪急長岡天神駅よりバス約10分。西山浄土宗の総本山の寺院である。法然上人が初めて念仏の教えを説いた地であることから「浄土門根元地」といわれ、境内に上人の廟所がある。近年は紅葉の名所としても広く知られる。 法然の弟子で「平家物語」で有名な熊谷直実(蓮生)*が1198(建久9)年、法然ゆかりの当地に...

等持院 ( 京都府 京都市北区 )
京福電鉄北野線等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅から北へ400m、立命館大学衣笠キャンパスの南にある。足利氏の菩提寺として十刹*の第一に挙げられた名刹である。お椀を伏せたような衣笠山を正面に見る境内の奥に土塀をめぐらし、方丈*・庫裏・書院・霊光殿*が禅寺らしいたたずまいをみせている。庭園・茶室*も、本院の魅力を引き上...

真正極楽寺(真如堂) ( 京都府 京都市左京区 )
市バス錦林車庫前または真如堂前から徒歩8分。かつての本堂の呼び名であった「真如堂」の通称で知られるが、正しくは鈴声山(れいしょうざん)真正極楽寺という。 寺伝によれば、984(永観2)年、比叡山の戒算上人が、延暦寺常行堂に安置されていた慈覚大師円仁作の阿弥陀如来像を移したのが始まり。のちに一条天皇が本堂を建て、勅願寺と...

写真提供:聖護院
聖護院 ( 京都府 京都市左京区 )
地下鉄東西線東山駅から徒歩15分、京阪鴨東線神宮丸太町駅から徒歩10分。市バス熊野神社前からは徒歩5分。平安神宮の北方にある本山修験宗の総本山。応仁・文明の乱などの火災でたびたび移転し、1676(延宝4)年に現在地に再建された。本尊は不動明王。平安時代後期、1090(寛治4)年白河上皇が熊野三山に参詣の折、増誉(ぞうよ)大僧正が先...

御香宮神社 ( 京都府 京都市伏見区 )
京阪本線伏見桃山駅から徒歩3分、または近鉄京都線桃山御陵前駅から徒歩2分。神功皇后を主祭神とし、仲哀天皇、応神天皇ほか6柱の神をまつる。神社の創建は古く、「延喜式」の式内社の御諸(みもろ)神社に当てる説もある。名前の由来*は平安時代の862(貞観4)年に境内からよい香りの清泉が湧き出し、これを飲んだ病人の病が癒えたことから...

藤森神社 ( 京都府 京都市伏見区 )
京阪本線墨染駅から神社正面である南門まで徒歩7分、JR奈良線藤森駅からは徒歩5分。深草から東福寺付近にかけての産土神で、素盞嗚尊、神功皇后、舎人親王など、12柱を祀る。社伝によると神功皇后が新羅出兵の凱旋後、この地に旗と兵具を埋め神祀りをしたのが起こりとされている。その後、伏見稲荷大社の社地*にあったと伝え、稲荷社の創立...

写真提供:パーソナル企画
隨心院 ( 京都府 京都市山科区 )
地下鉄東西線小野駅から徒歩5分。醍醐寺の北にあり、奈良街道の東側に面している。このあたりは小野と呼ばれ、昔は小野氏の領地であったことから、隨心院は小野小町*の住居跡に立つともいわれている。 雨乞のたびに雨を降らしたので”雨僧正”とも呼ばれた真言宗小野流の祖・仁海(にんがい)が、991(正暦2)年に開いた牛皮山曼荼羅寺に始...

写真提供:廬山寺
廬山寺 ( 京都府 京都市上京区 )
京都御苑のすぐ東にあり、寺町通に門を開く。「源氏物語」の作者・紫式部の邸宅跡に立ち、正式には廬山天台講寺という。1583(天慶元)年、元三大師良源*が船岡山の南に創建。天正年間(1573~1593)、豊臣秀吉の都市改造により現在地の寺町通に移った。皇室とのゆかりが深く、現在の本堂と尊牌殿は、1794(寛政6)年に光格天皇の勅命で仙洞...

写真提供:平野神社
平野神社 ( 京都府 京都市北区 )
市バス「衣笠校前」から北へ徒歩2分。西大路通の東側に朱塗りの大鳥居が立つ。794(延暦13)年、桓武天皇が平安遷都に際して、平城京の「田村後宮」に祀られていた今木皇大神、久度大神、古開大神、比賣大神の4神を当地に遷して創建された。朝廷の崇敬が篤く、のちに源氏・平氏の氏神として武門の信仰も集めた。 現在の社殿は寛永年間(16...

写真提供:今宮神社
今宮神社 ( 京都府 京都市北区 )
平安建都以前より、疫神を祀る社があったといわれる今宮神社は、地下鉄烏丸線北大路駅の西約1.6kmにあり、徒歩20分、または同駅より京都市バスで船岡山下車、徒歩7分で到達する。本社の祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)・事代主命(ことしろぬしのみこと)・奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)、境内にある摂社・疫神社の祭神は素盞嗚...

常寂光寺 ( 京都府 京都市右京区 )
JR嵯峨嵐山駅から徒歩20分、「百人一首」で知られる小倉山の中腹にある日蓮宗の寺。1596(文禄5)年、日蓮宗大本山本圀寺16世の日禛(にっしん)上人が開いた。その前年、豊臣秀吉が建立した方広寺大仏殿の千僧供養への出仕をめぐって、京都の本山が二派に分裂したとき、上人は不受不施派*の伝統を守って出仕しなかった。そして本圀寺を出て...

写真提供:祇王寺
祇王寺 ( 京都府 京都市右京区 )
JR嵯峨嵐山駅または嵐電嵐山駅からともに徒歩25分、市バスだと嵯峨小学校から徒歩15分。二尊院から化野念仏寺へ向かう道の途中を左折し、樹木がトンネルをつくる小径の奥にある。 「平家物語」によれば、平清盛の寵愛を受けた白拍子祇王*は、あとから現れた白拍子の仏御前*に寵愛を奪われた。清盛に追い出された祇王は母・妹とともに都...

写真提供:長岡京市商工観光課
長岡天満宮 ( 京都府 長岡京市 )
阪急長岡天神駅から徒歩10分。菅原道真公が大宰府に左遷される際に名残を惜しんだ地といわれ、のち祠を建て公御自作の木像を祀ったのに始まる。戦乱などで衰退したが、1498(明応7)年に再興されたといい、1780 (安永9)年に刊行された「都名所図会」には、天満宮が描かれている。もとは開田天満宮と称し、現社名は江戸時代になってから。...

写真提供:パーソナル企画
三室戸寺 ( 京都府 宇治市 )
京阪宇治線三室戸駅から東1kmの明星山の山裾にある。杉木立の茂る参道を上ると、本堂、阿弥陀堂などが立ち、本堂東方に三重塔が望まれる。770(宝亀元)年に金銅二臂(ひ)千手観音菩薩*を本尊に開創されたと伝え、皇室の帰依も篤かった。西国三十三所第10番札所で、霊宝殿には平安時代の古仏も残る。本堂左上には室町時代の社殿をもつ十八...

興聖寺 ( 京都府 宇治市 )
京阪宇治駅から宇治川沿いに歩いて約20分、JR宇治駅からの場合は徒歩30分で着く。興聖寺は、曹洞宗の祖・道元が1233(天福元)年、日本初の曹洞宗の修行道場として伏見深草に建立したのを起源とする。道元は1243(寛元元)年に越前に移り、のちに寺は途絶。これを惜しんだ江戸時代初期の淀城主・永井尚政が1648(慶安元)年、萬安英種禅師を...

出雲大神宮 ( 京都府 亀岡市 )
JR嵯峨野線(山陰本線)亀岡駅から北へ約6km、桜並木の七谷(ななたに)川を渡り、千歳(ちとせ)山を背にして鎮座する。祭神は大国主命と三穂津姫命*の二座。社伝では大国主命がこの地から杵築(出雲)大社*に遷したとされ、709(和銅2)年に初めて社殿を造営したと伝えている。このため「元出雲」ともいわれる。「延喜式」においても名神...

成相寺 ( 京都府 宮津市 )
日本三景の一つ天橋立を見下ろす標高569mの成相山(鼓ヶ岳)の中腹にある。山麓の府中駅から天橋立ケーブルまたはリフトで傘松公園まで登り、成相寺登山バスに乗り継いで7分で着く。西国三十三所観音霊場の第28番札所であり、三十三所中、最北端に位置している。 704(慶雲元)年、文武天皇の勅願により真応上人が開いたと伝わる。「今昔...

写真提供:笠置寺
笠置寺 ( 京都府 笠置町 )
JR関西本線笠置駅から徒歩15分。笠置山の山頂近くに立つ真言宗智山派の寺。高さ15mの大きな岩に刻まれた、日本最古最大と言われる「弥勒磨崖仏」を本尊とする。大友皇子または天武天皇の開基と伝えるが、本尊弥勒磨崖仏などから推測すると、奈良時代、東大寺の良弁(ろうべん)*や実忠(じっちゅう)*が参籠したときに、山岳信仰の修行場と...

写真提供:白沙村荘 橋本関雪記念館
白沙村荘 橋本関雪記念館 ( 京都府 京都市左京区 )
市バス銀閣寺前からすぐ、または市バス銀閣寺道から東へ徒歩3分、銀閣寺の西方に位置する。大正~昭和初期の京都画壇で活躍した日本画家、橋本関雪(かんせつ)*の邸宅であり、国の名勝に指定されている。敷地内には関雪の作品を展示する美術館も併設されている。 建物、庭園とも基本設計は関雪が手がけた。1916(大正5)年に居宅が完成...

法観寺(八坂の塔) ( 京都府 京都市東山区 )
東山安井または清水道バス停から徒歩5分、二年坂近くの立て込んだ民家の間にあり、八坂の塔で知られる。臨済宗建仁寺派。飛鳥時代の創建と伝えられ、古瓦、塼仏(せんぶつ)*などが出土する京都市内でもっとも古い寺院の一つ。四天王寺式の伽藍だったといわれ、法隆寺式との説もある。聖徳太子が如意輪観音の夢告により創建したというが、一...

写真提供:伊根町観光協会
伊根の舟屋群 ( 京都府 伊根町 )
日本海に臨む丹後半島の北東部に位置する伊根町。その町の南端、伊根浦地区では伊根湾に沿って、当地ならではの伝統建築「舟屋」がびっしりと立ち並び、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。山陰近畿自動車道の与謝天橋立ICから国道176・178号線で23km、約30分で到達する。 伊根浦は古くからの漁業集落。江戸時代末期~昭和...

写真提供:パーソナル企画
伏見の街並み ( 京都府 京都市伏見区 )
京阪本線中書島駅と伏見桃山駅の間にある伏見はかつて伏水と書き、平安時代には貴族の山荘が営まれた。豊臣秀吉が太閤堤をはじめとする土地改造、水路整備の上、壮大な伏見城*を造営すると、城下町として発展。廃城後も酒造りと淀川の水運に恵まれて、江戸時代には三十石船*が往来する宿場と商業の町として栄えた。今でも掘割沿いには切妻...

写真提供:上賀茂神社
賀茂競馬 ( 京都府 京都市北区 )
賀茂別雷(かもわけいかづち)神社、通称「上賀茂神社」境内で5月5日に行われる神事。地下鉄烏丸線北山駅から徒歩約15分、市バス上賀茂神社前からすぐ。 葵祭の前儀のひとつで、1093(寛治7)年以来の伝統をもつ。もとは宮中で催された競馬会に由来する。左方(さかた)、右方(うかた)*の2組に分かれて馬の競馳(きょうち)を行い、天...

田原の御田 ( 京都府 南丹市 )
「田原の御田」は毎年5月3日に、南丹市日吉町田原の多治(たじ)神社で営まれる民俗芸能。籾の準備から刈り取りまで1年間の稲作の過程を模擬的に演じ、その年の豊作を祈願する。同様の「お田植え」神事は全国各地でみられるが、一連の稲作作業を一貫して表現するのは非常に珍しく、国の重要無形民俗文化財に指定されている。多治神社へはJR山...

清凉寺 ( 京都府 京都市右京区 )
JR山陰本線(嵯峨野線)嵯峨嵐山駅、嵐電嵐山駅のどちらからも徒歩15分。嵯峨釈迦堂の別名で親しまれている清凉寺は嵯峨野でも有数の古刹である。豪壮な仁王門をくぐると、広い境内に本堂*・阿弥陀堂などの大堂が並び立つ。この地にはもともと『源氏物語』の光源氏のモデルともいわれる源融(みなもとのとおる)*の山荘・栖霞観(せいかか...

写真提供:パーソナル企画
桂川(嵐山周辺) ( 京都府 京都市右京区 / 京都府 京都市西京区 )
京都市左京区北西端の広河原と南丹市美山町境の佐々里峠を源とし、全長114kmの京都府を代表する河川の一つ。亀岡盆地を流れ、保津峡に入ると保津川(ほづがわ)、嵐山にかかると大堰川(おおいがわ)*と呼ばれ、渡月橋を過ぎると再び桂川と名前を戻し、その後鴨川を合わせ、さらに宇治川、木津川と合流して淀川となり、大阪湾へ向かう。保津...

写真提供:パーソナル企画
産寧坂の街並み ( 京都府 京都市東山区 )
市バス「清水道」から東へ清水坂を10分ほど上って行くと、有名な「七味家本舗」が立つ。産寧坂(三年坂)とは本来、この店の横から北へ下る50mほどの石段をいう。ただし一般的には、坂の下から北へ延びる石畳の道も含めて産寧坂といわれる。また産寧坂の北に続く二年坂、高台寺前を通る「ねねの道」*、石塀小路*あたりも含め、一帯は「京都...

嵯峨野トロッコ列車 ( 京都府 京都市右京区 / 京都府 亀岡市 )
嵯峨野トロッコ列車は、保津川の渓谷美を楽しめる観光列車。JR嵯峨野線(山陰本線)の嵯峨嵐山駅に隣接するトロッコ嵯峨駅からトロッコ亀岡駅までの7.3kmを約25分で走る。トロッコ亀岡駅から保津川下りの乗船場へ連絡バスが運行している(所要15分)。 1989(平成元)年3月、JR山陰本線の複線電化に伴い、嵯峨(現・嵯峨嵐山駅)~馬堀駅...

写真提供:アサヒグループ大山崎山荘美術館
アサヒグループ大山崎山荘美術館 ( 京都府 大山崎町 )
桂川、宇治川、木津川の三川合流域の北西、天王山の南麓にあり、JR京都線「山崎駅」、阪急京都線「大山崎駅」より徒歩約10分のところに位置する。 アサヒグループ大山崎山荘美術館は関西の実業家・加賀正太郎*が大正から昭和初期にかけ建設した別荘「大山崎山荘」を活かした美術館。加賀自らが設計した英国式の優美な本館に、世界的建築...

写真提供:右源太
貴船の川床 ( 京都府 京都市左京区 )
水の神を祀る貴船(きふね)*神社のそばを流れる貴船川沿いに約20軒の店が並び、5月から9月末までの間「川床」で食事を楽しむ事ができる。貴船は京都市街の最北にあたり、叡山電鉄貴船口駅から京都バスに乗り換え「貴船」下車、又は予約した店の無料送迎バスを利用する。 川床は清流の上や川岸に床を設けて食事をするもので、京都の鴨川...

宝泉院 ( 京都府 京都市左京区 )
洛北・大原の里。三千院の門前を北に進むと勝林院(大原寺)に突き当たる。宝泉院はその西隣にあり、京都バス「大原」から徒歩約15分で到着する。勝林院は天台声明の根本道場として1013(長和2)年に創建されたお寺で、宝泉院はその塔頭として平安末期に開かれたと伝わる。 宝泉院には盤桓園(ばんかんえん)、鶴亀庭園、宝楽園、鹿野園...

写真提供:淀川河川公園
背割堤のサクラ ( 京都府 八幡市 )
石清水八幡宮が鎮座する男山の北、木津川・宇治川・桂川の3つの川が合流*する地域にあり、京阪本線「石清水八幡宮駅」から徒歩10分。木津川と宇治川を分かつ堤防を「背割堤」と呼び、約220本のソメイヨシノがつくる並木が1.4kmにわたって続いている。一帯は「淀川河川公園背割堤地区」として整備されている。 背割堤にはかつて見事な松並...

写真提供:パーソナル企画
京都の湯豆腐 ( 京都府 京都市 )
京の名物料理として知られる湯豆腐。良質の地下水に恵まれた京都では、昔から評判のよい豆腐が作られてきた。その豆腐本来のおいしさを味わえるのが湯豆腐である。 豆腐の製法は平安時代に中国から遣唐使が持ち帰ったとも、鎌倉時代に禅宗とともに伝来したともいわれる。肉食を禁じる寺院の精進料理*として広まった食べ物であるが、庶民...

写真提供:青野株式会社 白龍園
白龍園 ( 京都府 京都市左京区 )
叡山電鉄鞍馬線二ノ瀬駅から南東へ徒歩7分、古くからの霊域とされる安養寺山の麓に広がる日本庭園。特に苔の美しいことで知られる。1962(昭和37)年、京都の老舗アパレル会社「青野株式会社」の創業者・故青野正一氏が、縁あって当時荒れていたこの山を手に入れた。当地の歴史と信仰を知った青野氏は復興を決意し、1963(昭和38)年、不老長...

写真提供:京都市文化財保護課
京菓子 ( 京都府 京都市 )
京菓子は御所で用いられる献上菓子、社寺の饗饌菓子、そして茶道の菓子として発達してきた。奈良時代に伝わった唐菓子(からくだもの)の団喜・餢飳(ぶと)*などは神仏への供え物としてつくられた。鎌倉時代に禅宗が流入。同時期に伝わったお茶うけ的な点心の「羹(あつもの)」には獣や魚の肉を使うものが多かったが、次第に植物性の素材...

写真提供:常照皇寺/撮影:村山仁志
常照皇寺 ( 京都府 京都市右京区 )
京都市北郊、周山地区の山里にある臨済宗天龍寺派の禅寺。京都駅からJRバス高雄京北線で約1時間30分の周山下車、京北ふるさとバス山国・黒田線に乗換え16分の山国御陵前下車、徒歩7分で到達する。 南北朝時代に北朝初代の天皇となった光厳天皇*が1362(貞治元)年に開き、歴代天皇の帰依を受けた皇室ゆかりの寺である。光厳天皇は上皇に...

愛宕念仏寺 ( 京都府 京都市右京区 )
阪急嵐山駅から京都バス清滝行きで「愛宕寺前(おたぎてらまえ)」下車。バス停の前に愛宕念仏寺の仁王門が立つ。嵐山方面から徒歩の場合は、嵯峨鳥居本に立つ愛宕神社の「一の鳥居」を過ぎ、愛宕街道*をさらに清滝方面へ300m進んだ先にある。 奈良時代、称徳天皇により現在の東山区松原通に愛宕寺として創建された。当時その地は山城国...

写真提供:京都鴨川納涼床協同組合
鴨川の納涼床 ( 京都府 京都市中京区 )
阪急京都線河原町駅、地下鉄東西線三条京阪駅、京阪本線清水五条駅・祇園四条駅・三条京阪駅下車。五条大橋から二条大橋の間の鴨川西岸の料亭・旅館・レストラン・カフェ・バーなどが、5月1日~10月15日(一部の店舗は9月30日)の間、鴨川の西側に沿って一段高く流れる禊(みそぎ)川*の上に設ける納涼施設。夕涼みしながら、屋外の床で鴨川...

写真提供:二尊院
二尊院 ( 京都府 京都市右京区 )
JR嵯峨嵐山駅から徒歩20分、「百人一首」に詠われた小倉山*の東麓にある。衆生を現世から来世へ送り出す「発遣(ほっけん)の釈迦」と、浄土へ迎え入れる「来迎の阿弥陀」の二尊*を本尊に祀ることから、二尊院と呼ばれる。正式名称は小倉山二尊教院華臺寺。承和年間(834~847)、嵯峨天皇の勅願で慈覚大師円仁が建立した。のちに荒廃した...

写真提供:安楽寺
安楽寺 ( 京都府 京都市左京区 )
京都駅から市バス岩倉操車場行きに乗り、真如堂前下車、徒歩15分。「哲学の道」の1筋山側、閑静な鹿ヶ谷の地にある。茅葺きの山門から本堂へと続く庭は苔とサツキの刈込みが美しい。法然上人の高弟であった住蓮上人と安楽上人が、鹿ヶ谷草庵を結び、浄土礼讃を称えたのが同寺の始まり。両上人の念仏の教えに感銘を受けた後鳥羽上皇の女官、松...

写真提供:実相院
実相院 ( 京都府 京都市左京区 )
叡山電鉄鞍馬線岩倉駅から徒歩20分。岩倉門跡とも呼ばれる門跡寺院で、もとは天台宗寺門派であったが、現在は単立寺院である。1229(寛喜元)年、関白近衛基通の孫・静基僧正が紫野に創建。のちに現・上京区実相院町に移り、応仁の乱の戦火を避けて現在地に再移転した。寛永年間(1624~1644)、足利義昭の孫・義尊が皇室や徳川家の援助を受け...

梅宮大社 ( 京都府 京都市右京区 )
阪急嵐山線松尾大社駅から東へ徒歩10分、桂川に近い梅津*にある。楼門・拝殿・本殿が一直線に並び、本殿は檜皮葺の美しい屋根をもつ三間社流造の建物。「延喜式」に載る名神大社*としての風格が漂う。約1,300年前、橘諸兄の母・県犬養三千代が橘氏の氏神として、橘諸兄の別荘があった京都府綴喜郡井手町に祀ったのが始まり。後に、嵯峨天皇...

写真提供:鹿王院
鹿王院 ( 京都府 京都市右京区 )
京福電鉄嵐山本線鹿王院駅から徒歩3分にある。1380(康暦2)年、足利義満は自らの長寿を願い、師である春屋妙葩*(しゅんおくみょうは。普明国師)を開山として、宝幢寺(ほうどうじ)を創建。その境内に開山塔を建て、鹿王院と称した。宝憧寺は京都十刹の第五位の名刹だったが応仁の乱で廃絶し、鹿王院だけが残った。のちの地震で大きな被...

写真提供:パーソナル企画
地蔵院 ( 京都府 京都市西京区 )
阪急嵐山線上桂駅から徒歩15分のところにある臨済宗の寺。竹林に包まれていることから「竹寺」とも呼ばれる。また、延命安産の地蔵菩薩を本尊とすることから「谷の地蔵」とも呼ぶ。衣笠内大臣といわれた歌人・藤原家良の山荘跡に1367(貞治6)年、室町幕府管領の細川頼之が夢窓疎石の高弟・宗鏡禅師を招請して伽藍を建立した。その後、北朝系...

写真提供:パーソナル企画
勝持寺 ( 京都府 京都市西京区 )
西京区大原野の山裾に位置。阪急京都線「東向日駅」から阪急バスで20分の「南春日町」下車、徒歩約20分で到達する。西行法師*が出家し、庵を結んだ寺と伝わり、境内には「西行桜」はじめ約100本の桜があり、古来「花の寺」と呼ばれている。世阿弥作の謡曲「西行桜」の舞台ともされる。 679(天武天皇8)年、天武天皇の勅により役行者が創...

圓光寺 ( 京都府 京都市左京区 )
叡山電鉄一乗寺駅から東へ徒歩15分にある。1601(慶長6)年、徳川家康が国内教学の発展を図るため、足利学校9代学頭の三要元佶(さんようげんきつ)を招き、伏見に建立した圓光寺学校に始まる。のちに相国寺山内に移り、1667(寛文7)年、現在地に移された。伏見にあった当時は、「貞観政要」など多数の書物を刊行。これらは伏見版、または圓...

写真提供:貴船神社
貴船神社 ( 京都府 京都市左京区 )
叡山電鉄鞍馬線貴船口駅から北へ約2km、貴船川畔にある。貴船口駅からバスなら4分の貴船下車、徒歩5分。祭神は水の供給を司る神・高龗神(たかおかみのかみ)。賀茂川の水源地に祀られ、818 (弘仁9)年以来、治水の神・祈雨祈晴の神として崇められ、日照りや長雨、国家有事の際には必ず勅使が差し向けられ、祈雨には黒馬、止雨には白馬を献...

写真提供:PIXTA
瑠璃光院 ( 京都府 京都市左京区 )
叡山電鉄八瀬比叡山口駅から徒歩12分。比叡山の西麓、八瀬にある寺院。岐阜市にある「浄土真宗無量寿山光明寺」の京都本院とされており、本尊は阿弥陀如来。明治時代に実業家の別荘として造営され、戦後は高級料理旅館などに利用されたが、2005(平成17)年、寺院に改められた。約4万m2の敷地に、延べ800 m2の数寄屋造...

京都の六斎念仏 ( 京都府 京都市 )
仏教の思想による六斎日(ろくさいにち)とは、毎月の8・14・15・23・29・晦日の6日をいう。この日は悪鬼が人に災いを及ぼすので精進潔斎し、在家信者は八戒*を守る日とされていた。六斎念仏は、平安時代に空也が南無阿弥陀仏と唱えながら鉦や太鼓を叩いて踊った踊躍(ゆやく)念仏に始まるといわれ、のちにその六斎が盂蘭盆(うらぼん)に...

写真提供:壬生寺
壬生大念佛狂言 ( 京都府 京都市中京区 )
壬生大念佛狂言は、壬生寺*で毎年3回(2月の節分とその前日の2日間、4月29日~5月5日の7日間、10月のスポーツの日を含む連休の3日間)行われる無言劇。一般に壬生狂言と呼ばれ、太鼓や鉦の音から「壬生さんのカンデンデン」と親しまれる。約700年の歴史があり、国の重要無形民俗文化財に指定されている。壬生寺へは阪急「大宮駅」または嵐電...

智恩寺(切戸の文殊) ( 京都府 宮津市 )
京都丹後鉄道天橋立駅の北東、徒歩約5分、天橋立の南端すぐ近くにあり、日本三文殊*の一つ「切戸(きれと)の文殊」で知られる臨済宗妙心寺派の禅寺。雪舟の「天橋立図」の中にも堂塔が描き込まれている。寺伝では904(延喜4)年に醍醐天皇から「天橋山智恩寺」の寺号を賜り、この年を創建としている。それ以前より文殊菩薩の霊地としての伝...

元伊勢籠神社 ( 京都府 宮津市 )
京都丹後鉄道天橋立駅から天橋立を渡って約3.5km、天橋立駅から徒歩3分にある桟橋から天橋立観光船で一の宮桟橋まで約12分、下船後徒歩3分。 社伝によればその歴史は神代から続くといわれ、天照大神が伊勢神宮に鎮座する以前にいまの奥宮あたりにあった豊受大神を祀る匏宮(よさのみや)に遷座し、吉佐宮(よさのみや)と呼ばれていたこと...

写真提供:パーソナル企画
大徳寺 ( 京都府 京都市北区 )
船岡山の北、北大路通の市バス大徳寺前のすぐ北が大徳寺。境内の東を通る大徳寺通に向かって総門が開き、西は今宮門前通を越えて千本通近くにまで及び、西端は塔頭孤篷庵。間に京都市立紫野高校や民家を挟んでいる。 臨済宗大徳寺派大本山、宗峰妙超(大燈国師)が1315(正和4)年に、赤松則村の援助で建てた小庵に始まる。花園上皇から寄...

写真提供:八幡市立松花堂庭園・美術館
八幡市立松花堂庭園・美術館 ( 京都府 八幡市 )
京都市の南西、大阪府との境にある八幡市、京阪電車石清水八幡宮駅から京阪バスで約15分「大芝・松花堂前」下車すぐにある。日本庭園、美術館、日本料理店がある複合型の施設である。 広さ約2万m2の松花堂庭園は、内園と外園で構成される。内園※には、江戸時代初期の石清水八幡宮の社僧で、当代一流の文化人であった松花堂昭乗...

写真提供:公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会
杉本家住宅・庭園 ( 京都府 京都市下京区 )
杉本家住宅は地下鉄烏丸線四条駅から徒歩5分、又は阪急京都線烏丸駅から徒歩5分にある。杉本家*は江戸中期に「奈良屋」の名で京呉服の店を出した名家で、堂々たる佇まいの住宅は京町家としては市内最大規模に属する。現在の主屋は禁門の変による大火後、1870(明治3)年に上棟されたもの。間口30m、奥行52mの敷地に建つ主屋は、表通りに面す...

大河内山荘庭園 ( 京都府 京都市右京区 )
京福電鉄嵐山本線「嵐山駅」から徒歩約15分。百人一首で有名な小倉山の南面に、映画俳優の大河内傅次郎*が約30年をかけて造り上げた別荘庭園。敷地面積は約2万m2に及ぶ。時代劇スターとして一世を風靡した傅次郎は、いずれ傷んで見られなくなる映画フィルムに対し、消えることのない美を追求すべく、1931(昭和6)年、34歳のとき...

京都市京セラ美術館 ( 京都府 京都市左京区 )
地下鉄東西線東山駅から徒歩約10分、岡崎公園*の一角、平安神宮の大鳥居前にある。1933(昭和8年)、昭和天皇即位の大典を記念し、「大礼記念京都美術館」として開館。戦後は進駐軍に接収されたが、1952(昭和27)年に「京都市美術館」と改称して再開館。以来、「京都アンデパンダン展」や「京都の美術 昨日・きょう・明日展」といったシリ...

重森三玲庭園美術館 ( 京都府 京都市左京区 )
吉田山の西麓にある吉田神社*の近く、市バス京大正門前から徒歩7分のところにある。昭和の名作庭家であり日本庭園史の研究家である重森三玲*が後半生を過ごした邸宅の一部を、一般に公開している庭園美術館。もとは吉田神社の社家の旧邸で、主屋は享保年間(1716~1736年)に、書院は1789(寛政元)年に建てられたものと伝わる。これらを19...

写真提供:正法寺
正法寺 ( 京都府 京都市西京区 )
西京区大原野にあり、「西山のお大師さま」と親しまれる真言宗東寺派の寺院。阪急京都線東向日駅・洛西口駅およびJR向日町駅・桂川駅からバスで約20分、南春日町下車、徒歩8分で到達する。 鑑真和上とともに唐より渡来した高弟の智威大徳が、天平勝宝6年(754)に隠棲地として開いた春日禅房が始まり。最澄が大原寺を建立した際、その塔頭...

写真提供:公益財団法人 樂美術館
樂美術館 ( 京都府 京都市上京区 )
地下鉄烏丸線今出川駅から徒歩で約13分、京都御所の西方、油小路通に面している。1978(昭和53)年開館。樂焼窯元・樂家*の歴代の茶碗などの作品を中心に、樂家に伝わった茶道工芸品や古文書、絵画、竹木工芸品など約1,200点を所蔵、年3回の展覧会で公開している。これらは好事家のコレクションではなく、450年にわたって、歴代が自らの研究...

相国寺承天閣美術館 ( 京都府 京都市上京区 )
地下鉄今出川駅から徒歩8分、広大な相国寺の境内にある。相国寺は1392(明徳3)年に室町幕府第3代将軍・足利義満が創建した臨済宗相国寺派の大本山。京都五山の中心的存在として宗教界だけでなく、政治・文化面でも多くの高僧が活躍した。承天閣美術館はその相国寺や、境外塔頭の鹿苑寺(金閣寺)・慈照寺(銀閣寺)などが所蔵する文化財を保...

丹後ちりめん街道 ( 京都府 与謝野町 )
丹後ちりめん街道は、与謝野町加悦の高級織物「丹後ちりめん*」で栄えた地区の通称である。旧加悦町役場庁舎から西山工場までの南北約700mの旧街道筋に面する地区を指し、一帯は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。京都丹後鉄道宮豊線与謝野駅、京都縦貫自動車道与謝天橋立ICのいずれからでも、車で約10分で到達する。 こ...

妙法院 ( 京都府 京都市東山区 )
京阪本線七条駅から徒歩10分。東大路通に面し、石垣上に築地塀を廻らせ、表門、唐門を構える。幕末まで代々法親王が住持を務めた名刹で、天台三門跡の一つ(ほかは青蓮院と三千院)。広大な境内に国宝の庫裏、重要文化財の大書院や玄関、宸殿など多くの殿舎が立つ。建物内部は通常非公開で、2027(令和9)年まで庫裏改修工事のため境内にも入...
堺市のふとん太鼓 ( 大阪府 堺市堺区 )
「ふとん太鼓」は西日本各地に存在する太鼓台といわれるもので、祭りの山車の一種。地域によって形状が千差万別である。堺市内では、5枚の布団に大きな房を4つ付けたものを、60人ほどの担ぎ手が担ぎ上げ、太鼓の音に合わせて房を揺らしながら進むのが大きな特徴。また、堺の宮大工が作り出した、蒲団を乗せる台の下に小屋根のある堺独自の形...
富田林の街並み ( 大阪府 富田林市 )
近鉄長野線富田林西口駅から徒歩7分。1560(永禄3)年頃に創建された宗教自治都市、寺内町*である。碁盤の目のように整然とした町並みになっている。また、東高野街道と堺、大和への道が出合う位置にあり、早くから交通と商業の中心地として開けていた。緩やかに起伏する閑静な羽曳野丘陵は、住宅地・文教地区として好まれ、1954(昭和29)...
黒門市場 ( 大阪府 大阪市中央区 )
大阪メトロ千日前線・堺筋線・近鉄難波線日本橋駅から徒歩約5分、千日前通と堺筋が交わる日本橋1丁目交差点の南東に位置する商店街である。 その起源は、江戸時代後期にこの地の圓明寺(えんみょうじ)にあった黒い山門近くに商人が集まり、堺や紀州から仕入れた新鮮な魚を販売したことで、長らく「圓明寺市場」と呼ばれていた。その後、...

写真提供:服部緑地スマイルパートナーズ
服部緑地 ( 大阪府 豊中市 / 大阪府 吹田市 )
豊中市と吹田市にまたがり、天竺川、高川に囲まれ、松林や竹林が広がる丘陵に1950(昭和25)年に開設された府立公園。鶴見緑地(大阪市鶴見区、守口市)、大泉緑地(堺市北区、松原市)、久宝寺緑地(大阪市平野区、八尾市、東大阪市)と並ぶ、府内4大緑地の一つでもある。大阪のターミナル・大阪メトロ御堂筋線梅田駅から直通する北大阪急行...
鶴見緑地 ( 大阪府 大阪市鶴見区 / 大阪府 守口市 )
大阪市鶴見区と守口市にまたがり、大阪メトロ長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅の南北に広がる大阪市立の都市公園。服部緑地(豊中市)、大泉緑地(堺市北区、松原市)、久宝寺緑地(大阪市平野区、八尾市、東大阪市)と並び、府内4大緑地と言われる。1972(昭和47)年に「市民園芸村」や芝生広場などが供用を開始し、整備が進められるなか、1990(平...

天王寺公園 ( 大阪府 大阪市天王寺区 )
1903(明治36)年に大阪で開催された第5回内国勧業博覧会の会場東側跡地を整備し、1909(明治42)年に開設された大阪市立の都市公園で、総面積は26万m2におよぶ。大阪メトロ堺筋線・御堂筋線動物園前駅、大阪メトロ堺筋線恵美須町駅、南海電車・JR新今宮駅、大阪メトロ谷町線・御堂筋線天王寺駅、近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅の各...
和泉市久保惣記念美術館 ( 大阪府 和泉市 )
主に、日本と中国の絵画、書、工芸品など東洋古美術約12,000点を所蔵する和泉市立の美術館として、1982(昭和57)年に開館した。阪和自動車道岸和田・和泉ICから車で約3分に立地し、公共交通機関を利用する場合には泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バスで約10分の「美術館前」停留所で下車する。 施設名に「久保惣」とあるように、和泉市を...

サントリー山崎蒸溜所ウイスキー館 ( 大阪府 島本町 )
サントリー株式会社が所有・運営する国産ウイスキーの製造工場。サントリー創業者の鳥井信治郎*が1923(大正12)年に着工、翌年から蒸溜を開始し、日本初のモルトウイスキー蒸溜所として歴史を刻んできた。 信治郎は、大阪府と京都府境の天王山山麓に位置する山崎の地が、日本名水百選にも選ばれる「離宮の水」が湧くなど良質な水が豊富...

小林一三記念館 ( 大阪府 池田市 )
現在の阪急阪神東宝グループを創業し、関西財界の第一人者でもあった小林一三* (雅号:逸翁)の事績を展示・紹介する。阪急電鉄宝塚線池田駅から北に徒歩約13分、五月山の麓に位置する。小林の住まいだった「雅俗山荘」と展示室「白梅館」のほか、茶室「費隠」、茶室「即庵」などが建つ。「雅俗山荘」は、当初、「逸翁(いつおう)美術館*...
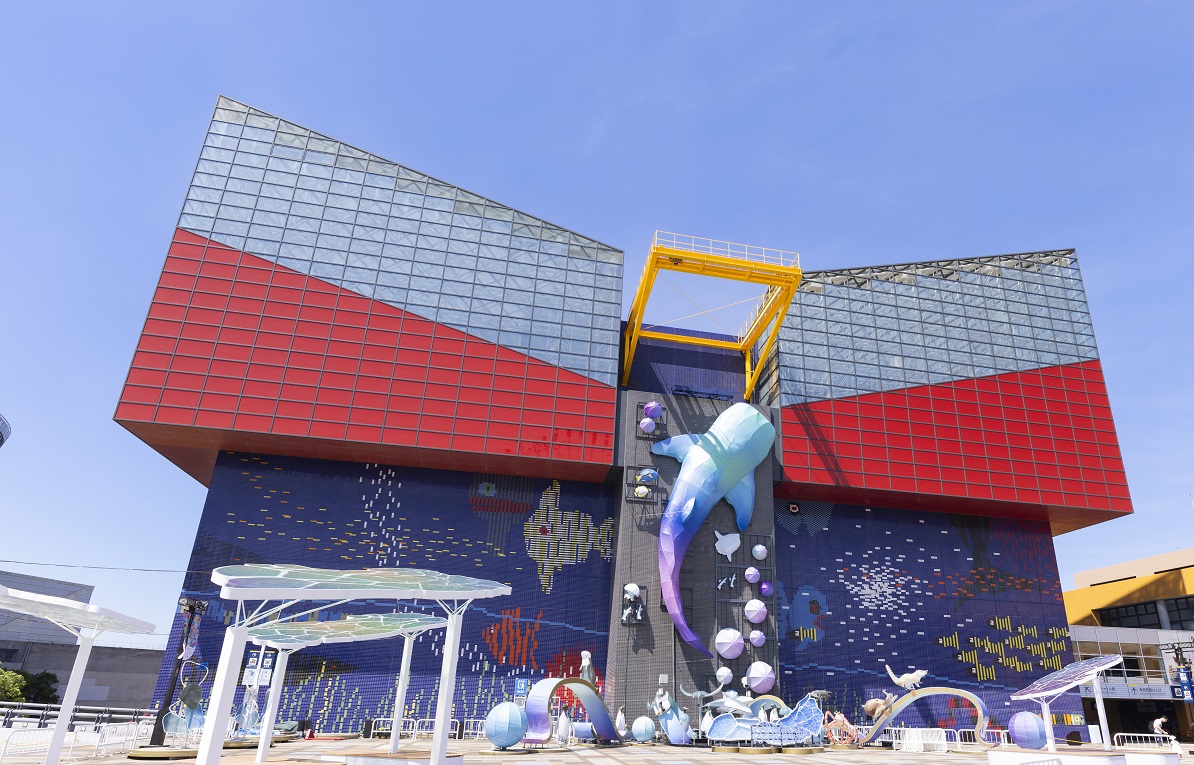
写真提供:海遊館
海遊館 ( 大阪府 大阪市港区 )
大阪メトロ中央線大阪港駅から徒歩約5分、大阪湾に面する「天保山ハーバービレッジ*」に立地する国内有数の水族館。世界最大の海洋である太平洋と、その周辺海域にみられる自然環境を忠実に再現し、約620種・30,000点の生物を飼育・展示する。 開発に際して、いまでは各地の水族館に普及したアクリルパネルの水槽を導入、ジンベエザメが...
写真提供:日本コナモン協会(農林水産省Webサイト)
大阪のお好み焼き ( 大阪府 大阪市 )
お好み焼きは鉄板に小麦粉を水で溶いた生地を薄くのばし、具材をのせて返して焼いた重ね焼きと具材を生地に混ぜて焼く混ぜ焼きに分かれる。大阪では大正から昭和初めには、庶民が洋食に憧れて、メリケン粉、キャベツ、ソースで作った洋食焼(重ね焼き)が人気となり、昭和初期にはお好み焼店が登場、そこから混ぜ焼きが生まれ、豚玉(豚の玉...
写真提供:日本コナモン協会(農林水産省Webサイト)
大阪のたこ焼き ( 大阪府 大阪市 )
大阪を代表する食文化のなかでも、アイドル的な存在であるたこ焼き。専用の鉄鋳物鍋にゆるめの生地を流しいれ、ゆでたマダコを15mmほどのさいの目カットしたものと天かすなどを入れて、ひっくり返して球体に焼き上げる。シンプルでありながらどこか愛嬌のある形と、テイクアウトで食べられる手軽さは、人々を引き付けてやまない。 大阪の...
大阪城 ( 大阪府 大阪市中央区 )
大阪城は大阪のランドマークとして位置づけられ、中核施設である大阪城天守閣の周囲に大阪城公園*が広がる。東西南北を鉄道路線に囲まれ利便性は高く、JR大阪環状線大阪城公園駅・森ノ宮駅、JR東西線大阪城北詰駅、大阪メトロ中央線森ノ宮駅・谷町4丁目駅、大阪メトロ長堀鶴見緑地線森ノ宮駅・大阪ビジネスパーク駅、大阪メトロ谷町線谷町4...

写真提供:大阪市中央公会堂
中之島公園の建築物群 ( 大阪府 大阪市北区 )
中之島公園は公的機関やオフィスビル、ホテルなどが集積する大阪市の中心部、中之島の東側を占める大阪市の都市公園。1891(明治24)年に、市内で初めて開設された公園で、北側の堂島川と南側の土佐掘川にはさまれ、西は御堂筋(国道25号線)にかかる淀屋橋・大江橋付近から、東は天神橋筋にかかる天神橋付近まで延長約1,000m、開園面積96,7...
住吉大社 ( 大阪府 大阪市住吉区 )
南海電車住吉大社駅の東側の通りには路面電車(阪堺電軌)の住吉鳥居前駅があり、その先に住吉大社の境内が広がる。大鳥居をくぐると正面に朱塗りの大きな反(太鼓)橋*1があり、これを渡って、さらに鳥居を抜けると住吉造*2の4棟の本殿*3が建つ。今は海に遠くなったが、かつては海に向かって西面していたという。手前に建つ第三(本宮)...

写真提供:勝尾寺
勝尾寺 ( 大阪府 箕面市 )
北大阪急行線箕面萱野駅から北へ約7㎞、阪急箕面線箕面駅から箕面ドライブウエイ・箕面大滝経由で約8kmの勝尾寺川最上流にある。大阪平野の北端、北摂山系の南端の山腹に寺域は広がり、山門・多宝塔・二階堂*1・本堂・大師堂・薬師堂*2(修復中)・荒神堂などが建ち並ぶ。源頼朝による再建と伝えられる薬師堂以外の堂宇は、たびたびの焼失...
大阪天満宮 ( 大阪府 大阪市北区 )
大阪メトロ谷町線・堺筋線南森町から天神橋筋商店街を経て表大門まで南東へ約350m、JR東西線大阪天満宮駅から北門(大工門)まで南へ100mほどのところにあり、都心の商店街やビル街の中にある。重厚な表大門をくぐると都心としては広々とした境内で、正面には1845(弘化2)年再建の本社をはじめ社殿*1が建ち並ぶ。また、境内西側には、天満...
施福寺 ( 大阪府 和泉市 )
泉北高速鉄道和泉中央駅から東南へ約10km。路線バスの終点槙尾山バス停*1(駐車場)の先に入山の受付(入山有料)があり、しばらく槙尾川沿いに舗装道を行くと大きな山門*2が建つ。ここから山道に入り、石段が随所にある参道を約1km、徒歩30分ほど登った槙尾山*3の尾根に同寺の堂舎がある。左手の金堂(本堂)を中心に拝堂・護摩堂・大師...
葛井寺 ( 大阪府 藤井寺市 )
近鉄南大阪線藤井寺駅の東にある商店街を南に300mほど歩くと、左手に朱塗の四脚門がある。この門は国の重要文化財に指定されている西門*1で、正面となるのは、さらに進み左手に曲がった南大門*2である。南大門の正面奥に本堂*3と護摩堂が立ち、阿弥陀堂*4(旧・二十五菩薩堂:2024年4月落慶)、大師堂、本坊などの建物が控え、4月中旬~下...
観心寺 ( 大阪府 河内長野市 )
南海電車河内長野駅から南東へ3.5km。国道310号沿いの山間に建つ古刹。 山門をくぐると、幅広い長い石段に導かれて国宝である金堂*1に着く。この金堂を中心に緩やかな傾斜を利用して建掛塔*2、霊宝館*3、講堂、訶梨帝母天堂(かりていもてんどう)*4などの堂宇が配されている。南朝ゆかりの寺で、後村上天皇陵*5や楠木正成首塚*6が...
杭全神社 ( 大阪府 大阪市平野区 )
JR大和路線平野駅から線路沿いに東南へ350mほど行ったところにあり、境内の東側に沿い、かつての平野環濠集落*1の環濠が遺されている。 同社には3棟の本殿があり、第一殿には素盞嗚尊(すさのをのみこと)、第二殿には熊野三所権現といわれる伊弉册尊(いざなみのみこと)・速玉男尊(はやたまのをのみこと)・事解男尊(ことさかのをの...
南宗寺 ( 大阪府 堺市堺区 )
阪堺電軌鉄道阪堺線御陵前駅から東へ約400mで南宗寺の北門に辿り着く。焼け瓦の埋めこまれた土塀を巡らす広大な境内に山(甘露)門*1、唐門*2、仏殿*3、鐘楼、浴室などが点在し、天慶院をはじめとする多くの塔頭が立っている。 草創は1526(大永6)年に京都の大徳寺(臨済宗)の住職古嶽宗亘が現在地の北あたり(現・寺地町3丁付近)に...
枚岡神社 ( 大阪府 東大阪市 )
近鉄奈良線枚岡駅すぐ、生駒山地の枚岡山麓に鎮座している。社伝では神武天皇ご東征の際、神事の神で皇室の守護神である天児屋根命(あめのこやねのみこと)と比売御神(ひめみかみ)を国土平定祈願のため、生駒山麓の聖地「神津嶽」(同社の本宮)に祀ったのが創祀*1となっている。さらに650(白雉元)年に現在の地に遷したと伝えられてい...
久米田寺 ( 大阪府 岸和田市 )
JR阪和線久米田駅から東南へ約1.2kmのところにある。行基*1が畿内に建造した49院の一つにあげられ、境内の南側には満水面積約456,000m2、周囲約2,650mの久米田池*2が広がる。この池は行基が725(神亀2)年から738(天平10)年まで14年の歳月をかけて築いた農業用水池として知られる。同寺の草創は734(天平6)年*3、聖武天皇の...
石切劔箭神社 ( 大阪府 東大阪市 )
腫物に霊験がある神で知られ、また延喜式内社に列したこの神社は、近鉄奈良線石切駅から西へ800m、同けいはんな線新石切駅から東へ約650mのところにある。古くからの門前町の石切参道商店街は石切駅からの道沿いとなる。一の鳥居、二の鳥居は社殿の南から参道に連なり、三の鳥居前で石切駅側からの参道と交わる。三の鳥居の南側に、重厚な...

住吉大社御田植神事 ( 大阪府 大阪市住吉区 )
全国の大社といわれる古社では、その年の豊穣を願い、御田植神事を行っているところが多い。そのなかでも、芸能神事とともに実際に神田で田植えを行う形式と、農作業を真似て執り行う形式のものがある。住吉大社は実際に田植えを行う形式で、伊勢の神宮などとともに中世の芸能神事の古式をよく遺しているといわれている。 第一本宮と住吉...
岸和田だんじり祭 ( 大阪府 岸和田市 )
「だんじり」*1は「地車」あるいは「壇尻」とも表記され、摂津・河内・和泉などの大阪を中心に西日本の祭の神幸行列で、地域により型式や曳き回し方には差異があるものの、ひろく見られる山車のことである。 そのなかでも、岸和田の「だんじり祭」は江戸中期からの歴史*2を誇り、各町会*3の「だんじり」が町中を勇壮、豪快に走り回り、...

四天王寺聖霊会 ( 大阪府 大阪市天王寺区 )
四天王寺の年間行事の中でももっとも大規模かつ重要な法会。聖徳太子の命日の4月22日に聖霊院太子殿から六時堂に太子像が遷され、六時堂とその前庭にある亀の池の上の石舞台には、四隅に巨大な赤い曼珠沙華を飾り、四天王寺一山式衆の四箇法要とともに舞楽が奉納される。まず、石舞台で聖徳太子始め諸仏を礼拝する声明の「惣礼伽陀(そうらい...

百舌鳥古墳群 ( 大阪府 堺市堺区 )
2019(令和元)年7月、古市古墳群とともに、「百舌鳥・古市古墳群」として、49基の古墳を世界文化遺産に登録させた。百舌鳥・古市古墳群は、古墳時代の最盛期(4世紀後半から5世紀後半)にかけて築造された、古代日本列島の王たちの墓群である。古代日本の政治文化の中心地の一つであり、大陸に向かう航路の出発点であった大阪平野に位置する...

古市古墳群 ( 大阪府 藤井寺市 / 大阪府 羽曳野市 )
2019(令和元)年7月、百舌鳥(もず)古墳群とともに、「百舌鳥・古市古墳群」として49基が世界遺産に登録された。百舌鳥・古市古墳群は、古墳時代の最盛期(4世紀後半から5世紀後半)にかけて築造された、古代日本列島の王たちの墓群である。古代日本の政治文化の中心地の一つであり、大陸に向かう航路の出発点であった大阪平野に位置する。...

応神天皇陵古墳 ( 大阪府 羽曳野市 )
近鉄南大阪線に乗って道明寺駅から古市駅に向かうと、右手に樹木が茂る丘のように見えるのが応神天皇陵古墳。築造は5世紀初頭と考えられ、宮内庁によって応神天皇恵我藻伏崗陵(えがのもふしおかのみささぎ)に治定され、誉田御廟山古墳(こんだごびょうやまこふん)とも呼ばれ、仁徳天皇陵古墳に次ぐわが国第2位*の前方後円墳である。墳丘...

心合寺山古墳 ( 大阪府 八尾市 )
近鉄信貴線服部川駅から徒歩約25分、八尾市大竹、玉祖神社の北西側にある前方後円墳である。古墳時代中期(5世紀前半)につくられた全長160m、後円部の高さ13m、直径92m と、中河内最大。この地域一帯を治めていた王の墓といわれている。2005(平成17)年、史跡公園として整備され、古墳にのぼることができる。墳丘の平坦部には円筒埴輪(レ...

今城塚古墳 ( 大阪府 高槻市 )
JR東海道本線摂津富田駅・阪急京都線富田駅から、北東徒歩30分にある前方後円墳。全長181m、墳丘の周囲には2重の濠がめぐる淀川流域最大級の古墳である。1958(昭和33)年に国の史跡指定を受ける。調査の歴史としては、1966(昭和41)年に地元の島上高校地歴部による平面図の作成、1970(昭和45)年からは、高槻市による土地の公有化*、航空...

山陰の松葉ガニ料理 ( 兵庫県 新温泉町、香美町 / 島根県 隠岐の島町 / 鳥取県 鳥取市、岩美町 )
松葉ガニはクモガニ科に属するやや大型の食用ガニで、正式にはズワイガニというが、山陰地方では成長した雄を「松葉ガニ」*と呼んでいる。京都の丹後地方では「間人(たいざ)ガニ」、福井県周辺では「越前ガニ」という。また、雄をズワイ、雌をコウバコと呼びわける地方もある。このカニは北方系で、日本海側では島根沖まで南下していると...

鶴林寺 ( 兵庫県 加古川市 )
JR神戸線加古川駅から南へ2km、山陽電鉄尾上の松駅から北へ1.2kmの所にある古刹。創建については、定かではないが、江戸時代に記された「鶴林寺縁起」では、高麗出身の高僧恵便が蘇我氏と物部氏の争いからこの地に隠遁したため、589(崇峻天皇2)年に聖徳太子が、秦河勝に命じて創建*1したと伝え、はじめは刀田山四天王聖霊院と称した。後に...

一乗寺 ( 兵庫県 加西市 )
神姫バス姫路駅より一乗寺経由社行で37分、一乗寺下車すぐ。北條鉄道法華口駅から約5km、法華山(標高243m)の山中の小盆地にある。境内は、木立が繁茂する法華山の南斜面が段状に造成され、そこに堂宇が建立されている。 同寺の創建については、650(白雉元)年、インドの高僧法道仙人*1が中国、朝鮮を経て飛来し、山に囲まれた同地の地...

香住海岸・但馬御火浦 ( 兵庫県 香美町 / 兵庫県 新温泉町 )
山陰海岸は、日本の国土が大陸から分離して日本海が形成され、その後に火山活動やマグマの貫入などによる地殻変動により生まれた地形と地質が、長い年月の風化・海食をうけ、奇岩絶壁を呈する海景となったもの。このため、山地が直接海に接するリアス海岸となっており、地質的にも玄武岩・安山岩・流紋岩などの火山岩や火山砕屑岩と礫岩・砂...

丹波篠山の町並み ( 兵庫県 丹波篠山市 )
JR福知山線篠山口駅から丹波篠山の町並みの中心にある篠山城跡*1まで東へ約5km。丹波篠山は兵庫県の東部、篠山盆地の中心に位置する城下町で、篠山川に沿って東西に細長く町並みがつづき、高峻な山地が盆地に迫る。古来、京都と山陰道を結ぶ街道の要衝の町として栄え、1609(慶長14)年に西国外様大名への抑えと大坂(阪)城攻略の要地とし...

篠山のぼたん鍋 ( 兵庫県 丹波篠山市 )
篠山のぼたん鍋は猪肉を地野菜(白菜、ねぎ、こぼうなど)とともに味わう。出汁は、旅館・食事処それぞれに白味噌や赤味噌をブレンドし、各飲食店が工夫を凝らして提供している。この地の猪肉が美味だとされる理由は、篠山盆地の周囲の山々が丹波栗、マツタケの特産地で知られるように照葉樹林のシイ・カシなどが多くエサとなる木の実などが...

浄土寺 ( 兵庫県 小野市 )
神戸電鉄粟生線小野駅から北東へ約4km、のどかに広がる田園風景の中にある。源平合戦の戦火による東大寺焼失をうけ、再建のための勧進職となった俊乗房重源*1は、建久年間(1190~1199年)にこの地方に従来からあった東大寺播磨別所(荘園)に加え、大半が荒野だった大部荘(おおべのしょう)の開発に力を注いだ。さらに1192(建久3)年の「...

湯村温泉 ( 兵庫県 新温泉町 )
JR山陰本線浜坂駅から南へ約9km、春来川のほとりに湧く山あいの温泉。開湯伝説として848(嘉祥元)年慈覚大師が開湯(開発)したと伝わるが、文献上でも平安中期の「和名類聚抄」には「二方郡」の項に「温泉 由」とあり、漢字2字で「ゆ」と読ませていたことが記されている。江戸時代に至っても、江戸中期の「但馬考」には、「此郷の湯村に温...

六甲山 ( 兵庫県 神戸市 / 兵庫県 芦屋市 / 兵庫県 西宮市 / 兵庫県 宝塚市 )
兵庫県神戸市の北西、標高931mの六甲山を最高峰として西に摩耶山、再度山を経て、東西方向に約30kmに伸びる連山である。神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市に属しており、これらの市街地から急傾斜でそそりたつ山並みは阪神地域のランドマークとなっている。北側の山麓は有馬温泉*1に繋がっており裏六甲として親しまれている。 六甲山の自然...

六甲山からの夜景 ( 兵庫県 神戸市 )
六甲山は神戸市街地の背面に屏風のようにそびえる連山で、南斜面は海岸線から僅か7㎞ほどの距離で標高931mの六甲山頂に達する。そのため山頂エリアからは眼下に広がる神戸市街地から大阪湾、淡路島、瀬戸内海までの雄大な展望が楽しめ、特に市街地の照明と暗い海の広がりの対比として「1000万ドルの夜景*」と呼ばれ、長崎・稲佐山からの夜景...

湊川神社 ( 兵庫県 神戸市 )
JR神戸駅の北、阪急・阪神・山陽各線高速神戸駅の東改札から地上にでたところにある。この地はもともと楠木正成*が1336(延元元)年に足利尊氏・直義等の軍勢と戦い、敗れ、刺し交え、生涯を閉じた場所であったとされ、文禄年間(1592~1596年)の太閤検地の際、免祖地となった。1692(元禄5)年には徳川光圀によって正成の墓所*が建立され...

太山寺 ( 兵庫県 神戸市 )
神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅から北東へ2.7km、または学園都市駅から北へ2.5km。境内は深い原生林の山に囲まれ、いわゆる「八葉蓮華」の地にある。創建は江戸初期の「播州太山寺縁起」によると、藤原鎌足の長男定恵和尚の開山と伝えられ、鎌足の孫の宇合が716(霊亀2)年に建立*1したとしている。鎌倉から室町時代にかけては多数の僧...

須磨寺 ( 兵庫県 神戸市 )
山陽電鉄須磨寺駅から須磨寺前商店街を通って北西へ約450mのところにある。正式には上野山福祥寺だが、古くから須磨寺と称されてきた。宗派は真言宗。創建は同寺の縁起では近くの和田岬の海中より出現した聖観世音菩薩像を安置するため、淳和天皇の勅命で会下山(兵庫区会下町)に北峰寺が建立されたのち、886(仁和2)年には光孝天皇の勅命...

神戸北野異人館群 ( 兵庫県 神戸市 )
神戸市の中心街・三宮や元町の北側、六甲山麓の南斜面にある山手一帯の北野町および山本通一帯は、明治から昭和初期に建った洋館がもっとも多く残っており、現在は「神戸市北野町山本通重要伝統的建造群保存地区」に選定されている。約9.3万m2に及ぶ保存地区には、国の重要文化財となっている旧トーマス住宅(風見鶏の館)*及び...

メリケンパーク ( 兵庫県 神戸市 )
JR・阪神元町駅から公園入口まで南へ約500m、神戸市営地下鉄みなと元町駅からは約300m、神戸市中突堤の東側にある。1868(明治元)年に外国船の荷揚げ港として造られたメリケン*1波止場と1938(昭和13)年に竣工された中突堤間を埋め立てた総面積約16万m2の公園で、1987(昭和62)年開園。神戸海洋博物館*2、「BE KOBE」のモ...

灘の酒蔵群(灘五郷) ( 兵庫県 神戸市 / 兵庫県 西宮市 )
14世紀からの酒造りの歴史を有する灘五郷とは、阪神間の今津郷(西宮市今津周辺)、西宮郷(西宮市西宮周辺)、魚崎郷(東灘区深江、魚崎周辺)、御影郷(東灘区住吉、御影周辺)、西郷(灘区新在家、大石周辺)を指し、東神戸一帯が含まれる。 この灘五郷と呼ばれる一帯は宮水と呼ばれる良質の水、六甲下ろしの寒風、播州米など、酒のた...

有馬温泉 ( 兵庫県 神戸市 )
有馬温泉の開湯は、神代*1からという伝承もあるが、もっとも古い記録としては「日本書紀」に舒明天皇及び孝徳天皇*2が行幸されたことが記されている。さらに平安時代には和歌に詠み込まれ、枕草子*3にもその名が出ており、極めて古くから都の貴庶を問わず入湯に来たことがうかがわれる。 また、「有馬温泉寺縁起」では、奈良時代の僧行...

神戸女学院 ( 兵庫県 西宮市 )
同学院は1875(明治8)年、アメリカから派遣されたタルカット、ダッドレーの二人の女性宣教師によって創立された。当初から、教育の根幹はキリスト教と国際理解の精神に根ざしたリベラルアーツを軸とする全人教育としている。中学部・高等学部・大学・大学院があり、大学の学部は1993(平成5)年以降、文学部、音楽学部、人間科学部の3学部で...

写真提供:関西学院大学
関西学院大学(西宮上ケ原) ( 兵庫県 西宮市 )
関西学院大学は1889(明治22)年、アメリカ人宣教師ウォルター・ラッセル・ランバスが牧師養成と青年への全人教育を目的とした男子校の創立を計画し、原田の森(現在の神戸市灘区)に木造校舎を建造したのが始まりである。キリスト教主義に基づく「学びと探究の共同体として・・・創造的かつ有能な世界市民」を育むことを教育の基本にしてい...

西宮神社の十日えびす ( 兵庫県 西宮市 )
西宮は江戸時代から酒の醸造が盛んで江戸への「下り酒」の積み出し港としても栄え、その繁盛のシンボルとして西宮神社*1は、「えべっさんの総本社」と親しまれてきた。今も、福の神、商売の神として多くの参拝客がつめかける。阪神西宮駅の南西、国道43号に面して広がる広大な社域。境内を巡る本瓦葺の大練塀*2は室町時代の遺構である。堅牢...

多田神社 ( 兵庫県 川西市 )
能勢電鉄多田駅から西へ約2kmのところにある。清和源氏一門の祖廟として970(天禄元)年に源満仲*1が創建。もとは多田院と号し、別称として鷹尾山法華三昧寺とも呼ばれた。その後、金堂・塔婆・学問所・法華堂・常行堂・御影堂等が造営され、源満仲・頼光*2の廟所があったことから、源氏姓を名乗る北条・足利など武家諸侯の信仰が篤く隆盛...

写真提供:高源寺
高源寺 ( 兵庫県 丹波市 )
JR福知山線柏原駅から北西に約20km、岩屋山(標高718m)の北麓にある。1325(正中2)年、中国(「元」)の杭州天目山の中峰明本(普応国師)に10年間学んで帰った遠谿祖雄禅師*が、霊夢で得た天目山に似たこの地に堂宇を創建した寺。同寺は遠谿祖雄禅師が日本へ帰国した後に、入元した業海本浄*が同じ天目山で学び、1348(貞和4)年に開創...

国営明石海峡公園 ( 兵庫県 淡路市 )
「国営明石海峡公園」は、兵庫県の淡路島と神戸市の双方にまたがる国営公園のうち淡路島側にあたる公園である。神戸市側の公園は、「あいな里山公園」の名称で公開されており、「国営明石海峡公園」という名称は淡路地区について使用されている。 公園までは神戸市街地から高速道路で明石海峡大橋を渡り、淡路I.C.を出て南に5分、32kmの距...

竹田城跡 ( 兵庫県 朝来市 )
JR播但線竹田駅の西、円山川左岸、標高約354mの古城山頂にある。この地は兵庫県のほぼ中央、但馬地方の南端にあり、但馬・丹波・播磨の三国の境に近く、播但道・山陰道が交差しており、交通の要衝となっている。竹田城の築城については、確かな記録は遺されていないが、但馬などの守護職にあった山名持豊*1(後に宗全と号す)が嘉吉の乱*2...

沼島 ( 兵庫県 南あわじ市 )
淡路島の南、南あわじ市の沖合4.4kmに浮かぶ面積2.7km2、周囲9.5km、最高地点は海抜117mの離島。南あわじ市灘の土生(はぶ)港と連絡船により10分で結ばれている。 この島は古事記・日本書紀に記された国生み伝説*1による最初に造られた島「おのころ島*2」であるとする説がある。「おのころ島」とは日本神話で伊弉諾尊(いざ...

圓教寺 ( 兵庫県 姫路市 )
JR山陽本線・山陽電鉄姫路駅より北へ7kmほどの書写山ロープウエイ山麓駅からロープウエイに乗って約4分の山上駅下車。ここから約1kmの急坂を登ると、徒歩20分ほどで圓教寺の摩尼殿(本堂)*1に着く(有料のマイクロバスあり、所要5分)。 標高371mの書写山の山上一帯は圓教寺の境内で占められ、全山スギ・ヒノキなどの深い森で覆われてお...

姫路城 ( 兵庫県 姫路市 )
JR山陽新幹線・山陽本線・山陽電鉄姫路駅から姫路城大手門前まで北へ約1km。姫路市街北西寄りの姫山(標高45.6m)の山上にある。明治以後、多くの城が失われたなかで、姫路城だけは、大天守・小天守をはじめ、渡櫓・塀・城門などが完備した形で残され、江戸初期の築城技術を知る上に重要な資料となっている。主要部を白漆喰総塗籠造*1でちょ...

写真提供:阪急電鉄株式会社 歌劇事業部
宝塚大劇場 ( 兵庫県 宝塚市 )
「宝塚大劇場」は、「すみれの花咲く頃、初めて君を知りぬ……」の歌に象徴される「宝塚歌劇団」*1の本拠地で、阪急宝塚線宝塚駅から「花のみち」*2をたどり500mほどのところにある。大劇場は座席数2,550席を擁し、各組80名ほどの団員からなる花組・月組・雪組・星組・宙組の5つの組により1年を通じそれぞれ特色のある公演が交代で行なわれて...

豊岡のコウノトリ ( 兵庫県 豊岡市 )
日本においてコウノトリ*は、江戸時代には全国に生息していたといわれるが、乱獲などにより1971(昭和46)年にその姿が確認されなくなった。そのため最後の生息地であった豊岡では、1999(平成11)年に野生復帰事業として「兵庫県立コウノトリの郷公園」を開設し、種の保存と野生化及び人と自然の共生に関する普及啓発などに取り組んでいる...

城崎温泉 ( 兵庫県 豊岡市 )
JR山陰本線城崎温泉駅から約350mほどのところ、東西に流れる大谿(おおたに)川の谷あいに沿って形成された温泉街。大谿川は温泉街のすぐ下流で、円山川と合流し日本海に注いでいる。温泉街はこの大谿川に沿うように柳の並木が植栽され、川には数メートルおきに丸い石橋も架けられている。この街並みには老舗の旅館*だけではなく、城崎名物...

玄武洞 ( 兵庫県 豊岡市 )
JR山陰本線豊岡駅から円山川の右岸を北へ車で15分、同じく城崎温泉駅からは南へ車で10分、円山川に沿って東に面した山裾に、玄武岩*の柱状節理の大岩壁がそそり立つ。岩壁の下部には洞穴があり、これは過去に採石場として人工的に掘られたもので、1925(大正14)年の北但大震災の際に崩落し、また自然崩落の危険性もあることから、今は入洞...

明石城 ( 兵庫県 明石市 )
JR西・山陽電鉄の明石駅北口から徒歩5分に位置し、明石城の内堀から北側の54万8,000m2が明石公園となっている。明石城址はその中の本丸にある2つの櫓(やぐら)と、二の丸・東の丸・稲荷曲輪を囲む石垣、及び正門が保存されている。 この城は1619年(元和5)年に初代明石藩主小笠原忠政(後の忠真)によって築かれた。小笠原...

魚の棚商店街 ( 兵庫県 明石市 )
JR西・山陽電鉄の明石駅南側、徒歩5分のところに位置するアーケード商店街で、東西に260m、南北の横道まで含めると延350mになる大規模なものである。鮮魚店や海産物店を中心に約100軒の店舗が連なっている。 明石市は明石海峡を挟む大阪湾、播磨灘に面し、強い潮流と複雑な地形により沿岸漁業が盛んである。その産物として特産の鯛、蛸を...

氷ノ山 ( 兵庫県 養父市 / 鳥取県 若桜町 )
標高1510mの須賀ノ山を中心に、兵庫県と島取県境一帯に鉢伏山・瀞川山・蘇武岳・妙見山・陣鉢山などの支脈をもつ山塊をいう。ただ、一般的には氷ノ山といえば、主峰の須賀ノ山を指すことが多く、白山火山帯に属しており、その山容は釣鐘型の溶岩円頂丘を示す。 須賀ノ山は、頂上付近に須賀ノ宮があったと伝えられており、須賀神を祭る神地...

天滝渓谷 ( 兵庫県 養父市 )
JR山陰本線養父駅から西へ大屋川に沿って約24.5km。氷ノ山から東に向かう起伏に富んだ尾根に広がる杉ケ沢高原の南麓、大屋川支流に沿う渓谷。最大のみどころは、落差98mの天滝(標高600m)で、滝への登山口の駐車場(標高250m)から山道を約1.2kmほどのところにある。途中、糸滝、夫婦滝、鼓ヶ滝などが点在する。 この滝が点在する地形は...

名草神社 ( 兵庫県 養父市 )
JR山陰本線八鹿駅から西へ約16km、標高1142mの妙見山(みょうけんざん)中腹に鎮座し、927(延長5)年に撰進された延喜に式内社として記載がある古社。創建は社伝では、585(敏達天皇14)年に養父郡の郡司が紀州名草の出身で、自らの祖神であった名草彦など七座の神を石原山(妙見山)に祀ったのが始まりとしているが、定かではない。ただ、...

丹波焼の里 ( 兵庫県 丹波篠山市 )
JR福知山線相野駅から北西へ約6km、四斗谷川に沿った谷あいの今田(立杭)地区に、約60軒ほどの丹波焼の窯元が軒を連ねており、「丹波焼の里」と称している。この地区は窯元のほか、「丹波伝統工芸公園 立杭陶の郷」*や「兵庫陶芸美術館」*など丹波焼に関する施設も整備されている。なお、地名から「丹波立杭焼」とも呼ばれている。 丹...

斑鳩寺 ( 兵庫県 太子町 )
JR山陽本線網干駅から北へ約3kmの鵤(いかるが)地区にある。創建の年代は不詳であるが、寺伝では 606(推古天皇14)年に聖徳太子が飛鳥豊浦宮(現・奈良県明日香村橘寺) で天皇の御前で勝鬘経を講説したところ、播磨国揖保郡の水田100町*1を賜り、その地に伽藍を建てたのが斑鳩寺の始まりとされる。その後、この地は法隆寺領鵤荘と呼ばれ...

大乗寺 ( 兵庫県 香美町 )
JR山陰本線香住駅から南へ1.7km、北流する矢田川が左右に大きく屈曲する懐部分にあり、かつては門前町として賑わったと思われる通りの真ん中あたりに丘を背にして建つ。大乗寺は「応挙寺」ともよばれ、円山応挙*1が長子応端、長沢芦雪*2など門弟12名とともに客殿13部屋に襖絵などとして描いた障壁画165面が遺されている寺として知られてい...

姫路城西御屋敷跡庭園好古園 ( 兵庫県 姫路市 )
JR山陽本線・山陽新幹線・山陽電鉄姫路駅から北へ約1.5km、姫路城の大手門からは内堀沿いに西へ250mほどのところに庭園の入口がある。好古園*は姫路城の西南に隣し、内堀と中堀の間の三角形状の約3.5万m2の広大な敷地に、1992(平成4)年に姫路市制100周年記念事業として、造営、開園した池泉回遊式の日本庭園である。この敷地...

写真提供:パーソナル企画
岡寺 ( 奈良県 明日香村 )
近鉄橿原神宮前駅から東へ約5km、明日香村の東の山腹に位置する。西国三十三所観音霊場の第7番札所。龍蓋寺ともいうが、古くから地名由来の「岡寺」の名で親しまれ、現在では宗教法人としての名も「岡寺」となっている。仁王門*1をくぐり石段を上ると、本尊の塑造如意輪観音坐像*2を安置する本堂*3を中心に、古書院*4、開山堂*5、三重宝塔*6...

写真提供:パーソナル企画
橘寺 ( 奈良県 明日香村 )
近鉄吉野線飛鳥駅から東へ約2.2km、飛鳥川の左岸、川原寺跡の南に対面して建つ。現在は、田園風景のなかに本堂(太子殿)、経堂、観音堂などの堂宇*1が並ぶ。本堂には本尊で国の重要文化財に指定されている木造聖徳太子坐像*2が安置されている。なお、正式名称は仏頭山上宮皇院菩提寺という。 創建*3について明確ではないが、寺伝では聖徳...

明日香村の古墳(キトラ古墳・高松塚古墳・石舞台古墳) ( 奈良県 明日香村 )
奈良盆地の中南部、明日香村の村内には、古代史を解き明かすために重要な古墳が数多くある。なかでもキトラ古墳、高松塚古墳、石舞台古墳はよく知られる。これらの古墳の周辺は国営飛鳥歴史公園*1のキトラ古墳周辺地区、高松塚周辺地区、石舞台地区として整備されている。 キトラ古墳は近鉄吉野線壺阪山駅から東に約1km、高松塚古墳から南...

写真提供:パーソナル企画
飛鳥寺 ( 奈良県 明日香村 )
わが国最初の本格的寺院。飛鳥にあるので飛鳥寺と呼ばれるが、当初は法興寺・元興寺ともいわれた。 飛鳥寺の創建の経緯は「日本書記」に記されている。仏教受容派の蘇我氏と排除派の物部氏の対立は、587( 用明天皇2) 年、皇位継承争いと相まって戦いとなり、蘇我馬子はこの戦いに際し寺院建立と仏法流布を誓った。物部守屋が滅亡すると、...

写真提供:信貴山朝護孫子寺
信貴山朝護孫子寺 ( 奈良県 平群町 )
近鉄生駒線信貴山下駅から約2.6km、生駒山系の南端、信貴山(標高437m)の南東中腹に広大な境内をもつ。ずらりと並ぶ千体地蔵を右に仁王門をくぐり、無数の石燈篭のつづく参道の先に本堂をはじめ朱塗の三重塔、多宝塔、霊宝館*1など多くの堂宇が軒を接している。なかでも鉄筋コンクリートで1958(昭和33年)に再建された舞台造の本堂は、急崖...

藤ノ木古墳 ( 奈良県 斑鳩町 )
JR関西本線(大和路線)法隆寺駅から北西へ約1.8km、法隆寺の西350mの住宅地にある直径約50m、高さ約9mの大型円墳*1。1985(昭和60)年の発掘調査で、豪華な馬具が出土して注目された。横穴式石室*2で、玄室の奥に未盗堀の朱塗りの刳抜式家形石棺があり、1988(昭和63)年に開棺調査された結果、2体の人骨と、歩揺*3をつけた筒形金銅製品、...

法隆寺 ( 奈良県 斑鳩町 )
JR法隆寺駅から法隆寺南大門まで北へ約1.5km。聖徳太子ゆかりの斑鳩の里にあり、斑鳩寺*1とも呼ばれた。矢田丘陵南端の山裾を背に立ち並ぶ金堂・五重塔などの伽藍は、現存世界最古の木造建築といわれる。 法隆寺の歴史は金堂の薬師如来光背銘*2によると、607(推古天皇15)年に聖徳太子と推古天皇が創建したとされる。ただ、日本書紀には6...

写真提供:パーソナル企画
法起寺 ( 奈良県 斑鳩町 )
JR関西本線(大和路線)法隆寺駅から北東へ約2.5km、法隆寺から北東へ約2kmのところにあり、もとは岡本寺(おかもとでら)・池後尼寺(いけじりにじ)とも称した。706(慶雲3)年完成とされる三重塔*1にあった露盤銘*2によると、聖徳太子の岡本宮を山背大兄王が寺に改め、638(舒明天皇10)年に金堂が建立、685(天武天皇10)年に三重塔の建...

中宮寺 ( 奈良県 斑鳩町 )
JR関西本線(大和路線)法隆寺駅から北へ約1.5km、法隆寺東院(夢殿)の北東に接しているが、室町時代(16世紀前半まで)は東方約500m*1にあり、斑鳩尼寺(いかるがにじ)とも呼ばれた。創建年代については諸説*2があるが、聖徳太子の母穴穂部間人(あなほべのはしひと)皇后の御所を寺としたと伝え、法隆寺若草伽藍とほぼ同時期に建立された...

写真提供:パーソナル企画
柿の葉寿司 ( 奈良県 五條市 / 奈良県 吉野郡 )
吉野地方に伝わる郷土料理で、一口大ほどの酢飯に塩サバなどをのせて柿の葉で包み、押しをかけた寿司。今では一年中食べられるが、本来は夏祭りのごちそうだった。 起源は不詳だが、江戸時代中期には柿の産地だった五條や吉野川流域ですでに作られていたといわれている。海から離れた奈良盆地や紀伊山地の山里では、海産物は極めて貴重な...

写真提供:パーソナル企画
奈良のシカ ( 奈良県 奈良市 )
奈良のシカは春日大社の神の使い*1とされ古く*2から大切にされてきた。現在は奈良公園に1,300頭(2024年7月現在)ほどが生息、国の天然記念物として保護されている。春日大社の参道脇に鹿苑があり、シカの保護育成にあたっている。公園内の売店で販売している「鹿せんべい」*3は観光客がシカに与えることができるが、それ以外は一切与えられ...

写真提供:パーソナル企画
春日山原始林 ( 奈良県 奈良市 )
奈良市の中心部から東に位置し、稜線を形作っているのが春日山で、奈良の市街から手前に見えるのが、春日大社の神山である御蓋山*1(標高297m)、その奥に標高498mの花山があるが、この両方、または一方を「春日山」と呼ぶ。この春日山を中心として北側に若草山(標高342m)、南側に高円山(432m)を見る面積298万m2の森が春日...

写真提供:平城宮跡管理センター
平城宮跡 ( 奈良県 奈良市 )
平城宮跡は、近鉄奈良線大和西大寺駅と同新大宮駅の間、佐紀路*1の南側に広々とした平地に遺された平城京*2の中心地であった史跡。現在は広大な遺跡公園となっている。平城京は710(和銅元)年に元明天皇により藤原京から遷都*3され、784(延暦3)年に桓武天皇により長岡京に遷されるまでの8代74年間の都であったが、延暦の遷都後は荒墟*4と...

写真提供:パーソナル企画
東大寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から東大寺南大門まで東へ約1.2km、若草山の麓に広大な寺域を占める巨刹。仏教文化が最高潮に達した8世紀半ばに、国力を傾けて造営された。寺号は平城京の東方にある大寺ということに由来する。正式には金光明四天王護国之寺*1とも称し、南都七大寺*2の一つであった。天災や兵火でたびたび伽藍を失いながらも、本尊の「奈良の...

写真提供:パーソナル企画
春日大社 ( 奈良県 奈良市 )
御蓋山(みかさやま)*1の麓、春日山原始林から続く深い杜の中に鎮座する古社。近鉄奈良線奈良駅から800mほどの興福寺境内のすぐ東に立つ一之鳥居*2から本社までさらに1300mほど続く表参道は、浅茅(あさじ)ヶ原、飛火野を通って行く。参道に燈籠が徐々に増え、二之鳥居を過ぎれば、両側に石燈籠が林立して、本社の南門*3へと導かれる。本殿...

写真提供:パーソナル企画
興福寺 ( 奈良県 奈良市 )
境内の南側から入るのならば、近鉄奈良線奈良駅からアーケードの東向商店街を南下し、三条通りを西へ。駅から約500mで五重塔のたもとに着く。北側からならば、近鉄奈良駅から大宮通り(登大路)を東へ300mのところが北参道の入口になる。 約2万5,000坪(約8万2,500m2)に及ぶ境内には、仕切りの塀もない松林の中に、中金堂*1・...

写真提供:薬師寺
薬師寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄橿原線西ノ京駅のすぐ南東にあり、境内に立つ三重塔は西ノ京のシンボルになっている。西ノ京駅から道を左にとれば、與楽門からすぐ境内に入れるが、正面は南側の南門となる。伽藍配置は、南門*1、中門、本尊の薬師三尊像(国宝)を祀る金堂*2、教学の中心となる大講堂*3、僧侶が食事をする食堂*4が南北に一直線に並び、金堂の左右(東西...

写真提供:パーソナル企画
唐招提寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄橿原線西ノ京駅から北へ約600m、閑静な五条町の集落の一角に、木立の深い境内が広がっている。南大門*1をくぐると、正面に「天平の甍」の金堂*2が建ち、その背後に平城宮から移された講堂*3が構えている。奈良に遺る古代寺院のほとんどが兵火にかかっているなかで、創建時からの姿を維持しつつ、奈良時代から近世までの各時代の伽藍*4をよ...

元興寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から南へ約1km、「ならまち」の古い街並みのなかに元興寺は建つ。この寺は、蘇我馬子が飛鳥に建立した日本初の本格的寺院、法興寺(飛鳥寺*1)を前身とする。平城遷都によって現在地に移転し、新しい伽藍*2を建立、大いに栄えた。しかし、都が京都へ遷り、平安時代も後期になると寺勢は衰退、東大寺や興福寺の傘下に組み込ま...

写真提供:新薬師寺
新薬師寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良駅から東南へ約2.3km、天平建築の本堂*1と本尊の薬師如来坐像*2、天平期の塑造彩色像の十二神将立像*3で知られている。草創については、聖武(しょうむ)天皇の病気平癒を祈って、747(天平19)年に光明(こうみょう)皇后が建立し、7躯の薬師如来像を安置したという。当時、天皇の発願による東大寺の大仏が造立されていたが、そのさ...

写真提供:パーソナル企画
圓成寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から東へ約12km、忍辱山(にんにくせん)*1の山号をもつ柳生街道沿いの第一の古刹。赤松や杉が茂り、苑池の広がる浄土式庭園*2と一段高く立つ瀟洒な楼門*3、さらに奥の本堂*4や本堂左手にある丹塗(にぬり)の白山堂・春日堂と宇賀神本殿*5が背後の森に包まれる幽邃境となっている。同寺の縁起*6では、756(天平勝宝8)年に...

写真提供:パーソナル企画
般若寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から北東へ約2.2km、京都に向かう奈良街道の奈良坂に面し、軒の低い二階屋の民家が並ぶなかに楼門が立つ。舒明天皇(593~641)のころ、高句麗の僧慧灌*1がここに一宇を建て、654(白雉5)年、孝徳天皇の病気全快を祈って蘇我日向臣(そがのひむかのおみ)が伽藍を創建したと伝えられる。さらに735(天平7)年、聖武天皇が平...

写真提供:パーソナル企画
不退寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線新大宮駅から北へ約1km、木立に囲まれた参道の先にある。正式な山号寺号は金龍山不退転法輪寺である。「大和国金龍山不退寺縁起」によると、平城天皇は809(大同4)年譲位後に、この地に茅葺(かやぶき)の仮殿(宮)を営み*1、第1皇子阿保(あぼ)親王、その子在原業平*2も引きつづいてここに住んだと伝えている。この地での寺院...

写真提供:法華寺
法華寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線新大宮駅から北西へ約1.3km、東大寺転害門から西へたどる佐保路(平城京の一条南大路)の突き当たりにある尼寺。天平時代に光明皇后*1が藤原不比等*2の邸宅を喜捨して寺を建て、総国分尼寺となり、法華滅罪之寺*3と称した。七堂伽藍を備えた大寺であったと推定されるが、平安遷都後は衰え、鎌倉時代に西大寺の僧叡尊が再興したが、...

正暦寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から南東へ約9km、JR桜井線(万葉まほろば線)帯解駅から東へ5km。高円山の南、菩提仙川を遡った沢沿いに堂宇が建つ。一条天皇の発願によって992(正暦3)年、藤原兼家の子・兼俊僧正が創建し、当初は堂塔伽藍86宇を数える大寺であったといい、北大和五山*1に数えられていた。1180(治承4)年、平重衡の南都焼き討ちの際に全...

写真提供:帯解寺
帯解寺 ( 奈良県 奈良市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)帯解駅から北200mほどのところにある。寺伝では勤操を開基とする巖渕千坊*1の一院で霊松庵であったとされ、文徳天皇の皇后藤原明子が子がなく悩んでいた折、同庵の地蔵菩薩に祈願をしたところ、見事懐妊し、無事にのちの清和天皇を安産したことから、858(天安2)年に伽藍を建立し、寺号を「無事安産し、腹帯が安...

白毫寺 ( 奈良県 奈良市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)京終駅から高円山に向って約2.2km、高円山の西麓、奈良盆地の眺望が開ける高台にある。境内は広くはないが、本堂と宝蔵などが建ち、本堂右手の池の奥には多宝塔跡や石仏を巡る「石仏の道」がある。創建は、諸説*1あり不詳だが、一説には天智天皇の本願により勤操*2が開基したともいわれ、高円山にあったとされる勤...

西大寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄大和西大寺駅の南出口から徒歩3分。765(天平神護元)年、称徳天皇の勅願*1によって東の大寺(東大寺)に対する西の大寺として創建され、官大寺の一つとして大伽藍を誇った。平安遷都、そして数度の火災によって衰えたが、鎌倉時代に叡尊*2が出て復興に努め、真言律宗の道場として再興した。現在は、江戸時代に再建された本堂*3・愛染堂*...

東大寺二月堂修二会(お水取り) ( 奈良県 奈良市 )
二月堂の本尊の前で罪障を懴悔し、国家の安泰と万民の快楽(けらく)などを祈る十一面悔過(けか)*1の法要。3月1日から14日まで行われる。752(天平勝宝4)年、実忠*2が笠置山の竜穴で菩薩たちの行法を見て創始*3したと伝えられ、もとは旧暦2月に行われたので修二会*4と呼ぶ。 現在の日程は次のとおりである。まず、前年の12月16日に翌年...
写真提供:一般財団法人奈良県ビジターズビューロー
若草山焼き行事 ( 奈良県 奈良市 )
東大寺の東、春日大社の北東にある標高342mの若草山*1で毎年1月第4土曜日に行われる。若草山の麓までは近鉄奈良線奈良駅から東へ約1.8km。18時15分に花火が打ち上げられ、18時半頃から山麓中央の大かがり火から松明に火を移し、法螺貝、ラッパの合図により若草山各所で一斉に山焼きの点火が行われる。山焼きの面積は約33万m2で30...

写真提供:パーソナル企画
奈良国立博物館 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から東へ800mほどのところにある。日本で2番目にできた国立博物館で、仏教美術に関する文化財を中心に収蔵しており、展示も仏教美術の鑑賞と研究に役立つように考えられている。ギャラリーは「なら仏像館」*1・「青銅器館」*2・「東新館」*3・「西新館」*4の4つ。また、仏教美術関連の調査研究資料の作成・収集などを行い、...

大和文華館 ( 奈良県 奈良市 )
1960(昭和35)年、近畿日本鉄道の創立50周年記念事業の一つとして開館された。蛙股池*1畔の松林に囲まれた小高い所にあり、美術館の建物は日本建築の特色に近代美を生かしている。日本と中国、朝鮮を中心とする東洋古美術をテーマとする展示のほか、講演会などの行われる講堂がある。絵画・書跡・陶磁・彫刻・工芸・染織品など、収蔵の美術...

写真提供:奈良女子大学
奈良女子大学 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から北へ約500m、佐保川の南岸にある国立の女子大学。1908(明治41)年に奈良女子高等師範学校として創立され、1949(昭和24)年に新制大学となった。現在は、奈良国立大学機構(2022年4月から)傘下の大学として文学部、理学部、生活環境学部、工学部の4学部が設置されている。明治期から近代女子教育の中心的な学校であっ...

写真提供:霊山寺
霊山寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線富雄駅から南へ約2.6km、富雄川に臨んで朱塗の大鳥居*1が立ち、境内は矢田丘陵を背後に控えて木立が多い。創建については諸説*2あり、不分明だが、寺伝の略縁起では、聖武天皇の勅願によって、天平時代に行基が開基となったという伝承が記されている。本尊の薬師如来像*3の胎内からは「治暦二年」(1066年)の紀年銘が記された紙片...

写真提供:一般財団法人奈良県ビジターズビューロー
月ヶ瀬梅林 ( 奈良県 奈良市 )
JR関西本線月ヶ瀬口駅から南へ約8km、奈良市街からは柳生経由で約30km、木津川の支流五月(名張)川の渓谷とダム湖の月ヶ瀬湖に沿い、両岸の岸辺から山腹へ約4kmにわたって梅林がつづく。その数1万本ともいわれ、両側から山が迫り、V字型をした渓谷は、2月下旬になると白い花に埋まり、芳香に包まれる。 梅林の起源*1は明らかではないが、...

写真提供:大神神社
三枝祭 ( 奈良県 奈良市 )
「ゆりまつり」とも呼ばれる。近鉄奈良線奈良駅から南へ約400m、大神神社の境外摂社、率川(いさがわ)神社*1で例年6月16~18日に行われる。17日には、三枝(さいくさ)の花(三輪山に自生するササユリ)を酒樽に飾って神前に捧げ、4人の巫女がユリをかざして舞を奉納、神話時代を再現する。また、午後からは七媛女(ななおとめ)・ゆり姫・...

奈良ホテル ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から南東へ約1.2km、JR関西本線(大和路線)奈良駅から東へ約2km。興福寺の南にあたり、旧大乗院庭園を南側に、東側は荒池に臨む奈良公園の高台に建つ。奈良ホテルは、日露戦争後、訪日外国人の増加に伴い、奈良にも洋式のホテル建設の気運が高まるなかで、鉄道会社やホテル事業者が中心になり、1909(明治42)年に開業した...

写真提供:海龍王寺
海龍王寺 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線新大宮駅から北西へ1.3km、平城宮跡の北東近くにある。710(和銅3)年、平城遷都の際、藤原不比等がこの地を土師氏から譲り受け邸宅を構え、北東隅にあった堂宇を引き継いだのが前身といわれる。731(天平3)年に藤原不比等の娘である光明皇后がこの地を皇后宮とし、伽藍を整備した上で、唐から帰朝した玄昉*1を住持に任じ開基とし...

依水園・寧楽美術館 ( 奈良県 奈良市 )
近鉄奈良線奈良駅から東へ約1km、東大寺南大門の西にある。依水園は1万3,481m2の敷地にかつては吉城川をひき入れ、若草山・春日山を借景とした庭園。前園と後園に分かれている。前園は、奈良晒*1を業とする清須美道清*2が延宝年間(1673~~1681年)に造園したもので、池泉回遊式の庭園内に三秀亭・挺秀軒・清秀庵などがある。東側...

石上神宮 ( 奈良県 天理市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)・近鉄天理線天理駅から東へ約2km、布留山(ふるやま・標高266m)の北西麓の高台にある。境内は、深い社叢に包まれ、山の辺の道の散策の北の起点にもなっている。「古事記」*1によると、神武天皇は東征の折、熊野で危機に陥ったが、高倉下(たかくらじ。人の名)が建御雷神(武甕雷神。たけみかづちのかみ)に下...

写真提供:長岳寺
長岳寺 ( 奈良県 天理市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)柳本駅から東へ約1.5km。山の辺の道の途中、龍王山(標高585m)の山裾にあり、古い大きな山門を入ると参道がつづく。824(天長元)年、空海の開基と伝えられ、大和神社の神宮寺であったともいわれる。寺が盛んだったころは、愛染堂、御影堂などの堂宇のほか、僧坊が42を数えるほどの大寺であったが、たびたびの兵...

天理の街並み ( 奈良県 天理市 )
奈良盆地の東部にあり、1954(昭和29)年に丹波市町を中心に6カ町村が合併し、全国最初の宗教名を市名にした宗教都市である。市の中心をなす旧丹波市町は、京都・奈良から初瀬・伊賀・伊勢に至る街道沿いにあたり、かつては伊勢神宮参拝途中の旅篭町として栄えた。明治以降は天理教*1の本拠として知られ、現在、街には天理教教会本部神殿・教...

写真提供:パーソナル企画
山の辺の道 ( 奈良県 奈良市 / 奈良県 桜井市 / 奈良県 天理市 )
現在の桜井市金屋の海柘榴市*1に始まり、大神神社(三輪明神)、景行、崇神陵を経て、石上神宮から奈良の旧市街へ北上する、奈良時代以前からあったとされる古道。大和の「青垣」*2と称されてきた三輪山、龍王山、高円山、春日山など奈良盆地の東縁部をなす山並みの山麓を縫う約26km余りの道で、「古事記」*3や「日本書紀」*4にも記述がみら...

大峰山 ( 奈良県 天川村 )
紀伊半島の中央部、南北50kmにわたって標高1,000~1,900m級の峰が連なっているのが、大峰山脈である。大峰山は狭義では、大峰山脈北部の主峰である山上ヶ岳(標高1,719m)を指し、広義では稲村ヶ岳(同1,726m)・弥山(同1,895m)・八経ヶ岳(同1,915m)などが連なる大峰山脈全体をいう。山脈の北部は古生層、南部は中生層を基盤とした曲隆...

洞川温泉の街並み ( 奈良県 天川村 )
天川村は、蔵王権現を祀る大峯山寺がある大峰山(山上ヶ岳。標高1,719m)の麓にある。村の東北部、標高約820mにある洞川温泉は、大峰山から発し熊野川の源流ともなっている山上川のほとりに湧く。古来、大峰山は山岳信仰に神道や仏教などが習合した修験道の根本道場で、洞川はその登山基地として開けた。温泉を掘削したのは昭和に入ってから...

天河大辨財天社 ( 奈良県 天川村 )
近鉄吉野線下市口駅から南へ約26km、天(てん)ノ川の流れに近く、山を背に社殿がある。創建については確かなことは不詳だが、同社の縁起によれば、7世紀後半に現れた修験道の祖、役行者*1が感得した辨財天を弥山*2(標高1,895m 大峰山の峰のひとつ)に祀ったのが始まりだという。現在も弥山山頂には奥宮が祀られている。また、弘仁年間(81...

慈光院 ( 奈良県 大和郡山市 )
JR関西本線(大和路線)大和小泉駅から北へ約1.5km、南流する富雄川(とみおがわ)の西の小丘にある。1663(寛文3)年に、石州流茶道の祖である小泉藩主片桐貞昌*1が父の菩提を弔うため建立*2した。あられ石の参道を通り、楼門を越えると、茅葺農家風の書院が現われる。簡素な書院*3は1664(寛文4)年に建てられたもので、12畳の主室ほか数室...

写真提供:パーソナル企画
金剛山寺(矢田寺) ( 奈良県 大和郡山市 )
近鉄橿原線郡山駅から西へ約4km、矢田丘陵の中腹にあり、矢田寺の名で知られる。「矢田地蔵縁起」*1の詞書では673(天武天皇2)年、入唐して玄奘から「唯識」(法相宗の仏教思想)を学んだと言われる智通が勅願により開基したと伝え、十一面観音を本尊とした。平安期に入り、中興の祖・満米(まんまい)上人によって地蔵菩薩を本尊とし、「矢...

郡山城 ( 奈良県 大和郡山市 )
近鉄郡山駅の北にあり、犬伏(いぬぶせ)城とも呼ばれる。1580(天正8)年には筒井順慶*1が織田信長からこの地一円を安堵されたが、郡山城以外の城の破却を命じ「大和一国破城令」により筒井城から居城を郡山城に移し、城下を含め整備を図ることとなった。1585(天正13)年豊臣秀長*2が100万石をもって入封、社寺の礎石や石仏をも使い、大規...

長弓寺 ( 奈良県 生駒市 )
近鉄けいはんな線学研北生駒駅から南へ約1.4km、近鉄奈良線富雄駅から北へ約3.4kmのところにある。富雄川沿いの高山街道を北上した静かな山懐にある。創建には諸説*1あるが、寺伝によると、鳥見(とみ)郷の名族小野真弓長弓(おののまゆみたけゆみ)が聖武天皇に供して狩りをした際、世嗣長麻呂の流れ矢にあたって死去したため、その死を哀...

写真提供:パーソナル企画
寳山寺 ( 奈良県 生駒市 )
近鉄奈良線・けいはんな線生駒駅の駅前にある生駒ケーブル線鳥居前駅から5分、宝山寺駅下車。生駒山の東側中腹にあり、「生駒の聖天(しょうてん)さん」の名で親しまれている。役行者(えんのぎょうじゃ)および空海の修行場*1と伝えられ、古来から弥勒菩薩の浄土とも考えられていたこの地に1678(延宝6)年、宝山湛海*2が歓喜天*3を祀り、当...

大台ヶ原 ( 奈良県 上北山村 / 三重県 大台町 )
大峰山脈の東、奈良・三重を分ける台高(だいこう)山脈の主峰部を指し、大台ヶ原山とも呼ばれる日出ヶ岳(標高1,695m)、三津河落山(さんづこうちやま・標高1,654m)などに囲まれた山頂部は、古生層および中生層からなる隆起準平原*1の名残とされる広い台地状を呈し、周囲は急峻な懸崖となっている。とくに南西部は大蛇嵓(だいじゃぐら)...

谷瀬の吊り橋 ( 奈良県 十津川村 )
JR和歌山線五条駅から約42km。まず、丹生川沿いに遡り分水嶺を越え、天の川、さらに下流の十津川沿いに谷あいを進んだところにある上野地集落の北端から対岸の谷瀬集落に向け架かっている。両岸を結ぶ鉄線橋*1で、長さ297m、川面からの高さは54mもある。同時に渡れるのは約20人までとなっている。十津川村は吊り橋が多いことで知られ、40本以...

山田寺跡 ( 奈良県 桜井市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)・近鉄大阪線桜井駅から南へ約4.5km。641(舒明天皇13)年に蘇我倉山田石川麻呂*1が氏寺として造営をはじめた寺で、643(皇極天皇2)年には金堂が建立された。しかし、649(大化5)年に石川麻呂は反乱の疑いをかけられ自害したため、造営は中断した。その後疑いが晴れ、663(天智天皇2)年には堂塔の建立が再開さ...

写真提供:長谷寺
長谷寺 ( 奈良県 桜井市 )
近鉄大阪線長谷寺駅から長谷寺の門前まで北東へ約1.2km。初瀬山*1の山麓から中腹に大伽藍を構えている。真言宗豊山派の総本山で、西国三十三所観音霊場の第8番札所。ボタンや紅葉*2などの名所としても知られ「花の御寺」の異名をもつ。 境内には本堂*3を中心に五重塔、大講堂*4などの堂塔が建つ。初瀬山の中腹に位置する本堂へは、山麓の...

写真提供:大神神社
大神神社 ( 奈良県 桜井市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)三輪駅のすぐ北側に参道があり、東へ約300mほどで二の鳥居*1がある。大神神社は祭神の大物主大神*2(おおものぬしのおおかみ)が三輪山*3(標高467m)に鎮まるために、古来、本殿を設けずに直接、山に祈りを捧げるという原初的な信仰形態を遺している神社で、延喜式内の大社のなかでもっとも古い神社の一つとされ...

写真提供:パーソナル企画
談山神社 ( 奈良県 桜井市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)・近鉄大阪線桜井駅から南へ約8km。桜井市の南、峰々を重ねた多武峰*1の山中に十三重塔*2を中心に本殿*3や拝殿、権殿*4、総社本殿など大小さまざまの社殿が配置されている。一ノ鳥居から社殿下の摩尼輪塔*5まで1丁ごとに丁石が立ち、建物の多くが桧皮葺の屋根、朱に彩られ、春は約500本のサクラ、秋は約3,000本も...

写真提供:聖林寺(写真:松村芳治)
聖林寺 ( 奈良県 桜井市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)・近鉄大阪線桜井駅から南へ約2.5kmの多武峰を背にした高台にある。創建は定かではないが、寺伝では、藤原鎌足の長子定慧*1が開山したといわれる多武峯妙楽寺*2の別院として和銅年間(708~715年)に開創されたと伝えられている。もとは「遍照院」と称したが、享保年間(1716~1736年)に妙楽寺の僧子暁によって「...

写真提供:安倍文殊院
安倍文殊院 ( 奈良県 桜井市 )
JR桜井線(万葉まほろば線)・近鉄大阪線桜井駅から南へ約1.5kmのところにある。大化の改新に際し、中大兄皇子(天智天皇)を支え、その後も右大臣蘇我倉山田石川麻呂とともに左大臣として朝廷の中枢にいた阿倍倉梯麻呂*1が崇敬寺(そうきょうじ)と称し創建されたと伝えられる。創建時は、現在地より南西にあったとされ、現在はその地は安倍...

写真提供:パーソナル企画
三輪そうめん ( 奈良県 桜井市 )
奈良盆地の南東部、桜井市三輪地区を中心に製造されている手延べそうめんである「三輪そうめん」は、喉越しなめらかで舌ざわりがよく、コシがしっかりしており煮くずれしにくいのが特徴だとして、全国に知られている。 「三輪そうめん」は、三輪山(大神)信仰に結び付けられ、宝亀年間に神主狭井久佐の次男、穀主(たねぬし)が、この地...

南法華寺(壷阪寺) ( 奈良県 高取町 )
近鉄吉野線壺阪山駅から南東へ約4km、高取山(標高584m、高取城跡*1)の中腹にある。正しくは南法華寺だが、壷阪寺の名で知られる。西国三十三所第6番札所として眼病に霊験があるという十一面観音像を祀る。開創*2は不明な点が多いが、寺伝の「南法花寺古老伝」では、703(大宝3)年に元興寺の僧弁基によるものとされている。847(承知14)年...

馬見丘陵公園(馬見古墳群) ( 奈良県 広陵町 / 奈良県 河合町 / 奈良県 大和高田市 )
奈良盆地の西部、馬見丘陵*1とその周辺地に馬見古墳群がある。奈良県内では佐紀盾列(さきたたなみ)古墳群*2、大和・柳本古墳群*3と並ぶ大型古墳群で、4~5世紀に築造された古墳が多く、総数は250基を超える。古墳群は大和高田市の築山古墳を中心とする南群*4、広陵町の巣山古墳を中心とする中央群*5、河合町の大塚山古墳を中心とする北群*6...

写真提供:一般財団法人奈良県ビジターズビューロー
賀名生梅林 ( 奈良県 五條市 )
JR和歌山線五条駅から南へ丹生川に沿って山間地を入って約9km、賀名生皇居跡*1の向かい側の山の麓から中腹まで広がる約2万本が植栽されたウメ林。西ノ千本・奥ノ千本など吉野山のサクラになぞらえて名を付けた場所もある。この地はカキの生産地としても知られており、カキ畑も随所にみられ、急斜地ではあるが数多くの農家も散在している。ウ...

写真提供:榮山寺
榮山寺 ( 奈良県 五條市 )
JR和歌山線五条駅から東へ約2km、西流する吉野川のほとりの緑のなかにあり、境内には山門、室町時代に再建され重要文化財の薬師如来坐像*1が祀られている本堂(薬師堂)、その右手奥には国宝の八角円堂が建ち、コンクリート製の鐘楼には平安初期に造られた国宝の梵鐘*2が吊るされている。同寺の創建*3は719(養老3)年、藤原武智麻呂*4による...

五條市五條新町の町並み ( 奈良県 五條市 )
五條地方は、吉野川の右岸にある河岸段丘の上にあり、須恵、五條などの集落では古くから大和・紀伊・伊勢を結ぶ街道の要(かなめ)として物産の集積地として市などが開かれていた。江戸時代に入り、1608(慶長13)年に吉野川河畔寄りに五條二見藩が置かれて城下に二見の町場が生まれた。さらに須恵や五條と、二見とをつなぐ形で新町の町場が...

写真提供:吉野山観光協会
吉野山のサクラ ( 奈良県 吉野町 )
奈良県南部に位置する吉野山は、ひとつの峰を指すものではなく、大峰山脈北端から吉野川南岸まで南北約8kmにわたって続く尾根をいう。一帯には金峯山寺をはじめ修験道に由来する社寺が集まっており、古くからサクラの名所としても知られる。現在は、山内の約50万m2に3万本以上ともいわれるサクラが植えられており、尾根から谷へと...

写真提供:パーソナル企画
吉野山寺社群 ( 奈良県 吉野町 )
奈良県南部、大峰山脈の北端、南北に約8km続く尾根が吉野山である。一帯には、修験道の根本道場である金峯山寺を中心に多くの社寺がある。 吉野山から山上ヶ岳(大峰山)までの大峰山脈北部の山々は、古くから金峯山(きんぷせん)と呼ばれ、神聖視されていた。伝承によれば、7世紀後半、役行者*1が金峯山で修行中に金剛蔵王権現を感得、...

写真提供:パーソナル企画
吉野葛 ( 奈良県 宇陀市 / 奈良県 吉野町 / 奈良県 御所市 )
多年草マメ科のクズは秋の七草のひとつで、花は可憐優雅なお茶花として親しまれ、また煎じたものは薬草として利用され、茎は強い繊維質であることから葛布が作られていた。葛の根*1はデンプン質が豊富で、このデンプンを精製したものが葛粉であり、料理や菓子の材料に使われる。吉野地方では極寒期に地下水のみで繰り返し精製する「吉野晒(...

當麻寺 ( 奈良県 葛城市 )
近鉄南大阪線当麻寺駅から西へ約1km、雄岳(標高517m)と雌岳(標高474m)からなる二上山*1やその東南麓の丸子山*2(標高212m)を背に、堂塔が建ち並ぶ。仁王門(東大門)から入ると、樹間越しに、左手前から奈良時代に造営された東塔、西塔の2基の三重塔*3が垣間見え、正面には国宝の梵鐘*4が吊るされている鐘楼がある。続いて中之坊*5をは...

写真提供:PIXTA
藤原宮跡 ( 奈良県 橿原市 )
近鉄大阪線大和八木駅から東南へ約2.4km、JR桜井線(万葉まほろば線)畝傍駅から東南へ約1.8kmのところに藤原京の中心であった藤原宮跡がある。大和三山に囲まれた地域に694(持統天皇8)年から710(和銅3)年に平城京へ遷都されるまでの16年間、持統・文武・元明*1の3代の天皇が営んだ宮跡。藤原宮は藤原京のほぼ中心に位置し、その規模は、...

写真提供:橿原神宮
橿原神宮 ( 奈良県 橿原市 )
近鉄橿原神宮前駅中央口から北西に拝殿まで約1km。畝傍山(うねびやま)の東南麓に約53万m2の広大な神域を有する。本殿・内拝殿・外拝殿など、のびやかで豪壮な社殿が深閑とした森に包まれて建つ。第一代天皇である神武天皇はこの地に橿原宮*1を造営し、辛酉年正月に即位したと「日本書紀」に記されている。その即位の地に、1890...

写真提供:パーソナル企画
今井町の街並み ( 奈良県 橿原市 )
近鉄橿原線八木西口駅から南西へ200~1,000mほどのところに広がる古い街並み。東西約600m、南北約310m、面積にして約17.4万m2が国の重要伝統的建造物群保存地区に選ばれている。地区内には約500件の伝統的建造物があり、9件*1は国の重要文化財に指定されている。 今井町は、古くは興福寺一乗院の荘園であったが、15世紀後半に...

写真提供:パーソナル企画
大和三山 ( 奈良県 橿原市 )
香具山(かぐやま。天香久山とも)・耳成山(みみなしやま)・畝傍山(うねびやま)の三山をいう。標高約140~200mの低い山で、奈良盆地の南部に三角形を作るように並び、そのほぼ中心に藤原宮跡が位置する。奈良盆地の各所から眺められ、緑したたる叙情的な印象が、万葉集*1のよい題材に選ばれてきた。「続日本紀」によると、708(和銅元)...

写真提供:パーソナル企画
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 ( 奈良県 橿原市 )
近鉄橿原線畝傍御陵前駅から南西へ約300mのところにある。藤ノ木古墳*1や唐古・鍵遺跡*2をはじめ、橿原考古学研究所が発掘調査した奈良県内の遺跡*3から出土した考古資料を中心に約3,700点を展示。資料は旧石器時代から室町時代までにわたり、日本の歴史を目でたどることができる。この常設展のほか、春と秋には特別展、夏には主に前年度に...

写真提供:パーソナル企画
室生寺 ( 奈良県 宇陀市 )
近鉄大阪線室生口大野駅から南へ約6.5km、室生川の上流の山間にある。室生川にかかった朱塗りの太鼓橋を渡り、「女人高野室生寺」の石柱が立つ門前を右折して進めば、左手に寳物殿*1が見え仁王門となる。これをくぐり参道を直進し左に折れ、鎧坂の石段を登れば弥勒堂*2と金堂(国宝)*3が並び、一段上がると伽藍の中心となる国宝の本堂(灌頂堂...

宇太水分神社 ( 奈良県 宇陀市 )
近鉄大阪線榛原駅から南へ約7.5km、芳野川(ほうのがわ)の河畔から参道がつづき、緑豊かな社叢に包まれるように建つのが宇太水分神社。延喜式の式内社の大和四水分社*1の一つとされ、水源を象徴し、水を分配する水神・天之水分神と、速秋津彦命、国之水分神の3柱を祀っている。創建は不詳だが、崇神天皇の勅命によって祀られたとも言い伝え...

写真提供:パーソナル企画
宇陀市松山の町並み ( 奈良県 宇陀市 )
宇陀市松山は、近鉄大阪線榛原駅から南へ約7km、奈良盆地の南東、宇陀山地を流れる宇陀川流域に発達した町で、古くは柿本人麿呂*1の歌にも詠まれた宮廷の狩場、阿騎野(あきの)の地にあたる。戦国時代に「宇陀三将」と称された秋山氏*2がここを拠点として城砦を構えたが、のちに豊臣家の支配下になり、さらに江戸時代に入って1615(元和元)...

写真提供:パーソナル企画
森野旧薬園 ( 奈良県 宇陀市 )
近鉄大阪線榛原駅から南へ約7km、旧街道に面して「元祖吉野葛」の看板を掲げる森野吉野葛本舗の裏山に広がるのが森野旧薬園である。1729(享保14)年に幕府薬草御用植村政勝(左平次)*1が大和へ薬草の採取に赴いた折り、葛粉製造を生業とする森野家の11代目森野通貞(初代・藤助)*2がこれに随行した。森野通貞(藤助)はその功によって幕府か...

写真提供:一般財団法人奈良県ビジターズビューロー(写真:矢野建彦)
大峯山寺 ( 奈良県 天川村 )
紀伊半島の中央部、南北50kmにわたって標高1,000~1,900m級の峰が連なっている大峰山脈。その北部の主峰・山上ヶ岳(標高1,719m)の山頂に大峯山寺はある。修験道の根本道場であり、古来、多くの修験者や信者を迎えてきた。7世紀後半に役行者*1が金峯山(大峰山脈北端の吉野山から山上ヶ岳までの一帯)で修行中に金剛蔵王権現を感得、その御...

写真提供:パーソナル企画
金峯山寺 ( 奈良県 吉野町 )
金峯山寺は修験道の根本道場で、吉野山はこの寺を中心に発展してきた。伝承によれば、7世紀後半、役行者*1が金峯山(吉野山から山上ヶ岳〈大峰山〉にかけての山々)で修行中に金剛蔵王権現を感得、その姿を桜の木に刻んで、山上(山上ヶ岳)と山下(吉野山)に堂を建てて祀った。これが金峯山寺の始まりとされ、山上の蔵王堂が現在の大峯山寺...

写真提供:パーソナル企画
吉野水分神社 ( 奈良県 吉野町 )
吉野山の上千本にある古社。近鉄吉野駅前の千本口駅からロープウェイで3分の吉野山駅下車、そこから吉野山の尾根道を3kmほど上った所に位置する。水の分配を司る天之水分大神を主祭神とし、ほかに玉依姫命(神像の玉依姫命坐像*1は国宝)らを祀る。子守宮とも呼ばれ、安産・子授け・子どもの守護神として信仰されている。創建年代は定かでは...

如意輪寺 ( 奈良県 吉野町 )
近鉄吉野線吉野駅前の千本口駅からロープウェイに乗り、約3分で吉野山駅に着く。吉野山駅からは3kmほど。近鉄吉野駅からは、県道37号線で約4km。金峯山寺や吉水神社などがある尾根筋とは沢を挟み、北東方向の尾根筋の中腹にある。 創建は、寺伝によれば、延喜年間(901~923年)醍醐天皇が帰依していたという日蔵(道賢)*1を開基とし、古...

玉置神社 ( 奈良県 十津川村 )
奈良、和歌山、三重3県の県境近く、大峰山脈の南端に位置する標高1,076mの玉置山の山頂近くに鎮座している。創建は、社伝*1では紀元前37年の崇神天皇の時代と伝えているが不詳。ただ、古くより熊野から吉野に至る熊野・大峰修験の行場*2の一つとされ、平安時代には神仏混淆となり玉置三所権現と称し崇敬を集め、修験道の霊場*3として社殿な...

写真提供:丹生川上神社(中社)
丹生川上神社(中社) ( 奈良県 東吉野村 )
近鉄吉野線大和上市駅から東へ約21km(または近鉄大阪線榛原駅から南へ約21km)、吉野川の支流高見川沿いの谷あいを遡った、河岸に建つ。境内は、川に沿って細長く、杉の大木に守られるようにして一段高い所に拝殿、その奥に本殿、東殿・西殿などの社殿が並ぶ。本殿、東殿・西殿は江戸末期に造替したもの。殿内収蔵の平安時代後期~鎌倉時代...

竹林院群芳園 ( 奈良県 吉野町 )
近鉄吉野線吉野駅前の千本口駅からロープウェイに乗り、約3分の吉野山駅下車、そこから吉野山上の尾根道を約1.6km進んだところにある。寺伝によると、竹林院は聖徳太子が創建し、のちに空海が入峰の折に一宇を設け椿山寺としたと伝わる。記録に残されているものとしては、平安期の史書「扶桑略記」に「道賢(今名日藏*1)以去延喜十六(916)...

法輪寺 ( 奈良県 斑鳩町 )
JR関西本線(大和路線)法隆寺駅から北へ2.6km、法隆寺から北へ1.5kmほどのところにある。法琳寺あるいは三(御)井寺(みいのてら)とも称された。創建には2説が伝えられている。一つは、670(天智天皇9)年の斑鳩寺(法隆寺)焼失後、3人の高僧が合力して造寺したとする説*1。もう一つは622(推古天皇30)年に聖徳太子の長子、山背大兄王が...

あらぎ島 ( 和歌山県 有田川町 )
奇観の棚田として知られている蘭島(あらぎ島)は、紀伊半島の北西部に位置する和歌山県有田川町の東部にある。高野山系に水源をもつ有田川の蛇行と浸食によって形成された扇形の河岸段丘上、約23,000m2の土地に、54枚の水田が広がっている。水田では主にキヌムスメ、ヒトメボレといった品種が栽培されている。また、耕地が限られ...

根來寺 ( 和歌山県 岩出市 )
JR阪和線和泉砂川駅から北へ約5km、葛城連峰の南麓に広大な境内を有するのが根來寺である。新義真言宗の総本山で、大伝法院と称した。二方に山を負い、約119万m2の寺域の中に大伝法堂はじめ大塔(多宝塔)・大師堂・本坊・光明殿・行者堂・聖天堂などが立つ。本坊わき道からひときわ奥まったところには、深い緑におおわれて開祖覚...

琴ノ浦温山荘園 ( 和歌山県 海南市 )
関西国際空港から南へ約50km、和歌山市中心部から国道42号沿いに約10km南下した、黒江湾に臨むところにある。大阪の実業家である新田長次郎*1の別荘として大正初期から昭和初期にかけて造園されたもので、海沿いの自然の地形を利用した潮入式回遊庭園である。約46,000m2という個人庭園としては桁違いに広大な敷地を有する。園内...

丹生都比売神社 ( 和歌山県 かつらぎ町 )
丹生都比売神社は、JR和歌山線笠田駅より南東へ約10kmの山間にある。金剛峯寺と慈尊院を結ぶ町石道の中間地点に位置し、丹生都比売神社の参拝後に高野山へ登ることが慣習とされていた。 主祭神の丹生都比売大神は、天照大神の妹神で高野山の地主神であり、空海に伽藍の土地を譲り、高野山の総鎮守になったとされる。丹生都比売は、古来魔...

紀伊国分寺跡 ( 和歌山県 紀の川市 )
紀伊国分寺跡はJR和歌山線下井阪駅より北へ約850mに位置する。 紀伊国分寺は、聖武天皇が741(天平13)年に発した「国分寺建立の詔」により全国68か国に設置された僧寺の一つで、756(天平勝宝8)年には寺院としての形態を整えていたと考えられる。2町四方(約218m四方)の寺域を有し、塔や金堂、講堂などの伽藍が整備された。塔跡には...

粉河寺 ( 和歌山県 紀の川市 )
JR和歌山線粉河駅から北へ約1km、門前町を15分ほど歩いたところにある。奈良時代末、770(宝亀元)年の開創と伝えられ、中世には高野山・根来寺に次ぐ僧兵を抱え、堂宇550、寺領四万余石を有して隆盛を極めたという。1585(天正13)年、羽柴秀吉の紀州攻めにあって堂塔を焼失したが、後に江戸時代に紀州徳川家の援助を受けて再興した。 鮮...

写真提供:丹生官省符神社
丹生官省符神社 ( 和歌山県 九度山町 )
南海電鉄高野線九度山駅から西へ約1.9km、神社の創建と同時期に建立された慈尊院背後の石段を登った山の中腹、足下に紀ノ川を望む地にある。慈尊院の鎮守で、神仏混淆の時代には神社を合わせて慈尊院といった。 空海が行脚の途中で一人の猟師と出会い、猟師の従えていた2頭の犬が高野山に導いた。その猟師を地主神が猟師に姿を変えたもの...

奥之院 ( 和歌山県 高野町 )
高野山奥之院は、高野山の山上東端に位置し、弘法大師・空海の御廟と、その参道の入口である一の橋から東へ広がる一帯を指す。一の橋から廟前までの約2kmの参道には、杉や檜がうっそうと茂り、両側には20万基を超える墓石*1が並んでいる。大きいものは高さ10mにも達する江戸時代各大名の巨大な五輪塔で、ほかにも位牌、方柱、宝篋印塔、無縫...

高野山 ( 和歌山県 高野町 )
高野山は、紀伊山地の南端に位置する山岳地帯であり、標高は約900mに達する。和歌山市から東へ約50km、大阪市から南へ約80kmの山上盆地に広がる高野山には、南北約3km、東西約6kmの範囲に多くの寺院や修行場が点在しており、日本の仏教文化を象徴する場所の一つで、最も重要な聖地の一つとして知られている。行政区としては高野町に位置付け...

高野山の宿坊の精進料理 ( 和歌山県 高野町 )
仏教の「殺生を避ける」考えに基づいて作られる精進料理は、肉や魚などの「生臭(なまぐさ)」を使わない野菜中心の質素な料理のイメージだが、高野山の精進料理のルーツは「振舞料理」であり、塗の御膳にたくさんの品々が並び見た目にも豪華である。平安時代から皇族や大名の参詣をはじめ、全国から参拝に来る檀信徒に対して、ようこそお越...

金剛三昧院 ( 和歌山県 高野町 )
金剛三昧院は高野山金剛峯寺から徒歩10分、小田原通りから南へ入った閑寂な地にある。1211(建暦元)年に鎌倉幕府初代将軍・源頼朝公の菩提を弔うために、その妻で尼将軍としても名高い、鎌倉二位禅尼・北条政子が創建した。開山に日本臨済宗の開祖である、明庵栄西禅師を請じ入れ、もとは禅定院と称したが、源実朝の死を悼んで堂塔を興し、...

金剛峯寺 ( 和歌山県 高野町 )
和歌山市から東へ約50km、大阪市から南へ約80kmの山上盆地に広がる高野山のほぼ中央に位置するのが、3,600寺を有する高野山真言宗の総本山、金剛峯寺である。真言宗の宗祖空海・弘法大師が、ここに伽藍を建立して以来1200年あまり、幾度かの浮沈の波を乗り越えて法燈を守り、宗派を越えた霊場として今日に至っている。 高野山は「一山境内...

写真提供:慈尊院
慈尊院 ( 和歌山県 高野町 )
慈尊院は南海電鉄高野線九度山駅から西へ約1.5km、雨引山の北東麓、 紀ノ川沿いにある。高野山真言宗のお寺、女人高野 慈尊院は、816(弘仁7)年、 空海が高野山を開くのに際し山麓の寺務所として建立したもので、高野山表街道の入口にあたる。空海の母阿刀氏がわが子を慕ってやってきたが、当時高野山は女人禁制のため麓にあるこの政所に住...

壇上伽藍 ( 和歌山県 高野町 )
壇上伽藍は高野山のほぼ中央部に建ち並ぶ堂塔群で、奥之院と並ぶ高野山の聖地であり、真言密教修禅の場である。19棟の堂塔で構成され、広さは約5万5千m2にも及ぶ。高野山における壇上とは、大日如来が鎮座する壇、もしくは道場を意味する。伽藍とは仏塔を中心とした僧房などを配置した場所のことである。 壇上伽藍の歴史は古く...

白良浜海岸 ( 和歌山県 白浜町 )
白良浜海岸はJR紀勢本線白浜駅より西へ約5km、複雑に入り組んだ白浜半島の西にくぼむ鉛山湾に面し、南紀では珍しくゆるやかな弧を描く砂浜である。延長約620mに渡る浜は波などによって浸食された珪砂砂岩(変質水成岩)で、石英を90%以上含有しておりまぶしいほどに真白い。昭和後期からの浜周辺の開発により浜がやせてきており、防砂ネット...
南紀白浜温泉 ( 和歌山県 白浜町 )
南紀白浜温泉は紀伊半島の南部、太平洋に面した和歌山県白浜町にある温泉郷である。JR紀勢本線の白浜駅、紀勢自動車道の南紀白浜インターチェンジ、南紀白浜空港がすべて至近にあり、アクセス抜群のロケーションとなっている。 白浜温泉の歴史は古く、『日本書紀』・『万葉集』・『続日本紀』などに「牟婁ノ湯」「武漏ノ湯」などと登場す...

南方熊楠記念館 ( 和歌山県 白浜町 )
南紀白浜空港から北西へ約5km、南紀白浜温泉の中心街からほど近い番所山にあるのが、日本の博物学者・生物学者・民俗学者として多くの研究実績を残した南方熊楠の記念館である。熊楠の没後、博物学の巨星を後世に伝え、学術振興と文化の進展を図ることを目的として1965(昭和40)年4月に開館。遺族から資料の寄贈を受け、南方熊楠の遺した業...

お燈祭り ( 和歌山県 新宮市 )
新宮市の熊野速玉大社の摂社、神倉神社で毎年2月6日に行われる古代以来の熊野山伏の伝統をもつ勇壮な火祭りである。 新宮節の一節に「お燈祭は男の祭り、山は火の滝下り竜」と歌われているように女人禁制の祭りで、精進潔斎した男性が、白装束に腰に荒縄をしめて、手にたいまつを持ち、石段を駆け下りる。その年に生まれた男子はおぶわれ...

神倉神社 ( 和歌山県 新宮市 )
神倉神社はJR紀勢本線新宮駅の南西約1km、熊野川の右岸の神倉山にある熊野速玉大社の摂社である。権現山の南側のおよそ100mの高さの断崖絶壁にある。源頼朝の寄進による参道の石段は538段あり、かなりの急勾配で登りにくい。山上の社殿裏にはゴトビキ岩*と呼ばれる磐座(いわくら)が鎮座し、神社のご神体となっている。ここは熊野三所大神...

熊野速玉大社 ( 和歌山県 新宮市 )
熊野速玉大社はJR紀伊本線新宮駅の北西約1km、熊野川が急に蛇行して熊野灘にそそぐ河口近くに鎮座する。主祭神の熊野速玉大神は伊邪那岐命(いざなぎのみこと)、熊野夫須美大神は伊邪那美神(いざなみのみこと)であり、夫婦神である。熊野三山の中で最も多い18柱の神々を祀っている。祭祀の起源は神倉神社のゴトビキ岩とする説があり、神倉...
新宮のめはりずし ( 和歌山県 新宮市 )
「めはりずし」は、和歌山県と三重県にまたがる熊野地方、および奈良県吉野郡を中心とした吉野地方の郷土料理である。千貼り寿司、大葉寿司、高菜寿司、芭蕉葉寿司と呼ぶ地域もある。漁業や林業が盛んな県南部地域で、忙しい漁や山仕事の合間に簡単に食べられるお弁当として広まった。塩で漬けた高菜で大きなおにぎりをくるんだもので、「め...

熊野古道 ( 和歌山県 田辺市 / 和歌山県 那智勝浦町 / 和歌山県 新宮市 )
紀伊山地は標高1,000~2,000m級の山脈が東西あるいは南北に走り、年間3,000mを超える豊かな雨水が深い森林を育む山岳地帯である。当地は自然神話の時代から神々が鎮まる特別な地域と考えられ、日本古来の自然崇拝に根差した山岳信仰や神道・伝来仏教・道教との融合によって形成された日本固有の神仏習合の霊場や山岳密教の霊場、修験道の霊場...
瀞峡 ( 和歌山県 新宮市 / 和歌山県 熊野市 )
新宮市から北西へ約30km、和歌山・三重・奈良の3県にまたがる新宮川の支流・北山川の峡谷の総称が瀞峡である。下流から下瀞・上瀞・奥瀞と分かれており、熊野川町玉置口から田戸までの1.2kmが下瀞で、瀞八丁と呼ばれる。さらにその上流、約2kmの間を上瀞、さらにその上流の小松から七色までの約28kmを奥瀞という。瀞峡で見られる岩石は過去の...
川湯温泉 ( 和歌山県 田辺市 )
川湯温泉は和歌山県田辺市本宮町、熊野本宮大社の南約3kmにある。熊野川の支流である大塔川の川底から湯が湧き、付近約200mの間の河原を掘れば、熱い湯が湧き出し、即席の露天風呂ができる。川の流量が減る冬季には、川をせき止めて作られる大きな露天風呂「仙人風呂」がオープンする。開湯期間中は多くの観光客が訪れ、夜間には満点の星の下...

熊野本宮大社 ( 和歌山県 田辺市 )
熊野本宮大社は南紀白浜空港から北東に約60km、JR紀伊本線新宮駅から北西に約35km、紀伊半島南部の山中に位置する。日本全国に4,700社あまり散在する熊野神社の総本宮で、熊野大権現として広く世に知られている。主祭神には、家津美御子大神(スサノオノミコト)*を祀っている。古くは熊野坐神社といい、延喜式神名帳には名神大社として記載...
湯の峰温泉 ( 和歌山県 田辺市 )
熊野本宮大社の南西2km、四村川の支流湯ノ谷川畔に白い湯けむりをあげているのが湯の峰温泉である。川湯温泉、渡瀬温泉と並ぶ、熊野本宮温泉郷の3つの温泉の1つで、十数軒の旅館・民宿が川沿いに立ち並ぶ温泉街となっている。 温泉の歴史は古く、4世紀頃に熊野の国造、大阿刀足尼によって発見されたとの言い伝えも残る。湯の峰の評判は、...
龍神温泉 ( 和歌山県 田辺市 )
龍神温泉は和歌山市から南東へ約90km、奈良県との県境にほど近い山中にある。護摩壇山・鉾尖岳・牛廻山などに囲まれ、日高川に面した標高500mの山峡に湧く温泉である。役行者により発見され、のち弘法大師が難陀龍王のお告げによって開湯したと伝えられるこの温泉は、紀州初代藩主・徳川頼宣が御殿を設けて浴室を整備し、地祖を免じたため発...

熊野三山 ( 和歌山県 田辺市 / 和歌山県 新宮市 / 和歌山県 那智勝浦町 )
熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社、那智山青岸渡寺を総称して熊野三山と呼ぶ。修験道の拠点である「吉野・大峰」と真言密教の根本道場の「高野山」が参詣道で結ばれ、この三霊場を取り巻く一帯が、ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」*1として2004年7月に登録された。紀伊半島南部一帯を指す「熊野」の語源は「こもりく...

熊野那智大社 ( 和歌山県 田辺市 )
熊野那智大社は、熊野速玉大社から南西に約22km、JR紀伊本線那智駅から北西に約8km、那智山の中腹、標高500mの地点にある。熊野速玉大社・熊野本宮大社とともに熊野三山の一社に数えられる当社は、463段の石段を登った先の社殿6棟に、熊野夫須美大神(イザナミノミコト)を主祭神として合計十三所の神々が祀られている。 那智の名が文献に...

青岸渡寺 ( 和歌山県 那智勝浦町 )
青岸渡寺はJR紀伊本線那智駅から北西に約9km、那智山の中腹に熊野那智大社と並ぶ天台宗の寺院であり、西国三十三所第一番の札所である。ユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」*1として2004年7月に登録された。 仁徳天皇のころ、インドから熊野に流れついた裸形上人が、那智の滝壷から見つけた観音像を安置して草堂を開いたのがそ...

那智の瀧(飛瀧神社) ( 和歌山県 那智勝浦町 )
那智山中には4本の渓流があり、その渓流に多くの滝がかかっている。一ノ滝・二ノ滝・三ノ滝・曽以ノ滝(文覚の滝)・陰陽ノ滝・松尾ノ滝など合計48本あり、一般的に那智滝と呼ばれるのはその中でも最も高さのある一ノ滝である。一ノ滝の滝口は3本に分かれているが、石英粗面岩の一枚岩壁の上を1本になって落下している。瀑下には飛瀧神社があ...

紀の川 ( 和歌山県 橋本市 / 和歌山県 紀の川市 )
紀の川は日本有数の最多雨地帯・奈良県大台ヶ原に源を発し、奈良と和歌山の二県を貫いて紀伊水道に注ぐ全長136km、流域面積1,750km2の一級河川である。奈良県では吉野川と呼ばれ親しまれている。和歌山県に入ってからの紀の川は、和泉山脈の南側をほぼ一直線に西流するが、橋本市から紀の川市東部付近では河岸段丘を形成している...

写真提供:広川町
広村堤防 ( 和歌山県 広川町 )
JR紀勢本線湯浅駅より南西へ約1km。湯浅広港に向かって並行に南にのびる内外2重の防波堤である。海に向かって前方の石垣は、室町時代に畠山氏*1が築いたものである。後方の土手は、濱口梧陵*2が私財を投じて1855(安政2)年に着工、延べ5万6700余人の労力と4年間の歳月を費やして築いた高さ5m、根幅20m、延長600m余の大防波堤である。1938...
南部梅林 ( 和歌山県 みなべ町 )
南部梅林は、南紀白浜空港から北に約20km、JR紀勢本線から北東へ約3km、南部川の川岸段丘4kmにわたって広がる梅の里である。晩稲(おしね)地区の香雲丘(こううんきゅう)に梅が植えられており、日本有数のスケールを誇る。梅干しの生産で日本一の規模を誇るみなべ町の梅林は基本的に果実採取のための産業用の農林であり本来は観光目的では...
煙樹ヶ浜 ( 和歌山県 美浜町 )
煙樹ヶ浜はJR紀勢本線御坊駅から南西へ約5km、本ノ脇から日高川の河口までつづく松林の美しい海岸である。クロマツ原と呼ばれる松林の幅は広いところで約500m、全長約4.5kmにおよび、近畿最大の規模となっている。この松林は今から約400年前、藩主徳川頼宣が防潮林として植林したもので、御留山として伐採することを禁じたため残ったといわれ...

写真提供:由良町観光協会
白崎海岸 ( 和歌山県 由良町 )
JR紀勢本線紀伊由良駅から西へ約7.5km、紀伊水道に面した半島の先に位置する。白崎海岸はその名の通り、岬全体が白い石灰岩でできている。白亜の巨大な石灰岩の岬と、真っ青な海のコントラストが異国情緒あふれる景観を呈し、「日本のエーゲ海」とも称される。古生代後半、約2億5000万年前のペルム紀にできたものだといわれており、今でもフ...
岩橋千塚古墳群 ( 和歌山県 和歌山市 )
和歌山市の中央から東へ約5km。岩橋山塊の前山地区を中心に、山塊全体に分布する古墳群である。古墳の総数は900基を超え、1952(昭和27)年に国の特別史跡に指定されている。史跡指定地内には500基ほどの古墳が所在する。4世紀末から7世紀にかけて造られた群集墳として全国有数の規模を誇る。古墳の築造時期は古墳時代中期から後期で、その中...
紀州東照宮 ( 和歌山県 和歌山市 )
紀州東照宮はJR紀伊本線紀三井寺駅より西へ約2km、和歌の浦の北部、天神山の林の中にある。祭神は徳川家康とその10男で紀州徳川家初代藩主の徳川頼宣である。1621(元和7)年に頼宣が家康を祭るために建てたもので、関西日光とも呼ばれ、「権現さん」の名でも親しまれている。参道両側には石灯篭が並び、侍坂と呼ぶ108段の急な石段を登り楼門...
紀三井寺 ( 和歌山県 和歌山市 )
紀三井寺は紀勢本線紀三井寺駅の南方約600m、名草山の中腹にある。正式名称は紀三井山金剛宝寺護国院(きみいさんこんごうほうじごこくいん)という。通称紀三井寺と呼ばれるのは、寺の周囲に吉祥水・楊柳水・清浄水の3つの井戸があるので三井寺の名が生まれ、近江の三井寺と区別するため紀の字をつけたとされる。 開基は770(宝亀元)年...
友ヶ島 ( 和歌山県 和歌山市 )
紀伊半島と淡路島のほぼ中間地点、和歌山市北西の紀淡海峡に浮かぶ4つの無人島、沖ノ島、地ノ島、虎島、神島を総称して「友ヶ島」と呼ぶ。 江戸期までは、修験道の山伏修行の場とされ、ほかに立ち入る者はほとんどいなかった。しかし黒船来航の頃から友ヶ島は大阪湾を守る要衝とされ、1888(明治21)年に陸軍用地となり、第2次世界大戦中...
日前神宮・國懸神宮 ( 和歌山県 和歌山市 )
JR和歌山駅から南東へ約1.5km、和歌山電鐵貴志川線日前宮駅の北100mにある。同一の境内に日前神宮・國懸神宮の2つの神社がある二社一体の大社で、総称して日前宮(にちぜんぐう)あるいは名草宮とも呼ばれる。御神体は日像鏡(ひがたのかがみ)と日矛鏡(ひぼこのかがみ)で、天孫降臨の際、三種の神器とともにそえられ、神武天皇東征の後、...
養翠園 ( 和歌山県 和歌山市 )
養翠園は和歌山市駅から南へ約6km、水軒浜の南端にあり大浦湾に臨む。入江を取り入れ、海水を引き入れた大小の池を中心に老松をめぐらした池泉回遊式庭園である。紀州藩10代藩主徳川治宝が1818(文政元)年から8年かけて造営した大名庭園で、敷地は33,000m2にも及び、その半分が汐入の池が占めるのが大きな特徴である。 この池...
和歌浦天満宮 ( 和歌山県 和歌山市 )
和歌浦天満宮はJR紀勢本線紀三井寺駅から西へ約2.5km、紀州東照宮の西隣、標高約93mの天神山の中腹にある。学問の神様・菅原道真を祀り、和歌浦一円の氏神としても尊崇されている。 菅原道真が大宰府に左遷されるときに和歌浦に船を停泊させたと言われ、康保年間(964~968年)に参議橘直幹が大宰府からの帰途にこの地に立ち寄り社殿を建...
和歌山城 ( 和歌山県 和歌山市 )
和歌山城は関西国際空港から南方に約24km、和歌山駅から西方に約2km、和歌山市中央部の丘に位置する。海上から見ると丘の稜線が、虎が伏せたように見えることから、虎伏山竹垣城の別名をもつ。 1585(天正13)年、紀州を平定した豊臣秀吉が弟の秀長に命じ、藤堂高虎や羽田正親一庵法印が普請奉行となり築城した。その後、秀長は郡山城(奈...

鞆淵八幡神社 ( 和歌山県 紀の川市 )
JR和歌山線笠田駅から南へ約13km、真国川(鞆淵川)北岸の幽邃の地にある。御祭神は応神天皇・仲哀天皇・比売大神。創建は定かでないが、平安時代の1008(寛弘5)年には、すでに京都の石清水八幡宮の領地であり、鞆淵荘16ヶ村の産土神でもあった。平安時代後期に制作された現存する日本最古のもので国宝に指定されている神輿(しんよ)は、鎌...

写真提供:鳥取県
大山 ( 鳥取県 大山町 )
大山(だいせん)は鳥取県米子市の東約10kmにある標高1,729mの山で、中国地方の最高峰である。鳥取県西部の旧国名を付けて伯耆大山(ほうきだいせん)と呼ばれる他、富士山に似た山容から伯耆富士や出雲富士とも呼ばれる。日本百名山に選定されている。 大山へのアクセスはバス・車が基本となる。山陰側の観光拠点である大山寺集落と桝水...

鳥取砂丘 ( 鳥取県 鳥取市 )
鳥取砂丘は鳥取駅の北側約8~9kmの日本海に面した位置にあり、鳥取市白兎海岸から福部町岩戸までの東西16kmに広がる海岸砂丘である。猿ヶ森砂丘(青森県下北郡)に次ぐ規模を誇り、国内で観光することができる砂丘景観としては日本最大級である。1955年(昭和30年)に国の天然記念物に指定されている。 現砂丘は千代(せんだい)川の流砂...

写真提供:鳥取県
弓ヶ浜 ( 鳥取県 米子市 / 鳥取県 境港市 )
弓ヶ浜半島は鳥取県西端部に位置し、美保湾と中海を分ける全長約17km、幅約4kmの半島である。この半島の美保湾に面した海岸は、境水道から日野川河口までの全長20km、幅4kmに及ぶ美しい弧を描いた砂浜となっており、弓ヶ浜*と呼ばれている。 砂浜には樹齢35~80年の美しい松原と白い砂浜が10km以上続いている。この美しい砂浜の成因は、...
浦富海岸 ( 鳥取県 岩美町 )
浦富海岸(うらどめかいがん)は鳥取県岩美郡岩美町に位置するリアス海岸である。鳥取砂丘の東側5~20kmにあり、その範囲は東端の陸上岬(くがみみさき)から西端の駟馳山(しちやま)までの間である。浦富海岸は海食・風食作用を受けた花崗岩の断崖・洞門・奇岩が点在しており、海上にも大小の島・岩が点在するため、山陰の松島と呼ばれてい...
妻木晩田遺跡 ( 鳥取県 大山町 )
妻木晩田(むきばんだ)遺跡は、鳥取県大山町(だいせんちょう)と米子市の丘陵上にある弥生時代の集落遺跡である。1999年に国の史跡に指定されている。遺跡面積は約1.7km2で、竪穴住居跡約460棟、掘建柱建物跡約510棟、墳墓(四隅突出型墳丘墓含む)39基、環壕等が見つかっている。 現在は、「鳥取県立むきばんだ史跡公園」とし...
三徳山三佛寺 ( 鳥取県 三朝町 )
三徳山三佛寺(みとくさんさんぶつじ)は、鳥取県東伯郡三朝町の三徳山にある天台宗の仏教寺院。三徳川の渓谷に沿った樹林の中を、三朝温泉からバス15分、倉吉駅からバス40分で到達する。 760(慶雲3)年に役行者*が開山したとされる。849(嘉祥2)年、慈覚大師円仁により阿弥陀・釈迦・大日の三つの仏が安置されたことから三佛寺と呼ば...
写真提供:鳥取県
大山寺 ( 鳥取県 大山町 )
大山寺は鳥取県西伯郡大山町、伯耆大山の北西斜面にある天台宗別格本山の寺であり、高野山金剛寺・比叡山延暦寺と並ぶ著名な山岳寺院である。米子道米子ICより県道24号線(大山観光道路)経由、大山寺集落・ナショナルパークセンター駐車場まで約15分。ここは博労座と呼ばれ、昭和初期まで牛馬市が立っていた歴史がある。ここから大山寺参道...
一ノ宮倭文神社 ( 鳥取県 湯梨浜町 )
一ノ宮倭文(しとり)神社は湯梨浜町の東郷湖の東岸、御冠山(みかんむりやま)に鎮座する神社であり、JR山陰本線・松崎駅から車で10分に位置している。倭文(しとり)は「しつおり(倭文織)」という古代の織物の一種のことで、社伝によれば、この織物の産地であったこの地方にちなんで機織りの神である建葉槌命(たけはづちのみこと)を祀...

写真提供:観音院
観音院 ( 鳥取県 上町 )
補陀洛山慈眼寺観音院(ふだらくさんじげんじかんのんいん)は、多くの社寺が集積している鳥取市の北東丘陵地にある天台宗の寺である。JR鳥取駅から東に1.6kmに位置する。境内にある日本庭園が江戸時代初期を代表する名園、観音院庭園として知られている。観音院は1632(寛永9)年の池田光仲の国替えに伴い雲京山観音寺として栗谷に建立され...

写真提供:鳥取市教育委員会
鳥取城 ( 鳥取県 鳥取市 )
鳥取城跡は鳥取市内、標高 263m の久松山(きゅうしょうざん)にあり、鳥取市のランドマークとしてその山容と石垣を市内各所から仰ぎ見ることができる。鳥取駅から 2.1km、久松公園としても親しまれている。 鳥取城は16世紀中頃、守護大名山名氏の同族争いの過程で、築城されたと言われている。その防御性の高さから「日本(ひのもと)に...

写真提供:岡 雄一
米子城 ( 鳥取県 米子市 )
米子城は、米子市の中心部、山陰本線米子駅から西1㎞に位置し、中海に張り出した標高約90mの湊山を中心に築かれた城である。その起源は15世紀後半に山名宗之が湊山に隣接する飯山に築いた砦とされる。近世城郭としての築城は戦国末期に吉川広家により開始され、関ケ原の合戦後に伯耆一国領主となった中村一忠が1602(慶長7)年に完成させた。...
写真提供:鳥取県
しゃんしゃん祭 ( 鳥取県 鳥取市 )
鳥取しゃんしゃん祭は、踊り手が傘を持って舞い歩く「しゃんしゃん傘踊り」を中心とするもので、8月のお盆に鳥取市の中心街で開催される。全国でお祭り時に住民が踊るのは盆踊りに代表される「手踊り」が基本で、「笠踊り」は山形の花笠、佐渡のおけさ笠など少数派である。まして柄の付いた傘を操る「傘踊り」はこのしゃんしゃん祭以外*には...

写真提供:とっとり花回廊
鳥取県立とっとり花回廊 ( 鳥取県 南部町 / 鳥取県 伯耆町 )
とっとり花回廊は鳥取県西伯郡南部町(一部、伯耆町)に位置するフラワーパークであり、山陰本線米子駅からシャトルバスで25分、米子自動車道溝口ICから10分の位置にある。総面積は0.5km2、花をテーマとした単一の園地*としては日本最大級である。花回廊という名前のとおり、全長1kmの屋根付きのサークル状の遊歩道があり、雨天...
三朝温泉 ( 鳥取県 三朝町 )
鳥取県東伯郡三朝町にある三朝(みささ)温泉は皆生(かいけ)温泉と並んで鳥取県を代表する温泉地である。三朝温泉への交通手段は、車では大阪から中国自動車道経由で3時間半、岡山駅から米子自動車道を経由して2時間弱、鉄道利用では山陰本線倉吉駅下車、10km、車で20分弱である。 開湯は1164(長寛2)年、源義朝の家来であった大久保左...
写真提供:鳥取県
大神山神社 ( 鳥取県 大山町 )
大神山神社は大国主命*を祀っており、本社は鳥取県米子市尾高、米子市街地から東に6kmほどの地にある。奥宮は鳥取県西伯郡大山町、伯耆大山の北西斜面の大山寺境内から奥宮参道を700m上がった標高900mの山麓にある。 大山は奈良時代に編纂された出雲国風土記には大神岳(おおかみのたけ)と記されているように古くから山岳信仰の対象で、...
鳥取東照宮 ( 鳥取県 鳥取市 )
鳥取東照宮は鳥取駅の北東に位置し、車で10分、路線バス15分で到達する。鳥取東照宮はその名前のとおり、日光東照宮の分霊である因幡東照宮として1650(慶安3)年に建立された。 鳥取藩を代々率いた池田家は徳川家康の信任が厚く、また、初代藩主池田光仲は家康の曾孫であったことから分霊が許されたのである。造営には日光東照宮を手が...
写真提供:鳥取県
打吹玉川の町並み ( 鳥取県 倉吉市 )
倉吉市は鳥取県の中央部、鳥取市と米子市の中間に位置し、かつて伯耆国の経済・文化の中心地として栄えた小都市である。室町時代に伯耆国の守護となった山名氏により打吹城(うつぶきじょう)が築かれ、以降、毛利、南条、中村一忠の支配を受けて城下町として発展した。しかし、打吹城は1615(元和元)年の一国一城令により廃城となり、以降...

写真提供:桜江町商工会
千丈渓 ( 島根県 江津市 / 島根県 邑南町 )
島根県中央部、江の川の支流八戸(やと)川に合流する日和(ひわ)川上流、約5kmにわたる渓谷。 3,500~4,000万年前の古第三紀と呼ばれる時代に起こった激しい火山活動によって噴出し堆積した流紋岩やデイサイト等の火砕岩で構成されており、岩質は硬く、亀裂が多く発達している。この亀裂に沿って河川の洗堀作用が進み、陸地の隆起に伴う...

写真提供:西村愛
断魚渓 ( 島根県 邑南町 )
大田市の南約40km、中国山地にある於保知(おほち)盆地*、その北東部の山間に刻む渓谷。江の川支流の濁川(にごりかわ)に浸食されてむき出しになった流紋岩の高低差100mほどの崖が、国道261号に沿って展開する。 石英粗面岩の岩盤が渓谷いっぱいに露出し、流れは滝となり淵となって、嫁ガ淵(よめがふち)・一夜橋(いちやばし)・箕ノ...

写真提供:一般社団法人 浜田市観光協会
石見畳ヶ浦 ( 島根県 浜田市 )
JR山陰本線下府(しもこう)駅の北へ約2km、国分町唐鐘(とうがね)海岸にある。1872(明治5)年の浜田地震で隆起したといわれるもので、高さ20mの海食崖、約5万m2の千畳敷と呼ばれる隆起海床*が広がる。これは第三紀層の礫岩・砂岩・頁岩の互層で、中に貝の化石や鯨の骨を含んでいる。まるで畳を敷いたように見える小さな亀裂が...

写真提供:津和野町観光協会
津和野城跡 ( 島根県 津和野町 )
蕗城(ろじょう)、橐吾城(たくごじょう)、三本松城(さんぼんまつじょう)ともいい、町の西に迫る標高367mの城山の山頂一帯に築かれた典型的な山城である。1295(永仁3)年、初代領主吉見頼行が築城にかかり、約30年を費やして息子・頼直の代に完成した。その後、坂崎出羽守が近世城郭の大改修を行い、本丸北方に出丸(織部丸(おりべまる...

写真提供:津和野町観光協会
津和野の町並み ( 島根県 津和野町 )
島根県の西端、山陰の小京都と呼ばれる小さな城下町。津和野川に沿って細長く町なみが連なり、東に青野山・西に城山がそびえている。町の中心殿町付近には武家屋敷や白壁の旧家が昔日の姿そのままに立ち、道ばたの掘割には色とりどりの鯉が群れ遊んでいる。 かつてはツワブキの茂る野であったという津和野の歴史は、吉見頼行・頼直親子が...

写真提供:津和野町観光協会
津和野弥栄神社の鷺舞 ( 島根県 津和野町 )
大橋のすぐ西にある弥栄(やさか)神社の例祭の祇園祭に奉納される古典芸能神事。京都八坂神社の祇園祭の鷺舞が1542(天文11)年に吉見正頼によって、山口を経てこの地に移されたものである。一時、坂崎出羽守の時代に中断したが、1644(正保元)年に復活し、それ以来、古式そのままを今日に伝えている。一方、京都では途絶してしまい、近年...

太皷谷稲成神社 ( 島根県 津和野町 )
城山の北中腹にある。1773(安永2)年、亀井7代藩主矩貞(のりさだ)が城の鎮護と藩民の安穏を祈願するため、京都の伏見稲荷を勧請したもので、日本五代稲荷の一つ。西日本では九州の祐徳稲荷と並んで信仰が厚い。 参道にトンネルのごとく立ち並ぶ朱の鳥居や荘厳華麗な朱塗の社殿にその繁盛ぶりを見ることができる。境内にはこのほか参集...

写真提供:知夫里島観光協会
知夫赤壁 ( 島根県 知夫村 )
知夫里島の西海岸に続く約1kmの海食崖をいう。玄武岩質のマグマにより形成された、高さ50~200mの削り取られた雄大な断層崖。隆起による2段の波食海壇をなし、断層崖は凝灰岩の赤・黄、玄武岩の黒、粗面岩岩脈の白色がみごとなコントラストをみせ、特に鮮やかな赤色が紺碧の空と海に映える。 海上から眺めるのが普通だが、赤壁の北にある...

写真提供:大田市観光協会
三瓶山 ( 島根県 大田市 )
大田市街の南東約14km、出雲・石見の国境にそびえる鐘状火山群。最高峰は男(お)(親(おや))三瓶で1,126m、ほかに女(め)(母(はは))三瓶(953m)・子三瓶(961m)・孫三瓶(903m)などの6峰が、室の内*と呼ばれる火口を環状に囲んでいる。『出雲国風土記』*では国引きの柱となり、佐比売山(さひめやま)と記されているが、史上に...

写真提供:大田市観光協会
石見銀山遺跡 ( 島根県 大田市 )
大田市域の南西の山峡にある、近世から近代にかけて栄えた鉱山遺跡。石見銀山は1527(大永7)年に九州博多の豪商神屋寿禎(かみやじゅてい)によって発見された。以後、室町・戦国の両時代を通じて、銀山は大内・尼子(あまこ)・毛利・小笠原4氏の、激しい攻防にさらされることになった。この結果、1562(永禄5)年ついに銀山の守り山吹城(...

写真提供:物部神社
物部神社 ( 島根県 大田市 )
JR大田市駅から南へおよそ5km。平安時代の法令集「延喜式」に記載のある式内社で、古来より文武両道の神・鎮魂の神・勝運の神と知られ、石見国一の宮として崇敬されてきた。古代の大氏族物部(もののべ)氏*がこの地方を開拓の折、祖神を祭ったのが起こりと伝えられ、御祭神の宇摩志麻遅命(うましまじのみこと)は、古くの大豪族で大和朝廷...

写真提供:大田市観光協会
温泉津温泉 ( 島根県 大田市 )
JR温泉津駅の北、温泉津川に沿って細長く旅館が立ち並ぶ。1300年以上前に旅の僧侶が、湯気の立つ水たまりに浸かってひどい傷を癒やしている古狸を目にしたことから発見されたという説が広く知られている。 平安時代には京都までその存在が伝わり、14世紀以降には湯治客が大勢訪れるようになった。近くの温泉津港が、毛利氏支配の中世以降...

写真提供:大田市観光協会
大森の町並み ( 島根県 大田市 )
大森町は大田市域の南西の山峡にある。石見銀山が徳川幕府の天領となって以降、その繁栄により銀山柵内(さくのうち)の北側にあたる大森地区の建設へと発展し、支配の中心地も銀山地区から大森地区へと移っていった。奉行所が置かれ、石見銀山の行政と商業の中心地として町が整備された。 山間の狭い谷間に作られた町は、身分に関係なく...

写真提供:松江市
多古の七ッ穴 ( 島根県 松江市 )
島根半島の最北を占める多古鼻にある日本海の荒波によりつくられた海食洞。集塊岩と凝灰岩の互層からなる高さ50m、延長400mにわたる絶壁に、海食によってできた大小4つの洞窟がある。これらの洞窟の入口は高さ約10mほどで、計9個あり、洞内へ小舟を乗り入れることができる。海上から一度に見える穴が7つなので七ツ穴と呼ばれる。 多古鼻一...

写真提供:西村愛
月照寺 ( 島根県 松江市 )
松江城の西に位置し、松江松平家の初代藩主である松平直政が母月照院の冥福を祈って1664(寛文4)年に建立し、以後松平氏の菩提寺となった。境内には多数の燈篭を従えた歴代藩主の廟が並んでいる。特に、小林如泥(こばやしじょでい)作の松江藩7代藩主である不昧(ふまい)公の廟門をはじめ、すぐれた廟門建築が見られる。 不昧公は木工...

写真提供:しまね観光ナビ
熊野大社 ( 島根県 松江市 )
JR松江駅から南へ約10km、意宇(いう)川の左岸、山を背にして社殿が立つ。『出雲國風土記』733(天平5)年に熊野大社、『延喜式神名帳』927(延長5)年に熊野坐神社とあり、日本火出初神社(ひのもとひでぞめのやしろ)とも称され、古来、杵築大社(出雲大社)と並んで出雲の國の大社と遇された。 朝廷の尊崇が極めて篤く、851(仁壽元...

写真提供:西村愛
美保神社 ( 島根県 松江市 )
島根半島の東、美保関港を目の前にする山麓にある。創建は未詳だが、「出雲国風土記」(733(天平5)年)に記載のある古社。事代主神(ことしろぬしのかみ)の総本宮で、母神である三穂津姫命(みほつひめのみこと)をともに祀る。事代主神(ことしろぬしのかみ)は大国主命の第一子といい、えびす様の名で知られ、漁業及び海上安全の神とし...

写真提供:西村愛
松江城 ( 島根県 松江市 )
宍道湖の北、標高28mの亀田山にあり、別名千鳥城の名をもつ。関ヶ原の戦いののち、出雲・隠岐に封ぜられて富田城(とだじょう)に入った堀尾吉晴(ほりおよしはる)が、1611(慶長16)年に築城*したものである。現在も天守閣*と石垣を残している。 城跡は城山(じようざん)公園と呼ばれ、桜の名所となっており、二の丸跡には松江神社、...

写真提供:松江市
ホーランエンヤ ( 島根県 松江市 )
松江市内を流れる大橋川などを舞台にして10年ごとに行われる、松江城山公園内にある「城山稲荷神社」の式年神幸祭。 ホーランエンヤは「松江城山稲荷神社式年神幸祭」の通称で、神事で使われる櫂伝馬船(かいでんません)が櫂を漕ぐ時の掛け声から名づけられたとも、また「豊来栄弥」から生じたことばとも言われている。 1648(慶安元...

写真提供:玉造温泉旅館協同組合
玉造温泉 ( 島根県 松江市 )
JR山陰本線玉造温泉駅から車で約5分、宍道湖畔から2km弱の距離にある温泉街。低い丘陵の間を北流する玉湯川に沿って、旅館、土産物屋、足湯などが1kmほど並ぶ。 温泉の歴史は古く、今から約1,300年前、奈良時代に記された『出雲国風土記』に、「ひとたび濯(すす)げば すなわち形容端正(かたちきらきら)しく、再び沐(ゆあみ)すれ...

写真提供:日本庭園 由志園
大根島のボタン ( 島根県 松江市 )
大根島は多孔質の玄武岩を基盤とするアスピーテ型の火山島である。ゆるやかな斜面の大部分は畑であり、特産の雲州人参や牡丹の花が育てられている。牡丹は約300年前、全隆寺住職が遠州(静岡県)の秋葉山へ修行に訪れ、その際に持ち帰って境内に植えたのがはじまり。当時は薬用として使われていた。現在では改良が行われ、500種を超える品種...

写真提供:しまね観光ナビ
立久恵峡 ( 島根県 出雲市 )
島根・岡山の県境赤名峠に源を発して大社湾に注ぐ神戸川の上流にあり、電鉄出雲市駅からは約10km南に位置する。清流に沿って約1kmにわたり高さ100~200mの岩壁がそそり立つ。特に左岸は、神亀岩・烏帽子岩・ろうそく岩・屏風岩などの名で呼ばれる奇岩が連続する。これらの奇岩は集塊質安山岩が風化・水食されてできたもので、小さな谷が複雑...

写真提供:しまね観光ナビ
出雲大社 ( 島根県 出雲市 )
出雲平野の西北端、島根半島の脊稜山地を背にする地にある。 創建は、『古事記』や『日本書紀』によると、神代、天孫降臨に際し、大国主大神が国土を譲られたのを喜ばれた天照大神が、大国主大神のために広大な宮殿「天日隅宮(あめのひすみのみや)」を建てたのに始まるという。この折、祭祀を司ったのが天照大神の第2子天穂日命(あめのほ...

写真提供:西村愛
日御碕神社 ( 島根県 出雲市 )
島根半島の西部、小島・岩礁が散在し変化に富んだ海岸線が特徴的で、稲佐浜から日御碕へつづく日御碕海岸*にあり、傾斜地を利用して権現造の社殿が立つ。朱塗の楼門をくぐると、正面に下の宮と呼ばれる日沉宮(ひしずみのみや)、右手上に上の宮と呼ばれる神の宮が鎮座するが、古く下の宮は海岸の「清江の浜」の経島(ふみしま)に、上の宮...

写真提供:一畑薬師
一畑薬師(一畑寺) ( 島根県 出雲市 )
島根県を代表する臨済宗の寺で、一畑薬師信仰の総本山でもある。島根半島の中央、標高200mの山上に位置する。松江と出雲から車で約30分。西暦894(寛平6)年、漁夫与市が日本海中から薬師如来を得たところ、夢のお告げにより盲目の母親の目が開かれたため、仏像をこの地にまつったのが寺の始まりである。「目のやくし」として信仰を集める他...

写真提供:しまね観光ナビ
鰐淵寺 ( 島根県 出雲市 )
一畑電鉄雲州平田駅から西へ約7km、島根半島西側の北山山中にある。 594(推古2)年創建の天台宗の名刹。平安時代末期に修験道の霊地として全国に知られ、多数の堂塔を擁した。14世紀にはそれまで北院・南院に分かれていた寺内が和合・統一し、根本堂が創建された。 また、出雲大社の祭事において鰐淵寺僧が大般若経転読(だいはんにゃ...

写真提供:西村愛
稲佐の浜 ( 島根県 出雲市 )
出雲大社西方800mほどにある海岸で、かつては弁天島の前まで波が打ち寄せていたが、近年砂浜が広がり、弁天島と浜がつながった。岩上には鳥居と祠があり、豊玉毘古命(とよたまひこのみこと)が祀られている。国譲り神話、国引き神話の舞台である。 国譲り神話では、高天原から降った建御雷神(たけみかずちのかみ)が、この浜辺に剣を立...

写真提供:しまね観光ナビ
出雲大社大祭礼 ( 島根県 出雲市 )
「山陰無双之節会、國中第一之神事ナリ」と称えられるほど盛大な祭事であった「三月会(旧暦3月1日~3日間)」を引き継ぎ、出雲大社が官幣大社に定められたのを記念して、1886(明治19)年から開催されるようになったもので、5月13日を前夜祭とし、14日から16日の3日間に渡る儀式は大祭礼と呼ばれている。 14日は「勅祭日」と呼ばれ、天皇...

田儀櫻井家たたら製鉄遺跡 ( 島根県 出雲市 )
島根県中部、JR山陰本線田儀駅から車で10分の所にある。たたら*製鉄とは、土製の炉の中で木炭の燃料で砂鉄を溶かして鉄をつくる日本古来の製法。中国地方では6世紀から盛んに行われた。出雲、石見地方は、良質の砂鉄と炭になる森林資源が豊富なことから、幕末から明治初頭にかけて鉄生産量の9割を占めた。 江戸前期、奥出雲町にある可部...

写真提供:島根県立古代出雲歴史博物館
島根県立古代出雲歴史博物館 ( 島根県 出雲市 )
一畑電車の出雲大社前駅から徒歩7分、出雲大社のすぐ東隣に位置する。 2007(平成19)年3月に開館。1984(昭和59)年、荒神谷遺跡(こうじんだにいせき)*から358本の銅剣が、その後続けて銅矛16本、銅鐸6個が発見され、文化財の保存・展示・活用の方法が模索される中、「島根県古代文化活用委員会」の設置から18年をかけ、博物館建設が...

写真提供:益田市観光協会
裏匹見峡 ( 島根県 益田市 )
裏匹見峡は、JR山陰本線・山口線の益田駅から南東へ約25km、広島県廿日市市との境界近くにある峡谷。 この一帯では約9000万年前の中生代白亜紀に非常に大規模な火山活動が起き、流紋岩~デイサイト質の火砕流が噴出し、主に凝灰岩や溶結凝灰岩からなる匹見層群を形成。匹見川および支流の広見川の浸食によって形成された匹見峡は、西中国...

写真提供:西村愛
萬福寺 ( 島根県 益田市 )
JR益田駅の東約2km、益田川の北畔にある。もとは現在の中須町(なかずちょう)にあって平安時代に建立され、安福寺と号した七堂伽藍をかねそなえた天台宗の大寺であった。1026(万寿3)年5月に石見地方を襲った大津波で、堂塔がことごとく流失した。その後、1319(元応1)年、遊行4代呑海上人(どんかいしょうにん)が下向のおり、時宗の道場...

写真提供:益田市観光協会
医光寺 ( 島根県 益田市 )
JR益田駅の東約2.5kmに位置する臨済宗東福寺派の寺院だが、もとは崇観寺の塔頭であった。崇観寺の創建は1363(貞治2)年で、室町幕府の保護を受け、また益田氏*の菩提寺として隆盛をきわめた。しかし、戦国の争乱に巻き込まれ、衰退していくことになる。 雪舟*は崇観寺の第5代住職で、文明年間(1469~1486年)に、塔頭のひとつに池泉観...

写真提供:隠岐の島町観光協会
白島海岸 ( 島根県 隠岐の島町 )
隠岐の島町のある島後を含む隠岐諸島は、島根・鳥取の県境から北方約60kmに位置し、約180の島と4つの有人島からなる。有人4島は「島前3島」と呼ばれる西ノ島(西ノ島町)、中ノ島(海士町)、知夫里島(知夫村)と島後(隠岐の島町)を指す。島後は隠岐諸島最大の島で、周囲151km、面積242.82km2、面積の約80%を森林が占めている...

写真提供:しまね観光ナビ
隠岐牛突き ( 島根県 隠岐の島町 )
1221(承久3)年の承久の乱*に敗れて、隠岐・中ノ島(海士町)に配流となった後鳥羽上皇が、小牛が角を突き合わせる姿をみて喜んだことから、島前で始まった。その後、島後(隠岐の島町)にも伝わり、以来、娯楽として楽しまれてきた、現在では島後(隠岐の島町)のみで行われている。 牛突きは、島が誇る伝承であり、現在行われている主...

写真提供:水若酢神社
水若酢神社 ( 島根県 隠岐の島町 )
本土と島後島(隠岐の島町)の玄関口である西郷港から北西へ13km、車で25分の五箇地区にある。 延喜式神名帳に名神大社と記されている隠岐国一宮。祀られている水若酢命は、隠岐の国土開発と日本海鎮護をされた神様だと伝えられている。社伝によると創建は仁徳天皇(在位は5世紀前半ごろ)の時代と言われている。 1795(寛政7)年に再...

写真提供:しまね観光ナビ
屏風岩 ( 島根県 隠岐の島町 )
本土と島後(隠岐の島町)の玄関口である西郷港から北へ7km、車で中谷駐車場の登山口まで60分、そこから屏風岩展望所までは徒歩で25分。 島後島の北東部で、今から550万年ほど前に大規模な火砕流を噴出するような火山活動が起きた。その時、噴出したものはトカゲ岩*を中心にして、南北6km、東西4.3kmにおよぶ範囲に分布していて、葛尾(...

写真提供:西村愛
雲樹寺 ( 島根県 安来市 )
JR山陰本線安来駅から南へ約6km、伯太川の右岸近くにある。1322(元亨2)年、後醍醐天皇から「国済」、後村上天皇から「三光」の国師号を授けられた孤峰覚明*によって開かれた。 参道半ばにある四脚門は創建当初のものといわれ、切妻造、本瓦葺。その他の堂宇は江戸後期に焼失し、その後再建された。方丈裏の出雲風禅宗庭園はツツジ・サ...

写真提供:安来清水寺
清水寺 ( 島根県 安来市 )
JR山陰本線安来駅の南東、山腹に広大な境内をもつ。寺伝では、587(用明天皇2)年、尊隆上人が、瑞光を発する十一面観音をこの地に得たのに始まり、597(推古天皇5)年、堂宇が建立されたと伝わる。山上に瑞光が現れ、その光にちなみ山号を「瑞光山」とした。また水清く、聖なる湧水を湛えていたことから「清水寺」と名づけられた。出雲地方...

写真提供:足立美術館
足立美術館 ( 島根県 安来市 )
JR山陰本線安来駅より南西へ約8kmに所在し、1970(昭和45)年に郷土出身の実業家・足立全康*氏が収集した日本画や陶芸を中心とした美術館である。横山大観*をはじめ、竹内栖鳳、川合玉堂、上村松園、橋本関雪など近代から現代の日本画壇の巨匠たちの作品を所蔵している。開館50周年を記念し完成した「魯山人館」*では、常時120点の北大路...

矢掛の宿場町 ( 岡山県 矢掛町 )
県の南西部、小田川の自然堤防の上に道を通してできた集落で、旧山陽道*の宿場町として栄えた。関ケ原の戦いののち天領・備中松山藩領(池田家)・庭瀬藩領(松平家)など支配体制がめまぐるしく変化したが、1699(元禄12)年に庭瀬藩領板倉家2万石の所領となり、その後、同家が11代にわたって支配し、明治を迎えた。この間、矢掛には陣屋が...

写真提供:公益財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会
旧閑谷学校 ( 岡山県 備前市 )
岡山藩主池田光政*によって創建された庶民のための教育機関。光政は岡山城内に藩校「岡山学校」を設けるとともに、藩内各地に123か所の手習所(てならいじょ)を設け、藩士や庶民の子弟の教育に力を注いだ。 光政は池田家の菩提寺であった京都妙心寺護国院が焼失したのを機に、墓所を岡山に移すこととした。その候補地として、和気郡木谷...

備前焼の里 伊部の街並み ( 岡山県 備前市 )
岡山県南東端、備前市の伊部(いんべ)は、六古窯*のひとつ、備前焼*のまちである。備前焼は釉薬を使わず、千数百度の高温で1週間以上かけて焼き締めた焼き物で、現在も松割木を燃料に、昔ながらの登り窯で焼かれている。陶土には「ひよせ」と呼ばれる、田の底にある鉄分の多い粘土を、風雨にさらすなどして数年寝かしたものが使われている...

中山神社 ( 岡山県 津山市 )
JR津山駅から北へ約5kmにある、古くは『延喜式』、『今昔物語』などにもその名を記す美作国一ノ宮。主祭神の鏡作神(かがみつくりのかみ)は、三種の神器の一つ「八咫鏡」を造ったとされる。創建は707(慶雲4)年と伝えられ、もとの社殿は毛利・尼子氏の二度にわたる戦乱で焼失したが、1559(永禄2)年、尼子晴久が美作地方を平定した際に再...

津山城 ( 岡山県 津山市 )
JR津山駅の北約1km、市の中央部にあり、別名を鶴山城ともいう。織田信長の小姓で本能寺の変で最期を遂げた森 蘭丸の末弟、森 忠政が1604(慶長9)年に築城にかかり、約13年かけて1616(元和2)年に完成させた。森家4代約19万石、越前松平家9代約10万石の居城として、明治の廃藩置県まで続いた。城の南部を吉井川が東流し、その支流である宮川...

衆楽園(旧津山藩別邸庭園) ( 岡山県 津山市 )
JR津山駅の北2kmにある衆楽園は、津山藩2代藩主、森 長継(ながつぐ)が江戸時代初期の明暦年間(1655~1658年)*に築いた池泉回遊式の大名庭園である。藩の接待などに使われ、「御対面所」とも呼ばれていた。その後、森氏に代わって入封した松平氏に引き継がれ、幕末に至るまで、主として藩の別邸の庭園として使用された。1870(明治3)年...

津山市城東町並み ( 岡山県 津山市 )
津山の城下町は、津山城を築いた初代津山藩主森 忠政*1により、吉井川の左岸(北側)に出雲街道*2に沿って東西に細長く形成された。城の周辺に武家地、街道沿いに町人地、町の外縁部に社寺を配置している。城下の出雲街道には、約3kmの範囲に18カ所の鍵曲がり(かいまがり)*3が設けられており、軍事色の強い城下町であった。大きな戦禍に...

鬼ノ城 ( 岡山県 総社市 )
JR吉備線(桃太郎線)服部駅からタクシーで15~20分、吉備高原南縁の鬼城山(標高約400m)に築かれた古代山城。『日本書紀』などの歴史書にその名がみられず、築造の目的・時期については諸説あるが、天智天皇2(663)年の白村江の戦いにおける敗北を受けて、国土防衛のために西日本各地に作られた山城の一つとみる説が有力である。鬼ノ城の...

備中国分寺 ( 岡山県 総社市 )
JR吉備線(桃太郎線)・伯備線総社駅から東へ約5km。奈良時代、天平13(741)年の聖武天皇の詔(みことのり)により日本各地に建立された国分寺の一つ。中世に廃寺となり、天正年間(1573~92)に備中高松城主清水宗治(しみず・むねはる)の援助で再興されたという。その後再び衰微したが、江戸時代中期に清水山惣持院住職の増鉄上人が、上...

熊野神社 ( 岡山県 倉敷市 )
瀬戸中央自動車道水島ICから県道21号線を岡山方面に1kmほど、蟻峰山(ぎほうざん)の山裾にある、紀州の熊野権現を勧請したと伝わる古社。近くの五流尊滝院とは明治まで神仏混交で、修験者が奉仕してきた。社伝によれば、修験道の開祖、役小角(えんのおづぬ、役行者ともいう)* が699(文武天皇3)年、呪術で民衆を惑わすという科で伊豆に...

円通寺 ( 岡山県 倉敷市 )
JR新倉敷駅より約4km、倉敷市西部、玉島の小高い丘(白華山)にある曹洞宗の古刹。創建については不詳であるが、同寺の縁起では、奈良時代の僧、行基の開基と伝えられ、「星浦の観音」と呼ばれる霊場であったとされる。本尊は聖観音菩薩。その後、1698(元禄11)年に徳翁良高禅師により再興された。江戸時代後期に、漢詩人・歌人・書家として...

倉敷川畔の街並み ( 岡山県 倉敷市 )
第二次世界大戦の空襲を免れた倉敷には、江戸時代から昭和まで各時代の建物が残っている。JR倉敷駅から南に徒歩15分ほど、倉敷川畔と鶴形山を含む倉敷美観地区*は、国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている。江戸から明治にかけて運河として利用された倉敷川の川畔には、白壁の商家や土蔵が並び、川沿いの柳並木と調和して、しっ...

倉敷アイビースクエア ( 岡山県 倉敷市 )
1889年(明治22年)に建設された紡績工場跡を再開発し、1974(昭和49)年に開業した、ホテルと文化施設をあわせもつ複合観光施設。倉敷美観地区に隣接し、その名のとおり、蔦(アイビー)に覆われた赤レンガ造りの建物と、1,400m2にも及ぶ広大な中庭広場(スクエア)が印象的な、地域住民や観光客の憩いの場となっている。敷地内...

大原美術館 ( 岡山県 倉敷市 )
倉敷川沿い、美観地区の一画にある大原美術館は、1930(昭和5)年開館の西洋美術を中心とした私立美術館である。開館前年に亡くなった西洋画家の児島虎次郎*1を悼み、その支援者だった倉敷の実業家、大原孫三郎*2が設立した。大原家は地元屈指の大地主で、クラボウ(倉敷紡績株式会社)の創業家である。現在の高梁市成羽町出身の児島は、東...

児島ジーンズストリート ( 岡山県 倉敷市 )
県の南端、瀬戸大橋の本州側の起点である児島は繊維産業が盛んで、1965(昭和40)年に初めてジーンズの国産化に成功し「国産ジーンズ発祥の地」となった。JR本四備讃線(瀬戸大橋線)児島駅から徒歩15分ほどの「児島ジーンズストリート」には、地元ジーンズメーカーの直営ショップやデニム雑貨を扱う店が連なる。2009年頃から地元メーカーや児...

写真提供:瀬戸内市観光協会
黒島ヴィーナスロード ( 岡山県 瀬戸内市 )
岡山ブルーライン邑久ICから約15分、JR赤穂線西大寺駅または邑久駅からバスで約30分、岡山県南東部、瀬戸内市の牛窓は古くから西国航路の風待ち、潮待ちの港として栄え、『万葉集』や『山家集』などにも詠まれている。江戸時代には、参勤交代や朝鮮通信使の寄港地として繁栄した。近年では、温暖な気候と点在する島々の風景から、「日本のエ...

牛窓オリーブ園 ( 岡山県 瀬戸内市 )
県南東部、瀬戸内市牛窓町にある日本オリーブ株式会社の自社農園。JR赤穂線邑久駅から南東へ約10km、瀬戸内海を一望できる高台にある。約2,000本のオリーブが10万m2の敷地に栽培されている大規模農園である。1942(昭和17)年に地元の資産家の服部和一郎(はっとり・わいちろう)が阿弥陀山(166.5m)の松林を開墾し、小豆島の友...

写真提供:蒜山観光協会
蒜山高原 ( 岡山県 真庭市 )
蒜山高原は、岡山県最北部、蒜山三座(上蒜山、中蒜山、下蒜山)の南麓に広がる東西20km、南北10km、標高500~600mほどの盆地である。西日本屈指の高原リゾート地で、遊園地、観光牧場、ワイナリー、ハーブ園、乗馬施設など多彩な観光スポットが点在している。鉄道は通っていないが、米子自動車道のインターチェンジから近く、週末や観光シー...

写真提供:真庭市
神庭の滝 ( 岡山県 真庭市 )
中国勝山駅の北西約5km、旭川の支流で星山(1,030m)を源流とする神庭川水域にある。高さ110m、幅20mの中国地方随一のスケールを誇る名瀑で、一帯は国指定名勝(神庭瀑)、岡山県立自然公園に指定されている。 水量が豊富で迫力があり、ただ豪快なだけでなく、岩肌に白布を引いたように見える水しぶきが神秘的だ。滝の中央には黒い岩が突...

頼久寺の庭園 ( 岡山県 高梁市 )
頼久寺は備中松山城の城下町にある、臨済宗永源寺派に属する寺院。創建は明らかではないが、足利尊氏の命により1339(暦応2)年に備中安国寺として再興される以前から存在した古刹。その後、永正年間(1504〜1521年)に備中松山城主、上野頼久が伽藍を再興し寺領を与えたことから、頼久の死後、その名を加え、天柱山安国頼久禅寺と称した。通...

備中松山城 ( 岡山県 高梁市 )
高梁市街の北側、大松山・天神の丸・小松山・前山の4つの峰から成る臥牛山(480m)に築かれた山城。承久の乱(1221年)後に有漢郷(現・高梁市有漢町)の地頭となった秋葉重信が、1240(延応2・仁治元)年、最北峰の大松山(470m)に砦を築いたことに始まると伝わる。戦国時代には、山陰と山陽を結ぶ要地として激しい争奪戦が繰り返されるな...

吹屋の町並み ( 岡山県 高梁市 )
JR備中高梁駅から約25km、吉備高原西部、標高550mの山あいにある、銅山*と赤色顔料のベンガラ*の製造で栄えたまち。旧吹屋往来*に沿って、赤褐色の石州瓦とベンガラ格子に赤い土壁や白漆喰壁の町並みが続く。この町並みは、ベンガラの製造・販売で財を成した豪商たちが石州(現在の島根県)から宮大工を招き、江戸後期から明治にかけて形...

備中神楽 ( 岡山県 高梁市 / 岡山県 井原市 / 岡山県 矢掛町 / 岡山県 総社市 / 岡山県 倉敷市 )
約400年前から備中地方一円に伝承されている神楽。その起源は、荒神*を勧請し、その前で演じられる荒神神楽*にある。備中地方の荒神は土地をひらいた地神(産土神・うぶすながみ)としての性質が強く、凶作、疫病、災害などは荒神の祟りであると信じられており、荒神の鎮魂を願う神事として荒神神楽があった。旧来の荒神神楽は面をつけない...

奥津温泉 ( 岡山県 鏡野町 )
岡山県北部、鳥取県境の鏡野町にある、こぢんまりした静かな温泉地で、美作三湯*の一つに数えられる。吉井川に架かる奥津橋を中心に温泉街が形成されており、数件の風情ある老舗旅館と素朴な民宿が並ぶ。また、同じく吉井川沿いの大釣、般若寺、川西などの温泉を含めて奥津温泉と呼ぶこともある。温泉の歴史は古く、江戸時代には津山藩が専...

写真提供:誕生寺
誕生寺 ( 岡山県 久米南町 )
JR津山線誕生寺駅の北西700m、法然の生家漆間家の屋敷跡に建つ浄土宗の特別寺院で、山号を栃社(とちこそ)山という。1193(建久4)年、法力坊蓮生(ほうりきぼうれんせい)*が創建した。法然の父、漆間時国(うるま・ときくに)は久米の押領使(おうりょうし)*で、法然が9歳のとき、預所(あずかりどころ)*の明石定明(あかし・さだ...

写真提供:吉備中央町
加茂大祭 ( 岡山県 吉備中央町 )
岡山自動車道賀陽ICから北東へ11kmにある加茂総社宮は、宇甘川のほとりに鎮座する。境内には樹齢500~600年のスギ、ヒノキ、イチョウの巨木がそびえ、歴史を感じさせる神社である。本殿は江戸時代中期のものといわれ、大祭のとき、神輿を安置する長床を左右に配している。 毎年10月第3日曜日に行われる大祭は、旧加茂川町(現、吉備中央町...

北木島の石材 ( 岡山県 笠岡市 )
岡山県西部の笠岡港から約26kmにある北木島*は、古くから良質の御影石の産地として知られる。江戸時代初期の大坂城修築の際には、大量の石垣石を送り出している。北木石は白色を主とした中粒の黒雲母花崗岩で、「中目」、「瀬戸白」、「瀬戸赤」、「サビ石」の4種類があり、「中目」が最も多い。断層により比較的大きな固まりとして島が形成...

写真提供:岡山市教育委員会
造山古墳 ( 岡山県 岡山市 )
岡山市北西部から総社市にかけての「吉備路」と呼ばれる一帯は、古代吉備王国時代の中心地だったと考えられており、畿内の大王墓に匹敵する巨大な古墳が多くある。なかでも、JR吉備(桃太郎)線 備中高松駅から南西へ約2.5kmのところにある造山古墳は、古墳時代中期(5世紀初頭)に築かれた全長約350m、県下最大、全国第4位の墳丘規模をもつ...

写真提供:吉備津神社
吉備津神社 ( 岡山県 岡山市 )
岡山市西部、吉備の中山*(標高175m)の西麓に鎮座する。当地を治めたとされる大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)*を主祭神とし、その一族の神々を祀っている。創建時期は不詳だが、927(延長5)年に撰進された延喜式神名帳では、すでに名神大社に列せられていた古社で、吉備国総鎮守として崇敬されてきた。7世紀後半頃、吉備国の三国...

写真提供:最上稲荷山妙教寺
最上稲荷 ( 岡山県 岡山市 )
羽柴(豊臣)秀吉の水攻めで有名な備中高松城址の北、龍王山にある日蓮宗の寺で、正式名称を最上稲荷山妙教寺という。明治の廃仏毀釈を逃れ、寺でありながら鳥居があり、神宮形式をあわせ持つ本殿(霊光殿)など神仏習合時代の形態を現在も残している。 縁起によれば、752(天平勝宝4)年、この地で修行していた報恩大師*に孝謙天皇の病...

岡山城 ( 岡山県 岡山市 )
岡山駅から路面電車の通る「桃太郎大通り」を東へ1.7km、岡山市内を流れる旭川西岸にあり、対岸には金沢の兼六園や水戸の偕楽園とならぶ名園とされる岡山後楽園がある。天守の黒く塗られた下見板張りの外観から、「烏城」(うじよう)、「金烏城」とも呼ばれる。かつて本丸には30の櫓と6の城門を誇っていたが、明治期の国有化と太平洋戦争下...

西川緑道公園 ( 岡山県 岡山市 )
岡山駅から路面電車の通る「桃太郎大通り」を東へ約500m、中心市街地を南北に流れる西川用水の両岸に、1974(昭和49)年から1983(昭和58)年にかけて整備された公園。桃太郎大通りから、旧国道2号線と交わる瓦橋までの1kmが「西川緑道公園中流」で、北に「西川緑道公園上流」(0.9km)、南に「枝川緑道公園」(0.5km)が整備され、総延長2.4...

写真提供:岡山後楽園
後楽園 ( 岡山県 岡山市 )
旭川をはさんで岡山城の対岸にあり、水戸の偕楽園、金沢の兼六園とともに日本の名園の一つとされる。岡山藩主池田綱政が家臣の津田永忠に命じて1687(貞享4)年に着工、1700(元禄13)年に一応の完成をみた。操山(みさおやま)をはじめとする東側の山を借景とした回遊式の明るく優美な庭園で、広い芝生や池、曲水、築山などが配されている。...

会陽(裸祭り) ( 岡山県 岡山市 )
JR赤穂線西大寺駅から徒歩10分、吉井川河畔にある西大寺観音院は、751(天保勝宝3)年に周防国玖珂庄(現、山口県岩国市玖珂町)に住む藤原皆足姫(ふじわらみなたるひめ)が、金岡郷(現、西大寺金岡)に小堂を建て観音像を安置したのが始まりと伝えられる。 会陽は、2月の第3土曜日22時に、西大寺観音院の本堂の御福窓から投下される2本...

写真提供:備前國一宮 吉備津彦神社
吉備津彦神社 ( 岡山県 岡山市 )
JR吉備線(桃太郎線)備前一宮駅からすぐ、岡山市西部、吉備の中山*(標高175m)の北東麓に鎮座する。祭神は当地を治めたとされる大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)*。 中世以後は、戦国大名の赤松氏や宇喜多氏からも尊ばれ、江戸時代になると岡山藩主池田氏の援助で社殿が再建・整備され、1697(元禄10)年には三間社流造・檜皮...

ままかり寿司 ( 岡山県 岡山市 )
「ままかり」とは、サッパという体長10~15cmほどのニシン科の魚を2枚におろして酢漬けにしたもので、「(自分の家のご飯を食べつくし)隣家にご飯(ママ)を借りに行くほどおいしい」ことに由来する。「ままかりずし」は、「ままかり」を握りずしにした岡山県の郷土料理で、昔から家庭の味としてつくられてきた。地元では酢漬けにする前の鮮...

三段峡 ( 広島県 安芸太田町 / 広島県 北広島町 )
広島県の北西部、太田川の支流柴木(しばぎ)川と八幡川・横川(よこごう)川の流域、延長約16kmの石英斑岩・花崗岩の基盤が深く侵食されたことによって形成された長大な峡谷。100mある絶壁に囲まれた黒淵や、切り立った狭門をくぐる猿飛などがよく知られる。また、針葉樹と広葉樹との混合からなる原始林は多種多様な植物相をなし、往古の姿...
海上自衛隊第1術科学校(旧海軍兵学校) ( 広島県 江田島市 )
広島市街から南に約17km、呉市街から西に約6km、瀬戸内海に浮かぶ江田島(えだじま)に位置する。 海軍兵学校が東京の築地から移築されたのは1888(明治21)年で、太平洋戦争終戦まで多くの海軍士官を輩出した。終戦により1945(昭和20)年に57年の歴史に幕を閉じ、以後11年間は進駐軍が施設を接収し使用していた。1956(昭和31)年に日本...
向上寺 ( 広島県 尾道市 )
瀬戸内海に浮かび、尾道と今治を結ぶしまなみ海道が通る生口島の瀬戸田港北側に位置し、山腹の松林に囲まれた中に本堂・三重塔がある。室町時代に名僧 愚中周及*を迎えて開闢(かいびゃく)代、祖としたことに始まる。三重塔は1432(永享4)年の建立。高さ約19m、朱塗りの和様を基調とした唐様を取り入れた建築であり、その特徴は組物に入れ...
西國寺(西国寺) ( 広島県 尾道市 )
JR尾道駅から北東に約2km、愛宕山の山腹に大伽藍が広がる。行基による奈良時代中期の創建と伝えられる古刹で、真言宗醍醐派の大本山。1066(治歴2)年の本堂の炎上により本尊薬師如来も焼滅したが、1081(栄保元)年、白河天皇の勅命により再建され、巨大な伽藍が完成、末寺も百数十を数える大寺となった。伽藍の規模は正に西国一という意味...
浄土寺 ( 広島県 尾道市 )
JR尾道駅から約2km、尾道市街の東端に位置する。創建は古く、616(推古天皇24)年、聖徳太子の開基と伝える古刹。鎌倉時代の終わり、奈良の西大寺の僧、定證上人の発願により再興されるが、火災によりわずか四半世紀で伽藍を焼失。しかしながら、尾道の民衆によって火災の翌年には再建された。室町時代には、足利尊氏が九州平定の際に参詣し...

千光寺公園 ( 広島県 尾道市 )
千光寺公園*は、JR尾道駅から北東に約1km、標高144.2mの千光寺山の山頂から中腹にかけて広がる公園。園内には、千光寺を中心に、全長約63mの展望デッキが特徴の頂上展望台、安藤忠雄氏の設計による尾道市立美術館、林芙美子*をはじめとした尾道ゆかりの文人の作品を刻んだ文学碑が点在する「文学のこみち」などがある。眼下には瀬戸内の多...
平山郁夫美術館 ( 広島県 尾道市 )
尾道市市街から南西に約16km、瀬戸内海に浮かぶ生口島(いくちじま)にある瀬戸田港の西約1kmにある。日本画の巨匠 平山郁夫*が「私の原点は瀬戸内の風土である」と語る自身の故郷に1997(平成9)年開館。幼少期の絵日記帳から、生まれ育った瀬戸田の風俗を取材した初期の作品、日本画家としての転機となった「仏教伝来」(1959(昭和34)年...
江の川 ( 広島県 北広島町 / 広島県 安芸高田市 / 広島県 三次市 )
江の川は、広島・島根県境の阿佐山(標高1,218m)に源を発し、幾つもの小支川をあわせながら広島県側を流れ、中国山地を貫流し、島根県江津市で日本海に注ぐ。かつての江の川は平地を流れて日本海に注いでいたが、中国山地の隆起後も川が大地を掘り下げる力のほうが強く、そのままの流れを保ってきたため、中国山地を横切って流れるようにな...
呉港の旧海軍関連等施設 ( 広島県 呉市 )
1889(明治22)年に、海軍が呉鎮守府*を開庁した呉市は、日本一の海軍工廠*を擁する街として発展した。戦艦大和を建造した高い技術力を基に、戦後も産業の街として今に至る。海軍用地であった呉港を中心とする沿岸部には、当時の造船ドックや建物を利用した工場が建ち並ぶ工業地帯や、護衛艦・潜水艦を眺めることができる海上自衛隊の基地...

写真提供:帝釈峡観光協会
帝釈峡 ( 広島県 庄原市 / 広島県 神石高原町 )
広島県の北東部、庄原市と神石高原町にまたがる、全長18kmにおよぶ帝釈川の峡谷。石灰岩台地が帝釈川によって深く浸食されて形成された。高さ8mの穴をくぐり抜ける鬼の唐門、石筍や石柱など変化に富んだ構造をもつ白雲洞、隆起と浸食作用によってできた長さ90m・幅19m・高さ40mの日本を代表する大きさを誇る天然橋の雄橋(おんばし)など、石...
竹原の街並み ( 広島県 竹原市 )
竹原市は広島県中央部、瀬戸内海沿岸に位置する。市街東側、塩を積み出ししていた本川に沿って、古い町筋が延びる。江戸時代に製塩業で財をなした豪商の町であり、製塩業を基盤に、酒造業や問屋業などの多角経営を行い、賑わいを極めた。また、商いでの親交によって上方の学問や、漢詩や茶道などの文化・芸術に親しみ、多くの町人学者*を輩...
嚴島神社 ( 広島県 廿日市市 )
嚴島神社は原始林の深い緑を背後にし、入江の海のなかに木造建物が建ち並ぶ日本でも珍しい神社。広島市の中心部から直線距離で約15km南西に位置する厳島に鎮座する。厳島には、宮島口桟橋からフェリーでわたるのが一般的だが、広島市街から高速船も就航している。 厳島は瀬戸内海に浮かぶ島々のなかでも標高約530mとひときわ高い弥山を擁...
西条酒蔵通り ( 広島県 東広島市 )
JR山陽本線・西条駅の南側に位置する。西条盆地で酒造りがはじまったのは江戸時代と言われる。西条の米、気候、龍王山の伏流水を活かした酒造りは、1894(明治27)年に山陽鉄道が開通して西条駅が設置されたことを契機に、本格的な酒造業へと発展した。西条が酒都(しゅと)と呼ばれ、吟醸酒発祥の地となったのには、酒造りには向かないとさ...
太田川(下流) ( 広島県 廿日市市 / 広島県 安芸太田町 / 広島県 北広島町 / 広島県 安芸高田市 / 広島県 東広島市 )
太田川は広島県西部に位置し、廿日市市の冠山(標高1,339m)に源を発し、支流を集めて流下、広島市街地に入り太田川放水路と旧太田川に分流し、旧太田川はさらに京橋川、猿猴川、天満川、元安川に分流し、広島湾に注ぐ。全長は103km,流域面積は1,710km2。流域の支川・本川は樹枝状に流れるのが一般的だが、太田川は、支川は北東...
縮景園 ( 広島県 広島市 )
JR広島駅から西に約1km、京橋川の南側に位置する大名庭園。江戸時代初頭の1620(元和6)年に広島藩初代藩主・浅野長晟(ながあきら)が別邸の庭として築成した。作庭者は茶人としても知られる家老の上田宗箇(そうこ)。山川の景、京洛の態、深山の致を庭の中に縮景していることから「縮景園」の名が付けられたといわれる。池泉回遊式庭園*...
広島市安佐動物公園 ( 広島県 広島市 )
広島市街から北西に約15km、山麓に広がる緑豊かな動物公園。開業は1971(昭和46)年。主にアフリカとアジアの動物を展示している。動物の飼育・展示にあたっては、野生と同じような行動を引き出し、生き生きと生活する様子を観覧できるよう、並べ方や広い展示空間の確保、間近で見られる工夫、群れでの展示等を意識した展示を行っている。 ...
不動院 ( 広島県 広島市 )
広島市街から北に約4km、太田川東畔に位置する。開基は行基とも空窓とも伝えられ、創建年代や由緒は諸説が残るが、本尊薬師如来像の様式から、平安時代には創建されていたと推察されている。足利尊氏・直義兄弟が日本全国に建立した安国寺のひとつ。戦国時代の戦いで伽藍は焼け落ちたが、安土桃山時代、安国寺恵瓊*が豊臣秀吉の時代に再興し...

写真提供:Nobutada OMOTE
神勝寺 禅と庭のミュージアム ( 広島県 福山市 )
JR福山駅から南西に約10kmに位置する。神勝寺は1965(昭和40)年創建の臨済宗建仁寺派寺院だが、その広大な境内を活かし、瞑想、食、墨跡、入浴、散策などの体験を通じ、禅とはなにかを感じるためのミュージアムとして、2016年にオープン。境内には、数々の伽藍や茶室のほか、彫刻家・名和晃平*らの設計によるアートパビリオンや建築史家、...
鞆の浦 ( 広島県 福山市 )
JR福山駅から南に14km、福山市の南端、沼隈半島の先端に広がる。江戸期の港湾施設(常夜燈、雁木、波止、船番所、焚場、等)がまとまって現存する国内唯一の港町であり、潮待ちの港として繁栄を極めた。いまもなお、豪商の屋敷や小さな町家がひしめく町並みが残る。海上には仙酔島を中心に、弁天島・皇后島が浮かび、みごとなその景観は日本...

福山城 ( 広島県 福山市 )
JR福山駅のすぐ北側にある。福山藩初代藩主の水野勝成*が、入封してからわずか3年で築城、1622(元和8)年に完成した平山城。西国鎮衛の拠点であり、五重天守をはじめ、本丸・二之丸には数多くの櫓や城門を配する。福山城天守北側は鉄板張りであり、鉄壁の防御の構えであった。これは全国の天守の中でも極めて特殊なもので、他に類例がない...
ふくやま草戸千軒ミュージアム ( 広島県 福山市 )
JR福山駅・福山城口(北口)から西へ400mの位置にある博物館は、1930(昭和5)年に芦田川の川底から発見された中世の港町・市場町である「草戸千軒町」の遺跡を中心に、瀬戸内地域の民衆生活と文化を紹介している。草戸千軒展示室には、中世の人々の暮らしぶりがよく分かる日常の生活用品などの出土品の展示のほか、発掘調査で明らかになった...
明王院 ( 広島県 福山市 )
JR福山駅から南西に約3km、芦田川の西岸にあり、眼下に草戸千軒町遺跡*を見渡す真言宗大覚寺派の古刹。もとは常福寺といい、創建は807(大同2)年、弘法大師(空海)の開基と伝えられるが、現在の形を整えたのは鎌倉末期である。江戸時代、水野勝成*が福山藩主として入府してからは、祈願寺として、その庇護を受けて栄えた。 境内には国...
上下白壁の街並み ( 広島県 府中市 )
広島県東部、福山駅の北東約50kmに位置する。江戸幕府の直轄地・天領でもあったことから、商業・金融のまちとして栄えた。当時、33軒もの両替商、いまでいう銀行があったと言われ、幕末から明治維新にかけてはその資金が徳川政権さらには明治新政権をも支えたと伝えられている。当地の金融業者の資金力は、やがて地元の福祉や教育の充実を図...

写真提供:大本山 佛通寺
佛通寺 ( 広島県 三原市 )
JR三原駅から北西に約17km、仏通寺川沿いに佇み、周囲の自然環境と調和した寺院。日本屈指の参禅道場として知られる臨済宗佛通寺派の大本山。1397(応永4)年、小早川春平*が名僧 愚中周及*を迎えて創建した。小早川一族の帰依を受け、最盛期には山内に88寺、西日本に約3,000寺を数えたが、応仁の乱後、幾多の興亡の歴史を経て現在に至る。...
寂地峡 ( 山口県 岩国市 )
山口県の最高峰寂地山(標高1,337m)の山麓にある峡谷で、宇佐川上流の3.5kmにわたる犬戻峡(いぬもどしきょう)と、下流合流点から北西1kmにわたる竜ヶ岳峡からなる。犬戻峡には犬戻し18滝と呼ばれるさまざまな滝があるが、険しい個所もあり、散策、ハイキングには向かない。竜ヶ岳峡は5つの滝(龍尾、登龍、白龍、龍門、龍頭)を中心とし...
長門峡 ( 山口県 山口市 / 山口県 萩市 )
長門峡*は山口市の北東部から萩市南東部をまたいで流れる阿武川を中心とした溪谷。北から流れる阿武川と南から流れる篠目川が合流する「道の駅長門峡」近くの丁字川出合淵から、下流の竜宮淵までの約5kmには遊歩道がありみどころとなっている。この渓谷は火山活動で生成された火山岩(流紋岩、安山岩)や凝灰岩などからなり、北西方向から侵...

秋吉台・秋芳洞 ( 山口県 美祢市 )
秋吉台は、山口県の西北部にある標高200~400mの石灰岩高原。日本最大のカルスト*1景観地として知られている。総面積130km2のカルスト台地のうち、45.02km2が国定公園に指定され、さらにそのうちの主要部が特別天然記念物として保護されている。ゆるやかな曲線をみせる広大な高原には、灰白色の石灰岩が無数に露出点...
青海島 ( 山口県 長門市 )
仙崎の先端からわずか100mばかり離れた日本海上に横たわり、仙崎とは青海大橋で結ばれている。島は、ほぼ中央でくびれ、標高300m内外の山地*が大部分を占め、平地はほとんどない。しかし、南部は傾斜がゆるやかで、古くから漁業を営む大日比(おおひび)・通(かよい)などの小集落が散在している。北部は日本海の荒波の浸食によって生じた...
赤間神宮 ( 山口県 下関市 )
JR山陽本線下関駅から海岸沿いに北東へ約3km、関門海峡大橋の手前にある。壇ノ浦の戦い*に敗れ、二位ノ尼に抱かれ8歳で入水した安徳天皇を祀る神社。安徳天皇*はこの地にあった阿弥陀寺境内に埋葬され、1191( 建久2)年には、朝廷の命によって御陵上に御影堂を建立し勅願寺とした。この阿弥陀寺が、明治政府による神仏分離政策によって赤...
東光寺 ( 山口県 萩市 )
JR山陰本線東萩駅から東へ約2kmの道のり、松陰神社の東、東光寺山の麓に寺域が広がっている。萩藩*1の三代藩主毛利吉就が1691(元禄4)年に建立した寺で、萩市街の西にある大照院と並んで毛利氏の菩提寺である。江戸中期の最盛期には堂塔40棟、僧侶80人を数えたというが、明治維新には寺禄を失い、往時の隆盛はない。しかし、黄檗(おうばく...
住吉神社 ( 山口県 下関市 )
JR山陽新幹線・山陽本線新下関駅から南東へ約1.5kmのところにある。伝承では、神功皇后が朝鮮出兵の帰途に神託により、現在地に「荒魂(あらみたま)」を祀ったのが始まりとされ、同様の神意で大阪の住吉大社も祀られたと伝えられている。また、同社は、927(延長5)年に成立した法制書の「延喜式神名帳」では「住吉(に)坐(す)荒御魂神社...
防府天満宮 ( 山口県 防府市 )
JR山陽本線防府駅から北へ1.5kmほどのところにある。同天満宮の縁起では、菅原道真*1が筑紫大宰府への左遷の途中、周防国司で同族の土師氏*2のところに立ち寄ったという因縁を伝え、903(延喜3)年、道真が志半ばで大宰府において亡くなったことを知った国司土師信貞が904(延喜4)年に創建*3したとされていることから、日本最古の天満宮...
常栄寺・雪舟庭 ( 山口県 山口市 )
常栄寺*1はJR山口線山口駅から北東に約3.5kmの道のりのところにある。もともとは、大内政弘*2の別邸で、のちに母妙喜尼の菩提のために寺とし、寺号を妙喜寺とした。当地の支配者の交代に伴い、合寺を重ね寺号も変遷し、1863(文久3)年には毛利氏の菩提寺であった常栄寺と合寺し、明治期に入り常栄寺と号するようになった。 庭園は本堂...
瑠璃光寺五重塔 ( 山口県 山口市 )
JR山口線山口駅から北へ道のり約2kmの香山公園内にある。1442(嘉吉2)年、足利義満に敗れ戦死した大内義弘*1の菩提を弔うために、弟の盛見が当時この地にあった香積寺(こうしゃくじ)*2境内に建立したもの。大内氏の盛時を偲ばせる室町中期の優れた建築物である。なお、瑠璃光寺*3は、香積寺が毛利輝元*4の萩入りとともに萩へ五重塔を...
萩城跡 ( 山口県 萩市 )
萩市街の北西端に位置する指月山(しづきやま)*1の麓にある。萩藩祖である毛利輝元*2は、豊臣政権下では中国地方で約112万石を領していたが、関ヶ原の戦で西軍に加わり周防・長門2カ国約36万石に減封となり、本拠地も広島から萩に移されたため、輝元は萩城を1604(慶長9)年に着工し、4年をかけて築城した。以後13代*3を重ね、1863(文久...
岩国城・吉香公園 ( 山口県 岩国市 )
JR山陽本線岩国駅から西に約5km、錦帯橋を渡った錦川西岸に吉香公園はある。岩国を支配した吉川氏*1の居館跡はすでに明治期に公園化されていたが、その後、同公園内にあった岩国高校が1968(昭和43)年に移転したため、これも合わせて都市公園とした。 園内には、錦雲閣*2、岩国徴古館*3、花菖蒲園、旧目加田家住宅*4、香川家長屋門、...
柳井市古市・金屋の町並み ( 山口県 柳井市 )
JR山陽本線柳井駅の北方500m。中世・近世を通じ、瀬戸内海の舟運の中心として栄えた、港町・市場町の柳井津。船着場であった柳井川沿いに古市・金屋の町筋がのびる。この町筋は柳井津のなかでも最も古くから開けたところで、そのため敷地割は室町時代そのままに生かされ、約200mの通りには江戸中期建築の約40棟の町家が軒を連ねる。藩政時代...
萩の城下町 ( 山口県 萩市 )
萩の城下町は、日本海に向って流れる阿武川の下流が二手にわかれて(東が松本川、西側が橋本川)できた三角州にある。1604(慶長9)年に萩藩*1の本拠地として毛利輝元*2は、三角州の北西部で日本海に突き出している指月山を背に萩城を築き、三角州に向かって城下町を整備した。 現在、世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産...
長府の町並み ( 山口県 下関市 )
長府の歴史は古く、日本書紀など記紀の神代の巻に、仲哀天皇が神功皇后とともに「熊襲」制圧の際、仮宮として穴門(長門)豊浦宮(とよらのみや)*1を置いた地として記されている。さらに7世紀の中ごろ、長門国の国府がこの地に設置され長府と称されるようになった。国府のあった場所は不詳ではあるが、現在の忌宮神社*2付近ではないかとさ...
旧毛利家本邸(毛利博物館・毛利氏庭園) ( 山口県 防府市 )
JR山陽本線防府駅から北東に2.5km、多々良山麓の高台にある。萩(長州)藩の旧藩主毛利家*の旧本邸で、1916(大正5)年に建設*され、現在は毛利博物館、毛利氏庭園として一般に公開されている。国の名勝指定を受けている面積は庭園部分が約8万4,000m2、邸宅の敷地部分が約4,000m2に及ぶ。広大な敷地のなかに、南側に...
錦帯橋 ( 山口県 岩国市 )
JR山陽本線岩国駅の西約5km、JR山陽新幹線新岩国駅からも錦川沿いに約5km、錦川の清流に架かる5連の木造アーチ橋が錦帯橋*である。岩国城や吉川家の館がある横山と町方の中心である錦見をつないでいた。5連橋のうち、両端は柱橋、中央部の3連がアーチ橋で、圧力が加わると橋の強度が増すという構造になっている。 この橋は、1673(延宝元...
山口県政資料館 ( 山口県 山口市 )
現在の山口県庁に隣接して建つ山口県旧県庁舎と旧県会議事堂の2棟を、1985(昭和60)年に県政資料館として開館した。建物は明治期の建築界の巨匠といわれる妻木頼黄(つまきよりなか)*の指導のもと設計され、いずれも煉瓦造2階建で1913(大正2)年に起工し1916(大正5)年に完工した。後期ルネッサンスシズムを主体に、細部意匠に日本の伝...

写真提供:ときわ公園
ときわ公園 ( 山口県 宇部市 )
宇部市街の東(JR宇部線宇部新川駅から東へ約4km)にある常盤湖*1を中心とした100万m2に及ぶ広大な都市公園。この公園は1925年(大正14年)に宇部市常盤公園として開設された。入江や岬が入り組んだ常盤湖は松林に囲まれ、主として、湖畔の南側に公園施設が集まる。 ここには、ときわ遊園地*2、ときわミュージアム(UBEビエ...
岩国寿司 ( 山口県 岩国市 )
岩国寿司は、岩国市を中心に食べられている「押しずし」*1の一種。その形状や調理法から「角ずし」*2とも呼ばれ、伝承されている由来*3から「殿様寿司」とも称される。調理法は、1970(昭和45)年発行の岩国市史の「角ずし」の項によると、「五升なり一斗くらいの飯をたき、これを酢できかせる。大きい長方形の折の底に、蓮の葉などをしき...
下関のふく料理 ( 山口県 下関市 )
日本人はフグを古くから食していたといわれ、約2万年前の旧石器時代、あるいは縄文時代の遺跡からもフグ科の骨が見つかっているという。その後、農耕の開始により、魚介類への依存が下がったところから、広汎に広がることはなかったとみられている。ただ、庶民の間では食べ続けられていたとみられ、豊臣秀吉が朝鮮出兵した際の本陣は、肥前名...

写真提供:元祖瓦そば たかせ
瓦そば ( 山口県 下関市 )
「瓦そば」は熱した瓦の上に茶そば、錦糸卵、牛肉などをのせ、小ネギ、海苔、輪切りのレモンともみじおろしが添えられて提供されることが多く、麺つゆにつけて食す。「瓦そば」が生まれたのは、JR山陽本線下関駅から北へ23kmの道のりのところにある川棚温泉*である。1962(昭和37)に、現在は「瓦そば」の専門店となった「たかせ」は、当時...
松下村塾 ( 山口県 萩市 )
松下村塾は、JR山陰本線東萩駅から南東へ約1.4kmの道のりの松陰神社境内の中央にある。吉田松陰(よしだしょういん)*1の父の弟である玉木文之進が、この地より約600m東にある自宅に私塾を開いたのが起こりで、松陰が幕末・明治維新の人材を育てたところとして名高い。 松陰がこの塾を継いだのは、実家杉家において幽囚の身であった1857...
金子みすゞ記念館 ( 山口県 長門市 )
JR山陰本線支線仙崎駅からまっすぐ北に向うみすゞ通りを約400mのところに記念館はある。金子みすゞ*は日本の童謡の隆盛期だった大正後期から昭和初期にかけて彗星のごとく現れた童謡詩人。20歳のころから雑誌『童話』『婦人倶楽部』『金の船』などに投稿を続け、詩人・作詞家の西條八十に「若き童謡詩人の中の巨星」と評価された。26歳で夭...

秋吉台山焼き ( 山口県 美祢市 )
毎年2月第3日曜日に開催*される。古くから農家が共同の採草地から良質の草を得るための農林事業として行われてきた。この山焼きの起こりは不詳だが、農業神の三宝荒神の祭事にも関係していたと言われ、かつては採草の入会権を有する集落ごとに火入れ*が行われていたという。現在は、景観保全と自然保護を目的としつつ、合わせて観光行事と...

写真提供:山口市ふるさとまつり実行委員会
山口七夕ちょうちんまつり ( 山口県 山口市 )
毎年8月6日、7日の2日間にわたり開催される。開催場所はJR山口駅から駅前通りを約150m、山口地方裁判所前から一の坂川を渡った早間田交差点付近までの約500mとそれに直交する中心商店街700mと一の坂川交通交流広場がメイン会場である。その沿道や広場一杯に長竹竿一本に40個の小さな赤い提灯が付けられた「ちょうちん笹飾り」が所狭しと並...

写真提供:下関市豊北総合支所
角島大橋 ( 山口県 下関市 )
角島大橋は山口県北西部の豊北町、中国自動車道下関ICから北へ約50km、JR山陰本線特牛(こっとい)駅からバスで25分にある。豊北町の北西約1.5kmに位置する角島*と本土を結ぶ、延長1,780m、幅員6.5m、2車線の橋で、1993(平成5)年に着工、1999(平成11)年に竣工し、2000(平成12)年に開通した。周辺海域の環境保全に配慮しながら、日本...
関門トンネル ( 山口県 下関市 / 福岡県 北九州市 )
関門海峡をくぐるトンネルは、玄界灘側の鉄道トンネル、瀬戸内海側の新幹線用の新関門トンネル、その間の瀬戸内海寄りにある国道トンネルの3本がある。 鉄道トンネルは世界で最初の海底トンネル*1で、日本においてはじめて圧気シールド工法*2を本格的に採用した海底掘削トンネルである。1936(昭和11)に着工し、下り線が1942(昭和17)...
周防国分寺 ( 山口県 防府市 )
JR山陽本線防府駅から北東に約2km、防府平野の北端に建ち、741(天平13)年聖武天皇の勅願によって諸国に建てられた国分寺のひとつ。周防国分寺の創建は不詳だが、756(天平勝宝)年よりはさかのぼるとされている。東南約900mのところには国府跡があり、西側には周防国分尼寺があったと見られる。寺域は200m四方あったとみられ、発掘調査の結...
須佐ホルンフェルス ( 山口県 萩市 )
北長門海岸国定公園の東端。須佐湾の東、標高532.8mの高山(こうやま)*が日本海に突き出した西麓に縞模様がくっきりとした須佐ホルンフェルスと呼ばれる海食崖がある。JR山陰本線須佐駅から北へ約4kmの道のり。 須佐ホルンフェルスは、海底に堆積した須佐層群(砂泥互層)に対し、約1,500万年前に高温の火成岩体[高山(こうやま)斑れ...
唐戸市場 ( 山口県 下関市 )
JR山陽本線下関駅から東へ2.4km、関門海峡に面してある魚市場*。ふぐの市場として知られているが、タイやハマチ等魚介類が豊富に取引されている。カマボコなどの水産加工品、農産物の直売所などもあり、「総合食料品センター」としての役割も果たしている。営業時間は平日と土曜日は5時から15時で、早朝の5時までは卸売販売が行われ、それ以...

大照院 ( 山口県 萩市 )
JR山陰本線萩駅から西へ約1kmに位置する臨済宗南禅寺派の寺院。萩藩7代*1にわたる藩主夫妻が墓地に眠ることで名高い。 1651(慶安4)年に亡くなった萩藩初代藩主毛利秀就(ひでなり)*2は、当時歓喜寺*3と呼ばれていた当寺に葬られた。2代藩主綱広(つなひろ)は父の菩提を弔うため寺の改築を始め、1656(明暦2)年に完工。亡き父の法...
四国八十八ヶ所・お接待 ( 徳島県 徳島市 / 香川県 高松市 / 愛媛県 松山市 / 高知県 高知市 )
四国八十八ケ所めぐりは弘法大師信仰の一つといわれる。 古代・中世の四国は、遍歴や巡礼を重ねる僧侶が修行を行う地であった。そのことは「今昔物語」(11世紀末から12世紀前半の成立)や歌謡集「梁塵秘抄」(12世紀後半に成立)に記されている。四国が修行の地であったのは、四国が仏教の後進地域であったため仏教を根付かせる必要性が...
阿波の土柱 ( 徳島県 阿波市 )
JR徳島線の川田駅から車で約10分、阿波山川駅からは車で約15分の所にある。土柱は、約100万年前から30万年前にかけて土砂が堆積した扇状地が地震活動によって隆起してできた山が、豪雨や地震によって崩壊し、そののち雨水によって土が削られ、長い年月をかけて形作られた。地下約600mに至るまで厚く堆積している。幅90mにいくつもの土の柱や...
轟九十九滝 ( 徳島県 海陽町 )
JR牟岐線・阿佐海岸鉄道 阿波海南駅からおよそ1時間かけて轟神社まで行く町営バスがある。轟九十九滝とは海部川上流の王余魚谷川(かれいたにがわ)の渓谷にかかる大小無数の滝の総称。本滝の轟の滝、別称王余魚(かれい)滝*は落差約58m、さらに本滝の上流の間には二重ノ滝、横見ノ滝などが連続し、最上部の鍋割の滝まで約1,500m、遊歩道が...
祖谷渓 ( 徳島県 三好市 )
剣山に源を発して西流する祖谷川は、松尾川などの支流を集めて吉野川に合流する。この祖谷川の下流部に発達した渓谷が祖谷渓である。一番の難所の約200mの七曲りの断崖、祖谷渓を見渡せるところに小便小僧がある。その昔、子どもや旅人がここで度胸試しをしたという逸話があるところ。近年、注目されているのが「ひの字渓谷」。蛇行する祖谷...
大歩危小歩危 ( 徳島県 三好市 )
石鎚山の東に源を発する吉野川が、石鎚・剣の山脈を横ぎる8kmのわが国の代表的な峡谷をつくりだす。大昔、四国山地が隆起する以前に流れていた吉野川が、山地が隆起するに従ってどんどん下刻をし、四国山地を横切るような峡谷となったのである。 「ボケ」は、切り立った崖を表す自然地形名称「ホケ」が地名化したものである。今から約200...
箸蔵寺 ( 徳島県 三好市 )
JR土讃線阿波池田駅から北東4kmほどに箸蔵寺がある。吉野川北岸にそびえる箸蔵山(約720m)の南斜面、中腹から山頂付近を占める広大な寺域である。 高野山金剛峰寺の『由来略記』によれば、828(天長5)年、当山で修行中の空海が金毘羅神からの託宣*を受けて七堂伽藍を建立したと伝え、俗に金刀比羅奥ノ院ともいう。慶長年間(1596~1615...
祖谷のかずら橋 ( 徳島県 三好市 )
JR土讃線大歩危駅からバスで約25分。祖谷渓の上流にかかる吊り橋で、その名のとおり野生のカズラ、シラクチカズラ(学名 サルナシ)*を主材料にして作られている。長さ約45m、幅2mで、中央の水面からの高さ14mの所にかかっている。 カズラを編んだ敷綱(しきづな)に、栗の木を割ったサナギと呼ぶ丸太をくくりつけて床部を造り、橋の手す...

写真提供:雲辺寺
雲辺寺 ( 徳島県 三好市 )
香川県と徳島県の県境、雲辺寺山(標高927m)にある、四国霊場八十八ケ所第66番札所。四国霊場では最も標高が高い。寺の住所は徳島県三好市だが、霊場としては古くから讃岐の打ち始めの札所として扱われ、最後の「関所寺」*である。歩き遍路では一つ前の三角寺(愛媛県四国中央市)から峠を越えて進み、徳島県側から雲辺寺山に登る。次の大...
吉野川(下流域) ( 徳島県 吉野川市 / 徳島県 石井町 / 徳島県 上板町 )
愛媛県と高知県に頂をもつ瓶ケ森(1,897m)より湧き出て、高知県の白猪谷を最源流とし、徳島県内にはいると、大歩危小歩危の渓谷で四国山地を横断し、三好市池田町で中央構造線*に突き当たり、川は直角に東へ向きを変えて、河口まで流れ、紀伊水道に注ぐ。全長194km、川幅最長部は2,380m。日本三大暴れ川の一つとして、坂東太郎(利根川)、...
剣山 ( 徳島県 三好市 / 徳島県 那賀町 / 徳島県 美馬市 )
徳島県西部に位置し、四国の屋根といわれる剣山地の主峰。標高1,955mは四国では石鎚山(いしづちさん)に次ぐ高峰であり、西日本で2番目に高い山である。古くから山岳信仰の山として昭和初期まで女人禁制が堅守されていた。名前の由来*は壇ノ浦の戦に敗れた平家の落武者が、祖谷にのがれる際、安徳天皇の剣を隠したことによるという。山名に...
徳島城跡 ( 徳島県 徳島市 )
JR徳島駅から徒歩10分足らずの場所にある徳島藩主蜂須賀氏の居城があったところで、徳島中央公園として市民に親しまれている。戦国時代、豊臣秀吉の四国攻めで戦功を上げた蜂須賀正勝の子、家政が入封。1585年(天正13)に築城を開始し、1586(天正14)年、長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)や小早川隆景(こばやかわたかかげ)などの助...

阿波おどり ( 徳島県 徳島市 )
「踊る阿呆に見る阿呆・・・」で、全国的に知られる阿波おどり。県内では、8月9日に開催される鳴門市阿波おどりを皮切りに、各地で阿波おどりが開催されるが、最もにぎわいを見せるのが、徳島市の阿波おどりである。踊り手約10万人・人出約130万人にも達するという、四国最大の夏祭りである。 阿波おどりの起源は、1586(天正14)年、蜂須賀...
新町川 ( 徳島県 徳島市 )
徳島市は川と橋のまちで、寺島、出来島、福島など、島のつく地名も多い。徳島も美称の「徳」で、「すばらしい島」を意味する。助任川、田宮川、住吉島川などたくさんの河川に囲まれた「水の都・徳島」で、その中でも市民がもっとも愛する川が新町川である。 徳島駅や城山、市役所などがある市の中心部は、助任川と新町川が囲んだ川の中州...
板東俘虜収容所跡 ( 徳島県 鳴門市 )
JR高徳線板東駅の北西に、第一次世界大戦時のドイツ兵の捕虜収容所跡地がある。第一次世界大戦が始まると、日本も参戦し、ドイツの租借地だった中国山東半島にあるチンタオ(青島)を攻撃。敗れたドイツ兵士約4,600人 が俘虜となり、日本各地の収容所へ送られた。大戦の長期化に伴い、四国の徳島・丸亀・松山にいた俘虜953人を一か所に集める...
鶴林寺 ( 徳島県 勝浦町 )
四国八十八か所第20番札所。最寄り駅はJR牟岐線立江駅で南西12km、バスは徳島駅からになる。 生名バス停の南が、鶴林寺参道の入り口で、ここから標高550mの鶴ノ嶽山頂まで急傾斜の山道が3km続く。この道は四国霊場の中でも有名な難所である。参道には、道標の丁石*が11基残っている。車の場合は、鶴林寺表参道入口のすぐ西側からドライブ...
大麻比古神社 ( 徳島県 鳴門市 )
JR高徳線板東駅から徒歩約20分。札所1番の北1.5kmにあり、地元の人びとには”おおあささん”の名で親しまれている阿波一ノ宮である。 『延喜式』式内社であり、かつては淡路国と阿波国の総鎮守として信仰を集めた。祭神は大麻比古大神と猿田彦大神。大麻比古大神は、天照大神の岩戸隠れのとき、サカキの木に玉・鏡・麻をかけて大玉串をつく...
藍の館 ( 徳島県 藍住町 )
藍住町とその周辺に藍作と藍染が発達したのは、吉野川が氾濫するたびに、毎年新しい壌土を運んでくれるため、土中の養分吸収度が高い藍でも、連作障害を起こすことがなかったからである。 藍作が盛んになったのは、1585(天正13)年、かねてから藍作に深い関心をもっていた蜂須賀家政*が播磨から国主として阿波に入封してからである。彼...

大窪寺 ( 香川県 さぬき市 )
四国霊場八十八ケ所第88番札所、四国遍路を締めくくる結願(けちがん)の寺である。縁起によると、717(霊亀3・養老元)年に行基菩薩がこの地を訪れた際に、霊夢を感得し草庵を建て修行をしたことが起源とされる。その後、816(弘仁7)年に唐から帰国した弘法大師が、現在の奥の院近くの胎蔵ヶ峰という岩窟で虚空蔵求聞持法を修法し堂宇を建...

写真提供:志度寺
志度寺 ( 香川県 さぬき市 )
県東部、道路一本隔てて志度湾に接する四国霊場八十八ケ所第86番札所。625(推古天皇33)年の創建と伝わる古刹で、海洋技能集団海人族の凡園子(おおしそのこ)が浦に流れ着いた霊木から十一面観音像を彫り、堂に祀ったのが始まりとされる。681(天武天皇10)年に藤原不比等が堂宇を増築し、「死渡(しど)道場」と名づけ、693(持統天皇7)...

満濃池 ( 香川県 まんのう町 )
大川(だいせん)山麓を水源とする金倉川の流れを台地上の浸食谷の端で堰き止め、谷全体に水を満たした大規模な人工の池。灌漑用のため池としては日本最大級のもので、大宝年間(701~704年)、国司道守朝臣(みちもりあそん)が創築したと伝えられる。その後、821(弘仁12)年に弘法大師空海が改修にあたり、日本初のアーチ型ダム方式の堤防...

写真提供:観音寺市観光協会
豊稔池堰堤 ( 香川県 観音寺市 )
豊稔池は観音寺市大野原町南部の五郷地区、阿讃山脈を分け入る柞田川(くにたがわ)上流にある農業用のため池である。堰堤は長さ145.5m、高さ30.4m、両端部は重力式、中央部は5個のアーチと6個の扶壁(バットレス)からなるマルチプルアーチ式ダムである。建造当時の米国の最新技術を導入しており、現存する同形式のダムの希少性から農業土木...

写真提供:観音寺市観光協会
琴弾公園 ( 香川県 観音寺市 )
県西部、観音寺市を代表する観光地。標高約59mの琴弾山を中心に、白砂青松が2kmほど続く有明浜に面し、約38.6haの広さを誇る。園内には琴弾八幡宮、四国霊場第68・69番札所の観音寺・神恵院、室町後期の連歌師で俳諧の祖、山崎宗鑑の旧居一夜庵*などの名所旧跡が点在している。琴弾山にはハイキング道やドライブウェイがつけられ、山頂の展望...

さぬき豊浜ちょうさ祭 ( 香川県 観音寺市 )
観音寺市豊浜町*で10月の第2日曜日を含む金・土・日の3日間に行われる祭礼。五穀豊穣と海上安全、豊漁を祈り、平穏を神に感謝する神事で、地元住民が中心となって伝統をよく受け継いでいる。各地区が誇る23台の「ちょうさ」が御輿のお供として太鼓を鳴らしながら町内を練り歩く。ちょうさとは内部に太鼓が積み込まれた山車(太鼓台)の一種...

丸亀城 ( 香川県 丸亀市 )
丸亀市のシンボルともいえる丸亀城は、標高66mの亀山に築かれた平山城で、「石垣の名城」として有名である。山麓の内堀から山頂の本丸まで、渦を巻くように4層に重ねられた石垣の高さの合計は60mにもなり、総高としては日本一高い*。緩やかであるが荒々しい野面積みと端整な算木積みの土台から、頂にいくにつれ垂直になるよう独特の反りを持...

塩飽本島町笠島の町並み ( 香川県 丸亀市 )
塩飽諸島*付近は、鳴門海峡と豊後水道からの潮流が交わる良好な漁場であり、瀬戸内の海上交通の要衝でもあった。島民は潮流を読むことにたけ、操船や造船を得意とし、中世ごろには塩飽水軍として活躍した。 笠島集落は、丸亀市本島*の北東端にある小さな港町で、北面に天然の良港が開け、三方は丘陵に囲まれている。笠島はまたの名を城...

飯野山 ( 香川県 丸亀市 / 香川県 坂出市 )
丸亀市と坂出市にまたがる飯野山は、標高422m、讃岐平野のほぼ中央に立つ独立峰である。周囲は約6kmに及び、どの方角から見ても円錐形*で、なだらかな裾野が美しい。穏やかな山容は別名「讃岐富士」と呼ばれ、地元の人々に親しまれている。瀬戸内海国立公園に含まれており、コナラ、クヌギ、ヤマザクラなどを中心とした広葉樹が多く、風景林...

写真提供:金刀比羅宮
金刀比羅宮 ( 香川県 琴平町 )
古くから「さぬきのこんぴらさん」として親しまれてきた金刀比羅宮は、仲多度郡琴平町の象頭山中腹に鎮座する、全国の金刀比羅神社の総本宮である。参道の長い石段は、本宮まで785段、奥社まで合計すると1,368段にも及ぶ。神域の入口である大門(おおもん)までは石段の両側に土産物店が軒を連ねる。広い境内には本宮のほか書院、旭社、四脚...

写真提供:金刀比羅宮
金刀比羅宮大祭 ( 香川県 琴平町 )
例大祭は毎年秋に行われる、金刀比羅宮でもっとも重要な祭である。その期間は8月31日の口明神事から、10月15日の焼払神事まで46日間にわたるが、主要な祭典は10月9日〜11日の3日間に行われる。なかでも10月10日の21時から行われる御神幸(おみゆき)の神事は、山上の神様が神輿で麓の門前町に降臨するもので、琴平では古くから「おさがり」、...

旧金毘羅大芝居(金丸座)で上演される歌舞伎 ( 香川県 琴平町 )
「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は、1835(天保6)年に建てられた現存する日本最古の芝居小屋である「旧金毘羅大芝居」(金丸座)で、年1回行われる歌舞伎公演。国の重要文化財に指定された舞台を活用した全国でも初めての試みで、1985(昭和60)年の初公演以来、毎年1回行われるようになり、現在では讃岐路に春を告げる風物詩となっている。開...

琴平門前町 ( 香川県 琴平町 )
「こんぴらさん」といえば、石段の両側にびっしりと土産店が建ち並ぶ表参道のようすが目に浮かぶ。現在の琴平門前町は、表参道とそれに続く新町商店街、参道口で表参道と交わる神明町通り、JR琴平駅から神明町までの通りがそのおおよその範囲である。神明町通りは1889(明治22)年に讃岐鉄道(現JR土讃線)の開通に合わせてできた新道で、旅...

瀬戸内海の多島海景観 ( 広島県 広島市 / 岡山県 倉敷市 / 愛媛県 今治市 / 香川県 直島町 / 徳島県 )
瀬戸内海は、本州西部、四国、九州に囲まれた日本最大の内海で、東西およそ450km、南北15~55 km、面積23,203km2である。灘や湾と呼ばれる広い部分が、瀬戸や海峡と呼ばれる狭い水路で連結された複雑な構造を持つ。平均水深が38.0mと非常に浅い海だが、瀬戸や海峡では水深100mを超える。700以上の島(有人島は約150)がある多島海...

屋島 ( 香川県 高松市 )
瀬戸内海に突き出た標高292m、南北約5km、東西3kmのテーブル状の高地で、大きな屋根のように見えるため屋島と呼ばれている。約1400万年前に噴出した山上の讃岐岩質安山岩が他の岩石よりも硬く、その後の浸食で取り残され、頂上部が平らになった。典型的な「メサ」と呼ばれる地形であり、南嶺(292m)と北嶺(282m)の2つのピークがある。かつ...

屋島寺 ( 香川県 高松市 )
屋島の南嶺(標高293m)にある天平勝宝年間(749~757年)の創建とされる古刹で、四国霊場八十八ケ所第84番札所。朝廷に招かれた鑑真が唐から当時の都、奈良に向かう途中、屋島に立ち寄り、北嶺*の霊地に普賢堂を建てたのがはじまりとされる。815(弘仁6)年には弘法大師が嵯峨天皇の勅願により、北嶺にあった伽藍を南嶺に移し、第84番の霊...

栗林公園 ( 香川県 高松市 )
高松駅から南へ3km、紫雲山(しうんざん)*東麓にある、面積約75haにも及ぶ広大な庭園。紫雲山を背景に6つの池と13の築山で構成され、1000本を超える手入れ松や多彩な石組を配した園内は変化に富み、歩みを進めるごとに風景が変わる「一歩一景」と称される。南庭と北庭とに分かれ、南庭は池泉回遊式大名庭園として優れた地割りや石組みを有...

四国村ミウゼアム(四国民家博物館) ( 香川県 高松市 )
屋島山麓にある四国村ミウゼアム(四国民家博物館)は、四国地方の伝統的な古民家や歴史的建造物を移築復原した野外博物館である。豊かな自然に囲まれた約5万m2の敷地に、江戸から大正期にかけての地方色豊かな建物が30棟あまり*配置されている。四国各地の民家、砂糖・和紙・醤油づくりなどに使用されていた伝統産業施設、農村...

写真提供:八栗寺
八栗寺 ( 香川県 高松市 )
高松市の東方、源平の古戦場、壇ノ浦を挟んで屋島と向かい合う五剣山(標高375m)の中腹にある、四国霊場第85番札所。五剣山にはもともと5つの峰があったが、江戸時代の1706年(宝永3)の大地震で東の峰が一部崩落した。 寺伝によれば、空海がこの地で修行中、天から降ってきた五本の剣を五つの峰に埋め、大日如来の像を刻み鎮護としたこ...

屋嶋城 ( 香川県 高松市 )
663(天智天皇2)年の白村江の戦い*を契機として、中大兄皇子が唐と新羅の侵攻に備え、対馬、九州から瀬戸内海沿岸にかけて築かせた山城の一つ。667(天智天皇6)年に築かれたことが「日本書紀」に記されている*。屋島はもともと陸地から切り離された島で、海上交通における要所にあり、メサ地形特有の断崖絶壁が発達し、眺望が利く場所も...

男木島の町並み ( 香川県 高松市 )
男木島は高松港の北方約10km、フェリーで約40分のところにある。周囲約5km、面積1.37km2、海に浮かぶ独立峰のような島で、島の最高地点は標高213mのコミ山。島の北端にある男木島灯台は、灯台守を主人公とした映画「喜びも悲しみも幾歳月」*のロケ地として有名である。古くから漁業の島として知られ、現在もサワラやタコなどを漁...

神谷神社 ( 香川県 坂出市 )
坂出市の東部、高松市との境界に位置する五色台の麓にあり、延喜式にも記載がある古社である。本殿は高さ1.5mほどの石積みの基壇の上に立ち、桁行3間、梁行2間の母屋から庇(向拝)を前方に伸ばしている。棟木(むなぎ)に書かれた墨書銘から1219(建保7)年の建立であり、造営年の明らかな神社建築では日本最古であり、国宝に指定されている...

白峯寺 ( 香川県 坂出市 )
坂出市の東、高松市に連なる五色台は瀬戸内海国立公園の中に位置し、その名の通り五峯(黄峯・白峯・赤峯・青峯・黒峯)からなり、北は瀬戸内海、南は讃岐平野を望む山々である。白峯寺は西よりの白峯(標高377m)の中腹にある四国霊場八十八ヶ所霊場の第81番札所で、崇徳上皇ゆかりの寺院でもある。 815(弘仁6)年、弘法大師が修行のた...

紫雲出山のサクラ ( 香川県 三豊市 )
紫雲出山は香川県三豊市、瀬戸内海に突き出た荘内半島のほぼ中央部にある標高352mの山。荘内半島には浦島伝説の地がいたるところにあり、紫雲出山は浦島太郎が玉手箱を開け、出た白煙が紫色の雲になって山にたなびいたことから名づけられたといわれる。 山頂近くまで車で行くことができ、山頂の展望台からは瀬戸内海の多島美が見渡せる。...

弥谷寺 ( 香川県 三豊市 )
古来より霊山として信仰された弥谷山(382m)の中腹、標高200mにある四国霊場八十八ケ所第71番札所。仁王門から最上部の本堂までは、540段*の石段を上る。 今からおよそ1300年前、聖武天皇の勅願により、行基が堂宇を建立し、光明皇后の経典を奉納したのが始まりとされ、山頂から八州が見渡せることから八国寺と命名された。弘法大師が幼...

本山寺 ( 香川県 三豊市 )
財田川の北岸に立つ四国八十八ケ所霊場第70番礼所。807(大同2)年、平城天皇の勅願により空海が建立したと伝えられる。当時は「長福寺」という名で、江戸時代19世紀頃に本山寺と称されるようになった。境内はおよそ2万m2と広大で、古くから七堂伽藍や塔頭を連ねた大寺として栄華を極めていたことが偲ばれる。 本堂は、正面5間...

寒霞渓 ( 香川県 小豆島町 )
瀬戸内海国立公園を代表する景勝地の一つ。東西7km、南北4kmの渓谷に、約1300万年前の火山活動により堆積した安山岩や疑灰角礫岩などが、度重なる地殻変動と侵食により、断崖や奇岩群を形成している。日本書紀にもその記述があり、元々は鉤懸山(かぎかけやま)、神懸山(かみかけやま)などと呼ばれていたが、1878年(明治11)年に儒学者の...

小豆島のオリーブ ( 香川県 小豆島町 )
三都半島の東、内海湾に面した小豆島町西村地区は日本で最初にオリーブ*が栽培された場所である。1908(明治41)年 、当時の農商務省の委託により三重・香川・鹿児島の3県で試験栽培を開始したところ、小豆島のオリーブだけが結実した。現在、栽培試験地一帯は「小豆島オリーブ公園」になっており、約2,000本のオリーブの木や約120種類のハ...

善通寺 ( 香川県 善通寺市 )
弘法大師空海*誕生の地として知られ、善通寺市のほぼ中央にある。高野山の金剛峯寺、京都の東寺とともに大師三大霊跡のひとつであり、真言宗善通寺派の総本山である。唐から帰朝した空海が、807(大同2) 年長安の青龍寺を模して建立した真言宗最初の根本道場で、空海の父、佐伯善通(さえき・よしみち)の名をとって寺号とした。四国霊場八...

写真提供:本州四国連絡高速道路株式会社
瀬戸大橋 ( 岡山県 倉敷市 / 香川県 坂出市 )
瀬戸大橋は、本州と四国を結ぶ本州四国連絡橋のひとつで、1988(昭和63)年に開通した。海峡部9.4km、上部が自動車道路(瀬戸中央自動車道)、下部が鉄道(JR本四備讃線、愛称:瀬戸大橋線)の道路・鉄道併用橋としては、世界最大級の橋梁群である。塩飽諸島の櫃石(ひついし)島・岩黒(いわぐろ)島・羽佐(わさ)島・与島の4つの島をつた...

写真提供:©YAYOI KUSAMA
ベネッセアートサイト直島 ( 香川県 直島町 / 香川県 土庄町 / 香川県 小豆島町 / 香川県 高松市 / 岡山県 岡山市 )
ベネッセアートサイト直島は岡山市に本拠を置く、通信教育などで知られる、株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人 福武財団が瀬戸内海の直島、豊島、犬島などで展開する現代アートに関わるさまざまな活動である。美術館、宿泊事業、集落の古民家などを使ったインスタレーション*のほか、刊行物やシンポジウムなどの情報発信も行っ...

外泊「石垣の里」 ( 愛媛県 愛南町 )
愛南町外泊は、幕末から明治時代初期にかけて隣の中泊地区からの分家の移住によってつくられた集落で、入り江に面した急斜面に、高い石垣をめぐらした家々が、山の中腹までひしめき合うように立ち並んでいる。石垣は台風や冬の北西季節風による潮害を防ぐために造られたもので、軒に達するほどの高さがあり、独特の景観を造りだしている。こ...

佐田岬 ( 愛媛県 伊方町 )
瀬戸内海と太平洋を区切るように突出した四国西端の佐田岬半島は、全長約40km、最大幅6km、最小幅500mの日本で最も細長い半島である。半島には、入り江ごとに集落が点在し、段々畑には地域特産の柑橘が栽培されている。岬の先端、潮流の渦まく崖の上に白亜の灯台が立っている。岬に立つと大型船の行き来する豊予(ほうよ)海峡を隔てて佐賀関...

和霊神社 ( 愛媛県 宇和島市 )
JR宇和島駅の北にあり、大鳥居*と夏祭りで名高い社。俗に「和霊さま」と呼ばれ、漁業を中心に広く産業の神として、地元の人々はもとより、九州・中国地方にまで知られている。祭神の山家清兵衛公頼(やんべせいべえきんより)は、伊達秀宗の家臣で宇和島藩総奉行として藩政改革に尽くしたが、1620(元和6)年政敵の陰謀で殺害された。その後、...

宇和島城 ( 愛媛県 宇和島市 )
宇和島城は、市の中心、標高73mの丘の上に築かれた平山城で、戦国時代には板島丸串城と呼ばれて西園寺氏の居城であったが、1595(文禄4)年藤堂高虎が入部、翌年から6年の歳月をかけて本格的な築城を行った。築城の名手と言われた高虎が大名として初めて自分の居城につくった城である。その後1615(慶長20・元和元)年に伊達政宗の長子秀宗が...

宇和島闘牛 ( 愛媛県 宇和島市 )
宇和島近辺の村々で行われてきた闘牛は、起源は定かではないが、土俵を設け本格的に行われるようになったのは約170年前からといわれる。最も盛んだったのは大正末期から昭和初期で、農閑期やお祭りでは盛大に開催されていた。 現在では、宇和島市営闘牛場*において、1月2日、5月3日、8月14日、10月第4日曜日の年4回、定期闘牛大会が開か...

遊子水荷浦の段畑 ( 愛媛県 宇和島市 )
「耕して天に至る」という言葉がぴったりの段々畑の集積。住民が石を積み、造成した幅1m、高さ1.5m前後の狭くて細長い畑が、海岸の集落近くから山頂までに続いている壮大な景観。宇和海沿岸部には稲作に適した土地が少なかったことから、人々は山の斜面を開墾し江戸時代の終わりころにはサツマイモの栽培が行われていたが、明治末から大正に...

由良半島 ( 愛媛県 宇和島市 / 愛媛県 愛南町 )
由良半島は愛媛県の西南部に位置する豊後水道に長く突き出た半島部で、男性的な渦潮と荒波の中に、大猿、小猿の島々が映え、そそり立つ断崖の至る所に海水浸食の洞、怪礁がみられる。昔は串灘と呼ばれたように、突端まで長さ18km、数え切れないほどの入り江と小半島を長い串で刺したような形をしており、尾根を境に宇和島市津島町と南宇和郡...

滑床渓谷 ( 愛媛県 宇和島市 / 愛媛県 松野町 )
滑床渓谷は足摺宇和海(あしずりうわかい)国立公園の一角で、宇和島市と松野町にまたがり、鬼ヶ城山・三本杭・高月山など1,000m級の山々に抱かれた長さ12kmに及ぶ渓谷である。その両側には自然探勝道*が取り付けられており、出合滑(であいなめ)・岳見岩(だけみいわ)・雪輪の滝(ゆきわのたき)・千畳敷(せんじょうじき)などの景勝が...

面河渓 ( 愛媛県 久万高原町 )
面河渓は石鎚山の南麓に位置する四国最大の渓谷で、結晶片岩を基盤とし、深成岩・変成岩が併入して形成されている。そのため、奇岩・断崖は黒・白・赤と様々な色彩を持ち、地質学上でも変化に富んだ峡谷美である。 面河渓の入口はバス停近くの両岸に70mもの絶壁が迫る関門(かんもん)で、鉢巻岩、面河川と鉄砲石川が合流する想思(そうし...

岩屋寺 ( 愛媛県 久万高原町 )
岩屋寺は四国霊場八十八ケ所第45番札所で、創建は815(弘仁6)年といわれている。三宝鳥(さんぽうちょう=コノハヅク)、慈悲声鳥(じひせいちょう=ヤマガラ)、鉦鼓鳥(しょうこちょう=キジバト)、鼓鳥(つづみどり=ホトトギス)、慈悲心鳥(じひしんちょう=ジュウイチ)、鈴鳥(すずどり=キビタキ)、笛鳥(ふえどり=ヒヨドリ)の...

四国カルスト ( 愛媛県 久万高原町 / 高知県 津野町 )
愛媛県と高知県との県境にまたがる約25kmのカルスト*台地で、山口県の秋吉台、福岡県の平尾台に並ぶ日本三大カルストの一つであり、標高が高いことが特徴となっている。 東部の標高1485mの天狗ノ森をピークにゆるやかな起伏の続く天狗高原、ほぼ中央の周辺に位置し、高山植物や200頭余りの牛が放牧され、のどかな風景が広がる姫鶴平(め...

来島海峡の潮流 ( 愛媛県 今治市 )
今治市とその沖に位置する大島の間の幅5km弱の海峡。「一に来島、二に鳴門、三とさがって馬関瀬戸(ばかんせと)」とうたわれる海の難所で知られ、鳴門海峡・関門海峡と並ぶ日本三大急潮流の一つである。来島海峡は、1日に平均約1000隻もの船が通る日本有数の交通量の多い海峡で、中水道では最大10ノット(時速約18km)の流れとなって、渦潮...

大山祇神社 ( 愛媛県 今治市 )
大山祇神社は天照大神の兄である大山積大神を祀り、全国に一万社余りある山祇神社と三島神社の総本社といわれる愛媛県内最古の神社である。海の神や山の神として古代から日本総鎮守として尊称されており、多くの武将が祈願してきた。 大山祇神社の本殿、拝殿は国の重要文化財に指定され、格式高く、立派で厳かな雰囲気が感じられる。また...

今治城 ( 愛媛県 今治市 )
関ヶ原の戦いでの戦功により伊予半国20万石を領した藤堂高虎が、瀬戸内海に面した海岸に築いた大規模な平城。香川高松城、大分中津城と並んで「日本三大水城」の1つに数えられる海の城。海砂が吹き揚げる海辺につくられたため、別名として吹揚城(ふきあげじょう)とも呼ばれる。 1602(慶長7)年に築城を始め、建造物も含めて完成したの...

石手寺 ( 愛媛県 松山市 )
石手寺は、四国霊場八十八ケ所第51番札所で、道後温泉から東に約1kmのところにある。 728(神亀5)年、伊予大領越智玉純(おちたまずみ)が国家鎮護の道場として創建した。翌年の729(神亀6・天平元)年には、行基(ぎょうき)が薬師如来を刻んで本尊とした。当時は安養寺(あんようじ)と称し、法相宗に属していたが、のちに弘法大師が訪...

太山寺 ( 愛媛県 松山市 )
太山寺は、四国霊場八十八ケ所第52番札所で、高浜港の東にそびえる経ケ森の中腹にある。 寺の縁起では587(用明2)年、豊後国臼杵(大分県)の真野(まの)長者が商いのために船で大阪に向かう途中、松山沖で海難に遭った際に、観音菩薩に祈って難を逃れられたことから、そのお礼として豊後の工匠を集めて木組みをした建材を松山まで運び...

写真提供:伊佐爾波神社
伊佐爾波神社 ( 愛媛県 松山市 )
伊佐爾波神社は、神功皇后・仲哀天皇が、道後温泉に御来湯の際の行宮跡に建てられたといわれ、延喜年間につくられた延喜式には既に記載が見られる古社で1000年以上前から信仰を集めていたことがうかがえる。一時期は湯月八幡宮とも、さらには道後八幡とも呼ばれていた。現在の社殿に建て替えたのは江戸時代の松山3代藩主、松平定長である。大...

写真提供:伊豫豆比古命神社
伊豫豆比古命神社(通称:椿神社) ( 愛媛県 松山市 )
伊豫豆比古命神社は御創建2000年以上の歴史があり、尊称・敬称も親しく椿神社・お椿さんとも慕われ、商売繁昌・縁起開運の神様として全国から崇敬を寄せられている。特に、旧暦の1月7・8・9日に齋行される椿まつりは、善男善女が参詣される大変賑やかなお祭りである。 椿さんの由来は、神社周辺が昔、海原であり津(海の意)の脇の神社、...

松山城 ( 愛媛県 松山市 )
松山城は松山市の中心地、城山(勝山)山頂に本丸があり、裾野に二之丸(二之丸史跡庭園*)、三之丸(堀之内)がある、広大な平山城である。加藤嘉明(かとうよしあき)が1602(慶長7)年に築城開始。1635(寛永12)年、松平定行が入封し、3年をかけて本壇を改築し三重の連立式天守を築造した。その後、1784(天明4)年、天守が落雷で焼失し...

ロシア兵墓地 ( 愛媛県 松山市 )
日露戦争で捕虜となり、この地で亡くなったロシア兵の墓が、ロシア兵墓地である。日露戦争が始まった1904(明治37)年、松山市に全国初の収容所が設けられた。松山が捕虜収容所となった理由としては諸説あるが、港があり輸送に便利なこと、気候が温暖であること、港から街まで鉄道があったことなどが理由といわれている。捕虜収容所には、延...

萬翠荘 ( 愛媛県 松山市 )
萬翠荘は城山公園の南側にあり、旧松山藩主の子孫である久松定謨(ひさまつさだこと)伯爵の別邸として建てられた建物で、1922(大正11)年、フランス風建築を得意とする建築技師である木子七郎(きごしちろう)によって設計・建築させた純フランス風洋館である。地上3階・地下1階建てで、建築面積は428.78m2、延床面積は887.58m<...

写真提供:道後温泉
道後温泉本館 ( 愛媛県 松山市 )
道後温泉は、松山市街の北東端に位置する『坊っちゃん』でおなじみの名湯であり、日本三大古湯の一つ。その道後温泉のシンボルとして、今も多くの湯客に利用されている共同浴場が、道後温泉本館である。近代的旅館の立ち並ぶ温泉街の中央に、1894(明治27)年建築の瓦葺、三層楼の建物が、威風堂々とした姿を見せる。日本の公衆浴場として初...

新居浜太鼓祭り ( 愛媛県 新居浜市 )
一宮(いつく)神社をはじめ新居浜市内各神社の総合例祭ともいうべき祭り。太鼓台は1台重さ約3t、高さ5.5m、長さ12mという巨大な山車であり、金糸銀糸で飾られた50台以上の太鼓台が市内を練り歩くさまは豪華かつ勇壮で、男まつりの異名もあるほど。地域の伝承によれば、神輿に供奉する山車の一種で信仰を対象とした神輿渡御の際、その列に参...

別子銅山跡 ( 愛媛県 新居浜市 )
別子銅山は、新居浜市(旧別子山村)四国山地の山中に位置しており、足尾・小坂・日立とともに日本の代表的銅山であった。1691(元禄4)年の開坑に始まり、1973(昭和48)年3月の閉山に至るまで283年の歴史を有する。地中深く掘り進められた坑道の延長は約700km、深さは地下1,000mまで掘り続けられ、総産出量は約65万tにものぼり、新居浜市...

西山興隆寺 ( 愛媛県 西条市 )
西条市丹原の西約3.5kmの山中にあり、養老年間(717~724年)に空鉢(くうばち)仙人が草庵を結んだのに始まり、桓武天皇のときには勅願寺となった。以来、千有余年、東予随一の霊地として信仰を集め、1187(文治3)年、源頼朝の帰依を得て、堂宇が造営されたが、現在の本堂は1375(文中4)年の建立で、石垣上に客殿や三重塔などとともに城の...
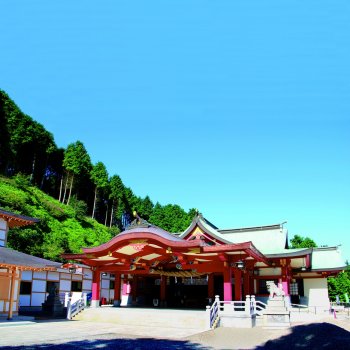
石鎚神社 ( 愛媛県 西条市 / 愛媛県 久万高原町 )
石鎚神社は日本七霊山の一つ石鎚山を神体山(神しずまります山)とする神社。山麓にたつ口之宮本社(くちのみやほんしゃ)、石鎚山中腹(7合目)の中宮成就社(ちゅうぐうじょうじゅしゃ)と土小屋遥拝殿(つちごやようはいでん)、石鎚山頂の奥宮頂上社(おくのみやちょうじょうしゃ)の4社を総称したものである。 祭神は石鎚毘古命(い...

武丈公園のサクラ ( 愛媛県 西条市 )
武丈公園はJR伊予西条駅の南、ひうち灘にそそぐ加茂川(かもがわ)沿いの市民公園にある桜の名所で、背後に標高196mの八堂山(はちどうやま)を控えた眺めは「四国の小嵐山」と称えられるほどで、約1,500本の桜並木は愛媛県有数である。彼岸桜(ヒガンザクラ)や染井吉野(ソメイヨシノ)などの桜並木が加茂川に沿って続き、ロケーションの素...

笹ヶ峰 ( 愛媛県 西条市 / 高知県 いの町 )
標高1,860m、愛媛県西条市と高知県いの町の境に位置し、笹ヶ峰から瓶ヶ森、石鎚山に続く尾根の姿は秀麗で「伊予の三名山」と呼ばれており、これらの石鎚山系は四国の背梁山地を形成している。メインの登山口である笹ヶ峰西条側登山口まではマイカーでアクセスすることができる。 日本二百名山および四国百名山の一つに数えられ、山名はな...

石鎚山 ( 愛媛県 西条市 / 愛媛県 久万高原町 )
西日本最高峰の石鎚山は標高1,982m、四国の屋根であり、西条市と久万高原町の境に位置する日本百名山の一つである。主峰の天狗岳を中心に、弥山、南尖峰の三山からなり、東西に石鎚山系の山々が連なって四国の背梁山地を形成している。 富士山、立山、白山、大峰山、釈迦ヶ岳、大山とともに、日本七霊山の一つにも数えられる信仰の山とし...

写真提供:愛媛県大洲市役所
肱川あらし(肱川の朝霧、雲海) ( 愛媛県 大洲市 )
「肱川あらし」とは、晴れた日の朝、上流の大洲盆地で涵養された冷気が霧を伴い、両岸が山で挟まれた肱川を河口まで流れ出すという珍しい自然現象のことである。これは、大洲盆地と伊予灘との間の夜間の温度差によって起こる現象で、日没1~2時間後から翌日の正午頃まで、寒冷多湿の強風が肱川に沿って流れ、海上へ吹き出すさまをいう。 ...

(金山)出石寺 ( 愛媛県 大洲市 )
大洲市と八幡浜市との境、標高812mの出石山(いずしさん)山頂にあり、石鎚山や大野ヶ原などの四国連山などが一望できる寺院である。境内は豊かな自然林に覆われ、本堂や庫裏、護摩堂、大師堂などが荘厳なたたずまいを見せており、静寂で心休まる雰囲気に包まれている。 本尊である千手千眼観世音菩薩には伝説が残されており、寺伝による...

如法寺 ( 愛媛県 大洲市 )
如法寺は、大洲市冨士山(とみすやま)の中腹にある臨済宗の古刹で、もともと室町時代に喜多郡の領主・宇都宮氏によって創立された寺であった。その後、廃寺となったが、大洲藩2代藩主 加藤泰興(かとうやすおき)の命により開かれた寺院で、1669(寛文9)年、深く帰依した高名な禅僧 盤珪(ばんけい)禅師を招いて如法寺を開山した。当初...

写真提供:愛媛県大洲市役所
大洲のいもたき ( 愛媛県 大洲市 )
「大洲のいもたき」とは、藩政時代から伝わる里芋などのブツ切りを、鉄鍋で煮込む郷土料理のことである。粘り気が強くホクホクとした食感の里芋、鶏肉を中心に、乾しいたけ、こんにゃく等を入れて煮込んだ、醤油ベースのほんのり甘い味が特徴となっている。 「大洲のいもたき」の歴史は、農民が集まる行事「お籠もり」から始まり、農民が...

皿ヶ嶺 ( 愛媛県 東温市 / 愛媛県 久万高原町 )
皿ヶ嶺は石鎚山系の西部に位置し、皿ヶ嶺連峰県立自然公園に指定されている。山名は山頂の近くに皿のような平坦地があることに由来しており、標高は1,271mである。動植物の宝庫といわれており、特に、山野草の宝庫で四季折々の植物を観賞できる。山頂から、久万高原町や石鎚連峰を望むことができる。 山麓から中腹までは自動車で通行可能...

歌舞伎劇場内子座の芝居 ( 愛媛県 内子町 )
内子座はJR内子駅近くにあり、1916(大正5)年、大正天皇の即位を記念して創建された歌舞伎劇場である。建物は正面約20.1m、側面約23.8mの規模で、木造、一部二階建、入母屋造、桟瓦葺、妻入である。大屋根に太鼓櫓をのせ、両袖には2階建の切妻造の櫓風別棟が造られている。内部は桝席、向こう桟敷、花道などが設けられ、電動式の回り舞台も...

写真提供:本州四国連絡高速道路株式会社
瀬戸内しまなみ海道(橋梁群) ( 愛媛県 今治市 / 広島県 尾道市 )
広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ西瀬戸自動車道の橋の愛称。自転車歩行者道、原付道が整備されており、海峡を横断して、自転車や徒歩でも渡ることができる。なお、新尾道大橋は、自動車専用道となっていることから渡船または隣接する尾道大橋を利用することとなる。橋や島々を含む付近一帯が、広域観光圏となっている。 新尾道大橋は、...

写真提供:(公社)高知市観光協会
高知の皿鉢料理 ( 高知県 高知市 / 高知県 土佐市 )
海、山、里の物を少量ずつ盛った口取り肴=「組物(くみもの)」や刺身=「なま」、すしを「皿鉢」(口径一尺二寸(約36cm)以上の浅い皿でサワチ、サアチ、サラチ等と呼ぶ)に盛りつけたもので、1つの器の料理をわけあって食べる。県下では冠婚葬祭はじめ各種宴会の定番料理で、高知市内で専門家が手がけるほか、家々での祝宴時等に調理され...

写真提供:高知県観光コンベンション協会
龍河洞 ( 高知県 香美市 )
土佐山田駅の東8km、バス20分。高知龍馬空港から車で15分、土佐くろしお鉄道阿佐線(ごめん・なはり線)のいち駅から8分、南国インターから25分。日本三大鍾乳洞のひとつ。標高322m三宝山中腹北方向きに開口した総延長で約4kmの鍾乳洞。 1931(昭和6)年に地元中学校教諭らの探検でそれまで知られていなかった上部開口部やその付近の弥生...
竹林寺 ( 高知県 高知市 )
文殊信仰の霊場である唐の五台山に登って奥義を授かる夢をみた聖武天皇の命により行基が唐の五台山に似た霊地としてここを選び、724(神亀元)年に開創されたと伝わる。大同年間(806~809年)に弘法大師がここで修行したという由縁から、のちに四国霊場第三十一番札所になった。江戸期には土佐藩山内家が代々祈願寺とし、学侶が集まり、近世...
高知城 ( 高知県 高知市 )
高知市中心部にあり、現在は高知公園として整備されている。バスまたは路面電車「高知城前」下車。日曜なら「蓮池通(はすいけどおり)」下車で追手筋の「日曜市」を抜けて城へ向かうのも良い。 17世紀初頭・慶長年間築城の平山城。城の立つ大高坂山(おおたかさかやま)は南北朝時代から軍事拠点として利用されてきた。二本の川に挟まれ...

写真提供:高知県立牧野植物園
高知県立牧野植物園 ( 高知県 高知市 )
1958(昭和33)年、高知県が生んだ植物学者、牧野富太郎*博士の業績を顕彰するため、高知市・五台山にある竹林寺の境内を譲られて開かれた県立の植物園。 約8haの園地には、博士ゆかりの植物など3,000種類が四季を彩り、1999(平成11)年に新設された牧野富太郎記念館では、博士の生涯を紹介する常設展に加え折々の企画展を開催している...

写真提供:高知県観光コンベンション協会
四万十川 ( 高知県 四万十市 / 高知県 四万十町 / 高知県 )
全長196km、流域面積2,186km2、支流総数は319を数える渡川(わたりがわ)水系本流の一級河川。清流、鮎の漁場として名高い。また代表的な景観として増水時に水中に沈むように設計された欄干のない沈下橋がかかる風景も知られている。 津野町の不入山(いらずやま、1,336m)東斜面が水源とされる東側の本流と最大支流の西側の梼...

室戸岬 ( 高知県 室戸市 )
高知市から車で2時間弱。土佐湾の東端、室戸市の最南端。古くはむろとざき(室戸崎)。1927(昭和2)年に日本新八景として注目され、1928(昭和3)年に「室戸岬亜熱帯性樹林および海岸植物群落」が国の天然記念物、ついで国の名勝「室戸岬」の指定をうけた。 亜熱帯性樹林のなかでも目をひく存在としてアコウの林が紹介されている。たこの...

金剛頂寺 ( 高知県 室戸市 )
四国八十八ケ所霊場第26番札所。807(大同2)年に平城天皇の命をうけ弘法大師によって創建されたといわれる。室戸三山*において通称「西寺(にしでら)」と呼ばれる。金剛頂寺は、高知市方面から国道55号をバス停元橋西の信号で左折、集落を通って山道を2kmほどのぼった台地にある。 駐車場から33段の女坂、42段の男坂、61段の厄除坂から...
最御崎寺 ( 高知県 室戸市 )
四国八十八ケ所霊場第24番札所。東寺*とも呼ばれる。室戸岬突端部後方の高い位置にあり、室戸市街地方面から室戸岬スカイラインで上っていくと、参拝路入口・駐車場まで行ける。 807(大同2)年の唐から帰国した空海が嵯峨天皇の命で開き、本尊・虚空蔵菩薩は空海作と伝わる。室町時代に足利氏の土佐の祈願所(安国寺)となり、江戸期に...

大堂海岸 ( 高知県 大月町 )
白い花崗岩の断崖景観。高さ30mの石柱の観音岩は遭難者をみちびいたという伝説、120mの断崖のお万の滝については悲恋物語が語り継がれている。 観音岩から大堂山展望台まで高低差200m、全長6kmの遊歩道がある。すべてを歩くと登山となるが、観音岩までは県道から近く比較的気軽に足を運べる。 柏島、竜ケ浜も見渡すことができる。海岸...

柏島 ( 高知県 大月町 )
高知県西南端、足摺宇和海国立公園内。宿毛湾口にある周囲4km、面積0.6km2の島で、大月半島と橋で結ばれている。島の沿岸は南からの暖流黒潮(貧栄養)と、瀬戸内海から豊後水道を南下してくる富栄養な海水とが混じりあうことで、多種多様な海洋生物の宝庫*。 1990(平成2)年代以降ダイビングスポットとして有名になり、多く...
杉の大スギ(八坂神社境内) ( 高知県 大豊町 )
日本における代表的な杉の古木のひとつ。八坂(やさか)神社の境内に立つ。根本が合着した2本が寄り添っているような形状のいわゆる「夫婦杉」で南大杉の樹高が約60m根回り約20m、北が樹高57m根回り約16.5m。 1894(明治27)年の国道32号開通以降、馬車や人力車交通時代の宿駅であった杉のまちの大杉は知名度を増した。大正期に内務省天然...
豊楽寺 ( 高知県 大豊町 )
JR土讃線 大田口駅から徒歩30分。大田山大願院豊楽寺。724(養老8・神亀元)年、行基による創建が伝えられている真言宗寺院。 その薬師如来は国内有数に名高く、四国らしい谷をはさむ急峻な山の中腹にありながら信者参拝を迎えてきた。「柴折薬師(しばおりやくし)」ともよばれる。荒天による大破を被っては長宗我部元親(ちようそかべも...

足摺岬 ( 高知県 土佐清水市 )
高知西南交通バス「足摺岬」下車。土佐清水市街から車で約20分。四国最南端の岬であり、足摺宇和海国立公園の中核的景勝地である。足摺岬の断崖にたつ国内最大級の灯台は高さ18m。1914(大正3)年の点灯。 バスの停留所は第38番札所、金剛福寺*(手前の駐車場)にあり、県道27号道路を挟んで食堂、喫茶店などの建物が軒を並べている。南...
(土佐)国分寺 ( 高知県 南国市 )
土佐くろしお鉄道阿佐線(ごめん・なはり線)後免(ごめん)駅の北2.5km。高知市内に通じるとさでんバスの最寄りバス停から徒歩20分。 紀貫之*が国司として4年間滞在した国府の地。土佐国分寺は、天平年間(729~749年)に諸国に建てられた国分寺の一つで行基により741(天平13)年創建。本尊は行基作と伝わる千手観音。庭園などに杉苔が...

戸畑祇園大山笠 ( 福岡県 北九州市 )
毎年7月の第4土曜日を挟む3日間に行われる。博多祇園山笠、小倉祇園太鼓とともに福岡県夏の三大祭りの一つとされる。起源は1803(享和3)年。疫病が戸畑地区で広まった折、疫病退散を須賀大神に祈願すると御神徳により平癒したため、山笠をつくり祝ったことが始まりといわれる。 山笠は戸畑区内にある4地区により展開され、それぞれ東大山...

写真提供:小倉祇園太鼓保存振興会
小倉祇園太鼓 ( 福岡県 北九州市 )
八坂神社の夏季大祭で、博多や戸畑の祇園と並び福岡県三大夏祭りの一つである。「太鼓祇園」とも呼ばれるように太鼓が中心の祭りで、映画や歌でよく知られる「無法松の一生」で有名になった。山車の前後に乗せた太鼓をヂャンガラという鉦に合わせて、4人の打ち手が両面から力いっぱい打ちならし、町を練り歩く。 起こりはおよそ400年前。...

小倉城 ( 福岡県 北九州市 )
JR小倉駅の南西約1,000mにある。関ヶ原の戦いののちに入国した細川忠興が1602(慶長7)年に以前の城の大改築を始めたもので、最盛時は148基もの櫓が立ち並んだ大城郭であったという。細川氏が肥後へ転封後は1632(寛永9)年に播磨明石より小笠原忠真が入り、以後、小笠原氏が10代235年間にわたって九州の要としての重責を果した。 当初の...

黒崎祇園山笠 ( 福岡県 北九州市 )
400年以上の歴史を持つ祇園祭で、北九州市八幡西区にある岡田神社(岡田宮)、春日神社、一宮神社に奉納される。毎年7月の3・4週目のなかで4日間にわたって開催され、前夜祭の山笠競演会に始まり、街中巡行、解散式と続く。黒崎祇園山笠は、お清めの儀式である「お潮井とり」を終えたのちに、山笠の装飾が、笹を2本立て注縄で繋いだ笹山笠か...

犬ヶ岳のツクシシャクナゲ ( 福岡県 豊前市 )
犬ケ岳は豊前市の南方、大分県との県境付近に位置する標高約1,130mの山で、一帯は高山植物の宝庫。尾根沿いのブナ林帯に淡いピンク色のツクシシャクナゲが自生する。「犬ヶ岳ツクシシャクナゲ自生地」が国の天然記念物に指定されている。

写真提供:海の中道海洋生態科学館
マリンワールド海の中道 ( 福岡県 福岡市 )
玄界灘に突き出た海の中道の一角に位置する。博多湾に面し、対岸に福岡市街中心部を望む。2017(平成29)年4月にリニューアルオープンし、展示の進化、空間演出の強化、施設の快適性の向上により、“海をより身近に感じられるリゾート施設”へと生まれ変わった。 正面から空に向かって広がるような扇形の建物は3階建てで、館内には10のテー...

写真提供:大濠・西公園
西公園のサクラ ( 福岡県 福岡市 )
福岡市のほぼ中央、丘陵地にあり、古くから博多湾を望む景勝地。展望台からは博多湾・志賀島などが一望に収められる。黒田長政の福岡移封と同時に、この地に東照権現を守護神として祭り、以降、霊山として知られた場所であり、敷地内には黒田孝高・長政を祭る光雲神社や、徳富蘇峰の詩碑など史跡もある。 園内は桜の名所で、福岡県で唯一...

筥崎宮 ( 福岡県 福岡市 )
筥崎八幡宮とも称され、宇佐、石清水八幡宮とともに、日本三大八幡宮の一つに数えられる。応神天皇が主祭神として祀られており、醍醐天皇が社殿を建立したと伝わる。創建時期は平安時代中頃とされているが諸説ある。 鎌倉時代中期、蒙古襲来(元寇)で勝利を収めたことを機に厄除け、勝運の神として知られるようになる。足利尊氏、大内義...

写真提供:福岡市
福岡城 ( 福岡県 福岡市 )
関ケ原の戦の功により、筑前52万3,000石を拝領した黒田長政が1601(慶長6)年から7年間かけて建立した城。壮大な平山城で、堀を含めた総面積110万m2、東西1km、南北700mの全国でも有数の規模である。現在残っているのは、天守台・多聞櫓・(伝)潮見櫓・下之橋御門・旧母里太兵衛邸長屋門・名島門など。城跡は舞鶴公園として公開...

写真提供:大濠・西公園
大濠公園 ( 福岡県 福岡市 )
福岡市のほぼ中央、福岡城跡の西に立地。黒田長政が福岡城を築城する折、城の外堀として利用した博多湾の入江を、昭和初期に県営公園としたもの。総面積約39万8,000m2のうち、半分以上の約22万6,000m2を池が占める水の公園で、池畔には柳・ツツジが植えられ、中の島には観月橋が架かり、ボートが浮かぶ。池の周辺には...

博多祇園山笠 ( 福岡県 福岡市 )
博多最大級の祭礼。博多祇園山笠の起源は諸説あるが、鎌倉時代、承天寺の聖一国師が博多に流行った病魔退散を祈願し、施餓鬼棚を町人にかつがせて町々を回り、疫病を封じたことが始まりとするのが通説である。むかしは約五十尺の山笠をそのままかついだが、電線などの障害物のため、明治の末ごろから飾り山笠とかき山笠に分かれた。飾り山笠...

福岡市博物館 ( 福岡県 福岡市 )
福岡タワーの南にある歴史民俗博物館。「Fukuoka アジアに生きた都市と人びと」をテーマに、福岡の歴史と人々のくらしを紹介する。特に、大陸文化の玄関口であった福岡ならではの、対外交流に重点を置いた構成になっている。 国宝の「金印*」をはじめ、黒田家の家臣「黒田二十四騎」のひとり、母里太兵衛が福島正則から”呑み取った”とさ...

承天寺 ( 福岡県 福岡市 )
臨済宗東福寺派の寺院で、1242(仁治3)年に謝国明が創建し、開山は後に京都の東福寺を開いた聖一国師による。博多での聖一国師との結びつきから、承天寺は臨済宗東福寺派で中心的役割をなし大いに栄え、盛時には塔頭が43寺もあったと伝わる。第二次世界大戦で山門、勅使門、塔頭二寺を焼失、さらに戦後の都市計画により、境内の規模は大幅に...

写真提供:福岡市動植物園
福岡市動植物園 ( 福岡県 福岡市 )
1933(昭和8)年、昭和天皇御即位記念事業として整備された御大典記念・福岡市動植物園が前身。戦時中の閉鎖を経て、1953(昭和28)年に現在の場所に動物園が開園。2018(平成30)年に開園65周年を迎えた。 ほ乳類38種210点、鳥類57種210点、は虫類12種49点を展示(2020年4月末現在)。 現在、一部老朽化が目立つ園内はエリアごとにリ...

写真提供:田川市石炭・歴史博物館
田川市の炭坑節 ( 福岡県 田川市 )
「月が出た出た 月が出た ヨイヨイ」の歌詞で知られる炭坑節。田川市の三井田川炭鉱で、坑内から運び出された炭塊を選り分けるときに歌う選炭唄がルーツで、石炭ブームにのって全国に広がった。歌詞の中の「一山、二山、三山越え」というのは3峰よりなる香春岳を指している。 1932(昭和7)年、最初に「炭坑唄」を収録したのは日東レコ...

石人山古墳 ( 福岡県 広川町 )
八女市と広川町にまたがる八女丘陵には大小約300基の古墳がある。これらの古墳群のうち代表的な石人山、岩戸山、乗場、善蔵塚、弘化谷、丸山塚、丸山、茶臼塚の八基が八女古墳群として1978(昭和53)年史跡に指定された。 その中の一つ石人山古墳は、長峰丘陵の一部を利用し5世紀前半代に築造された八女地方最古の前方後円墳。最古期の装...

写真提供:岩戸山歴史文化交流館
岩戸山古墳 ( 福岡県 八女市 )
八女古墳群のひとつである岩戸山古墳。墳丘長約135m、全長170m以上の規模を誇る北部九州最大の前方後円墳である。古墳の形の特徴として、後円部の北東側に1辺約43mの方形区画が存在する。筑紫君磐井の墓といわれ、石人・石馬や多くの埴輪が出土。出土品は八女市岩戸山歴史文化交流館に多数展示。

写真提供:田川市役所
風治八幡宮 川渡り神幸祭 ( 福岡県 田川市 )
風治八幡宮の例大祭で、福岡県指定無形民俗文化財第1号に登録された祭り。福岡県五大祭りの一つにも数えられている。 永禄年間(1558~1570年)、伊田村に疫病が流行した折、氏神である風治八幡宮に終息を祈願、成就のお礼に幟山笠を奉納したことが起源とされる。 神輿2基と、各町内から出る幟山笠が彦山川を渡るさまが人気で、毎年多...

英彦山神宮 ( 福岡県 添田町 )
英彦山の山内至る所に社殿が散在している。主な社殿は上宮、中宮、下宮と、奉幣殿および摂社の高住神社や玉屋神社などがあるが、鬱蒼とした杉の長い参道や坊跡に修験道の往時を伝える。参道は銅鳥居(かねのとりい)からはじまり、民家や坊の並ぶ桜並木の石段を500m登ると神宮下。さらに300段の石段を登ると奉幣殿で、そこから上宮までは約2k...

写真提供:添田町役場
旧亀石坊庭園 ( 福岡県 添田町 )
室町時代の画僧・雪舟が、英彦山中腹の亀石坊に滞在し、1476~79(文明8~11)年の間に築いたと伝わる699m2の池泉観賞式の庭園。1928(昭和3)年に国の名勝に指定された。自然の山林を背景に巨石を配し、滝を模した石組が設けられており、複雑に入り組んだ池の形状も特徴的で美しい。

写真提供:築上町
旧藏内邸 ( 福岡県 築上町 )
築上町の田園風景のなかに立つ大邸宅。筑豊地方の炭鉱経営で財を成した、藏内家三代(藏内次郎作、保房、次郎兵衛)の本家住宅である。敷地は7135m2、延床面積1250m2にも及び、九州では最大級の規模。1906(明治39)年ごろの造営で、その後大正時代に入って増築されたものという。大玄関をはじめ、大広間、煎茶の茶室...

大野城跡 ( 福岡県 大野城市 / 福岡県 宇美町 / 福岡県 太宰府市 )
大野城市、宇美町、太宰府市にまたがる四王寺山(大城山)一帯に残る古代の山城跡。 百済軍に加勢し唐・新羅軍と戦うために朝鮮半島に出兵した大和朝廷は、663(天智天皇2)年、白村江の戦いに敗戦。唐・新羅軍の侵攻の脅威を受け、まずは664(天智天皇3)年、筑紫国に水城を築く。さらに665(天智天皇4)年、大宰府政庁を防衛するために...

写真提供:大牟田市
三井三池炭鉱跡 ( 福岡県 大牟田市 / 熊本県 荒尾市 )
1469(文明元)年に、地元の農夫が焚き火の中で燃える石を見つけたというのが、大牟田における石炭発見の歴史だと伝わる。 江戸時代から採掘が行われ、1873(明治6)年には官営化され、西洋技術による近代化を進めていった。1889(明治22)年、三井財閥に払い下げられ、勝立坑、宮原坑、万田坑などを次々と開坑。日本の近代化を支えてきた...

写真提供:太宰府市
大宰府政庁跡 ( 福岡県 太宰府市 )
大宰府は律令制下において九州を治め、外交と防衛を担った地方役所。大陸に近いという立地の重要性から対外交渉を担うなど朝廷から大きな権限を与えられた時期もあった。7世紀後半に太宰府市内にその中枢がおかれ、その遺跡が残っている。 現在、大宰府政庁跡は3基の石碑の立つ辺りが正殿跡、ほかに中門・南大門・東殿・西殿などの礎石が...

九州国立博物館 ( 福岡県 太宰府市 )
「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」というコンセプトのもと、全国4番目の国立博物館として2005(平成17)年に開館。太宰府天満宮奥手の丘陵地に立ち、太宰府天満宮から長いエスカレーターでアプローチすると、周囲の山並みに溶け込む穏やかな曲線を描いた全面ガラス張りの近代的な建物が突如現れ、圧倒される。自然光が差し込むエ...

篠栗四国八十八カ所 ( 福岡県 篠栗町 )
若杉山の麓に広がる、自然豊かな篠栗。9世紀、唐から帰った弘法大師が修法したとされる地で、古来より山岳信仰や真言密教の聖地と伝えられている。 篠栗四国八十八カ所は、尼僧・慈忍が1834(天保5)年、弘法大師の教えを広めるため四国八十八ケ所の霊場を模擬しようとしたが、途中で挫折。当地の藤木藤助が後を継いで88体の仏像を彫刻し...

写真提供:高良大社
高良大社 ( 福岡県 久留米市 )
市の東郊高良山にある。4世紀の創祀と伝え、筑後國一之宮であり古くは九州の宗廟とあがめられた。全国六社のうち九州では一社だけしかない国幣大社*である。 現在の社殿は1660(万治3)年に筑後久留米藩3代藩主・有馬頼利公が造営したもので、天竺様、唐様*、和様を用いた杮(こけら)葺の権現造*。また、山内には孟宗金明竹と呼ばれる...

写真提供:公益財団法人 久留米観光コンベンション国際交流協会
柳坂曽根のハゼ並木 ( 福岡県 久留米市 )
耳納連山北麓、谷川の高曽根川沿いに、南北約1.2kmにわたってつづく江戸時代に植えられた並木。久留米市荘島町生まれで明治時代に活躍した洋画家の青木繁が、「わが国は 筑紫(つくし)の国や 白日別(しらひわけ) 母います国 櫨多き国(はじおほきくに)」と詠んだことでも知られる。1964年(昭和39)年5月には県の天然記念物にも指定さ...

写真提供:朝倉市商工観光課
秋月城下町 ( 福岡県 朝倉市 )
朝倉市の中心市街地から北へ約7km、標高約860mの古処山の麓に広がる城下町・秋月。中世からここに拠った秋月氏が豊臣秀吉に抗して遷されたのち、黒田長政の三男長興が秋月藩初代藩主となり、1624(寛永元)年に新たに城を築き、5万石の城下町として復興した。今は石垣と堀の一部が残り、黒門や長屋門などに昔日の面影が偲ばれる。 町全体...

関門海峡 ( 福岡県 北九州市 / 山口県 下関市 )
本州山口県下関市と九州福岡県北九州市の間に位置する。日本海側の響灘と、瀬戸内海や周防灘を結ぶ海峡で、古くから海上交通の要衝であり、重要な航路であった。 歴史的にも、壇ノ浦の戦いで安徳天皇が入水した地、また巌流島での宮本武蔵・佐々木小次郎の決闘の場でもある。 両側にある海域で生じる潮位差により、急潮流や複雑な潮汐...

筑後川(中下流) ( 福岡県 うきは市 / 福岡県 久留米市 / 福岡県 他 )
大分・熊本に端を発し、福岡・佐賀にまたがって流れる九州第一の大河。その長さ143km、流域面積2,860km2におよぶ。源は九重山地に発する玖珠川と阿蘇外輪山に発する大山川。このふたつの流れが日田盆地で合流して三隅川になる。さらに、大分・福岡県境の渓谷を経て筑紫平野へ流れ込んでいく。ここで筑後川と呼ばれるようになり、...

新川田篭の町並み ( 福岡県 うきは市 )
筑後川の支流の一つである隈上川沿いの谷筋に広がる集落。川水を、水路を使って利用し、石垣で造成した棚田で稲作を営んでいる。上から見ると棟がコの字型をした「くど造り」と呼ばれる形式の民家・平川家住宅*を代表とした寄棟造の茅葺きの主屋など、昔ながらの建築が残り、かつての農村景観を今に伝えている。

写真提供:有田観光協会
有田焼窯元群 ( 佐賀県 有田町 )
有田は日本有数の磁器の産地。17世紀の初めに、朝鮮人陶工・李参平が泉山で陶石を発見したことに始まり、2016(平成28)年に有田焼創業400年を迎えた。町内に約100の窯があるが、県道281号沿いに展示即売する店が軒を連ねる。代表的な窯元としては柿右衛門窯・今右衛門窯・源右衛門窯のほか、香蘭社・深川製磁などがある。

写真提供:有田商工会議所
有田陶器市 ( 佐賀県 有田町 )
1896(明治29)年に、深川栄左衛門と田代呈一の主催で陶磁器品評会が開かれたのがきっかけ。のちに、品評会と同時に開催されるようになった大売出しが陶器市のはじまりだ。現在は有田商工会議所が主催する。延々4kmに窯元、商社の店舗が並ぶ。陶磁器を山と積んで年に一度の蔵ざらえで人気を呼んでいる。4月29日~5月5日の会期中は、全国から...

写真提供:武雄温泉(株)
武雄温泉の大衆浴場 ( 佐賀県 武雄市 )
温泉駅の西方、蓬莱山麓に湧く武雄温泉は「肥前風土記」にも登場し、神功皇后が三韓出兵の折に湯浴みしたと伝わる古湯。湯は弱アルカリ単純泉で、疲労回復・神経痛・筋肉痛・関節痛などに効能があるという。温泉街の中心には竜宮城のような朱塗の楼門が立ち、ひときわ目を引く。設計は東京駅舎などを手がけた辰野金吾で、国の重要文化財に指...

御船山のツツジ ( 佐賀県 武雄市 )
御船山の南西麓にある。鍋島家の別荘跡で、その庭園は第28代藩主茂義が1852(嘉永5)年に京都より絵師を招いて計画を書かせ、3年の歳月を費して造園した。桜・ツツジ・藤・シャクナゲなどが見られる。ことに5万株(20万本)もあるツツジがピンクや白い花をつける4月末から5月にかけてがみごと。

川古のオオクス ( 佐賀県 武雄市 )
市の北、若木町川古の日子神社にある。樹齢3,000年以上といわれ、樹高25m、根回り33m、枝張りは東西・南北27mもある巨木。幹の空洞に稲荷を祭る。国の天然記念物。

虹の松原 ( 佐賀県 唐津市 )
松浦川口の東唐津から浜玉町玉島川尻まで、ゆるい弧を描く砂浜にクロマツがびっしりと根をはっている。幅400~700m、長さ約4.5kmにわたる広大な松原は、日本三大松原*のひとつで、玄海国定公園を代表する景勝地である。初代唐津藩主・寺沢志摩守広高が防風防潮林として植えたもので、現在約100万本。遠浅で波静かな海岸は絶好の海水浴場。

写真提供:肥前名護屋城歴史ツーリズム協議会
名護屋城 ( 佐賀県 唐津市 )
名護屋城は豊臣秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際して拠点とした城で、全国の諸大名が普請し1591(天正19)年10月からわずか6カ月で築城したと伝わる。唐津市の北西、小高い丘陵にあり、玄界灘を望む。名護屋城の周囲約3km以内に、全国各地から集まった名だたる戦国大名の陣屋が130以上も立ち、多いときには20万人以上の人口がいたという...

写真提供:一般社団法人 唐津観光協会
見帰りの滝のアジサイ ( 佐賀県 唐津市 )
相知町の北方、伊岐佐の山間にある落差約100mの滝で、アジサイと紅葉期の景観は絶景となる。標高887mの作礼山に源を発する伊岐佐川にあり、昔から川魚も多く生息し、アユ釣りができる。滝と下流の周辺に約50種・4万株のアジサイが植えられており、1988(昭和63)年以降、毎年6月に「見帰りの滝アジサイ祭り」が催される。 滝のすぐ側に駐...

写真提供:唐津市役所
唐津くんち ( 佐賀県 唐津市 )
唐津神社の秋季例祭で11月2日の宵曳山に始まり、3日の御旅所神幸、4日の翌日祭に終わる。唐津の地主神、唐津大明神の市中巡行に供奉して曳山が従うもので、むかしは傘鉾であったという。 現在の曳山が巡行するようになったのは1819(文政2)年からである。くんち当日は法被姿の若者達が笛・鐘・太鼓にのって、鯛・鳳凰丸・飛龍などの勇壮...

多久聖廟 ( 佐賀県 多久市 )
JR多久駅の南4kmにある孔子廟。1699(元禄12)年、多久家4代茂文が東原庠舎を建てて孔子と四哲(四配)の像を祭り、1708(宝永5)年の完成を待って聖廟にこれらの像を移した。廟は朱塗で屋根は入母屋造、正面に唐破風の向拝をつけている。内外に動植物の彫刻を施した壮麗な建物で、中国様式を取り入れた日本建築である。

写真提供:小城市役所
小城公園のサクラ ( 佐賀県 小城市 )
小城駅の北300mにある。小城藩初代藩主・鍋島元茂と2代・直能が造った名庭園・自楽園と蛍川を公園に整備した。3月下旬には約3,000本の桜が、5月上旬には約2,500本のツツジ・藤が咲き誇り花見客の目を楽しませる。 小城公園自体は1875(明治8)年、佐賀県で最初の公園に指定された。園内には、小城藩主別邸跡や、7代藩主・直愈が建立した小...

写真提供:祐徳稲荷神社
祐徳稲荷神社 ( 佐賀県 鹿島市 )
日本三大稲荷の一つに数えられる九州屈指の神社。石壁山を背後にして本殿が立ち、広い境内に楼門・神楽殿・岩本社・石壁社・奥ノ院などが点在する。本殿は18mの舞台上に三方唐破風の屋根をつけた朱塗の絢燗たるもの。また楼門の随神像や装飾に有田焼が用いられている。本殿へのアプローチは、以前は階段のみだったが、近年、エレベーターも設...

浜中町八本木宿の町並み ( 佐賀県 鹿島市 )
江戸時代に長崎街道の脇街道である多良海道の宿場町として栄えた。また、多良岳山系の清水と佐賀平野の米に恵まれ、江戸中期頃から酒造が次第に盛んになり、江戸後期には10数軒の酒屋があった。現在も全国に銘酒を送り出す酒蔵が3蔵残る。旧多良海道は通称「酒蔵通り」と呼ばれ、醸造町として初めての重要伝統的建造物群保存地区の選定を受け...

大和町巨石群 ( 佐賀県 佐賀市 )
古くは、肥前風土記にも記された大和町下田山中の巨石群。10mをはるかに上回る巨石群は、肥前国一の宮として栄えた与止日女神社のご神体と考えられている。巨石のある山の麓は巨石パークとして市が管理している。釣り体験コーナー、多目的広場などもある。

嘉瀬川の石井樋 ( 佐賀県 佐賀市 )
嘉瀬川は佐賀市三瀬の脊振山系に源を発し、神水川、名尾川などの支川を合わせながら山間部を流れ、途中多布施川を分派し、さらに下流で祇園川を合わせて佐賀平野を貫流し、有明海に注ぐ。一級河川。流域は佐賀市をはじめ3市。 佐賀平野は、干拓によって干潟から農地に変えるなどしてできた土地。佐賀平野での農業用水として活用されてきた...

写真提供:佐賀元祖忍者村 肥前夢街道
佐賀元祖忍者村 肥前夢街道 ( 佐賀県 嬉野市 )
嬉野温泉街の東部に広がる。面積約7万m2に、江戸時代の長崎街道の町並みや風物を、時代考証に基づいて再現。園路に沿って、関所、代官所、本陣、忍者屋敷、からくり時計台、旅籠、芝居小屋などが次々に出現する。園内では大道芸人が妙技を披露し、当時の扮装をした案内人などが、江戸情緒を演出している。「はがくれ忍者屋敷」は、...

大興善寺 ( 佐賀県 基山町 )
JR基山駅の北西4kmにある。717(養老元)年の開山で、のち円仁が中興して栄えた。境内には約5万本のツツジがあって、「つつじ寺」とも呼ばれ4月中~5月中旬がツツジの見頃である。 6月はアジサイ、新緑が美しい。また、11月中旬から下旬にかけて500本のもみじの紅葉も風情がある。

大川内山(伊万里焼) ( 佐賀県 伊万里市 )
市南部の大川内山は1675(延宝3)年に有田南川原山から鍋島藩の御用窯が移されて以来、明治時代まで色鍋島・鍋島青磁などが焼かれていたところである。今日、個人窯がその技術を受け継いでいるが、御用窯時代の関所跡、登窯跡、陶工の墓なども残っている。大川内山のレンガ造の煙突や磁器の破片の落ちた小道には窯元の町の雰囲気がある。 ...

写真提供:平戸城
平戸城 ( 長崎県 平戸市 )
平戸港南部に突き出たような小半島の高台、海抜約50mにある。平戸藩6万1,700石の居城。総面積は約0.18km2。 1599(慶長4)年、平戸藩主の松浦鎮信(法印)が「日の岳城」を築いたが、わずか13年後の1613(慶長18)年に大火により焼失*。「日の岳城」焼失後は平戸港北側の「御館(おたち)」(現在の松浦史料博物館の裏山)に...
神浦の町並み ( 長崎県 平戸市 )
平戸港から約15km北にある的山大島(あづちおおしま)の神浦地区にある港町。江戸中期から昭和初期の町家が連続して建ち並ぶ。 江戸時代、平戸藩の招きにより井元(いのもと)氏が大島政務役として大島に入り、1661(寛文元)年、三代政務役の井元義信が藩主の命令で神浦を捕鯨基地とした捕鯨業を開始した。この捕鯨業は成功を収め、オラ...
島原城 ( 長崎県 島原市 )
島原鉄道の島原駅西側約750m、徒歩12分程度で到達する。森岳城とも呼ばれ、キリシタン弾圧の中心となった城としても有名である。現在の天守閣は五層*であり、1964(昭和39)年に復元されたものである。復元された巽の櫓は北村西望*記念館、丑寅の櫓は民具資料館になっている。 1616(元和2)年、大和から転封された松倉豊後守重政が約7...
島原湧水のまち ( 長崎県 島原市 )
島原湧水群とは、市内約70ヵ所に点在する湧水のことで、水量は1日に約22万トン。古くから水路が整備され、生活用水に利用されてきた。 江戸時代の古文書『寛政4年地変記』には、「前山の北方、4月朔日埋没したる地に清水湧出し、また、上の原の井戸は地変後、にわかに水あふれ、その近方は、すべて数ヵ所より清水湧出し、白土池となる。島...
具雑煮 ( 長崎県 島原市 )
正月の雑煮は、全国各地でその地域ならではの特色があるが、島原地方の雑煮は具だくさん。山の幸と海の幸が盛り込まれ、島原の豊かな食文化の集大成といえる。島原の乱の時、一揆軍で考案*されたと伝えられており、これをもとに初代糀屋善衛エ門が生み出したのが具雑煮の始まりと伝えられ、2代目より屋号を姫松屋に改め現在に至っている。山...
雲仙岳(平成新山・普賢岳) ( 長崎県 島原市 / 長崎県 雲仙市 )
島原半島の中央部にあり、雲仙市と島原市の境界に位置している。標高1,483mの平成新山を主峰とし、西側に連なる普賢岳、妙見岳・国見岳を含めて雲仙岳と総称している。また、絹笠山や九千部岳を含めることもある。山麓に雲仙温泉が湧き早くから観光地として開け、瀬戸内海などとともにわが国岳最初の国立公園の指定をうけている。また、ミヤ...
かんざらし ( 長崎県 島原市 )
「かんざらし」は、古くから島原市一帯で作られてきた伝統のスイーツである。原料となる餅米のくず米を大寒の日前後に石臼で水とともに粉砕し、その後、乾燥させて米粉(白玉粉)にしていたことから、「寒ざらし*」と呼ばれるようになった。 その歴史は江戸時代にまでさかのぼる。年貢として納める米を食べられなかった庶民は、主食とし...
眼鏡橋 ( 長崎県 長崎市 )
長崎市内中央を流れる中島川に架かる。長さ22.35m、幅4.68mで、2つのアーチが川面に映った姿が眼鏡に見えることが名前の由来。 1634(寛永11)年、興福寺*2代住職だった中国江西省出身の唐僧 黙子如定(もくすにょじょう)が架設した日本最古のアーチ型石橋。それ以前、中島川(当時は大川と称した)にかかる橋の多くは木橋だったが、腐...
野母崎の水仙の丘 ( 長崎県 長崎市 )
野母崎は長崎半島の先端を占め、西端部の野母、南部の脇岬、その対岸の樺島*が主な集落。一本釣り・定置網など漁業が主だが、ミカン・ビワの果樹栽培も盛ん。海岸風景が美しく、長崎市近郊の観光地として人気がある。この地域では野母浦祭り*が毎年8月13日に開催されている。祭りは約1300年の歴史があるといわれ、漁業の信仰と海上の安全を...
稲佐山からの夜景 ( 長崎県 長崎市 )
稲佐山はJR長崎駅の約1.8km西方にそびえる標高333mの山であり、南北に尾根を連ねる峰々の中心に位置する。山頂一帯は稲佐山公園として開かれている。山頂からは長崎市街と長崎港を一望でき、湾曲する長崎の地形的特徴が生きた景色が広がる。天候の良い日は雲仙・天草・五島列島までも遠望できる。特に、夜景が有名。長崎港を中心に山々が取り...
長崎孔子廟 ( 長崎県 長崎市 )
長崎市の東山手地区にある中国人が海外に建立した唯一の聖廟(儒教の祖である孔子を祀る廟)。 1893(明治26)年に、在長崎華僑と清朝政府の協力により建てられたもので、建物の細部に至るまで本格的な中国様式が取り入れられている。中心的な建物は、黄色の屋根瓦が鮮やかな儀門と大成殿。これらを取り巻くように立つ「72賢人像」は、孔...
長崎くんち ( 長崎県 長崎市 )
長崎くんちとは、長崎市の諏訪神社の秋季大祭のこと。長崎市内の中心部、特に諏訪神社*とお旅所*と呼ばれる大波止の地に作られた仮宮などで奉納踊りが披露される。くんち*の語源は、旧暦の9月9日を良き日として祝う中国の風習が伝わり、9日(くにち)をくんちと読み、祭礼日の意味としたとする説が一般的である。長崎市では尊称をつけて「...
三菱重工長崎造船所 ( 長崎県 長崎市 )
三菱重工長崎造船所は1857(安政4)年 、徳川幕府によって着工された長崎鎔鉄所*に始まり、現在は長崎港西岸に工場が広がる。かつて戦艦「武蔵」を建造した船台と2つの30万トンドックがあり、護衛艦などの建造・修理改造を行っている。 1898(明治31)年、三菱合資会社三菱造船所の鋳物工場に併設して赤煉瓦造りの「木型場」が建設された...

写真提供:グラバー園
グラバー園 ( 長崎県 長崎市 )
JR西九州新幹線・長崎本線長崎駅から南へ海岸沿いに約2.7km、長崎港を見下ろす南山手にある。園内には、この地がかつての外国人居留地だった時代から遺る旧グラバー住宅、旧オルト住宅*1、旧リンガー住宅*2の3棟を中心にして、長崎市内に散在していた明治期の洋風建築の旧ウォーカー住宅、旧三菱第2ドックハウス*3、旧スチイル記念学校な...
長崎市東山手・南山手の洋風建築群 ( 長崎県 長崎市 )
長崎における外国人居留地は、1858(安政5)年に締結された日米修好通商条約をはじめとする安政の五カ国条約を機に、1859(安政6)年に長崎は開港場となり、外国人居留地が設定されため、同年、長崎湾奥の東側、大浦海岸を中心に埋め立て、造成工事が着手されたことに始まる。居留地は、外交団の要求もあり、順次埋め立て面積が広げられ、山...
端島(軍艦島) ( 長崎県 長崎市 )
長崎港の南西に約18km、船で約40分の海上に浮かぶ端島(はしま)は、石炭の量産地として有名だった島。岩礁の周りを埋め立てられて作られた人工の島であり、島の周囲をコンクリートの岸壁が囲み、高層アパートが密集して建ち並ぶその外観が軍艦「土佐」に似ていることから、「軍艦島」と呼ばれるようになった。 1810(文化7)年に端島で石...

写真提供:長崎ペンギン水族館
長崎ペンギン水族館 ( 長崎県 長崎市 )
長崎ペンギン水族館は長崎市中心街の東側の橘湾に面して立地しており、長崎駅前交通広場バス停からバスで約30分で到達する。 長崎ペンギン水族館の前身である長崎水族館は1959(昭和34)年に開館しているが1998(平成10)年に閉館した。しかし長崎市民やペンギンファンの願いもあり、移転・規模縮小の上で2001(平成13)年に体験型水族館...

卓袱料理 ( 長崎県 長崎市 )
長崎においては中国(唐風)料理は近世以前から中国貿易の進展とともに伝わっていたが、1635年(寛永12)年から中国貿易が長崎港に限定され、さらに1689(元禄2)年に唐人屋敷(現・長崎市館内町)が完成すると、中国人の往来が制限されたため、この地が中国(唐風)料理の日本における本場となった。この中国(唐風)料理を供する際に、日本...

写真提供:一般社団法人 対馬観光物産協会
浅茅湾 ( 長崎県 対馬市 )
対馬の中央南よりの部分が西側から沈降してできた典型的なリアス海岸。西側には幅3kmの大口瀬戸が口を開き、東側は江戸・明治に掘削された大船越瀬戸と万関瀬戸で対馬海峡に通じている。 湾内には、仁位(にい)湾、濃部(のぶ)湾、洲藻浦(すもうら)などの支湾があり、さらに細かい湾入がいくつも見られる。その湾入の間には無数の半島...
万松院 ( 長崎県 対馬市 )
7世紀から対馬国の国府が置かれ、江戸時代には対馬藩*10万石の城下町であった厳原町の山すそにある。1615(元和元)年、2代藩主宗義成(そうよしなり)が、父である初代藩主宗義智(そうよしとし)の冥福を祈って建立した宗氏の菩提寺。 仁王像の立つ桃山様式の山門は、対馬最古の木造建造物と言われている。山門横には、百雁木(ひゃく...

写真提供:一般社団法人 対馬観光物産協会
椎根の石屋根倉庫 ( 長崎県 対馬市 )
食料品や衣類、農具や漁具などの日常生活用品を保管するための倉庫。高床式の倉庫に平たい自然石で葺いた屋根を乗せている。柱は椎材で、周囲の壁、床、天井には松材が用いられている。 対馬は、冬になると強い北西の季節風が吹きつける。強い風や火事から貴重品を守るため、石で屋根を葺いた頑丈な倉庫が造られた。対馬には板状に薄くは...
和多都美神社 ( 長崎県 対馬市 )
浅茅湾の入り江のひとつ仁位(にい)湾にある古社。祭神は彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と豊玉姫命(とよたまひめのみこと)の夫婦神。豊玉姫命は海神である豊玉彦尊(とよたまひこのみこと)の娘で、「古事記」の海幸山幸神話*に登場する女神。航海守護・安産・豊漁などの庶民にも身近な神徳があるとされる。 豊玉彦尊がこの地...

写真提供:一般社団法人 新上五島町観光物産協会
若松瀬戸 ( 長崎県 新上五島町 )
新上五島町若松郷は約30の群島から成り、若松瀬戸を挟み中通島の西側の西島を含めて若松郷という。新上五島町奈良尾港から自動車で16.5km、約20分に位置する。若松瀬戸は若松島と中通島の間の瀬戸で複雑に変化するリアス海岸で西海国立公園に指定されている。瀬戸の急流と点在する小島が調和して美しい景観となっている。海がきれいな若松瀬...
大瀬崎断崖 ( 長崎県 五島市 )
福江島の最西端に位置する大瀬埼灯台は、大瀬崎断崖の上に建ち、九州本土で最も遅い時間に夕陽が沈む場所。福江港から大瀬崎灯台の展望台まで自動車で37km、約1時間。大瀬崎断崖は西海国立公園の特別地域に指定されており、削りだしたような断崖が約20kmも続く。 大瀬埼灯台に向かう道沿いには、灯台を望む展望台が複数あり、晴れた日には...
鬼岳火山群 ( 長崎県 五島市 )
鬼岳火山群*は約50万年前に始まった火山活動によって形成されたなだらかな台地の上に、5万年前からの噴火による火山噴出物が重なり合って臼のような形になった。約1万8000年前の最後の噴火によって山頂が削り取られ、臼のような形をしている。鬼岳、火岳、城岳、箕岳、臼岳などの火山から形成されている。その中でも鬼岳は、その恐ろしい名...

写真提供:雲仙市 観光物産課
雲仙のミヤマキリシマ群落 ( 長崎県 雲仙市 )
ミヤマキリシマは、九州各地の高原に自生するツツジの一種。長崎県では雲仙の標高700m以上の高地に群生していて、県花に指定されている。別名はウンゼンツツジ。町の北東、雲仙ゴルフ場付近一帯に群落する「池の原のミヤマキリシマ」は国の天然記念物に指定されている。 霧島へ新婚旅行に訪れた植物学者・牧野富太郎*が発見し、「深い山...
雲仙温泉 ( 長崎県 雲仙市 )
長崎市内から車で約1時間30分、雲仙岳の南西麓、標高約700mに開ける高原温泉。古湯・新湯・小地獄に分かれ、1653(承応2)年に始まるといわれる古湯は無気味な噴煙を上げる雲仙地獄の北西付近にあって、繁華な旅館街を作っている。また、新湯は明治になって長崎に近いことから外国人の避暑地、高原リゾート*として開発され、雲仙観光ホテル...
大浦天主堂 ( 長崎県 長崎市 )
長崎市の南山手の丘にある、現存する日本で最古の教会。1597(慶長元)年に殉教した日本二十六聖人に捧げられた教会で、正式には「日本二十六聖人殉教者聖堂」と言い、殉教地である西坂の丘に向かってゴシック様式の教会が立つ。 1860(万延元)年に長崎に外国人居留地が開かれた後、居留地に住む外国人向けの教会として、パリ外国宣教会...
大野教会堂 ( 長崎県 長崎市 )
長崎市下大野町、西彼杵半島西岸の外海地域にある教会。国道202号線、長崎バスで大野下車、徒歩15分。1879(明治12)年、パリ外国宣教会のフランス人司祭ド・ロ神父(Marc Marie De Rotz:1840-1914)が外海地区の主任司祭として赴任し、神父の設計により1893(明治26)年に、神浦・大野地区の信徒26戸のために建設された。信徒は高齢で貧しい...
浦上天主堂 ( 長崎県 長崎市 )
県営バス・長崎バスで天主堂下・センター前・神学校前下車、徒歩すぐ。長崎市の浦上地区にある。 浦上は長崎開港当時、幕府と有馬氏のキリシタン領となったところで、歴史的にキリスト教の影響が強く、キリスト禁教後も多くの信徒が潜伏して信仰を続けていた。1865(元治2)年、浦上の潜伏キリシタンが大浦天主堂を訪れ、自分たちの信仰を...
出津教会 ( 長崎県 長崎市 )
長崎バスで出津文化村下車、徒歩8分。西彼杵半島西岸の外海地域*にある教会。パリ外国宣教会のフランス人司祭、ド・ロ神父*が設計し、私財を投じて1881(明治14)年に、レンガ造りの小さな聖堂を建設した。そののち、信徒がふえたので、1891(明治24)年、現在の祭壇方向に約1.5倍の長さに広げ、上に十字架をいただき小塔を建てた。さらに1...

写真提供:五木村教育委員会
五木・五家荘の渓谷 ( 熊本県 五木村 / 熊本県 八代市 )
熊本県五木村と八代市泉町の五家荘は九州脊梁山地にあり、国道445号線や川辺川により隣接する。地理的・民俗的な共通点も多いことから「五木・五家荘地域」と呼ばれる。 五木村は県南部の球磨郡北端に位置し、九州自動車道人吉ICから車で約50分にある。標高1,000m以上の山々が連なる山岳地帯で、村の中央を川辺川が流れ、川沿いに国道445...

不知火 ( 熊本県 宇城市 )
熊本県南西岸から鹿児島県北西岸にかけての九州本土と天草諸島に囲まれた八代海(別名不知火海)上に見られる自然現象で、旧暦8月1日(八朔)の未明に八代海(不知火海)上に見られる無数の火を不知火と呼ぶ。不知火が発生する要因は不明な点もあるが、潮の干満差や海上の気温差など、八代海北東部海域の地形と気象条件の下に、漁火や対岸の...

八代妙見祭 ( 熊本県 八代市 )
熊本県中央の八代市、九州自動車道八代ICから車で5分、JR八代駅からバスで10分に八代神社がある。妙見祭は八代神社の秋の大祭で、江戸時代から約380年続く八代地方最大の祭礼行事である。 11月1日から1か月にわたり関連行事が行われる中で、メインとなるのは11月22日のお下りと23日の神幸行列お上りである。お下りは、22日の午後に神馬を...

黒川温泉 ( 熊本県 南小国町 )
熊本県北部の阿蘇郡南小国町、九州自動車道熊本ICから車で約1時間10分、大分自動車道日田ICから車で1時間にある。阿蘇くじゅう国立公園に隣接し、大分県との県境に位置する。 標高700mの田の原川渓谷沿い直径5km圏内に、旅館と店舗がそれぞれ約30軒ずつの閑静な山あいに位置する小さな温泉郷で、熊本を代表する温泉地のひとつとされる。 ...

第一白川橋梁 ( 熊本県 南阿蘇村 )
熊本県北東部の阿蘇郡南阿蘇村、九州自動車道熊本ICから約45分にある。JR豊肥本線と南阿蘇鉄道が乗り入れる立野駅の南東1,500mほどに位置する。 阿蘇カルデラ内側の平地は中央火口丘により南北に二分され、北の阿蘇谷と呼ばれる地域には黒川が、南の南郷谷と呼ばれる地域には白川が流れる。二つの川は立野で合流し、外輪山唯一の切れ目で...

写真提供:地獄温泉青風荘.
地獄温泉 ( 熊本県 南阿蘇村 )
地獄温泉は、南阿蘇鉄道の長陽駅から車で約15分、阿蘇五岳の一峰、烏帽子岳の西南中腹、標高750mの山中に位置する。「阿蘇神社の祭神である健磐龍命(たけいわたつのみこと)が、身重の妻の姿を隠す屏風とするために一夜のうちにこしらえた」と伝わる、夜峰山(よみねやま)の火口内にある。地獄温泉の由来は温泉の裏山に火山ガスが噴出し草...

白川水源 ( 熊本県 南阿蘇村 )
熊本県北東部の阿蘇郡南阿蘇村、九州自動車道熊本ICから車で約50分、南阿蘇鉄道南阿蘇白川水源駅から徒歩約10分にある。阿蘇カルデラ内の中央火口丘群の南の裾野に位置する。 熊本市内の中央を流れる一級河川の白川は、流水のほとんどが上流域の阿蘇カルデラに降り注いだ雨や湧水が集まったもので、この白川の源となるのが白川水源である...

天草西海岸 ( 熊本県 天草市 / 熊本県 苓北町 )
天草下島*の西海岸域一帯(以下、天草西海岸)は、熊本市から西南西へ約80km、車で約2時間半の距離にあり、天草灘(東シナ海)に面している。 天草西海岸は、約7500万年前に堆積した姫浦層群などの地層が隆起し、波の侵食によってできた高さ数十mに及ぶリアス式海岸で、海蝕洞門や鍾乳石も見られる。また海には大小様々な島や岩礁が浮か...

﨑津教会 ( 熊本県 天草市 )
﨑津教会のある﨑津集落(天草市河浦町)は天草下島*の南部に位置する漁村で、熊本市から西南へ約85km、車で約3時間の距離にあり、羊角湾の北岸に面している。古くは“佐志の津”とも呼ばれていた。1563(永禄6)年にキリスト教布教のため日本に訪れた、ポルトガル人宣教師ルイス・フロイスが著した「日本史」によると、1569(永禄12)年にア...

写真提供:人吉市
球磨川(人吉付近) ( 熊本県 錦町 / 熊本県 人吉市 / 熊本県 球磨村 )
球磨川は、その源を熊本県球磨郡水上村の銚子笠(標高1,489m)に発し、多くの支川を合わせながら流れる。人吉市近くでは川辺川と合流して水量も豊かな河川となり、人吉盆地をほぼ西に向かって貫流する。盆地を抜けると、流向を北に転じながら山間の狭窄部を縫うように流下し、河口付近の八代市では、球磨川の本流、分派した前川、南川が広大...
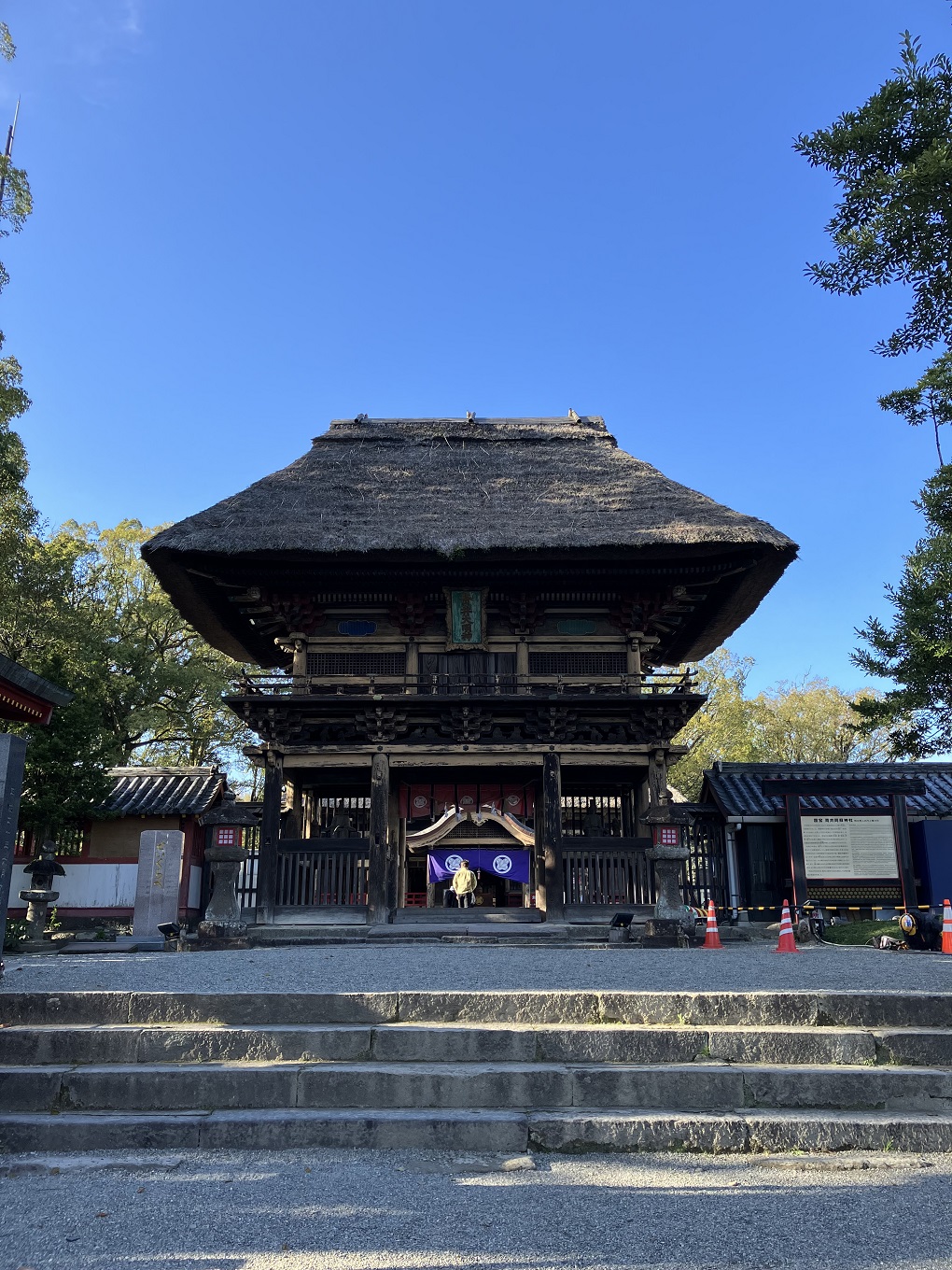
青井阿蘇神社 ( 熊本県 人吉市 )
熊本県南部の人吉市、九州自動車道人吉ICから車で10分、JR肥薩線人吉駅から南へ徒歩5分にある。 阿蘇市一の宮町の阿蘇神社の分霊を勧請したとされ、阿蘇神社に祀られる12神のうち、神武天皇の孫神で阿蘇を開拓した健磐龍命(たけいわたつのみこと)を主神として、その妃の阿蘇津媛命(あそつひめのみこと)、その子供である国造速瓶玉命(...

人吉城 ( 熊本県 人吉市 )
人吉城は、JR肥薩線の人吉駅、くま川鉄道の人吉温泉駅から東南東へ約1.3km、徒歩で約20分の距離にある。球磨川と胸川の合流地点に位置する。球磨川と胸川を自然の堀とし、球磨川に迫る険しい地形を利用した要害で、国指定史跡となっている面積は216,000m2。 もと平頼盛の代官矢瀬主馬佑の山城であったが、1198(建久9)年、相...

天草松島 ( 熊本県 上天草市 )
熊本市から南西へ約40km、車で約1時間半、天草諸島の大矢野島(上天草市)*と天草上島(上天草市、天草市)*の間に浮かぶ大小30あまりの島々は、北東~南西方向に走る丘陵性山地が沈水したもので、地質は主に新生代第三紀の火山活動に由来すると思われる白い凝灰岩などからなっている。アカマツ、クロマツをはじめとした緑のマツで覆われた...

旧国鉄宮原線コンクリートアーチ橋梁群 ( 熊本県 小国町 )
旧国鉄宮原線は、大分県南西部の九重町恵良駅から熊本県最北端の小国町肥後小国駅までの26.6kmを結ぶ線路で、35年という工期をかけて1954(昭和29)年に開通した。通勤・通学や木材等の搬送に使われていたが、国鉄再建法による赤字路線の廃止により、開通から30年後の1984(昭和59)年、九州で最初に廃線となった。 山間部を通る線路であ...

通潤橋 ( 熊本県 山都町 )
熊本県東部の上益城郡山都町、九州中央自動車道山都通潤橋ICから車で約10分にある。 阿蘇南外輪山の裾野に位置する山都町の白糸台地は、川が削り取った深い谷に囲まれて川から水を引くことができず、湧き水を利用した農業に限られていた。この白糸台地に農業用水を送るため、現在の町長にあたる惣庄屋布田保之助(ふたやすのすけ)*が代...

五老ヶ滝 ( 熊本県 山都町 )
熊本県東部の上益城郡山都町、九州自動車道山都通潤橋ICから車で約10分にある。 阿蘇南外輪山の裾野に位置する山都町には数多くの滝が点在し、矢部四十八滝*と呼ばれる。その中で水量、落差ともに最大級である。滝の周囲は阿蘇山の噴火に起因する溶結凝灰岩から成り、滝つぼの壁面に柱状節理*が見られる。 五老ヶ滝という名前の由来...

写真提供:山鹿市教育委員会
チブサン古墳 ( 熊本県 山鹿市 )
熊本県北部の山鹿市、九州自動車道菊水ICから車で15分にある。 全長55m以上、墳丘長44m、高さ7mの6世紀前半に造られた前方後円墳。長軸をほぼ東西に向け、南に入口がある複室の横穴式石室で、後円部にある全長6mほどの石室*には前室(約1.9m四方)と後室(約3.6m四方)の二つの正方形の部屋がある。後室には石屋形*が置かれ、屋根全体...

山鹿灯籠まつり ( 熊本県 山鹿市 )
山鹿灯籠まつりの行われる山鹿市中心部までは、九州自動車道菊水ICから東北東へ約8km、車で約15分。山鹿灯籠まつりは、毎年8月16日に大宮神社例祭「燈籠祭」で斎行される神事と、8月15日、16日の2日間に渡り催される奉納踊りや千人灯籠踊り、花火大会や松明行列など関連行事からなっている。 燈籠祭の起源は、一説によると、深い霧に行く...

八千代座で上演される歌舞伎 ( 熊本県 山鹿市 )
八千代座のある山鹿市中心部までは、九州自動車道菊水ICから東北東へ約8km、車で約15分。 八千代座は、1910(明治43)年、山鹿の商工会が町の繁栄を図るため劇場組合を作り、1株30円の株を募って建てた木造2層の本格的な芝居小屋。入母屋造妻入、瓦葺の本屋の周囲に瓦葺の庇を設けている。間口約29m、奥行き約35mの建物で、正面に櫓を立て...

鞠智城 ( 熊本県 山鹿市 )
鞠智城は、九州自動車道植木ICから北東へ約12km、車で約20分の距離にある。菊池川中流域の標高90~170m前後の丘陵地に位置し、北は福岡県境に連なる山々を望み、南は菊池川により形成された平野が広がっている。面積は南北約1.2km、東西約1km、約550,000m2の規模を有し、総延長約3.5kmの土塁線や急峻な崖線で囲まれている。 ...

藤崎八旛宮 ( 熊本県 熊本市 )
熊本市街地の北東、熊本市電水道町から徒歩15分、熊本電鉄藤崎宮前から徒歩5分にある。熊本の総鎮守といわれ、熊本市を代表する神社の一つである。 935(承平5)年、朱雀天皇の平将門の乱平定の勅願により、京都の石清水八幡大神(応神天皇、比咩大神(ひめおおかみ)、神功皇后)を国家鎮護の神として熊本の地に勧請したのに始まる。社地...

本妙寺 ( 熊本県 熊本市 )
熊本城の北西に位置し、熊本市電本妙寺入口から徒歩約10分にある。 中尾山(本妙寺山)中腹に建つ加藤家の菩提寺で、開創から400年以上の歴史を持ち、九州における日蓮宗の巨刹として格式を誇る。境内には加藤清正の廟所がある。 1585(天正13)年、清正が父清忠の菩提のため大阪に建立したのにはじまり、1588(天正16)年、清正が肥後...
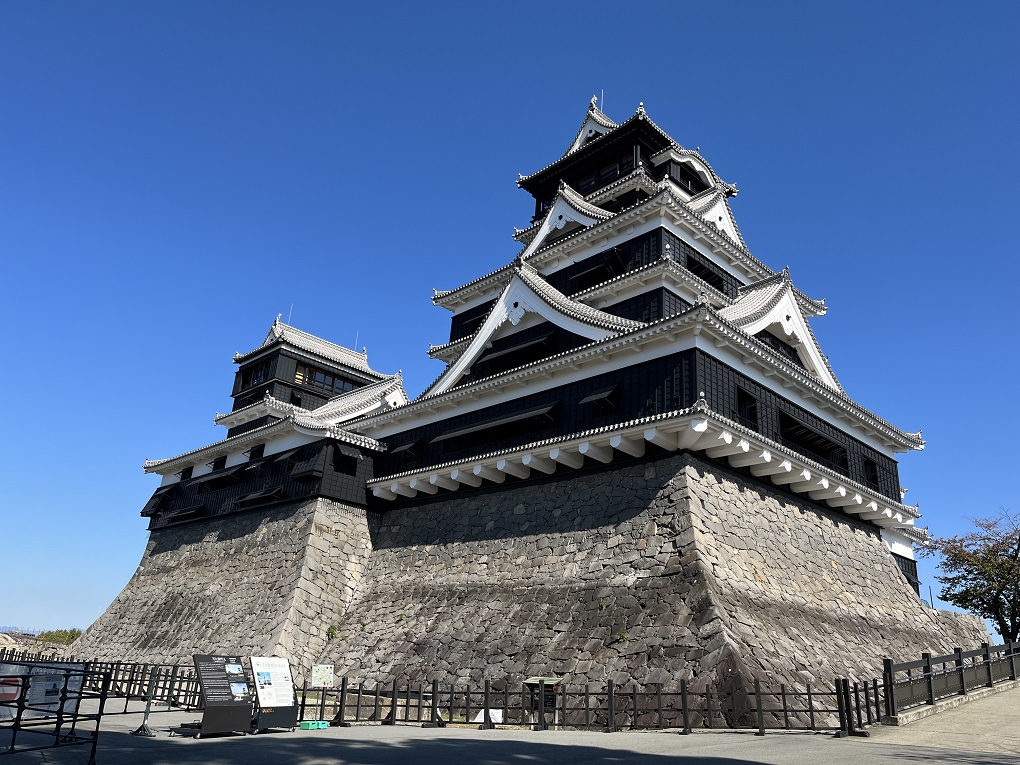
熊本城 ( 熊本県 熊本市 )
熊本市の中心部、熊本市電熊本城・市役所前から徒歩10分にある。 城域は茶臼山*と呼ばれた丘陵地全体を占め、周囲5.3km、総面積は980,000m2におよぶ。往時は大小の天守閣をはじめ、櫓49、櫓門18、城門29を持ったとされ、武者返し*と呼ばれる独特な反りをもつ石垣がめぐらされた、実践を想定した巨大要塞、難攻不落の堅城とし...

水前寺成趣園 ( 熊本県 熊本市 )
熊本市街地の南東、熊本市電水前寺公園から徒歩約4分にある。面積約73,000m2の回遊式の大名庭園で、夏目漱石*の「湧くからに流るるからに春の水」の句で知られる。 1632(寛永9)年、加藤家の改易により肥後に入国した細川家三代細川忠利*が熊本城南東の湧水地に水前寺を建立し、同地に数寄屋風の茶屋を建て「水前寺御茶屋」...

菊池渓谷 ( 熊本県 菊池市 )
熊本県北部の菊池市東端、九州自動車道植木ICから車で約50分、熊本駅から車で約1時間30分にある。阿蘇外輪山の北西に位置する。 菊池渓谷は菊池川の源流部をなす全長約4kmの渓谷で、標高約800m地点から流れ落ち、標高500m地点で終わる。阿蘇火山の莫大な噴出物からなる地層で、天然の広葉樹が渓谷を覆い囲むように迫り、その間を阿蘇外...

三角西港 ( 熊本県 宇城市 )
熊本県中央部の宇城市、九州自動車道松橋ICから車で約50分、JR三角駅から車で約10分、宇土半島の西端にある。 日本に現存する明治時代の石積港湾施設で、石積の埠頭、水路、建造物などがほぼ完全な形で残っている。 1876(明治9)年の神風連の乱や1877(明治10)年の西南の役で焦土と化した熊本県の殖産興業を目的として港湾を建設する...

阿蘇山 ( 熊本県 阿蘇市 / 熊本県 南小国町 / 熊本県 小国町 / 熊本県 産山村 / 熊本県 高森町 )
九州の中央部に位置する複式火山*で、世界的に有名な活火山。阿蘇山という単体の山はなく、東西約18km、南北約25km、面積約350km2の世界最大級規模のカルデラ*の中央に並ぶ阿蘇五岳*を中心とした中央火口丘群の総称を阿蘇山と呼ぶ。広い意味では、外輪山や火口原も含めて阿蘇山と呼ぶ。 阿蘇火山の活動は約27万年前に始まり...

草千里ヶ浜 ( 熊本県 阿蘇市 )
熊本県北東部の阿蘇市、九州自動車道熊本ICから車で約1時間20分、JR阿蘇駅から車で約20分にある。 標高約1,100mに位置し、阿蘇五岳のひとつ烏帽子岳の北麓に広がる直径約1km、面積約785,000m2の大草原で、烏帽子岳の側火山*として活動した草千里ヶ浜火山の火口跡である。約3万年前に形成された直径1kmほどの火口の中に約400m...

写真提供:阿蘇市
阿蘇の野焼き ( 熊本県 阿蘇市 )
阿蘇五岳の山裾や外輪山の稜線に広がる広大な草原が今も残るのは、1,000年以上もの間、人々が自然と共生しながら、放牧、採草、野焼きなどを続けて維持してきたからである。 毎年2月下旬から3月に行われる野焼きは野草地に火をつけて地表面を焼く作業で、野焼きにより家畜に影響を及ぼす害虫を駆除し、燃えた灰が栄養となり芽吹きを促し、...

阿蘇のあか牛料理 ( 熊本県 阿蘇市 / 熊本県 小国町 / 熊本県 産山村 / 熊本県 高森町 / 熊本県 南阿蘇村 )
あか牛は阿蘇地方を中心とした熊本県内の中山間地域で飼養され、全国のあか牛の95%以上が熊本で生産されている。耐寒・耐暑性に優れ、放牧に適し、おとなしい性格で飼育しやすいという特性を持つ。一般的な和牛が穀物で飼育されるのに比べ、あか牛は牧草や野草で育てられる。 あか牛は正式には褐毛和種(あかげわしゅ)のことで、熊本系...

写真提供:熊本県観光連盟
ヒゴタイ公園 ( 熊本県 産山村 )
熊本県北東部の阿蘇郡産山村、九州自動車道益城熊本空港ICから車で約1時間30分、JR豊肥本線宮地駅から車で約40分にある。 標高900mに位置し、南から西にかけて外輪山、阿蘇五岳、瀬の本高原を、東には九重連山を見晴らす。敷地面積は約15万m2で、8月中旬から9月中旬に産山村の村花であるヒゴタイが咲くほか、ハルリンドウ、カ...

大江教会 ( 熊本県 天草市 )
大江教会は天草下島*の南部に位置し、熊本市から西南へ約85km、車で約3時間の距離にある。 戦国時代、領主の天草氏は1566(永禄9)年に布教を許可した。その後、キリシタン大名・小西行長*が肥後南部を支配すると、天草氏は配下になり、豊臣秀吉の「伴天連追放令*」後も宣教師を庇護した。禁教後、この地の潜伏キリシタンは島原天草一...

写真提供:由布市
由布岳 ( 大分県 由布市 )
標高1,584mの双耳峰。鶴見岳とともに別府市の背景をなすトロイデ型(鐘状)の秀峰で、豊後富士とも呼ばれている。10月下旬には潅木や草が微妙に色づき、冬は霧氷が美しい。山頂は東西2峰からなり、眺望は雄大で、初夏にはミヤマキリシマ、夏にはミヤマオダマキ、シコクフウロウなどの高山植物が花咲く。 主要な登山道は正面登山口で、車で...

湯平温泉 ( 大分県 由布市 )
町の南端、大分川支流の花合野川に沿った山間にある温泉。温泉街の中央に敷かれた長い石畳の道は、およそ300年前の享保年間(江戸時代)に病魔退散を祈願した工藤三助により建設されたもの。その狭い石畳の道を挟み、旅館や土産物店が立ち並び、まさに湯治場というにふさわしい雰囲気がある。弱食塩泉、60~80度。胃腸病に効能があるという。

祖母山 ( 大分県 豊後大野市 / 大分県 竹田市 / 宮崎県 高千穂町 )
大分・宮崎県境にそびえる標高1,756mの山。祖母傾山系の主峰であり、急峻な山相が特徴。火山活動によって形成された山であるため巨大な岩石が随所に見られる。ブナ・モミ・アカマツなどの原生林におおわれ、特別天然記念物に指定されているニホンカモシカや、イワナ、ムササビなどが生息する。祖母山周辺は銅や錫、マンガン、水晶など、鉱物...

富貴寺 ( 大分県 豊後高田市 )
市の東部、国東半島ののどかな山里にある。六郷満山*の中で、満山を統括した本山末寺の一つで、寺伝では718(養老2)年の創建と伝える。大堂と庫裏が立つだけだが、大堂のまわりには五輪塔・笠塔婆・宝篋印塔などの石造物も残り、古刹らしい雰囲気に包まれている。 大堂は国宝指定。平安後期の建築で、平等院鳳凰堂や中尊寺金色堂などと...

写真提供:豊後高田市
田染荘 ( 大分県 豊後高田市 )
火山活動でできた円錐形の国東半島。その南部に広がる田染盆地では、743(天平15)年の墾田永年私財法の成立によって、この地を豊かな水田地帯にしようと、農民や宇佐神宮が尽力。誕生したのが、この田染荘だ。宇佐神宮の「本御荘十八箇所」とよばれる根本荘園のひとつで、最も重用視された荘園として栄えた。土地の地形をそのまま利用した、...

別府八湯 ( 大分県 別府市 )
鶴見岳と伽藍岳の2つの火山の麓に立地する別府市。市内いたるところに多数の温泉が湧き出ている。日本一の湧出量を誇り、日本にある10の泉質のうち、7種が存在する。街中の随所から立ち昇る湯けむりも印象的な風景として知られる。別府・鉄輪・観海寺・明礬・亀川・柴石・堀田・浜脇の市内全域に点在している8カ所の温泉地を総称して、別府八...

写真提供:公益社団法人ツーリズムおおいた
鉄輪温泉 ( 大分県 別府市 )
市街の北西部、扇山の北東裾野にある温泉。もといわゆる地獄地帯であったのを一遍上人が埋めて開いたといわれ、湯治場として発展した。今もいたるところから蒸気が噴出して壮観であり、別府観光のハイライトである地獄もここに集中している。外湯と呼ばれる立ち寄り共同浴場も多い。 九州横断道路の入口になって以来、宿泊施設は近代化し...

写真提供:日田市役所
日田祇園祭 ( 大分県 日田市 )
約300年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事。毎年7月、疫病や風水害を払うとともに安泰を祈念し、絢爛豪華な山鉾が祇園囃子の音色とともに隈・竹田地区、豆田地区の町並みを巡行する。毎年作り替えられる山鉾は「ヤマ」と呼ばれ、現在、祭りで曳き出されるヤマは、隈地区の三隈町、大和町、竹田地区の川原町、若宮町、豆田地区の下町、上町、港...

写真提供:添田町役場
英彦山 ( 福岡県 添田町 / 大分県 中津市 )
福岡県田川郡添田町と大分県中津市山国町の県境に広がる。北岳・中岳・南岳の3つのピークがあり、標高は1,199m。かつては出羽の羽黒山、熊野の大峰山と並ぶ日本屈指の霊場、修験場として栄え、最盛期の江戸時代には、俗に「彦山三千八百坊」といわれ、3,000人の衆徒と坊舎が800を数えたと伝えられている。山中には修験場を思わせる、数多くの...

写真提供:一般社団法人 中津耶馬渓観光協会
耶馬渓 ( 大分県 中津市 )
英彦山に源を発する山国川を中心に、東西36km、南北32kmに及ぶ地域を占め、本・羅漢寺・深・裏・奥・東・羽高・津民・南・椎屋の耶馬十渓に大別される。耶馬渓溶岩台地が浸食されたもので、頼山陽*が絶賛して以来、無数の岩峰が造形する南画的風景で名高い。5月の新緑や10・11月の紅葉期の景観は格別である。 みどころとして有名なのは、...

耶馬渓橋 ( 大分県 中津市 )
山国川に架かる石橋で、青の洞門*の下流約500mにある。1923(大正12)年に竣工。日本で唯一の八連石造アーチ橋で、橋長116m。日本百名橋の一つ。また地元では「オランダ橋」という愛称で呼ばれているが、これは長崎県に多い水平な石積み方式であるため、と推測されている。

岡城跡 ( 大分県 竹田市 )
瀧廉太郎*の名曲「荒城の月」*を生んだ岡城跡は、JR豊後竹田駅の東方にある。1185(文治元)年、緒方三郎惟栄(これよし)が、稲葉川と白滝川が合流する天然の高台に築城した。のち1594(文禄3)年、中川秀成(ひでしげ)が入城し、明治まで中川氏13代の居城となった。城郭は中川氏によるもので、本丸、二の丸、三の丸、西の丸などから成る。...

写真提供:竹田市役所
くじゅう連山 ( 大分県 九重町 / 大分県 竹田市 )
玖珠郡九重町と竹田市久住町にまたがる連山で、阿蘇くじゅう*国立公園の中部に位置する。久住山(1,787m)を盟主として、大船山(たいせんざん)、星生山(ほっしょうざん)、三俣山(みまたやま)など1,700m級の山々が11峰、1,000m以上の山々が35峰連なり、“九州の屋根”と呼ばれている。 山群は大別して久住、大船、涌蓋(わいた)の3火...

写真提供:長者原ビジターセンター
坊ガツル湿原 ( 大分県 竹田市 )
くじゅう*の山々に囲まれた標高1,200~1,300m付近に位置する湿原。2005(平成17)年、長者原のタデ原湿原とともにラムサール条約*に認定された。希少な植物の宝庫でもある。

長湯温泉 ( 大分県 竹田市 )
久住山を背に、芹川のほとりに湧く温泉。竹田市直入町の中心エリアであり、付近には旅館や商店が立ち並ぶ。「風土記」にも記載があるとされる古い歴史をもつが、江戸時代に岡藩主・中川氏に愛され、岡藩普請による御前湯が作られ、温泉地として整っていった。 高濃度の炭酸を含む茶褐色の湯で知られ、慢性消化器病などに効能があるという...

竹田の井路群 ( 大分県 竹田市 )
竹田市周辺には、「井路」と呼ばれる農業水利施設が多く残っている。井路とは水路、灌漑用水路のこと。 「音無井路円形分水」は、竹田から高千穂へ向かう県道8号からさらに細道に入った場所にある。円形分水の名前の通り、水の争いを解決することを目的に造られた、公平に水を分配する仕組み。1934(昭和9)年に完成した。円形の真ん中に...

白水ダム ( 大分県 竹田市 )
JR豊後竹田駅の南西約11kmの里山にある。水に恵まれない周辺地域の安定水源として、1934(昭和9)年着工、1938(昭和13)年に完成した石造りのダム。正式名称は「白水溜池堰堤水利施設一溝」という。 設計は小野安夫技師によるもので、堰堤下の岩盤が弱いため、水圧を抑える工夫がされている。右岸は「武者返し」と呼ばれる曲面流路、左岸...

高崎山のサル ( 大分県 大分市 )
大分・別府両駅のほぼ中間に位置する標高628mの高崎山に約1,200頭(2018(平成30)年12月現在)の猿が生息する。一帯は猿の生息地として国立公園に指定され、保護されている。公園の中央部に設けられた餌をまく寄せ場を中心に集まる。 もともとは、1952(昭和27)年に高崎山一帯の猿による農作物の被害を守るため餌付けしたもの。1955(昭...

両子寺 ( 大分県 国東市 )
国東半島のほぼ中央にそびえる両子山の南中腹にある。718(養老2)年の創建と伝える六郷満山中山本寺(山岳修行の根本道場)で、江戸時代には杵築城主松平氏の祈願所となり、六郷満山の総持院として隆盛を誇った。 現在の本堂である護摩堂は明治の再建だが、堅固な石垣や奥の院本堂・総門・仁王像などに往時がうかがえる。境内は紅葉の名...

原尻の滝 ( 大分県 豊後大野市 )
大野川の支流・緒方川にかかる幅120m、高さ20mの滝。ゆるやかに弧を描く岩壁を豊かな水流が落下する雄大・華麗な瀑布で、その景観から、「大分ナイヤガラ」の別名もある。この岩は、約9万年前に阿蘇山の火山活動によって生まれた溶結凝灰岩でできており、火砕流が冷えて固まる際にできた柱状節理もみられ、「おおいた豊後大野ジオパーク」のジ...

久住高原 ( 大分県 竹田市 )
くじゅう連山*の南、東西10km・南北8kmに及ぶ広大な高原。阿蘇くじゅう国立公園に属する。標高600~1,000mで、浅い谷が放射状に刻まれ、ススキ・ネザサなどにおおわれている。春から夏にかけては、緑のじゅうたんを敷き詰めたような草原となり、いっせいに放牧が行われる。 毎年、放牧地で行われる野焼きは、春の訪れを告げる風物詩。山...

飯田高原 ( 大分県 九重町 )
くじゅう連山*の北側、標高800~1,000mの地に広がる約8km四方の高原。阿蘇くじゅう国立公園に属する。この地を訪れた川端康成が、その美しさに魅せられ、小説『千羽鶴』の続編『波千鳥』において飯田高原を描いている。 別府と阿蘇を結ぶ「やまなみハイウェイ」が中央を縦断しており、阿蘇方面からアプローチすると牧ノ戸峠からハイウェ...

九重“夢”大吊橋 ( 大分県 九重町 )
2006(平成18)年10月30日にオープン。長さ390m、高さ173m、幅1.5m。歩道専用として日本一の高さを誇る吊橋。橋からは、日本の滝百選にも選ばれた震動の滝(雄滝)や雌滝を望み、眼下には筑後川の源流域を流れる鳴子川渓谷の原生林が広がる。遠くに、三俣山や涌蓋山など雄大なくじゅう連山*が横たわり、360度の大パノラマが絶景。

写真提供:臼杵石仏事務所
臼杵石仏 ( 大分県 臼杵市 )
凝灰岩の岩壁に刻まれた磨崖石仏。平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫刻されたと言われる。その規模と数、また彫刻の質の高さにおいて、わが国を代表する石仏群であり、1995(平成7)年6月15日には磨崖仏では全国初、彫刻としても九州初の国宝に指定。61体ある中、59体が国宝となった。石仏群は4群に分かれ、地名によって、ホキ石仏第1群(...

写真提供:宇佐神宮
宇佐神宮 ( 大分県 宇佐市 )
宇佐駅の西約3.5km、国道10号の南側に社叢が広がる。豊前国一の宮であり、全国4万社余りある八幡社の総本社。伊勢神宮に次ぐ宗廟として朝廷から崇敬を受けた屈指の名社である。 寄藻川にかかる神橋を渡ると樹木の多い整然とした境内が菱形池を中心に広がる。広さ約50万m2、イチイガシなどの大樹がうっそうと茂る最奥の亀山に鎮...

院内町の石橋群 ( 大分県 宇佐市 )
75基もの石橋が残る宇佐市院内町は石橋のまちとして知られる。このうちアーチ橋(めがね橋)は64基もの数を誇る。江戸時代末期から、大正時代を中心に昭和にかけて架けられたもので、そのほとんどが今も使われている現役の橋である。 院内町は深い谷に集落が点在する地形ゆえ、それらを結ぶ必要があったこと、また急流のために木橋でなく...

写真提供:(一社)別府市観光協会
明礬温泉 ( 大分県 別府市 )
鉄輪温泉の西に湧く山の湯。別府八湯のうちいちばん高所にある。温泉名が示すように藩政時代は全国一の明礬*の採取地であったが、明治以後、湯の花*の採取地に変わり、温泉旅館が開業された。湯の花の採取は今も盛んで、藁葺小屋の採取所が立ち並び、噴気と硫黄臭が一面に漂っている。温泉は硫黄泉、酸性泉で38~98度。皮ふ病に効く。宿泊...

写真提供:別府地獄組合
別府地獄めぐり ( 大分県 別府市 )
地獄とは地中から熱湯・噴気・熱泥が噴出するところのことで、そのようすが灼熱地獄を思わせるのでこの名がある。市内に十数ケ所あり、鉄輪温泉街の北西端に密集するほか、柴石温泉のそばの地獄が知られる。 「地獄めぐり」は地獄組合所属の海地獄、血の池地獄、龍巻地獄、白池地獄、鬼石坊主地獄、かまど地獄、鬼山地獄の7箇所を巡るのが...

霧島山 ( 宮崎県 えびの市 / 宮崎県 小林市 / 宮崎県 都城市 / 鹿児島県 霧島市 )
宮崎県と鹿児島県にかけて広がり、最高峰は標高1,700mの韓国岳(からくにだけ)。獅子戸岳(ししこだけ)、新燃岳(しんもえだけ)、中岳(なかだけ)、高千穂峰(たかちほのみね)、白鳥山(しらとりやま)、甑岳(こしきだけ)など20以上の山からなる火山群の総称である。やわらかな山容に神秘的な火口湖を複数抱いているのも特徴で、大浪...

写真提供:霧島市
霧島山のミヤマキリシマ ( 宮崎県 えびの市 / 鹿児島県 霧島市 / 宮崎県 他 )
樹高は1mほど。ツツジの一種で九州各地の高山に生息する。紫紅色、桃色、薄紅色の花をつける。命名は日本を代表する植物学者の牧野富太郎博士。1909(明治42)年に霧島へ新婚旅行に訪れた折に発見した。 開花時期は、高千穂河原(たかちほがわら)が5月下旬、韓国岳(からくにだけ)山頂が6月上旬。

写真提供:宮崎県えびの市観光協会
えびの高原のミヤマキリシマ ( 宮崎県 えびの市 )
えびの高原は、霧島連峰を構成する、韓国岳(からくにだけ)、甑岳(こしきだけ)、白鳥山(しらとりやま)などに囲まれた標高約1,200mに位置する高原。高原北部には不動池や六観音御池(ろっかんのんみいけ)、白紫池(びゃくしいけ)などの火口湖がある。「えびの」の名称は、韓国岳山麓の硫黄山(いおうやま)から噴出する亜硫酸ガスによ...

写真提供:延岡市 北川総合支所
大崩山 ( 宮崎県 延岡市 )
祖母傾国定公園(そぼかたむきこくていこうえん)を代表する山のひとつで、大崩山系の主峰。延岡市北西部にある祝子川(ほうりがわ)温泉から、1時間ほど歩いた場所が登山道の入り口である。標高は1,644m。大崩山系は火山活動によって形成された地下岩脈が、隆起侵食によって現れた山々だ。大崩山を筆頭に、鉾岳、比叡山、矢筈岳、行縢山など...

鹿川渓谷 ( 宮崎県 延岡市 )
市の北西、日之影町(ひのかげちょう)との境を流れる綱ノ瀬川上流のさらに支流、鹿川沿いに続く渓谷。祖母傾(そぼかたむき)国定公園の中心に位置し、源流は鬼の目山。付近の山々同様に花崗岩質が特徴で、渓谷の中には花崗岩の一枚岩でできた大小のなめ滝が点在する。県道214号線を10数km進んだ先にある。

北川 ( 宮崎県 延岡市 )
源流地は大分・宮崎両県境付近にある祖母傾山(そぼかたむきやま)系で、延岡市街地で五ヶ瀬川*の河口付近に合流する。総延長51.3km、流域面積573.5km2。上流部は、祖母傾山系国定公園に属し、美しい渓谷景観が広がる。大きな蛇行が印象的な中流部には砂洲が点在し、河畔林も繁茂。汽水域である下流部には、広大な干潟などが広が...

青島神社 ( 宮崎県 宮崎市 )
広さ約4万m2、周囲約1.5kmの青島。その中央部に青島神社の社殿がある。ちなみに島全体は青島神社の神域。祭神は彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと)、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、塩土大神(しおつちのおおかみ)。創建年代は不明だが、平安朝の国司巡視記「日向土産」の中に 「嵯峨天皇の御宇奉崇青島大明神」と 記され...

フェニックス・ワシントンヤシ並木(別名ワシントニアパーム) ( 宮崎県 宮崎市 )
宮崎市の街路や公園に植えられているフェニックスは、アフリカのカナリー島が原産。幹が太く、羽状の複葉は3~4mに達する。葉柄の基部に長い刺があり、葉は強靭で全体は濃緑色。病害虫に対する耐性が強く、寿命が長いため、「不死鳥」を意味するその名が付けられた。大正初期、宮崎市の天神山公園に植えられたのが最初。宮崎県の県の木である...

写真提供:「みやざき観光情報旬ナビ」
日南海岸 ( 宮崎県 宮崎市 / 宮崎県 日南市 / 宮崎県 他 )
宮崎、鹿児島両県にまたがる日南海岸国定公園。その宮崎県側一帯が一般的に「日南海岸」とよばれる。 太平洋に沿うように、北は青島から、堀切峠、鵜戸神宮、都井岬など数々の観光スポットがある。温暖な気候のため、海岸一帯や海岸沿いを走る国道220号には、ビロウやアコウ、ソテツ、ワシントニアパームといった亜熱帯性植物が茂り、青い...

高千穂峡 ( 宮崎県 高千穂町 )
五ヶ瀬川水系の本流である五ヶ瀬川が阿蘇火山活動で噴出した火砕流を浸食してできた深いV字形の峡谷。浸食された峡谷は、平均で約80mの高さがあり、東西約7kmに渡って続く。1934(昭和9)年には「五箇瀬川峡谷」として国の名勝・天然記念物に、 1965(昭和40)年には祖母傾国定公園(そぼかたむきこくていこうえん)の一部に指定された。峡谷...

高千穂神社 ( 宮崎県 高千穂町 )
「日向三代」と称される皇祖神とその配偶神と、三毛入野命(みけいりののみこと)とその妻子神9柱からなる「十社大明神」。高千穂郷八十八社の総社で、約1900年前の垂仁天皇時代に創建された。1778(安永7)年に再建された本殿は、五間社流造で九州を代表する大規模なもの。 本殿は2004(平成16)年に国の重要文化財に、 鎌倉時代に源頼...

西都原古墳群 ( 宮崎県 西都市 )
西都原は西都市街の西方に北から南に延びる東西2.6km、南北4.2kmにおよぶ洪積台地。この標高60mほどの平坦な台地上に、瓊瓊杵命(ににぎのみこと)や木花開耶姫(このはなさくやひめ)の墓とされる古墳をはじめ、4世紀初頭から7世紀に造られた300基以上の大小さまざまの古墳が続き、全国初の特別史跡公園として整備されている。 公園は花...

関之尾の甌穴群 ( 宮崎県 都城市 )
日本有数の甌穴*群。霧島山地の裾野から湧き出る清流が、約34万年前の加久藤(かくとう)火砕流などでできた地層に流れ込み、小石や岩石の破片を回転させることで、この地層に穴が開き、形成された。甌穴群は千数百の数が確認され、川幅約80m、長さ約600mのエリアに広がっている。甌穴の造成は現在も進行中で、世界的にも珍しく、地質学上貴...

飫肥城 ( 宮崎県 日南市 )
酒谷川(さかたにがわ)と山川に臨む丘の上にある。約600年前までには築城されていたと考えられ、この間28年に渡る島津豊州家と伊東義祐*の攻防戦が演じられた。1588(天正16)年、伊藤祐兵(いとうすけたけ)が入城し、5万1千石の飫肥藩の居城として1871(明治4)年の廃藩置県に至った。 難攻不落の名城として知られた飫肥城だが、石垣...

写真提供:伊佐市曽木の滝観光案内所
曽木の滝 ( 鹿児島県 伊佐市 )
幅210m、高さ12mの壮大なスケールを誇る滝。二度の火山の噴火によって火砕流が堆積。そこに湖ができ、川内川の浸食によって湖の端が削られてできたといわれている。

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟
藺牟田池 ( 鹿児島県 薩摩川内市 )
飯盛山の噴火でできた火口部に水がたまってできた火山湖で、直径約1km、周囲は約4kmの円形をしている。飯盛山をはじめとする6つの外輪山に囲まれている。最大水深は約3mと火口湖*としては浅い。湖の北西部は泥炭層が堆積し、低層湿原になっている。珍しい浮島*があり、泥炭形成植物群落*として天然記念物の指定を受けている。 湖岸に沿...

入来麓武家屋敷群 ( 鹿児島県 薩摩川内市 )
鎌倉時代からの領主、入来院(いりきいん)氏が築城した清色(きよしき)城を中心に広がる、山と川に囲まれた武家屋敷集落跡。城のすそ野に家臣の住まいを配置する「麓」*を形成し、集落へと発展した。山、川、田などの環境が一体となり、屋敷の配置や区割り、野石を使った美しい玉石垣や生垣、武家屋敷門(茅葺門)、大手門前の濠や広馬場...

写真提供:新田神社
新田神社 ( 鹿児島県 薩摩川内市 )
薩摩川内市街の北西、うっそうとした老樹が茂る神亀山とよばれる小山の頂にある、日本神話に登場するニニギノミコトを祭る神社。枚聞神社とともに薩摩国の一の宮である。本来、一の宮は一国に一社だが、新田神社は島津氏によって一の宮と認められた。 大鳥居をくぐり、社殿まで行くには一直線に続く322段の石段を上る。御神木のクスをはじ...

長目の浜 ( 鹿児島県 薩摩川内市 )
上甑島の景勝地。島の北西部の山すそが風や波によって崩れ落ち、潮風の力でつくられた幅約50m、長さ約4kmの砂州状の弓型の浜。その浜の内側に、なまこ池、貝池、鍬崎池(くわざきいけ)の大小3つの池と、外側に須口池がある。それぞれの池で生態系が異なり、海水と淡水の二層になっているなまこ池にはナマコや魚介類が生息し、貝池はその名の...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟
開聞岳 ( 鹿児島県 指宿市 )
薩摩半島の最南端に位置する標高924mの独立峰。縄文時代からたびたび噴火を繰り返してきた活火山で、885(仁和元)年の噴火で今の姿になり、現在は活動を停止している。日本百名山*のひとつ。山全体が樹木におおわれていて、その美しい円錐形の山容から薩摩富士ともよばれる。崖となって落ちる海側とは対照的に、陸側はゆるやかな裾野が広が...

池田湖 ( 鹿児島県 指宿市 )
薩摩半島の南東部にある、九州最大の湖。周囲15km、水深233m。約5500年前に開聞岳の噴火によって池田火山が陥没してできたカルデラ湖。湖の北西側に駐車場があり、湖岸に開聞岳を望む景勝地でもある。一帯は四季折々の花がきれいに咲いている。北西岸を除いて湖の周囲のほとんどが急崖。湖水は藍色に澄んでいる。

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟
指宿温泉郷(指宿、山川伏目海岸)の砂むし温泉群 ( 鹿児島県 指宿市 )
20余りの湧出地区がある、九州を代表する温泉郷のひとつ。なかでも特徴的なのが、世界でも珍しい海岸から自然湧出する温泉の熱を利用した天然の「砂むし」場があること。体を砂の中に埋めての砂むし湯治が300年以上前から行われている。現在、砂むしを行っているのは2か所。摺(すり)ガ浜と山川伏目(やまがわふしめ)海岸で、いずれも泉質...

写真提供:枚聞神社
枚聞神社 ( 鹿児島県 指宿市 )
古来より薩摩一の宮*として、地元の人々から篤く信仰されてきた神社。特に、交通・航海の安全や、漁業守護の神として崇敬されている。縁起は定かでないが、現在の社殿は1600(慶長5)年に島津義弘が創建し、のちに改修された。 開聞岳を仰いで参拝するために北向きに建てられた社殿は、総漆塗り。元々は開聞岳をご神体とし、今も開聞岳の...

桜島 ( 鹿児島県 鹿児島市 )
鹿児島湾(錦江湾)を隔てて鹿児島市街の対岸約4kmにある火山島。桜島一周は約36km、車で約1時間。島といっても1914(大正3)年の噴火で大隅半島と陸つづきになっている。一つの山に見えるが、中央に北岳(1,117m)・中岳(1,060m)・南岳(1,040m)が南北に並ぶ成層火山*で、南岳は現在も活動を続け、断続的に黒い噴煙をあげて灰を降らせて...

照國神社 ( 鹿児島県 鹿児島市 )
第11代藩主・島津斉彬(しまづ なりあきら)を祀る神社で、城山の麓に社殿を構えている。斉彬の死後、1864(元治元)年に創建され、別格官幣社に列格。建物は第二次大戦で戦災に遇い、拝殿は1958(昭和33)年に再建されたもの。鹿児島の総氏神様として県民に親しまれており、初詣には大勢の参拝客でにぎわう。境内に斉彬、久光の銅像が立ち、...

写真提供:株式会社 島津興業
仙巌園 ( 鹿児島県 鹿児島市 )
1658(万治元)年に、島津家19代光久(みつひさ)によって築かれた島津家の別邸。目の前に広がる錦江湾(きんこうわん)を池、桜島を築山に見立てた壮大な大名庭園で、敷地面積は約1万5千坪。島津家歴代に愛され、篤姫や西郷隆盛も訪れている。 28代斉彬がガス灯の実験に用いたと伝わる鶴灯籠や、琉球国王から贈られた望嶽楼(ぼうがくろ...

写真提供:いおワールドかごしま水族館
いおワールドかごしま水族館 ( 鹿児島県 鹿児島市 )
桜島と錦江湾を背景に、海沿いに立つ水族館。南北600kmにもわたる鹿児島県の海にこだわり、南西諸島のサンゴ礁域から、深海域のある内湾で、しかも活火山の海である錦江湾、そして黒潮の海まで、多様性に富んだ鹿児島の海と、そこに生きる生物たち、約500種30,000点を展示している。 人気の高い「黒潮大水槽」には、鹿児島沿岸で捕獲され...

桜島周辺地域の墓地 ( 鹿児島県 鹿児島市 )
桜島の「赤水湯之平口」バス停を降りると、道路の脇が墓所になっている。ここの墓はすべて屋根付き。四隅の柱で屋根を支え、その中に墓石と墓碑銘が立つ。一見すると壁のない小屋が密集したミニ集落のようで、墓と墓の間は細い路地になっている。これは桜島の降灰から墓を守るための知恵で、垂水市など桜島から近い地域には、同じような屋根...

写真提供:鹿児島市 維新ふるさと館
鹿児島市 維新ふるさと館 ( 鹿児島県 鹿児島市 )
明治維新を支えた西郷隆盛や大久保利通らが幼少期を過ごした甲突川(こうつきがわ)沿いに立つ歴史観光施設「維新ふるさと館」。2018(平成30)年にリニューアルオープンした。明治維新をわかりやすく、楽しく学ぶための歴史観光施設で、薩摩の偉人・英雄列伝や篤姫のコーナー、「翔ぶが如く」「西郷どん」の世界が楽しめる大河ドラマシアタ...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟
出水麓の町並み ( 鹿児島県 出水市 )
鹿児島の最北部、肥後藩との藩境にあった出水麓*は、重要な防衛基地のひとつ。薩摩藩の「外城」として藩内で最初に築かれ、規模も最大だった。出水麓には、3,000人~5,000人の武士たちが暮らし、整然と区画された武家屋敷が立ち並んでいた。碁盤の目のような町割りや、川石を積み上げた石垣、緑の生垣など、今も400年前と変わらぬ風景を残し...

千本イチョウ ( 鹿児島県 垂水市 )
園主である中馬夫妻*が30年をかけて植えたというイチョウが、季節になると黄金色に染まり人々を魅了する垂水市の名所。先代から受け継いだ山を開墾し、夫妻が植えたイチョウは1,200本以上になる。

坊津町のソテツ ( 鹿児島県 南さつま市 )
沖縄から奄美大島にかけて自生する亜熱帯植物、ソテツ。自生地の北限は九州の南端、薩摩半島および大隅半島の南部の海岸を望む岩地である。南さつま市坊津町、指宿市山川、肝属郡(きもつきぐん)南大隅町佐多・肝付町(きもつきちょう)内之浦に自生しているソテツが国の天然記念物に指定されている。 薩摩半島の西南端に位置する南さつ...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟
知覧の茶畑 ( 鹿児島県 南九州市 )
薩摩の小京都といわれる知覧町は、薩摩半島中南部に南北に長い町域をもち、南は海に面している。 ここは日本有数の茶の産地として有名で、黒色火山灰土壌の台地で茶の栽培が始まったのは明治初期。低木の茶なら台風の影響が少ないと考え、紅茶品種の栽培から始まり、その後、緑茶品種に変えて生産量が増加した。茶葉を刈る大型機械の導入...

写真提供:知覧武家屋敷庭園 有限責任事業組合
知覧武家屋敷群 ( 鹿児島県 南九州市 )
江戸時代、武士の数が多かった薩摩藩は、領地を外城(とじょう)とよばれる地区に分け、地頭や領主の屋敷を中心に「麓」とよばれる武家集落をつくって統治していた。これは鹿児島城下に武士団を結集させず、分散して軍事拠点を複数つくるためでもある。外城は鹿児島県内に102カ所もあったが、なかでも知覧には武家集落、「麓」の典型的な姿が...

薩摩焼の里美山 ( 鹿児島県 日置市 )
日置市東市来町にある薩摩焼の里「美山」は、410年以上前に朝鮮半島より伝わった薩摩焼の里として歴史ある町。薩摩藩17代藩主の島津義弘が、朝鮮出兵のときに陶工を連れ帰り、島津藩の庇護のもとで開窯をしたのが薩摩焼の始まり。 薩摩焼には、白薩摩(白もん)と黒薩摩(黒もん)の2種がある。白もんは白い表面に貫入とよばれる細かなヒ...

霧島神宮 ( 鹿児島県 霧島市 )
建国神話の主人公であるニニギノミコトが祀られている神社。創建は6世紀、最初は高千穂峰と火常峰(ひけふのみね:御鉢)の間にある背門丘(せとお)に建てられたといわれているが、霧島山の噴火による焼失と再建を繰り返し、500年以上前に現在の場所に移された。現社殿は1715(正徳5)年、薩摩4代藩主・島津吉貴(しまづ よしたか)が寄進し...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟
霧島温泉郷 ( 鹿児島県 霧島市 )
霧島連山の南麓に広がる温泉郷。新湯(しんゆ)・湯之谷・関平(せきひら)・栗川(くりかわ)・野々湯・丸尾・林田・硫黄谷・殿湯(とのゆ)の9つの温泉を総称したもので、硫黄泉を中心に、個性豊かな湯が楽しめる。硫黄谷温泉は単純硫黄温泉、新湯温泉は乳白色で古くから皮ふ病に効くといわれている。また、関平温泉は飲泉としても人気があ...

写真提供:ネイチャーガイドオフィス まなつ
屋久島の森 ( 鹿児島県 屋久島町 )
屋久島は鹿児島の南方、九州本土最南端佐多岬から南南西約60kmの洋上に位置する、ほぼ円形をした島。周囲約130kmで、その9割が森林。九州最高峰の標高1,936mの宮之浦岳をはじめ1,000m以上の高峰が40座以上あり、八重岳とよばれるほど山が連なる。 島の土台となっているのは、砂岩や泥岩などの堆積岩が重なった日向層群(熊毛層群)とよば...

写真提供:ネイチャーガイドオフィス まなつ
縄文杉 ( 鹿児島県 屋久島町 )
胸高周囲16.4m、樹高25.3m、確認されている屋久杉の中でも最大級の老大木。1966(昭和41)年に島の役場職員により発見された。荒川登山口から約8kmのトロッコ道を歩き、約3kmの登山道を登りたどり着く、標高1,300mの地点にある。途中、登山道に入り約600mで、ウィルソン株がある。縄文杉の推定樹齢は2200年から7200年まで諸説ある。根の踏み...

写真提供:ネイチャーガイドオフィス まなつ
千尋の滝 ( 鹿児島県 屋久島町 )
屋久島の南部本富岳(モッチョム岳、標高940m)の麓にかかる落差60mの滝。滝に向かって左側の250m×300mの巨大な岩盤が特徴的な、島を代表する滝のひとつ。壮大なV字谷の景観は、この島が海底のマグマの隆起で現われた花崗岩で覆われた島であることと、年間降雨量が多いことが関係している。島に降る大量の雨が、鯛ノ川(たいのこ)となって花...

写真提供:ネイチャーガイドオフィス まなつ
宮之浦岳 ( 鹿児島県 屋久島町 )
標高1,936m。1,800mを越える山々が連なり「洋上のアルプス」とよばれる屋久島の最高峰であることはもとより、九州最高峰でもある。最南の日本百名山。 女性的な山容で、淀川登山口から登山道が整備されており、屋久杉の森、花之江河(はなのえごう)を抜け、標高1,700m前後で樹林帯を抜けると、その後はヤクザサとシャクナゲと花崗岩の巨...

写真提供:ネイチャーガイドオフィス まなつ
永田岳 ( 鹿児島県 屋久島町 )
九州一の宮之浦岳(1,936m)の北西に聳える、九州第二の高さを誇る標高1,886mの山。女性的な宮之浦岳とは対照的に花崗岩が露出した男性的な山容で、特に西側は岩壁で、深く永田川源流に落ち込んでいる。ローソク岩など切り立った岩峰が特徴で、南西側の大川(おおこ)源流には、屋久杉原生林や鹿之沢湿原が広がっている。新日本百名山のひと...

写真提供:公益社団法人 鹿児島県観光連盟
花之江河湿原 ( 鹿児島県 屋久島町 )
淀川登山口から約4km、標高1,640mに位置する、日本最南端の高層湿原*。島の南部の集落から始まる各登山道(尾之間歩道、湯泊歩道、栗生歩道など)の合流ポイントでもあり、この地から宮之浦岳への登山道が一本化される。400mほど離れた場所に小花之江河がある。北に黒味岳を望む開けた地で、可憐な花を咲かせる高山植物が群生し、その間を清...

写真提供:ネイチャーガイドオフィス まなつ
ウイルソン株 ( 鹿児島県 屋久島町 )
推定樹齢2000~3000年、江戸時代に木材用に切り倒されたといわれている屋久杉の大株。1914(大正3)年に屋久杉を調査し、大株を紹介したアメリカの植物学者ウィルソン博士にちなんで名付けられた。根回り32.5mの切株の中は10畳ほどの広さの空洞になっていて、泉が湧きだし、小さな流れをつくっている。付近はモミ、ツガの針葉樹、ヒメシャラ...

写真提供:宇検村役場観光課
湯湾岳の照葉樹林 ( 鹿児島県 宇検村 / 鹿児島県 大和村 )
湯湾岳は標高694m。奄美群島の最高峰だ。山頂一帯にはミヤマシロバイ、ミミズバイなどハイノキ属の樹木が4種も出現するなど注目すべき特徴をもった低木林が発達しており、貴重な亜熱帯性の照葉樹林として保護されている。 7合目付近にある宇検村の「湯湾岳公園」までは車で行くことができる。「湯湾岳公園」には展望台があり(2019(令和...

写真提供:龍郷町
安木屋場のソテツ・バショウ群生地 ( 鹿児島県 龍郷町 )
奄美大島の龍郷町、今井崎の西側に位置する安木屋場集落。集落の背後に控える神山「オダキ」の斜面に、ソテツとイトバショウの群落がある。 ソテツもイトバショウも島人の暮らしに深く関わってきた植物だ。イトバショウは芭蕉布の原料として、ソテツは実や幹のでんぷんを水でさらして毒を抜き、救荒食物として昔から島の人の命を支えてき...

昇竜洞 ( 鹿児島県 知名町 )
「花と鍾乳洞の島」といわれる沖永良部島の地盤は、琉球石灰岩でできている。島のほぼ中ほどにある大山の麓を中心として、島には200から300もの鍾乳洞がある。代表格がこの昇竜洞で、1963(昭和38)年に山内浩教授率いる愛媛大学学術探検部によって発見された。 全長3,500mのうち、600mが観光洞として一般に公開されている。鍾乳石の発達...

写真提供:一般社団法人沖永良部島ケイビングガイド連盟
大山水鏡洞 ( 鹿児島県 知名町 )
「島の地下はすべて鍾乳洞」といっても過言ではないほど鍾乳洞が発達している沖永良部島では、洞窟を探検するケイビングツアー*が楽しめる。ケイビング目的で島を訪れる人も多い。ツアーで入れる代表的な洞窟は、海見洞、大山水鏡洞、水連洞、銀水洞などだが、初心者でも比較的入りやすいのが大山水鏡洞。ここは大山のふもとから海まで続く...

与那国の与那国馬(与那国島) ( 沖縄県 与那国町 )
那覇から650km離れた日本最西端の与那国島。この島の在来馬が与那国馬。日本に残る在来馬8種のうちのひとつで、沖縄にはほかに宮古島に宮古馬という在来種がいる。 与那国馬の体高はおよそ110~120cm、体重は約200kgと小さく、全身が茶色、改良種には出ないといわれる、鰻線(まんせん)という背骨に沿ってたてがみから尻尾までをつなぐ濃...

名護のひんぷんガジュマル ( 沖縄県 名護市 )
国道58号から名護城公園方面へ300mほど入った、名護市道路の中央にそびえる推定樹齢300年以上のガジュマルの木。国指定天然記念物。 名護市を象徴する名木。このガジュマルの隣に立つ石碑「三府龍脉碑」の形がヒンプン(屋敷の前庭と母屋の間に立てるついたて)のように見えることから、地元では「ヒンプンシー(ひんぷん石)」とも呼ばれ...

斎場御嶽 ( 沖縄県 南城市 )
琉球の創世神「アマミキヨ」がつくったといわれる7つの御嶽(沖縄独特の祈りの場)のひとつで、琉球王国最高の聖地。南城市の海に近い琉球石灰岩の岩山にあり、6つのイビ(神域)で構成されている。御門口(うじょーぐち)から石畳の道を上がると、最初にあるのが大庫理(うふぐーい)、その先に寄満(ゆいんち)、そして巨大な三角形の岩が...

写真提供:那覇市文化財課
識名園 ( 沖縄県 那覇市 )
首里城の南、約3kmの那覇市真地(まあじ)の高台にあった琉球王家の別邸。王族の保養や、中国からの使者(冊封使)をもてなすために、1799(寛政11)年、尚温王の時代に造営された。総面積約42,000m2。「心」という形につくられた園池を中心に、御殿(母屋)・築山・果樹園・樹林と、それらを結ぶ園路からなる。池の周囲を歩きな...

座喜味城跡 ( 沖縄県 読谷村 )
標高約120mの丘陵地、読谷村のほぼ中央高台にある。15世紀初頭(1420年ごろ)、読谷山按司の護佐丸が築城したといわれる。面積約1万m2で、2つの郭からなり、一の郭には殿舎が建てられていた。この城は要塞としての機能を重視して造られており、郭を取り囲む城壁はいくつもの曲線が組み合わされるような構造。石垣の幅は、厚いとこ...

写真提供:垂見健吾
渡嘉志久ビーチ(渡嘉敷島) ( 沖縄県 渡嘉敷村 )
那覇からの船が着く渡嘉敷港がある島の東側から、島中央部に連なる小高い山を越えて車で約10分。島の西側の山の上から目に飛び込んでくるのが、白い砂浜が約800mも続く渡嘉志久ビーチだ。ここは三方が山に囲まれた湾になっているので、波は穏やか。 このビーチの特徴はウミガメに会える確率が高いこと。海底にウミガメの好物である海草が...

写真提供:垂見健吾
ニシ浜(波照間島) ( 沖縄県 竹富町 )
波照間島は西表島の南に位置し、有人の島では日本最南端の島。島名は「はてのうるましま」からきたものと伝えられる。島の南側は切り立った断崖が続くが、北西側には美しい「ニシ浜」がある。「ニシ」とは沖縄の言葉で北のこと。沖に西表島や仲ノ神島の島影が望めるニシ浜の海は、淡い水色からコバルトブルー、沖の藍色まで、ハテルマブルー...

浦内川(西表島) ( 沖縄県 竹富町 )
沖縄県では本島に次ぐ面積を誇る西表島は、およそ90%が亜熱帯の自然林で覆われている。降水量が豊富なこの島には、大小あわせて40本以上の川がある。なかでも水量豊かなのが、西表島の北西部を流れる浦内川。古見岳(469m)に源を発し、テドウ山と波照間森の間を流れて東海岸に注いでいる。支流も含めて全長39kmあり、沖縄県内で最長の河川...

写真提供:糸満市役所
糸満ハーレー ( 沖縄県 糸満市 )
豊漁と海の安全を祈願して、沖縄の多くの漁村で旧暦5月4日に行われる競漕行事。ハーリーとは「爬竜」の中国音で竜をさす。中国から伝来した行事だが、糸満は那覇より伝来が古いとの説もある。糸満ではハーレーと呼び、漁業のまち・糸満を代表する年中行事のひとつとして、今も盛大に行われている。 糸満ハーレーは旧暦5月4日の早朝、山巓...

写真提供:座間味村ホエールウォッチング協会
座間味のクジラ ( 沖縄県 座間味村 )
1960年代前半まで捕鯨の漁場であった座間味村周辺の海で、再びクジラが目撃されたのが1985(昭和60)年。徐々に頭数が増え、現在は毎年1月から3月末頃まで、座間味島周辺の海にザトウクジラがやってくるようになった。温暖で島影が多いので、波静かなこの海でクジラたちは繁殖活動を行い、やがて子クジラに体力がつく4月頃、エサが多い北の海...

写真提供:今帰仁村教育委員会
今帰仁城 ( 沖縄県 今帰仁村 )
今帰仁城は、南は谷を隔てて背後のクバの御嶽に連なり、東と北は40~100mの断崖下に志慶真川が流れる要害の地にある山城。琉球が尚氏によって統一される以前、北山・中山・南山の3つの勢力に分かれていた三山時代に、本島北部一帯から与論島、沖永良部島あたりまでを勢力下におさめた北山王の居城で、築城は13世紀末といわれている。 約7....

写真提供:やんばる学びの森
やんばるの森 ( 沖縄県 国頭村 / 沖縄県 大宜味村 / 沖縄県 東村 )
沖縄島北部の国頭村、大宜味村、東村を含む通称「やんばる」地域。「山々が連なり森の広がる地域」を意味するこのエリアは、世界的にも貴重な自然の宝庫である。森林率が80%以上で、南北約23km、東西約12kmの日本の総面積のわずか0.1%の範囲の中に、多くの固有動植物、稀少動植物が生息している。2016(平成28)年には、やんばるの陸地と海...

砂山ビーチ(宮古島) ( 沖縄県 宮古島市 )
宮古島の中心市街地平良から北へ約4kmの位置にある砂山ビーチは、名前の通り、真っ白い砂の山を越えると広がっている小さな浜。海に向かって左手にあるアーチ状になった琉球石灰岩の岩山がビーチのポイントだ。

伊良部大橋 ( 沖縄県 宮古島市 )
沖縄本島の南西約290kmに位置する宮古島と、その西にある伊良部島を結ぶ。離島同士に架かる全長3,540mの橋で、無料で渡れる橋として全国一の長さを誇る(2018(平成30)年現在)。歩いて渡ることもできる。伊良部島の人たちが架橋要請活動を始めてから完成まで40年以上を要し、2015(平成27)年1月に開通式が行われた。架橋以前は、宮古島の...

写真提供:一般社団法人 久米島町観光協会
ハテの浜(久米島) ( 沖縄県 久米島町 )
那覇の西方約100kmに浮かぶ久米島は、緑豊かな山が連なり、水が豊富な島。琉球王国時代から、球美(くみ)島とも呼ばれてきた風光明媚な島で、なかでもハテの浜は島を代表する景勝地。島の東側にある奥武(おう)島、オーハ島のさらに沖合に連なる3つの砂洲(前の浜、中の浜、ハテの浜)を総称してハテの浜と呼ぶ。サンゴ礁の土台にサンゴや...

写真提供:一般社団法人 久米島町観光協会
奥武島の畳石(奥武島) ( 沖縄県 久米島町 )
奥武島の南岸に広がる国指定天然記念物の奇岩群。火山活動で噴出した安山岩質の溶岩が、ゆっくり冷えて岩石になる時にできた割れ目が亀甲模様になっている。直径1~2mの五・六角形の石の数は、砂におおわれたものを含めて1,000個以上に及ぶといわれ、南北50m、長さ250mにわたって広がり、干潮時に現れる。これらは柱状節理の断面が露出したも...

写真提供:一般社団法人 久米島町観光協会
久米島の桜並木(久米島) ( 沖縄県 久米島町 )
久米島を代表するサクラの名所は、「アーラ林道」と「だるま山園地」の2カ所。アーラ林道は島の南側、儀間集落と島尻集落を結ぶアップダウンのある林道で、4kmの道のりの両側を約1,500本のサクラが彩る。島の中央西寄りに位置するだるま山園地は、公園内およびその近隣の池のまわりなどに500本以上のサクラが植えられている。 いずれも種...

琉球村 ( 沖縄県 恩納村 )
「伝えたい むかし沖縄」をコンセプトに、琉球の文化・伝統を今に伝える体感型テーマパーク。多幸山のふもとの広大な敷地に、沖縄各地に残された古民家を移築し、古き良き沖縄を再現している。 園内では、藍染め、陶芸、織物、紅型などの工芸体験や、芸能のアトラクションが楽しめる。水牛が砂糖車を引いてサトウキビを絞る製糖風景は、...

写真提供:垂見健吾
二見ヶ浦海岸(伊是名島) ( 沖縄県 伊是名村 )
沖縄本島の本部半島の北、約27kmにある伊是名島は、琉球王国の礎を築いた尚円(しょうえん)が生まれた島として名高い。尚円は第二尚氏王統を樹立、その王統は1872(明治5)年の琉球処分まで400年以上続いた。島には尚円ゆかりの史跡も多く、南側には尚円の家族や親族が眠る伊是名玉陵がある。 この伊是名玉陵あたりから「海ギタラ」と呼...

写真提供:伊江村役場
伊江島城山(伊江島) ( 沖縄県 伊江村 )
本部半島の北西、約9kmにある伊江島は、面積約23km2、周囲22.4kmのピーナツ形の島だ。 本部港との間を所要30分で村営フェリーが結ぶ。さとうきび、島らっきょう、葉タバコ、花卉などの農業をはじめ、畜産業や漁業も盛んな島。沖縄戦の激戦地となったこともあり、現在も米軍基地が残るこの島では教育民泊として年間多くの修学旅...

勝連城跡 ( 沖縄県 うるま市 )
勝連半島の付け根に位置する丘陵上に築かれた城跡。正確な築城年は定かではないが、13世紀前後に造られたと考えられている。自然の地形を利用して石灰岩の石垣をめぐらせた5つの曲輪からなり、北西の最高部から一の曲輪、二の曲輪、三の曲輪、四の曲輪へと階段状に低くなり、再び南東側の東の曲輪で高くなっている。 歴代の勝連按司(あじ...

写真提供:渡嘉敷村
慶良間諸島の海 ( 沖縄県 渡嘉敷村 / 沖縄県 座間味村 )
沖縄本島の西、約30kmの海に広がる約20の島々が慶良間諸島。有人島には渡嘉敷島(渡嘉敷村)、座間味島、阿嘉島、慶留間島(以上、座間味村)があり、その他は無人島である。これらの島の大部分には山があり、海岸線はギザギザして複雑だ。これは山地が沈んだ島である証。200万年~150万年前、琉球列島が中国大陸と陸続きだった時代に、その...

写真提供:垂見健吾
八重岳のサクラ ( 沖縄県 本部町 )
八重岳は、本部町と名護市の境に位置する標高453mの麗峰。県道84号の八重岳入口から山頂まで道路が整備されており(約4km)、この道沿いがサクラの並木になっている。もっとも多く見られるのはリュウキュウカンヒザクラ。濃いピンク色の花がうつむきがちに咲く。八重岳一帯にはおよそ7,000本のリュウキュウカンヒザクラが植えられている。 ...

写真提供:名護中央公園管理事務所
名護のサクラ ( 沖縄県 名護市 )
沖縄本島北部の玄関口、名護の市街地は、毎年1月末~2月にかけてサクラを目当てに県内外から訪れる人たちでにぎわう。その中心となるのが市街地の南東約1km、名護岳の麓に広がる名護城(なんぐすく)公園(名護中央公園)。ここは県内随一のサクラの名所で、「日本の桜の名所100選」にも選ばれている。南口の駐車場から名護神社までの石段や...

石垣島 四カ字の豊年祭(石垣島) ( 沖縄県 石垣市 )
沖縄では旧暦6月(新暦の7月)頃に稲の収穫を終える。この時期に、石垣島をはじめ八重山各地の集落で御嶽を中心に行われるのが、収穫儀礼である「豊年祭」。今年の実りへの感謝と、来年の豊作を祈る大切な行事だ。沖縄本島やその周辺の島では「ウマチー」と呼ばれる行事がこれにあたる。 最も規模が大きく見学者も多いのが、石垣島の中心...

写真提供:国営沖縄記念公園(海洋博公園):エメラルドビーチ
エメラルドビーチ ( 沖縄県 本部町 )
国営沖縄記念公園・海洋博公園内の最北端に位置するビーチ。Y字型に突き出した3エリアからなる珍しいかたちで、向かって中央が「眺めの浜(汀線長150m)」、左手が「憩いの浜(250m)」、右手が「遊びの浜(350m)」と名付けられている。ビーチが3方向を向いているので、それぞれ目の前に広がる光景が異なり、変化に富んでいる。沖縄本島では...
